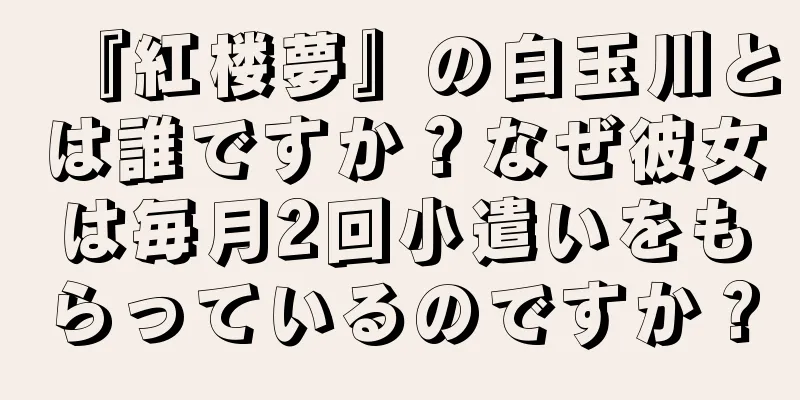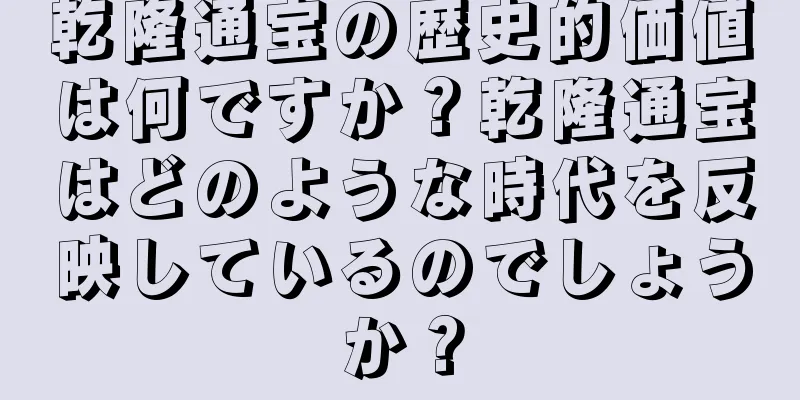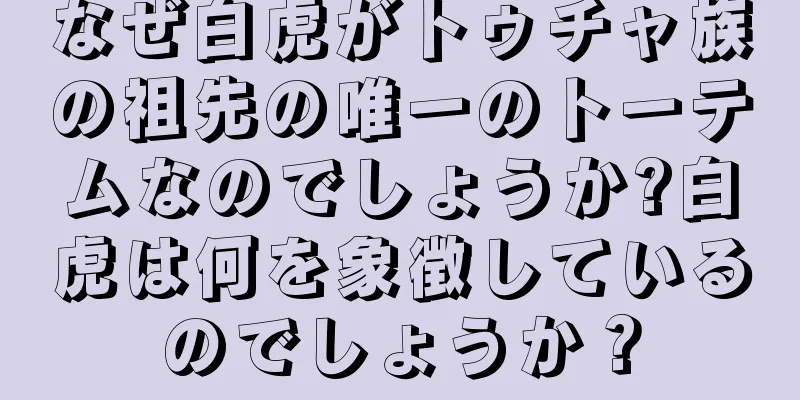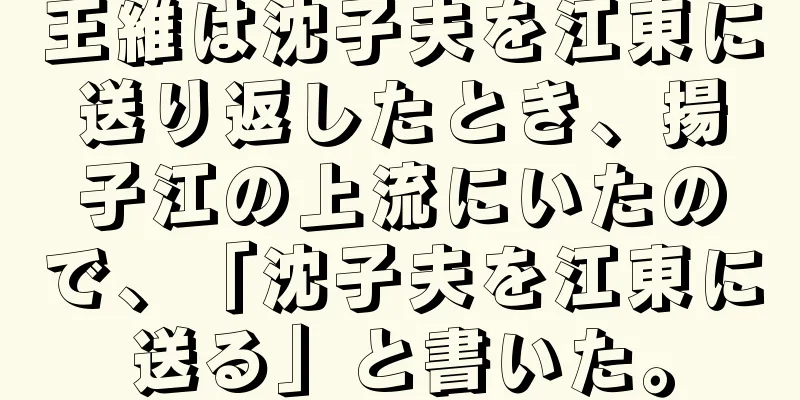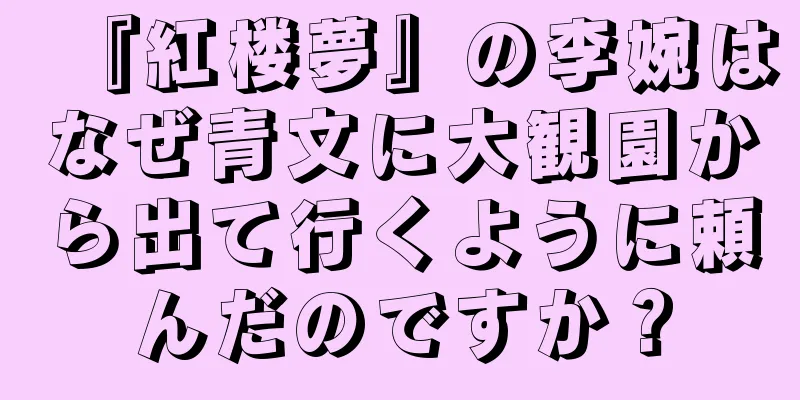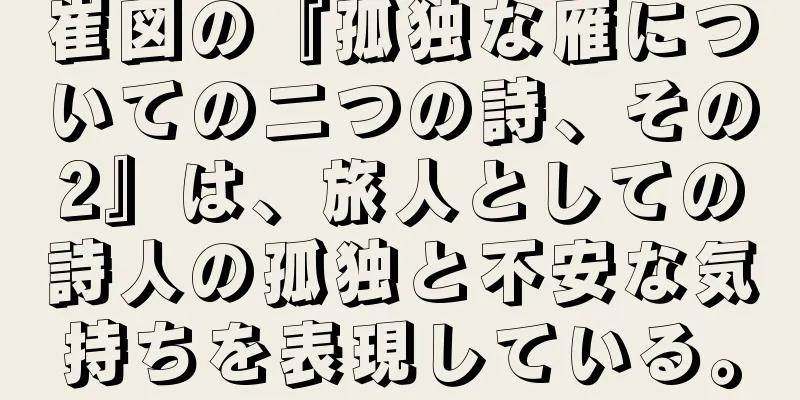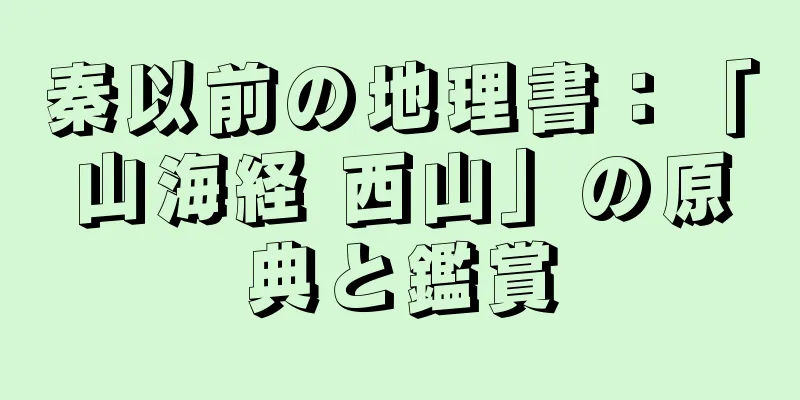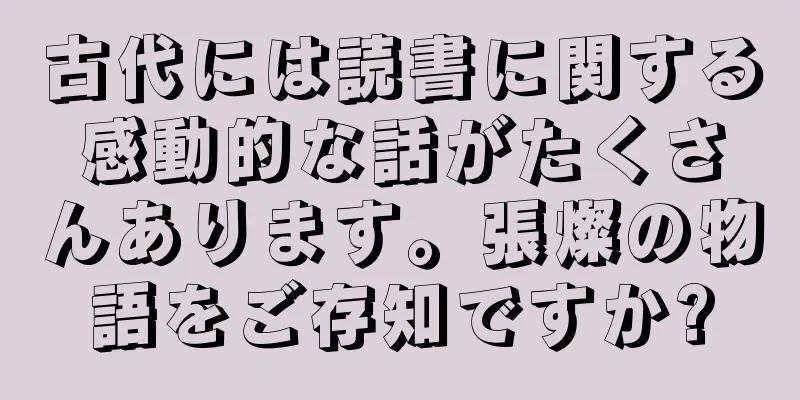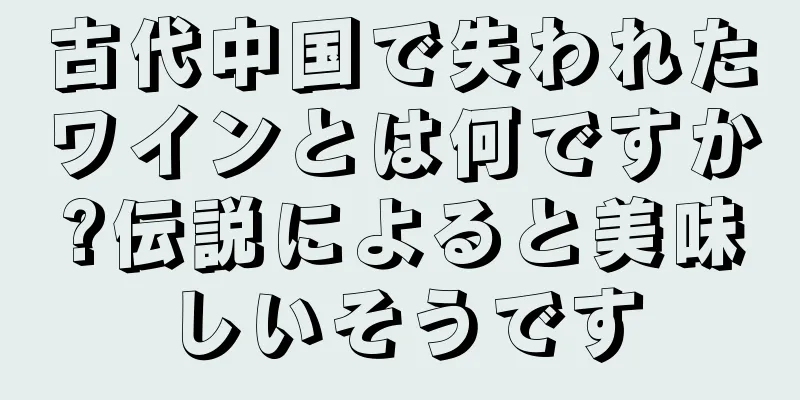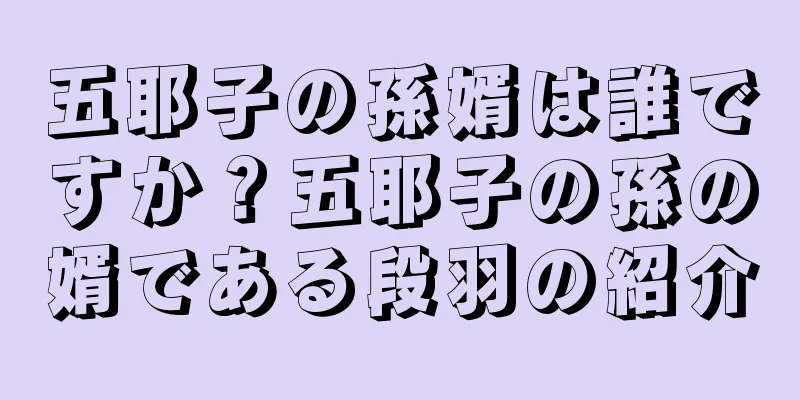王維の有名な詩句の鑑賞:漢の皇帝とその大臣たちの宴会が終わり、雲台で軍事的功績が議論された
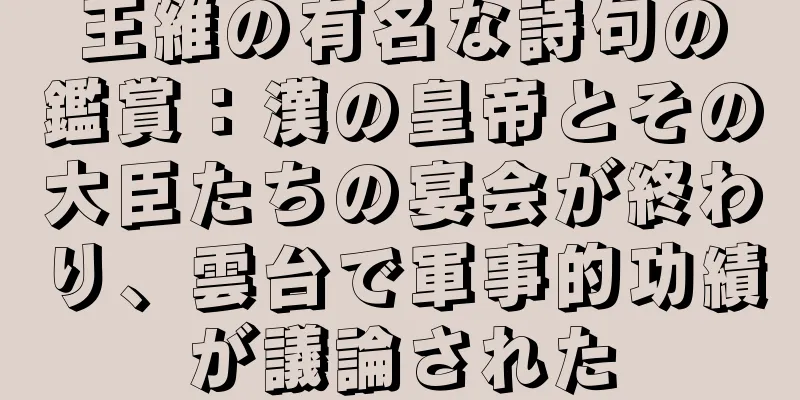
|
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先の故郷は山西省斉県であった。唐代の詩人、画家。王維は禅を修行して悟りを開き、詩、書、音楽、絵画に秀でていた。開元・天宝期の詩作で名声を博し、特に五音詩に優れ、その多くは山水や田園を歌ったものであった。孟浩然とともに「王孟」と呼ばれた。仏教に深く帰依していたため、「詩仏」と呼ばれた。 彼の書と絵画は特に優れており、後世の人々は彼を南派山水画の創始者とみなしました。 『王有成全集』や『画秘』などを著し、約400編の詩を残している。北宋の蘇軾は「王維の詩を味わえば、詩の中に絵がある。王維の絵を見れば、絵の中に詩がある」と評した。そこで、次の興味深い歴史編集者が王維の「青春四詩」をお届けします。見てみましょう! 新豊の高級酒は一杯一万の値段がし、咸陽の騎士たちは長年さまよっている。 会うと、私たちはあなたのためにお酒を飲み、高い建物の横の柳のそばに馬をつなぎます。 彼は漢の時代に楡林郎として生まれ、当初は騎兵隊に従って楡陽で戦いました。 私が国境で苦しまないと誰が知っているだろうか?私が死んだ後も、私の騎士道精神は依然として匂い立つだろう。 彼は一人で二本の彫刻弓を割ることができ、何千もの敵の騎兵隊は取るに足らないものに見えました。 金色の鞍に座り、白い羽を整えながら、5人のチャンユを次々と射殺した。 漢の皇帝と大臣たちの宴会が終わり、雲台殿で軍事上の功績について議論された。 皇帝は目の前の将軍に侯爵印を授け、将軍はそれを身に着けて明光宮を去った。 【注意事項】 ⑴新豊:陝西省臨潼県の北東部に位置し、良質のワインが豊富。一万斗:高価で財産に値する上質のワインを指します。 ⑵咸陽:もともとは戦国時代の秦の首都咸陽のこと。当時の有名な武将である桂、荊軻、秦武陽などは咸陽を訪れたことがある。ここでは唐の首都長安を指す。 ⑶玉林郎:漢代の近衛兵の武名。兵の数は決まっておらず、近衛兵や侍従の役目を担当し、主に六県の貴族の子息が務めた。隋・唐の時代まで使われていました。 ⑷霍奇:かつて騎軍将軍を務めた霍去兵のこと。毓陽: 古代幽州、現在の河北省薊県。漢王朝がフン族と頻繁に戦った場所。 ⑸ 苦しみ:「死」とも呼ばれます。 ⑹裂:開いて分離する。 「腕」とも表記される。彫刻弓:彫刻や絵画で装飾された美しい弓。 ⑺重:「群」とも書く。 ⑻白羽:矢尻に白い羽根が飾られている矢を指します。 ⑼五呦:もともとは漢の宣帝の治世中に匈奴の内乱で王位を争った5人の指導者のことを指す。漢の宣帝の治世中、匈奴は内紛を起こして互いに殺し合い、様々な王がそれぞれの王国を建てた後、匈奴は5つの王国に分裂しました。この比喩は、国境を脅かす少数派の王たちを指しています。 ⑽宴会:成功を祝う宴会のこと。 ⑾雲台:後漢の洛陽宮殿にあった壇上。明帝の時代に鄧愈をはじめとする28人の建国の英雄の肖像画が描かれ、歴史上「雲台二十八将軍」として知られています。 ⑿玄:宮殿の前の敷居。 ⒀明光宮:紀元前101年(漢の武帝の太初4年)秋に建てられた漢代の宮殿の名称。 【感謝】 この詩群の最初の詩は、若い騎士の楽しい集まりと飲酒を描写しています。この詩は「良い酒」で始まる。なぜなら、酒を三杯飲めば約束が果たされ、五つの山は明るく見える。目が眩み、耳が熱くなった後、精神は生き返るからである。(李白の「青春の旅」)当時、飲酒は精神を奮い立たせることができるため、英雄的なことと考えられていた。 「万斗」という句は曹植の『名都志』の「平楽に帰って宴を催し、一万斗の美酒を飲んだ」という句から来ています。李白の詩『酒歌』によると、「昔、陳王は平楽で宴を催し、一万斗の美酒を飲んで楽しんだ」とあります。この詩の意味は李白の詩と似ており、酒の美味しさを称賛するだけでなく、先人の言葉を使って寛大で親切で、歓喜に満ちた盛大な行事を書いています。遍歴の騎士が酒を飲むのは、本来は孤独で退屈しのぎのためではなく、客人がいるところではその奔放な精神が存分に発揮される。 2 番目の文では「咸陽騎士」について言及されていますが、これは京都の騎士によって表されます。僑騎士の多くは都市の街路や市場から来たので、司馬遷は『史記・僑騎士伝』の中で彼らを直接「街路の僑騎士」と呼んでいます。咸陽は秦の首都だったので、都が僑騎士の源泉であったことは言うまでもありません。ここでは全体を代表するために、その中から最良の例を引用します。詩の最初の2行は「新豊の美酒」で始まり、続いて「咸陽の遍歴の騎士」が登場し、「何年」が記事全体のアウトラインとなっている。詩の最後の 2 行はさらに一歩進んで、若い騎士の友情と厚い仲間意識を重んじるスタイルを描写しています。偶然出会った見知らぬ人同士でも、一杯の酒を飲めば親しい友人になることができる。「友情を語るなら幽孟に従え、心豊で酔う」(李白『野で青年に会う』)や「人生で何回笑えるか?酒を飲みに会うと必ず酔う」(岑深『涼州閣で裁判官と夜会う』)という言葉は、彼らの共通の熱意を示している。そのため、豪快に酒を飲む彼らの気さくな態度には、友を思いやる、友に忠実であるといった人間性の美しさも染み込んでいるのです。ワインは鏡のようなもので、人生に対する率直でオープンな姿勢を映し出します。この詩は人物の肖像ですが、最後は風景の描写で終わります。詩人は建物内の光景を無視して、建物の外の風景について書き始めました。実際、外部の光景について書くことは内部の光景に役立ちます。最後の文の「高い建物」は最初の文を反響させ、登場人物の大胆で奔放なスタイルを暗示するだけでなく、そのまっすぐで堂々とした姿勢で下品で卑しい外見を一掃します。「馬を柳につなぐ」は、馬と柳のイメージを利用して、若い騎士の若々しくハンサムなスタイルを引き立てます。この筆致により、場面が生き生きと描かれ、登場人物の大胆さが表現されると同時に、繊細で整然とした印象を与えます。詩全体の生き生きとした機敏な文体は、若者の奔放な性格と精神と一致しています。 2番目の詩は、騎士の国境への遠征を描いています。この詩に出てくる「漢に仕える」や「騎兵」、それに続く2つの詩に出てくる「五人の漢人」や「漢の君臣」は、いずれも漢の出来事を使って唐代を比喩的に表現したものであり、唐の詩ではほぼ一般的な手法となっている。ここには、その若者が皇帝に仕えることに専念し、官職に就いた当初は楡林郎の地位に就いたと記されています。楡林郎は内廷の衛兵であり朝廷に近いため、その地位は非常に重要であり、誰でも選ばれるわけではありませんでした。 『後漢書地理』には「漢王朝の建国後、六県の良家の子弟が皇帝の近衛兵に選抜された」と記されており、このことが垣間見える。騎兵とは、漢の武帝の治世中の名将、霍去兵のことを指します。霍去兵は大軍を率いて何度も匈奴の侵略に抵抗し、優れた軍事的功績を残しました。その若者は国に仕え、世界に貢献することに熱心だった。国が困難に陥ると、彼はためらうことなく軍隊に入隊した。国境は遠く、荒涼としており、戦場での戦いは生死を分ける問題である。主人公は「虎のいる山に行くことを承知で」、国のために身を捧げるこの精神は、曹植の『白馬伝』の「国のために命を捧げ、死を故郷に帰ることだと考える」若い英雄の精神と一致している。違いは、曹の詩が三人称の視点で客観的に描写し、賞賛しているのに対し、ここでは少年が自分の声で本当の気持ちを表現している点です。3番目の文は自問自答の口調で感情の波を急激に呼び起こし、最後の文は断定的な言葉で終わります。また、「誰が」「ない」「たとえ」「それでも」などの機能語の連続使用により、次の展開で常に口調が強まり、少年の冷静で毅然とした表情と揺るぎない決意が生き生きと伝わってきます。文章の中で休止を使って登場人物の内面世界を表現するこの技法は、強力であるだけでなく、騎士の「精神」の意味合いをさらに深めます。 3番目の詩は、敵を殺した若者の勇敢さを描いています。詩人は主人公を孤独で危険で不吉な戦争状況に置きます。 「敵の騎兵数千人」は、敵の大軍が国境に迫り、包囲網を形成していることを指します。 「敵の首領たちは全員全力で出撃し、優勢な力で勝利を収めようとしています。しかし、この若者は「一体となって」敵の「数千人」に立ち向かい、まるで空き地にいるかのように敵の陣形を左右に突進し、リーダーを先に捕らえ、凶暴で激しい敵の首領を「射殺」することができます。彼の並外れた勇気と武術ははっきりと見ることができます。少年はここで孤独な英雄として描かれており、彼の勇敢さと傑出した軍事的功績を強調することを意図しています。詩の1文目と3文目は、クローズアップショットを使用して少年の勇敢で機敏な姿勢を描写しています。「彫刻された弓を2つに分ける」は、彼が強くて射撃が上手で、両手で射撃できることを意味します。「金の鞍に座っている」は、彼が乗馬に熟練しており、疾走する馬の背でさまざまな姿勢を自由に変えることを意味します。 「白羽を合わせる」とは、動きの中で的を狙うのが上手で、決して的を外さないという意味です。2番目と4番目の文は、敵から始まり、若者の高いスキルと勇気を対比しています。敵と私たちの力の差が大きいほど、主人公の恐れを知らない英雄的精神を表現することができ、この精神は生死への献身から来ています。このように、この詩は前の詩を反映し、大きな功績が報われないことについての次の詩のモデルとなっています。詩に登場する彫刻された弧、金色の鞍、白い羽には、色付きのペンでわずかに点在しています。本来は、人と物を愛することを意味します。ここでの物は人に色を添えます。人と物は互いに補完し合うこともできます。繁栄した唐代の詩人は、しばしば武士の精神を表現することを好みました。たとえば、李白は自分自身を「弓を曲げて緑の弦を開き、満月を恐れない」と呼びました。彼は立派な馬に乗ってのんびり狩りをし、一矢で二頭の虎を射止めました。 「(宣城の宇文太守に献上し、崔世瑜に献上した)」杜甫は自分自身についてこう言った。「私はかつて鐙を放し、腕で鳥を撃ち落としたことがある。 「(荘有)王維」は従兄弟の一人を褒めて言った。「彼は学問を修め、馬に乗り、射撃をし、剣を持って淮陰に旅した。西凡の旗の下で罪を問われ、色とりどりの服を着た人々は皆捕らえられた。」これらは詩の中の理想のイメージの現実的な根拠といえます。 4番目の詩は騎士の成功を描いているが報酬は得られていない。前の詩では若い騎士が敵を撃退した勇敢さがすでに描かれているので、この詩では功績に対する宮廷の褒賞が描かれており、彼がその褒賞を受ける主人公となるはずです。詩の最初の3行は、祝賀式の厳粛さと温かい雰囲気を描写している。皇帝と大臣たちが一緒に宴会を開き、雲台舞台で功績が議論され、皇帝がホールに現れ、爵位と位を授与する。予想されていた主人公が登場した瞬間、褒賞を受ける人物が突然「将軍」であることが判明する。ここでの「将軍」と、二番目の詩「骠骑に続いて毓陽で戦う」の「骠骑」は同一人物であり、軍の総司令官を指している。 「将軍は嘲笑され、民光宮から追放された」という表現は、李白の『辺境の歌』の第三節にも出てくる。「皇帝が成功をおさめた後、林閣には霍、邵、堯だけが描かれている」。これは、皇帝に寵愛された権力者や富豪が皇帝の労働の成果を享受し、血みどろの戦いで戦った勇敢な戦士は取り残されるという意味である。この詩は、主人公を際立たせる手法で主題を繰り返し誇張しているが、結局その性格は別の人物に移され、最初の3つの詩で活躍していた主人公は静かにゲームから追い出されてしまう。実際には賞賛しながらも抑圧するというこの芸術的な手法により、この詩の不正義に対する叫びが力強く表現されており、ここでそれを詳しく説明するのは冗長であろう。 王維の『四つの青年詩』は、大胆で奔放、国のために命を捧げ、功績を主張し、成功しても満足しないという騎士道をロマンチックなスタイルで賛美しており、強い英雄的色彩を示しています。彼が創り出した若き遍歴の騎士のイメージは、唐代全盛期の他の詩人たちが創り出したイメージと同様に、実は当時の理想を擬人化したものだ。これら 4 つの四行詩はそれぞれ独立した作品であり、それぞれに焦点が置かれていますが、連続してつながっており、互いに補完し、支え合っています。筆致は現実的か想像的か、明白か隠れているか、自由で柔軟、そして型にはまらないもので、若々しいメロディーに満ちた力強い行進曲をうまく構成しています。 |
<<: 潘大林の名詩を鑑賞する:三国の地理的優位、永遠の功徳の波
>>: 王長齢の有名な詩句を鑑賞する:丹陽市の南には秋の海が暗く、丹陽市の北には楚の雲が深い
推薦する
ジャッジ・ディー第14章:農夫の馬容を戦いに誘い、村人の江忠と心から語り合う
『狄公安』は、『武則天四奇』、『狄良公全伝』とも呼ばれ、清代末期の長編探偵小説である。作者名は不明で...
汪希峰によって女中に昇進した後、平児の主な仕事は何でしたか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
人間は類人猿から進化しましたが、類人猿はどこから来たのでしょうか?
古代の類人猿から猿人へと進化した森林猿は、漸新世後期から中新世中期にかけてヨーロッパ、アジア、アフリ...
李白の「山隠者と酒を飲む」:この詩は大胆で奔放だが、単に自己表現をしているだけではなく、波もある。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
孟浩然の詩の名句を鑑賞:皇城は清明節を非常に重視し、人々の心は悲しみで満たされている
孟浩然(689-740)は、浩然、孟山人としても知られ、襄州襄陽(現在の湖北省襄陽市)の出身です。唐...
馬志遠の「首陽曲江空夕雪」:作者の「小湘八景」組曲の一つ
馬志遠(1250年頃 - 1321年 - 1324年秋)は、東麗とも呼ばれ、大渡(現在の北京、身元を...
古代の人々はどんな呪いの言葉を使っていたのでしょうか?古代における呪いのさまざまな方法
はじめに:瞿香宮は研究の結果、古代中国でよく使われていた呪いの言葉が「子孫なし」であり、俗語で子孫が...
林黛玉が頼めば、宝の二番目の妻になれる可能性があると言われているのはなぜですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
景浦の習慣 景浦の葬儀習慣の紹介
老人が亡くなると、葬式に来た男たちは火薬銃を持って故人の村まで歩いて行き、まず一発発砲し、その後、故...
伝説によると、蛇はどのようにして龍に進化したのでしょうか?どのようなトレーニングと練習が必要ですか?
蛇が龍に変わるまでに、いくつの変化を経なければならないのでしょうか?これは多くの読者が気になる質問で...
呂本中の「草を踏む雪は梅の花のようだ」:この詩のテーマは最後の文に表れている。
呂本忠(1084-1145)、号は巨人、通称は東来氏。祖先の故郷は莱州、出身地は曙州(現在の安徽省豊...
済公の原型は誰ですか?神の世界では、済公と楊堅のどちらの方が地位が高いのでしょうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、神の世界では済公と楊堅のどちらが地位が高いのかをお話しします。皆さん...
『紅楼夢』で賈夫人が腐った高麗人参の袋を持っていたのはなぜですか?意味は何ですか
賈祖母は、石夫人とも呼ばれ、賈一族で最も権力のある人物です。今日は、Interesting Hist...
清朝の将棋家、范曦平の将棋スタイルについて、後世の人々はどのような結論を導き出したのでしょうか。
ファン・シピンは正直で素朴な人物で、チェスをする以外に金儲けをしようとはしません。もしお金を持ってい...
「パートリッジ・スカイ:ロータスの鑑賞」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
パートリッジスカイ・ロータス鑑賞蔡松年(宋代)美しい月と香りが池の向こう十里まで広がり、夕方には水面...