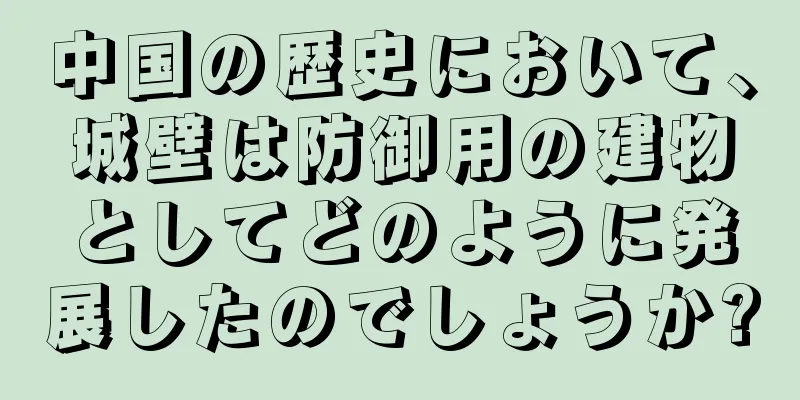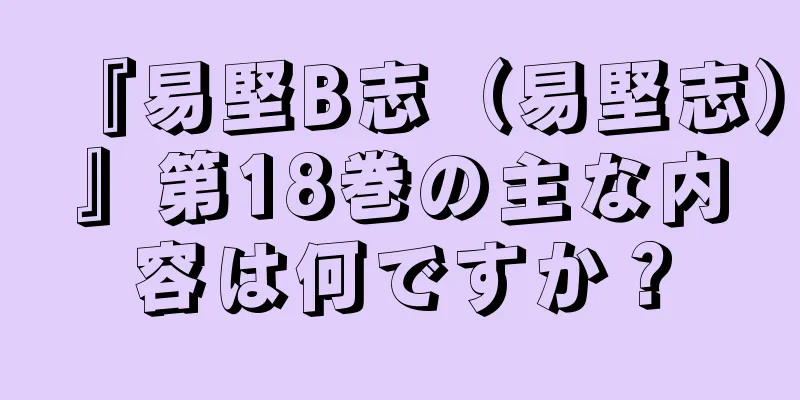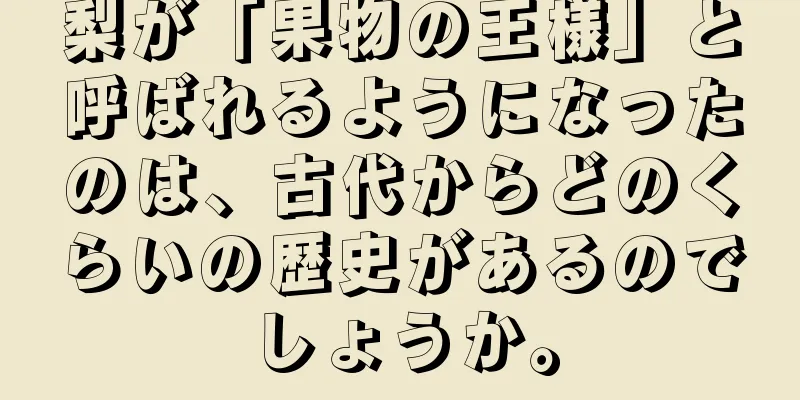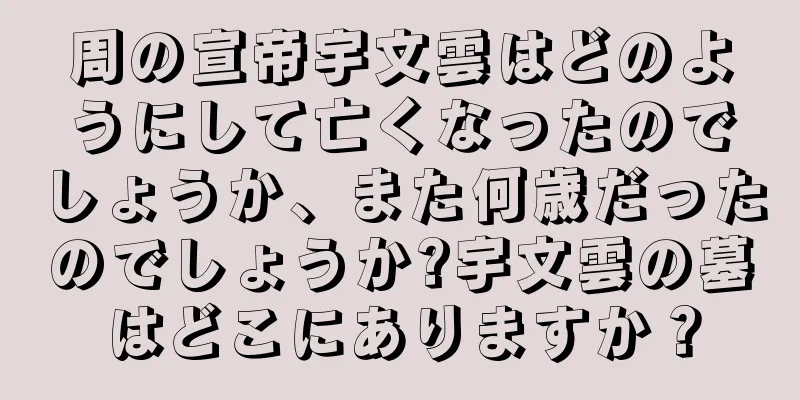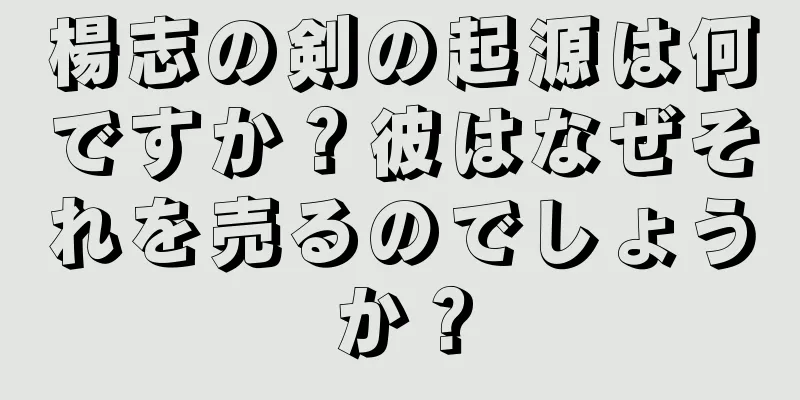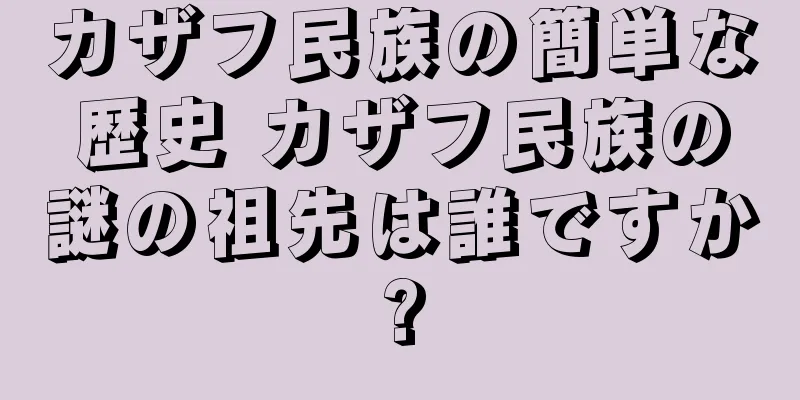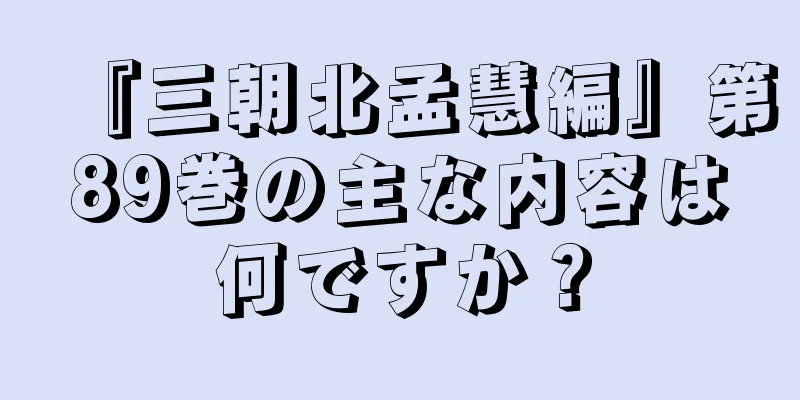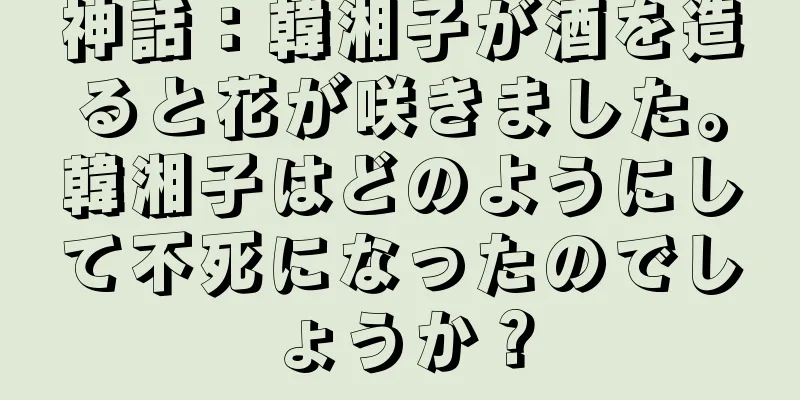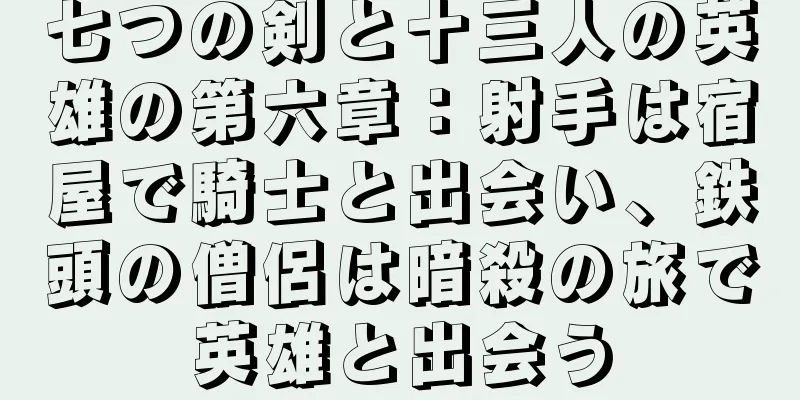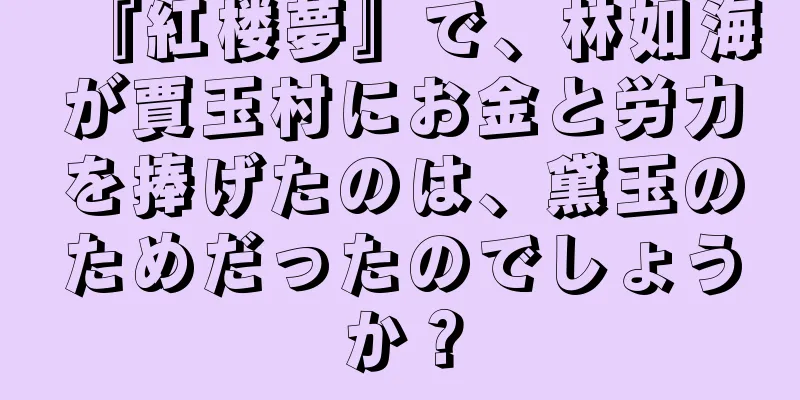「開拓後五篇の詩」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
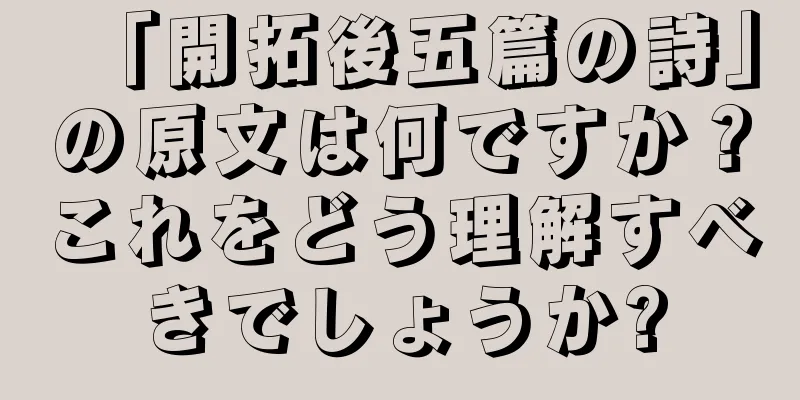
|
杜甫(唐代)の「後辺の詩五篇」 男はこの世に生まれたら、成人したら侯爵に叙せられるべきである。 戦いと征服によって大きな成果が得られたのに、なぜ私たちは古い丘に留まらなければならないのでしょうか? 集門に行く人を募集してください。軍隊が移動しているので、彼らは留まることができません。 鞍は金貨1,000枚、ナイフの刃は金貨100枚かかります。 道では近所の人たちが見送り、親戚たちが私を取り囲んで見送ってくれます。 年配者は上段に座り、酔っ払うと一般的なごちそうが出されます。 若者は特別な才能を持っており、微笑みながら呉狗を見つめています。 午前中に東門キャンプに入り、夕方に河陽橋を登ります。 夕日が旗を照らし、馬明鋒は機嫌が悪かった。 平らな砂の上に何千ものテントが並び、各部隊が呼びかけに応じた。 明るい月が空にかかっていて、寒い夜を寂しくしています。 悲痛なスオナの音は、戦士たちの悲惨さにもかかわらず、彼らを感動させた。 将軍は誰ですか?残念ながら霍彪瑙だと思います。 古代人は国境を守ることを非常に重視しましたが、現代の人々は高い名誉を非常に重視します。 英雄的なリーダーが軍隊を長旅に導くことになるとは誰が予想したでしょうか? 世界は一つの家族であり、四蛮族は孤立している。 これにより、勇敢で勇気ある戦士たちは勇気を示すのに十分な勇気を持つようになりました。 剣を抜いて荒野を襲い、毎日胡馬の群れを捕らえる。 私は神秘の北を開き、それを主に仕えるために保持することを誓います! 勝利の貢物が次々と捧げられ、二人の蛮族は平和になった。 毓陽は英雄の地であり、人々が太鼓を打ち鳴らし、笙や玉を演奏する場所です。 帆は遼海を回り、日本米は東呉にやって来る。 越の絹と楚の絹が車体を照らします。 指揮官の地位はますます高くなり、彼の傲慢さは首都を見下すほどになりました。 国境にいる人々はあえてそのことについて議論しようとはせず、議論する者は死ぬだろう。 私は良い家庭に生まれ、多くのスキルを学んできました。 傲慢さは悩みを増やすだけであり、自分の体の価値は言うまでもありません。 私は20年間乗馬を続けていますが、賢明な主君の優しさに応えられないのではないかと心配しています。 座って、幽州の騎兵隊が一直線に河洛河に向かって行進しているのが見えました。 夜中に家に帰ったのですが、故郷は誰もいませんでした。 幸いにも彼は悪評を逃れたが、子供も孫もいないまま貧しくなり、老いてしまった。 背景 『二度目の辺境征伐後五首』は、安禄山が初めて唐に対して反乱を起こした755年(唐の玄宗皇帝天宝14年)の冬に書かれたものと考えられる。その目的は、逃亡して帰還した兵士の自伝を通じて安禄山の反乱の真相を暴露し、唐の明皇帝を早く目覚めさせ、安禄山の反乱の原因が安禄山自身の名声への愛着と辺の将軍に対する過剰な恩寵であり、安禄山が辺の功績で恩寵を得て、結局は虎を育てて問題を起こしてしまったことを指摘することであった。 感謝 連作詩「第二次辺境伐後五篇詩」は、開元(713-741)・天宝(742-756)年間の兵士の入隊から単独脱出までの経験を描いたもので、一人の人物の経験を通して、天宝の乱の「混乱期」の歴史的現実を深く反映している。 開元中期以降、玄宗皇帝は地方の軍事制度を徴兵制度に変更し、兵士と農民を分離して職業軍人を生み出した。徳宗皇帝の治世中、李密は徴兵制度が混乱の根本原因であると主張し、徴兵された兵士たちは地元民でも氏族でもなく、命よりも報酬を重視していたと述べた。 『第二次開拓後の五つの詩』の主人公はまさにそのような志願者です。何も心配のない男は軍隊に勤め、食べ物を食べるだけで幸せです。詩の中で、呉鉤を贈った「若者」は、唐の詩によく出てくる若い遍歴の騎士に違いない。類は友を呼ぶ、この詩の主人公もそんな人なのだろう。この連作の最初の詩は、主人公が入隊の動機と家を出る盛大な機会について自ら語る詩であり、2番目の詩は軍隊に向かう途中の経験と指揮官の賞賛を描写し、3番目の詩は詩人の議論であり、4番目の詩は集門の指揮官の傲慢さを暴露し、5番目の詩は軍隊からの脱出の経験を描写している。この詩群の優れた点は、「典型的な環境における典型的なイメージ」を創り出していることです。この詩の鑑賞は、この中心を中心に展開されるべきである。 かつては大いなる名声と成功を夢見ていた兵士が、後に逃亡した。逃亡の動機は詩の中ではっきりと述べられている。それは、集門軍の「総大将」(安禄山のこと)がますます傲慢になり、皇帝に敬意を欠き、朝廷は裏切り者を黙認しているのを見たからである。「総大将の地位はますます高くなり、その傲慢さは都を圧倒し、辺境の人々はそれを議論することを敢えてせず、議論した者は道中で殺されるだろう」。彼は国に忠誠を誓うためにここに来たが(「宣明の北を開き、皇帝に仕えるためにそれを保持することを誓う」)、予期せず「海賊船」に乗り、「座って、幽州の騎兵が一直線に河洛河に向かっているのを見た」ので、三十六策の中では逃げることが最善だった。 詩では、主人公が国境に行く目的が「貴族の称号」を求めることであることが、冒頭から非常に明確にされています。「第一章は幸せな言葉で始まります。傲慢な将軍に従えば、報酬を得て成功するのは簡単です。」(浦其龍)この人物は、第三の詩で「名誉を重んじ」、「勇敢で努力で知られる」現代の人々の一人です。 「私は剣を抜いて荒野を討ち、日々胡馬の群れを連れ込んでいる。宣明の北を切り開き、それを保持して主君に仕えると誓う」というのがこの種の人々の自慢話である。第一詩の「人はこの世に生まれ、若くして侯爵にならねばならない」という告白から、第五詩の「私は馬に乗って二十年になるが、主君を失望させてしまうのではないかと心配だ」まで、主人公の名誉と褒賞への欲求は一貫しており、何ら変化していないことが分かる。 「古代人は国境を守ることを非常に重視していた」という6つの文は、詩の登場人物の考えの変化として理解することはできず、時事問題に対する詩人自身の解説、あるいは詩の登場人物の考えや行動に対する批判としてしか理解できません。杜甫の本性がここに表れていると言うだけでは不十分であり、著者が情熱的な文章で自らの意見を直接表現していると言うべきである。物語と議論を組み合わせるこの技法は、杜甫の詩では珍しいことではありません。 同典によれば、「開元・天宝年間、国は平和で、辺境の将軍たちは恩恵を求めて征服を企てた。西の青海守備隊、東北の天門軍、七渓塔羅の戦い、雲南の長江渡河の戦いなど、数十万の軍隊が異国の地に集結した。渤敵の内部侵略はなく、四度の天下遠征も止まらず、崩壊の勢いは計り知れないほどだった!」当時の辺境戦争は、玄宗皇帝の好戦的な性格によるものであることは間違いないが、軍制の変化も重要な原因であった。扶平制度はもともと、農耕と軍事を兼ねる兵士の制度であった。将軍は自らの軍隊を指揮することは許されていなかったため、唐代初期には軍の分離独立事件は起こらなかった。兵士の募集に関しては、李密が言ったように、志願兵のほとんどは何の仕事をもしない無頼漢だった。彼らは功績と巨額の報酬に貪欲で、それが軍に好戦的な精神を生み出した。朝廷から兵士まで、彼らは互いに影響を与え合っていました。それはちょうど「英雄的なリーダーが長い間軍隊を率いることを誰が知っているか。天下は一つの家族になり、四夷は孤立した軍隊に過ぎません。したがって、猛烈で勇敢な兵士は、聞いたとおりに勇敢に行動します。」戦争が進むにつれて、隣国を侵略することへの関心が高まり、野心的な将軍が羽ばたく機会を得ました。 「第二次開拓後の五つの詩」は、この特定の時代における歴史的生活を芸術的に再現しています。この詩の主人公は徴兵制度下の典型的な徴兵対象者のイメージである。彼は徴兵兵が持つ通常の功績への欲求と戦争への愛、そして国家としてのアイデンティティーの感覚の両方を持っていた。彼は功績に対する称号を得るために国境へ赴き、裏切り者の「悪評」を避けるために逃亡した。この詩は祝賀的な雰囲気で始まり、個人的な運命の悲劇である荒涼とした悲しい形で終わります。 |
<<: 「武侯祠」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
>>: 「山の中で」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
推薦する
呉俊の『胡無人行』:詩全体は言葉が洗練され、文章が力強く、リズムが速い。
呉俊(469-520)、号は叔祥、南朝梁の作家、歴史家。呉興市古章(現在の浙江省安吉市)の出身。彼は...
三勇五勇士第48章:裏切り者を訪ねて処刑し、追従者を降格させ、真の義人を皇帝の前に連れて行く
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
三国志の正史において、敵の隠された矢によって最終的に死亡した将軍は誰ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
薛宝才が北京に選ばれに行くのは、宝才が賈邸でうまく暮らすための口実なのか?
『紅楼夢』のプロローグは最初の 5 つの章で構成されており、さまざまな角度から本全体のプロットの展開...
李奇の「秦川を見る」:感情と情景が融合した稀有な詩
李斉(690-751)は漢族で、昭君(現在の河北省昭県)と河南省毓陽(現在の河南省登封市)の出身。唐...
古典文学の傑作「北遊記」第21章:族長は悪霊を鎮めるために太宝山へ行った
『北游記』は、『北真武帝玄天来』、『怪帝来』とも呼ばれ、明代の于湘當が著した神魔を扱った中編小説であ...
「覚醒結婚物語」第96章:道教の女性2人が人々から金を騙し取り、衙門のランナーが公有財産を回収
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
古代の「恋愛詩の王」李尚雯は、今日まで伝わる無題の詩を書いた。
今日は、Interesting Historyの編集者が李尚銀についての記事をお届けします。ぜひお読...
薛鋒の『長安の夜の雨』は、叶わなかった野望に対する詩人の嘆きを表現している。
薛鋒は、字を淑塵といい、唐代の官吏、詩人であった。彼は傲慢で、意見が鋭く、権力者の怒りを買うことが多...
『紅楼夢』に大観園が造られたのはなぜですか?賈家の若旦那の中で唯一、大観園に住めないのは誰ですか?
グランドビューガーデンに非常に興味がある方のために、Interesting Historyの編集者が...
秘密を暴く:歴史上最も偉大な皇帝、唐の太宗・李世民が起こした「四大不正」
唐の太宗皇帝、李世民は、一方では「寛大な宥和」を唱え、啓蒙的な政治を実施し、人道的な配慮を体現したが...
水滸伝の李逵とはどんな人物でしょうか?母親は李逵にどのような影響を与えたのでしょうか?
本名を呂達といい、花僧の異名を持つ呂智深は、圧制に抵抗する最も強い意志を持った人物で、恐れを知らず、...
唐代の領土:唐代で最も繁栄した時代は、唐の高宗皇帝の龍朔時代であった。
唐王朝は、唐の高宗の龍朔の時代に最盛期を迎えた。当時、中央アジアのオアシス地帯は唐の支配下にあった。...
清朝の孔思珍公主はどのようにして亡くなったのでしょうか?孔思珍の墓は死後どこにあるのでしょうか?
孔思珍(1635-1713)は、清朝初期の定南王孔有徳の娘であった。順治9年(1652年)、李定国は...
大別山脈はどの省と市にありますか?大別山の主峰は何ですか?
大別山はどの省のどの市にありますか? Interesting History の編集者が関連コンテン...