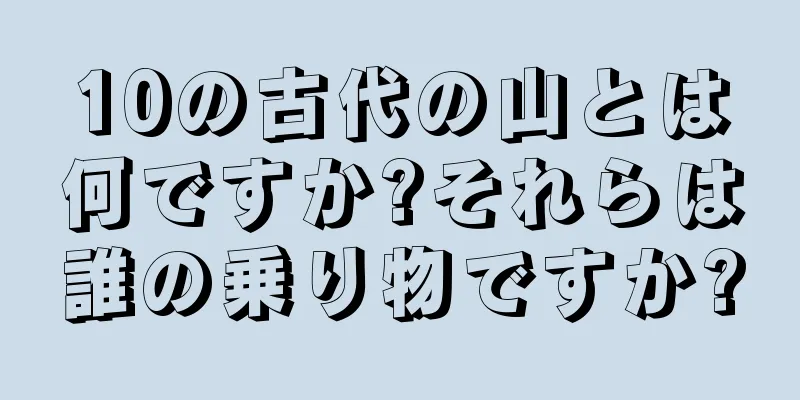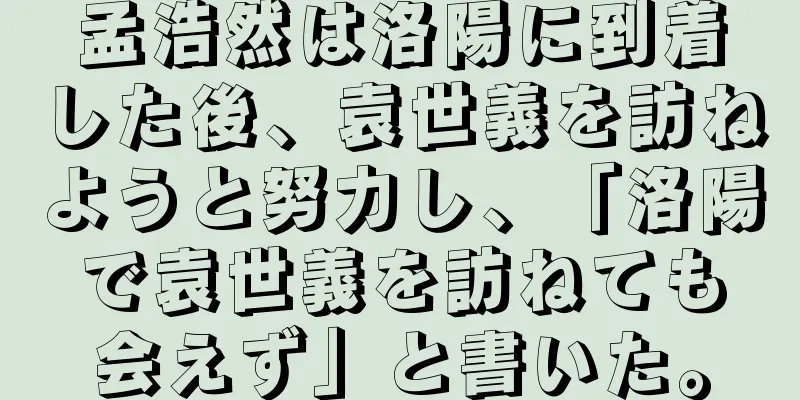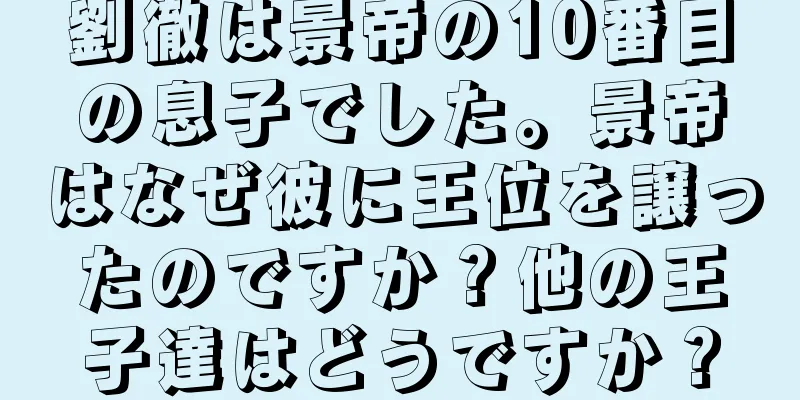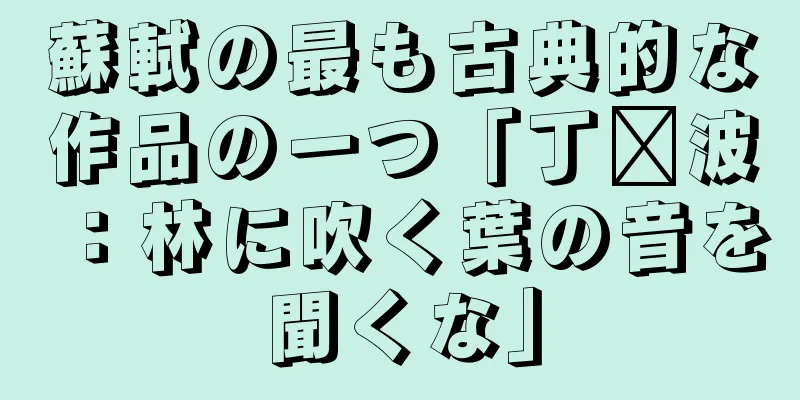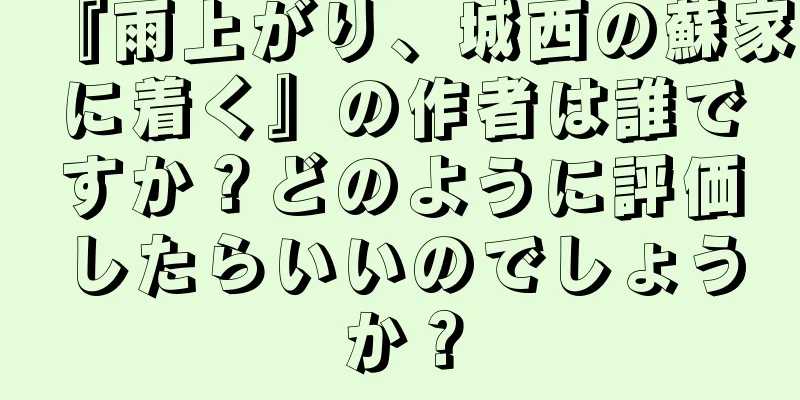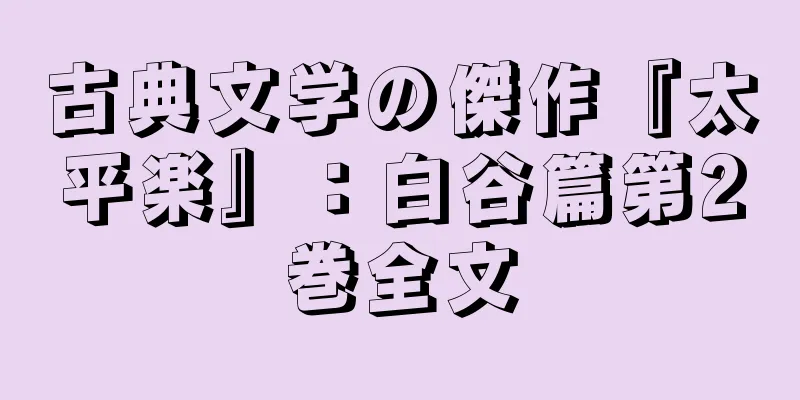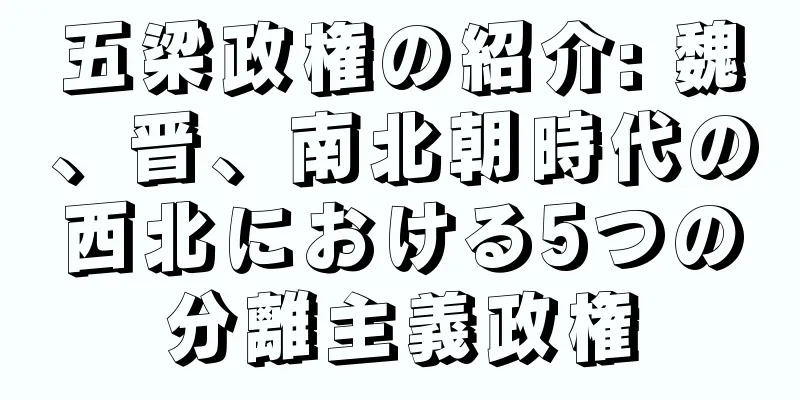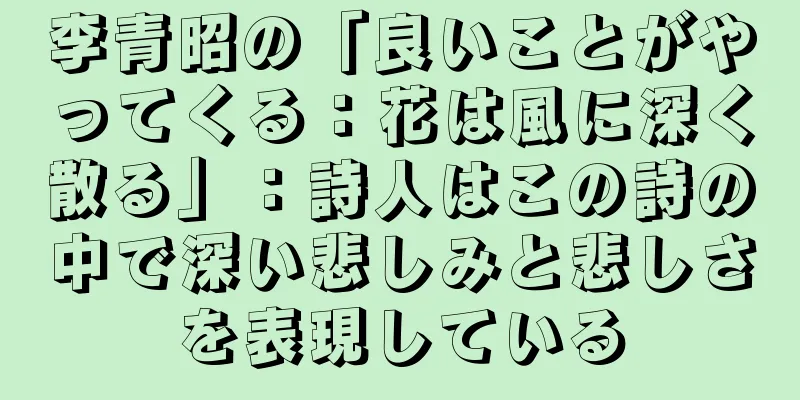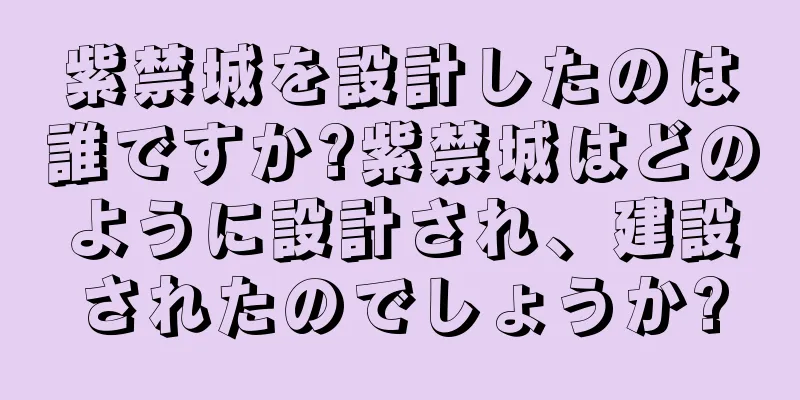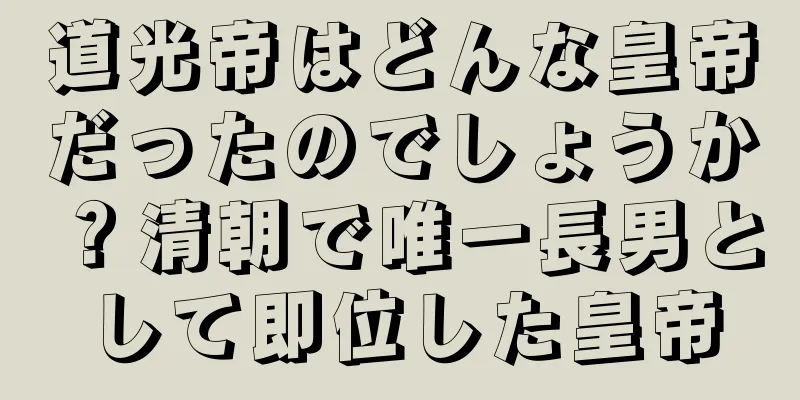仏教の未解決の謎:観音菩薩の起源と、彼女にはいくつのアイデンティティがあるのでしょうか?
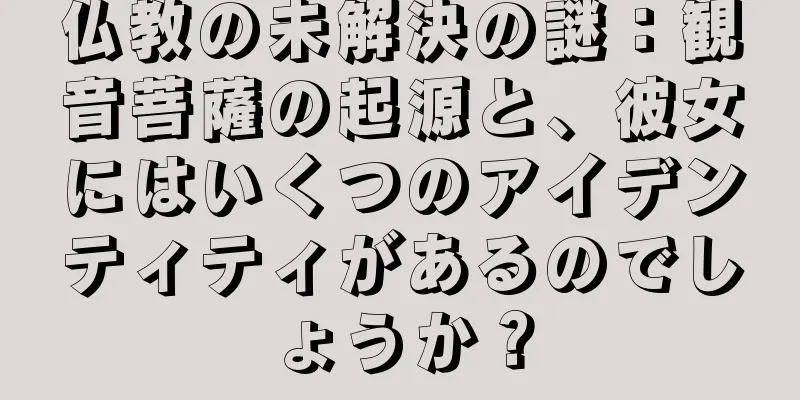
|
観音菩薩は仏教における菩薩の中で第一位に位置づけられており、中国において最も崇拝されている菩薩であり、信者数も影響力も最も大きい。 それで、観音はどのようにして観音になったのでしょうか?これには2つのバージョンがあります。 『達磨大菩薩経』には、遠い昔、阿弥陀仏がまだ転輪王と呼ばれていた頃、観音菩薩は転輪王の長男で「普民」と呼ばれていたと伝えられています。観音菩薩は、師である宝如来にすべての衆生を「救う」という大誓いを立てましたが、彼の本来の名前があまりにも奇妙で、衆生が疎外感を感じるのではないかと恐れたため、宝如来は彼に「観音」という名前を与えました。しかし、『霊韻経』には、観音が前世で「観音如来」を師と崇めていたと記されている。「観音如来」は観音が仏法を学ぶのに非常に優れていると考え、「観音」と名付けた。仏典には、宝蔵如来と観音如来が同じ仏であるかどうかは書かれていません。両者が観音と名付けられた理由から、宝蔵如来が観音如来である可能性が高いと思います。しかし、釈迦牟尼は、観音には名前が一つだけではないことを指摘しました。『千光眼観世音菩薩秘法経』には、観音が釈迦牟尼より先に仏陀となり、「正法光明如来」と名付けられたと記されています。釈迦牟尼はこの「正法光明如来」の弟子でした。この観点から見ると、観音は「法光如来」の後の正体です。不思議ですね。観音様はすでに「如来」の身体なのに、どうして前世や来世があるのでしょうか?もし正法光如来が永遠不滅であるならば、観音の前世について語る必要はない。もし正法光如来が「涅槃」にあるならば、それはさらに不思議なことである。なぜなら、如来は極楽浄土に住まうべきだからです。 「涅槃」の後に私たちが到達できる世界は、楽園よりも良い世界なのでしょうか? 私はこれらの疑問に対する答えを仏典で探し、数え切れないほどの劫の後に阿弥陀仏が「逝去」し、観音が西方極楽浄土を引き継いで西方極楽浄土の新たな主となり、名前を「普光功徳山王如来」と変えると経典に記されていることを発見しました。 「ニルヴァーナ」とは「涅槃」を意味し、今日では一般的に「悟り」と呼ばれています。ああ、阿弥陀仏でさえ「浄土を去って」浄土を去らなければならない。どこへ行くのだろうか?本当に浄土よりも良い場所があるのでしょうか?それは「究極の」浄土と呼ばれるのでしょうか?しかし、浄土の外にもう一つの「究極の」楽園があると述べている仏教の経典はありません。 「観音菩薩は昔仏陀になったが、生きとし生けるものを救うために、如来ではなく菩薩の姿を現した。仏陀になることと涅槃になることは同じ概念ではないようだ!」と言う人もいます。もちろん、「仏の運命」と涅槃の違いはわかっています。問題は、これらの仏陀にも「滅」があることです。彼らにとって、彼らは「仏の運命」か涅槃のどちらかです。 仏教の経典によれば、観音には前世、現世、来世があり、仏や菩薩も涅槃に入って移動するとされています。私はまだ仏教のことが理解できません。 |
<<: 仏教物語の解読:地蔵菩薩はなぜ仏陀の境地に達しなかったのか?
>>: ギリシャ神話における異常な結婚のリスト:父と娘、母と息子の関係とは?
推薦する
壮族文化 壮族文化のさまざまな要素は何ですか?
壮族の文化には長い歴史があります。同時に、さまざまな文化を通じて少しずつ蓄積されてきました。チワン族...
嘉慶帝は何をしましたか?それは実際に風神銀徳の王室に対する憎悪を深めた。
和申は乾隆帝の寵愛を受ける大臣であったが、実際は多くの人に害を及ぼす汚職官僚であった。しかし、乾隆帝...
夜華はなぜ彼女に蘇蘇と名付けたのですか?夜華は本当に蘇瑾が好きなのか?
白浅が人間だった頃はいつも地味な服を着ていたため、夜華は蘇蘇と名付けられました。夜華は蘇瑾を嫌ってい...
『紅楼夢』の宝仔と李婉は同じタイプの人物ですか?それらの類似点は何ですか?
実際、「紅楼夢」の中で、李婉の薛宝柴に対する評価は依然として非常に高かった。この二人の女性は多くの点...
朱元璋は国家統一のために、元朝の残党とどのような戦いをしましたか?
洪武帝の初年、元朝の中原支配は終わっていたが、上都に撤退した北元朝は依然として一定の軍事力を有してお...
十六国時代の成漢の皇帝、李寿の略歴。李寿はどのようにして亡くなったのでしょうか?
李寿(300-343)は、礼名を武高といい、李湘の息子で、李特の弟である。十六国時代の成漢の皇帝であ...
どのような状況下で、慧子娟の恋の詩は芒羽を試したのでしょうか?
子娟は自分の妻である林黛玉のために、花の守護神である賈宝玉に頼むことにした。ご存知ですか?次はInt...
『紅楼夢』では賈家の生活はどれほど変化したのでしょうか?なぜ賈夫人はもっと細心の注意を払わなかったのでしょうか?
賈家は金陵の四大家のうちの長であり、毎年莫大な費用を必要としている。以下の記事はInterestin...
岑申の詩「韓遜を都に遣わして皇帝に会わせ、科挙を受けさせる」の本来の意味を鑑賞する
古代詩:「韓遜を都に遣わして皇帝に謁見させ、科挙を受けさせる」時代: 唐代著者: セン・シェンニセア...
なぜ西漢時代には郡と王国が共存していたのでしょうか?劉邦の無力な妥協
なぜ西漢時代には県と王国が併存していたのでしょうか。郡国制と呼ばれる郡と王国の併存制度は、西漢初期に...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 王紫安』の原文の筋書きは何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
「中国のスタジオからの奇妙な物語」からの「王子安」の原文東昌[1]の有名な学者である王紫安は、畑に閉...
燕王后らは劉宝安をどのような罪で告発すれば王位継承権を剥奪できるのだろうか?
元初二年、東漢の安帝劉虎は、寵愛する燕を妃に立て、宮女の李が長男劉宝を産んだばかりで、喜ばしい出来事...
なぜ宋代の歌詞は中国文学史上最も有名なのでしょうか?
はじめに: 『宋辞』は新しいスタイルの詩であり、宋代に流行した漢文学の一ジャンルであり、宋代文学の最...
張中蘇の「秋夜の歌」:この詩は仕上げの手法を用いている
張仲粛(769年頃 - 819年頃)は唐代の詩人で、雅号は慧之としても知られています。彼は富里(現在...
数十年のうちに曹魏が司馬家に簒奪されたのはなぜ曹丕の責任だと言われるのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...