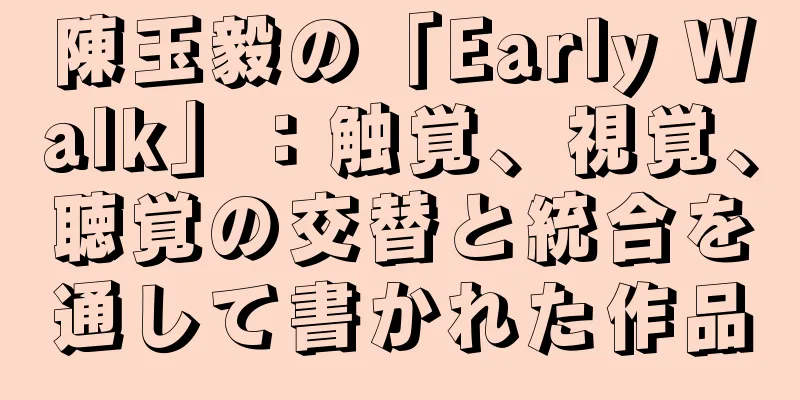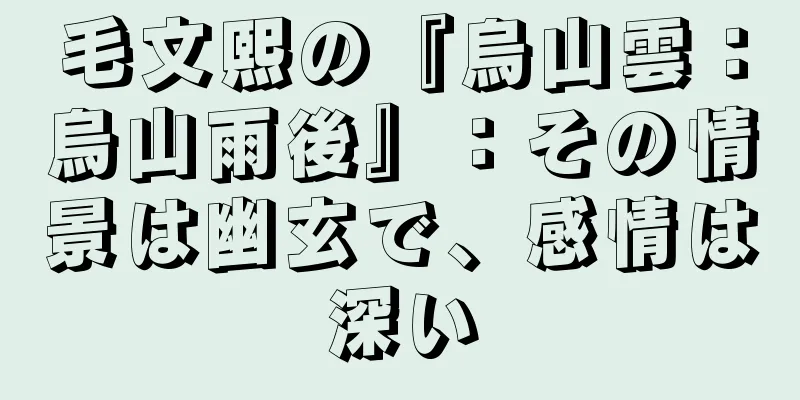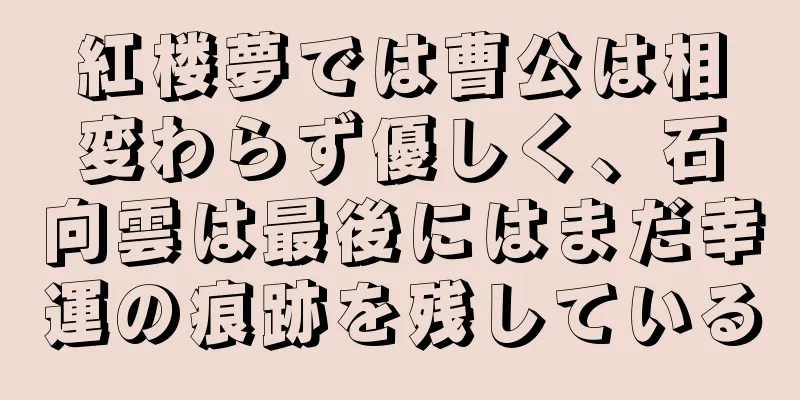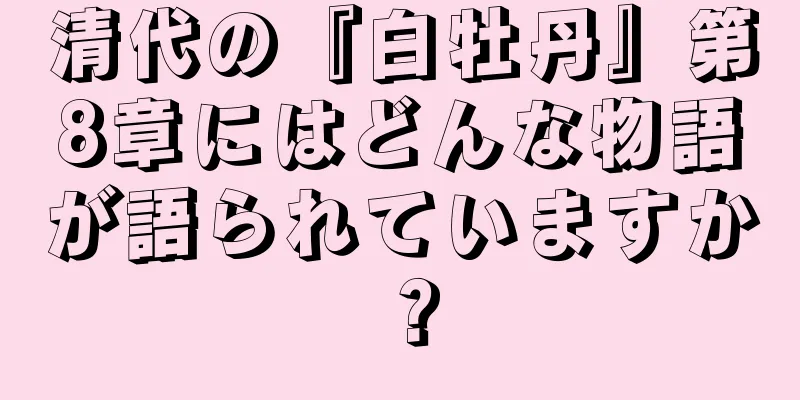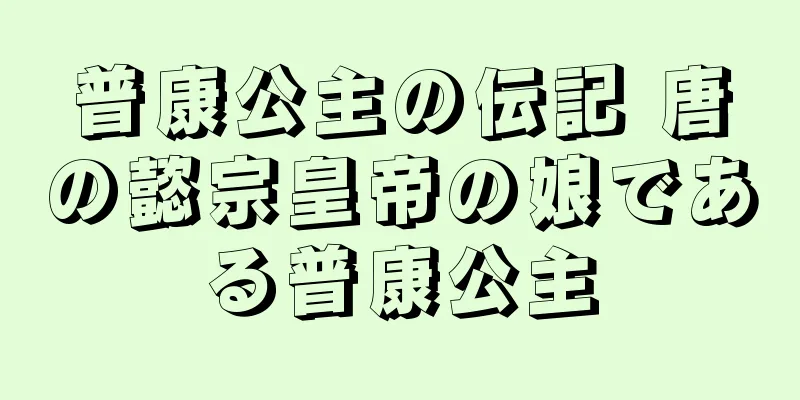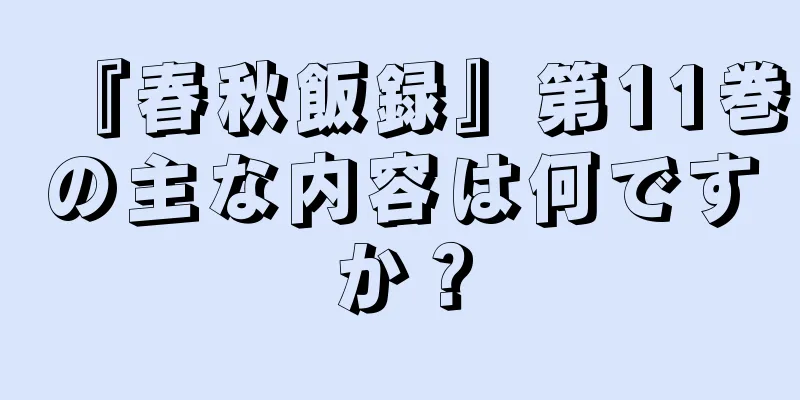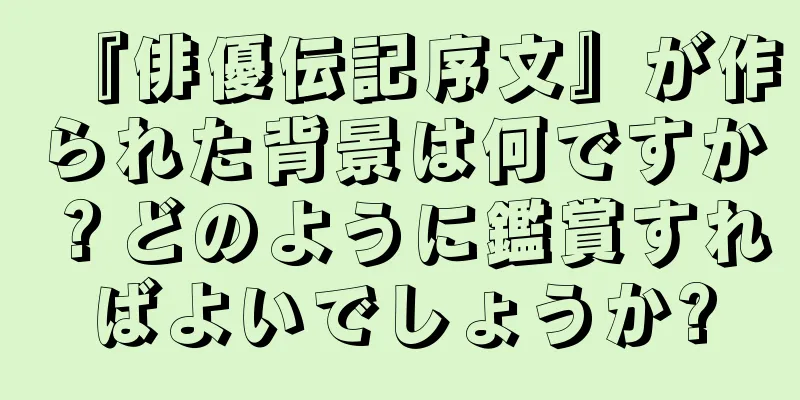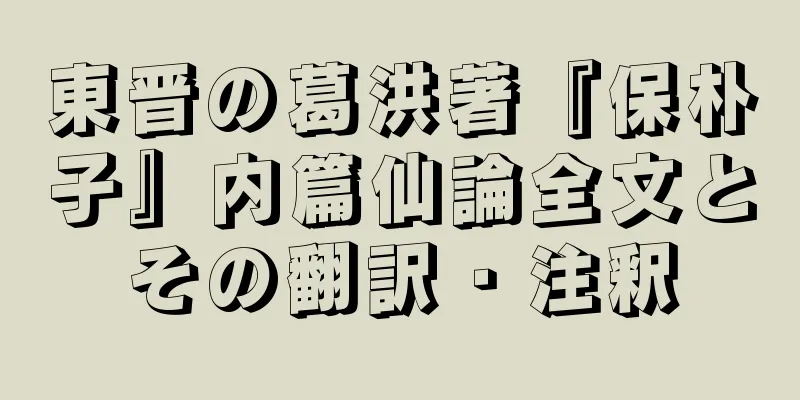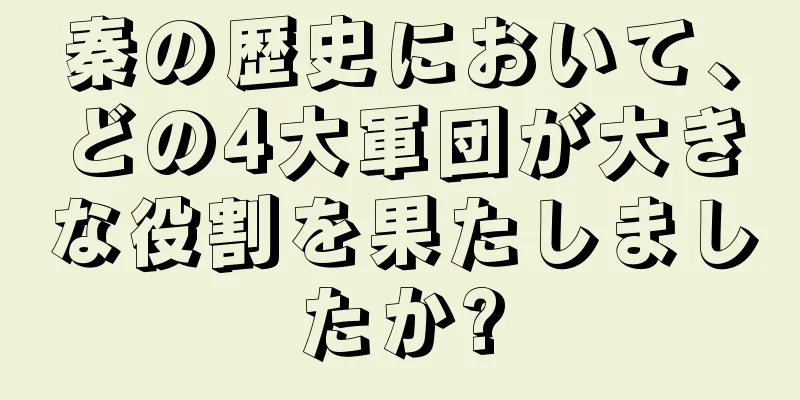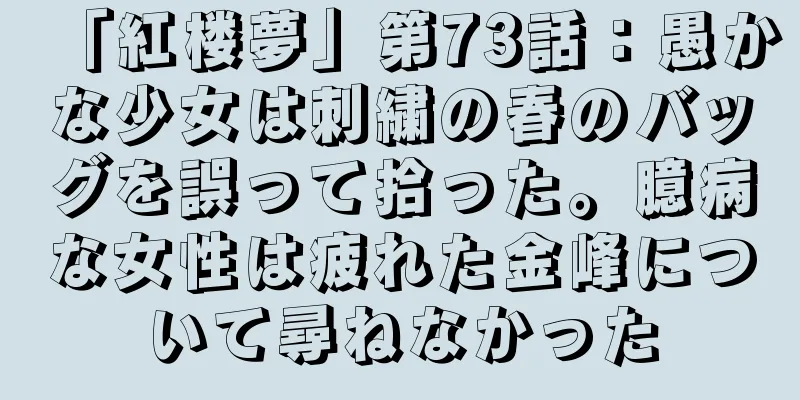明代古詩の鑑賞:湖畔亭の雪見。この古詩はどのような情景を描いているのでしょうか。
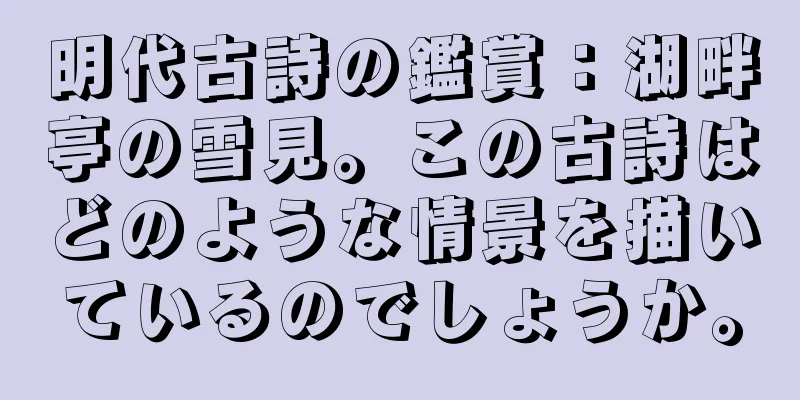
|
明代の張岱による『湖畔亭の観雪図』、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! 崇禎五年十二月、私は西湖に住んでいました。 3日間大雪が降り、湖には人や鳥の鳴き声も聞こえなかった。その日の真夜中、私は小さなボートに乗って、毛皮にくるまり、湖の真ん中にあるあずまやまで雪を見に行きました。空も雲も山も水も、すべて霧氷で白く染まっていました。湖に映る影は、長い堤防と湖の真ん中にあるあずまや、小さなボートと、ボートに乗っている2、3人の人影だけでした。 (ユナはユナとしても知られています) 東屋に着くと、二人の人が畳の上に向かい合って座り、少年がストーブで酒を沸かしているのが見えました。彼は私を見てとても喜んで、「湖にあなたのような人が他にもいるなんて!」と言って、一緒に飲もうと誘ってくれました。私は白ワインを3杯飲んで帰りました。苗字を尋ねると、彼は金陵出身で、ここの客だと言いました。船を降りるとき、周子は「頭がおかしいなんて言わないで。あなたより頭がおかしい人はたくさんいるわ」とつぶやいた。 明代後期の随筆は、中国散文史において、秦以前の哲学者や唐宋の八大家の随筆ほど目を引くものではないが、それでも一定の地位は持っている。それはまるで、山深い岩の割れ目に咲く蘭の花束のようで、花と雄しべがまばらで、風に吹かれて芳香を放ち、眩しいほど華やかではないが、独特の気高い魅力を持っています。 崇禎五年十二月、私は西湖に住んでいました。 最初の 2 つの文は時間と場所を示しています。過去の旅を記録したコレクションの作品のほとんどには、彼らが故郷を忘れていなかったことを示すために明代の日付が記されている。ここでの「崇禎五年」も同様です。 「12月」は真冬の雪が降る時期であり、「私は西湖に住んでいます」は私が西湖の近くに住んでいることを示しています。冒頭のこの2つのさりげない文章は、時間や場所の面で、その後の大雪や湖の雪景色に微妙につながっています。 3日間大雪が降り、湖には人や鳥の鳴き声も聞こえなかった。 冒頭からよく見ると、この二文だけで雪に覆われた湖の情景が想像でき、読んでいると寒さが迫ってくるような気分になります。作者の巧妙さは、大雪を視覚ではなく聴覚で描写している点にある。「湖には人や鳥の音はない」。大雪の後の静寂について書いている。湖や山々は凍りつき、人も鳥も震えて外に出る勇気がない。寒すぎて音も出ず、空気さえ凍りついているようだ。 「絶対に」という言葉は、すべてが静まり返った氷と雪の世界の、ぞっとする冷たさを伝えています。大雪の荘厳さを、人の聴覚や心理的感覚の観点から巧みに表現した、高度なフリーハンド技法です。それは唐代の劉宗元の有名な詩「河上雪」を思い起こさせます。「千の山に鳥は飛び立たず、千の道に人は見えず、蓑に麦わら帽子をかぶった老人が、雪の下の冷たい川で一人船に乗って魚釣りをしている。」劉宗元のこの河上雪景色の絵は視覚的な側面に重点を置いています。河上と空は広大で、「鳥は見えず」、そこには「雪の中で魚釣りをしている」老漁師が一人いるだけです。張岱は「人も鳥も沈黙している」と書いたが、この沈黙はまさに人間の聴覚であり、沈黙の中にも人間は存在する。劉さんの詩はわずか20語から成り、最後に「雪」という言葉が出てくるが、これは結果から原因を辿っているとも言える。張岱は「3日間の大雪」により「湖には人や鳥の声が聞こえなくなった」と記しており、これは原因から生じた結果であると言える。両者は手法は異なりますが、どちらも風景を鮮やかに描写するという芸術的な効果を実現しています。 「河上雪」の「千山に鳥は飛ばず、千道に人は見えず」という一節が、寒い川で一人漁をする漁師を誇張して興奮させる意図で書かれたものであるとすれば、張岱はそれを、寒さに耐えて雪を眺める次の場面を反映させるために使ったのである。 その日の真夜中、私は小さなボートに乗って、毛皮にくるまり、湖の真ん中にあるあずまやまで雪を見に行きました。 「この日」は「三日間の大雪」の後の極寒の日を指し、「明けの見張り」は夜8時頃の寒さが倍増する最初の見張りを指します。 「毛皮にくるまって、暖炉のそばで」という文章では、寒さを防ぐ素材を使って、骨まで凍るような寒さと対比させています。想像してみてください。氷と雪が降る「人や鳥の声も聞こえない」世界で、実際に夜遅くに「湖の真ん中のあずまやに行って、一人で雪を眺める」という人がいます。なんと孤独で優雅な趣味でしょう。これは主流とは大きく異なります。「湖の真ん中のあずまやに行って、一人で雪を眺める」の「一人で」という言葉は、「冷たい川の雪の中で一人で釣りをする」の「一人で」という言葉に似ています。ここに作者の純粋で超然とした誠実さと、孤高で自画自賛的な気分が言葉では言い表せないほどに表れているのではないだろうか。夜に一人で出かけたいと思うのは、他人に見られたくない、他人に会いたくないからだろうが、この孤独感には、世間から逃げ出したいという恨みも含まれているのではないだろうか。 霧氷が厚く、空、雲、山、水がすべて白く、作者が湖の雪景色を幻想的な筆致でどのように描いているかをご覧ください。湖に映る影は、長い堤防、湖の真ん中に点在する東屋、小さなボート、そしてボートに乗っている2、3人だけです。 まさに夜の湖と山に積もった雪をぼんやりと描いた水墨画です。「霧氷」とは、湖面に広がる雪のような光と水蒸気を表現した言葉です。 「空も雲も山も水もみな一色」というように、「そして」という文字を3つ繰り返して使うことで、空も雲も湖もみな白く区別がつかない情景を鮮やかに表現しています。作者はまず、まるで「上から下まで真っ白」を俯瞰しているかのような大まかな文章を書いている。雪を眺めるという視点から見ると、一目見たときの全体的な感覚や印象と非常に一致している。その後、視点が変わり、「長い堤防の跡」、「湖の真ん中にある一点のパビリオン」、「残っている小さな船」、「船には2、3人の人」など、詩的なクローズアップショットに変わります。これはシンプルな絵画と夢のような詩であり、人々にそこにいるような、そしてそこにいないような、漠然としたトランス状態の感覚を与えます。著者が数量詞を洗練させる技術には驚かざるを得ません。 「上下白」の「一」はぼやけて判別しにくいものを表すので大きいと感じますが、「跡」「点」「芥子粒」の「一」はぼんやり判別できるものを表すので小さいと感じます。まさに「一」という言葉から生まれる心境といえるでしょう。同時に、「長い堤防の跡」から「湖の真ん中にある東屋の点」、「残った船の芥子粒」、「船の中の人の二、三粒」まで、レンズはどんどん小さくなり、極小になります。 「痕跡」「点」「芥子粒」「粒」といった、それぞれが小さい数量詞は、視線の動きや風景の変化を表現し、まるで天地のために作られ、そこに固定され、少しも揺るがないと感じさせます。この一節は風景を描写しているが、それは単なる風景の描写にとどまらず、この氷と雪の混沌とした世界から、この世の生命は「太倉米」のように広大であるという作者の深い感情を感じることは難しくない。 次のステップでは別の場面に変わります。東屋では、2 人の人物がマットの上に向かい合って座り、少年がストーブで酒を沸かしています。彼は私を見ると大喜びし、「湖にあなたのような人が他にもいるなんて!」と言って、一緒に飲もうと誘ってくれました。私は白ワインを3杯飲んで帰りました。苗字を尋ねると、彼は金陵出身で、ここの客だと言いました。 「私は一人で雪を見るために湖の真ん中にあるあずまやに行った」が、予想外に誰かが私より先にあずまやに到着していた。この予想外の一筆は作者の予想外の驚きを表現し、読者の予想外の驚きも引き起こした。しかし作者は驚いたとは言わず、二人の客が「私に会えてとても嬉しかった」と書いている。背中に白粉を塗って客を亭主のように描いているが、これは作者の筆遣いがいかに機敏で変化に富んでいたかを示している。 「湖の中に、彼のような人が他にもいるなんて、あり得るだろうか?」この叫びは二人の客に向けて発せられたものだが、実はそれは著者の心の声だった。著者の天才性は、一言も語らずに「その優雅さを完全に捉えている」点にある。二人の客は「一緒に飲もう」と誘ってくれて、三者三様のバランスがとれた。親しい友人に出会えたことは幸運だった。寒くて寂しい湖と山々に少し暖かさが加わったようだったが、荒涼とした雰囲気は本質的には変わらなかった。これは李白の「杯を上げて明るい月を招き入れると、私と私の影は三人になる」に似ていますが、それは単なる幻想的な慰めです。 「他にどこで見つけられるか?」というのは、そのような人は稀だということである。 「無理やり白ワインを3本飲む」というのは、親しい友人に感謝するためです。 「無理やり飲む」人は、本来は飲めないのに、この場面、この時、この人に会うと飲まざるを得ないのです。酒を飲んだ後、二人は別れを告げて「彼の姓」を尋ねたが、驚くべきことに彼は詳しく話さず、「私は金陵から来た客人です」とだけ言った。湖の上でこの二人の友人はもともと異国の地をさまよっていたことがわかり、彼らの言葉は将来再び会うのは難しいだろうということを暗示していた。この補足的なナレーションは、作者の限りない憂鬱を表しています。この広大な世界では、真の友人を見つけるのは難しいです。人生は雪と泥の中の足跡のようなもので、一瞬のうちに私たちは皆離れ離れになります。そう思うと、とても悲しい気持ちになります。私たちの意見としては、記事はここまで完成しており、完璧で何の後悔もありません。しかし、著者はまだ満足していなかったので、さらにいくつかの文章を書きました。 船を降りるとき、周子はつぶやいた。「頭がおかしいなんて言わないで。あなたより頭がおかしい人はたくさんいるわよ!」 これを読んで、本当に驚きました。古代人が詩を論じたとき、点と染料の理論がありました。この結末は、点と染料が一つに融合したものと言えます。船頭の言葉を通して、「愚か」という言葉が指摘され、「愚か」という言葉は、夫の「愚かさ」を「夫と同じくらい愚かな人々」の愚かさと比較し、感染させることによって完全に説明されます。いわゆる「夫と同じくらい愚か」は、夫の「愚かさ」を軽減するのではなく、同じ調子で夫の「愚かさ」を強調します。 「つぶやく」という言葉は、船頭が独り言を言い、困惑している様子を表現しており、まるで船頭の声が聞こえ、船頭の姿が見えるかのように見えます。こういうところも作者の誇りであり、感動の場所です。文章は感情に溢れており、長く残る余韻を残します。 「痴」という言葉は特別な感情を表し、山や川を愛し、無関心で孤独な彼の独特の性格を表しています。 この短編は物語、風景、叙情性が融合しており、時折登場する人物の描写も生き生きとした調子である。軽妙かつ奥深い文章で書かれており、句読点を含めた全文は200語未満です。これだけでも、私たちが参考にし、学ぶ価値があります。もちろん、それが明らかにする傲慢さや受動的な現実逃避を盲目的に評価するのではなく、批判的に扱い、歴史的に分析する必要があります。 |
<<: 宋代古散文の鑑賞:岳陽塔碑文。この古散文はどのような場面を描写しているのでしょうか。
>>: 『易経』は何について語っているのでしょうか?なぜこの作品は古典の最初の作品とみなされているのでしょうか?
推薦する
秦の始皇帝の兵馬俑の価値はいくらですか?誰かが彼の命と引き換えにしたのでしょうか?
秦の始皇帝の兵馬俑の価値はいくらでしょうか? 誰かが自分の「命」と引き換えに手に入れたのでしょうか?...
白居易の古詩「余暇」の本来の意味を理解する
古代詩「余暇」時代: 唐代著者: 白居易給与は高く、ポジションも低くなく、部門内での余暇時間もありま...
『清代名人奇譚』第4巻の登場人物は誰ですか?
◎ジ・ウェンダの前世世に伝わる有名人の前世は、すべて星や霊や僧侶によるものであり、この説は完全に間違...
「別れの思いと東流の水、どちらがいいか聞いてみろ」という有名な言葉はどこから来たのでしょうか?
まだ分からない:有名な一節「東流の水に尋ねてみよ、どちらに別れの気持ちが長いか、短いか」はどこか...
中国古典の原典の鑑賞:『書経』『周書』『虫子篇』
武王は三百台の戦車と三百匹の虎の護衛を擁し、秦王と穆野で戦い、『穆史』を著した。厲子の日の明け方、王...
『紅楼夢』の賈夫人の感情知能はどのくらい高いのでしょうか?一言で恥ずかしさは解消できる
『紅楼夢』の賈牧の感情知能はどれくらい高いのでしょうか?これは多くの読者が気になる問題です。次は一緒...
国外の親族が政務に介入するケースがなぜ多いのでしょうか?後漢中期から後期にかけて、どのような独裁事件が起こりましたか?
古代中国の封建王朝では、権力に関与したい場合、王族の血統に頼ったり、美貌で後宮を支配したり、科挙に合...
『女仙秘史』第13章:ヒロインを松陽に招き、男装に着替えて洛邑の仙人を訪ねる
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...
『紅楼夢』における賈元春と賈一族の盛衰との関係は何ですか?彼女の結末はどうなったのでしょうか?
元春は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物。賈家の長女で、四姉妹のリーダーである。 「歴史の流れを遠く...
『丁鋒波:暖かい日の窓辺に映る緑の紗』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
丁鳳波:暖かい日、窓に映る緑の紗欧陽瓊(五代)暖かい日には、何もない窓に緑の紗が映り、小さな池の湧き...
蘇哲の『詩集』は歴史上どのように評価されてきたのでしょうか?
蘇哲の『詩集』は歴史上どのように評価されたのでしょうか?これは多くの読者が特に知りたい質問です。次の...
本草綱目第8巻水防の具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
フェイ・インドンとヌルハチの関係の秘密を解明
費英東とヌルハチ費英東とヌルハチはともに中国清朝の人物である。一人は大臣で、もう一人は皇帝であった。...
なぜ王昭君は漢の元帝に寵愛されず、外国の王子と結婚させられたのでしょうか?
昭君の辺境への旅については、多くの人が知っているはずです。しかし、貂蝉、西施、楊貴妃とともに四大美女...
『紅楼夢』で、リン・デイユはなぜ両親を亡くし、他人の家に住むことになったのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...