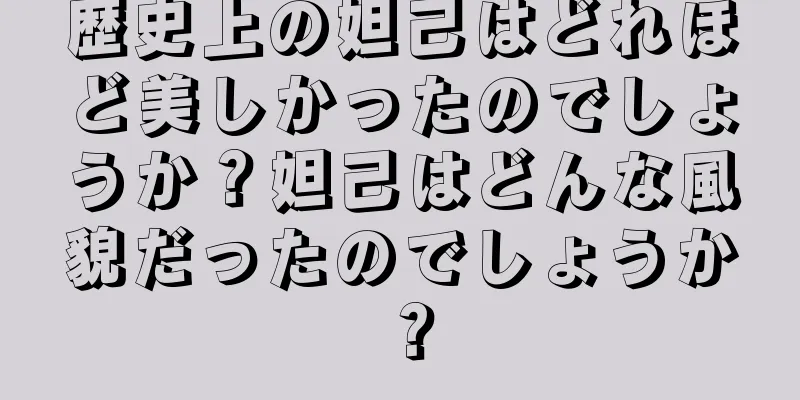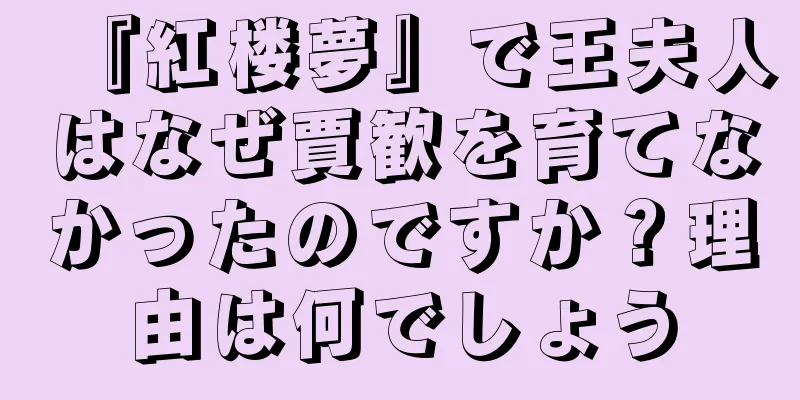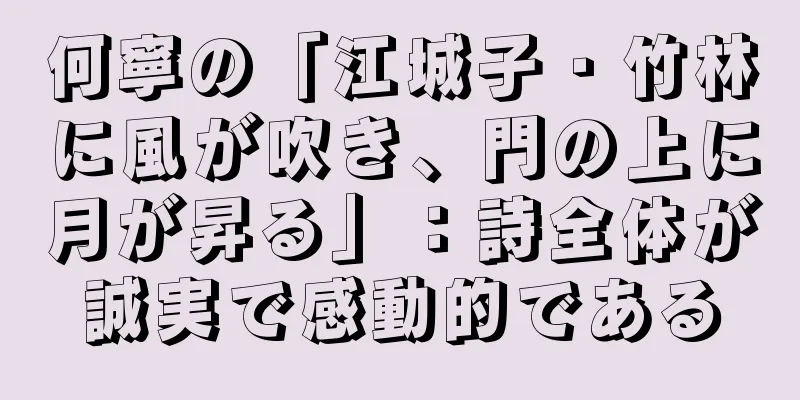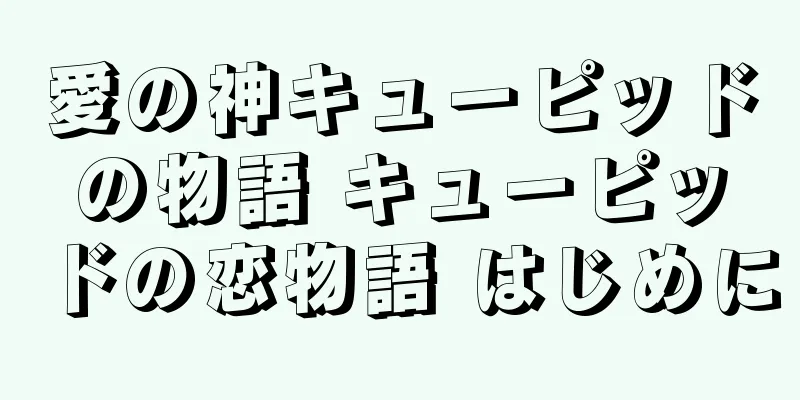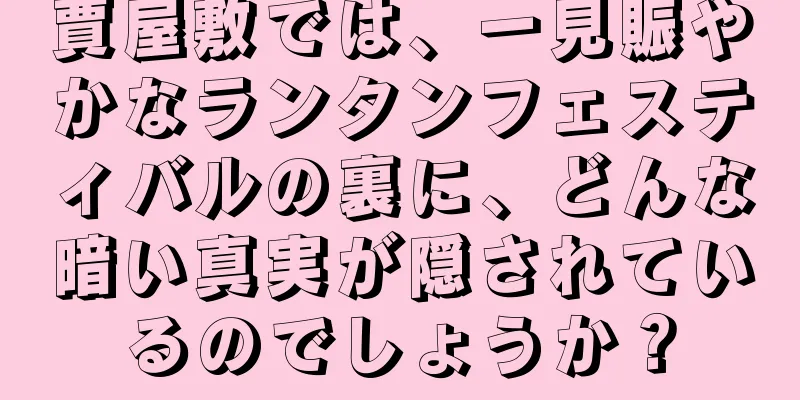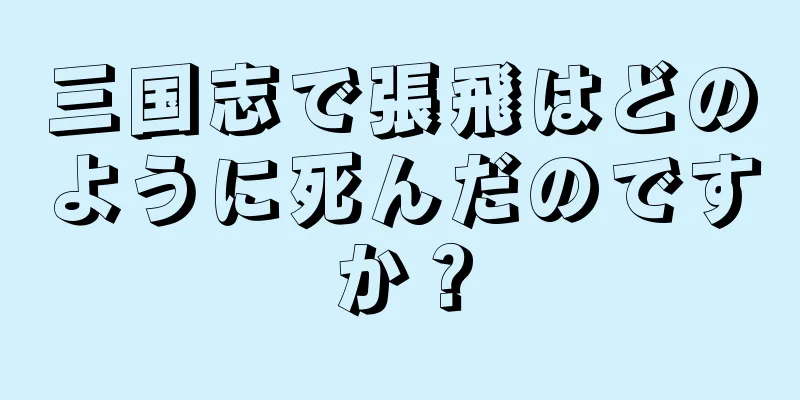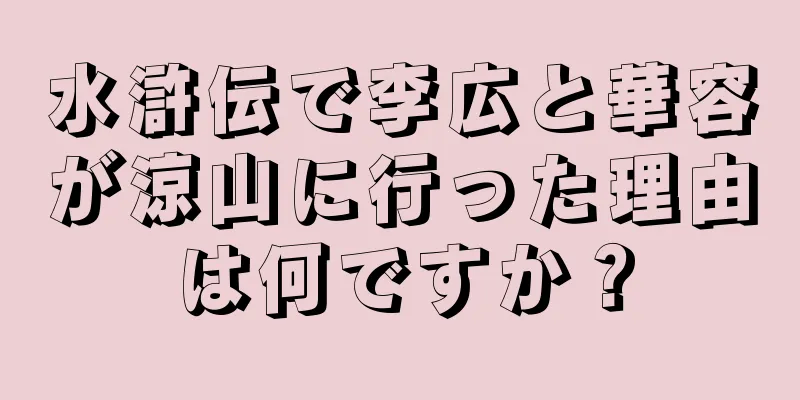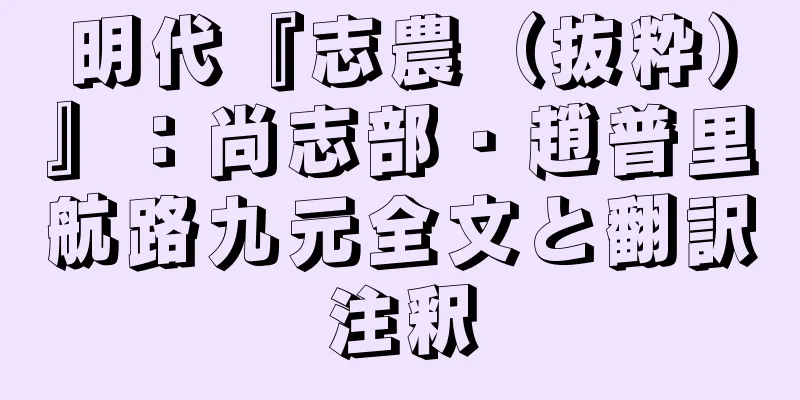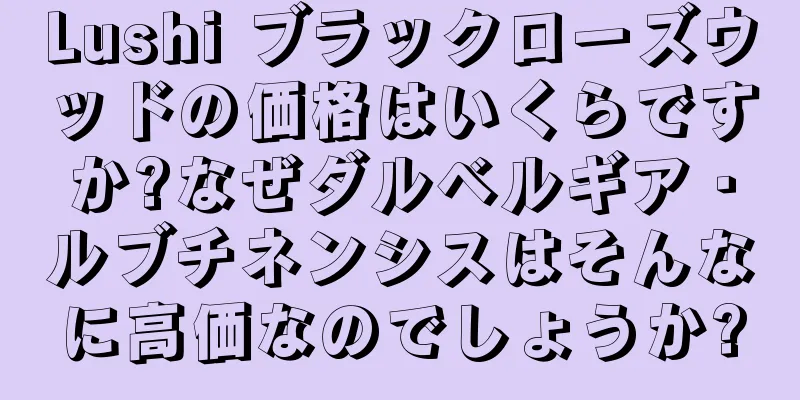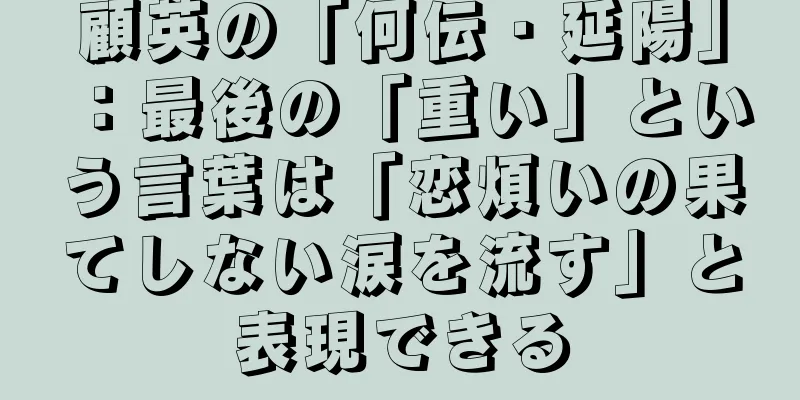古典文学の傑作『太平天国』:地理編第11巻全文
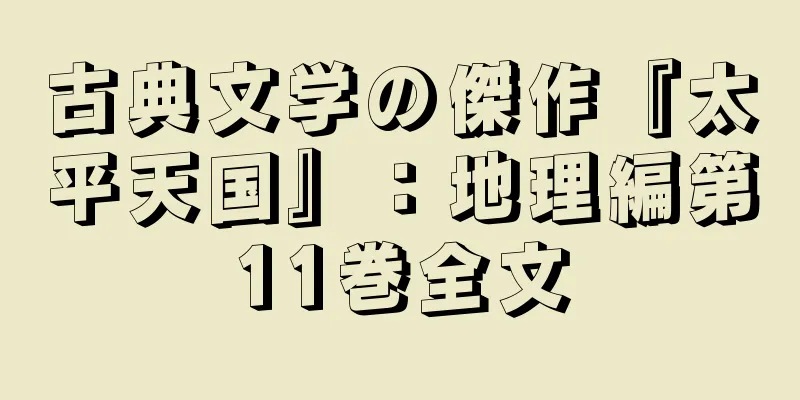
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が地球部門第11巻の詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! ○江東の山々 景亭山 『県州志』と『宋永初山河志』には、万嶺の北に景亭山があり、山頂には神社があり、謝条が雨と競って詩を書いた場所であると記されている。この神様は紫花富君と名付けられ、非常に効果があります。 カバーマウンテン 紀伊の『宣成記』にはこう書かれている。「蓋山を100段ほど登ると泉がある。」昔、シュウという名のまだ結婚していない娘がいました。彼女の父親がここで薪を分けていました。突然、娘は泉の近くに座り込んでしまい、引き離すことができませんでした。父親は急いで家族に知らせました。その後、彼らは澄んだ泉だけを見ました。そこにいた女性は音楽が好きだったので、弦楽器を弾きました。すると、泉が波とともに湧き出て、一組の赤い鯉が飛び出しました。今日も楽しく楽しく、春はまだまだ沸き立っています。 九華山 『九華山記』にはこう記されている。「この山は独特で美しく、雲よりも高く、峰や尾根の形が奇妙で、その数が九つなので、九子山と呼ばれている。」李白が長江と漢江を旅したとき、この山の美しさに気づき、九華山と改名しました。 山には数エーカーの池や数千石の水田もあると言われています。池には魚がいます。一番年長のものは長さが半フィートあり、平らな頭、赤い尾、赤いひれ、赤い腹を持っています。観察したい人は木をたたくと魚が飛び上がります。池に食べられるものをまき、食べたら隠れます。その水は龍潭に流れ込み、滝となって流れ、龍潭渓に流れ込む。そこには小麦粉のような土だが固くない白い洞窟があり、凶作の年にはよく食べられる。 顧野王の『地理志』にはこう記されている。「九華山は高さ1000フィートである。」 劉玉熙は序文でこう言っている。「かつて私は中南と太華を愛し、それ以外に特別なものは何もないと思っていた。かつて私は女冀と荊門を愛し、それ以外に美しいものは何もないと思っていた。しかし九華を見たとき、以前はそう言うのがいかに簡単だったかを後悔し始めた。」 檜山 『宣城土井』には、夷山は北で九華山とつながっており、山頂は険しく、遠くから見ると王冠のように見えるため、夷山と呼ばれている、とある。 牛頭山 『宣城土経』には、牛竹山が川に突き出ており、そこは牛竹崎と呼ばれ、古代の渡し場である、と記されている。 『江表伝』にはこうある。司馬徽の『天命論』にはこうある。「南東に黄色い旗と紫の傘が見える。最終的に天下を治めるのは、静陽の君主だろうか?」 寿春の子供たちの間では、「皇帝は西へ行くべきだ」という噂も広まっていました。孫昊は大いに喜び、すぐに妻と数千人の妾を連れて牛竹の陸路を西へ進み、青雲に乗って洛陽に入った。たまたま大雪が降っていて、凍え死にそうになりました。 『地理記』にはこう記されている。牛竹山の頂上に忍び寄った男がいた。彼は、この場所は洞庭湖とつながっていて底なしだと言った。彼は奇妙な形の金色の雄牛を見て、驚いて逃げ出した。牛竹山の北側は菜石と呼ばれています。彩石渡し場の向かい側に謝将軍の神社があります。 『源河記』には、「商人はこの地から石を採り、都に石の島を建てたので、菜石と名付けられた。呉の初めに、周瑜が牛竹に駐屯し、鎮西将軍の謝尚もここに駐屯した」と記されている。 マザーマウンテン 『宣城土井』には、慈母山は当踏県の北に位置し、川に面している、と記されている。 『丹陽記』には「この山には笛を吹くための竹が生える」とある。王宝の『東暁譜』には「もともと笛が生える場所は揚子江の南の丘陵と遺跡である。ここがその場所である。竹は丸くて細く、他の場所のものと異なっている。霊倫が渭谷で竹を集めて以来、この竹だけが大切にされてきた。歴代の楽局に贈られ、一般に古初山と呼ばれている。山には慈母寺がある」とある。 五湖山 『宣城地図帳』には、蕪湖山は県の南西部にあり、その山の名前は湖にちなんで付けられていると記されている。漢末期、湖のほとりに蕪湖県が設けられた。土地が低く、水深が浅かったため、雑草が生えていたため、郡名が付けられた。金は重要な町であり、謝尚と王盾の両者がここに駐留していた。陳平県は廃止され、その領地は当途県に編入された。 王府山 『宣城土経』にはこう記されている。昔、ある男が楚へ行き、何年も帰ってこなかった。妻が夫を探すために山に登ったが、石になってしまった。この山は川に隣接しており、周囲は50マイル、高さは100フィートです。 博王山 『宣城土井』には、博王山、長江の両側に2つの山があり、東の山は博王山と呼ばれ、西の山は天門山と呼ばれていると記されています。 『県州記録』には「天門山は峨眉山とも呼ばれ、楚が呉の軍を捕らえた場所である」と記されている。この2つの山は向かい合って位置しているため、当時の人々は東梁山、西梁山と呼んでいたが、県図では天門山となっている。 『地理志』には、東西に川を挟んで向かい合う伯王と涼山は、数マイル離れており、天門と呼ばれている、と記されている。 宋の孝武帝は「梁山は天上の衛を表し、国の象徴とする。二つの山を門として用いるので、天門と呼ばれる」という勅令を出した。 霊陽山 『宣城土井』には、楊霊山は荊県の南西130マイルにあると記されている。 『仙人伝』には、霊阳子明が白龍を捕まえて放したとある。 5年後、丹陽の霊陽山に龍がやって来て子明を迎え、100年以上経って子明は不老不死を達成した。その山は1000フィート以上の高さがある。子安という仙人もいて、20年間子明に従っていたが、突然亡くなり、山のふもとに埋葬された。そこには黄色い白鳥が木に止まって「ジアンジアン」と歌っていることが多い。 白鹿山 『宣城地図帳』には、宣州の白鹿山は県の東5マイルにあり、元々の名前は楚山であったが、桓温が娼婦を連れてこの山を訪れ、白鹿の歌を歌う音楽を演奏したため、白鹿山と改名されたと記されている。 中山 『宣城地図帳』には、宣州中山は独山とも呼ばれ、麗水県の南東10マイルに位置し、他の山々とはつながっていないと記されている。古代の伝説によると、中山には美しい筆を持つ白ウサギがいたそうです。山の前には「独水」と呼ばれる水源があります。 『于地記』には「宣州麗水県に孤山があり、その下には果てしなく流れる孤川がある」と記されている。これがその山である。 三河山 『宣城土経』には、三和山は麗水県の南東60マイルにあると記されている。昔、パンという名の三兄弟が不老不死を求めてこの山にやって来ました。後に彼らは悟りを開き、三羽の白い鶴に姿を変えてこの地から空に飛び立ちました。 イーシャン(イーイー) 『歙県地図帳』には、北邑山は歙県の北西168マイルに位置し、標高は1,170フィート、豊楽川はそこから流れ出ていると記されている。かつては黄山と呼ばれていましたが、天宝6年に勅令により改名されました。揚子江南部の最も大きな山には天台山と天母山があります。天母山は浙江省に近く、天台山は広大な海を見渡せます。河川や海は、実はすべての河川が流れ込む地下の場所です。しかし、歙州は河川の上流であり、海の源です。現在、社川の平地は既にこの二つの山の高さと同じ高さになっており、山の高さは天と同じである。浙江省の東西にある玄山、社山、池山、饒山、江山などの山々はすべてこの山の支脈であることは明らかである。すべての山頂はまるで石から切り出されたかのように岩でできています。山の下には果てしない霧と靄が漂い、雷と雨が降っています。下城洞、不動滝、泉はどの山頂にも見られます。森や小川の下、岩山の上を見ると、言葉では言い表せない不思議な痕跡や形があります。それは仙人の洞窟や住居に違いありません。山頂には伏丘公の祭壇があり、そこには色とりどりの魔法の鳥が住んでいます。ここは伏丘公と容成子が旅した場所です。しばらく前、ある人が祭壇に着くと、突然明るく光る塔が見えました。塔の前には蓮池があり、両側には塩と米が山積みになっていました。彼は家に帰り、村人たちを連れて塩と米を取りに行きましたが、どこにあるのか分かりませんでした。山のふもとに住む人々は、山頂から聞こえてくる天上の音楽の音をよく耳にします。 霊山 「郡と州の記録」にはこう記されている。「歙県には神聖な山がある。雨が降りそうな時、真っ先に太鼓と角笛の音が聞こえる。」山の上に車のカバーのような丸い石があります。郡では太鼓の音を戦争の合図として使用します。一度鳴らすと人々は移動を命じられますが、鳴らさなければ人々は立ち去りません。この山は三宮山とも呼ばれています。3年に一度山火事が起きます。火事で木がすべて燃え尽きなくても、人々が木を燃やすと雨が降ります。 『新安記』はこう言っています。霊村の山には霊香という香りのよい草が生えていて、また、シベリアヒオウギも生えています。山には道教徒が祈りを捧げる祭壇があり、線香を焚かなくても自然の香りが漂います。村人たちはここでよく狩りをしていたが、山の神を怒らせ、何も得られなかった。 『地理志』には、霊山は高く険しく、高さ数フィートの丸い石があり、その上に石の蓋がしてあるとも記されている。 ロック 善千之の『丹陽記』には、次のように記されている。「穆陵県の南方三十里に岩山があり、西側に石室があり、東の道の左側に長さ十フィートの四角い石があり、呉の功績を讃える碑文が刻まれている。孫昊が建てた。」 三つの山 山千之の『丹陽記』には、江寧県の北12マイルに、川でつながる3つの山があり、三山と名付けられている、と書かれている。そこは昔の渡し場だった。 横山 山千之の『丹陽記』には、丹陽県の東方十八里に水平な山があり、その長さは数十里に及んでいると記されている。楚の子王は衡山まで行ったという説もある。 鉄岩山 山千之の『丹陽記』には、「雍世記」に「鉄仙山は県の南に百里余りあり、幅は約二百里。この山は鉄を産出し、揚州では現在それを鋳造している」とある。 九景山 『古書紀』には、この県の南10里に九景山があり、殷仲文が桓公に従って九景を訪れ、9月9日に詩を詠んだ場所であると書かれている。 石城山 『江城地記』は言う:「石城山の稜線は千里に及び、姿は似ている。旅人は呉の石城を楚の九夷に似ていると思う。」矢竹や桑の木がたくさんあります。 (山の上に都市があるので、その名前が付けられました。) シェシャン 『江城地記』によると、胡村には佘山という山があり、その山には健康維持に使える薬草がたくさん生えているので、その名が付けられたそうです。山の四方には多くの尾根があり、形が傘に似ていることから観光客は山山と呼んでいます。かつて山頂には周江城寺がありました。 黄鶴山 『景口記』には「黄河山があり、県境内にある」とある。晋の王公が太守だったとき、南西塔を万水、北西塔を芙蓉と改名しました。どちらも現在も残っています。 『地理記』には、この塔は川から飛び出し、鉄の鎖で縛られていたとも記されている。 シップレックヒル 『梁武帝東征記』には、南には富川山、九陽山、高麗山がある、と記されている。かつて高麗の娘が中国に来たとき、東シナ海の神が船でやって来て酒と求婚を申し出たが、娘は断ったという。海の神が船を転覆させ、酒が曲江に流れ込んだため、曲江酒は美味しいものになった。 北鼓山 『南徐州記』には、城の北西部に川に通じる尾根があり、三方を水に囲まれており、雲北谷と呼ばれている、と記されている。劉震の『景口記』にはこうある。「尾根は川に変わり、崖は水の上に垂れ下がっている。」昔の北谷は Gu と書かれていました。梁の皇帝高祖はこう言いました。「 Gu という文字が真を表すのに使われているのは事実ですが、北の港を眺めると本当に素晴らしいです。 Guwang のように Gu と書き直すのは理にかなっています。」 『地理志』にはこう記されている。「山に登って空が晴れていると、広陵の城が青空にあるかのように見える。」 タイガーヒル 顧凱之の『虎丘序』にはこう書かれている。「武城の北西に虎丘がある。」 『岳傑書』によれば、赫璽孟の名は虎丘で、彼の青銅の棺は三層であった。 女性の山 善千之の『南徐州記』には、丹踏県の西9マイルに、川沿いに女山がある、と書かれている。ここは山東省の徐公克が孫策を暗殺した場所です。 秦 呂山 善千之の『南徐州記』にはこう記されている。「浙陽県の南西35マイルに秦路山がある。」秦の始皇帝は川や海を見渡すためにこの山に登ったと言われています。 馬恩山 善千之の『南徐州記』には、済陽県の北9マイルに馬安山があり、東には郭普が埋葬された黄山があると記されている。 中州山 善千之の『南徐州記』にはこう記されている。「南沙県の北百里に中州山がある。かつては海の中にあり、海岸から七十里離れていたが、宜渓以来、砂が隆起して海岸と繋がった。」 三白山 善千之の『南徐州記』には、善県に三百山があり、鉄を産出し、しばしば軍事装備を供給していたと記されている。山東岬の南側には高さ10フィート以上、10人以上が入れる石の洞窟があり、常に唾液で湿っています。雨が降りそうなとき、南から雲が来て山に影を落とします。山もそれに呼応して雲を生じます。それが禹山に達すると、大雨になります。 ホースシューマウンテン 劉震の『景口記』には、「石県は東の馬臥山とつながっており、山の岩に馬の蹄の跡があるためにこの名が付けられた」とある。 ガーリックマウンテン 劉震の『経口記』にはこう書かれている。「舒安山には峰がなく、尾根は川に近い。魏の文帝は南を眺めてため息をついた。」 恵海山 『呉県沿海四郡記』には、岱海に慧海山がある、とある。 この山には金の牛がいると言われています。昔、三兄弟が一緒に掘って探しましたが、溝が崩れて三兄弟とも死んでしまったので、この山は金の牛にちなんで名付けられました。 石老山 劉道珍の『銭塘記』には、石木山に似た形の石の蒸し器があり、険しい山の頂上にあり、周囲は数十フィートで、下には三つの石で支えられている、と書かれている。 大皮山 『県州記録』には、次のように記されている。「余杭大壁山は、もともと余杭山と呼ばれ、幽泉とも呼ばれ、最も高く、最も険しい山である。」その隣には籐紙を生産する油泉村があります。 『晋書』にはこう記されている。郭文は、字を文居といい、余杭の大別山に隠遁して住んでいた。かつて、山の凶暴な獣が寺のそばの鹿を殺しました。文居はそれを人々に伝え、人々は鹿を捕まえて売り、そのお金を尼寺に寄付しました。ウェン・ジュは「必要なら売る。だから話し合う必要はない」と語った。 フラワーマウンテン 呂道占の『呉県記』には、「呉県に華山があり、太康年間に千弁の蓮が生えていたので、華山と呼ばれた」と記されている。 玉山 呂道占の『呉君記』にはこう記されている。「海邑県の西6マイルに毓山があり、そこに中勇の墓がある。」 陽澄山 董堅の『呉志』には、富春に陽城山があり、郡家の人々がそこに埋葬されていると書かれている。漢末期、陽城山には光があり、空には雲が浮かんでいた。 姑蘇山 董堅の『呉志』には、姑蘇山は姑虚とも呼ばれ、横山の北に位置すると記されている。 『越覚書』にはこう記されている。呉の徐門の外には九つの曲がり道がある。赫盧は姑姑台を訪れ、湖を眺め、白姑を垣間見るためにこの道を造った。 『淮南子』では古宇とも呼ばれる。 堰石山 董建の『武帝記』にはこう書かれている。「巌石山は県の西門の外にあり、またの名を石鼓山といい、その上に琴台がある。」 『越境書』には「呉の人々は硯石の上に観巴宮を建てた」とある。 劉逵の『武都譜』の注釈には楊雄の『方言』を引用してこう記されている。「呉には官娑宮があり、呉の人々は美しい女性を「娑」と呼ぶ。そのため、『三都譜』にはこう記されている。「幸いにも私は官娑宮に行き、そこでは女楽師が大臣たちを楽しませていた。」現在、呉県には官娑郷がある。 香山 董建の『呉志』には、呉王が美女たちに香を採らせたことから香山と名付けられたと書かれている。そのため、香を採る道があった。 華山 『華山景社記』にはこう記されている。『老子枕草子』にはこう記されている。「呉の西境に華山があり、そこで困難を乗り越えることができる。」長老たちは言った。「山頂の北側に池があり、千弁の蓮が生えている。それを食べると天に昇ることができるので、華山と名付けられた。」森は広大で密集しており、荒涼とした森が太陽を遮っています。 『地理記』には、この山には石の太鼓があり、晋の龍安年間に鳴らされ、その後孫恩の乱が起こったと記されている。この山は県の西63マイルにある。 宝山 「武帝紀」は言う:「宝山は県の西130マイルにあり、その真ん中に洞庭湖があり、その深さは誰も測ることができないほどです。」呉王は霊威張人を17日間洞窟の中に送り込んだが、すべてを見つけることはできなかった。彼は玉の葉を手に入れ、それに霊宝経二巻を刻み、孔子に見せて、これは禹の書だと言った。 『県州記録』には、洞庭山に五つの門を持つ宮殿があり、東は臨武、西は峨眉、南は羅浮、北は太月へと通じていると記されている。 『玄奘記』によると、呉国の西に莒区があり、山々に囲まれた沼地があり、洞庭湖の宝庫があり、地下に通じて琅牙と東呉に通じている。 『淮南子』には「洞庭湖の長蛇を斬れ」とある。 『左伝』には、哀公の元年、夫差が夫居で越を破ったとある。現在、太湖には藤澳山があり、その麓には大東宮があり、五山とつながっています。昔、宝山には三つの群れは存在せず、蛇、虎、キジと呼ばれていました。侯景の反乱の後、虎や蛇が人々に危害を加え始めました。 石鼓山 『県国記』には、呉王の宮殿は石鼓山にあり、越王はこの山に西施を献上したと記されている。山には石の馬があり、まるで人が馬に乗っているように見えます。南には石の太鼓があり、太鼓が鳴ると軍隊が立ち上がる。 スーシャン 『武帝紀』には、蘇里山は新石頭山とも呼ばれているとある。頂上には城があり、その下には飛泉と石の杵があり、呉の先王が碑文を刻んだ場所である。石竹の西側に家があり、昔ここで金が採掘されていたという言い伝えがある。 劉道珍は次のように記録している。「県の西に老木山がある。尾根の頂上には石の蒸し器があり、一人が揺らせば千人のごとく動く。」 ディンシャン 『呉地方記』には、頂山は浙江河の真ん中に突き出ており、波が打ち寄せ、旅人の妨げとなっていると記されている。 謝霊雲の詩にはこうある。「朝、玉浦南から出発し、夕方、富春鎮に泊まる。」頂山には雲も霧もなく、赤亭には湖も池もない。これが山です。 山の閉鎖 「武興記」は言う:「鳳珠は武康県の東18マイルにあり、古代の鳳峰王国であり、鳳公寺がある。」水は鳳珠、山は鳳山です。 奇山 「武興記」はこう言った。「玉前県の西2マイルに、旗丘という山があります。そこには高さ約30フィートの崖があります。謝安はかつてそこに登り、崖のそばに立って言いました。「伯渾は無名です。どうしてここを通り抜けることができましょうか。」当時は、それは難しいと考えられていました。もともとは太湖にあったが、禹が治水の際にこの地に移されたといわれている。 ルジ山 『五行記』にはこう記されている。「東銭県に汝子山がある。」徐如子は友人を弔うために呉に行き、かつてこの山に登ったことからこの名前がついた。 香山 『五行記』にはこう記されている。万山の北18マイルに香山がある。山のふもとで人が話すと、どんなに声が大きくても、その音は歪んで反響します。 夕べの山 『五行記』には、玉泉県の西60マイルに万山がある、とある。これらはすべて本物の墨の原料となる松の木で作られています。 百丈柳湘山 「五行記」はこう言った。「山溪村には百丈山と柳湘山という二つの山がある。」堯が洪水に遭遇したとき、この山は水没せず、高さ百フィートしか残っていなかったため、この山の名前が付けられました。水は山の尾根に沿って流れるため、六郷と名付けられました。 銀珠山 「五行記」は言う。銀竹山は伏溪河に隣接しており、山の上流から県までの水路は岩だらけで道も悪く、船の航行は不可能だが、下流の水路は安全なので、旅人はそこに集まる。晋王胡志は呉興の太守であったが、殷竹に到着するとため息をついてこう言った。「ここは気分が明るくなるだけでなく、太陽と月が澄んで明るく見える」。島の横の石の模様が印章に似ていることからこの名がついたと言われている。 天目山 『県州記録』には、天目山に、香峰樹という樹齢数百年の樹木があると記されている。 『于地之』にはこう記されている。頂上には二つの湖があり、それぞれ左目と右目と呼ばれているので、天目と名付けられた。山々は非常に高く険しく、美しい石の泉や有名なお茶がたくさんあります。 『道教雑書』にはこう記されている。「天目山は左側の地面より 7,500 フィート高く、右側の地面より 7,000 フィート高い。幅は 3,000 マイル。頂上には深淵があり、そこには食用魚がいるが、毒虫はいない。」 『水景珠』にはこう記されている。呉興県玉前県の北に天目山がある。山は極めて高く険しく、断崖や尾根が重なり合っている。西は後江に面している。山には霜木があり、いずれも樹齢数百年である。向峰林と呼ばれている。東側には、蛟龍池と呼ばれる数エーカーの深い沼地に流れ込む滝があります。水は県の西部を南に流れ、県の西渓河となる。 ビアンシャン 「郡および州の記録」には、扁山は扁和が翡翠を採掘した場所であると記されている。山東省には高さが数フィートもある籠がある。晋の太康年間に誰かが開けようとしたが、暗くて風が強かったため中止された。時代を経て彼に与えられた称号が何であったかは誰も知らない。 『宋書』には、蕭慧明が呉興の知事であったと記されている。郡境には汴山があり、その麓には項羽の廟があった。項羽は郡政によく出仕していたと伝えられている。彼の前後の7人の知事は、あえて官庁に出向くことをしなかった。慧明は崗冀に「孔済公はかつてこの県に仕えていたが、災難の知らせはなかった」と言った。そこで、盛大な宴会を開き、数日間客をもてなした。しばらくして、慧明は突然、身長が一メートルを超える男を見た。弓を引き、矢を射かけたが、男は姿を消した。その結果、男は背中に発疹を患い、十日後に死亡した。 |
>>: 『紅楼夢』で、賈家の母は、幽二潔が賈邸に入ったことを知ったとき、どのように反応しましたか?
推薦する
『紅楼夢』における西春と有施の関係はどのようなものですか?
希春は『紅楼夢』の登場人物。金陵十二美女の一人であり、賈家の四美女の末っ子である。歴史の流れを遠くか...
年庚瑶が好まれた理由は何ですか? 年庚瑶はどのようにして死んだのですか?
なぜ年庚瑶はそんなに好まれたのか?今日は、おもしろ歴史編集長が詳しく説明します〜年庚瑶は軍功が大きく...
水滸伝で穆洪はどのように死んだのですか?
水滸伝で穆洪はどのようにして死んだのでしょうか? 穆洪の簡単な紹介:穆洪は「梅哲蘭」や「天九星」の異...
石公の事件簿 第63話:地元の役人が石里亭で送別会を開き、桃花亭はパニック状態に
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
『紅楼夢』で薛宝才はなぜ迎春を抑圧したのですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
水滸伝で武松のお気に入りの女性は誰ですか?孫二娘と関係があるのでしょうか?
Interesting History の編集者は、読者が武松の物語に非常に興味を持っていることを知...
ロシアの農奴制改革の成功は主に統治者の支援によるものであった。
ロシアの農奴制改革は、ロシア近代史における重要な歴史的出来事です。ロシアの農奴制は長い歴史を持ち、長...
西洋史第7章:九輪杖が力を発揮し、四つの悪魔を一掃する
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
宋代の素晴らしい詩:男性と女性では全く逆の読み方をする
本日は、Interesting History の編集者が、皆様のお役に立てればと思い、宋代の奇妙な...
『清平月 博山行物語』の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
清平楽:博山への道新奇集(宋代)蹄鉄が柳の横を飛んでおり、露が重い旅の服を濡らしている。ねぐらにいる...
ルーウェン王女の伝記 唐の武宗皇帝の娘、ルーウェン王女
羅文公主(?-?)、唐の武宗皇帝李厳の娘。母親は不明。武宗皇帝の徽昌5年(845年)8月に爵位を授け...
兵法三十六策の簡単な紹介。これはどの物語から来ているのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、三十六計略についての記事をお届けします。ぜ...
『西遊記』で沙生はガラスのランプを壊したために現世に降格されたのですか?
本日、Interesting History の編集者は、皆様のお役に立てればと願いながら、『西遊記...
『紅楼夢』でなぜ丹春は鳳凰の凧を揚げたのですか?それはどういう意味ですか?
『紅楼夢』では、物語の展開や登場人物の個性の表現が、特定の対象を中心に展開されることが多い。Inte...
韓国の人々の伝統的な楽器はどのようなものですか?
韓国の民族楽器はもともと40種類以上あり、その中には東韶、短笛、笛、笙などの管楽器、箏琴(シャンフ)...