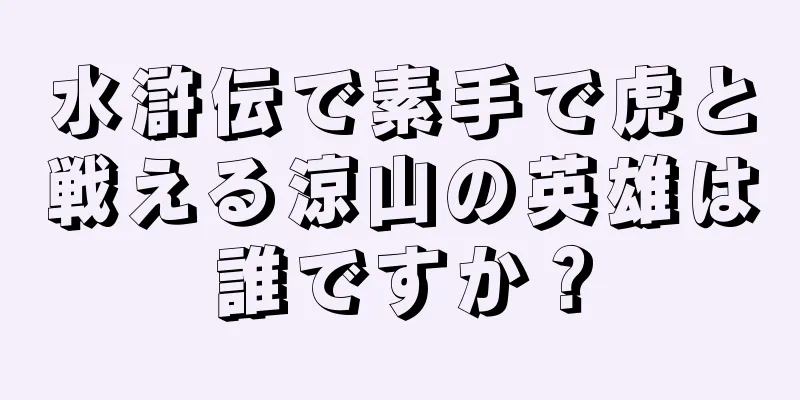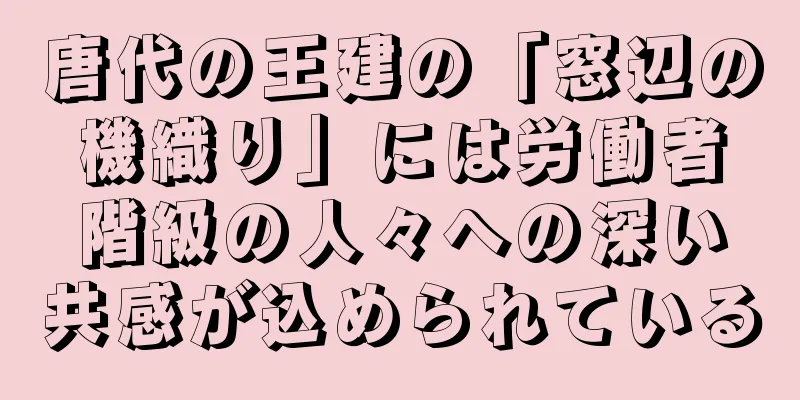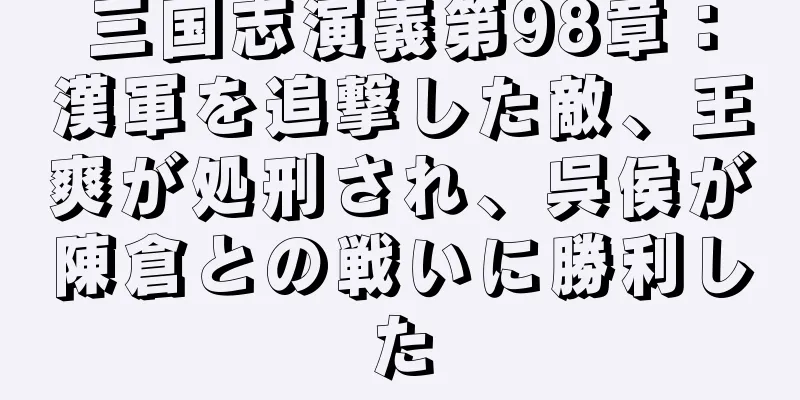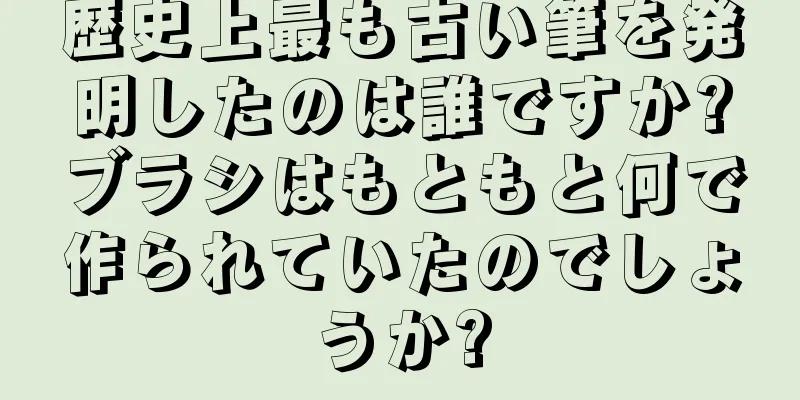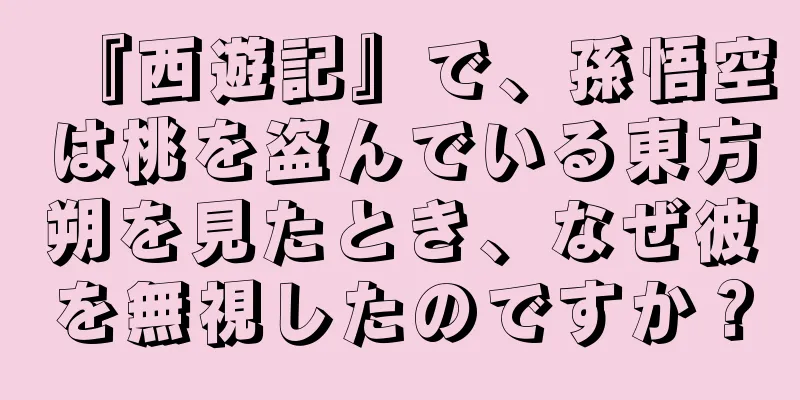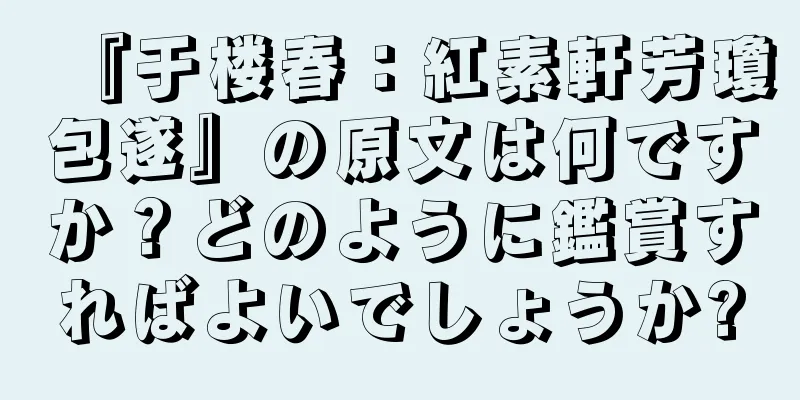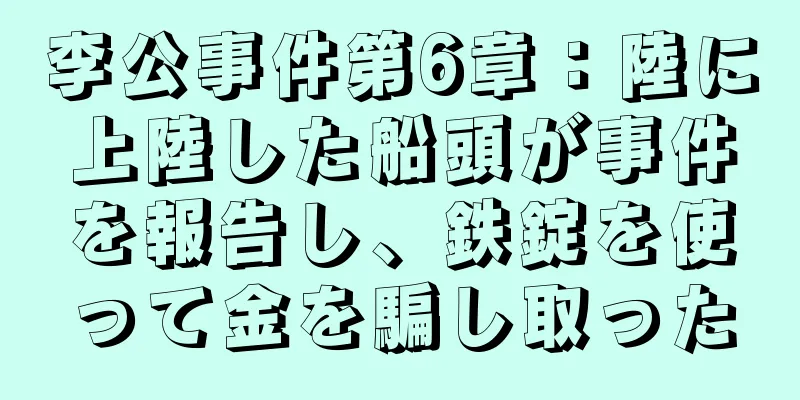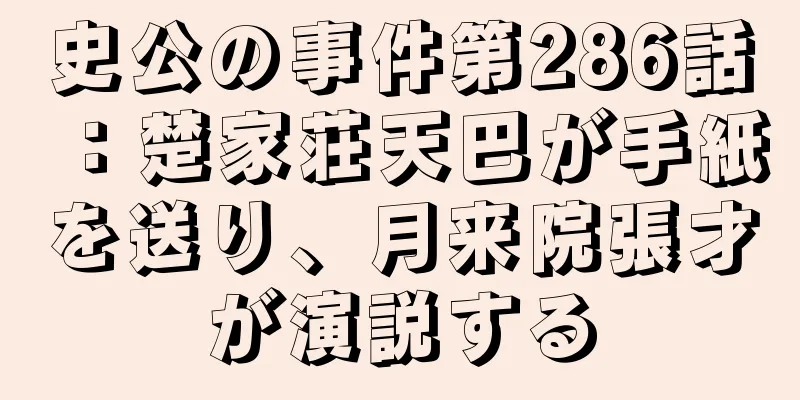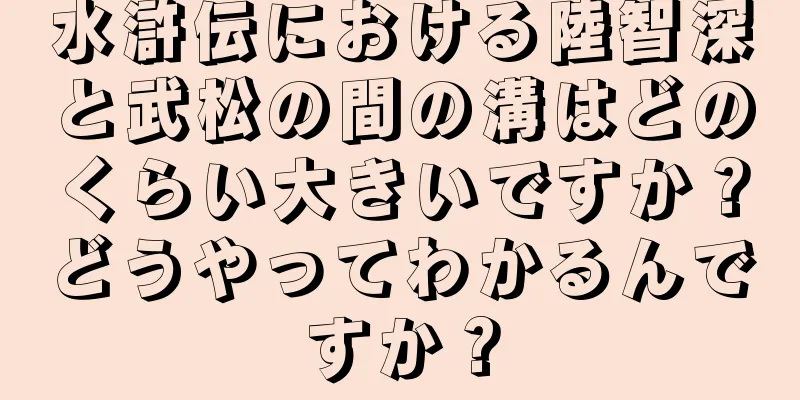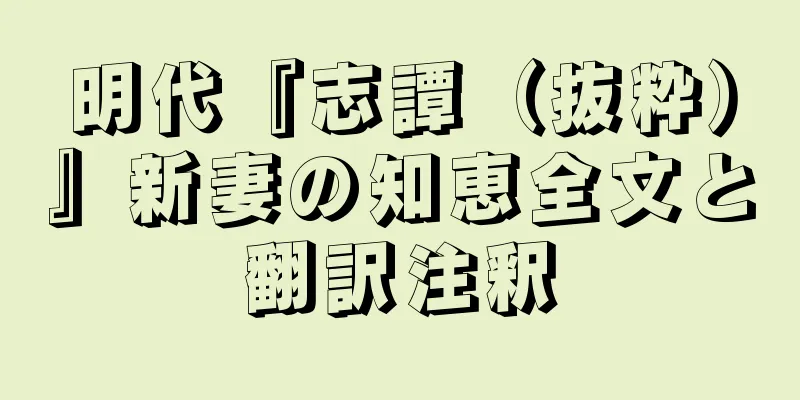古典文学の傑作『太平天国』:周君部第七巻全文
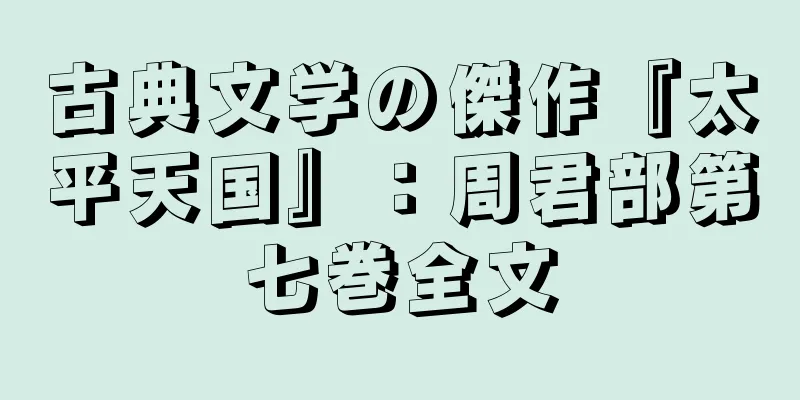
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が周君布第7巻の詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! ○ 河北路沿い 淮州 『元河県地図』には、淮州、河内県と記されている。 「禹の朝貢」は、潭淮の地である冀州の地域を指します。周は首都圏と魏・韓・雍の三国から構成されていました。春秋時代には晋の領地であった。七国時代には漢と魏の支配下にあった。秦は天下を統一し、魏を滅ぼし、三川県を建てた。 『禹貢』には「譚淮は偉大な功績を残し、衡と張にまで及んだ」とある。 『後漢書』にはこう記されている。光武帝は河内を征服したが、守備が難しいと感じたので、鄧愈に尋ねた。「将軍のうち、誰を河内守備に派遣すればよいか?」 愈は答えた。「昔、高祖は蕭何に関中に任じられたので、西のことは心配する必要がなかった。今、河内は川によってしっかりと守られ、人口も多く、北は上当、南は洛陽とつながっている。敵の荀は民軍ともに装備が整っており、彼を倒すには彼を倒すしかない。」そこで、彼は荀を河内の知事に任命した。荀は従属する各県に手紙を送り、兵士と弓術の訓練を指示し、占園で竹を切って矢を作り、馬を飼育して小作料を徴収して軍隊に供給した。 『左伝』は言う:周と鄭の人々 蘇芬生の田:周、興、回、淮。 (周、現在のハノイ県) また、襄王は晋の文公に楊凡、文、袁、瞻茂の地を与えたとも言われている。その後、金は南陽を占領し始めた。 (金山の南、川の北に位置するため、南陽と呼ばれています。) 『元河県地図』には、河内県は『春秋実録』に登場する野王鎮であると記されている。 『左伝』は言う:晋の人々は野王で顔若を捕らえた。 『韓志』によれば、武徳県は河内に属する。始皇帝が東方を巡視した際、自らの武徳によって天下を統一したと信じたため、この名がつけられました。 『十州記』には、秀武はもともと寧夷であったと記されている。 『韓氏外伝』には、武王が周王を破り、軍を寧に駐屯させたため、秀武と改められたとある。 『韓非書』には、秦の昭王が昌平で趙を破り、西の秀武を攻撃したと書かれている。 『漢書』にはこう記されている。漢の武帝が高氏を訪ねようとしたとき、冀県の新中郷に到着し、南越の宰相陸嘉の首を捕らえ、これによって霍家県を建てた。 孟州 「土井」は河陽県孟州と記されている。 『朝貢禹記』に出てくる冀州と禹州の領土は、武王が周王を破って会議を行った場所です。周は首都内にあり、蘇芬が生まれた町でした。後にJinyiになりました。 『左伝』はこう言っています。晋の公は王を召して諸侯と会わせ、また王に狩りを命じました。鍾倩は「大臣として王を召し出すのは、適切な教訓ではない」と言った。そのため、この書には「天王は河陽で狩りをした」と書かれている。 『北斉書』には、神武は潘越を派遣して北城に守備させ、高永楽を派遣して南城を守らせ、西魏に備えさせたと記されている。東魏が築いた中渝城には、まだ河陽関が残っていたため、河陽の3つの城には侯爵がいた。 『冀州土経』には、河陽は河内県の南64マイルにあり、そこに宮殿があると記されている。 『晋書』には、潘越は比類のない才能と名声を持った男であったが、多くの人から羨望の的となり、河陽の知事に任命されたと記されている。 『左伝隠三三』は次のように語った。鄭吉祖は軍を率いて文から小麦を奪い取った。秋には、彼はまた、成州から穀物を奪った。 また、「羲の10年」には、狄が文(現在の河内文県)を滅ぼした。文の息子は魏に逃亡した。周の襄王は晋の文公に土地を与えた。 魏州 『元河県地図』には、冀県渭州と記されている。 『朝貢禹』の冀州の地域は後に殷の首都となり、朝歌は衛県の境界となった。戦国時代には魏に属していた。秦の時代には河東県に属していた。 (漢代には冀県の地であった。) 『地理志』には、河内は殷の古都であると記されている。周が殷を征服した後、その都は三つの国に分割された。『詩経』に記されている北、雍、衛がこの三つの国である。北は周王の息子である武庚を封じ込めるために使われ、雍は管叔によって統治され、衛は蔡叔によって統治され、彼らは殷の人々を監督するために使われ、三監と呼ばれました。 『史記』には、周丹が成王の命を受けて軍を起こし、武庚と呂布を殺し、関叔を殺し、蔡叔を追放し、康叔を殷の残党とともに魏の君主として封建し、黄河と斉河の間にある商の旧跡に定住したと記されている。 『韓志』によれば、朝歌は河内に属し、周王の都であった。周の武王の弟である康叔に与えられ、衛と改名された。王莽はこれを雅歌と呼んだ。 「劉子」は言った。「その町は超閣と呼ばれ、墨子は馬車を方向転換した。」 『後漢書』には、于胥が超閣の知事であったと記されている。盗賊が多く、問題は何年も続いていた。多くの親族や友人が哀悼の意を表して言った。「超閣はどうしてこんなにひどいのか」。徐は笑って言った。「私は困難なことを避けず、容易なことに従う。これが大臣の忠誠だ」。徐は河内知事の馬霊を訪ねた。霊は言った。「あなたは儒学者なのに超閣にいるのか。私はあなたをとても心配している」。徐は言った。「盗賊はただ犬や羊が集まって食べ物や暖かさを求めているだけだ。澳倉からわずか百里しか離れていないが、どうやってそれを食べ物にすればよいのか分からない。清や冀州の人々は盗み方を知らず、封鎖された場所を守るために彼らを徴兵する。これは世界の右腕を切り落とすようなものだ。今はそうではない。これは無駄な計画だ」。徐は彼ら全員をなだめた。 『春秋後記』にはこう記されている。「太康五年、呉の侵略はようやく平定された。私は江陵から襄陽に戻り、武装を解除して休息した。そして、かつての志を改めて、『春秋』釈と『経論集』を編纂した。」当初、冀州冀県の人々が領土内の古墳を発掘し、古書を発見したが、それらはすべて簡略化され、官文にまとめられていた。発掘者たちはそれらにあまり注意を払わなかったため、書物はあちこちに散らばっていた。科挙の本は長い間放置されていたため、最後まで読むことができませんでした。原本は秘密の書庫に隠されており、後になって見ることができました。 劉承之の『山水今昔記』には、「溧陽は古代の黎王国である」と記されている。 『詩経』には「魏に李侯が住まう」とある。これは真実である。 香州 『元河県地図』には、香州、イェ県と記されている。 『朝貢禹記』の冀州の地域。春秋時代、この地は晋の所有であった。戦国時代、魏に属し、魏文厚は西門豹を派遣して鄴を守らせた。秦が天下を統一すると、邯鄲県と上当県の領土となった。漢の皇帝高祖は衛県を分割し、鄴に都を置いた。 『文経』にはこう記されている。「何丹嘉は宰相であった。」 『後魏書』には、道武が鄴を訪れ、州の名前を尋ねたと記されている。尚書崔光は答えた。「昔、賀丹賈が宰相であったので、湘州と呼ぶべきだ。」道武は同意した。 『韓志』によれば、衛県は、鄴、官濤、赤丘など18の県を管轄していた。 『後魏書』にはこうある。文帝の太和18年、遷都を決意し、鄴を通り過ぎ、青銅雀楼に登った。検閲官の崔光らは言った。「鄴城は平野が千里あり、四方に水運があり、西門使と古い痕跡があり、富める。徳を頼りにすれば危険を冒すよりもましだ。ここを都にしてください。」文帝は言った。「あなたは一つのことを知っていて、他のことを知らない。鄴城は長く続く場所ではない。過去に石虎が滅ぼし、将来慕容が滅ぼした。富んでいても贅沢をする国は、成功も早く、失敗も早い。さらに西には王仁山、東には連仁県、北には百仁城がある。君子は名を嫌って盗んだ泉を飲まない。」そこで彼は立ち止まった。 『魏書』にはこう記されている。黄武二年、魏県の東部を陽平県と名付け、西部を広平県と名付けた。広平、陽平、衛平の3つの県は三衛と呼ばれています。 『土京』には、安陽は周王の首都であり、斉江と桓江の間に位置し、殷虚北中と呼ばれていたと記されている。 『戦国の兵法』には、周王が百万の兵を集め、左の斉河から水を飲んで川を干上がらせ、右の桓河から水を飲んで川の流れを止めたとある。 『晋伝』には、石勒とその将軍たちが鄴を首都にしようと計画し、三台を攻撃しようとしていたと書かれている。張斌は「三台は危険で堅固だ。最後まで占領するのは不可能だ」と言った。そこで彼らは湘国に進軍した。 『韓志』によれば、内皇は渭県に属する。 『春秋実録』には「呉王と晋侯が黄池で会見した」と記されている。現在、黄沢は西にあり、陳留は外黄を持っているため、「内」という言葉が付け加えられた。 明州 『十省記』には、羅州広平県と記されている。 『朝貢禹記』では冀州地方に属する。春秋時代には赤棍族の領土であり、後に晋の領土となった。 『左伝』には「晋の荀林甫が曲梁で赤帝を破った」とある。七国時代には趙に属していました。秦は天下を統一し、邯鄲県とした。漢代初期に広平国が建国された。 『禹貢』には「譚淮は偉大な功績を残し、衡と張にまで及んだ」とある。 (横章は肥郷県にあります。) 『左伝』によれば、恵公、善清公、その他の諸侯は冀澤で同盟を結んだ。杜のメモにはこう書かれている。「ジゼは広平郡曲梁県にある。」 「韓直」:広平州は16の県を管轄していた。武帝の正和2年に平安国と改められ、宣帝が元の状態に戻した。王莽はそれを府昌と呼んだ。 『十州記』には、洛水県はもともと漢代の張県であったと記されている。 「韓志」曰く:この国は塩辛いので、池張という。 衢州は広平国に属していたとも言われている。芒は周志と名付けた。 『土井』によると、邯鄲の「ダン」は終わりを意味し、「ハン」は山の名前で、邯鄲山の終わりを意味します。 興州 『十州記』には、邢州莒鹿県とある。 『朝貢禹記』の冀州の地域。秦が天下を統一したとき、莒鹿県に属する新都県をここに設置した。 「左伝」はこう言った。「江、興、毛は周公の子孫である。」 また、『成15年』には、楚の官吏神公が晋に逃亡し、晋は彼を邢の官吏に任命した。 (東陽は金の山東省であり、潭州の広平も同様である。) 『県国記』には、次のように記されている。「興州尚書坊の東に平地があり、周囲は百段余りある。人馬がそこを歩くとゴロゴロと音がする。掘ると火が出る。」 『十三州記』には、唐・禹の時代には莞鹿は大洛の地であったと記されている。 『文経』には「堯は数百人の大臣を使って舜を試し、彼らを大山麓に来るように命じた」とある。山麓とは最も大きな森林のことである。堯が舜に王位を譲ったとき、彼はそれを全世界に見せたかったので、大臣と庶民を全員集めて大路の荒野に連れて行き、そして舜に王位を与えて、自分が王位を譲ったことを明らかにしたかったのです。 『張寅伝』にはこう記されている。高祖が平城から帰るとき、趙を通った。趙王は自ら彼に食事を与え、態度は非常に謙虚であった。高祖皇帝は足を組んで座っていた。趙相官高らは毗仁と百仁の出身で、それを望んでいる。皇帝は泊まろうと思ったが、心が動かされたので、「その郡の名前は何ですか?」と尋ねた。「白仁」と答えられた。皇帝は、「白仁とは、他人に強制されるという意味だ!」と言って、泊まらずに去っていった。 (百人、現在の姚山県) 冀州 『十省記』には冀州新都県とある。 『元河県図』には、春秋時代には晋の領地であったと記されている。七国時代には趙に属していました。秦の時代には莒鹿県に属していた。 李公胥の『趙記』には、趙の孝成王が趙の都として祭壇と壇の宮殿を建て、諸侯の宮廷を開いたため、新都と呼ばれたとある。 『史記』には、秦の時代に張二を説得したロビイストがいたと記されている。「二人の王は亡命生活に閉じ込められており、独立するのは難しい。趙王妃を立て、義をもって支えれば、成功するだろう」。そこで張二は趙謝を探し出し、趙王として新都に住まわせた。 『漢書』には、項羽が趙を分割し、張耳を常山王に任命して新都に住まわせ、その地を項国と改名したと記されている。 『晋書』には、張斌が石勒を説得して「湘国は山岳地帯に位置し、戦略上の優位性がある。地理的に見てもよい国であり、首都にできる」と言ったとある。そこで石勒はそこに首都を置いた。 『晋書』にはこうある。「古は左に、月は右に、言葉を発せよ、あるいは口に入れ」。「古は左に、月は右に」という言葉は胡である。 「Rang Qu Yan」は「翔」という言葉です。 「または入口」は国を意味します。すぐにそれは石勒の首都になりました。 『後漢書』には、王朗が王位を簒奪し、河北の民衆が皆これに呼応したと記されている。光武は冀から南下して下博に着いたが、どこへ行けばよいのか分からず困惑していた。一人の白髪の老人が道端に立っていて、指さしながら言った。「頑張れ! 信都は長安の守護者になるだろう。」光武はすぐに信都に駆けつけ、太守の任光は門を開けて出迎えた。 「魏志」は言った。「韓魏は冀州の太守であり、公孫瓚は彼を攻撃しようとしていた。」袁紹は高幹を派遣して傅に冀州を邵に明け渡すよう説得させた。傅は生まれつき臆病だったので、その計画に従った。傅の宰相耿武は彼に助言した。「冀州は遠く離れているが、百万の兵と十年分の穀物がある。袁紹は一人ぼっちで軍隊も貧弱で、手のひらにのった赤ん坊のようだ。乳を絶てば、すぐに餓死してしまう。なぜ彼に国を譲るのか?」傅は言うことを聞かず、邵に国を譲った。 陸志の『冀州風俗記』には、「冀州は聖賢の泉であり、皇帝の古地である」と書かれている。 『十三県記』には「冀州の地は古都である」とある。人々は激しさを恐れるので、「官吏が倭人に偶然出会うことはまずない」ということわざがあります。 『後漢書』には、王朗が反乱を起こしたとき、光武帝は冀から南に急ぎ、南宮に着くと、激しい嵐に遭遇した。光武帝は馬車を道端の空き家に突っ込んだ。馮儀は薪を運び、鄧愈は火を焚き、光武帝はかまどに向かって衣服を燃やしたと記されている。ウサギの肩肉入り麦ご飯も添えました。 『魏志』は言う。太祖は鄴を捕らえて冀州の太守となった。ある者は太祖に「古の制度を復活させて九州を置き、冀州が広い地域を支配し、天下を平定する」よう進言した。太祖は同意したが、荀攸は「そうすれば、冀州は河東、豊義、扶豊、西河、游、兵を手に入れ、それは多い。冀州が今分裂すれば、皆が誘惑されるだろう。ひとたび変化が起これば、天下を平定するのは困難になる」と言った。公は同意した。 趙州 『元河県地図』には趙州、趙県と記されている。 『朝貢禹記』の冀州の地域。春秋時代には晋の領地であった。戦国時代には趙に属していた。秦では邯鄲県でした。漢代には平済県、常山県、趙国の領地であった。漢魏の時代以来、封建社会の子孫。 『趙記』はこう言っています。「女性たちは美しく飾られ、音楽や弦楽器を演奏し、長袖を着ており、すべての王子の中で最も魅力的です。」 『左伝』によれば、斉の士と斉の軍、魏の孔郁と項羽は晋を攻撃し、冀普を占領した。 (現在は平吉県となっている。) 『史記』には、蘇秦が趙に言った、「現在、山東には趙より強い国はない。趙の面積は2000里で、西は常山、南は漳河、東は清河、北は燕と岱に囲まれている。」とある。 『韓志』によれば、元氏は常山県に属している。王莽はそれを景官亭と呼んだ。ここは趙の袁王の領地であったため、袁市と呼ばれました。 『後漢書』には、光武帝が北上して彭冲を攻めたとき、尹皇后は彼に従い、元始川社で明帝を産んだと記されている。章帝は元氏を訪れ、郡邸で光武帝と献宗帝に祭祀を捧げ、また世聖殿で献宗帝に祭祀を捧げた。音楽を奏し、新しい詩を詠み、元氏の祖先を蘇らせた。 『十路記』には高邑県は昭芳子鎮とあり、『竹書』には「鲂子」とある。漢代には郝県と呼ばれた。後漢の時代には再び高邑に改められた。 『後漢書』にはこう記されている。光武帝が趙に到着すると、臣下たちが即位を求めたので、趙の南にある千丘高亭武成墨に祭壇を築いた。 (現在の趙州市白郷県) 鎮州 『十省記』には「鄭州、常山県」とある。 『元河県地図』には「『毓公』の冀州の領土」とある。周は汪州の地であった。春秋時代は玄羽国であった。戦国時代には趙に属していた。秦は天下を統一し、莒鹿県を建てた。 『十三県志』には、鎮定はもともと東源と名付けられていたが、河東に源があったため「東」の字が付け加えられたとある。 『漢書』にはこう記されている。「高祖の時代に、戴の宰相陳熙が反乱を起こし、趙離を派遣して東源を守らせた。皇帝は自らこの都市を攻撃したが、失敗した。兵士たちは皇帝を呪い、皇帝は激怒してすぐにさらに多くの軍隊を派遣し、都市を攻撃した。皇帝は呪いをかけた者の首をはね、この都市を鎮城と改名した。 「韓志」曰く:景星は常山県に属する。 『穆皇行記』には、皇帝が旗山に狩りに出かけたと記されている。注:燕と趙はこの山の尾根を「鉶」と呼んでいましたが、これは今日の景星にあたります。 『史記』には、秦の始皇帝の治世18年に、始皇帝は趙を攻撃し、景興を占領したと記されている。 『元河県地図』には、霊寿県はもともと中山国の首都であったと記されている。 『十三州志』には、中山武公は周の武公と同じ姓を名乗ったとある。その後、桓公は国政に関心がなかった。晋の史官である禹が周の王に会ったとき、周の王は「どの君主が先に滅びるか」と尋ねた。周は「中山の風習では昼を夜とみなす。私の観察では、中山が先に滅びるだろう」と答えた。後に、魏の楽陽が文侯の将軍となり、中山を占領して霊首の称号を与えた。 『戦国の兵法』には、九門県にはもともと9つの家があったが、趙の武霊王が九門県に改めたとある。 『史記』にはこう記されている。趙の恵王38年、林相如は9つの門を持つ大きな城を建設した。 丁州 『十省記』には定州伯陵県とある。 『朝貢禹記』の冀州の地域。豫順の十二国は荊州の地域を覆っていた。春秋時代の仙羽・白帝の国は、後に中山国に改称されました。 張瑶の『中山記』にはこうある。「この県は中山が治めており、城内に山があるために中山と呼ばれる。」郡庁所在地は中仁城にあるとも言われている。 『韓志』によれば、廬奴県は中山国に属していた。呂河はここから流れ出ています。 『絵本』にはこう記されている。「安渓県は古代の呂奴県である。」ここには、深くて流れのない黒い水の古い池があります。人々は、黒い水を「呂」、流れない水を「涸」と呼んでいます。 『漢外親伝』には、宣帝の母である王夫人が、宣帝が幼かったころ、流宿城で涙を流しながら父に別れを告げたと記されている。 (豊義県にて) 『世道志』には、唐県はもともと春秋時代の仙邑鎮であり、漢代には唐県の所在地であったと記されている。 『韓志』によれば、唐県は中山国に属していた。王莽は結婚を和解させるよう言った。だからそれはヤオの国だったのです。堯が唐の侯爵であったとき、ここに都を置いた。姚山は唐の王都の北東に位置しています。孟康は言った。「晋の荀武は仙羽を攻めて中仁に入りました。中仁閣は今ここにあります。」 英邵の『風俗経』には、中仁城の北40マイルに左仁亭があり、そこは仙嶼の古鎮である、と記されている。 (左仁亭は唐県です。) 『漢書』には、王都は中山国に属していたと記されている。マン氏は、調整はスムーズだったと語った。北には姚山、南には姚山の母山である清都山があります。姚山に登ると、都山が見えることからこの名前がつきました。 「土井」曰く、興義県はもともと七国時代の中山国の倶興県であった。 『史記』には次のように記されている。李克は中山の宰相であった。顧興の役人は、収入が以前よりはるかに高くなったと報告した。克は言った。「顧興の上には肥沃な山や森林はなく、下に牛や馬が休む沼や湿地もありません。収入が以前よりはるかに高くなり、国民を困らせるでしょう。」そこで彼は役人を解任した。 『十州志』には、古城県は春秋時代には古子の町であり、漢代には下曲陽の地であったと記されている。 「左伝」は言う:晋の荀武は鼓を囲み、鼓手元帝を連れて戻った。 (ジュル族の夏曲陽には太鼓奏者がいる。) 『十三県記』には、中山に尚曲陽があるので、下の耳を加えたとある。 『土京』によれば、北平県はもともと秦の秦蕪県の領地であり、中山国に属していた。 『漢書』には、高祖が北伐から帰ったとき、群邑を通り過ぎ、城壁を登った。彼は巨大な家々を見て、「なんと素晴らしい城だ。私は世界中を旅したが、洛陽とこの城しか見たことがない」と言ったと記されている。そこで、陳平を群邑侯に任命した。 『後漢書』には、張帝が北上して北越を訪れた際、群邑という名前がよくないと思ったので、溥陰と改めたと記されている。 瀛州 『十省記』には、瀛州は河間県であると記されている。 『朝貢禹記』の冀州の地域。舜の十二州は汀州の一部であった。春秋時代には燕と趙の国に属していました。秦が天下を統一すると、ここは河間県となった。漢は河間国であった。 『県州記録』には、瀛州は海に面しており産物が豊富であることから名付けられたと記されている。英海にちなんで名付けられたとも言われています。 『韓志』によれば、河間国は楽城、后井、烏水、公高の4つの県を統治していた。王莽はそれを朔定と名付けた。英邵は言った。「二つの川の間に。」 『漢書』にはこう記されている。武帝の治世に、占い師が「西北に非常に高貴な女性がいる」と言った。そこで、彼らは彼女を探すために河間に行き、狄嬪夫人を見つけた。 『十州記』には、博業県はもともと漢代の立霧県の領地であったと記されている。 『十三州志』には、太初元年、立武侯之が孝之帝の後を継いで孝桓帝となったと記されている。父の立武后羿は死後、孝宗皇帝として尊崇され、その陵墓は伯陵と名付けられたため、県名は伯鄴県に改められた。 『韓志』によれば、高陽県は卓県に属する。王莽はそれを高亭と名付けた。高河の南側に位置するため、高陽と呼ばれています。 『韓志』によれば、東平書は渤海県に属する。代県に平樹があるため、ここに「洞」という文字が追加されました。 (平樹県) |
推薦する
定公10年の儒教古典『春秋古梁伝』の原文は何ですか?
定公10年の儒教経典『春秋古梁伝』の原文は何ですか? これは多くの読者が特に知りたい質問です。次の興...
『後漢書』第89巻の原文は何ですか?
南匈奴の西洛世主帝禅于弼は、胡漢野禅于の孫であり、五主六如帝禅于の息子であった。胡漢野の後、彼の息子...
『紅楼夢』で王希峰が鉄観寺に棺を送りに行ったとき何が起こったのですか?
王禧峰は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人です。今日は、Interesti...
陶淵明の詩『山海経を読む』に描かれている 2 つの神話物語はどれですか。
みなさんこんにちは。陶淵明の言葉といえば、みなさんも聞いたことがあると思います。景微は小さな木片を口...
トゥチャ族の習慣と風習 トゥチャ族の口で「zi」という言葉はどういう意味ですか?
トゥチャ族の農民がよく使う「子」の中には、書き言葉に変換できないものもあり、その真の意味は表現できな...
『紅楼夢』の賈歓は、父と母に愛されていない哀れな奴である。
周知のように、『紅楼夢』の賈歓は賈正の三男で、趙叔母の私生児である。彼も名人であるが、父と母に愛され...
ブーラン族はどのような手工芸品を持っていますか?
プーラン族の手工芸のレベルは高くありませんが、竹編み、織物、布染め、茶作りなどには強い民族的風味が漂...
儒教の古典『古梁伝』の熙公三年の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
王勉の最も古典的な梅の花の詩は世界を驚かせた
王勉の最も古典的な梅花詩は世界を驚かせました。興味のある読者と『Interesting Histor...
ビアン:古代神話の「龍の九子」の一人。虎のような姿をしており、訴訟好き。
ビアン(bì àn)は、古代中国の神話や伝説に登場する架空の獣です。虎に似ており、訴訟が好きですが、...
「日の出と日の入り」が作られた背景は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
日の出と日の入り(匿名)(漢代)あなたは自分の人生に満足していますか? 時代は時代によって異なります...
秦の始皇帝陵のさらなる発掘を中止した理由は何だったのでしょうか?
秦の始皇帝陵が発見され、紫禁城の80倍の大きさであることが証明されました。なぜ専門家は発掘をためらう...
『西遊記』の王はなぜ王妃を「子桐」と呼んだのでしょうか?この名前はどうやって生まれたのですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が「紫桐」の起源についての記事をお届けします。...
王維は友人への心からの友情を表現するために、「王川の裴秀才迪に贈る」と書いた。
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
李青昭は杭州に長く住んでいたのに、なぜ西湖について言及しなかったのでしょうか?
杭州の長い歴史の中で、李清昭は間違いなく重鎮の人物である。彼女の詩は、「生きているときは英雄で、死ん...