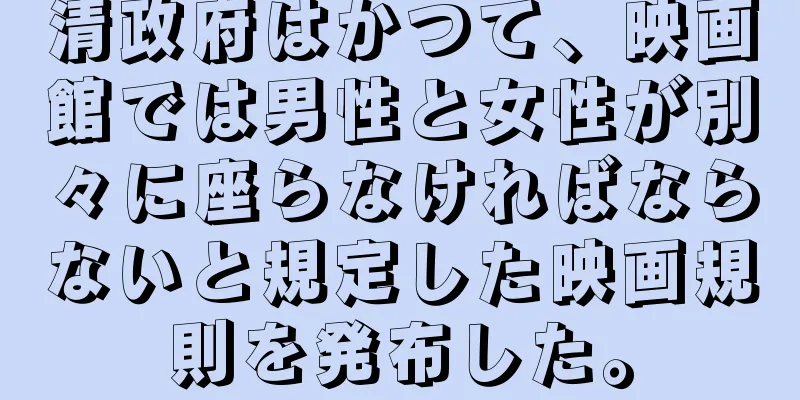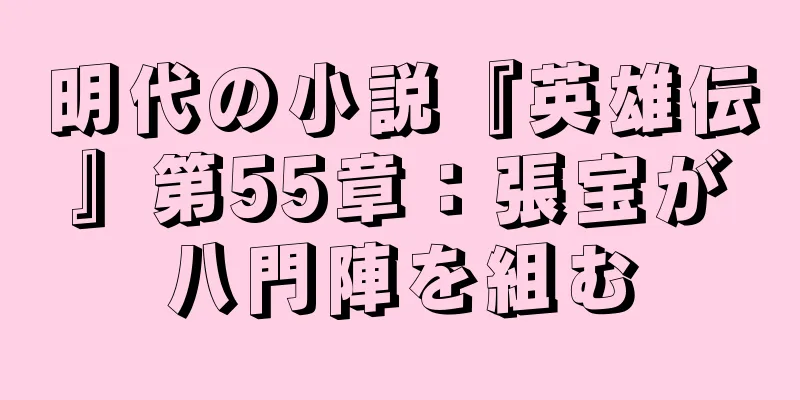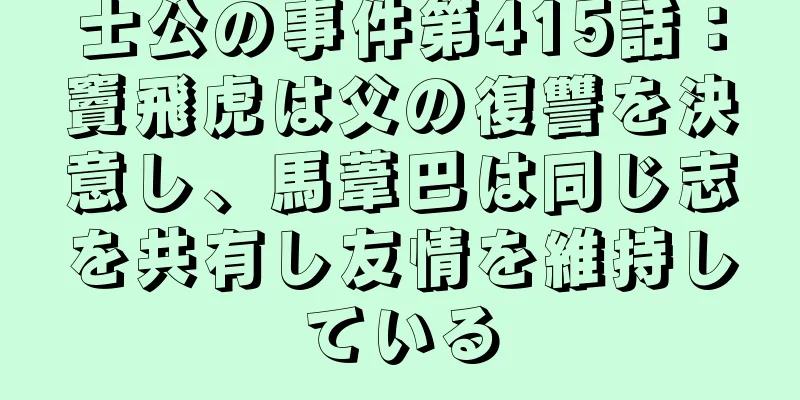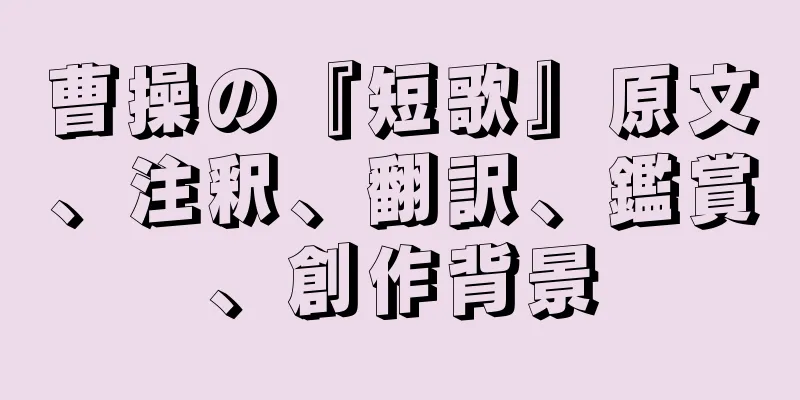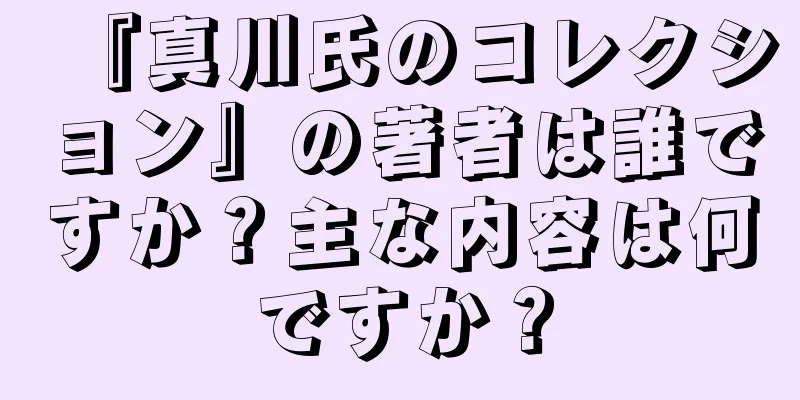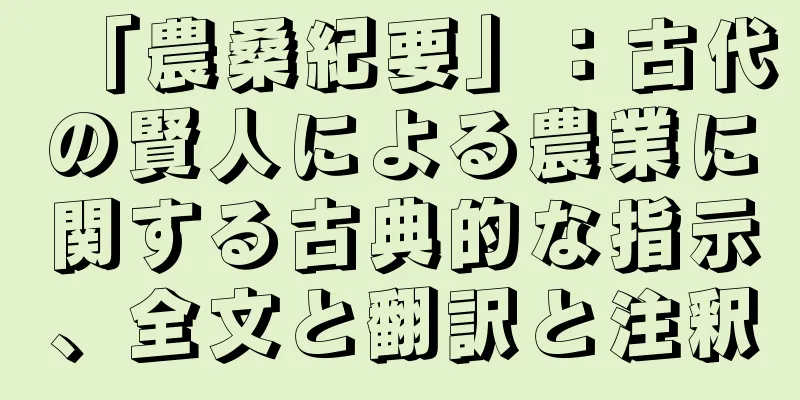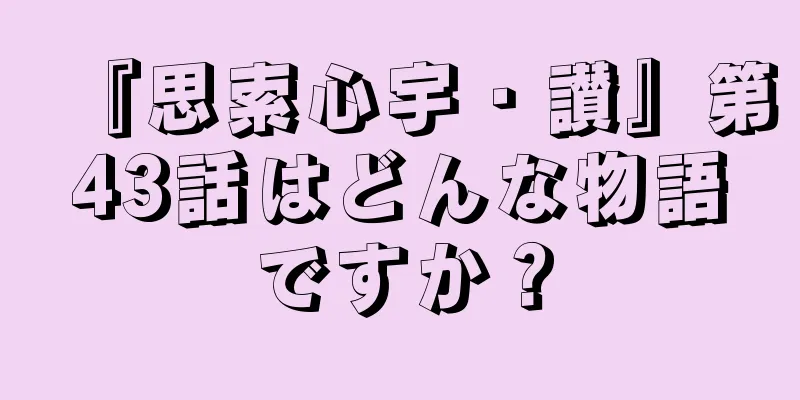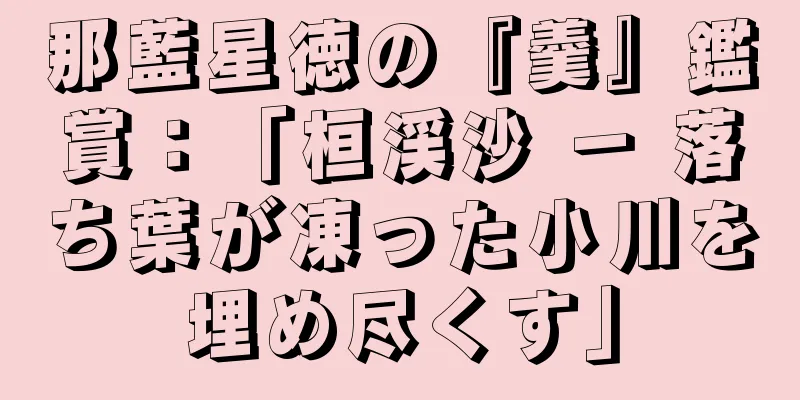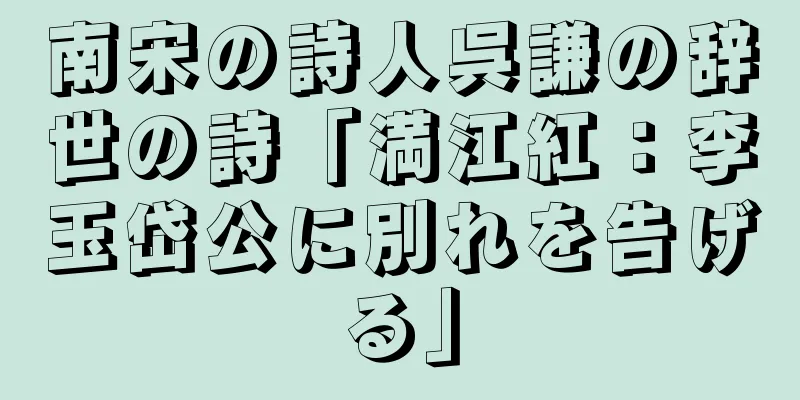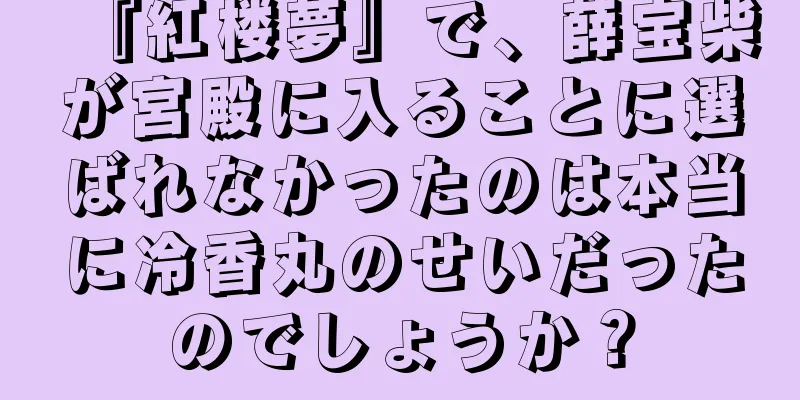「四聖心の源」第 4 巻: 疲労と怪我の説明: 便に血が混じる 全文
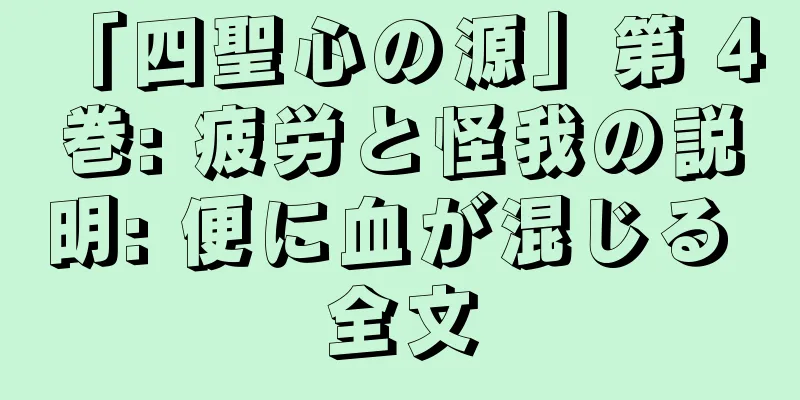
|
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています。著者は黄帝、奇伯、秦月人、張仲景を医学の四聖人とみなしている。この本は『黄帝内経』『難経』『熱病論』『金堂要』の意味を解説しています。第2巻は天と人について、第26巻は気について、第3巻は脈法について、第4巻は疲労による損傷について、第5巻から第7巻は雑病について、第8巻は七穴について、第9巻は傷と潰瘍について、第10巻は婦人科について説明しています。伝統的な中国医学の基礎理論と臨床医学の一部を収録した総合的な著作です。次に、興味深い歴史編集者が、第 4 巻「疲労と損傷の解説: 便に血が混じる」について詳しく紹介します。見てみましょう。 血は脾臓で作られ、肝臓に蓄えられます。肝臓と脾臓の陽気が強いと、血液は温かく上昇するため、漏れ出ません。水が冷たく、土が湿っていて、脾臓が沈み、木が沈んでいるとき、風が動いて風を散らす命令を出し、便が出なくなります。 陽気が抑制されると、土は暖かくなり、水は暖かくなります。脾臓が湿り、腎臓が冷えている場合は、庚金の抑制命令は機能しません。後世の人々は、腸風は清熱と湿潤の方法で治療すべきであると信じていましたが、それは脾陽の虚弱をますます悪化させ、終わりが見えない原因になるだけでした。 肝陽と脾陽が不足し、紫色、黒色、鬱血、腐敗などの症状が現れます。火と乾いた土を補って残りの陽を回復させ、血液と肝を温め、憂鬱な状態を解消します。痔、瘻孔、直腸脱を治療したい場合にも、この方法を使用できます。 桂枝黄土煎じ 甘草2銭、白朮3銭、トリカブト3銭、ロバ皮ゼラチン3銭、地黄3銭、黄耆2銭、桂枝2銭、黄土3銭をストーブに入れて、水を半カップ沸騰させ、温かいうちに飲む。 血便の症状は、水や土の冷えや湿気、木の滞りや風の動きによっても起こります。中景黄土煎じ液は、枸杞子、川芎、トリカブトを配合し、土を養い、寒さを和らげます。一方、芍薬、地黄、黄耆を配合し、風を清め、火を鎮めます。黄土は水分を乾かし、脾臓を養うので、これに勝る方法はありません。ここで、シナモンの小枝を追加すると、木材の停滞を緩和することができ、これも非常に正確です。 |
<<: 四聖心の資料:第4巻:負傷と疲労の説明:血を吐くことの全文
推薦する
なぜ洪秀全は李秀成の救命計画を拒否したのか?主な理由は何ですか?
李秀成といえば、私たちは彼のことをよく知っているはずです。彼は太平天国運動の重要な将軍でした。太平天...
冬の初めに最も健康を保つ食べ物は何ですか?ピーチカーネルとリリーオートミールの機能は何ですか?
立冬には何を食べたらよいでしょうか。立冬の到来は、本格的な冬の到来を意味します。立冬から冬至までは、...
ウズベキスタンの北と南の住居の違いは何ですか?
新疆南部のウズベク人は一般的に、平らな屋根と緩やかな傾斜のある長方形の土造りの家に住んでおり、それぞ...
古典文学の傑作『論衡』:第5巻:甘粛篇全文
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
長寧公主の伝記 唐の懿宗皇帝の娘、長寧公主
唐代の王女である長寧公主(?-?)は、中国の唐代の第17代皇帝である唐の懿宗皇帝李玉の娘の一人でした...
戦略家郭嘉の何がそんなに素晴らしいのでしょうか?弱点はどこでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
水滸伝の楊林の結末は何ですか?金宝子楊林の簡単な紹介
水滸伝の楊林の結末は? 金豹楊林の紹介古典小説「水滸伝」の登場人物で、金豹の異名を持つ。楊林はずっと...
隋の文帝が開皇律令を完成した後、彼の立法上の功績は主にどのような点に反映されましたか?
開皇律の題名と基本的な内容は北斉律に基づいており、「後斉の制度を多く取り入れた」と言われています。そ...
ブイ族の民俗習慣の特徴は何ですか?
ブイ文化は特殊な生活環境の中で形成され、発展したため、ブイ族の自然崇拝や神崇拝の多くがブイ文化に...
宋代の李宋が残した「幽霊」画「骸幻戯」は何を表現したかったのか?
宋代の李宋が残した「鬼」画「骸骨幻想戯」は何を表現したかったのか?興味深い歴史の編集者が詳細な関連コ...
古梁邁が書いた『春秋実録』古梁伝には、定公元年に何が記されているか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
辛其基は職を解かれ隠遁生活を送り、野望が果たせなかったため、『冬蓮花』を著した。
辛其基(1140年5月28日 - 1207年10月3日)、元の字は譚復、後に幽安と改め、中年になって...
「皇居を想う春の日の旅」を鑑賞するだけで、詩人魏荘の深い感情が伝わってくる。
魏荘(紀元836年頃 - 910年)、雅号は端済。荊昭府都陵県(現在の陝西省西安市)の出身で、唐代末...
「世界覚醒の物語」第34章
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
清代の五字詩「湘東阮局から魯西まで」を鑑賞します。詩の作者はどのような場面を描写していますか?
清代の湘東邨から陸渓、車神星まで、以下の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!古...