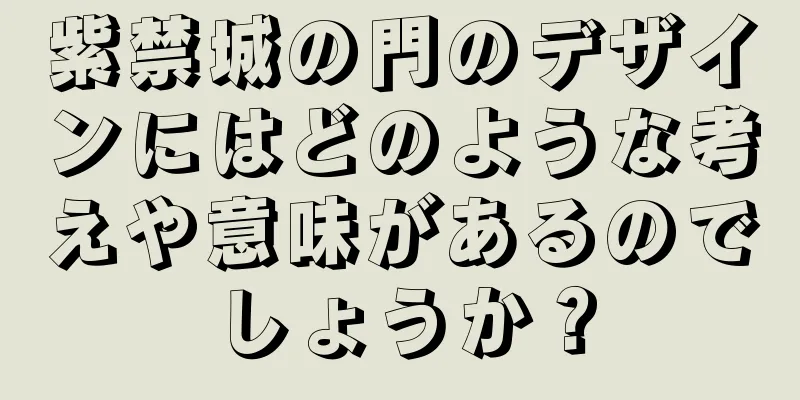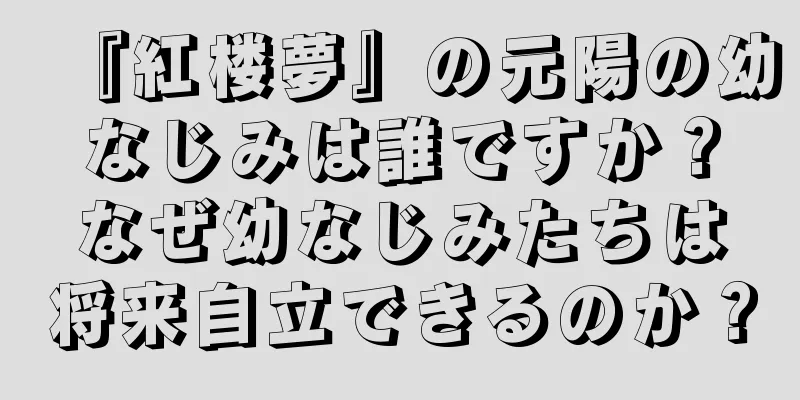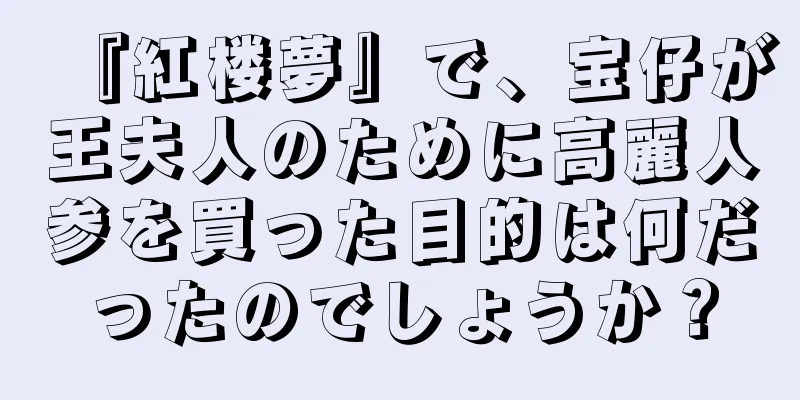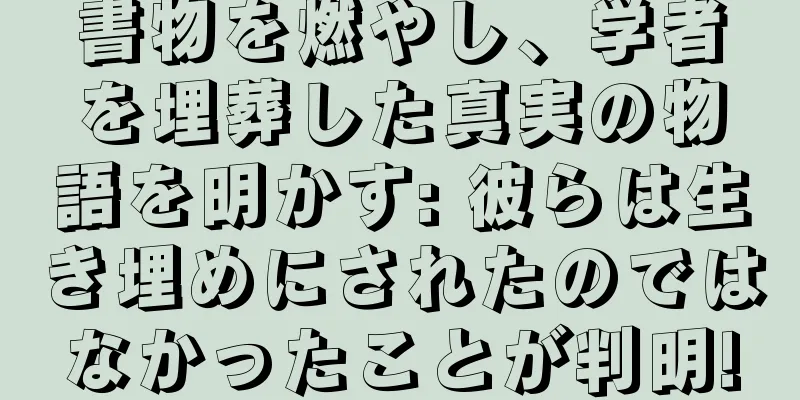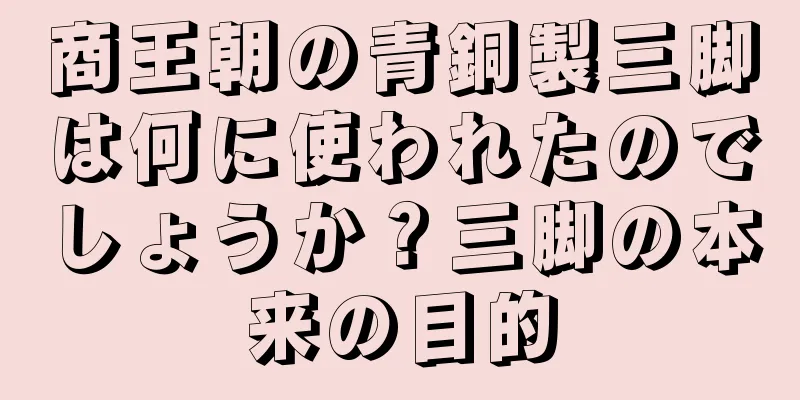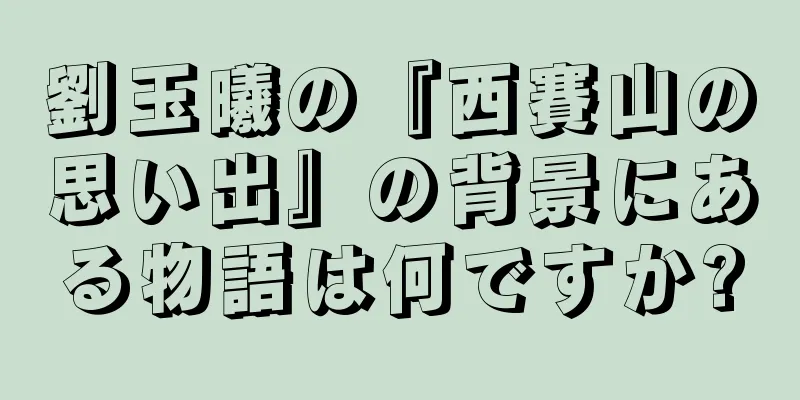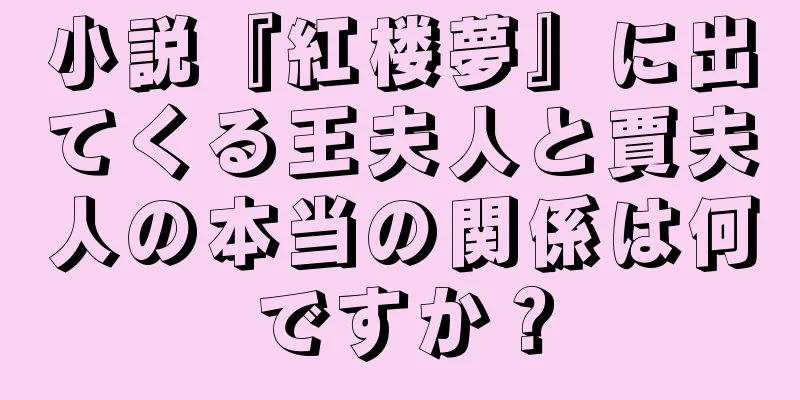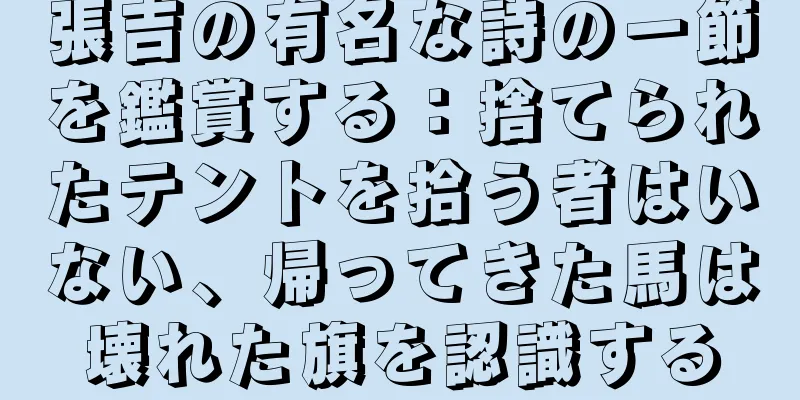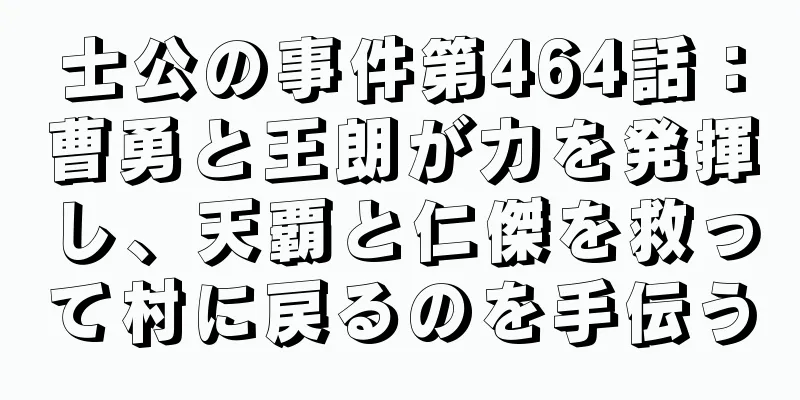飛竜伝説第23章:匡音は叔母の杜公を喜ばせるために桃を味わい、莫谷で甥と出会う
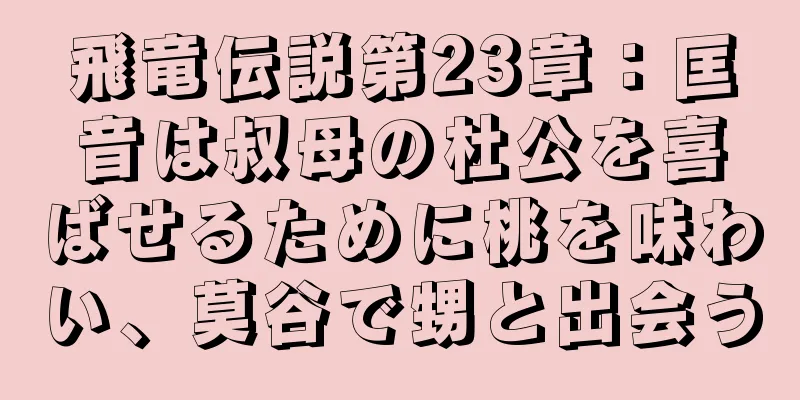
|
本日は、Interesting Historyの編集者が『飛竜全伝』第23章の全文をお届けします。これは清代の呉玄が『飛竜伝』の旧版を基にして加筆・翻案した、全60章からなる長編英雄伝小説である。飛龍:皇帝のことで、空を飛ぶ龍のように高い地位を占め、世界を支配しているという意味です。この本は主に趙匡胤が暴君に反抗し、世に逃れて義侠の行いをし、善人と親しくなり、最終的に宋王朝を樹立するまでの物語です。 その詩はこう述べています。 私は遠くまで旅をして禅寺に泊まり、別れを告げて古道を急ぎました。 地元の特産物を味わう価値があり、エキゾチックな珍味も食べることができます。 その荘厳なオーラは時代を超えて残り、その英雄的な精神は何千年も輝き続けるでしょう。 党内の年長者や親族は誰であっても、常に鋭く、決して謙虚ではありません。 柴容は元帥官邸の内廊下で、叔父や娘、近親者らと楽しく酒を飲んでいたと伝えられている。宴会の最中、郭維は日頃の抱負を明かした。彼は出世して覇者になりたいと思っていた。これは柴容がまさに考えていたことだった。郭維の言葉を聞いた柴容は心の中で考えた。「叔父が私を罰しようとしているのなら、この機会に彼をそそのかして、偉業を成し遂げる基盤を築いてみてはどうだろうか。それに、叔父は年老いていて跡継ぎもいない。王位はいずれ私のものになる。言葉で答えを見つけよう。」決心した後、柴容は尋ねた。 「叔母様、あなたは高貴な容貌をしており、この珍しい物をお持ちなので、甥の私が拝見したいのですが、よろしいでしょうか?」郭維はこの時すでに少し酔っていた。これを聞いて、彼は思わず髭を上げて笑った。「甥が見たいと言うのなら、私も衣を脱いでお見せしましょうか?もし雀が本当に人々を豊作に導くことができるなら、その時が私が王になる時です。必ずあなたを皇太子にし、宮殿を守らせ、偉大な基盤を継承させます。」柴容はこれを聞いて密かに喜び、すぐにテーブルを離れて礼を言った。郭維は大喜びし、召使たちに宴会の片付けを命じ、二人の女中を呼び寄せ、袈裟を緩め、内衣を脱いで両腕を露出させた。柴容は前に進み出て、よく見てみた。それは確かに自然で素晴らしい形だった。左右の玉状の腫瘍は5インチ以上離れており、まるで向かい合った二つの峰のように、つながるのを待っているようだった。彼は、「叔父さんはお世辞を言う人だ。さっきお礼を言ったら、とても喜んでくれた。今度は、おじさんを褒めて、どんな反応をするか見てみよう」と考えました。そこで、一方の手で左腕の雀を、もう一方の手で右腕の穀物をつかみ、一緒に動かし始めました。いつの間にか、彼は雀を穀物の中に押し込んでいました。柴容は大声で叫びました。「おじさん、今日はスズメが谷にやって来ました。」 読者の皆様、柴容の言葉は金言であり、天からの祝福として実現しました。この言葉は大したことではなかった。なぜなら、すでに虚空を通り過ぎた神々を驚かせていたからだ。彼らは魔法の力を発揮し、鳥の翼に息を吹きかけ、鳥を穀物に移動させた。そこで彼らはしっかりと結びついていて、離れることができなかった。これも運命であり、郭薇が繁栄する時なので、それが実現します。郭維はこれを聞いて、鳥が自分をからかっているのだと悟り、大声で言った。「甥よ、手を握れば自然に繋がるだろう。手を離せば、一緒に握れるようになるだろう?」柴容は手を離したが、鳥は木目の中で全く動かず、まるで自然が作り出したもので、動けないかのように。柴容はこれを見て、長い間呆然として、「さっきまで5インチ以上離れていたのに、どうして今は本当につながっているのだろう?」と考えていました。彼は不安になり、大声で言いました。「おばさん、こっちに来て見てください。鳥は本当につながっています。甥は嘘をついていません。」柴夫人はこれを聞くと、近づいてよく見ました。確かにつながっていて、一点の間違いもありませんでした。彼女は大声で言いました。「旦那様、甥の言ったことは本当です。信じられないなら、化粧鏡を持ってきて見てください。そうすれば真実が分かります。」そこで郭維は二人の侍女に化粧鏡を運んで真ん中に置くように命じました。彼は明るいダイヤモンド型の手鏡を持ち、それを背後の化粧鏡に向けた。前から後ろまで見てみると、二つの物体が確かにつながっていることがはっきりと分かった。彼は思わず喜びに踊り、笑いました。「素晴らしい!素晴らしい!今日、私の願いがついに叶いました。これは私を守ってくれる甥の祝福です。」その後、彼はメイドに鏡を運ばせ、再び宴会の準備をし、再び話をしました。みんなは夜遅くまで幸せでした。彼らは一緒に夜を過ごした。それは本当です。過去の果てしない心配は、今日喜びに変わりました。 翌日、郭維は朝廷に行き、将軍たちの出席を受け入れ、柴容を軍司令官に任命して戦略計画を担当させた。そこで郭維は言った。「将軍である私は、王の命によりこの関を守る義務がある。兵士も将軍も少なく、要所の防衛が困難であることを常に心配していた。今日、私は甥をこの職に特別に任命した。各門に行って旗を立て、兵士と馬を集め、作戦に備えなさい。これは国家の重要な問題であり、甥が間違いを犯さないことを願う。」郭維は公の場でこのように言ったが、本音を直接表現するのは適切ではなく、公権力を私利のために利用して世論を覆い隠した。それから彼は密かに彼を育て、行動する適切な時期を待ちました。柴容はすぐに命令を受け入れて礼を言い、軍印を下げて司令部を出て、四つの門に行き、旗を立て、兵士を募集し、馬を買い、英雄を選んだ。予想通り、全国から優秀な人材が集まり、軍に登録され訓練を待つ準備が整った。それを証明する詩があります。「命令が最初に発令されると、募集事務所が開設され、強い男たちと勇敢な戦士たちが風を見に来ました。」 当時、人々は王に忠誠を誓うことだけを考えていましたが、王が自らを守り、攻撃できるとは誰が知っていたでしょうか。 柴容は兵士を募集し、馬を購入し、密かに大きな計画を練っていたことは言うまでもない。趙匡胤は興龍寺に1ヶ月以上住んでいたが、この日、寺を出て西へ向かおうとしていたという。長老たちは彼を引き留めようとしたので、彼を見送るためにワインを用意しなければなりませんでした。客や亭主が酒を飲み終えると、匡胤は馬に鞍を置き、鎧、荷物、包み、武器などを持ち、身支度を整え、腰に魔法の杖を巻き付け、山門を出て馬にまたがった。長老は僧侶たちを率いて彼を見送り、山道の分岐点に着くと、僧侶たちは互いに別れを告げた。 今は初冬で、寒くなってきました。彼はずっと馬に拍車をかけて道に沿って駆け抜けた。気が動転していたとき、ふと見上げると道の脇に庭がありました。庭にはまばらに植えられた数十本の桃の木以外、木はありませんでした。それぞれの木には、ボウルほどの大きさの新鮮な桃が数十個ぶら下がっていて、赤と白が完璧に混ざり合って、みずみずしく美しい見た目でした。彼はとても好奇心が強くなり、「今は冬なのに、この木にはまだ新鮮な桃が実っているのはなぜだろう。今までどうやって生き延びてきたのだろう、それとも、このような品種を生み出すのは地元の産物なのだろうか」と考えました。彼はとてもうらやましくてよだれを垂らし始め、いつの間にか馬の後を追って庭に入っていきました。彼は桃の木の下に行き、あぶみを放り投げて馬を縛りました。そこに誰かがいるかどうかは気にしませんでした。手を伸ばして赤い桃を摘み、一口食べました。それは香りがよく、甘く、口の中はジューシーな果汁でいっぱいでした。とてもおいしかったです。この桃は雪桃と呼ばれるものだそうです。3月に花を咲かせ実をつけ、冬まで栽培されて食べられるそうです。雪が降る時期は特に美しく、見て楽しいだけでなく食べても美味しいです。その種類はユニークで、世界中で有名です。その後、金族が反乱を起こして陝西省に侵入し、人々を殺し、土地を荒らしました。金族が都市に侵入した後、すべてが破壊され、桃の木は枯れてしまいました。残念です! その時、匡胤は雪桃をゆっくりと食べ、全身がリフレッシュしてリラックスした気分になった。一つ目では足りなかったので、もう一個食べたくなり、もう一つ取って、とても幸せな気分で食べました。すると彼は考えました。「庭には誰もいないけれど、ただで食べさせるわけにはいかない。それに、彼は何日も何ヶ月も一生懸命働いてきた。お金をあげないと、罪悪感を感じる。この桃は1個10セントの価値があるはずだから、あげなくちゃ。」それから腰から20セント札を取り出し、草に結びつけて木に吊るしました。それから彼は考えました。「あと2つ摘んで、出かけるときに持って行って楽しもうか。何が悪いんだ?」彼はさらに20枚のコインを残し、桃を摘むために手を伸ばしました。ちょうどそれを降ろそうとしたとき、桃の世話をしていた女中が戸口から出てくるのが見えました。誰かが桃を盗んでいるのを見て、女中は何も言えませんでした。彼女は横を向いて中を覗き、家の主に知らせるために出て行きました。 一家の主はヒロインでもあり、家族の英雄でもあります。彼女は30歳を超えており、生まれつきの強靭な体と火のように激しい気性を持っています。たとえ火や水の中を通らなければならないとしても、彼女は何も恐れません。しかし、彼女は醜く、愚かで、粗野だったので、人々は彼女を「母ヤクシャ」というあだ名で呼んでいました。その時私は部屋に座っていました。女中がやって来て、「庭で泥棒が桃を盗んでいます」と報告しました。彼女はすぐに怒り、急いで鋳鉄のハンマーを2つ拾い、庭に走って行きました。ちょうどその時、匡胤が雪桃を抱いているのが見えました。女鬼は大声で叫んだ。「泥棒、どこから来たの?よくもこんなところで桃を盗んだな。早く捕まえて!」すると、何十人もの侍女が後ろからついてきた。侍女たちは立ち止まって一緒に叫んだが、前に進む勇気はなかった。匡胤が馬に乗って出かけようとしたとき、誰かが叫んでいるのが聞こえた。振り返ってよく見ると、目の前には強面の女がいて、変な感じがした。私が見ることができたのは、彼のこめかみは乱れ、髪は三つ編みにされ、眉間にしわが寄っていて、目は輝いていたということだけだった。黒い麺は肉で覆われ、香りのよい粉が均等に塗られており、まるで雪を覆う暗い雲のようです。赤い口は広く、顎は広く、黄色い歯が一面に生えており、まるで金が埋め込まれた血の洞窟のようです。彼女の元色のシャツの袖はまくり上げられ、優雅さの痕跡もなく彼女の力強さを誇示していた。彼女の緑の絹のスカートは風になびき、彼女の純粋な凶暴さと頑固さを示していた。彼女は七寸の金色の蓮華を広げ、二種類の武器を手に持っていた。 匡胤はそれを見て、申し訳なさそうに笑って言った。「お義姉さん、何も言わないでください。私はあなたの桃をただで食べたわけではありません。なぜ怒っているのですか?」女鬼は叫んだ。「この赤い顔の泥棒!誰もいないのに、あなたは桃を盗んだのです。どうしてただで食べなかったと言えるのですか?」匡胤は言った。「お義姉さん、私を責めないでください。私は遠くから来た旅人で、ここを通りかかったのですが、宝の庭にある美しく新鮮な桃を見て、本当にうらやましくなりました。周りに誰もいないという事実を無視して、うっかりして庭に侵入し、いくつか食べてしまいました。それは間違っていました。もうただで食べるのはよくないと思い、お金を返しました。今は木に吊るしてあります。自分の目で見てください。」 、そうすれば真実がわかるだろう。少なすぎると思うなら、倍にして返す。なぜそんなに怒っているのか?」これを聞いた女鬼は太い眉毛を立て、奇妙な目を見開いて叫んだ。「この泥棒!こんな馬鹿げたことを言うのはまだ夢を見ているのか。ここが民芸品だと思っているのか、よくもそんな大胆なことができるもんだ。これは私たちに送られてきた雪桃で、地元の産物だ。誰が触ろうというのか?左手で桃を摘んだ者は左手を切り落とされ、右手で桃を摘んだ者は右手を切り落とされ、一粒食べたら歯が折れる。返すお金があるなんて言わないで。何千本ものお金があっても足りないよ。」そう言うと、彼女は突進し、ハンマーでドアの上部を叩いた。クアンインは横に避けた。女悪魔は再びハンマーで殴りつけた。匡音はまた身をかわして叫んだ。「義姉さん、昔から『無知は罪にならない』という諺があります。『過ぎたことは過ぎたこととして忘れなさい』とも言っています。あの時は間違っていましたが、もう自分の過ちを認めました。あなたはそんなに本気なのに、どうしたのですか?」女鬼は激怒して言った。「あなたは禁制品を盗むという重大な罪を犯しました。まだもっと言って私を苦しめるのですか!」彼女は鉄槌を振り回して無差別に彼を殴りつけた。匡音も激怒し、向かってくるハンマーをかわして蹴り飛ばし、女悪魔を地面に叩きつけた。匡音はそれを踏みつけ、手を伸ばして桃の棒を掴み、彼女の頭と顔を殴り、彼女は雷鳴のような叫び声を上げ続け、絶え間なく轟音を立てた。匡胤は「この意地悪な女、よくも客をいじめるな」と叫んだ。女鬼は「この赤い顔の泥棒め!桃を盗んだのは罪だ。今日は私を殴り殺すぞ。私は絶対に屈しないぞ」と言った。匡胤はこれを聞いてさらに激怒し、桃の棒を拾い上げてまた彼女を殴った。女夜叉はもう我慢できず、「赤面の勇者よ、どうか私を助けて、桃を摘んで食べさせてください」と懇願しました。 匡音は笑って言いました、「この意地悪な女よ、慈悲を乞うたのだから、放っておいてあげよう。もしまた他人をいじめたら、殴り殺すぞ」。 それから、「起きろ!」と叫びました。 女夜叉は髪を振り乱し、目は腫れ、鼻は曲がり、靴は足の裏に引きずられ、スカートとズボンは両手で持ち、二人の侍女に助けられながら、歩いて行きました。彼は家に戻ると、テーブルをたたき、椅子にぶつかり、泣き崩れた。まさにその通りです。トラブルは人を探すのではなく、トラブルそのものを探すのです。 匡寅は女鬼を解放し、二つの雪桃を腕の中に隠し、馬に乗って園門から出て、前へ進みました。約2マイル歩くと、道路脇に「千家店」という大きな文字が3つ書かれた別の境界標識が見えました。彼は馬に乗って境界を抜け、商人ホテルの前に到着しました。彼は馬を降りてホテルに入り、馬と荷物をウェイターに渡し、ナイフを手に取り、きれいな部屋を選びました。ウェイターは馬を連れて餌をやり、荷物を部屋に運びました。すぐにワインと食べ物が出され、Kuangyin は食べ終えました。ちょうどその時、店主が話しかけに来たので、匡音は店主に名前を尋ねました。店主は「私の姓は王で、息子は一人しかいません。この店は先祖から受け継いだもので、神の助けにより繁盛しています」と言った。店主が話していると、給仕が慌てて入ってきて叫んだ。「親方、明日は10月15日で、太歳が山を下りる日です。先ほど、手下が私たちに粟を30石量って王に納めるように言いました。明日王が来たら、私たちは自分で粟を刈らなければなりません。あなたに代わりを雇わせてはいけません。私の命令に従わなければ、責任を問うことになります。親方、早く決断してください」。店主はこれを聞いて不安になり、手をこすりながらためらい、うめいた。匡胤はこれを見て困惑し、尋ねた。「老店主、今店員が言ったことが全く理解できません。太歳はどこにいるのか、王はどこにいるのか分かりません。この三十石の粟をどうするつもりですか。本当の莫古とは何ですか。なぜ代わりの名前に置き換えることができないのですか。老店主が教えてくれるといいのですが。」店主は言った。「ご主人様、あなたは知らないのです。ここから二十里以上離れたところに太行山という山があります。その山には二人の王がいます。一人は衛山王、もう一人は荀山太宝といいます。彼らは五千人の兵馬を率いており、非常に強力です。最近、もう一人莫古王という王がやって来て、三番目の席に座っています。」匡胤は言った。「この名前は彼には馴染みのないものです。」 宿屋の主人は言った。「そんなことを言うのも変な話だ。この男は生まれつき犬肉が大好きで、犬肉を香ばしくおいしく調理した。この男が一味に入ってからというもの、毎月1日と15日に犬肉を調理し、子分たちに村の宿屋に運ばせ、交代で穀物を拭くように命じている。彼らは上、中、下の3つの階級に分かれていて、一軒一軒回ってみんなを呼び出し、香りのよい犬肉を口に塗って匂いを嗅ぐ。残念ながら口には届かず、代わりに米を払わなければならない。高位の家庭は一回こするごとに米30石、中位の家庭は一回こするごとに米30石を払わなければならない。米を拭く家は1軒につき20段の穀物を納めなければならない。米を拭く家は1軒につき10段の穀物を納めなければならない。米は山の砦に送られ、これらの人馬を養うため、彼は米王と呼ばれている。これは彼が確立した新しい規則です。誰が彼に逆らうでしょうか?明日は旧暦の15日です。千家店に来るのは私たちの番なので、前払いしました。対応が難しいので心配です。どうしたらいいですか?」これを聞いた後、匡音は笑って言った、「だから理由はたくさんある。老店主、躊躇しないでください。明日彼がここに来たら、私が出てあなたの代わりになるのを待ってください。どうか王様に会わせて、ルールを学ばせてください。」店主は慌てて手を振り、「そんなわけにはいきません。王様の命令は山のように強いのです。どうして私が王様の意志に逆らってトラブルを起こすことができるでしょうか。」と言い、匡胤は「そんなことは問題ではありません。王様の命令はただのはったりです。どうして王様に真実と嘘、善悪の区別がつくのでしょうか。心配しないでください、老店主、私は決してトラブルを起こしません。」と言いました。匡胤が行く決心をしているのを見て、店主は彼を止めるのは難しいと思ったので、「客が行きたいのだから、他のトラブルを避けるために注意して気を付けなければなりません。しかし、あなたも私も血縁関係を認めて親戚の代わりをしなければなりません。」 匡嬰は考えました。「じゃあ、叔父さんって言えばいいのに。」 宿屋の主人は言いました。「まずい、まずい。どうしてあなたのような年寄りに、こんなに若い叔父さんがいるんですか? 国王が知ったら戦争になるんじゃないの?」 ウェイターは言いました。「ボス、あなたは頑固で無茶な人だということがわかりました。この宿屋が親戚の代わりをしてくれるのなら、なぜ年齢を気にする必要があるのですか? 明日、国王に会ったとき、この叔父さんはあなたの祖母の生まれだと言えばいいのに。それでいいじゃないですか。」 3人は一緒に笑いました。まさにその通りです。密かに罠を仕掛けて、ジャッカルが群れをなしてやってくるのを待ちます。 しばらく三人で雑談したり笑ったりしていたら、いつの間にか日が暮れていた。店主と店員は別れを告げて店を出て行った。クアンインは荷物を広げてそこで一夜を過ごした。 翌日、朝食後、オーナーがやって来て、気をつけてトラブルを起こさないようにと何度も指示を与えた。二人が話していると、外から大騒ぎが聞こえ、大地と天が揺れ、「王子様が到着しました。オーナー様、食事にお越しください。」と大きな声が叫ばれました。ウェイターが走って入ってきて、匡音と一緒にドアから出て行きました。私は王が馬に乗っているのを見ました。その両側には従者たちがいました。馬の前の従者たちは朱色の食料箱を持っていました。彼らは皆、権力を誇示し、庶民を威圧していました。匡胤は目を上げて王をよく見ました。彼は確かに威厳のある大男でした。どうして知っていますか? 彼は頭に無地のサテンのスカーフを巻き、紫色の絹のローブを着て、腰には鳳凰のベルトを巻き、足には黒いブーツを履いていた。彼は太い眉毛と星のように明るい目、高い鼻と月のように丸い顔、長く流れるようなあごひげ、そして背が高くて力強い体を持っています。私は将軍が天から現世に降りてくると誤解していたが、実は山の王が要塞を離れるところだった。 匡胤はこれを見て、心の中で喜びましたが、知らないふりをしました。手下たちは大声で叫んだ。「あの赤い顔をした男、なぜこっちに来てひざまずかないのか?王子が誰だか分からないのか?」 匡胤は同意しなかった。他の数人が言った。「これは目が見えず耳が聞こえない人に違いない。気にしないで、老王に出て来るように頼めばいい。」それから皆が叫んだ。「王官、王様が来ています。出て来て食べなさい。」王様はこれを聞いて、真っ先に馬に乗って、匡音を見た。そして従者たちに尋ねた。「この人が店を切り盛りしている老王ですか。」従者たちは答えた。「いいえ、老王の代わりになっていると思います。」王様は激怒して叫んだ。「馬鹿げている!昨日、雇えるのは元の店主だけで、代わりは許されないと言ったじゃないか。なぜ私の命令に従わなかったのか。急いで元の店主に出て来て話をするように頼みなさい。」ウェイターはひざまずいて報告した。「うちのボスの老王は体が麻痺していて起き上がれないので、叔父さんに代わりを頼んだんです。穀物を拭いて穀物を支払えるようにしなさい。今日の期限が過ぎたら、役人に来てもらって、次回は命令に従うようにします。王様が慈悲を示してくれることを願います。」王様は言いました。「老王様は病気なので、急いで叔父様に上って来るように頼みなさい。」家来たちは一斉に叫びました。「老王様の叔父様、王様はあなた方に穀物を拭いてほしいと言っています。」匡胤は言いました。「穀物が欲しくないなら、私が降りて行きます。穀物を拭きたいのなら、早く持って来て拭かせてください。」王様はそれを聞いて、家来たちに赤い漆の食箱を開け、犬肉の足を取り出し、匡胤のところに持って来るように命じ、叫んだ。「老王様の叔父様、これは法定の五香の犬肉です。一度こすると災難が消えて福がもたらされます。二度こすると病気が消えて寿命が延びます。今日あなたがそれを味わえるのは天からの恵みです。早くこすりなさい。」 クアンインはそれを手に取って一口で全部食べました。家来たちは皆、混乱して叫んだ。「ああ!誰が本気で食べろと言ったんだ?これがルールだ。こすったら三十石、一口食べたら六十石だ。犬肉を全部食べたということは、王爺の名前を名乗っているだけでなく、王爺の名前を書いているということだ。」 匡音は言った。「あなたはとても心が狭い人だ。心が狭すぎる。私がこれだけ食べたのに、無駄だと思うのか?諺にあるように、「食べ物屋は大腹を恐れない」。」 「粟を食べるのがお好きなら、良いものを選んで持ってきてください。そうすれば主君は喜んで食べられます。60石どころか、6000石欲しいのです。私と一緒に取りに来てください。なぜそんなに急いでいるのですか?」王は馬の上でこの言葉を聞きました。匡胤は体格ががっしりしていて、容姿も並外れているので、扱いにくい相手だと思い、「狗肉を食べさせてください。私が清算します」と考えました。王は家臣を呼び、「この男は大言壮語しているから、食べさせてください。私が清算します」と言いました。家臣たちは同意しました。それから、前足、後ろ足、蜂蜜壺を匡胤に渡して言いました。「叔父様、あなたは楽しく食べたいとおっしゃったので、王様は穀物を量るためにわざわざ私に持って来るようにおっしゃったのです。」匡胤は大喜びしました。彼は前足を取って、それをいくつかに引き裂いて食べました。予想通り、味は調和がとれていて美味しかったです。彼は後ろ足と蜜壺も一緒に食べました。彼はただ彼とトラブルになりたくて、「まだ足りない、まだ足りない。食料箱を持ってきて、心ゆくまで食べさせてくれ」と叫び続けた。手下は何が自分にとって良いことなのか分からず、食料箱を持ってきた。匡胤は箱の中を見て、まだ背もたれの破片が残っているのに気づきました。彼は言いました。「あなたは本当に残酷だ。おいしい食べ物を取っておいて、私に与えなかった。私とどう決着をつけるつもりなのか、見せてよ。」すると、手下の一人が手を伸ばして背もたれをつかみ、匡胤に渡そうとしました。意外にも、匡鑫が弱点を見つけようとしたとき、彼はわざと手を緩め、後部座席が彼のローブの上に落ちた。彼はすぐに顔をしかめ、歯を食いしばって叫んだ。「この犬ども、雌犬ども!なぜ私の服を汚したんだ?」彼は立ち上がって、片方の手のひらでチンピラを地面に叩きつけた。 王はこれを見て激怒し、「顔を真っ赤にした泥棒め! よくも私の部下を殴ったな」と叫びました。そして拳を握りしめ、袖をまくり、馬から飛び降りて、匡胤に駆け寄り、顔を殴りました。クアンインは頭を下げ、左手でそれをブロックし、パンチを返した。王様も避けました。匡雍は心の中で「この盗賊はなかなかの名人だ。三回戦わねばならない」と考え、叫んだ。「この野郎!手足を使うんだから、武術を知っているに違いない。まず三回やらせて、それからどちらが上手いか見てみよう」。王は笑って言った。「赤面した盗賊!お前の話を聞く限り、お前はかなりの知識があるようだ。お前が最初になる勇気がないなら、まずは私が三回やるのを見ていろ」。その後、彼はその場で飛び上がり、飛び蹴りを放ち、構えを捨てて動き始めた。彼は本当にボクシングが上手だった。それを証明する詩があります。私は幼い頃から五足の運動を学び、長拳と短パンチの英雄になりました。 まず 4 段のフレームを開き、ドラゴンをひっくり返して洞窟から出させます。 それから王は三度歩き、三つのポーズをとり、足を組んで立ち、叫んだ。「赤面した泥棒め!もしお前に度胸があるなら、私に決闘を挑んで、どちらが勝つか見てみろ。」これを聞いた後、匡胤は反対側に歩いて行き、そこに立ち、まず足を曲げ、次に地面から8フィート以上離れたところで、双龍の飛び蹴りを蹴った。それから彼は構えを取り、力強く動いた。彼の武術のスキルは以前よりもさらに進歩しているように見えた。それを証明する詩があります。太祖の魔拳は少林寺から来たものであり、彼の能力が世界の結末を決定します。 古代の賢人の精神を引き継ぎ、中国民族に400年にわたる永続的な遺産を築きます。 匡音も三歩三歩と動きをし、叫んだ。「この泥棒犬め!どんな技を持っていても、それを使ってみろ。お前を踏み潰して絶対に諦めないと誓う!」王は激怒し、まず左拳を突き出し、右手をその上に置き、横に歩いて前に突進し、左足を踏み鳴らし、右足で匡音の顔を蹴った。匡胤は横に避けたが、足の甲に掌が当たった。王は掌打に負けたのを見て、姿勢を変え、飛び蹴りを引っ込め、代わりに長い足を使い、最初に泰山押さえ込み技を使った。クアンインはまたも回避した。王はまた、獲物に襲い掛かるために空腹の虎を、また海を探検するために夜叉を派遣した。 Kuangyin はこれら両方の動きを回避しました。王様は手当たり次第に殴ったり蹴ったりした。匡陰は彼の無秩序な行動を利用し、彼と戦い始めました。彼らが戦っていると、音がして、一人が倒れた。この争いだからこそ、教えがある。顔を合わせると親しさがわからず、共存は難しいが、辿って初めて善悪がわかり、感情的なつながりが生まれるのだ。それはまさに次のようなものです。寛容になると言いましたが、手を挙げませんでした。しかし、手を挙げた時には寛容ではありませんでした。 |
<<: 『紅楼夢』で、賈おばあさんは宝琴を宝玉と結婚させたかったので、宝琴に誕生日を尋ねたのですか?
>>: 四聖心の源泉:第9巻:潰瘍と潰瘍の説明:癰の根本原因
推薦する
古典文学の傑作『論衡』:巻14:荘流篇全文
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
トゥ族の食習慣の特徴は何ですか?
トゥ族の食習慣は、主に農業に従事し、畜産も行うという彼らの生産特性と密接に関係しています。毎日の主食...
『北斉二詩』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
北斉の詩二首李尚閔(唐代)笑顔は国を滅ぼす可能性があるのに、なぜ棘で傷つく必要があるのでしょうか...
有名な哲学書『荘子』雑集:楞�王論(1)原文と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...
「幽雲十六県」はどのようにして遊牧民の手に渡ったのでしょうか? 「幽雲十六県」はどれくらい重要ですか?
本日は、おもしろ歴史編集長が「幽雲十六県」の歴史をお伝えし、皆様のお役に立てれば幸いです。幽雲十六州...
『紅楼夢』の易洪院で宝玉に仕えた人は何人いましたか?
紅楼夢は『紅楼夢』の大観園の主要場面の一つであり、男性主人公賈宝玉の住居である。皆さんも聞いたことが...
古代の科挙は死刑に繋がったのでしょうか?なぜ死後遺体を運び出すことが許されないのでしょうか?
古代、科挙で人が死んだ?なぜ死後遺体を運び出すことが許されなかったのか?次の興味深い歴史編集者が詳し...
宋代の詩の鑑賞:人形への頌歌。作者はこの詩の中でどのような比喩を用いているでしょうか?
宋代の楊儀の『傀儡頌』については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!宴会...
ヨーロッパのクリスマスはどんな感じでしょうか?ヨーロッパではクリスマスにどんな食べ物が食べられますか?
世界中の食べ物は、その生産から味まで、さまざまな国や民族の文化的伝統を反映しています。たとえば、西洋...
梅超鋒は誰が好きですか?梅超鋒と陳玄鋒のラブストーリー
梅超鋒は陳玄鋒が好きです。金庸が創造したキャラクター、梅超鋒は愛ゆえに美しい人生を送りましたが、愛ゆ...
奇談集第二巻第10巻:趙五虎が陰謀を企てて一族の争いを起こそうとしたが、莫大朗はすぐに裏切り者を解任した。
『二科派経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。 1632年(崇禎5年)に書籍として出...
チベット暦 チベットの伝統的な暦の特徴は何ですか?
チベット伝統暦の紹介と特徴チベット人は千年以上前に独自の暦を作りました。チベット暦は月の満ち欠けに基...
水滸伝の関勝と林冲はどれくらい強いですか?違いは何ですか
『水滸伝』は中国文学の四大傑作の一つで、英雄伝説を章立てで描いた長編小説です。今日は、Interes...
宋代の四大才女の一人である呉淑姫の代表的な作品は何ですか?
宋代の四大才女の一人である呉淑姫の代表作は何でしょうか?次の『おもしろ歴史』編集者が詳しい記事紹介を...
歴史インサイダー:アヘン戦争はこんな感じだった!
中国人は、第一次清英戦争を「アヘン戦争」と呼ぶことに慣れているが、実際には、この戦争の原因は決して「...