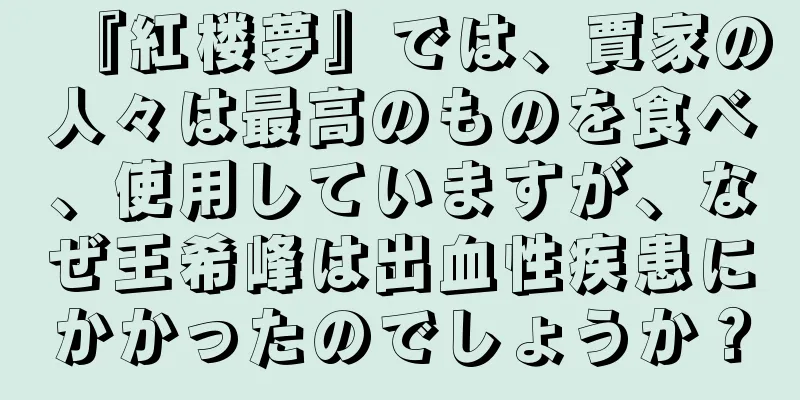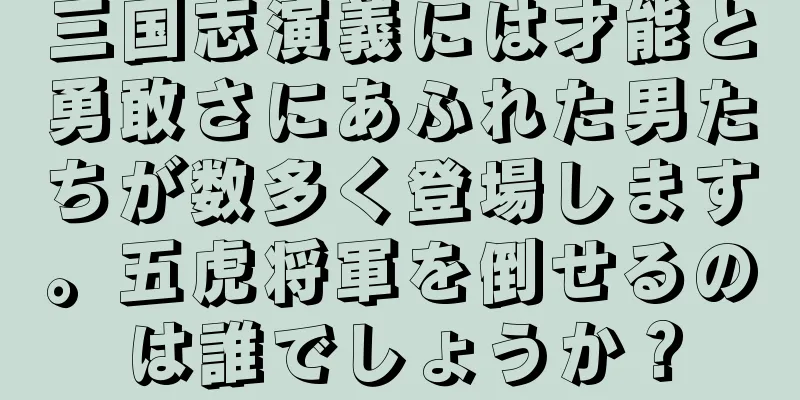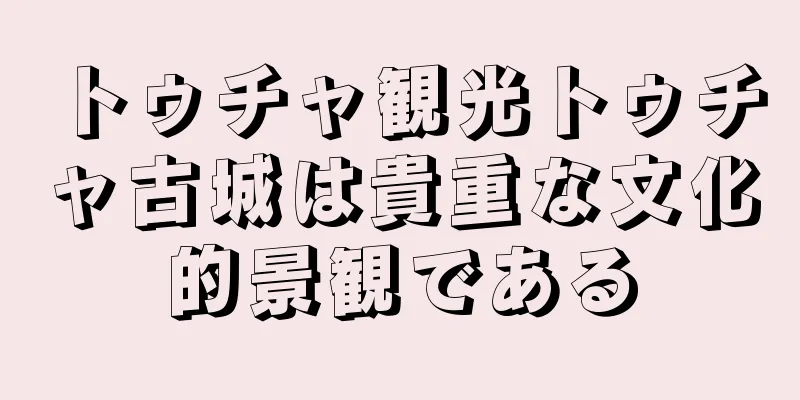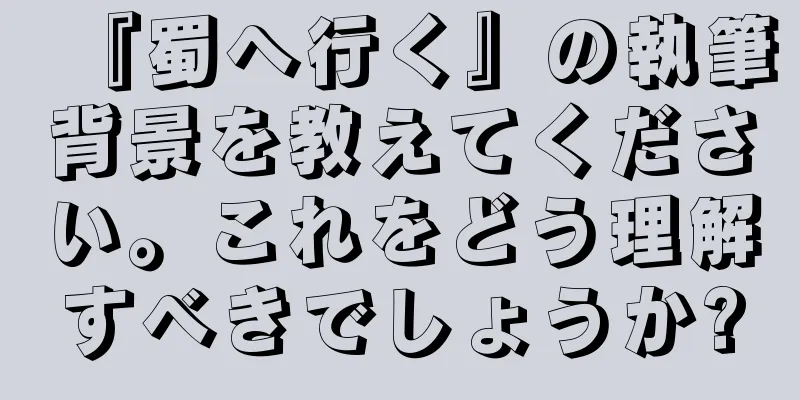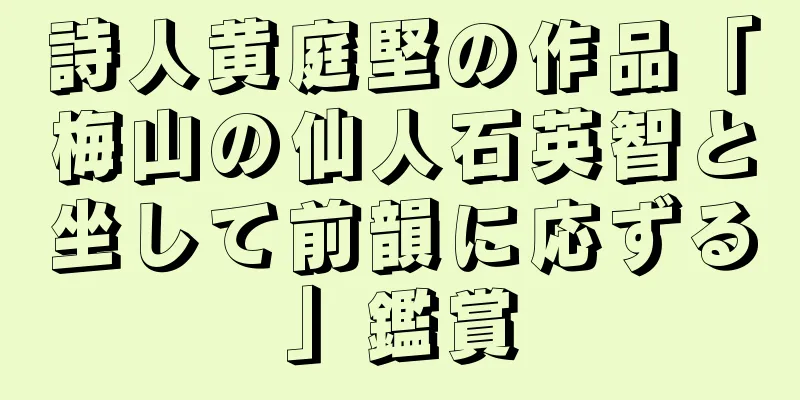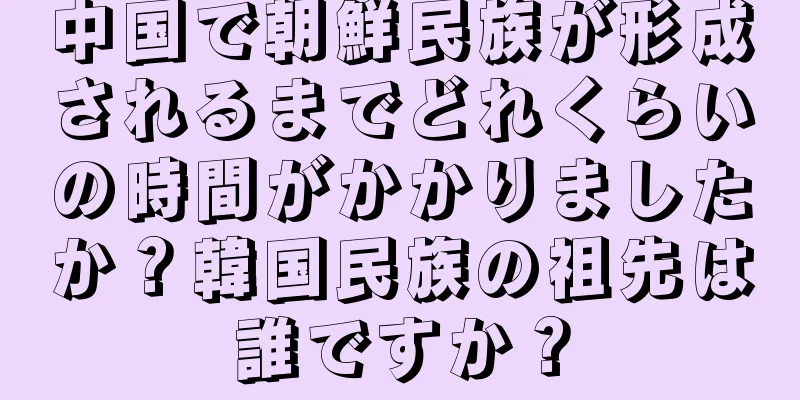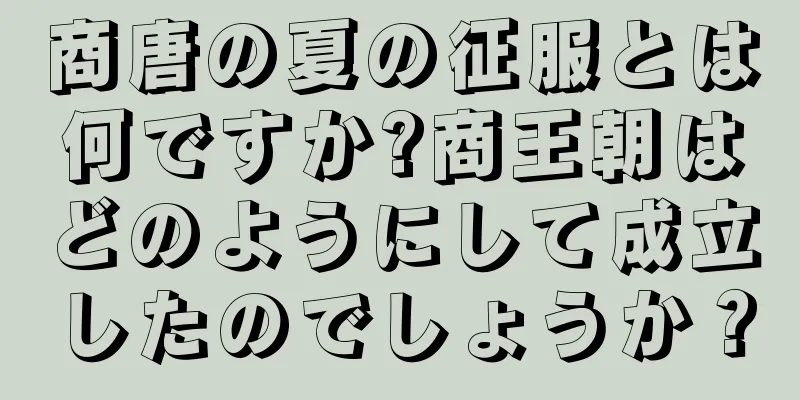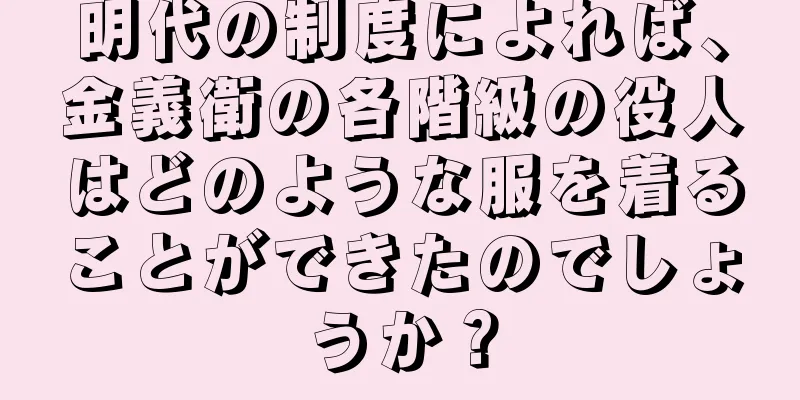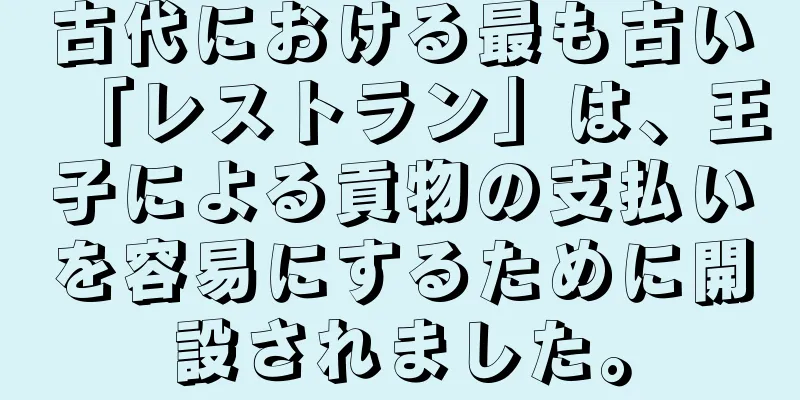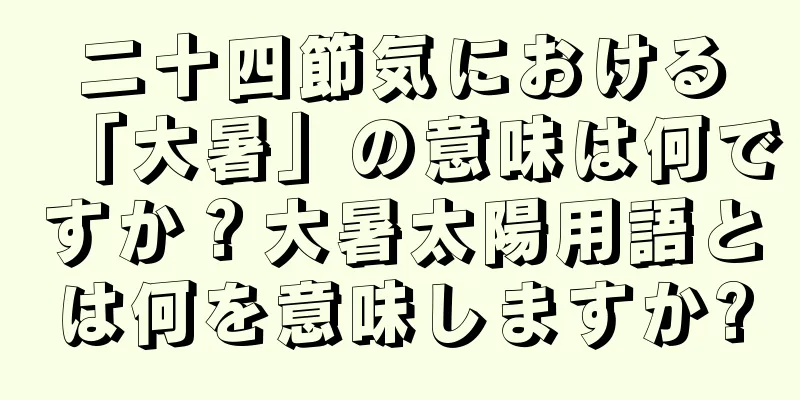古代の科挙は死刑に繋がったのでしょうか?なぜ死後遺体を運び出すことが許されないのでしょうか?
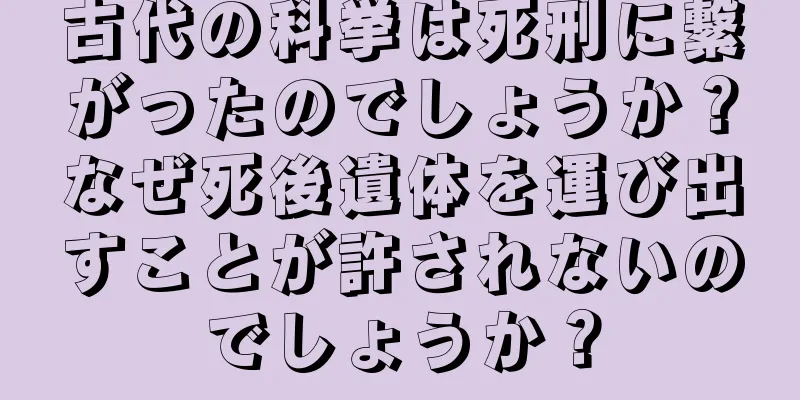
|
古代、科挙で人が死んだ?なぜ死後遺体を運び出すことが許されなかったのか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。ぜひ読んでください~ 私の国の清朝時代には、3年ごとに省級の試験が行われていました。これは国家の科挙界における一大行事でした。州試験は通常秋に、主に主要な州都で開催されます。省級試験に合格することを「中級」といい、合格者は一般に「級人」と呼ばれます。皆さんも聞いたことがあると思いますし、テレビでもよく見たことがあると思います。科挙に合格して准官になると、官吏となる資格が得られ、官職としての人生が始まります。 もちろん、試験勉強は「何千人もの人が一枚板の橋を渡る」ようなもので、好きな人もいれば心配する人もいます。科挙試験では不正行為の要素があるだけでなく、レベルも人それぞれで、運の要素もあります。一発で合格して順調に進む人もいれば、幼少期から老年期まで受験し続けて何も得られない人もいます。 地方試験の季節になると、何千人もの学者が長距離を旅したり、山や川を越えて地方の首都に行き、試験を受けました。大学入試と同じように、チャンスを逃さないために、病気にも負けず歯を食いしばって受験する者もいれば、老衰や虚弱をものともせず、狭くて低い試験室で三日三晩耐えて合格を待つ者もいた。 そのため、3年ごとに行われる地方試験の期間中、多くの受験者が試験会場で病気で亡くなりました。神報は清朝末期、報道の自由を主張した全国商業新聞であった。1872年にイギリス人実業家リチャード・マッカーサーによって上海で創刊され、当時の中国社会に幅広い影響力を持っていた。 沈豹によると、1882年8月、浙江省の科挙が杭州科挙会場で行われた。3回の試験の後に多くの人が死亡し、「試験中に10人以上が死亡した」という。1891年8月12日、浙江省太平県(現在の温嶺)の受験生が午後に突然体調を崩し、嘔吐と下痢を起こし、その日の夕方に急死した。 1902年8月、浙江省の試験中に、4人の受験者が試験室で病気で亡くなりました。「1人は温州出身、1人は湖州出身、他の2人は出身地不明でした。」 光緒帝の治世29年(1903年)8月、中国史上最後の地方試験が杭州公苑で開催されました。 2回目の試験では、70代の老学者が試験中に意識を失い、職員によってすぐに試験室から運び出され、その後すぐに病気で死亡した。 これを踏まえると、清朝時代には試験場で人が死ぬことは確かに一般的だったようですが、奇妙なことはこれから起こります。歴史の記録によると、清朝の科挙では、受験者本人、その家族、試験官、使用人を問わず、試験室で死亡した者は試験室の門の外に運び出されることは許されなかった。 しかし、生きている限り、どんなに重い病気であっても、搬送は許可されます。そのため、故人と親しい関係にあった候補者の中には、故人をキルトで包み、両脇から支えて歩くなどして、故人がまだ生きているように見せ、煩わしさを軽減する人もいます。 誰かが外で亡くなった場合、遺体は家に戻らなければなりません。診察室に遺棄されたのでしょうか? もちろん違います。正門から遺体を運び出すことが許されないのであれば、どうやって遺体を運び出すのでしょうか? 1893年の新聞『申報』には、その年の8月に浙江省の試験の主任試験官が、魯迅の祖父である周福清を投獄した尹如章であったという出来事が記録されている。ある日、殷如章の弟子の一人が全身に熱を出し、治療がうまくいかず科挙会場で亡くなりました。 『神報』によれば、当時は「壁の外に十字の形に木を立て、その上でロープを引っ張り、遺体を吊り上げた」という。つまり、壁の外側に支点として木を立て、ロープを使って遺体を検査室から吊り上げたのである。 清朝時代にはなぜこのような奇妙な規則があったのでしょうか。しばらくの間、多くの人が理解できませんでした。歴史家による研究の結果、ついに答えが出ました。 清朝の統治者たちは、先祖が残した葬儀の慣習に従っていたことが判明した。つまり、家族の中で誰かが亡くなったときは、必ず遺体を玄関から運び出すのではなく、窓から運び出さなければならなかったのだ。満州人はドアは生きている者の通路であり、死者は通ってはならないと信じていたため、科挙会場の死体が壁から吊るされていたのもこの理由による。 |
<<: 磁器はいつ登場したのでしょうか?中国磁器の発展の歴史を紹介します!
>>: 「正果運河」とは何ですか? 「鄭国運河」は秦の国にとって妨げになったのか、助けになったのか?
推薦する
西遊記に登場する聖なる乗り物の中で、なぜ緑牛鬼だけがあんなに威圧的なのでしょうか?
『西遊記』で聖人として戴冠された乗り物の中で、なぜ緑牛魔だけがあんなに横暴なのでしょうか。隣にいる九...
杜甫の有名な詩の一節を鑑賞する:天気の良い日には、無理やり食べたり飲んだりするが、それでも寒い。暗い部屋に座って、キジの冠をかぶっている。
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
北宋時代に開封府が特別な地位と影響力を持っていたのはなぜでしょうか?
北宋(960年 - 1127年)は、中国の歴史上、五代十国に続く王朝であり、9人の皇帝が統治し、16...
欧陽秀、劉玉熙、辛其基の晩年はどのようなものだったのでしょうか?まだオープンマインドで自由気まま
欧陽秀、劉毓熙、辛其基はいずれも有名な作家であり詩人です。彼らの晩年の生活はどのようなものだったので...
『紅楼夢』の劉夫人は誰ですか?彼女は賈家で何をしているのですか?
劉姐は『紅楼夢』の登場人物。ウーアーの母親であり、大観園の厨房責任者。 Interesting Hi...
『紅楼夢』における平児の結末は何ですか?私たちは彼女の知恵から何を学べるでしょうか?
平児の結末が分からない読者のために、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。読み続けてください〜私...
すでに家政婦としての能力を持っている李婉はなぜ自分の才能を発揮したがらないのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
薛剛の反唐戦 第20章:薛剛が鉄丘陵を掃討、馬登が同城湖を救出
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
涼山における劉唐の順位は?劉唐の具体的なランキングを見る
劉唐は『水滸伝』の有名な登場人物であり、梁山泊での彼の順位は常に話題となっている。小説の描写と歴史研...
「才能があり学識がある」というフレーズの由来
「八斗」は、三国時代の南朝の詩人謝霊雲が魏の詩人曹植を賞賛するために使った比喩です。彼は言った。「世...
康熙帝と乾隆帝の時代に、康熙帝に関連する重要な人物や出来事は誰でしたか?
清朝初期は依然として非常に繁栄しており、かつては康熙帝と乾隆帝の繁栄期を経験しました。今日、Inte...
『紅楼夢』のユウ姉妹は自ら不幸を招いたのでしょうか?美しいが自尊心がない
『紅楼夢』の于家の姉妹に何が起こったかご存知ですか?次は『おもしろ歴史』編集者が解説します。 1. ...
岳中武廟を訪ねて:二人の英雄、于謙と岳飛の相互尊重
ユー・チエン一頭の馬が南にやって来て浙江を渡ると、汾城の宮殿は雄大で遠くに見えました。維新期の将軍の...
王の「卜算子·送宝浩然之浙东」:春への別れと別れが一緒に書かれている
王観(1035-1100)、通称は童蘇、通称は朱克、台州如皋(現在の江蘇省如皋)の出身。胡淵の弟子で...
『水滸伝』で王倫はどのようにして村長の地位を奪われたのでしょうか?
小説『水滸伝』の登場人物である王倫は、「白衣の学者」として知られています。これに非常に興味がある人の...