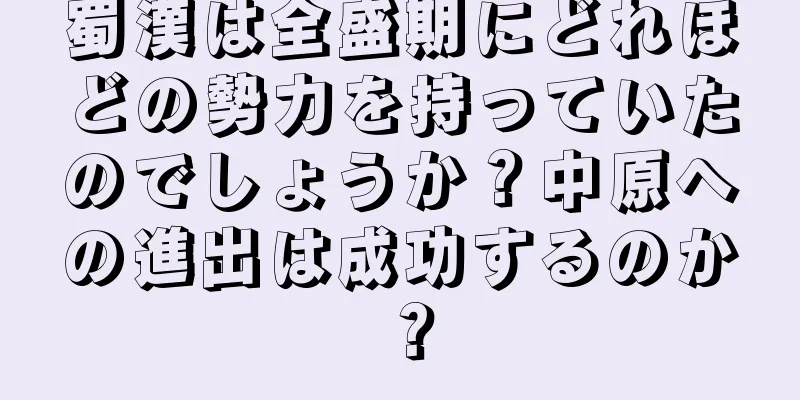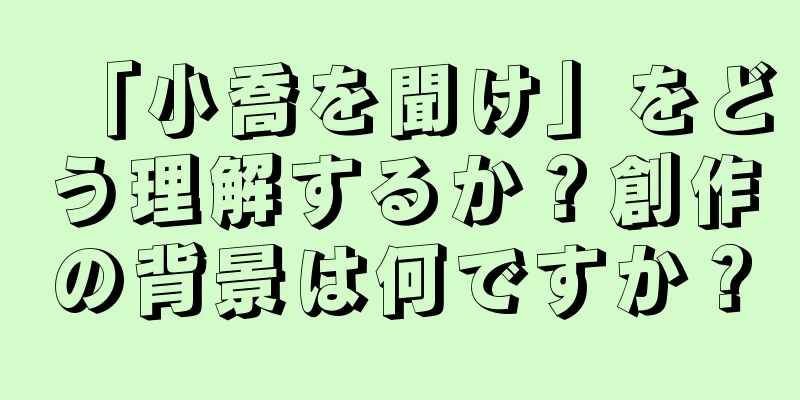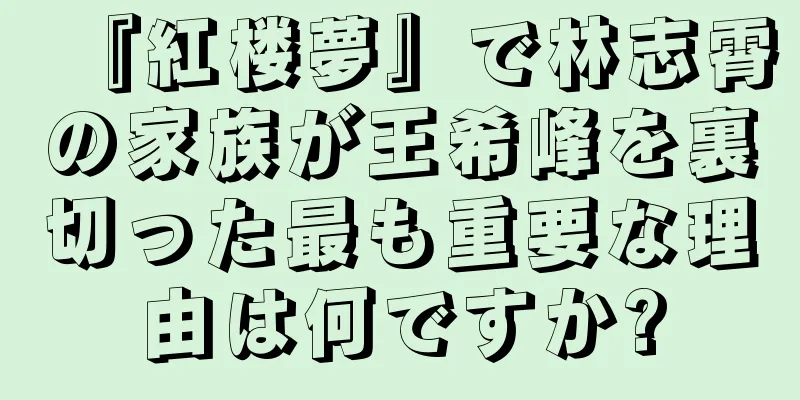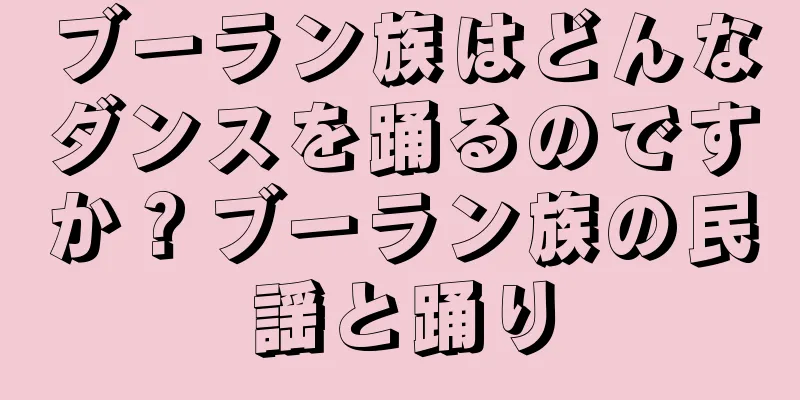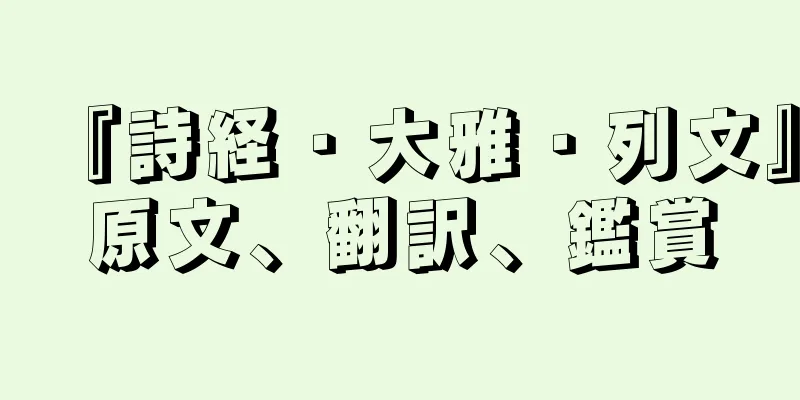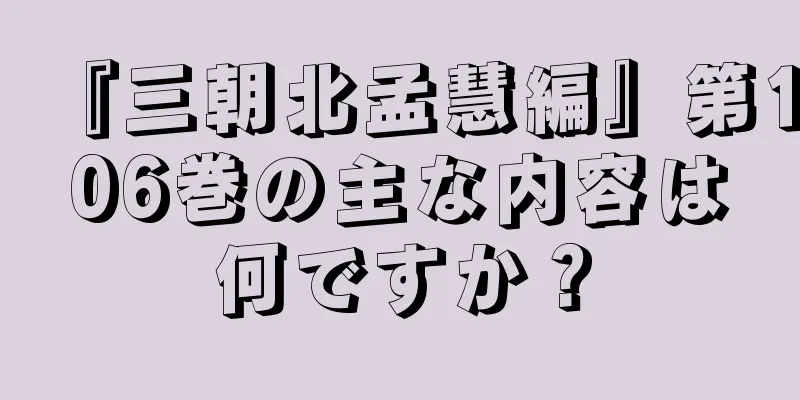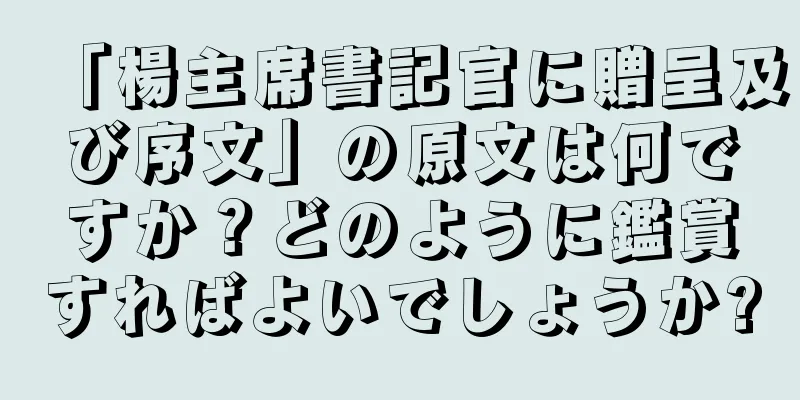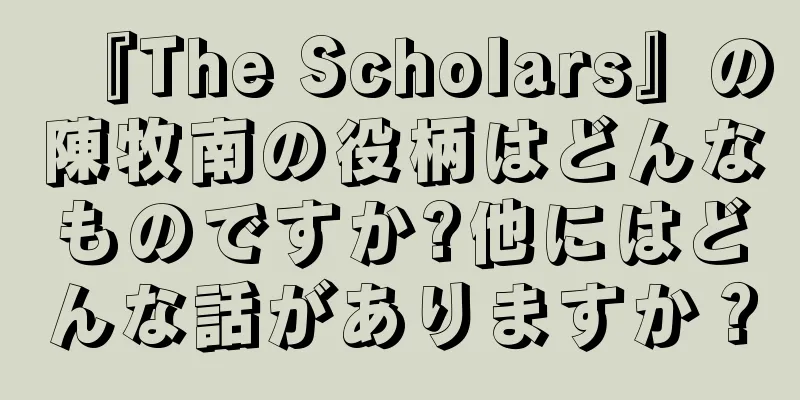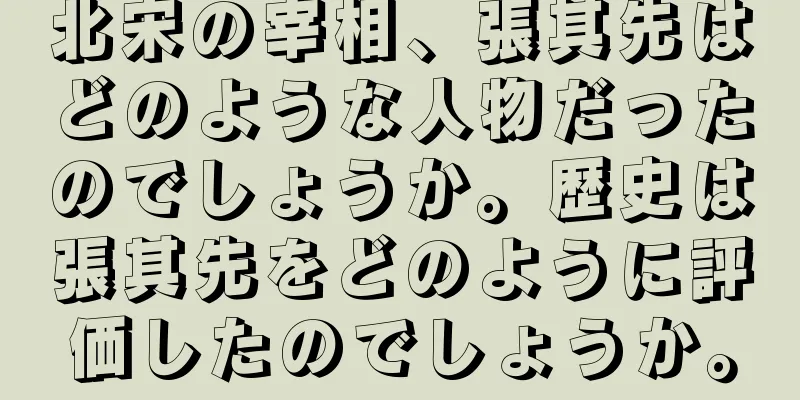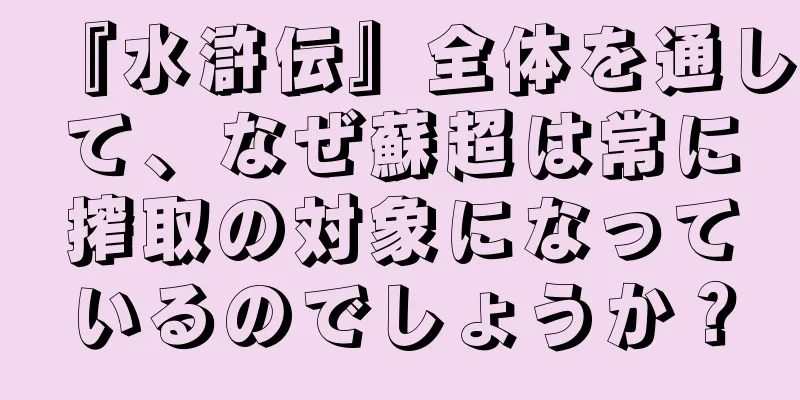中国における仏教の初期の普及:仏教音楽は張騫によって初めて紹介された
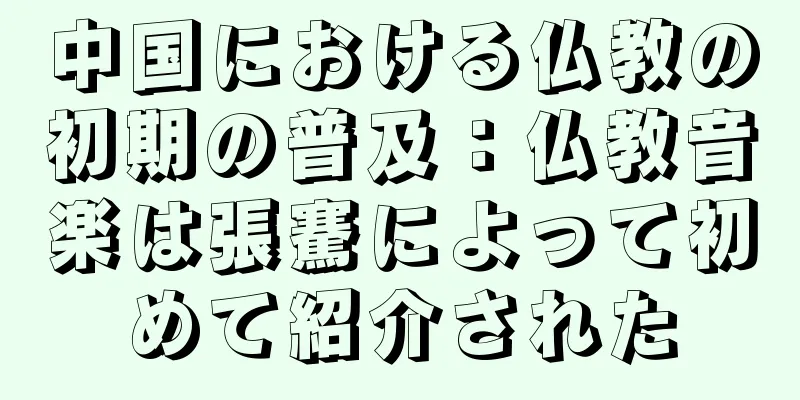
|
古代インドは音楽が非常に発達した国であったため、仏教音楽は古代インドで非常に栄えていました。慧教は『高僧伝』の中で、鳩摩羅什の言葉を次のように記録している。「インドの風習は文芸体系を重んじる。国の宮廷や商売のリズムは、絲弦で奏でるのが一番である。仏に会う儀式では、讃美歌を歌うことを重んじる。経典の偈句はすべてこのスタイルである。」唐代の僧侶易経も現地調査の後、『南海集帰内法伝』の中で、「西洋諸国の儀式や教えは広く賞賛されている」と述べている。現在中国に存在する仏教音楽は古代インドの仏教音楽と同じものですか? 両者の関係はどのようなものですか? インド仏教音楽の中国への導入について語るとき、人々は慧教のよく引用される言葉を思い浮かべるだろう。「偉大な教えが東に流れて以来、多くの人がテキストを翻訳したが、広めた者は少ない。これは、サンスクリットの音が反復的であるのに対し、中国語の音が単純で奇妙であるためである。サンスクリットの音を使って中国語を詠唱すると、音が複雑になり、詩が無理やりになる。中国の歌を使ってサンスクリットを詠唱すると、韻は短く、言葉は長くなる。そのため、金言は翻訳されたが、サンスクリットの音は伝わっていない。」慧教は仏教の歴史家であるだけでなく、音楽に対する深い理解も持っていたようだ。彼は、仏教音楽が仏教とともに中国に伝来した後に遭遇した困難を正確に指摘した。これは、歌詞のある音楽(声楽)が他の言語環境に入るときに必ず遭遇する問題、つまり歌詞の翻訳と音楽のマッチングの問題です。慧嬌氏は、長くて反復的な「サンスクリット語の音」を「単一で奇妙な」中国語に合わせるために使用した場合、一つの漢字を多くの音符に合わせる必要があり、メロディーが「複雑」になりすぎると指摘した。逆に、既成の「中国の歌」を元のサンスクリット語に合わせると、メロディーが短すぎたり、歌詞が長すぎたりして収まらないという問題が生じます。しかし、慧嬌の「金言は翻訳されているが、サンスクリット語は伝わっていない」という結論は、必ずしも決定的な結論ではない。音楽には歌詞のある声楽と歌詞のない器楽の2種類があり、仏教音楽も例外ではありません。無言の「梵音」は「金言」と直接調整する必要がないため、慧嬌が指摘した問題は存在しません。中国では歌詞付きの仏教歌も歌われてきました。 まず、言葉にできない喜びの仏教音楽を調べてみましょう。中国人が仏教を中国に伝えたよりも以前に、仏教音楽が中国に伝わったというのは驚くべきことです。 仏教音楽を中国に初めて紹介したのは、偉大な旅行家である張騫でした。 『晋書楽』には「張騫(張騫は伯王侯の爵位を授けられた)は西域に入り、西京で教えを広めたが、マハドゥーラを一曲しか得られなかった。李延年は胡の音楽を基に28曲の新しい音楽を作り、軍楽として使用した」とある。張騫は西域に2回派遣された。1回目は前漢の建元3年(紀元前138年)から元碩3年(紀元前126年)まで、2回目は元寿4年(紀元前119年)である。このとき、仏教はまだ中国に伝わっていなかった。 [1] 漢代の最古の軍楽である李延年がこの「胡楽」をもとに作曲した軍楽「二十八楽」がどのようなものであったかは不明だが、張騫が持ち帰った音楽は仏教音楽であったようだ。 Dou Le は人の名前であるはずです。呉志謙訳の『易祖経』には『独楽バラモン経』があり、独楽が外国の宗教を迷信していたところから釈迦牟尼の啓示を受けて仏教に改宗するまでの物語が語られている。 「マハ」はサンスクリット語で「大きい」「偉大な」という意味です。ドゥレは信仰を変えて最終的に「マハドゥレ(偉大なドゥレ)」となり、それがこの曲のテーマとなっているようです。この仏教歌は、おそらく歴史的な記録とともに中国に伝わった最初の仏教歌であると考えられる。 [2] この仏教音楽「二十八解釈」は漢の武帝によって軍楽として使用され、後漢の時代にも辺境の将軍の力を誇示するために使用されました。それは「万人の将軍」によってのみ使用されました。しかし、魏晋の時代以降、二十八篇の解釈はすべて残っておらず、「黄虎」を含めてわずか十篇しか残っていない。劉宋の郭茂謙が『月府詩集』を編纂した頃には、「言葉がすべて失われた」と嘆くことしかできなかった。 『月府詩集』第21巻の『恒垂曲辞』の「解説」には、「恒垂曲、28篇、李延年作。魏晋代以降、伝承されたものは10篇のみ。1篇は『黄湖』、もう1篇は『龍頭』…」とある。 中国に最初に伝わったこの仏教の歌は、軍楽として使われてから縁起が悪かったようで、中国で盛衰し、戦争で消えていった。 話すことの喜びについて話しましょう。慧嬌が「金言は翻訳されているが、梵語の音は伝わっていない」と主張したのは、中国仏教音楽の歴史において言及しなければならないもう一人の人物、曹植を紹介するためであった。慧教は、仏教音楽の翻訳と作曲の問題で中国仏教徒が混乱していたことを概説した後、喜びを込めて次のように書いている。「初めに陳思王曹植がいた。曹植は音楽を愛し、経文の音に注意を払っていた。盤茶の吉兆の音に精通しており、玉山の神学体系に感化を受けていた。曹植は『吉兆応元』を編集・編纂し、学者の祖とした。伝承された音は3000以上あり、契約には42の音がある。」 曹植が玉山で仏杖を作ったという話は広く伝わっており、多くの仏典に記録されているだけでなく、儒教や道教でも大いに語られています。南宋の劉景舒の『易源』には、「陳思王が山中を旅していたとき、突然空中に経文を詠唱する音が聞こえた。その音は澄んで遠く、大きく、発音を理解して仙人の声だと思い、書き留めた。道士たちはそれを真似て不虚音と書いた」と記されている。唐の道士の『法源竹林』にも、「曹植はかつて玉山を訪れ、突然空中にブラフマーの音を聞いた。それは澄んでいて優雅で悲しげで、心を打たれた。長い間聞いていたが…、その音節を真似てサンスクリットの詠唱として書き留めた…」と記されている。また、この記述は唐の道宣の『光洪明記』などの古典にも記録されている。 曹植(192年 - 232年)は曹操の妻である扁の三男であった。彼は幼少のころから聡明で、10歳で詩を暗唱することができた。彼の『七段詩』や、兄の曹丕から迫害を受けた話は中国でよく知られている。彼は機知に富み、「子供のころから詩を書くのが好き」で「多くの作品を書いた」だけでなく、音楽にも堪能で「世界のあらゆる芸術を習得した」。彼の思想も非常に豊かでした。仏教に改宗したことはなかったものの、高度な理解力を持つ知識人として、また政治的には成功せず評価もされなかった人物として、当時最も流行していた新しい思想である仏教に本能的な興味を持たずにはいられなかったのです。彼は仏教の経典に没頭していた。法源竹林は「仏典を読むたびに、究極の真理だと思って、長々と感嘆していた」と述べている。仏教に魅了され、高い教養と音楽の才能を持っていたからこそ、「上昇音と下降音を伴う七音の賛美の旋律を作曲し、世界の風刺と教育のモデルとなった」のである。 中国の古代書物で作曲について論じる際、「天から音楽が聞こえる」とか「神の啓示を受ける」といった表現がよく出てきます。これは古代人が音楽の創造を崇拝していたためかもしれませんし、神秘的な効果を求めて意図的に雰囲気を作ったのかもしれません。具体的には、この二つの記録には、曹植が作った仏教音楽がインドの仏教音楽と関連しているというヒントが含まれています。では、曹植は中国仏教音楽にどのような貢献をしたのでしょうか? 問題の鍵は、「音声伝送に関しては3000以上あり、契約に関しては42ある」という文をどのように理解するかにあります。 実は、「契」という言葉は、もともとは「刻む」という意味でした。 「契」とは書面による契約のことを指し、「記録して永久に変更なく保存する」という意味です。このように、慧嬌の言葉は、「口承で伝えられた曲は3,000曲以上あり、そのうち42曲が録音されている(そしておそらく慧嬌の時代にはまだ入手可能だった)」と分かりやすいです。 本来、「契」は書くという意味です。音楽を書き記すとしたら、それは楽譜以外の何でしょう?では曹植はどんな楽譜を使ったのでしょうか?おそらく『韓書』に出てくる「音曲」ではないかと思います。王献謙(1842-1917)は『漢書』の注釈の中で、「声の曲がり具合は、唐代には楽譜と呼ばれ、現在は梵語と呼ばれている歌の楽譜を指している」と説明している。 「音のねじれと曲がり」は、比較的原始的で直感的であり、音の高低を曲線で表したあまり正確ではない表記法です。現代の楽譜のようにピッチの値を正確に定義することはできませんが、使用する人にとっては一種の「メモ」として役立ちます。 「気」は楽譜であり、「音曲線」のような曲線の楽譜であり、既存の宗教音楽書の例によって検証することができます。日本の『大正新脩大蔵経』第2712巻には『玉山明書集』、第2713巻には『玉山四超』があり、どちらも楽譜に傍注をつけた経典集である。楽譜は「曲譜」の形をしており、両楽譜集には「玉山」という名前が付けられており、日本の僧侶の心の中では仏教の楽譜は曹植によって作られたものであることを証明しているだけでなく、「音曲譜」の例としても『漢書』の記録を裏付けることができる。 学者の中には、私が「『三千余りの音が伝わる』とは三千余りの歌を作曲することと理解しているが、これは間違いだ!」と言っているのに、反対する人もいます。彼らは、「古今を通じて三千の歌詞と曲を作曲した人は少なく、三年間毎日三曲の歌を書き、それぞれの歌を代々伝えてきた人はさらに少ない」と考えています。したがって、彼らは「音」という言葉は「音符」、つまり「三千余りの音符」と解釈できると考えています。もちろん、私は「三千余り」の「音」という言葉をメロディーと解釈することが唯一の合理的な説明だとは思いません。また、「三千」は「三十」の間違いではないかと疑っています。しかし、歴史を通じて、「音符」は音楽の測定単位として使用されたことはありません。言い換えれば、「私は x-x 音符を書きました」と言うミュージシャンはいないということです。さらに、曹植がそれほど多くの曲を書けなかったと考えるだけでは十分な理由にはなりません。それどころか、音楽の歴史上、普通の人には信じられないような天才が数多く存在します。例えば、モーツァルトは生涯で22のオペラ、49の交響曲、40以上のドイツ舞曲、26の弦楽四重奏曲、15のミサ曲、9つの賛美歌、130以上の賛美歌などを作曲しました。オペラや交響曲の音符の数を数えてみると、その数は 3,000 を下回らないことがわかります。実際には、作曲家は36歳までしか生きなかった。 『三国志』の曹植の伝記には、「10歳を過ぎたころには、詩、随筆、散文など数十万字を暗唱することができた」とある。このような才能があれば、3000曲を歌うことも不可能ではないだろう。もちろん、曹植はこれら 3000 曲のすべてに満足したわけではないでしょう。そのため、契約では「そのうち 42 曲」だけを選択しました。 では、曹植は歌詞のある中国仏教音楽の唯一の創始者と言えるのでしょうか? 残念ながらそうではありません。なぜなら陳思王曹志以前にも、残北が存在していたと思われるからです。理論的に言えば、僧伽になった後は必ず仏を崇拝する儀式を行わなければならず、また仏を崇拝する儀式を行った後は必ず賛美の言葉を唱えなければなりません。後漢から三国時代にかけて、曹植を除いて、他の初期の仏教音楽の作者は基本的に外国人でした。例えば、芝謙は月氏、康僧慧は康居、石里密多羅は西域の人、芝丹月も月氏でした。彼らが作った仏教の詠唱には、インドと西洋の文化の痕跡が残っていなかったはずがない。曹植が作った仏教音楽もインドの仏教音楽を元に作られたものです。 このように考えると、曹植の貢献が理解できるようです。「七段で詩を作った」と言われるこの有能な学者は、3世紀初頭に「音の紆余曲折」に似た一種の楽譜を使用したり作ったりし、「音節を真似て」、聞いた「天上の音楽」、つまりインドの仏教の詠唱を大量に録音しました。彼は「後世の手本となる文章を書き、音楽を作曲した」ほか、中国仏教の初期の時代にインドから仏教音楽を広めた。そして「ここからサンスクリット語の音が世界に現れ始めた」。 |
<<: 古代人は占いに何を頼りにしていたのでしょうか?占いは本当に未来を予測できるのでしょうか?
推薦する
元代胡思惟著『陰氏正要』全文:第2巻:食物の反対語
『陰氏正瑶』は、元代に胡思惟によって書かれ、元代天暦3年(1330年)に完成しました。全3巻から構成...
連江最大の古墳の考古学調査が1か月間続くも、墓の所有者は謎のまま
少し前、丹陽鎮東平村宝林寺の裏山で、県内最大の古墳が発見された。地元の人によると、唐代の皇后の墓だと...
『紅楼夢』では、李夫人の他に、宝玉の周りでもっと権力を持っている人は誰ですか?
賈宝玉は、有名な中国の古典『紅楼夢』の男性主人公です。今日は、Interesting History...
朱熹の『易経本意』は占いに使われるのでしょうか?
朱熹の『易経本意』は占いに使われたのか?これは多くの読者が知りたい疑問です。次の『興史』編集者が詳し...
ウイグル人の習慣と習慣 ウイグル人の葬儀習慣の紹介
ウイグル族の葬儀は壮大かつ厳粛な儀式です。ウイグル族がイスラム教に改宗した後、葬儀はイスラムの儀式に...
曹操は後継者選びに迷った。なぜ曹魏の王族は関与しなかったのか?
かつて曹操は後継者選びに迷い、一部の人々がどちらか一方に味方する事態を引き起こした。この問題で曹魏一...
学者と庶民の違い:魏、晋、そして後の南朝を悩ませた最大の政治問題
漢王朝は推薦制度によって官僚を選出しましたが、これは後に名家によって代々官僚が任命される制度に発展し...
唐仙祖の「友人は私を哀れみ、黄山と白月への旅を勧めなかった」:著者は金持ちや権力者に気に入られようとはしなかった
唐仙祖(1550年9月24日 - 1616年7月29日)は、江西省臨川出身で、字は易人、号は海若、若...
政治と経済が発展するにつれて、朱元璋は社会救済に対してどのような態度をとったのでしょうか。
政治と経済の発展に伴い、明代の社会救済事業は大きく進歩しました。公的救援機関はより充実し、民間の社会...
太平広記・第78巻・錬金術師・毛安道の具体的な内容は何ですか?どう理解すればいいですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
朱元璋は遺言書『黄明祖訓』の中で「征服されなかった国」としてどこを挙げているでしょうか?
明王朝は古代我が国において比較的強力な王朝でした。『鄭和の西航』と『万国朝貢』はどちらもこの王朝時代...
『紅楼夢』で、林如海が黛玉を北京に呼び寄せ、賈邸に住まわせた目的は何だったのでしょうか?
『紅楼夢』では、林黛玉の運命は多くの制約を受けていましたが、彼女は家族の富の循環において重要な役割を...
「ヤマウズラの空 残った煙を夜風に吹き飛ばせ」の内容は何ですか?詩「ヤマウズラの空・残った煙を夜風に吹き抜けて」の鑑賞
本日は、Interesting History の編集者が「Partridge Sky: 残った煙を...
唐の景宗皇帝、李占はそれほど高齢ではなかったにもかかわらず、なぜ放蕩皇帝のリストのトップに挙げられたのでしょうか?
私たちの印象では、皇帝は常に国事に忙しいという印象を受けます。特に清朝の皇帝は、非常に厳格な規則を遵...
「川の伝説:湖の上で」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
川の伝説:湖の上で文廷雲(唐代)湖の上。のんびりとした表情。雨がざわめいている。燕浦花橋までの道は長...