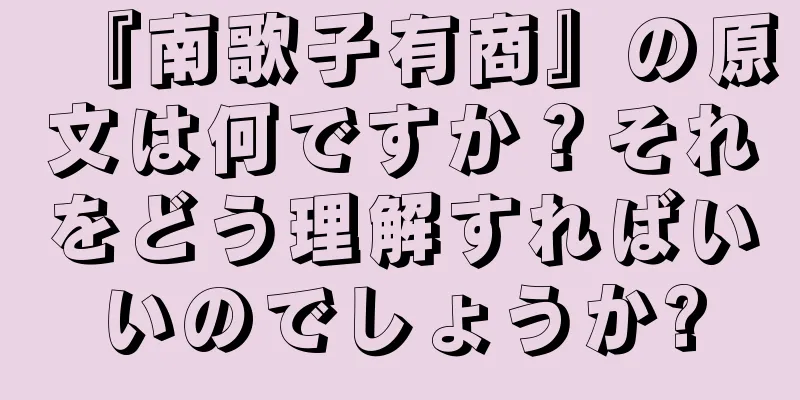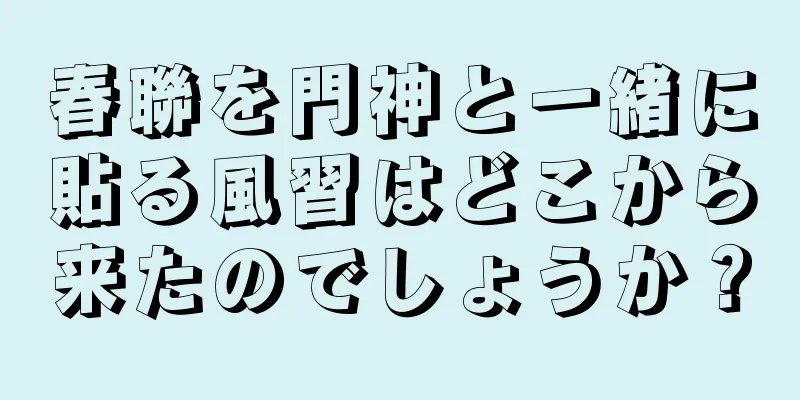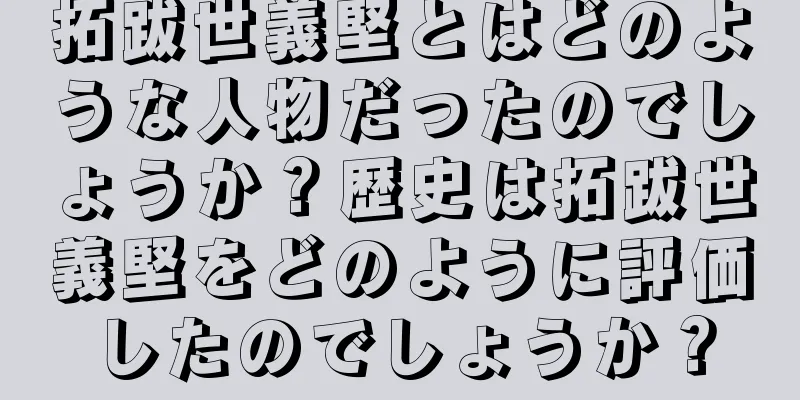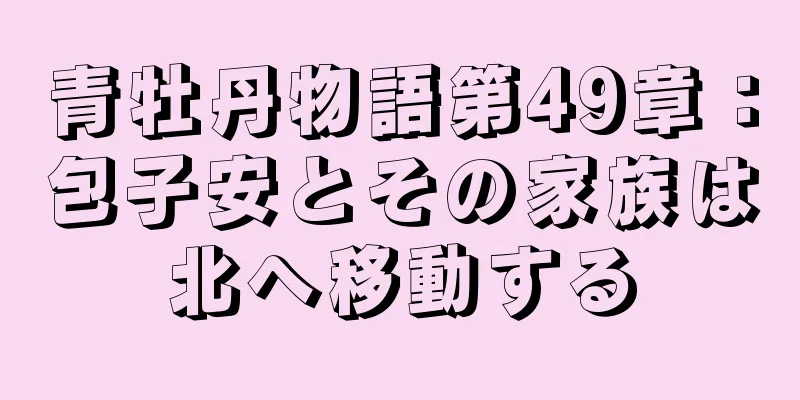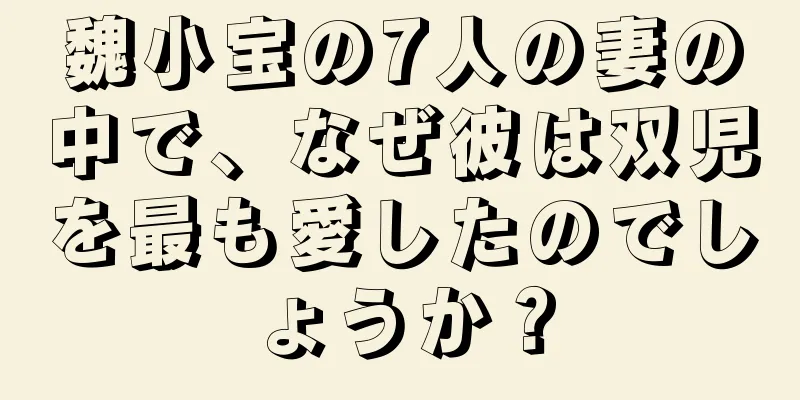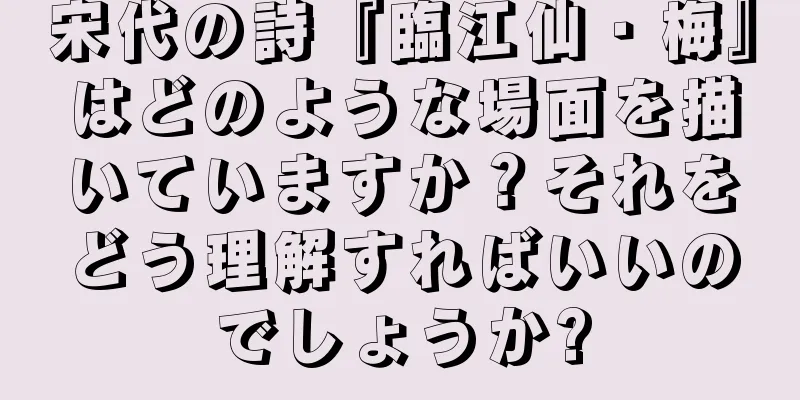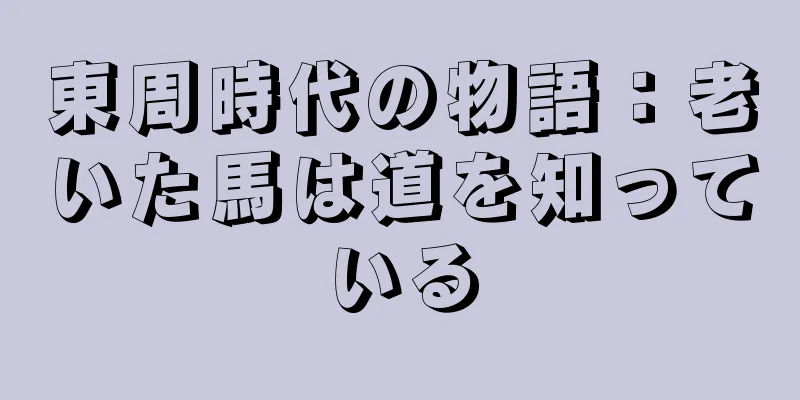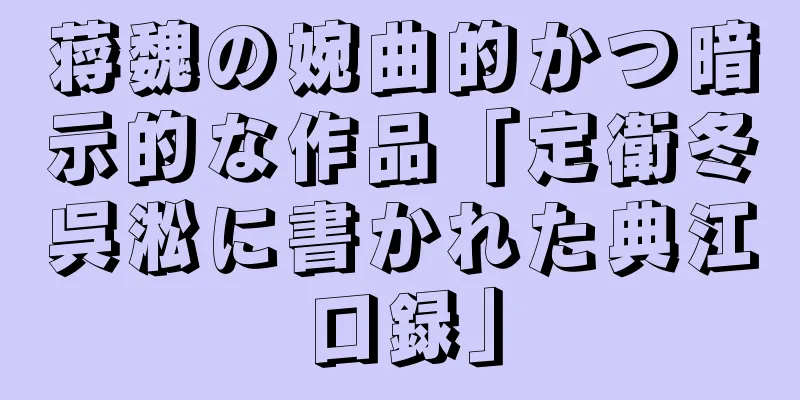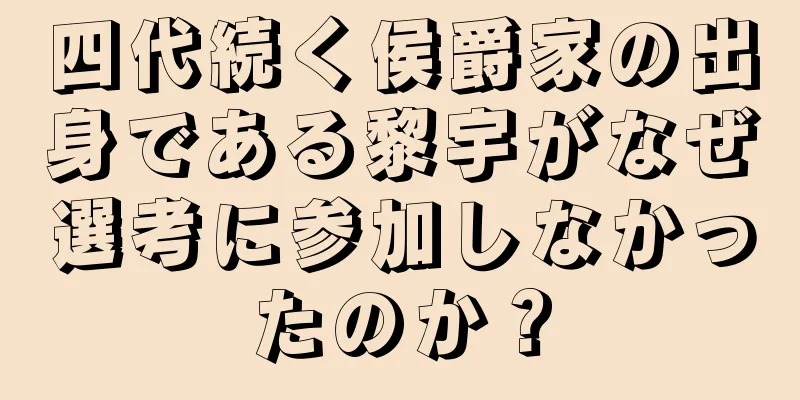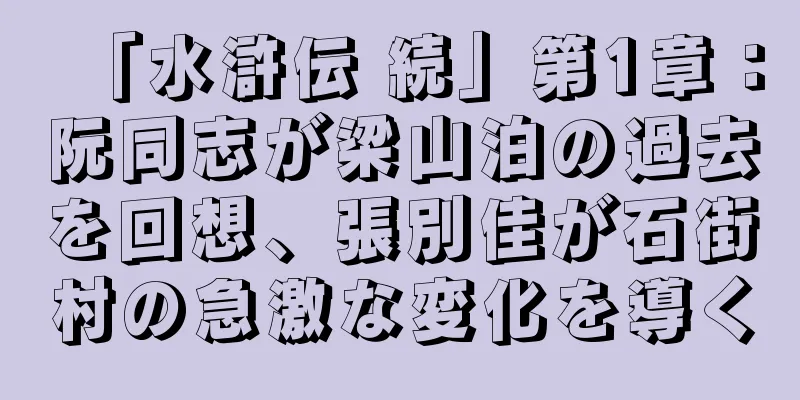「一流の学者」という用語の公式な定義を持ち始めたのはどの王朝ですか?
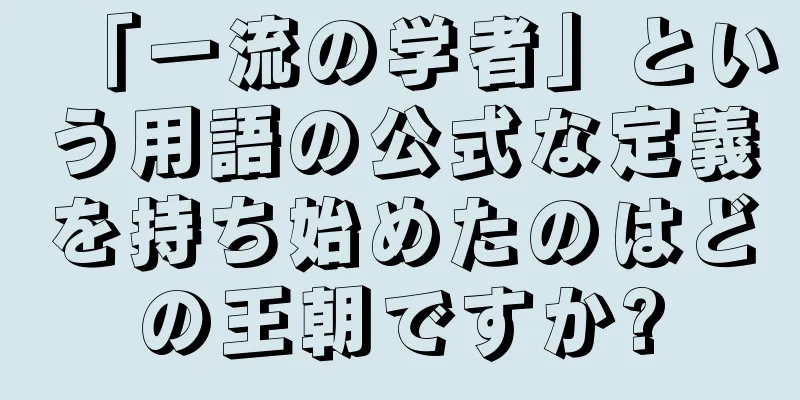
|
『四庫全書』に収録されている正史を調べてみると、「一流の学者」という用語の最も古い定義も『晋史』にあることが分かりました。巻51には、成安4年、皇帝が宰相に勅を出し、「一回の試験で二人の第一学者を選ぶのはよくない。次の科挙では詩文、古典、時事の科目で一人の第一学者を選ぶ。明経や法律などの科目もあるが、他の科目と同様に扱う。」と言った。そこで、科挙を同じ日に行い、それぞれが自分の専門分野で試験を行うことが決定された。古典と散文は依然として等級に分けられており、1位は最高得点者、2位は古典と解釈の最優秀者であり、古典と散文の2位と同じ優遇措置が与えられます。残りの人々は二つのカテゴリーに分けられ、中流階級と下層階級は詩と散文のそれより下に位置していた。いわゆる「勅旨」は天皇の布告です。正史「選帝侯録」に記録されているので、根拠があるはずです。秦慧天は『五礼全考』第175巻にこのテキストを書き写しており、関係学者の注目を集めていることが分かります。 晋の科挙制度は非常に特殊で、進士試験ではあったものの、ほとんどの場合、治府進士と靖易進士の2種類に分かれていました。ある時期に、もう一つの種類、寇倫進士が追加されました。ここでは、一流学者の定義が明確です。今後は、詩と散文の全国試験で1位になった人が一流学者となりますが、それ以前は「1つの試験で2人の一流学者」、つまり、古典で1位になった人と詩と散文で1位になった人が両方とも一流学者でした。これは、「荘園」という用語に関して私たちが目にした中で最も古く、最も信頼できる法的拘束力のある声明です。 「成安」は晋の張宗皇帝の年号である。4年目は1199年で、進士試験が設立されてから594年後である。もちろん、ここでの定義は単にトップクラスの学者というだけなので、不十分であるように思われます。 『金史』は元人によって編纂されたが、宋洪の『宋墨記文』第2巻には、すでに金人の「荘元」などの定義が記録されている。 金族の科挙は、まず各州の郡で行われた。詩文科の者は1日かけて論文と政策を書かなければならなかったが、古典科の者は3日かけて論文と政策を書かなければならなかった。この試験は「郡試」と呼ばれ、郡知事が試験官を務めた。予備試験を受験する者のうち、雑則違反を犯した者のみを退学とする。リストの一番上は「湘源」または「桀源」と呼ばれます。翌年の春、試験は3つのルートに分かれ、河の北から女真族まではすべて燕へ、関西から河の東から雲中へ、河の南から汴へ向かった。これを「省試験」と呼んだ。試験は詩、散文、随筆、時事政策などから構成されています。古典の解釈が5問、政策が3問、随筆が1問、一般原則の解釈が1問出題され、2名中1名が選抜されます。リストの一番上は「Fu Yuan」と呼ばれます。秋の終わりには、全国から受験者が集まり、「合同試験」と呼ばれる宴会が開かれます。6人の中から1人が選ばれ、最優秀の受験者は「致頭」または「荘園」と呼ばれます。上位カテゴリ、中位カテゴリ、下位カテゴリの 3 つのカテゴリに分かれています。宋代高宗の建延三年(1129年)、洪昊は慧有閣の司役、礼相代理として金に派遣され、15年間拘留された後、帰国した。彼は金代の関連法令を読んでいたはずなので、この記録は捏造ではないはずだ。これは、金人がすでに「荘元」「項元」「結元」「扶元」「致頭」「項氏」「扶氏」「会氏」という称号を明確に定義していたことを示しています。金人による定義の証拠は、南宋の宇文茂昭の『大金史』にも見ることができます。天徽科挙第35巻には次のように記されている。 科挙には神州科挙、平州科挙、振定科挙などがある。太宗の天徽10年、国は平和で、太宗は契丹のような制度を設ける勅令を出し、郷、県、省レベルで3年ごとに3回の試験を設けることを定めた。科挙のたびに、受験者はまず各州の郡を訪ねて試験を受ける。詩、随筆、政策論文の試験が 1 日、古典と政策論文の試験が 3 日の場合、その試験は「州試験」と呼ばれ、郡の行政官が試験官を務める。当時、有能な学者が県や郡に行くことを望まない場合は、何の調査もされずに解雇された。試験を受けることを希望する者は、軽微な違反を犯した場合のみ退学となる。リストの一番上は「湘源」または「桀源」と呼ばれます。翌年の春、試験は3つのルートに分かれて行われました。黄河の北から女真までは全員燕へ、関西から黄河の東までは雲中へ、黄河の南からは汴へ行きました。これを「省試験」と呼びました。試験は、詩、散文、エッセイ、時事問題に関する政策から構成されます。試験は、政策 3 つ、エッセイ 1 つ、一般理論 1 つの計 5 つのパートから構成されます。 2人が1つを選ぶたびに、一番上のものは「Fu Yuan」と呼ばれます。秋の終わりに、全国から候補者が集まり、「結師」と呼ばれる宴会が開かれました。6人の中から1人が選ばれ、リストのトップの人は「致頭」または「荘園」と呼ばれました。上位カテゴリ、中位カテゴリ、下位カテゴリの 3 つのカテゴリに分かれています。彼は尚嘉の位を授かり、南朝の承義郎である承徳郎に任命された。 南宋の『建延後年注』李新川(1167-1240)巻129にも同様の記録がある。「晋の科挙制度は、まず諸国の県で科挙を行い、県令を科挙官とする。これを「州科挙」という。雑多な罪を犯した者だけが罷免され、そのトップを「州勝者」と呼んだ。翌年の春、科挙は3つのルートに分かれ、黄河以北から女真までは皆燕へ、関西、何(おそらく派生語-作者)、河東は雲中へ、黄河以南は汴へ行き、いずれも勅令により選ばれた。試験は「附試」と呼ばれ、2人の中から1人を選び、トップの者は「附遠」と呼ばれた。秋には各地の受験生が集まって宴会を開き、「会試」と呼ばれ、6人の中から1人を選び、トップの者は「荘遠」と呼ばれた。彼らは3つのクラスに分けられ、トップの者は赤いローブを授与された。(原注:これは洪昊の『宋墨記文』に基づくもので、注:張棣の記録とは異なり、現在はわずかに削除されています。)いわゆる「張棣記録」は『正龙世事記』を指すはずであり、削除され改訂されたテキストは、もちろん彼が信頼できると信じていたものである。 これらの記録は比較的一貫しているが、いずれも『晋史選記』について説明していない。 翌年、受験者は「合同試験」と呼ばれる試験を受けるために首都に連れて行かれました。試験に合格した者は皇帝自ら宮中で審査を受ける。これを「朝廷試験」または「宮廷試験」と呼ぶ。ランキングは1位、2位、3位に分かれています。第一級には荘元、邦厳、譚華の三人だけが壬氏という称号を授けられ、第二級には壬氏という称号を授けられた者が多数おり、第三級には童壬氏という称号を授けられた者が多数いる。 1番、2番、3番の名前はシステムによって決定されます。文人や官吏は一般的に、地方の試験で1位を取ったものを「結院」、都の試験で1位を取ったものを「慧院」、2位または3位の試験で1位を取ったものを「川禄」とみなしていた。科挙の成績上位者は編纂官に、2位と3位は編纂官に任じられ、2位と3位で秀吉に選ばれた者は皆翰林官に任じられ、その他の者は集氏、于氏、朱氏、中書、興人、平氏、太昌、国子博士に任じられ、あるいは県検事、県知事、県知事などの官吏に任じられた。 (同上)ここでは、「Bangyan」、「Tanhua」、「Huishi」、「Dianshi」、「Jieyuan」、「Huaiyuan」、「Chuanlu」なども定義されています。 『清代史草稿』にも定義があり、基本的には明代から継承されているため、明代と清代の科挙制度は基本的に同じです。 「選抜III」の冒頭にはこう書かれている。「清代の学者を選抜する科目は、明の制度にならい、8部構成の論文式である。問題は『四書五経』の易、蜀、史、春秋、歴代に基づいており、これを「知易」という。3年間の大競争で、学生は直轄地で試験を受け、「郷試」と呼ばれ、合格者は「居人」と呼ばれる。翌年、居人は首都で試験を受け、「会試」と呼ばれ、合格者は「公試」と呼ばれる。皇帝が宮中で受験者を自ら審査し、「宮廷試」と呼ばれ、一級、二級、三級に名前が分けられる。省級の試験で1位になった者は「桀院」、都級の試験で1位になった者は「慧院」、2位になった者は「川禄」と呼ばれる。いずれも明代の古い呼び名である。…1位になった者は編纂官に、2位と3位になった者は編纂官に、2位と3位になった者は書記官、朱子官、中書官、興人官、平氏官、伯氏官、推官官、支州官、直先官などの官吏に授与される。 金、明、清の政府はいずれも「一流の学者」という用語について非常に明確な定義を持っていました。晋の「郷試」や「斌院」などの用語の定義は明清のそれとは大きく異なっていたが、晋の「西院」を著した「董斌院」は実際には明清の第一学者に相当するだけであったが、晋の「荘院」という用語の意味は明清のそれと同じであった。晋は宮廷の試験を行わないこともあったが、その皇帝は他の王朝とは比べものにならないほど地方の試験を重視しており、すでに宮廷の試験に近いものであった。また、宋代には「梁安房」が何回かあったが、宮廷の検査は行われなかった。実は、今日の人々の頭の中にある「一流の学者」という概念は、基本的に明清政府の定義から来ています。ただ、他の王朝、特に唐と五代における科挙の実態を理解していない人が多いのです。彼らは、科挙の全期間を通じて、一流の学者と呼ばれる人は、明清王朝と同じように、宮廷試験の後に皇帝が「自ら選んだ」と誤解しています。 |
<<: 古代から現代までの漢民族の伝統的な祭りを包括的に振り返る
推薦する
ヘスティアはどんな神様ですか?ギリシャ神ヘスティアの紹介
古代ギリシャ神話では、ヘスティアは炉の女神であり、家の守護神であり、ギリシャの三人の処女神の一人です...
並列散文とは何ですか?並列散文はどのように発展したのでしょうか?
まだ分からないこと:平行散文とは何ですか?平行散文はどのように発展したのですか?平行散文は、平行...
宋代に金と戦った女性英雄、梁洪宇の略歴。梁洪宇はどのようにして亡くなったのでしょうか。
梁洪宇(1102-1135)は安徽省池州の出身で、江蘇省淮安で生まれました。彼女は宋代に金と戦った有...
なぜ夏雪怡は何紅瑶ではなく文怡に恋をしたのでしょうか?
まず、何紅瑶の名前を見てみましょう。何紅瑶の名前は、江逵の詩「揚州閑静」から来ています。橋のそばの赤...
後南祭はどの少数民族のお祭りですか?また、その伝統的な風習は何ですか?
プーラン族の后南祭はいつですか?プーラン族のホウナン祭は「サンカン祭」や「ソンカン祭」とも呼ばれてい...
鮑嗣の生涯についてはどのような神話や伝説がありますか?
鮑嗣は西周時代の鮑の出身で、周の有王の二番目の王妃であり、深く愛されていました。歴史記録によると、包...
聯句の最初の行「向かい合って麺を食べる」は蘇暁梅が考え出したものですが、僧侶が考えた2番目の行は何でしょうか?
あなたは本当に蘇暁梅を知っていますか?Interesting Historyの編集者が詳細な関連コン...
玄昭帝の苻堅とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は苻堅をどのように評価しているのでしょうか?
前秦の玄昭帝、苻堅(338年 - 385年10月16日)は、雅号を雍固、また文有といい、劍頭とも呼ば...
宋代の詩「董香閣・雪雲散」を鑑賞するにあたり、この詩をどのように理解すべきでしょうか?
董仙歌:雪雲散霧消、宋代李元英、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介を持ってきますので、見てみましょう...
『鏡の中の花』の主人公は誰ですか?キャラクター設定はどうですか?
『鏡花』は清代の学者、李如真が書いた長編小説で、全100章からなり、『西遊記』『冊封』『唐人奇譚』な...
「正直な政務官として3年間、銀貨10万枚」!清朝の知事はなぜそんなに多くの収入を得たのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、清朝の知事がなぜそんなに多くの収入を得たの...
『水滸伝』の愛された放蕩息子、燕青はどんな不名誉なことをしたのでしょうか?
放蕩者の延卿は呂俊義に従って涼山に赴き、天岡の中で36位にランクされました。これに関して皆さんはどう...
司馬遷の簡単な紹介:歴史家司馬遷の歴史における真の姿
人物:司馬遷(紀元前135年 - 紀元前90年)は、字を子昌といい、西漢時代の夏陽(現在の陝西省漢城...
厳吉道の「遠人を想う 晩秋の紅葉と黄色い花」:この詩の最も素晴らしいところは「涙」の描写である。
顔継道(1038年5月29日 - 1110年)は北宋時代の有名な詩人である。名は書源、号は蕭山。福州...
『別れの顔世源』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
ヤン・シユアンを送る春風がヘルー市3のオール2に吹き、水の国の春4は寒く5、その後曇りや晴れ6。霧雨...