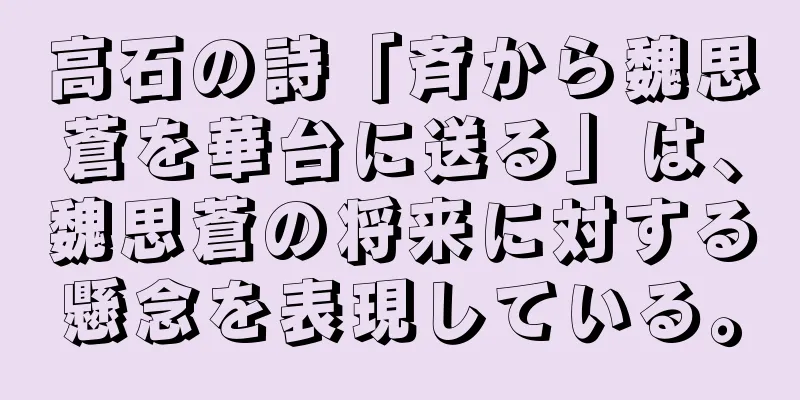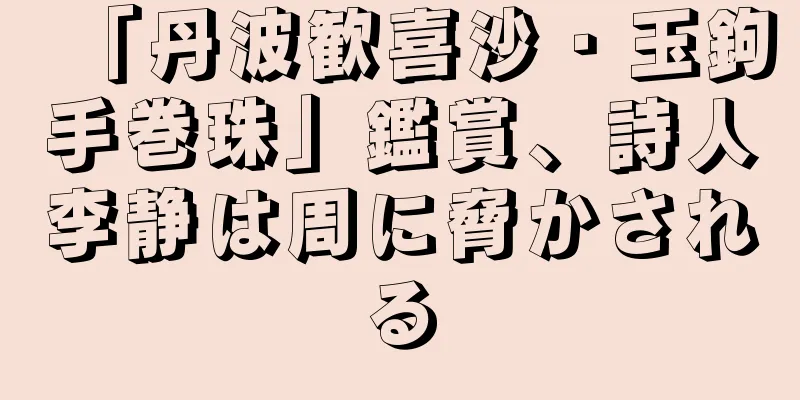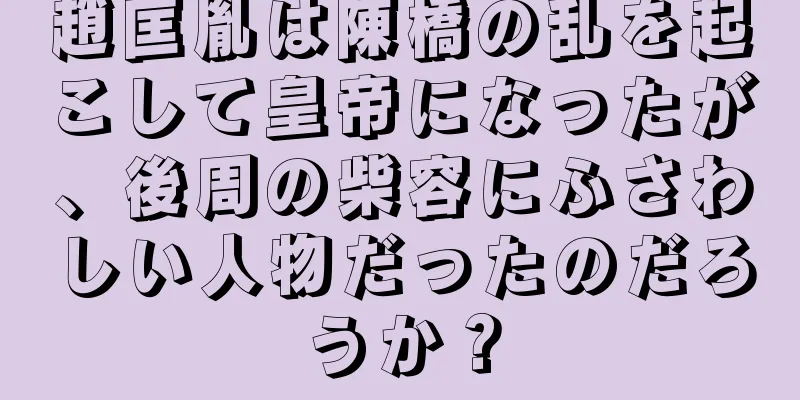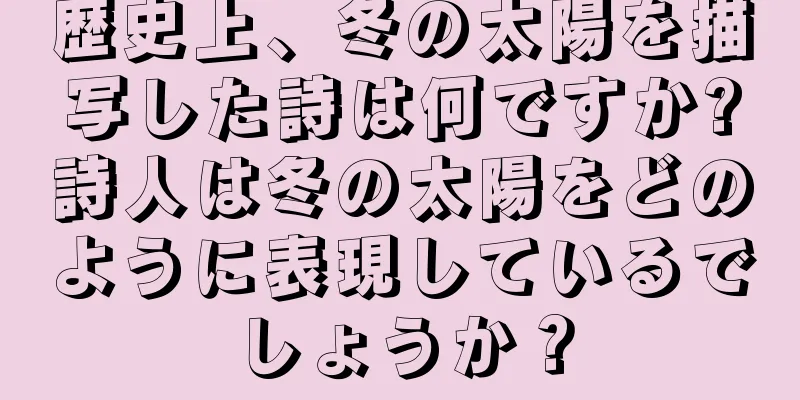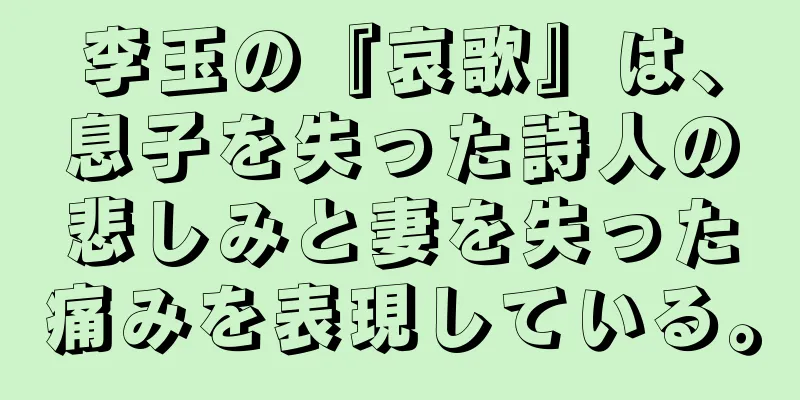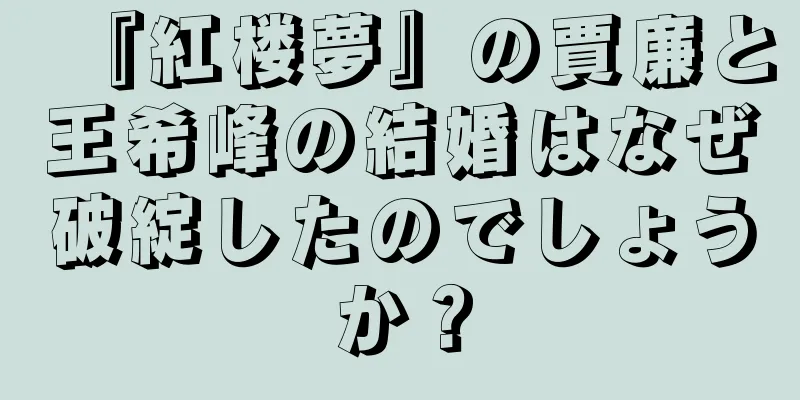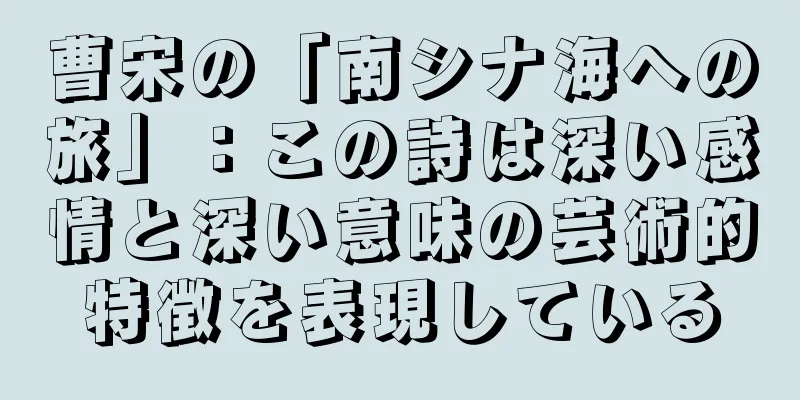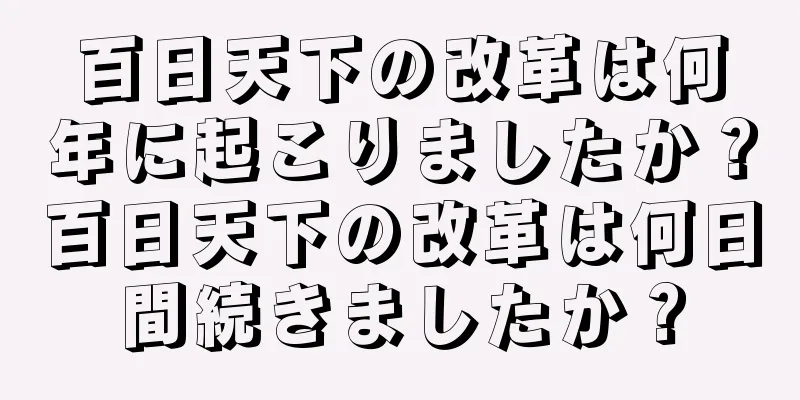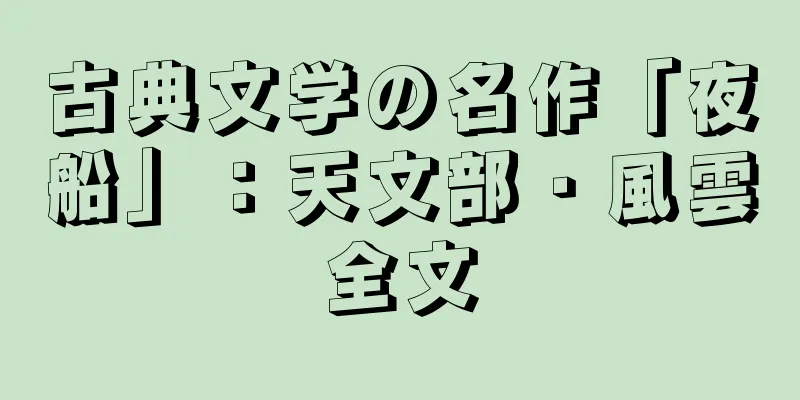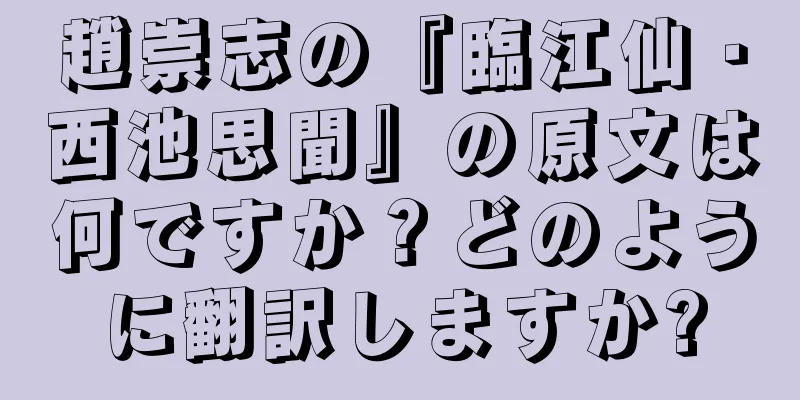第二次世界大戦中の日本軍における大佐の階級は何でしたか?
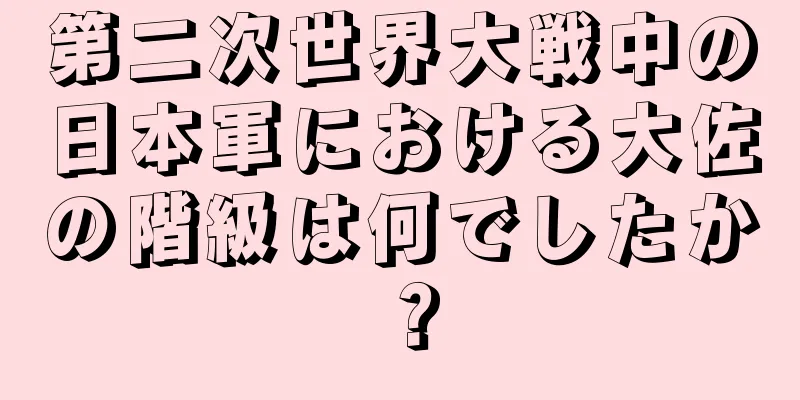
|
大佐は日本の軍隊の階級です。第二次世界大戦中、日本の軍の将校制度は、大将、中尉、中尉、そしてさらに少佐、中尉、少佐に分かれた3段階9等級制を採用していました。このうち大佐の階級は大佐と同等かそれ以上である。 第二次世界大戦後、日本は1950年に軍の再建を開始し、1954年までに陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊を設立しました。軍隊の階級は幹部と軍曹の2つのカテゴリーに分かれています。幹部は依然として将軍、中尉、中尉の3階級9階級である。 1945年の第二次世界大戦終結前、日本軍の階級は大将、少将、中尉、准尉、下士官、兵の6階級16段階に分かれていた。いわゆる下士官は准尉であり、下士官は軍曹である。 16階級の順位は、日本語の称号によれば、大将、中将、少将、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、准尉(准尉)、曹長(曹長)、伍長(伍長)、一等兵、一等兵、二等兵の順である。 「大佐」という言葉は日本語から翻訳されたもので、大佐に相当するものとしてよく使われます。中国では大佐を「連隊長」と呼ぶのが慣例だが、日本軍の実情はもっと複雑である。 日本軍において中佐が就くことができる役職には、連隊長、旅団参謀長、師団参謀長などがある。師団参謀長は主に大佐であるが、所属系統が異なり師団長(中将)の傍らに勤務するため、実質的な権限は少将である旅団長よりも大きい。 全員が大佐であっても、連隊長、旅団参謀長、師団参謀長の階級は異なる場合があります。 1937年(昭和12年)に芙蓉書房から出版された外山宗編著『陸海軍将官人事概観』には、師団長(大佐)が記載されており、日本軍において師団長は既に将官とみなされていたことがわかる。 日本軍には准将や大佐という役職は存在しない。厳密に区別する必要がある場合は、連隊長を「大佐」、旅団参謀長を「大佐」、師団参謀長を「准将」とするのが適切であろう。 |
<<: 清朝宮廷劇の大臣たちはなぜひざまずくときに腕を二度振るのでしょうか?
>>: 楚国の簡単な歴史: 楚の人々はどこから来たのでしょうか?楚国の起源は何ですか?
推薦する
遼・金・元の衣装:元代の女性の衣装
元朝の貴族の女性は一般的に毛皮の帽子とクロテンの毛皮のローブを着ていました。このタイプのローブは比較...
『清平悦:禁庭の春の日』を鑑賞するには?著者は誰ですか?
清平月:禁じられた庭の春の日李白(唐)春の日の禁じられた中庭では、オリオールズは新しく刺繍された羽で...
ジゴン伝記第215章:魔法の武器はモンスターを捕まえることに成功し、善悪を区別し、ジゴンは弟子を救う
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
張暁祥の「博算子・雪月至上」:この詩には過去と現在の無限の感情が込められている
張孝祥(1132-1170)は、名を安国、通称を玉虎居士といい、溧陽呉江(現在の安徽省河県呉江鎮)の...
海上輸送も穀物輸送以外にも非常に成功していました。なぜ道光帝は途中でそれを放棄したのでしょうか?
道光帝は生涯を通じて倹約家として有名でした。少々倹約しすぎたところもありましたが、皇帝としては非常に...
西遊記の白龍はどれくらい有能ですか?なぜ黄色いローブを着た怪物と戦おうとするのですか?
実は、この白い小さな龍は、西海の龍王であるアオ・ルン陛下の第三王子だったのです。今日は、おもしろ歴史...
『紅楼夢』で青文は死ぬ前に宝玉に何と言いましたか?それはどういう意味ですか?
青文の悲劇的な運命は確かに悲しいものです。これについて話すとき、あなたは何を思い浮かべますか?青文に...
「宴会のザクロへの頌歌」の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
宴会でのザクロの詩孔紹安(唐代)庭の木々の根が動かされ、漢の役人を追い払ってしまったのは残念だ。遅す...
金鉄線GE窯とは?金線・鉄線 Ge 窯の特徴をご紹介!
金鉄線窯とは?金鉄線窯の特徴をご紹介します!Interesting History編集部が詳しい記事...
陸志の「黄金経典:邯鄲路の夢」:歌全体に明確な文脈があり、文章は上から下までつながっている
陸智(1242-1314)、号は楚道、別名は神老、号は叔寨、浩翁。元代の卓君(現在の河北省卓県)出身...
魏英武の有名な詩の一節を鑑賞する:娘に会いに帰ってきたとき、涙が頬を伝った
魏英武(生没年不詳)、号は易博、荊昭県都陵(現在の陝西省西安市)の出身。魏蘇州、魏左司、魏江州として...
三勇五勇士第69章:杜勇が妾に情事を教え、秦昌が謝罪し、侍女が死亡
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
耿延は何人を殺したのですか?耿延が市内で300人を虐殺したというのは本当ですか?
東漢六大家とは、東漢初期に劉秀が東漢を再興するのを助けた鄧毓家、耿延家、梁通家、竇栄家、馬遠家、殷家...
暑さの終わり:秋の第二節気。暑い夏の終わりを意味します。
今日は2022年8月23日です。今日の11時16分に、二十四節気の終秋を迎えます。中秋は二十四節気の...
古代では反乱は重大な犯罪であったのに、将軍が反乱を起こしたときに抵抗する兵士が少なかったのはなぜでしょうか。
中国の5000年の歴史を通じて、王朝の交代は常に戦争と切り離せないものであった。中国の歴史の発展を見...