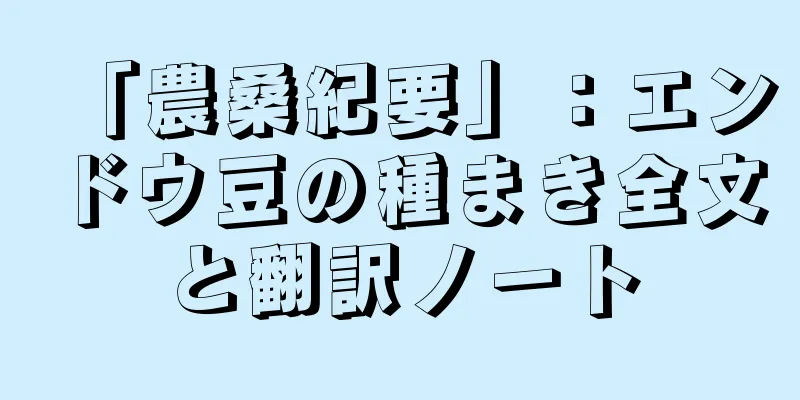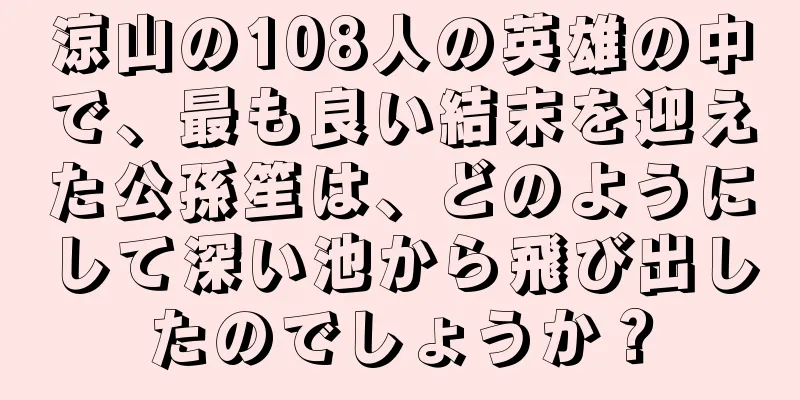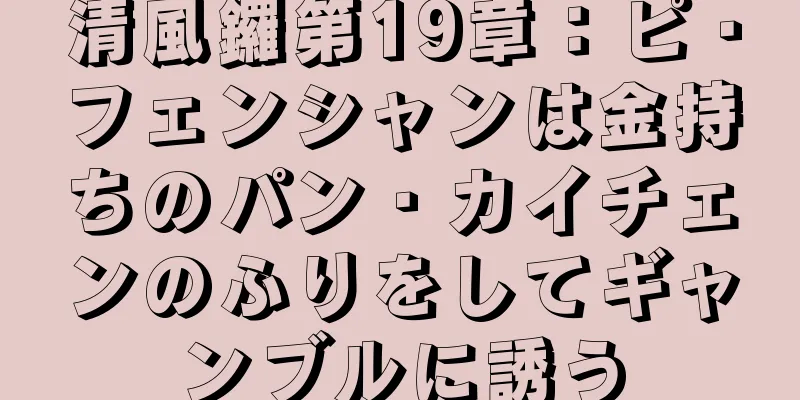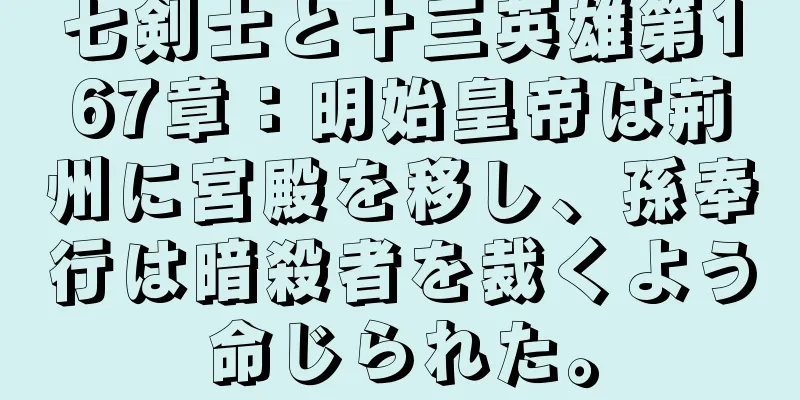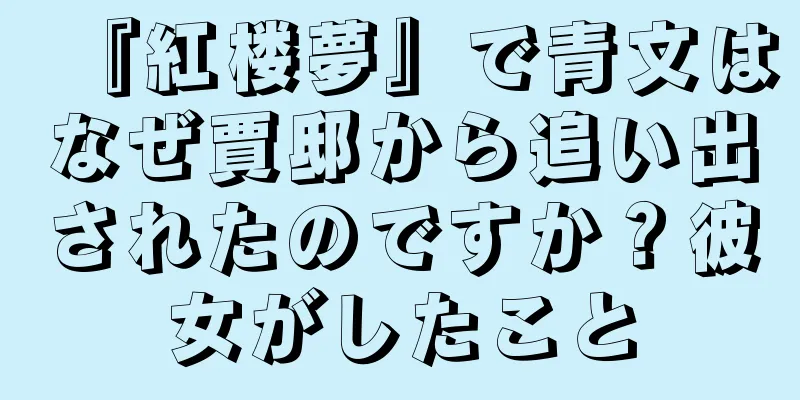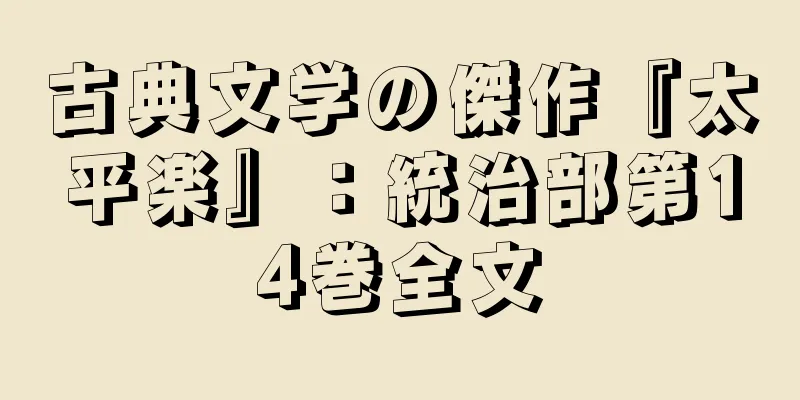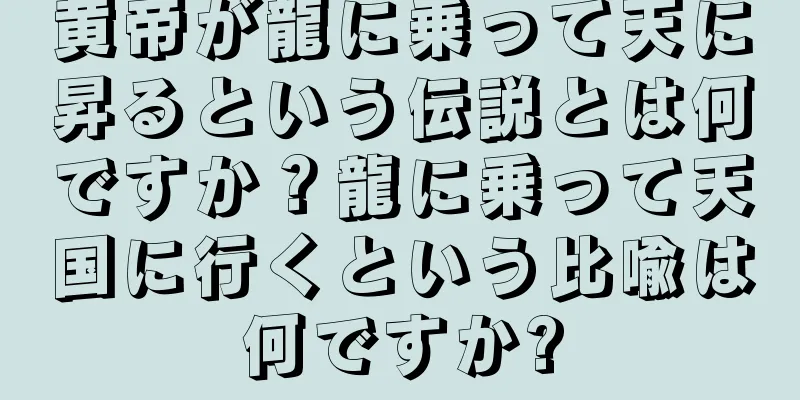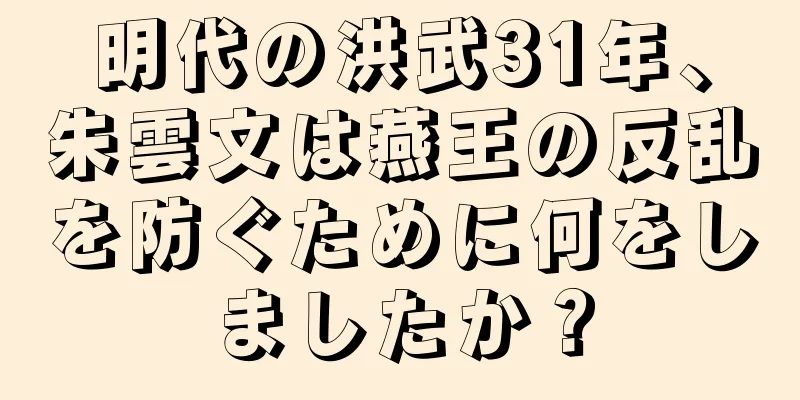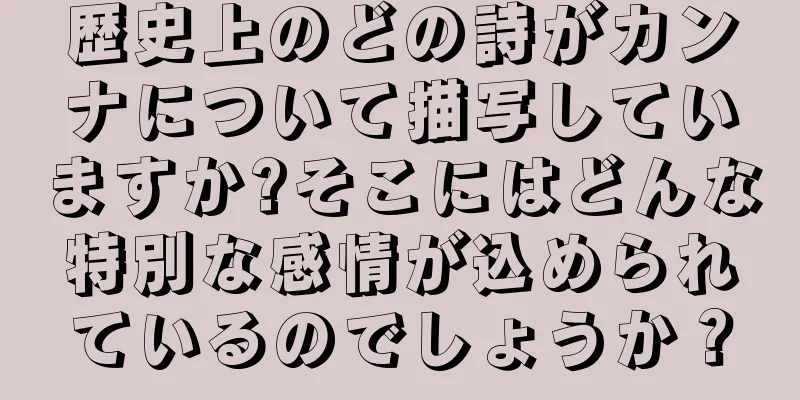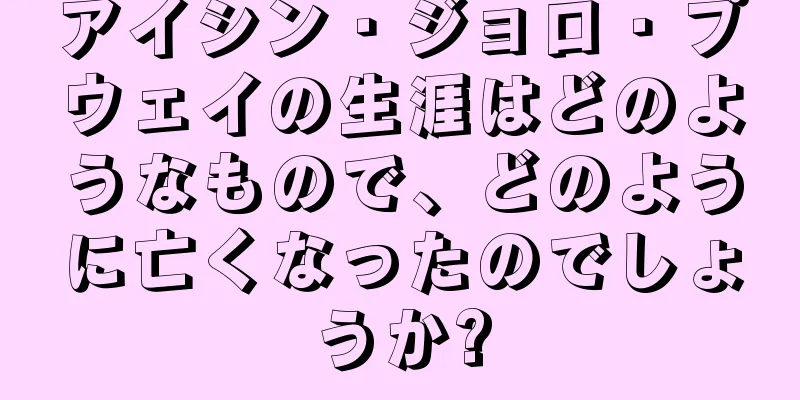羅貫中の『三国志演義』に出てくる出来事はすべて歴史的事実ですか?
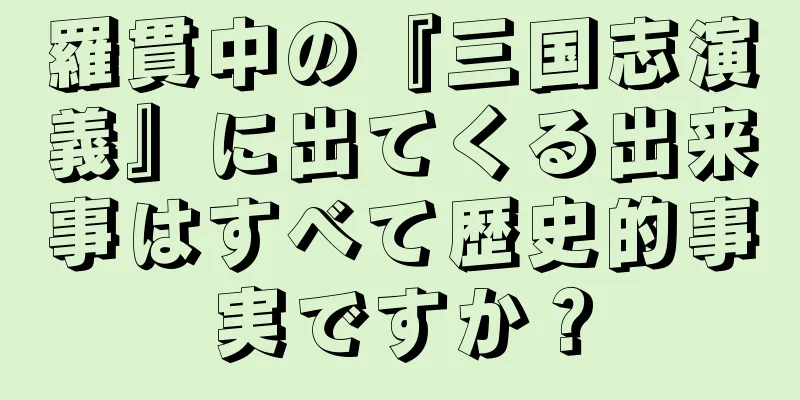
|
羅貫中は、本名を本、号を貫中といい、元代から明代初期の小説家である。彼の代表作は『三国志演義』であり、現在では四大古典の一つとして総称されている。羅貫中の父親は実業家で、羅貫中を北から南の杭州に連れてきました。もともと羅貫中の父親は息子に商売をさせたかったのですが、後に羅貫中は商売に興味がなくなったため、父親の同意を得て文人と親しくなり始めました。 1356年、羅貫中は張世成の弟子となった。石乃安と張世成は友人であったため、この時期に羅貫中は石乃安の弟子となった。 羅貫中の銅像 羅貫中が『三国志演義』を執筆していたとき、石乃安が他界したため、師匠の石乃安の遺作『水滸伝』を手掛けた。作品を完成させたとき、羅貫中はすでに60代の男性だった。本を出版するために、杭州から福建省の建陽まで行ったが、羅貫中の作品は出版されなかった。羅貫中は『三国志演義』や史乃安の『水滸伝』の翻案のほか、『隋唐史』、『五代史』、『三隋討魔伝』なども著した。しかし、『三国志演義』は羅貫中の作品の中で最も完成度が高い。黄巾の乱から始まり、最終的には西晋の統一まで、羅貫中は三国時代の複雑な政治と軍事の闘争をマクロな視点から描いている。 羅貫中の歴史記録には、彼が何年に亡くなったかは明確に記されていません。1385年から1388年の間、羅貫中に関するニュースはなかったと推定されています。また、当初は羅貫中の祖先がどこなのかについても論争がありました。しかし、後に羅貫中の家系図が山西省太原にあることが発見されました。そのため、学者たちは羅貫中が山西省太原の出身であることを確認しました。羅貫中は各地に多くの足跡を残しているが、歴史書に記録されているものは非常に少ないため、私たちは羅貫中の発掘に引き続き尽力しなければならない。 羅貫中の三国志演義 羅貫中の『三国志演義』は、中国初の章立ての長編歴史ロマンス小説であり、呉、蜀、魏の三つの政治グループ間の戦争に焦点を当てています。黄巾の乱、董卓の乱、軍閥間の覇権争いから三国志、そして最後に三国志が西晋に戻るまで、羅貫中は兵法三十六計をこの小さな本にすべて書き記し、登場人物の行動のほとんどは歴史の原型の中に見出すことができますが、これらの人物に対する彼自身の好き嫌いも加えているため、非常に読みやすいです。しかし、三国志の本当の歴史を理解するために、三国志演義はすべて歴史的事実ではなく、多くのプロットは想像と融合しているため、歴史的事実とは見なされません。 三国志演義の桃園三英雄 『三国志演義』の題材は、三国時代の歴史文書であると同時に、民間に伝わった物語でもある。三国時代は元朝末期から明朝初頭までの数千年の歴史があり、当時はまだ三国を研究・評価する人が多く、羅管仲に筆記材料を提供した。羅管仲自身も朱元璋が元朝を倒して明朝を建国した際に農民反乱に参加した。羅貫中は民衆の苦しみをよく知っていた。知識人として自らこの混乱した状況を終わらせたいと願い、『三国志演義』を著した。 羅貫中の成功は、軍事と政治の描写と人物造形にあります。羅貫中は戦争を描写するたびに、その戦争の特徴を書き出すことができました。さらに、官渡の戦い、赤壁の戦いなど、描写した環境に応じて、書いた戦略や戦術も異なっていました。また、羅貫中は登場人物の葛藤を描く際にも非常に柔軟である。人物の特徴を描く際、彼は言語、性格、行動などさまざまな側面から人物を形作る。しかし、個人的な感情から、羅貫中は好きな登場人物を神格化し、嫌いな登場人物を中傷するが、これもまたこの小説の特徴の一つである。 羅貫中はどの王朝の出身ですか? 羅貫中は、元代末期から明代初期にかけて、およそ1330年から1400年にかけて生きた人物です。羅貫中は章立て小説の創始者です。以前、ネット上で羅貫中の文化レベルについて議論したことがあります。7歳で勉強を始めたという人もいます。14歳で母親を亡くした後、父親に従って蘇州や杭州に行き、実業家になりました。しばらくして、当時の有名な学者である趙宝鋒に師事するために慈渓に行きました。1356年に出発し、張世成の弟子になりました。その後、張世成に失望した後、故郷に戻るつもりでしたが、蘇州で石乃安に会い、それ以来ずっと石乃安に同行しました。 羅貫中記念館の銅像 羅貫中は7歳から14歳まで私立学校で勉強していたと推定する人もいる。これは現代の中学生レベルに相当する。しかし、後に趙宝鋒に師事し、独学だったと考えられているため、実際の文化レベルを推定するのは難しい。しかし、古代人の文化レベルを現代人の文化レベルと比較することはできないことを理解する必要があります。なぜなら、古代には14歳、あるいは12歳でも読書家だった人がたくさんいて、彼らの経験は現代人の経験とは異なっていたからです。現在、一般に普及している『三国志演義』は、清朝時代に毛宗剛親子が編纂したバージョンですが、羅貫中の『三国志演義』は史料に基づいており、その作品には民間作家の才能と経験が反映されています。そのため、羅貫中の文化レベルは、現代の私たちの多くよりも高いと言えます。 確かに羅管中に関する歴史資料は少なすぎます。羅管中の正体については、歴史上羅管中と一致する人物が多数いるため、いまだに多くの人が議論しています。例えば、石乃安は羅管中だと考える人もいますが、石乃安は羅管中の師匠に過ぎないと言う人もいます。しかし、二人は数百年前に亡くなっているので、推測することしかできません。 『呂桂不虚編』では羅貫中はどこの出身だとされているのでしょうか? 『続呂帰布』は、羅貫中が太原出身であるとされており、世界で唯一現存するこの本は寧波の天一閣に所蔵されている。研究によると、『続呂帰布』の作者は明代初期の賈仲明で、羅貫中の前任者だった。当時、羅貫中は戯曲を3作しか書いておらず、『三国志演義』などの有名な作品はまだ完成していなかった。賈忠明は、太原出身で胡海三人としても知られる羅貫中について言及した。彼に賛同する人はほとんどいなかったが、二人は友人だった。しかし、予期せぬ出来事が起こり、二人は別々の道を歩むことになった。 羅貫中石像 羅貫中は賈仲明より年上である。二人が再会したとき、賈仲明はすでに21歳だったので、10歳年上の羅貫中は31歳であるはずである。羅貫中は1357年に張世成を離れたので、賈仲明と出会ったのは1364年である。この7年間の間にいくつかの作品を書いた可能性がある。1366年に趙宝鋒が亡くなり、羅貫中は故郷を離れて慈渓に向かった。彼の後期小説はすべて1366年から1399年の間に完成した。そのため、賈仲明が81歳で『続・呂帰布』を書き終えたとき、彼は60年以上も羅貫中に会っていなかった。羅貫中が亡くなったかどうかは定かではなかったため、彼は「行方不明」で羅貫中の生涯を終えた。逆に言えば、賈仲明がこの60年間に羅貫中に何が起こったのかを知ることは不可能だ。賈仲明が太原出身だと主張したことは、1996年に太原祁県河湾村で羅貫中の家系図と生きた遺品が発見されたことでようやく確認された。600年以上もの間推測されてきた羅貫中の故郷の謎は、ついに山西省太原であることが確認された。 羅貫中は中国史上傑出した小説家の一人ですが、当時は小説家の地位が低いとされていたため、歴史上羅貫中の生涯を知る人はほとんどいません。明清時代から、羅貫中の出生体験については絶えず論争がありました。しばらくの間、「三国志演義」は元の羅貫中によって書かれたのではないかという疑問もありました。現在、この作家は徐々にその素顔を明らかにしています。研究が深まるにつれて、私たちは羅貫中を理解するようになると信じています。 |
<<: 「建安七賢」の一人である王燦は、なぜ曹植とともに曹王とも呼ばれるのでしょうか?
>>: 有名な儒学者であり釈義家であった段玉才は、どのような重要な業績を残しましたか?
推薦する
古典文学の傑作『太平天国』:学術部第3巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
七剣十三英雄第3章:呉天宝が宜春の庭で騒ぎを起こし、李文暁が普天鈞を鞭打つ
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
古典文学の傑作『世を覚ます物語』第10巻:劉小関の男女の兄弟
「世界を目覚めさせる物語」は、中国語の短いメモを集めたものです。明代末期に馮夢龍によって編纂された。...
漢王族の縁戚である劉延はどのようにして東漢王朝を滅ぼしたのでしょうか?
漢王朝は、約405年間の統治期間を有し、周王朝を除けば最も長い封建王朝であると言えます。残念ながら、...
孔子はどのようにして項子先生から琴の演奏を学んだのでしょうか?この事件は後世にどのような啓蒙を与えるのでしょうか?
孔子(紀元前551年 - 紀元前479年)、名は丘、字は仲尼。東周の魯国鄒邑(現在の中国山東省曲阜市...
『紅楼夢』で西仁が薛宝柴を支持することを選んだのはなぜですか?理由は何ですか?
希仁は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物。金陵十二美女の2番目であり、宝玉の部屋の4人の侍女のリーダ...
光緒帝の金妃はどのようにして端康皇后になったのでしょうか?
光緒帝の金妃はどのようにして最終的に端康帝の貴妃になったのでしょうか?金妃は最終的に端康皇貴妃の称号...
なぜ太上老君は金嬌王に5つの魔法の武器を与えたのでしょうか?理由は何でしょう
『西遊記』で最も魔法の武器を持つモンスターといえば、間違いなく平頂山の金角王と銀角王でしょう。彼らは...
徐晃は有名な五大将軍の一人です。正式な歴史では彼はどのように亡くなったのでしょうか?
徐晃は三国時代の魏の将軍であり、有名な五大将軍の一人でした。このような有名な将軍の最後はどうなったの...
『紅楼夢』で怡紅と他の美女たちが主催する夜の宴会に、なぜ王希峰は出席しなかったのですか?
王希峰はなぜ一鴻組の美女たちの夜の宴会に参加しなかったのか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します...
史公の事件第221話:方世傑が黄天覇を追い払い、蔡江衛が誤って王山殿に入る
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
趙高と胡海の会話は、秦の始皇帝がどのように死んだかについて何を明らかにしていますか?
秦の始皇帝が病死したのか、趙高と胡亥の陰謀によって殺害されたのかについては、歴史上明確な結論は出てい...
なぜこれほど多くの人が劉邦のために命を捨てる覚悟があるのでしょうか?劉邦にはどのような個人的な魅力があるのでしょうか?
劉邦は偉大な人物でした。司馬遷の著作では彼はならず者として描かれていますが、帝国を築いたのはまさにそ...
『西遊記続』第11章: 後の原因はすべて以前の結果です。異端者はそれらを連れ戻し、自分の家族になります。
明代の神話小説『続西遊記』は、『西遊記』の3大続編のうちの1つです。 (他の2冊は『続西遊記』と『補...
『新説天下一篇 方正』第33章に記録されているのは誰の言葉と行為ですか?
『十朔新于』は、魏晋の逸話小説の集大成です。では、『十朔新于方正篇』第33号には、誰の言葉や行いが記...