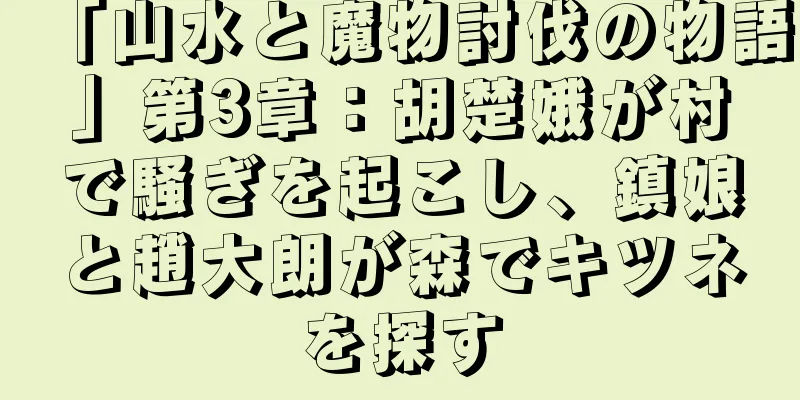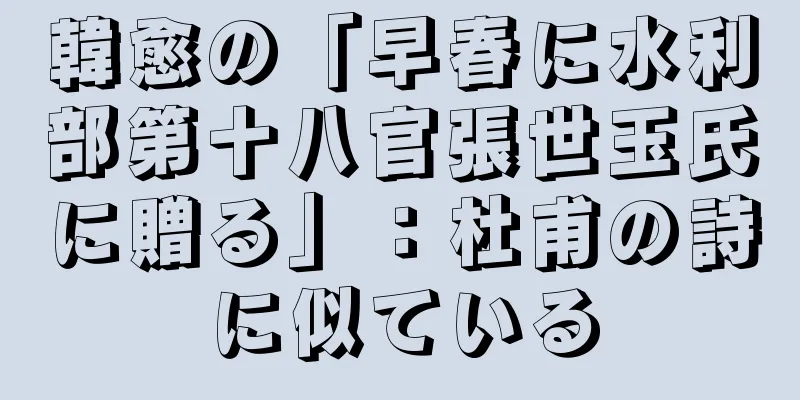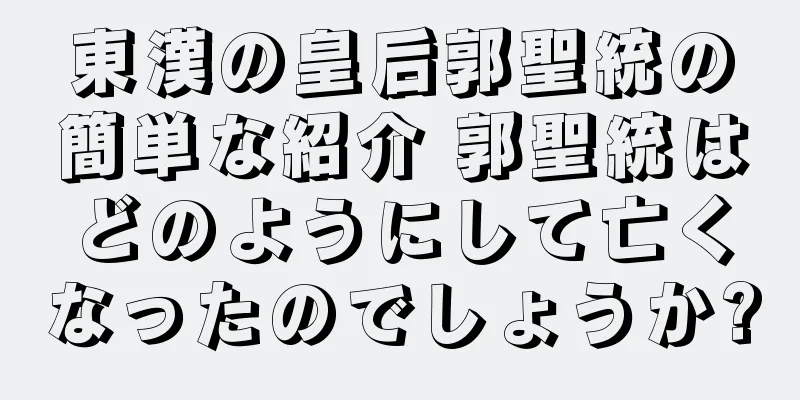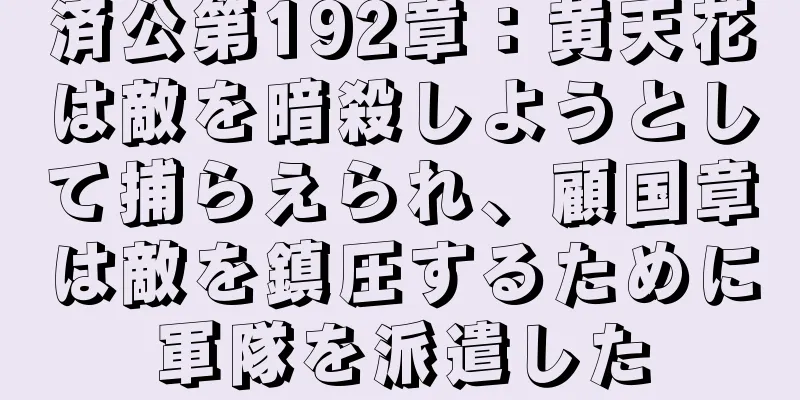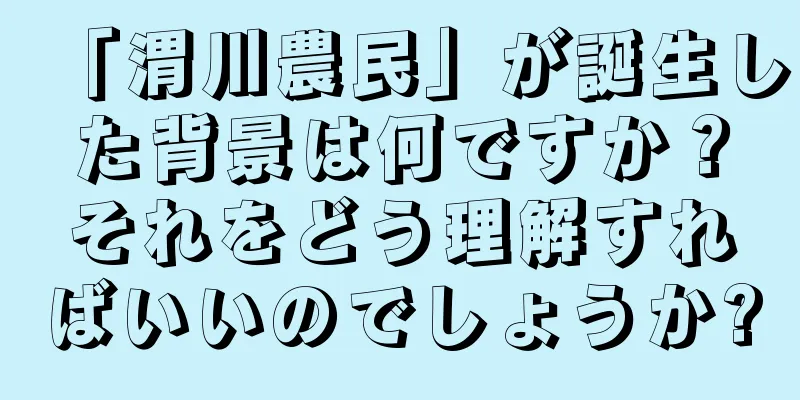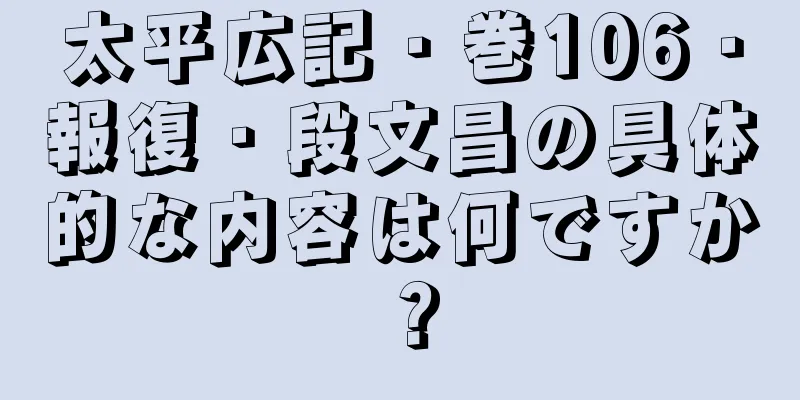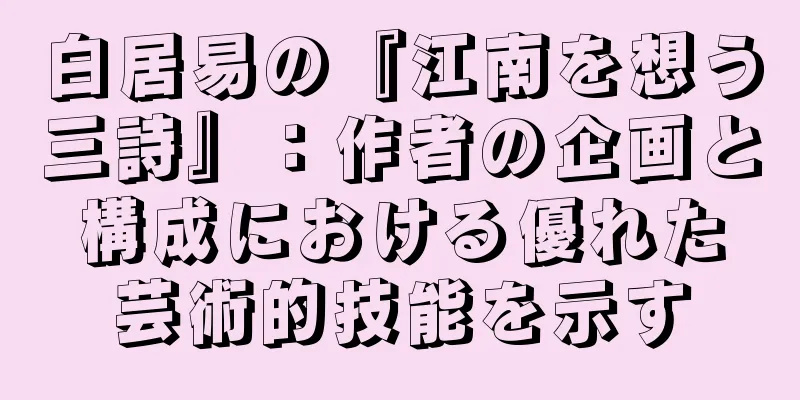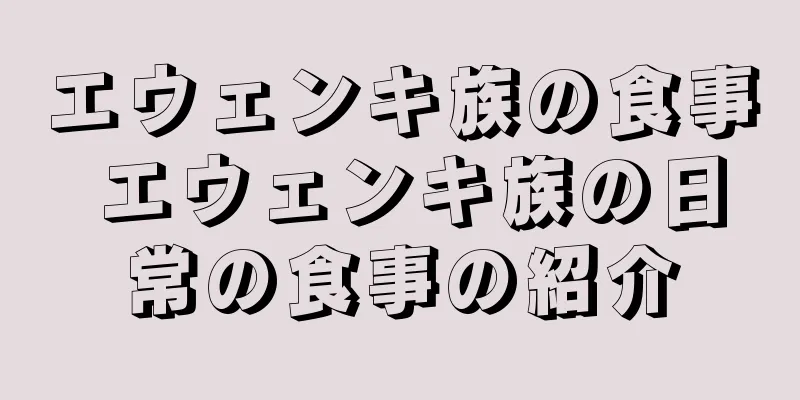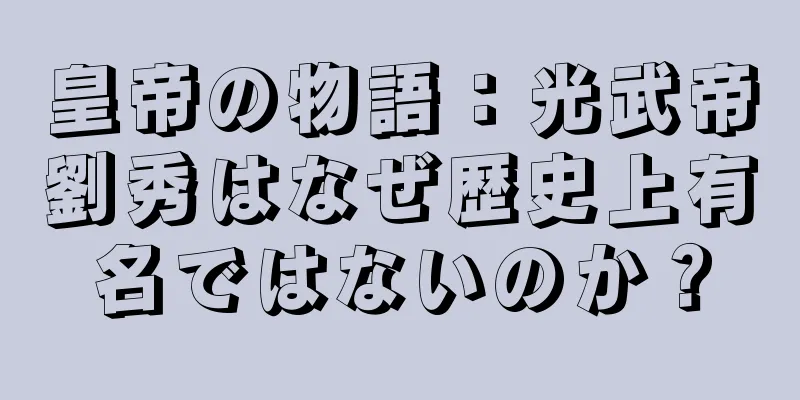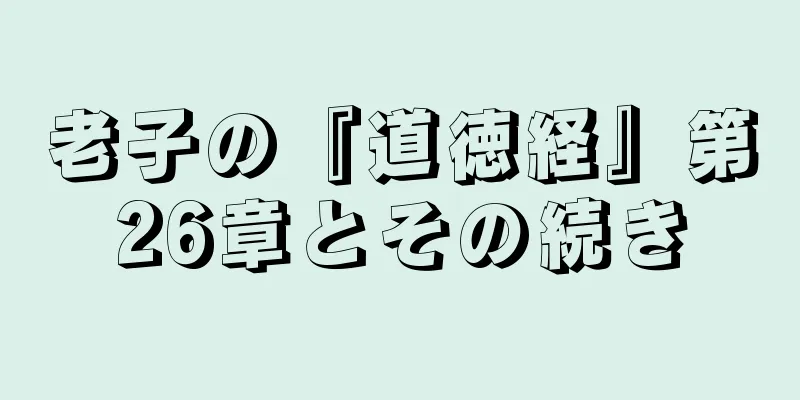「黄色い花」とは何の花のことを指しますか?未婚の女の子はなぜ「処女」と呼ばれるのでしょうか?
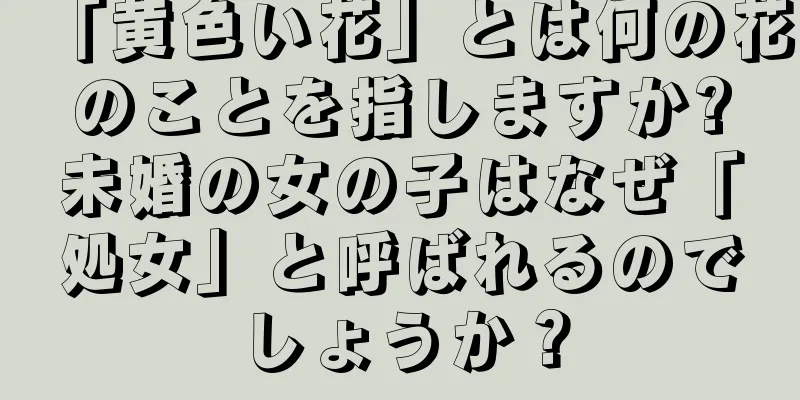
|
「黄色い花」とはどんな花のことでしょうか?未婚の少女はなぜ「黄色い花の少女」と呼ばれるのでしょうか?よくわからない読者は、Interesting History の編集者と一緒に読み進めてください。 古代人は、特定のタイプの人々を指すために常にさまざまな方法を持っていました。また、異なるグループの人々には独自の異なる名前もありました。たとえば、人々はまだ寝室にいて結婚していない女の子を「処女の女の子」と呼びました。しかし、なぜ人々はそのように呼ぶのでしょうか? 「赤い花」や「青い花」などの色ではなく、「黄色い花」と呼ばれるのはなぜでしょうか? 黄色い花はどこから来たのでしょうか? また、この言葉はどのようにして生まれたのでしょうか? 「黄花姫」は未婚の少女を指すことが多いが、処女を指すこともある。何が起こっているのか? 漢代から、女の子たちは「梅の花化粧」を好んでいました。梅の花粉で作った粉を使って化粧をするのです。この粉は黄色いので、「花黄」と呼ばれています。具体的な使用方法は、薄紙片、ドライフラワー片、雲母片、蝉の羽、魚の鱗、トンボの羽などを粉末にして黄金色に染め、花や鳥、魚など様々な形に切り取って額や口角、こめかみなどに貼り付けます。 南北朝時代、「花皇」は若い女の子にとって欠かせない顔飾りでした。南朝の陳の后皇帝の『蓮摘み歌』には、「夫に促されて暗いうちに起きる。化粧は前日に済ませてある。唇には上手に化粧をし、黄色い花を少しつける」とある。北朝の民謡『木蘭の歌』には、「窓辺で髪をとかし、鏡の前で黄色い花をつける」とある。 未婚の女性は「華皇」メイクを施し、既婚の女性は別のメイクを施します。昔から民間には「今日は黄色い花をつけた白い顔の奥さん、明日は緑の髪をした赤い髪の奥さんになる」という言い伝えがあります。そのため、「花黄」は若い女の子のための特別なアイテムです。 一方、「黄色い花」は古代では菊のことを指していました。菊は霜や寒さに耐えることができ、道徳心のある人を表すのによく使われます。そのため、人々は「娘」という言葉の前に「黄色い花」を付けます。これは、女の子がまだ結婚していないことを示すだけでなく、女の子の高貴な性格と貞潔さを称賛する意味もあります。 この習慣は、金・元の時代に遊牧民が中原に侵入してから徐々に廃止されましたが、「処女」という言葉は未婚の少女の同義語として受け継がれてきました。 「今日は顔が白くて黄色い花の娘、明日は顔が赤くて緑の髪の妻」ということわざがあります。黄色い花を着るのは古代の女性の結婚前の服装でした。結婚後は服装を変えなければなりませんでした。したがって、「黄色い花の娘」という用語が首陽から受け継がれたというのは絶対にあり得ないことです。では、「黄色い花の娘」という用語の由来はどこにあるのでしょうか?古代人はなぜ未婚の女性を「黄色い花の娘」と呼んだのでしょうか? 民間の言い伝えによると、宋の武帝の娘である首陽公主の黄色い花の物語は、南北朝時代に遡ります。首陽公主は宮廷の侍女たちと遊んでいたとき、疲れて昼寝をしていました。そよ風がロウバイの花を姫の額に吹きつけました。汗で汚れた花は姫の額に跡を残しました。宮廷の侍女たちはその光景に衝撃を受け、言葉にできないほど美しいと感じました。これにより、後世の宮殿でも模倣されるようになり、次第に民衆にも広まっていった。 最も初期の流行した染付黄色は梅の汁で染めることに限られていましたが、開花時期や季節の制限により、花黄色の選択範囲は継続的に拡大され、毒性がない限り、すべての黄色の花が使用され、その中で最も代表的なのは菊です。その後、使いやすく素早く使用できるように、花粉から作られた粉末が開発され、これらの粉末は植物性のものだけでなく、動物性や鉱物性のものもあります。 その後、人々は「花黄」または「黄色い花」を特に未婚の少女を指す言葉として使うようになりました。 「今日彼女は黄色い花を持つ少女だが、明日彼女は緑の髪を持つ少女である」という詩があります。結婚を望む女性を表すときに使われます。同時に、黄色い花は梅の花だけでなく、菊の花も指します。霜や寒さに耐える菊の気高い道徳心は、特に未婚の女性の道徳心と貞操を意味します。 |
<<: 「物を買う」という言葉はどのようにして生まれたのでしょうか? 「ものを買う」というお話!
>>: 「旗山棗子麺」にまつわる歴史的逸話は何ですか? 「旗山棗子麺」はどうやって生まれたのですか?
推薦する
岑申の「安渓に人を送る」:詩全体が愛国心の誇りに満ちている
岑申(718?-769?)は、荊州江陵(現在の湖北省江陵県)あるいは南陽桀陽(現在の河南省南陽市)の...
三英雄五勇士第29章:丁昭慧が茶室から鄭欣を盗み出し、占雄が飛湖亭で周老と出会う
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
蒋魏の婉曲的かつ暗示的な作品「定衛冬呉淞に書かれた典江口録」
以下に、Interesting History の編集者が、姜逵の『汷江口・呉淞定衛冬記』の原文と評...
孔子は言った。「賢者は仁に利益をもたらす」これにより、関羽の名声は後世まで受け継がれることになるでしょう。
今日、Interesting History の編集者は、皆さんのお役に立てればと、孔子の思想の分析...
呉文英の『勇遊楽 譚美慈世才韻』:文章はゆったりとしていて、感情は深く繊細である
呉文英(1200年頃 - 1260年頃)は、雅号を君特、号を孟荘といい、晩年は妓翁とも呼ばれた。思明...
「秀雲閣」は幽霊や老婆を集めて道を試し、赤い鯉の怪物族から疑惑を生み出す
幽霊を集める老婆は、赤い鯉の怪物に疑惑を生ませようとした斉喬と朱蓮は斧を持って歩きながら、密かに話し...
李白の古詩「荀陽城に下り、蓬里に渡って黄士に遣わす」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「荀陽城に下り、蓬里に船で行き、黄判に送る」時代: 唐代著者: 李白波は観音井を揺り動かし、陽...
朱光熙の『江南四歌』は、新鮮で素朴、明るく生き生きとした月下詩である。
朱光熙は、号は不明だが、唐代の山水・田園詩人、官吏である。開元14年に崔国夫、斉無謙とともに進士とな...
明代の神宗皇帝朱義君の生涯
明代の神宗皇帝の本名は朱懿君であり、明代の第13代皇帝であった。彼が10歳のとき、父親が亡くなり、少...
孟伯の仕事は何ですか?孟伯の本来の正体は何だったのでしょうか?
みなさんこんにちは。孟伯の言葉といえば、みなさんも聞いたことがあると思います。古代の神話や伝説では、...
明代の数秘術書『三明通会』第2巻:人袁思詩について全文
『三明通卦』は中国の伝統的な数秘術において非常に高い地位を占めています。その著者は明代の進士である万...
王陽明の心の哲学とは何ですか?それは私たちにどんなインスピレーションをもたらすのでしょうか?
王陽明の心の哲学をご存知ですか?今日は、興味深い歴史の編集者があなたにまったく新しい解釈をお届けしま...
南宋が臨安を首都に選んだ理由は何ですか?南京を選んでみませんか?
宋の秦宗皇帝の景康の時代、宋ではそれまでの王朝では考えられなかったことが起こりました。北方の遊牧民で...
古典文学の傑作『太平天国』:官部第19巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
呉三桂の反乱はなぜ失敗したのか?これは彼の優柔不断な性格とどう関係があるのでしょうか?
1662年、清朝の康熙帝の治世の初期に、明朝の元官僚である呉三桂が雲南省昆明で南明朝最後の皇帝である...