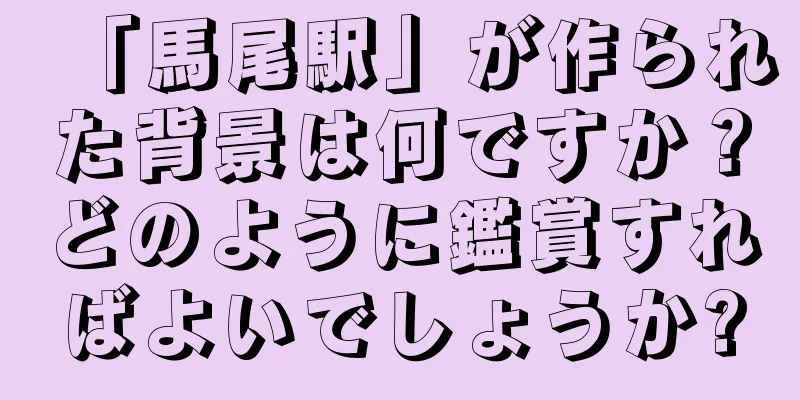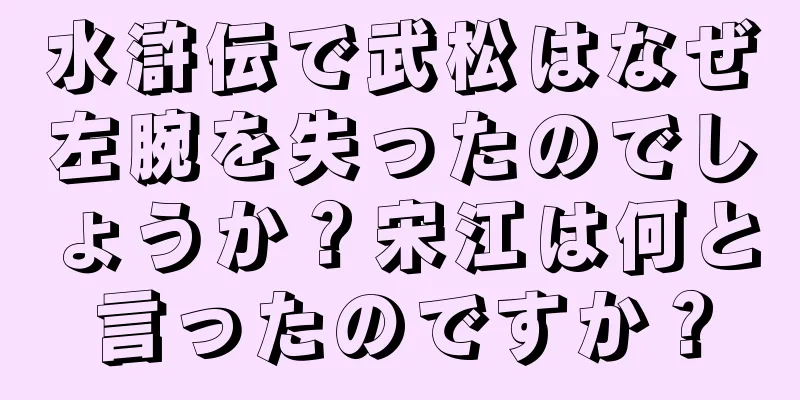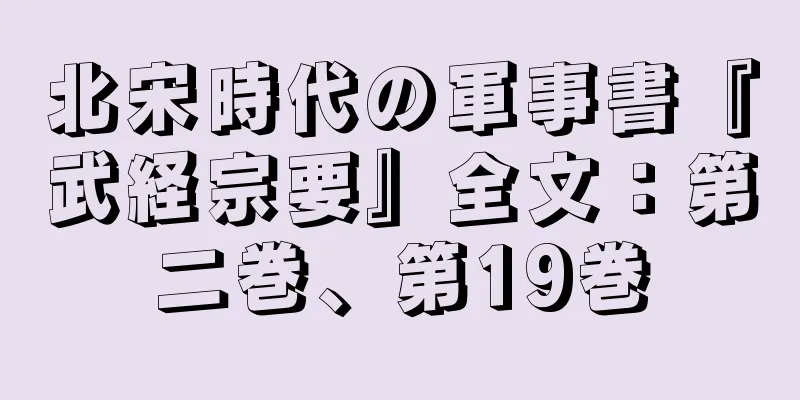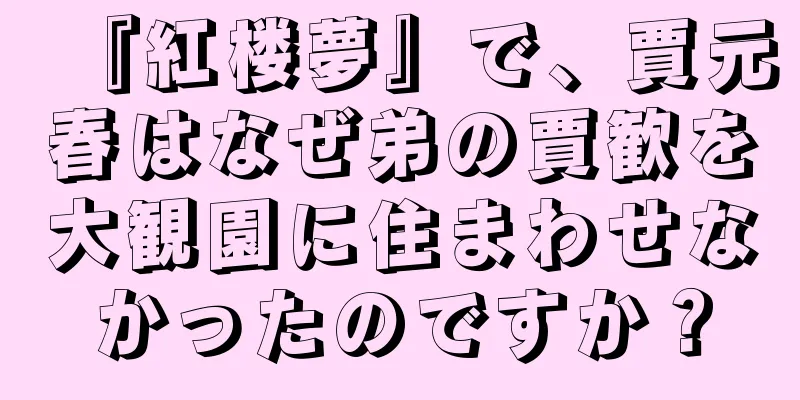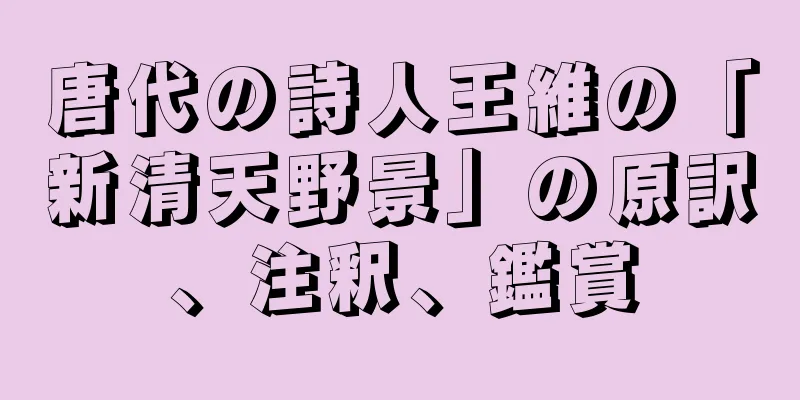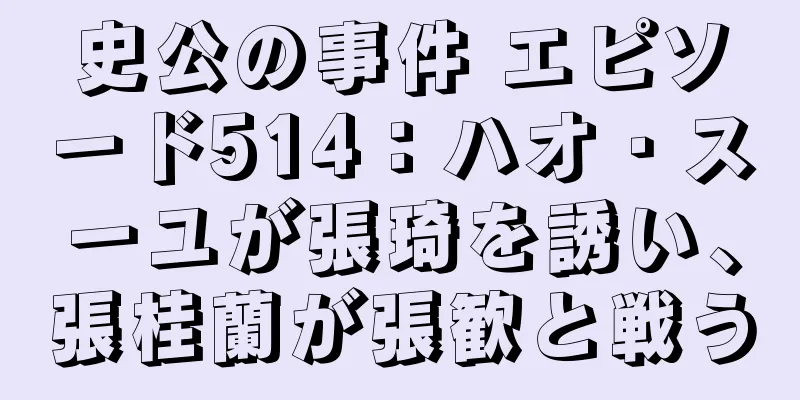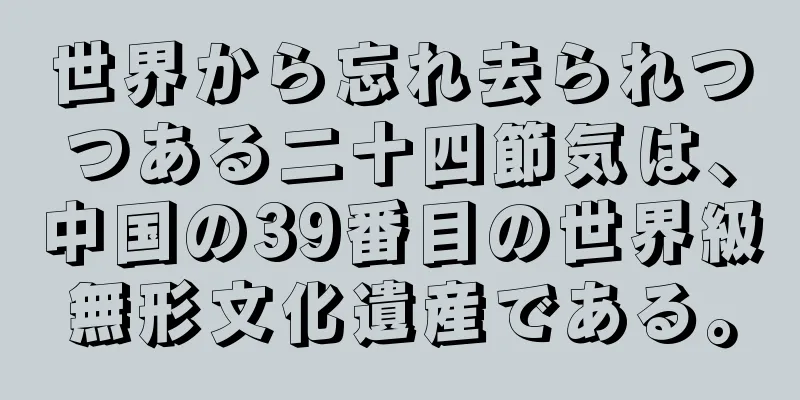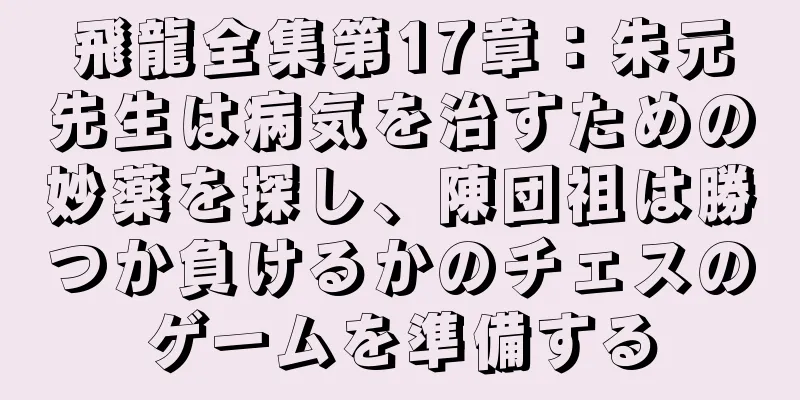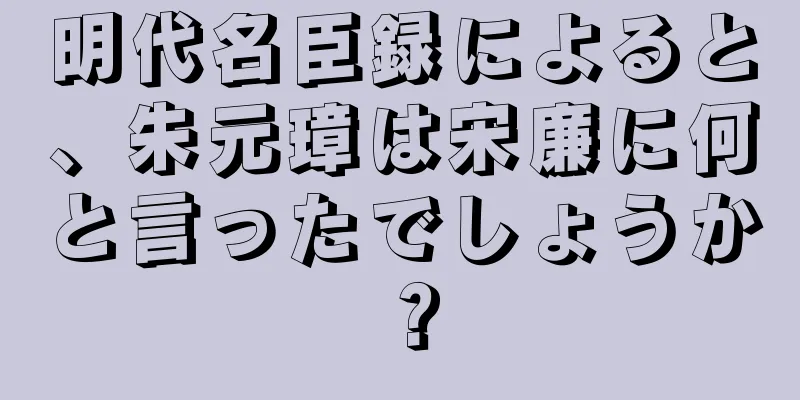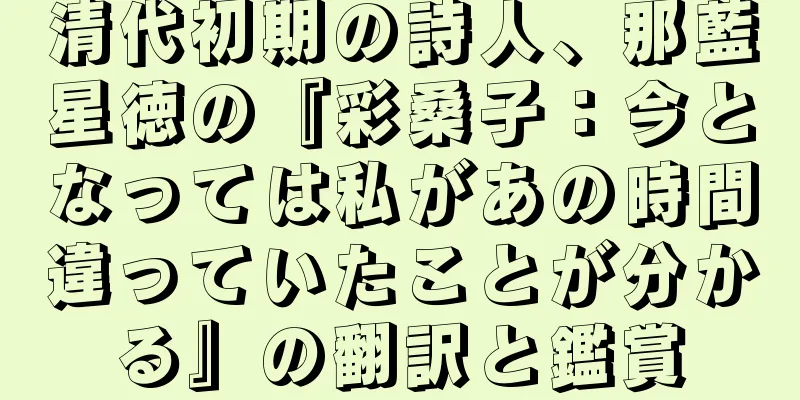「物を買う」という言葉はどのようにして生まれたのでしょうか? 「ものを買う」というお話!
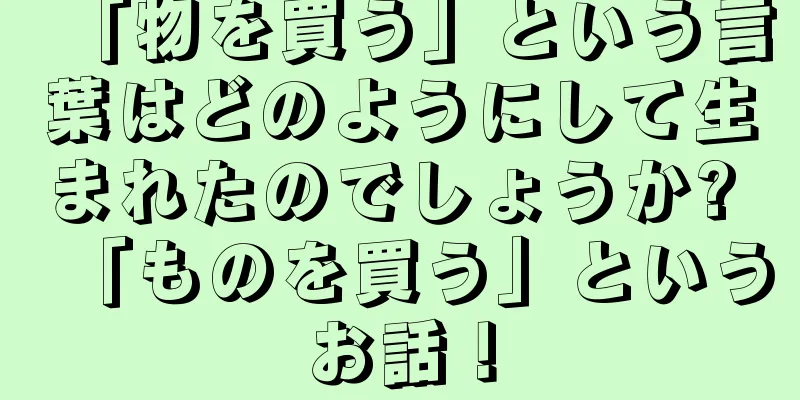
|
「物を買う」という言葉はどうやって生まれたのでしょうか?「物を買う」にまつわるお話です!今日はそれに関連したコンテンツをお届けして、皆さんにシェアします。 買い物といえば、誰もが毎日何かを買わなければなりませんが、なぜ物を買うことを物を買うというのか、なぜ南北に買うことを南北に買うと言わないのか、という疑問を持ったことはありませんか。実は、これらは今でもよく知られています。実は、これは朱熹という古代の人と切っても切れない関係にあります。では、その状況はどうなっているのでしょうか。編集者と一緒に秘密を明かし、分析してみましょう。 よく話題になる「東西」という言葉は、単なる方向を示す言葉ではなく、普遍的な代名詞であるようです。買い物:「物を買う」、悪態:「何もない」、アイテム:「物を見つける」など、リストは続きます。では、なぜ北と南を使わないのでしょうか? 実はここにはたくさんの歴史と文化が詰まっています。 南宋時代の偉大な儒学者である朱熹が官職に就く前、故郷に盛文和という親友がいたと言われています。盛文和もまた学識があり才能のある人でした。ある日、二人は路地で出会いました。盛は手に竹籠を持っていました。朱熹は彼に尋ねました。「どこへ行くのですか?」 盛さんは「買い物に行ってきます」と答えました。 朱熹は真理の追求を通して知識を追求する人でした。彼は盛の言葉を聞いて非常に興味を持ち、「何かを買うと言ったとき、なぜ南北を買うとは言わないのですか?」と尋ねました。 聖文和は朱熹に尋ねた。「五大元素が何か知っていますか?」 朱熹は答えた。「もちろん知っています。金、木、水、火、土ではないですか?」 盛は言った。「そうだ、君がこれを知っていれば簡単だ。教えてやろう、東は木、西は金、南は火、北は水、真ん中は土だ。私の籠は竹でできているから、火を入れれば燃えるし、水を入れれば漏れてしまう。木と金しか入れられず、土は入れられない。だから私は物を買うとしか言えない、北と南を買うことはできない。」 これを聞いた朱熹はため息をついて「そういうことか!」と言った。 「物を買う」という言葉には、このような意味合いがあるのですね。私たちの生活の中には、まさに古代人の知恵が隠されているのですね。 清朝の乾隆年間、龔維という学者は、東漢の頃には商人のほとんどが東京の洛陽と西京の長安に集中していたと信じていました。 「東で買え」と「西で買え」ということわざがあります。つまり、人々は商品を買うために東京や西京へ出かけ、時が経つにつれて「东」は商品の同義語になったのです。 古代では、「南北」に対応する「水と火」と「中心」に対応する「土」は価値がなかったため、売買する必要はありませんでした。古代人は、南を向いて北に背を向けるのが最善であると信じていました。つまり、南北は通路であり、物は東西側に置かれていました。物を指すときは、自然に東西を指すため、東西は物の総称として使用されていました。 誰かを侮辱するときに、なぜその人を「クソ野郎」と呼ばなければならないのでしょうか? なぜなら、もし人々が東と西に分かれていなければ、北と南に分かれているからです。 南は火に属し、北は水に属します。古典中国語では、「水と火」は排尿と排便を意味します。 つまり、誰かを何かと呼ぶことは、その人を糞尿だと言っているようなもので、これは現代の「臭い糞」という呪いに相当します。 昔の人は人を呪うのが上手だったようです。人を呪うのにこんなに遠回りして、しかも汚い言葉は一切使っていない。何も「ないもの」を発明できる学者には本当に感心します。すごいですね! これで、誰もが「南北を買う」のではなく「物を買う」と言われる理由が分かりましたね? 大切に保管しておけば、将来友達にこの話をして、教養のある人だと思わせることができるかもしれませんね? |
<<: 「週」という言葉は中国にどこから来たのでしょうか?古代の週制度はいつ始まったのでしょうか?
>>: 「黄色い花」とは何の花のことを指しますか?未婚の女の子はなぜ「処女」と呼ばれるのでしょうか?
推薦する
三国時代、劉封の自殺はなぜ彼自身の責任だと言われていたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
もし孫権が陸孟と陸遜を派遣して合肥を攻撃したら、戦況はどのように変化するでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
宋代の貨幣とは何ですか?これらのコインはどのようなものですか?
宋代には何種類の貨幣があったかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting His...
北宋時代に金と戦った名将・武夷とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は武夷をどのように評価しているのでしょうか?
呉潔(1093-1139)、号は金卿、徳順軍竜干(現在の甘粛省景寧)に生まれ、興国州永興(現在の湖北...
『霊陵県慈心亭』の執筆背景は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】遠くの川岸には木々が浮かんでおり、空の果てには一本の煙が上がっている。川と空は自然に溶...
国民楽器バンジョーはどのように作られるのでしょうか?プレイ時に注意すべきことは何ですか?
中国の古代弦楽器の多くは、琴、筝、竪琴など、五弦形式を経てきたことはよく知られています。では、国民楽...
北宋時代の程浩が書いた「春日折詩」は詩人の内なる誇りと喜びを表現している。
程昊は、号を伯春、号を明道といい、通称は明道氏。北宋代に朱子学を創始した。弟の程毅とともに「二人の程...
なぜ劉備は息子の世話をする大臣として諸葛亮と李延を選んだのでしょうか?権力は一人の手に渡ってはならない
劉備の出世が成功したのは、人をうまく利用したからである。彼は、適切な時に適切な人を利用することによっ...
『史記』の物語の紹介 - 秦の始皇帝が六国を征服
秦の始皇帝嬰政は秦の荘襄王の息子であった。秦の荘襄王は怡仁と名付けられ、若い頃は趙の国で人質となって...
「黄鶴楼登り」の制作背景は何ですか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
黄鶴楼崔浩(唐代)古代の人々は黄鶴に乗って去ってしまい、ここには黄鶴楼だけが残されています。黄色い鶴...
『紅楼夢』で、賈正は賈宝玉を殴った後、なぜ地面にひざまずいて賈の母親に罪を告白したのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
遼王朝の全盛期の領土は宋王朝の領土と比べてどうだったでしょうか?
遼王朝(907-1125)は、中国の歴史上、契丹族によって建国された王朝です。9人の皇帝がいて、21...
『旧唐書伝』巻131にはどのような出来事が記録されていますか?原文は何ですか?
『旧唐書』は唐代の歴史を記録した偉大な歴史文学作品です。後金の開雲2年(西暦945年)に完成し、全2...
東林党争議とは何ですか?東林党闘争の起源、過程、結果
東林党争議とは、明代末期の東林党、宦官党などの派閥間の争いを指す。「声を上げる者はますます国を治める...
本草綱目第8巻生薬類キプリペディウムの具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...