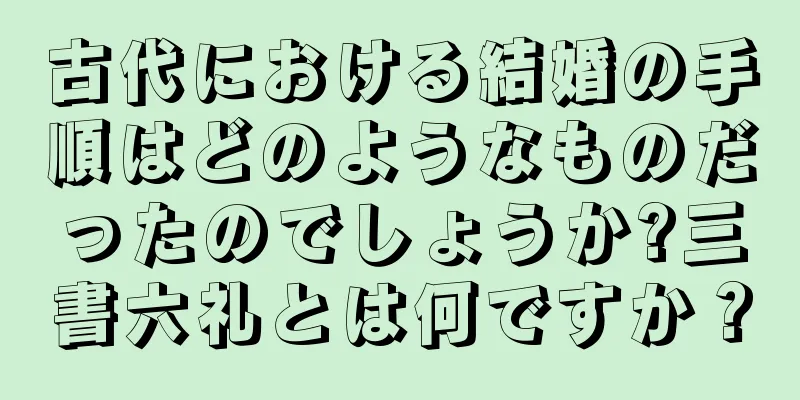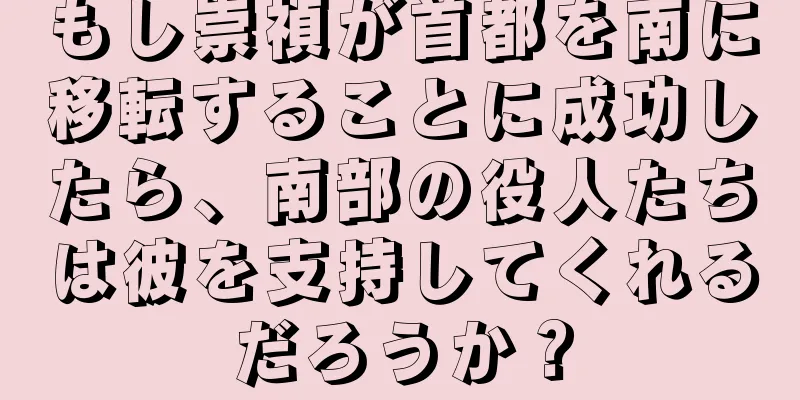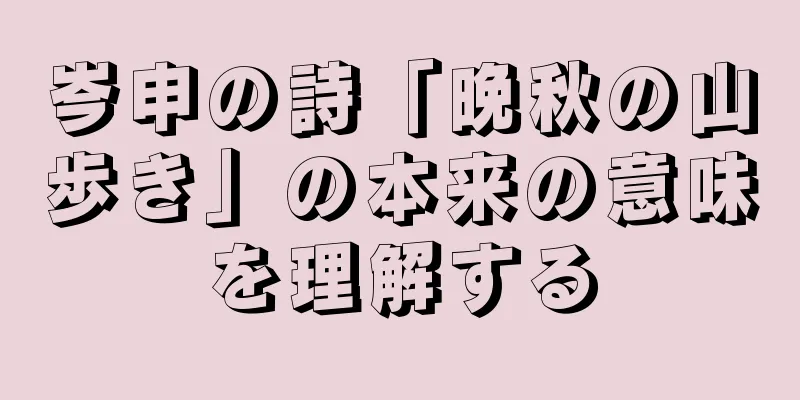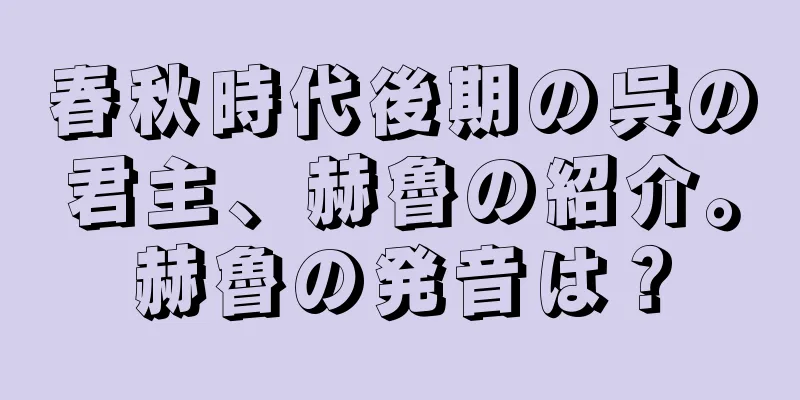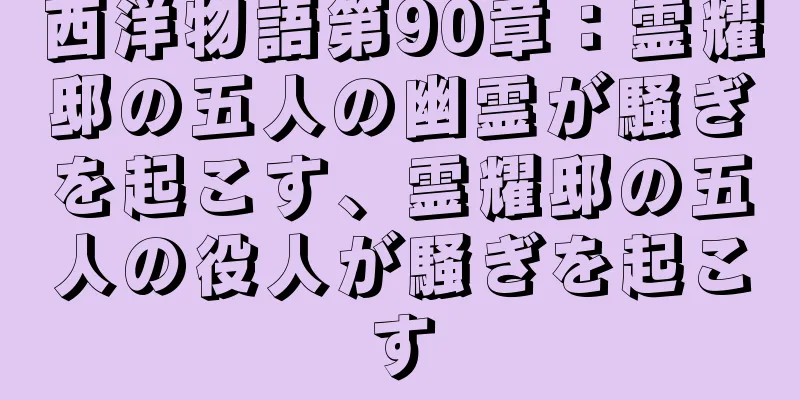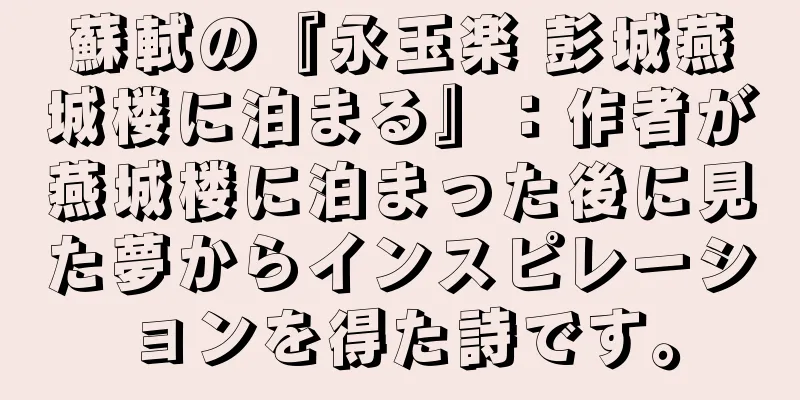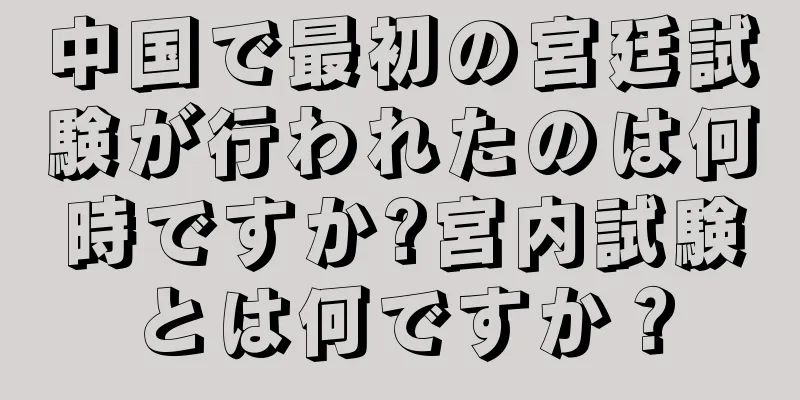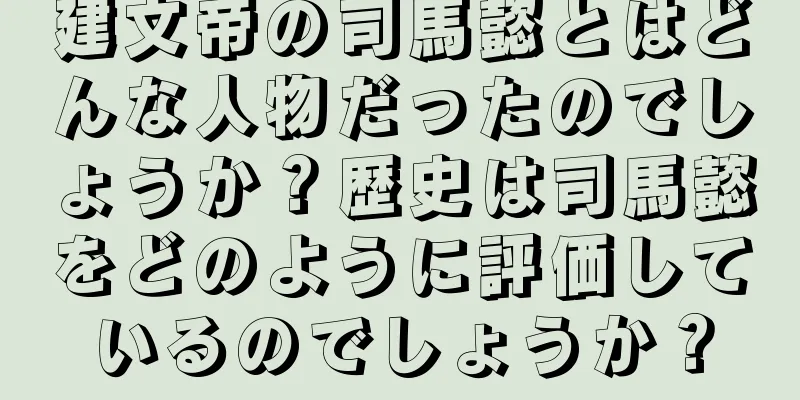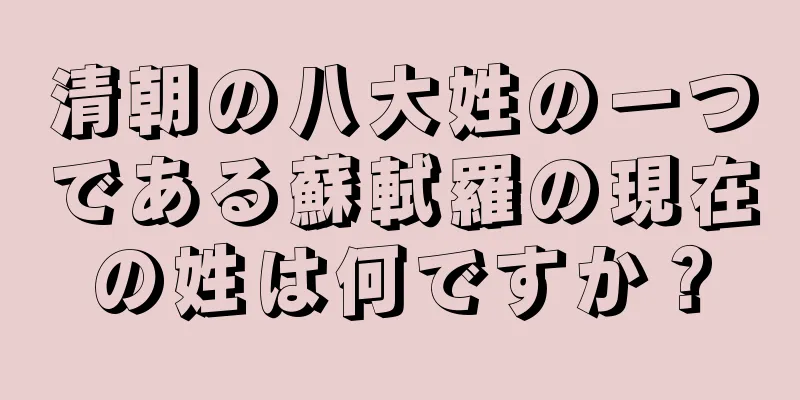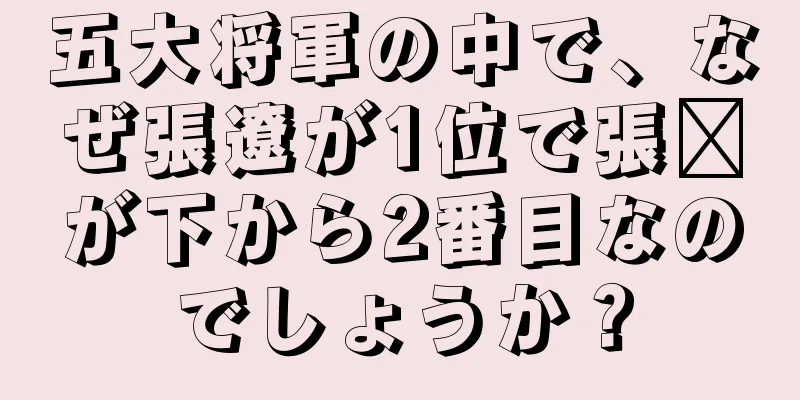何事にも限界はある!なぜ秦王朝は孔子と孟子の中庸の教えを国を統治するために使わなかったのでしょうか?
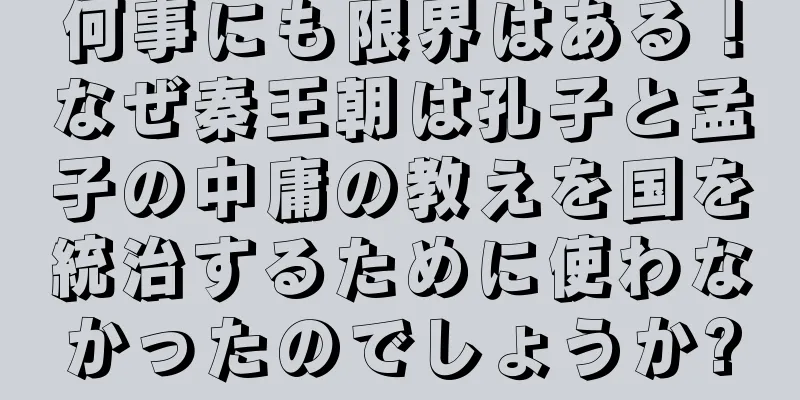
|
今日は、Interesting Historyの編集者が孔子と孟子の中庸の教えについての記事をお届けします。ぜひお読みください~ 秦の時代が孔子と孟子の教えを活用しなかった理由は2つある。第一に、儒教は道教ほど目立たないようにする賢明さがなく、「一見混乱しているが実際には混乱していない」時代に人々の生活を回復することに関しては、道教と比較すると見劣りする。第二に、厳しい法律と厳しい刑罰を伴う法家思想の「暴政」がなければ、百家思想の影響がまだ残っていた時代に、「暴政」の力で思想を統一することは困難だった。 中庸の教義の重要性は、「多すぎることは少なすぎることと同じくらい悪い」という考えにあります。 「多すぎるのも少なすぎるのも悪い」という考えは、常に未来の世代に偏見を持たないこと、事実から真実を求めること、公平であることを思い出させます。秦王朝がたった2世代しか続かなかったという事実も、極端さが物事の早期の衰退につながることを証明しています。 1. 秦の時代は「混乱というほどではない」時代であり、百家思想の余韻がまだ残っていた。 秦の時代は、かなり特殊な時代でした。秦の始皇帝が天下を統一したばかりで、百家争鳴の余韻がまだ残っていました。この時代、名目上は天下は統一されていましたが、実際にはいくつかの暗流がありました。秦の始皇帝の時代にも、当時の社会環境に適した施策を採用し、文化や民生に力を入れることが必要でした。秦の始皇帝が解決しなければならなかった問題は、一方では戦争後の祖国の再建であり、他方では国内の人々の心を維持し、極端な思想が広まるのを防ぐことであった。 しかし、秦の始皇帝は、法家の「厳しい法律と厳しい刑罰」によって国の安定を維持しようとして、「上からの統制」という抑圧的な方法を使う傾向が強かったようだ。属国同士の戦場で勝利を収めた秦の始皇帝は、やはり国の「軍事力」を強化することに最も関心があったようだ。しかし、これは理解できます。結局のところ、中原は統一されていましたが、国境のフン族は依然として時々人々を嫌がらせしており、それは確かに少し迷惑でした。そこで秦の始皇帝は大規模な建設事業を開始し、万里の長城を築き、国境の防衛を強化し、一連の措置を講じて中央権力を強化した。 秦の始皇帝の視野は依然として「国家」同士の対立にとらわれており、彼はまだ「国家対決」の戦場から目を離していない。おそらく秦の始皇帝は、長年の戦争を経験した人々が平和を望み、故郷の再建を望み、復興を望んだことに気づかなかったか、気づく時間がなかったのでしょう。 そのため、諸侯の覇権争いの戦場をようやく生き延びた庶民は、ほっと一息ついたかに思われたが、すぐに再び秦の厳しい法に突き落とされた。また、戦国時代の百家思想の余韻がまだ冷めておらず、民衆は依然として比較的「イデオロギー的」であり、当然ながら民衆の反感を招いていました。秦の始皇帝は高い地位にあり、歴史の転換点に立つ「万世一系の皇帝」であったため、世論を煽ろうと下心のある人々によって前面に押し出されることは容易であった。したがって、上記の分析から、秦の始皇帝は国を統治するために儒教を選択することは本当にできなかったことがわかります。なぜそう言うのでしょうか?読み進めてみましょう。 2. 儒教は民生回復の点では道教ほど優れておらず、百家思想がまだ生きていた時代に思想を統一するのに適していない。 秦の始皇帝の時代、諸侯間の大戦は終わったものの、人々の暮らしは戦時中よりわずかに良くなった程度で、家は戦争で跡形もなく破壊され、同時に、人々の間ではさまざまな学説が流行し、人々の心は乱れていました。さらに、海外には彼らを狙う強大な匈奴族がいました。実際、人々の生活はそれほど良くはなく、秦の始皇帝は天下統一後も安心できるとは言えなかった。 秦の始皇帝の最優先事項は、第一に目立たないようにして人々の生活を回復すること、第二に思想を統一して人々の心を落ち着かせることであった。当然のことながら、儒教は道教よりも目立たないようにする上で大きな役割を果たすことはできません。儒教の「祭祀制度」へのこだわりについては、葬儀や祭祀など、当時の社会状況では不適切な出費が生じやすい場合が多いです。統一思想という点では、さまざまな学派の影響が依然として残っており、儒教はその形態において貴族階級を維持するという明確な特徴を持っていました。同時に、法家のような「優位性」を欠き、あまりに穏やかで、その関心は一貫していないように見え、それは確かに「一般大衆」に受け入れられることを困難にしていました。したがって、人々の生活を回復する点でも、人々の心を落ち着かせる点でも、儒教は秦の始皇帝の時代にはあまり適していませんでした。 3. 中庸の意義:秦の極端主義は、中庸に反することは物事の衰退を加速させることを証明している。 節度の意味を見てみましょう。いかなる時も、極端は良くありません。中庸という考えは、公平であること、物事をやり過ぎたり、やり足りなかったりしないことを教えてくれます。しかし、秦の始皇帝の厳しい法律と国家建設における大規模な建設事業はやりすぎだったようで、それに応じて、民生の発展においては不十分だったようです。その結果、複数の要因が重なり、最終的に秦王朝の「短命」につながった。したがって、秦の時代を例にとったとしても、中庸の教えの意義は、盲目的に妥協したり、極端になったりせず、状況に応じて中庸に物事を行うように後世に警告し、「物事が極端になり、その後逆戻りする」という悲劇を避けることであることがわかります。 したがって、以上の分析から、秦の始皇帝の時代は、世界が「一見混沌としているが、実際には混沌ではない」という底流の時代であり、各派の影響力は依然として残っており、国内の思想は統一されておらず、民衆の生活は衰退し、外部には強敵が存在していたことは容易に理解できる。儒教は、一方では、道教の回復思想の「静けさ」を持たず、「一見混沌としているが、実際には混沌ではない」時代に民衆の生活の回復に「害を及ぼした」。他方では、法家思想の「運動」を持たず、各派の影響力の残る時代には、「覇権」の力で思想を統一することは困難であった。そのため、人々がまだ力を競っていた秦の始皇帝の時代には、儒教は依然として見劣りするものでした。中庸の教義の役割は、「過剰は不足と同じくらい悪い」ということを示し、原則に基づいて物事を行う際に「程度」を把握するように人々に警告することです。 |
<<: 「秦の成否は法家にかかっている」と言われるのはなぜでしょうか?法家は秦の国にどのような影響を与えたのでしょうか?
>>: 人間の本質は善か悪か?宋代と明代の儒教をどう区別するか?
推薦する
北斉の文宣帝、高陽の略歴。高陽はどのようにして亡くなったのでしょうか?
文宣帝高陽(526年 - 559年11月25日)は、字を子進といい、北魏の懐朔鎮(現在の内モンゴル自...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源第116巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
賈潭春に対するこの平手打ちは傲慢で非道なものとみなされたのか、それとも喜ばしいものだったのか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『紅楼夢』の王夫人はなぜ妙玉を大観園に置いたのでしょうか?
『紅楼夢』の妙玉は非常に謎めいた人物で、その正体はこれまで明かされていません。では、なぜ王夫人は妙玉...
「襄王送還」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
翔裁判官を送る王安石(宋代)蘆洲島は崩れ、楓橋は落ち、渡し場の砂は正午の潮の後もずっと残っている。山...
華雄とは誰ですか?華雄は歴史上どのように亡くなりましたか?
華雄って誰ですか?この質問は非常に簡単です。『三国志演義』や『三国志演義』を読んだことのある人なら、...
「小園頌」:南北朝文学界の「ネットセレブ」于鑫の隠れた傑作
杜甫の詩に「于新の文体は年を重ねるにつれて円熟し、その文体は力強く伸びやかになった」という一節がある...
古典文学の傑作『太平天国』地理編第4巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
かつて劉璋はためらうことなく劉備を助けたのに、なぜ二人は最終的に敵対することになったのでしょうか?
三国時代、劉璋と劉備の関係は常に非常に良好だったと言われています。そのため、劉備が困ったとき、劉璋は...
『緑氏春秋・不狗論』の「不狗」は何と書きますか?それをどう理解すればいいのでしょうか?
『禄氏春秋』の「武狗論」は何を書いているのか? どのように理解するのか? これは特に多くの読者が知り...
済公第169章:王勝仙は彼女の美しさを見て欲情し、陸玉侯は泥棒に裏切りの計画を実行するよう依頼する
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
唐の武宗皇帝、李厳には何人の息子がいましたか?唐の武宗皇帝の子供は誰でしたか?
唐の武宗皇帝(814年7月1日 - 846年4月22日)は、本名は李禅であったが、後に顔に改名した。...
陳叔宝は皇太子として即位したが、なぜ人々は彼の王位は苦労して獲得したものだと言っているのだろうか。
"Book of Chen·Chronicles Volume 6·Later Lord&...
『旧唐書伝』第88巻にはどんな物語が語られていますか?
『旧唐書』は全200巻。著者は後金の劉儒らとされているが、実際に編纂したのは後金の趙瑩である。では、...
「四聖心源」第七巻 雑病解説その二 日射病の根源
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...