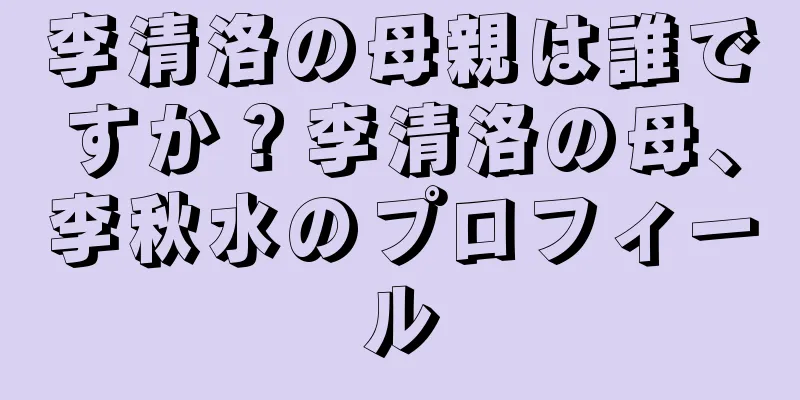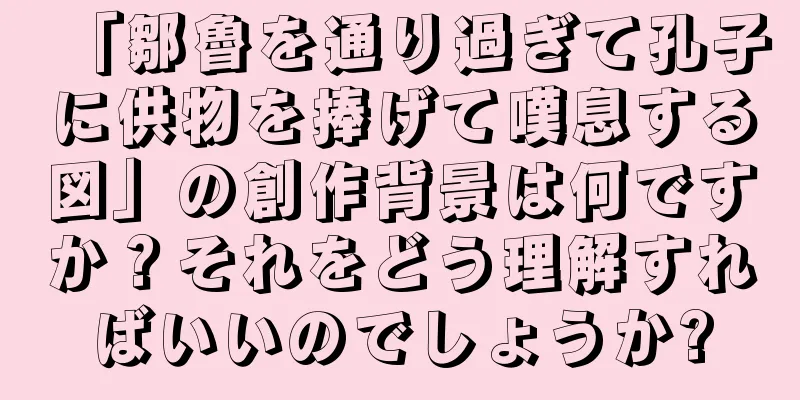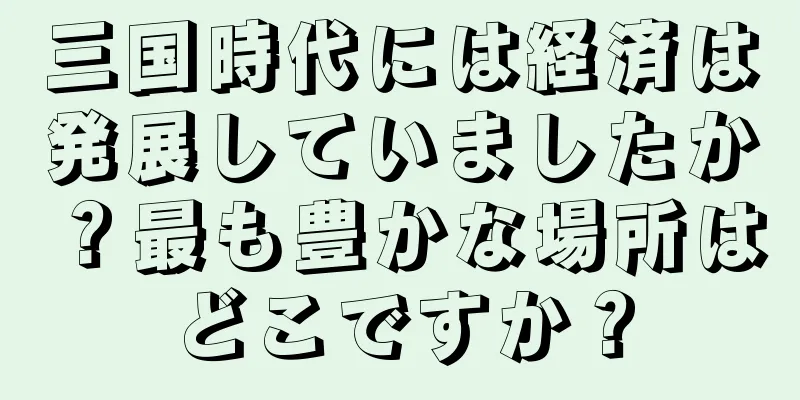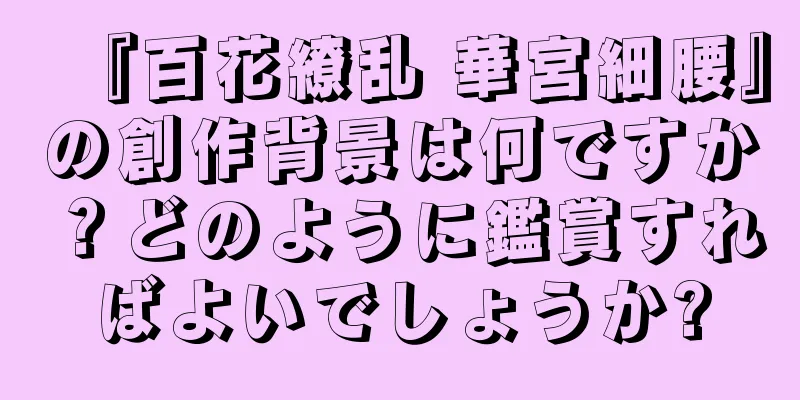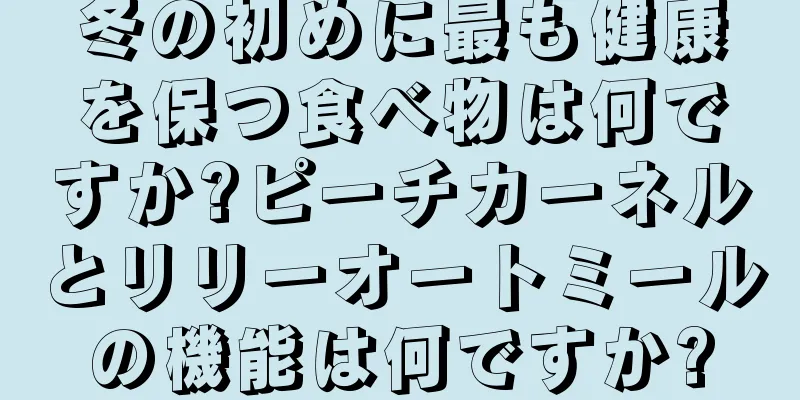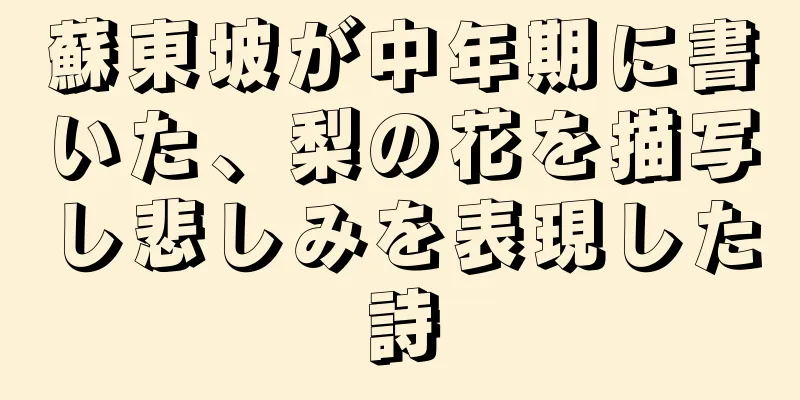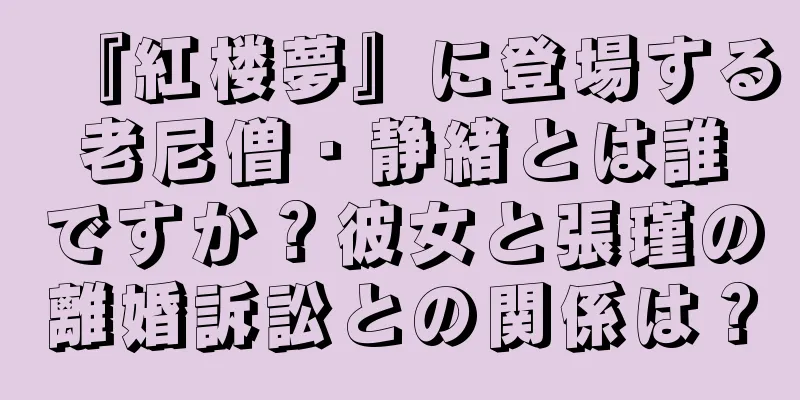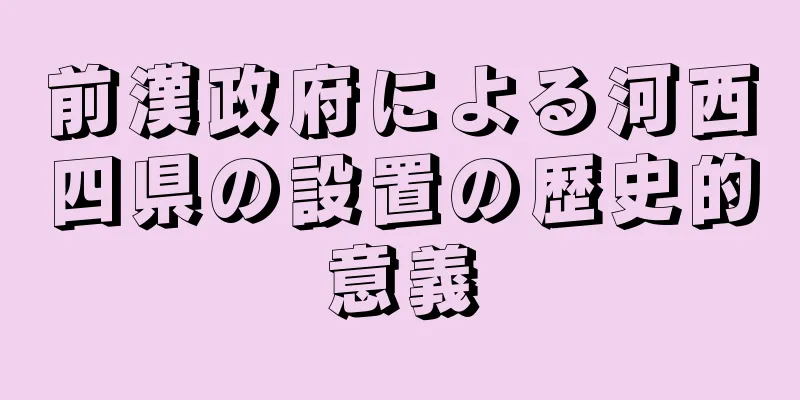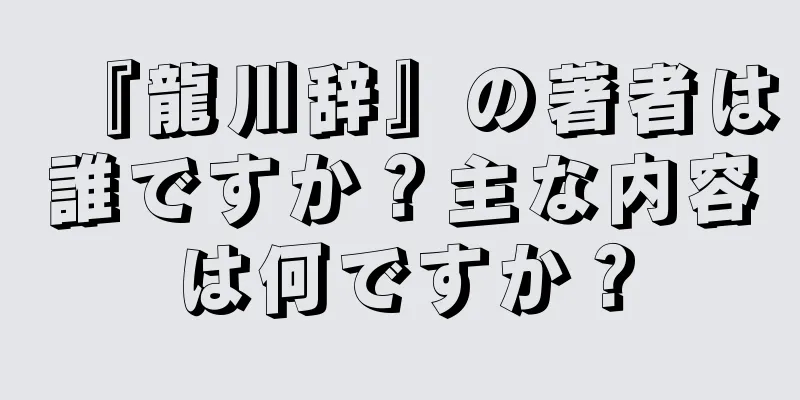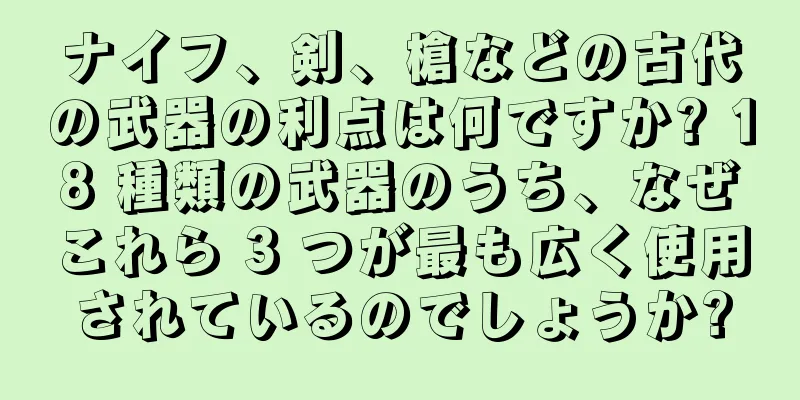歴史上、役人を選出する制度はいくつあったでしょうか?古代の官選制度はどのように発展したのでしょうか?
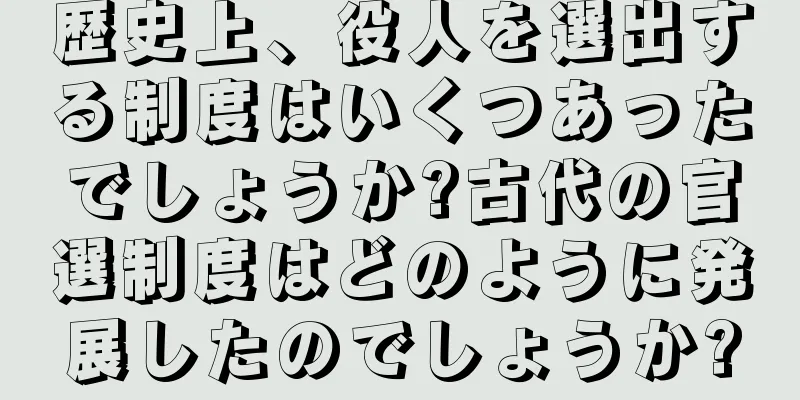
|
今日は、歴史上の公選制がどれくらいあるのかを「おもしろ歴史」編集長が紹介します。皆さんの参考になれば幸いです。 古代の学者の夢は、学問で成功を収めた後、文武両道を学び、学んだことをもって皇帝に仕えることでした。しかし、この理想を実現するには、朝廷の選抜に合格するという段階を踏まなければなりません。これが、この記事で説明する官選制度の起源と継続的な変化です。では、古代中国における主な官選制度とは何でしょうか。それらはどのように継承され、継続され、発展したのでしょうか。 まず、異なる王朝で実施された官吏選抜制度も異なっていました。一般的に言えば、4つの段階に分けることができます。最初の段階は先秦王朝以前で、実施された主な制度は世襲貴族制度であり、これはいわゆる世襲官吏制度であり、つまり、貴族は代々官吏を務めることができ、官吏は世襲官職の特権を有していました。周王朝が商王朝を滅ぼした後、周の皇帝は一族の帝国を拡大・強化するために、同姓や親族、功績のある官僚に大領地という形で統治権、土地、人民を与えた。与えられた大臣や王子たちは王朝を統治する貴族として、世襲官吏制度に頼って自らの統治と周の皇帝への忠誠を維持した。しかし、時が経つにつれ、周の皇帝の威信は徐々に低下し、君主たちの権力は徐々に高まっていった。特に春秋戦国時代には、世襲官僚制度の欠点が徐々に明らかになった。例えば、官職は貴族に限られ、身分が低く才能に優れた人物を任命することができなかった。自国の統治に適応するために、各国の属国は改革を進め始めた。その中で最も徹底していたのは秦であった。商鞅の改革後、秦は軍功制度を実施し始めたが、軍功制度にも欠点があり、統一された秦王朝に適応できなかった。 漢代には、第二の官吏選抜制度、すなわち推薦制度が形成され、発展し始めた。世襲官吏制度と比較すると、推薦制度は官吏選抜制度において独自の理論と実施方法を持っていた。漢の恵帝・呂后の時代は推薦制度の萌芽期であった。当時、朝廷は孝行や兄弟愛、また畑仕事に励む者を推薦するよう勅令を出した。当時は褒賞に過ぎず、官職は与えられなかった。漢の文帝の時代には、具体的な試験や等級が制定されたが、それらは完全ではなく、統一された選抜基準や試験方法もなかった。漢の武帝の時代になって初めて、推薦制度は完全な人材選抜の仕組みとなった。この制度は、中央政府の三公爵と九大臣、郡知事、侯爵、地方の高官らが、一定の基準に従って道徳、品行、能力の面で当時の支配階級のニーズを満たす民間人や下級官吏の中から人材を選び出し、宮廷の官吏として働かせるというものでした。 推薦制度の実施により、両漢王朝の発展に必要な人材が確保された。しかし、東漢末期になると、推薦制度の欠点が表面化し始めた。前述のように、庶民や下級官吏が朝廷に出仕したり昇進したりするには、高官の推薦が必要だった。数百年の発展を経て、高官や富豪一族は自らの威信と権力を頼りに、庶民や下級官吏のキャリアに影響を与え始め、多くの中小地主とその知識人が政治に参加する機会を失うか、依存的になった。矛盾はますます顕著になり、大多数の人々が政治に参加する機会を保証するために、新しい官吏選抜制度が緊急に必要となった。 推薦制度の次に、三番目の官選制度が生まれました。それは九位制で、曹丕が陳群の提案を採用して導入した新しい官選制度です。いわゆる九位制は、一般的に各州と郡が1人の大中正を指名し、その大中正が小中正を選出する制度を指します。中正とは、人材を評価する責任を持つ官職の名称です。中正官吏の評価内容は主に人物の背景と道徳的性格であり、背景と道徳的性格に基づいて等級が与えられます。九階制が確立された当初、人の位は道徳的性格に基づいて決定され、出自は参考程度にしか使われませんでした。しかし、晋の成立後、優先順位は逆転し、位は完全に家柄に基づいて決定されました。貧しい家の人は、どんなに品行が評価されても下位にしかランクされず、裕福な家の人は、品行が良くなくても上位にランクされました。上層階級に平民はおらず、下層階級に貴族はいない。これが当時の具体的な現れであり、やがて九階制は貴族の家の選挙の道具となった。 もともと晋の武帝、司馬炎も九位制の不合理さに気づいていたが、自らの統治を維持するために、この官吏選任制度を黙認した。司馬炎以降の西晋の皇帝たちは権力闘争に忙しく、他のことに時間を割く余裕がなかった。雍嘉の乱の後、金朝は南下し、東晋の皇帝にとって貴族階級は最後の頼みの綱となった。貴族政治はますます顕著になり、貴族階級の利益に沿った九階制は当然改革する必要がなかった。その後の南北朝の統治者は貴族階級の影響力の弱体化を望んだが、200年以上の発展を経ても、朝廷における貴族階級の影響力は依然としてかけがえのないものであり、そのため、魏晋南北朝の官吏選抜の主な制度は九品制となった。 魏、晋、南北朝を経て、隋の時代に天下は新たな統一を迎えた。官吏の選抜方法や、朝廷による人材の活用方法は、隋の皇帝が考えなければならない問題となった。隋は推薦制度と九階制に基づいて人材を評価する科挙制度の原型を導入し、唐の時代に科挙制度がようやく形成された。唐代から清代末期までの1300年以上にわたり、各王朝は科挙制度を利用して人材を選抜してきました。明代と清代を例にとると、科挙は同師、元師、相師、会師、典師の5段階に分かれており、段階が上がるほど恩恵も厚くなりました。 科挙制度の実施により貴族の独占が打破され、より多くの階級の人材が朝廷で採用されるようになった。以前の官選制度と比較すると、科挙制度はより公平なものとなった。銭牧氏は「良い制度が永遠に続くと、政治は窒息してしまう」と述べた。科挙制度についても同じことが言える。科挙制度が発展するにつれ、その欠点も現れ始めた。例えば、試験のために八字文を奨励したことで、革新性や進取の精神に欠ける人材が選ばれ、多くの知識人の思考が制約された。科挙制度によって貴族政治は排除されたが、縁故主義は依然として存在し、官僚同士が互いに庇い合い徒党や派閥を形成する現象も時折発生した。 清朝後期に西洋の思想が流入するにつれ、科挙制度は時代の発展にますます追いつけなくなってきたように見えた。特に清朝がニューディール政策を実施した後、科挙制度は特に場違いに見えた。最終的に、袁世凱と張之洞の要請により、光緒帝は科挙制度を廃止する勅令を発布し、全国で学校教育を推進し始めた。 秦以前の時代に始まった世襲官吏制度から、漢代の推薦制度、魏晋南北朝に実施された九階制、そして隋唐時代に始まった科挙制度に至るまで、古代の官吏選抜制度は変化していったものの、変わらない核心があった。それは、知識を普及させることに加えて、できるだけ多くの人材を採用して朝廷に仕えることであった。冒頭で述べたように、文武両道を学んで皇室に仕えるという考え方は、微妙な影響を通じて長い間人々の心に深く根付いてきた。 |
<<: 歴史上、子年に起こった大きな出来事は何ですか?違いは何ですか?
>>: 古代史には「皇孫」が何人いたのでしょうか?朱雲文が最初ですか?
推薦する
古典文学の傑作『太平天国』:帝部第20巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
宋江が呂俊義を獲得するためにあれほど苦労した理由は何だったのでしょうか?
陸俊義は涼山に行った後、趙蓋の仇討ちに成功したこと以外には目立った功績はほとんどなかった。しかし、彼...
宋の元帝劉紹には何人の子供がいましたか?劉紹の子供は誰でしたか?
宋の元帝、劉紹(426年頃 - 453年)は、号を秀元といい、彭城の遂里の出身であった。南宋の第4代...
「彭公安」第280章:欧陽徳が偽の悪魔を発見し、叔父の息子が峠の外で捕らえられた
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
清代史草稿第15巻原文
◎高宗皇帝実録(第6巻)五十一年の正月一日に日食があり、法廷は中止された。武神では、税務省は救済のた...
唐詩の代表的人物の略歴:初期唐詩の革新者の一人、陳彬
陳子昂(661-702年)は、雅号を伯禹といい、淄州歙洪(現在の四川省歙洪市)の出身である。唐代の作...
包公の事件 第59章: 邪悪な教師が弟子を惑わす
『鮑公案』は『龍土公案』とも呼ばれ、正式名称は『都本鮑龍土百公案全伝』で、『龍土神段公案』とも呼ばれ...
『大連花宇寺蘭亭古今街道』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
蝶の愛の花·豫寺蘭亭古今街道陸游(宋代)豫寺と蘭亭の古道と現代道。澄み切った霜の夜、湖畔の木々はすべ...
北宋時代の詩人黄庭堅の『羊飼いの少年詩』の原文、翻訳、注釈、鑑賞
黄庭堅の「羊飼いの少年の詩」、興味のある読者はInteresting Historyの編集者をフォロ...
ナンマンはなぜナンマンと呼ばれるのですか?三国時代の南蛮とは具体的にどの地域を指すのでしょうか?
南蛮はなぜ南蛮と呼ばれるのでしょうか?三国時代の南蛮とは具体的にどの地域を指すのでしょうか?よく分か...
『紅楼夢』では、薛宝才、林黛玉、賈牧らはどのようにして互いの間の亀裂を解決したのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
『紅楼夢』で賈廉と幽二潔の情事を知った後、王希峰は何をしたのでしょうか?
『紅楼夢』を読んで、王禧鋒に感銘を受けた人は多いでしょう。次は『おもしろ歴史』編集者が歴史物語をお届...
『太平広記』第358巻の「神訓一」の原文は何ですか?
龐阿媽、権力のある女性、無名の夫婦、王周、鄭其英、劉少友、蘇来、鄭勝、魏寅、斉彬の娘、鄭の娘、沛公、...
秦小公とは誰ですか?秦の孝公には何人の息子がいましたか?
秦の孝公(紀元前381年 - 紀元前338年)。『越傳書』では秦平王、『史記索隠』では屈良と記録され...
厳書の「清平月・金風和風」:この詩は『祝于辞』の有名な一節である。
顔叔(991年 - 1055年2月27日)、号は同叔、福州臨川県江南西路(現在の江西省臨川市)の人。...