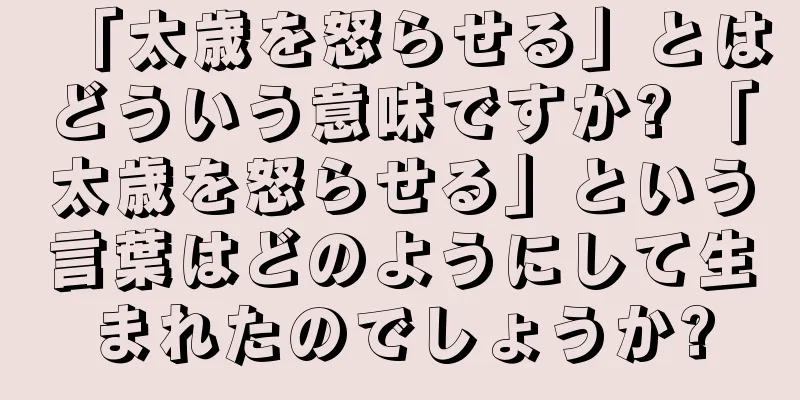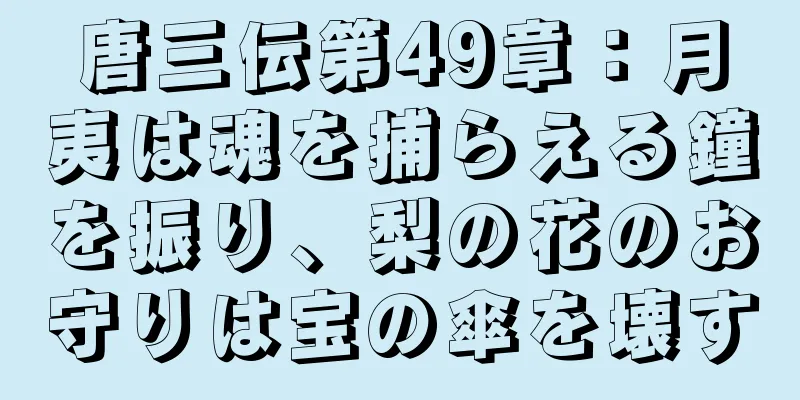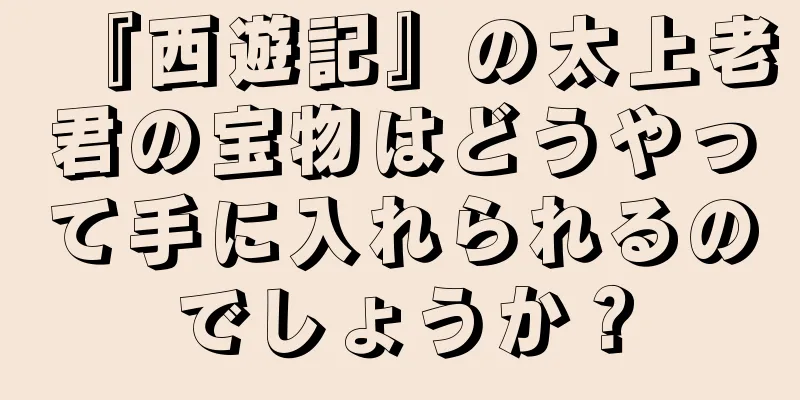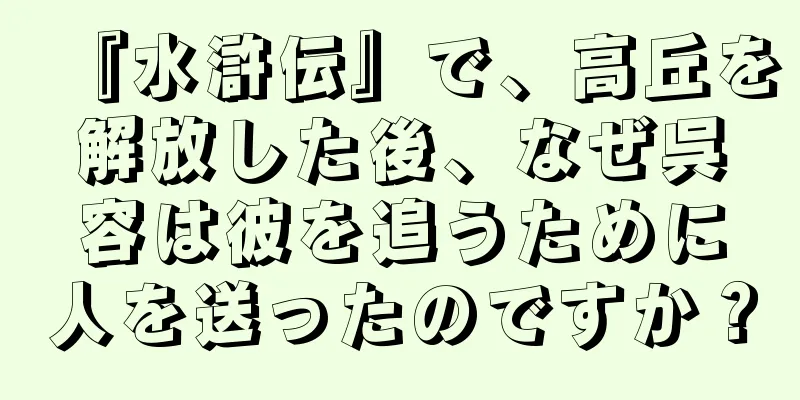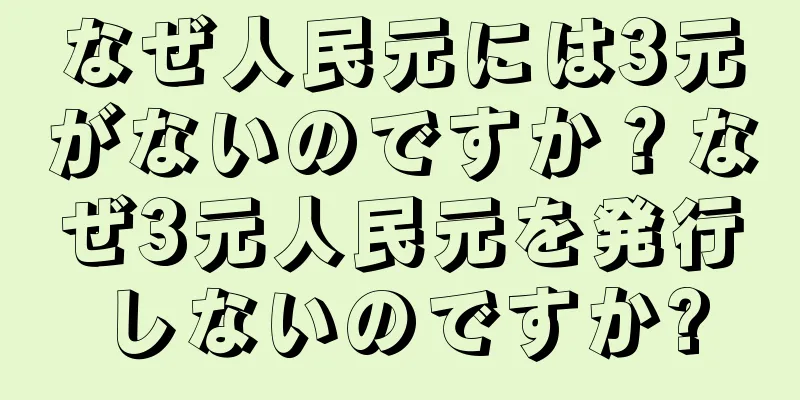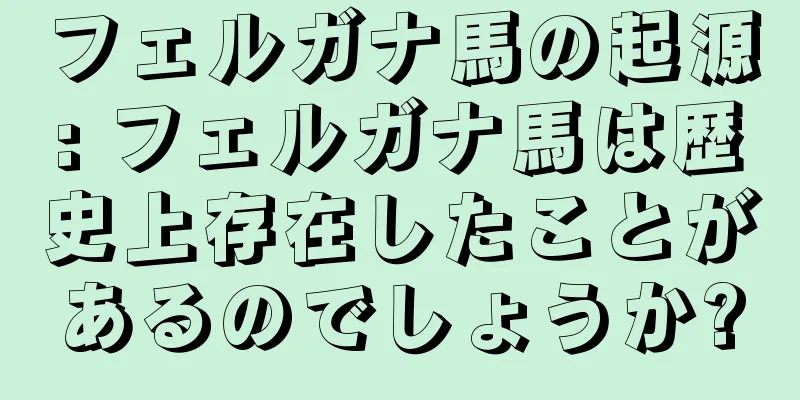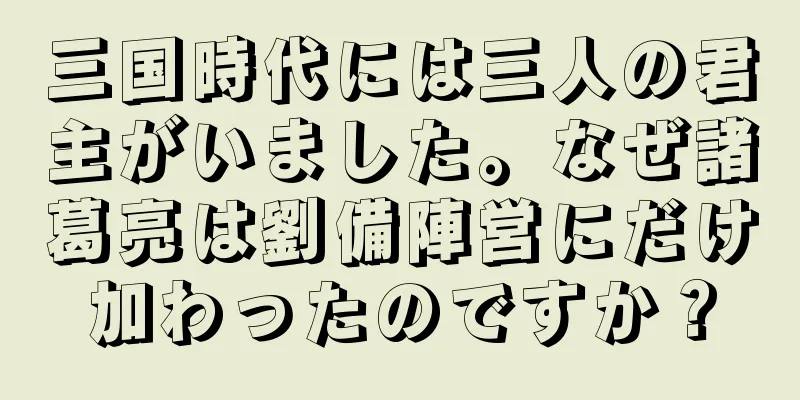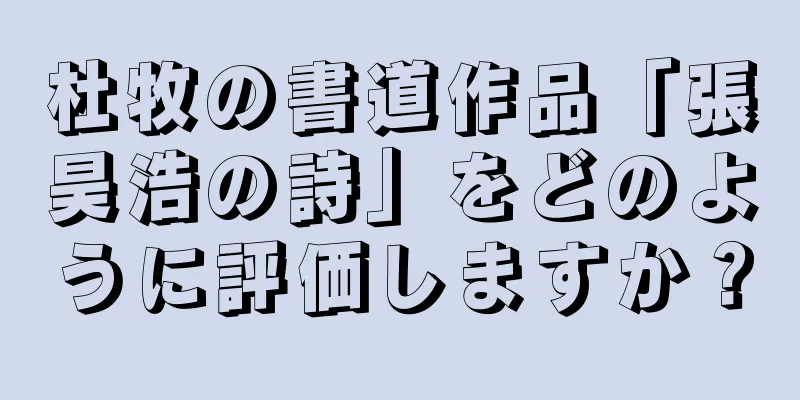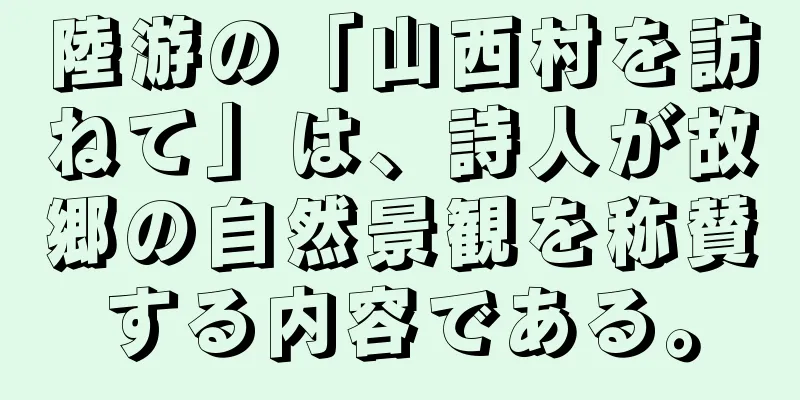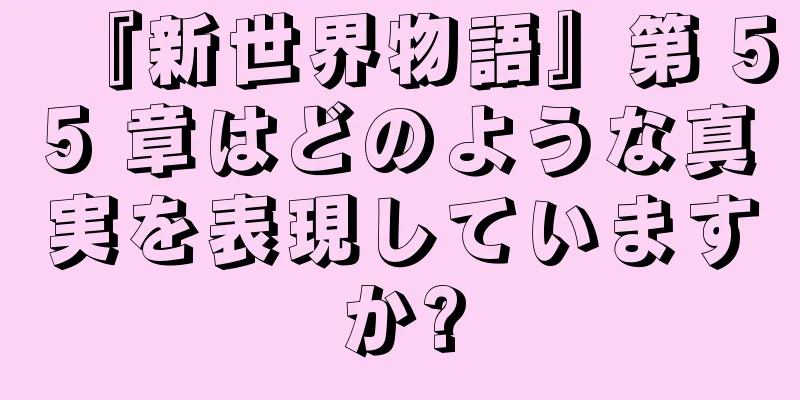西洋列強の攻撃に直面して、清朝が沈黙を守った一方で、日本が近代国家となったのはなぜでしょうか?
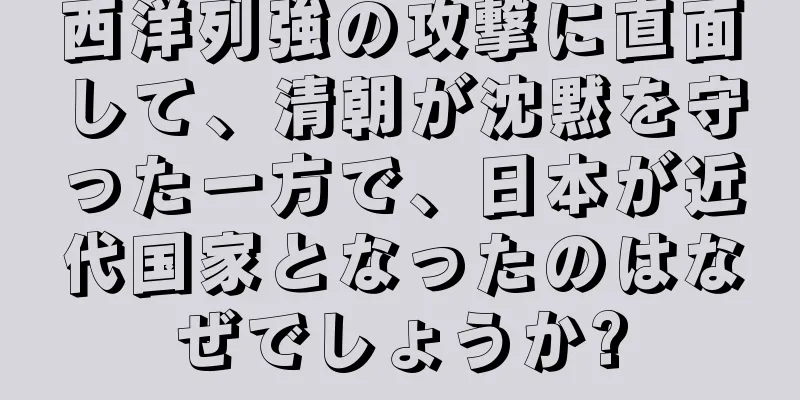
|
今日は、清国が躊躇していたのに日本が近代強国になれたのはなぜなのかをおもしろ歴史編集長がお伝えします。皆様のお役に立てれば幸いです。 19世紀半ば、西洋列強の圧倒的な力の影響を受けて、アジアの2つの鎖国国家、中国と日本は門戸を開き、近代化のプロセスを開始せざるを得なくなりました。ご存知のとおり、両国の運命はまったく異なっていました。 日本は急速に発展しました。西洋諸国が200年以上かけて成し遂げた産業革命を、日本人はわずか20年で成し遂げただけでなく、明治維新後、西洋の教育制度、政治制度、価値観を全面的に導入し、アジアで最も早い近代国家へと発展しました。 この点に関して、有名な現代歴史家スタヴリアノスはかつて、これは大きな例外であると嘆いた。「西洋以外の先住民が住む他のすべての海外地域がヨーロッパ列強の直接的または間接的な支配下に置かれたとき、日本人だけが征服される運命を免れた」。 中国の運命はもっと悲惨なものでした。当時の中国は、西側諸国の侵略と拡大に直面して反撃する能力がほとんどなく、主権を失って国を屈辱し、半植民地化という歪んだ発展の道を歩み始めたのです。この困難な時期は中国国民に「遅れをとれば負ける」という重大な教訓を残した。 もし中国がアヘン戦争後に日本のように近代化への挑戦を迅速かつ積極的に受け入れることができていたら、現代の悲劇を避けることができただろうか。日本の例から判断すると、理論的にその可能性が否定されるわけではない。しかし、歴史的事実は、中国も西洋化運動や1898年の改革開放運動など、一連の近代化改革を開始したものの、最終的には失敗し、ほとんど成果を上げなかったということです。 なぜ中国の近代化プロセスはこれほど遅く、停滞しているのでしょうか? 人々はこの問題について広範囲に研究と議論を重ね、清朝政府の腐敗と無能、盲目的な傲慢さ、鎖国政策による歴史的機会の喪失、封建的独裁制度の保守性と後進性、帝国主義の侵略による政治的抑圧と経済的略奪など、教科書に載っている標準的な答えを含む多くの答えを出してきました。 外国人学者の中には、部外者の観点から、独自の見解を述べる者もいる。例えば、日本の学者山本真氏は、中国の近代化が遅い理由として、以下の3つが最も顕著であると考えています。 まず、清王朝は征服者の王朝でした。満州人は人口の大半を占める漢民族を支配した。 山本晋の見解では、清朝はかつては成功していた。漢民族を味方につけ、北方の遊牧民をなだめ、二つの大きな問題を見事に解決した。しかし、清朝がぐっすり眠っていたちょうどその時、清朝が夢にも思わなかった第三の大きな問題が起こった。それは、清朝がどう対処してよいのか全くわからなかった近代西洋諸国からの挑戦であった。 状況が悪化するにつれ、征服王朝はますます不器用になり、以前の漢王朝よりも威信を失いました。彼らは、大多数の人々の側に立って国全体の利益を考慮するのではなく、自分の政権と自国の利益を維持することだけを考えるようになりました。 山本伸氏は「漢民族が建てた王朝であれば、全体を考えて先見の明のある人がいて、主導的な役割を果たしていたはずだ。明治維新が辛亥革命より50年も早かったのも、徳川幕府が大和民族が建てた政権だったからとも言える」とみる。 第二に、清朝の支配階級は戦士ではなく文官であった。 これは当時の日本とは非常に異なっていました。明治維新の主たる推進者は、主に中級・下級武士で構成された改革者達であった。西洋の強力な船や砲を前に、日本の軍事的不利にいち早く対応し、「富国強兵」政策を改革の重点とし、特に「軍備の強化」に力を入れました。文民統治の伝統が強い場所では、軍事的価値は最優先されません。 山本信はまた、中国の科挙制度は身分に関係なく人材を選抜する制度であり、世襲制よりはるかに優れていたが、伝統的な経典に通じ、科挙を経て高官となった者にとって、外国の知識や技術を受け入れることは容易ではなかったと指摘した。なぜなら、「西洋の学問」に目を向けることは、苦労して得た特権を放棄することに等しいため、彼らはしばしば保守的になったからである。 第三に、中国文明は長い間、比類のない絶対的優位性を維持してきたため、伝統的な文化を誇りにしており、新しい文明が出現して接触すると、傲慢になり、他の文明の優位性をまったく認めず、自らの後進性を直視して対応する対策を講じることもしません。 中国は、新たな資本主義産業文明の急成長に直面して、西洋文明の外に留まり、独自の文明を維持したいという消極的な抵抗姿勢をとった。しかし、日本は西洋文明に抵抗しても成功しないことを認識して、「脱亜入欧」という積極的な受容の姿勢を取り、西洋文明に浸り、彼らと同じ運命をたどった。 |
<<: 清朝時代の爵位の付与制度はどのようなものだったのでしょうか?どのような人に称号を与えることができますか?
>>: 昔の日本はどんな国だったのでしょうか?唐代の将軍の墓には、真実の状況を記した碑文が残されている!
推薦する
隋の初代皇帝である楊堅はどのようにして皇帝になったのでしょうか?その後、彼は誰に王位を譲ったのでしょうか?
隋の始皇帝である楊堅はどのようにして皇帝になったのでしょうか?その後、楊堅は誰に王位を譲ったのでしょ...
楚と秦の間の隔たりは何か?なぜ楚は秦を倒せなかったのか?
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日は、楚が秦に勝てなかった...
国を治めるのに優れた皇太子であった朱彪は、なぜ王位に就く日まで生きられなかったのでしょうか。
1368年初頭、朱元璋は英田州で自らを皇帝と宣言し、国名を明と名付け、皇帝の称号を洪武としました。朱...
『紅楼夢』で賈屋敷の元宵節に賈おばあさんはなぜ西仁を叱ったのですか?
賈祖母は、容邸と寧邸の「仁」世代の唯一の生き残りの先祖です。これについて話すとき、皆さんは何を思い浮...
北魏の改革の実際の指導者は誰でしたか?それは孝文帝の改革にどのような影響を与えたのでしょうか?
拓跋鈞は北魏の文成帝としても知られる。南北朝時代の北魏の第5代皇帝。太武帝拓跋涛の長孫、景武帝拓跋涛...
古代の王子と王女は、なぜ新婚初夜の前に王女と試し結婚をしたのでしょうか?
古代の王子と王女は、新婚初夜前に王女と試しに結婚した理由は何でしょうか。これは多くの読者が気になる疑...
『紅楼夢』で青文が扇子を引き裂いたのは一体何だったのか?真実は何なのか?
『紅楼夢』第31章「扇を裂いて千金の笑顔を」は、一見平凡な一節だが、明かされれば人々に衝撃を与えるだ...
「六策・虎の戦略・危機に立ち向かう」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
【オリジナル】武王は太公に尋ねた。「私は国境で敵と対峙しています。敵は来るかも知れないし、私は去るこ...
中国に伝わる十大名画の一つ「富春山居図」は何を描いているのでしょうか?
「富春山居図」は、元代の画家、黄公望が1350年に制作した紙に描かれた水墨画で、中国に伝わる最も有名...
『紅楼夢』の李婉はどんなキャラクターですか?
李婉は古典小説『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人である。次回はInteresting H...
皇帝にラベルを付けなければならないのなら、なぜ宋の真宗皇帝が最も迷信深いのでしょうか?
皇帝に名前を付けるなら、宋の真宗皇帝が最も迷信深い皇帝に違いありません。宋の真宗皇帝の治世中に、大規...
烏孫の坤密の公式の立場は何でしたか?なぜクンミを大クンミと小クンミに分ける必要があるのでしょうか?
クンミはクンモとも訳され、古代中国の西域にあった烏孫王国の名称です。 漢の宣帝の甘暦元年以来、烏孫に...
清朝の時代、中国はすでに西洋に遅れをとっていました。「康熙・乾隆の繁栄の時代」は今でも繁栄の時代と言えるのでしょうか?
清朝時代、中国はすでに西洋に遅れをとっていました。「康熙乾隆の繁栄時代」は今でも繁栄の時代と言えるの...
七剣十三英雄第40章:老婆は死の危機に瀕した沈三郎を罠にかけるために策略を練る
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
唐代の楊居源の『何連秀才楊柳』は、春風を使って友人との別れを表現している。
楊居元は、字を荊山、後に聚吉と改めた唐代の詩人である。史料によると、詩人楊居元は、白居易、袁真、劉毓...