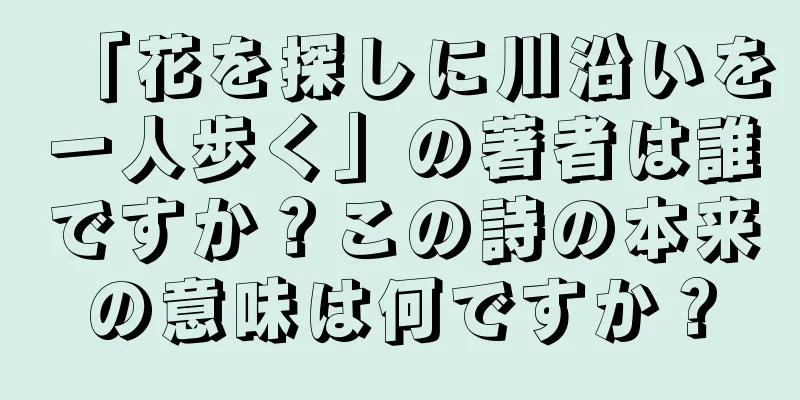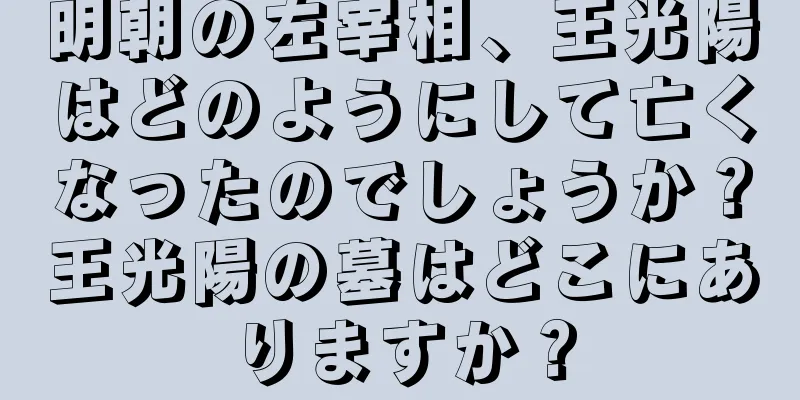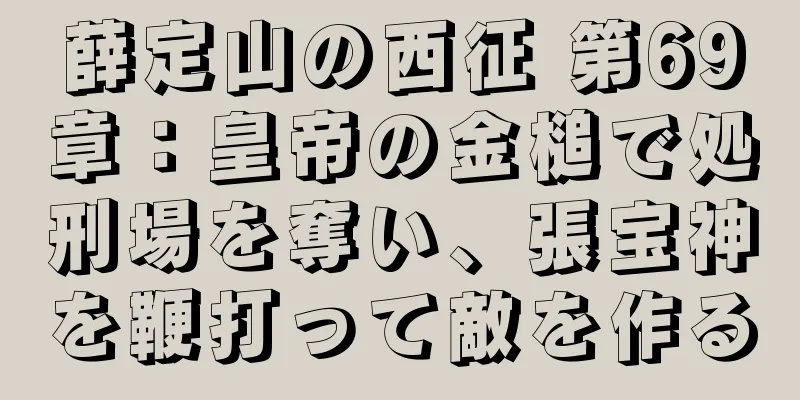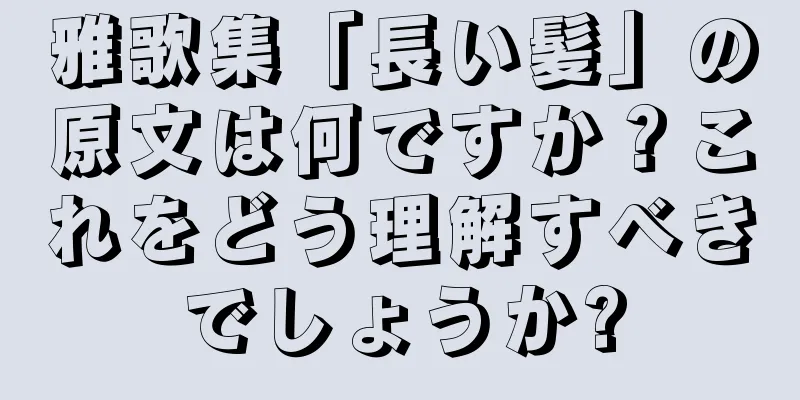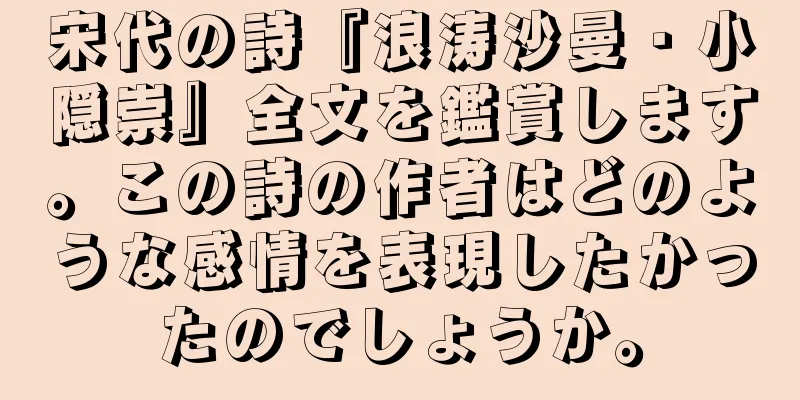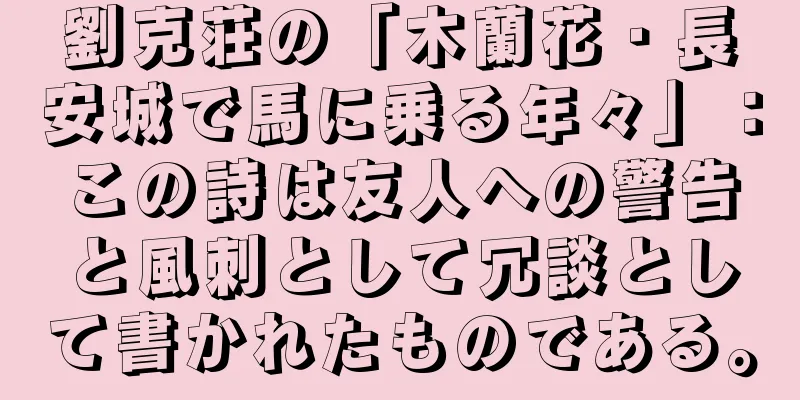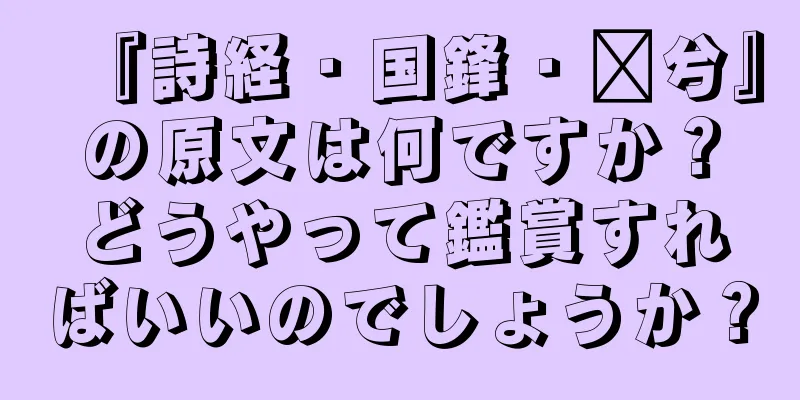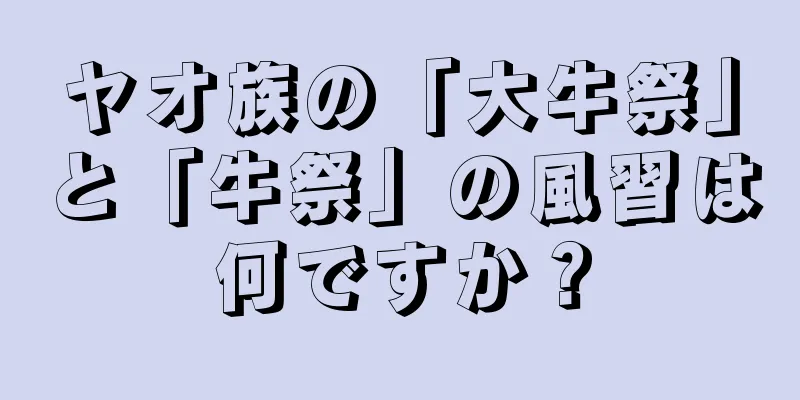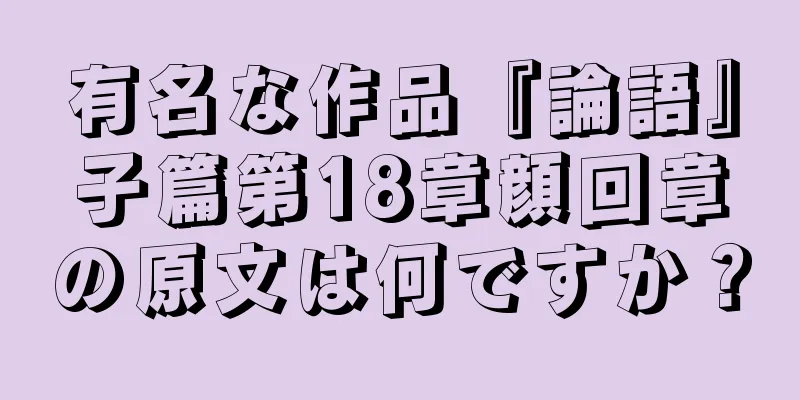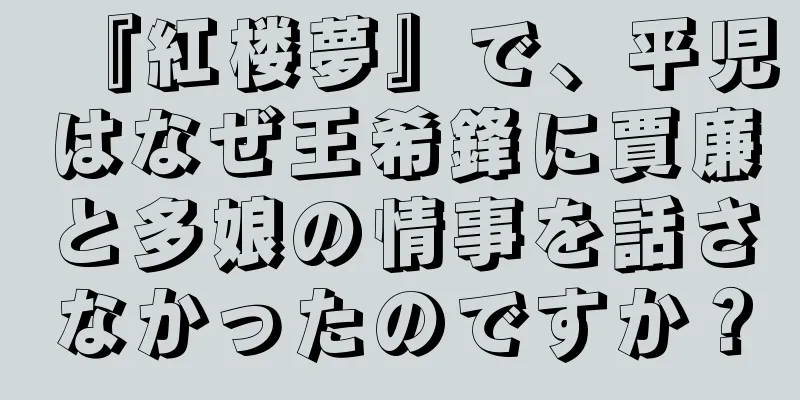古代の科挙の名称はどのように分けられていたのでしょうか?
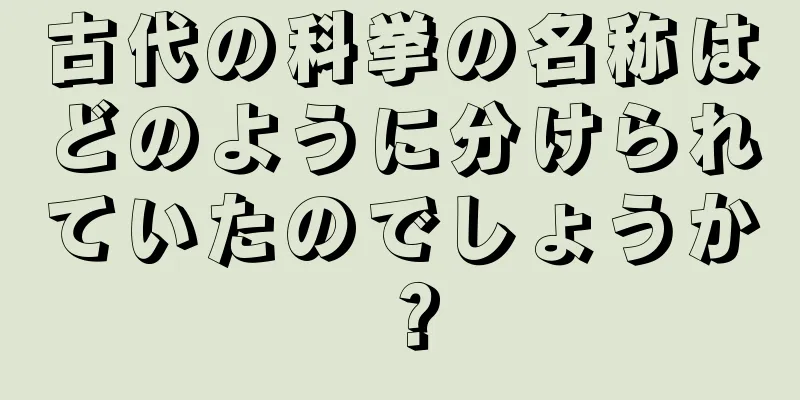
|
古代の科挙では、先勝、秀才、公勝、増勝、扶勝、林勝、十人、進士、さらには譚化、方眼、荘園などの称号を見ることができます。実は、これらの名前は古代の科挙試験で受験者が得た栄誉のレベルを表しています。 上記の称号の意味は、王朝によって異なる。清朝の場合、上記の称号を理解するには、まず同勝について話す必要がある。 通勝:年齢に関係なく、県試と県試に合格したが学者試験にまだ合格していない、科挙試験のために勉強するすべての学者を総称して通勝と呼びます(つまり、学者になるには、まず通勝にならなければなりません)。 向生:学院の試験に合格した学生、学生とも呼ばれ、一般的には学者とも呼ばれます。郡立学校から入学した「易学生徒」と県立学校から入学した「准学生徒」が含まれます。学校名は湘なので、顧は湘生と呼ばれます。 「庠」という単語は「祥」と同じ発音で、「扬」ではないことに注意してください。先ほど見た会話では、「庠生」が人の名前として誤って読まれていましたが、これも「扬生」と誤って読まれていました。 学者:定義は王朝によって異なります。 明代の学者とは、郡校や県立学校に合格した学生、つまり学生のことでした。そのため、「秀才」は「香生」の別名でもあります。 しかし、清朝時代の学者になるための試験は非常に厳しく、郡試験と県試験に合格した後、学者試験に合格しなければなりませんでした。そうして初めて、その人は学者と呼ばれることができるのです。アカデミーの試験は皇帝が任命したアカデミー会員によって主宰されなければならない。大学入試で1位を取ることを「安勝」といいます。 学者試験に合格すると、立ったまま郡知事と話すことができ、皇帝の奉仕を免除され、処罰されないなどの特権が与えられました。しかし、学生は毎年試験を受けなければならず、試験に不合格になった学生は叱責、警告、さらには退学処分を受けることもあります。 奨学生は、政府奨学金を受ける学生、追加奨学金を受ける学生、追加奨学金を受ける学生の 3 つのカテゴリーに分けられました。 官費留学生とは、年試と科挙の両方で優秀な成績を収めた学者を指します。このうち、学生(現在の小役人のような)には政府が毎月奨学金を支給しており、いわゆる「給費生」と呼ばれていましたが、給費生の人数は限られていました。そして、表彰学生として選ばれる資格があります。 「増勝」とは、年ごとの試験や科挙の成績が官費留学生に次ぐ者を指す。政府は食費補助金を出さない(筆者はふと、現在の公務員制度外の臨時職員を思い浮かべた)。この部分は主に、学者が増え、学校に通いたい人が増えたが、政府の奨学金を受けている学生の数は限られているため、一定数の学生が追加されました(現在の入学者数の増加)。この部分の学生を政府の奨学金を受けている学生と区別するために、彼らは「曽光学生」、つまり「曽生」と呼ばれています。 学生数が増え続けるにつれ、追加の学生が入学し、学生の末尾に追加されました。彼らは「付属学生」または「付属学生」と呼ばれました。 官費留学生や追加留学生の定員は決まっていたが、附属留学生の数に制限はなかったため、儒学に初めて入学した学生はすべて附属留学生と呼ばれるようになった。その後、選考を経て、附属学生の中から奨学生および追加学生を募集します。 公生とは、県、州、県、さらには省などの地方政府から朝廷に推薦され、教育当局によって選抜され、特に成績が優秀で皇室学院の学生となる学生のことです(笑。北京大学や清華大学が推薦した学生です)。しかし、皇学院の他の学生とは異なり、公勝は正当な学生でした(金で買収されたわけではありません。つまり、皇学院には金で地位を買収した学生もいたということです)。公生は、さらに勉強するために都の大学に送られ、卒業後は人事部によって郡守、県知事、講師などの官職に任命された。そのため、大学に入学した公生は公監とも呼ばれた。 公勝は、十人衆の悪徳リストに相当します。公勝は、水公、允公、有公、八公、利公に分かれています。 年貢: 毎年または数年に一度、県、州、郡は政府の奨学金を得て1人または2人の学生を選び、帝国学院で学ぶよう首都に推薦することができた(北京大学と清華大学の推薦学生も参照)。これは「年貢」と呼ばれた。 エンゴン:国家的な祝賀行事や即位の勅旨があるとき、その年に進貢学生となる者を全てエンゴンと呼ぶという意味です。 秀貢:各省は3年ごとに、品性や学業成績が優秀な学者を選抜し、省教育長の評価と知事の推薦を経て、2~6名の候補者を都に送り出す。科挙に合格した後、成績が優秀な者は一級県令に、二級県令は教師に、三級県令は研修官に任命される。彼らは「秀貢」と呼ばれる。 選抜された貢進生:礼部は候補者に科挙を受けるよう推薦し、一位または二位になった者は保河殿で再試験を受ける。一位または二位になった者は都の七等小官、または県知事、教師に任命される。 副貢学生とは、地方試験において陪人に加えて副貢名簿に登録された者であり、彼らは貢学生となって帝国学院で学ぶことが許される。 慣例の朝貢:礼部は朝貢学生を科挙に選抜するよう勧告する。一位または二位の者は保河殿で再試験を受ける。成績が優秀で一位または二位の者は都の七等小官、または県知事、教師に任命される。 十連:地方の試験に合格した学者。省の試験は3年ごとに、子、毛、呉、幽の年の8月に行われました。秋に行われたため、「秋の試験」と呼ばれていました。各州の学者は州都の帝国学院に集まって試験を受けたが、すべての学者が受験資格を得たわけではなく、州や郡の教育官が実施する科挙で1位、2位、3位になった者だけが受験資格を得た。 省級試験に合格した者のうち、1位は結院、2位は雅院、3位から5位は静奎、6位は雅奎、7位以下はすべて文奎と呼ばれました。 公師:科挙に合格した人は公師と呼ばれました。 合同試験は通常、地方試験の翌年の 3 月に、礼部が主宰して行われ、一般に「春季試験」と呼ばれていました。公師の資格を取得して初めて、試験の最終段階である宮廷試験を受けることができます。 壬氏:宮廷試験に合格した学者は壬氏と呼ばれました。宮廷試験の等級は一級、二級、三級に分かれています。宮廷試験に参加するすべての受験者をリストアップできます。 一級一位は首席学者と呼ばれ、進士の称号が与えられます。 2位は方眼、3位は丹花と呼ばれ、両者とも進士の称号を授けられた。二等壬氏には壬氏という称号が与えられ、一等壬氏には川禄、三等壬氏には壬氏という称号が与えられた。 |
<<: なぜ準優勝者は3位ほど有名ではないのでしょうか?どんな人が3位になれるのでしょうか?
>>: 武則天はどんなキャラクターを創造しましたか?なぜ後世では使われないのでしょうか?
推薦する
杜甫の「君子哀歌」:詩全体は詩人が見聞きした情景と感情を描写している。
杜甫(712年2月12日 - 770年)は、字を子美、号を少陵葉老といい、唐代の有名な写実主義詩人で...
司馬一族は曹魏政権を掌握した後、1世紀に渡る混乱をどのように終わらせたのでしょうか?
三国志の後の王朝は、司馬一族によって建国された、歴史上西晋として知られる晋王朝です。司馬一族は曹魏か...
『紅楼夢』の大晦日から旧暦1月15日まで、賈府はどれほど賑やかですか?
『紅楼夢』に描かれている賈邸は、社会的地位が非常に高い貴族の邸宅です。 Interesting Hi...
ケインリングとは何ですか?ケインリングを発見したのは誰ですか?
ケイン リングとは何ですか? ケイン リングを発見したのは誰ですか? 興味のある読者は編集者をフォロ...
「英を悼む二つの詩」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
英を悼む二つの詩陸游(宋代)商王朝と周王朝の統治が最も長く、一方北方の斉王朝と晋王朝は勢力を競ってい...
ユンジンはどのように進化し、発展したのでしょうか?最も古い時代はいつまで遡れるのでしょうか?
南京錦の誕生と発展は南京の都市史と密接な関係があり、南京の絹織物産業は三国時代(西暦222年 - 2...
「百悩集」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
白有吉興杜甫(唐代)私が15歳のとき、心はまだ子供で、再び走り出す黄色い子牛のように力強かったことを...
戦争に最も長けた皇帝は誰ですか?最も強い軍事力を持っているのは誰ですか?
古代のどの皇帝が最も戦争に長けていたかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting...
皇帝は毎日どんな食べ物を食べていたのでしょうか?お料理は何品ありますか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、皇帝が何を食べているかについての記事をお届...
宋代の詩「千秋随・梟の鳴き声」を鑑賞、この詩はどのような場面を描いているのでしょうか?
宋代の張邊が書いた『千秋随・梟の声』について、次の興味深い歴史編集者が詳しい紹介をお届けしますので、...
封建領主の分離主義政権はどの王朝に属していましたか?軍事総督による分離主義統治はどのようにして始まったのでしょうか?
封建領主の分離主義政権はどの王朝に属していましたか?唐代の安史の乱の後、中央政府が弱体化し、諸侯が力...
襄公7年に古梁邇が書いた『春秋古梁伝』には何が記録されていますか?
古梁邁が書いた『春秋古梁伝』には、襄公七年に何が記されているのでしょうか?これは多くの読者が気になる...
周の景帝が即位した後、楊堅は王位を簒奪するためにどのような準備をしたのでしょうか?
楊堅はどのようにして北周の景帝を退位させたのか?楊堅が最終的に皇帝になれた根本的な理由は何だったのか...
なぜ李斯は義理の息子である扶蘇を助けようとしなかったのでしょうか?趙高はどうやって彼を脅したのですか?
秦は世界を統一し、中原を平定した最初の王朝であり、多くの人々が秦王朝がもっと長く続くことを願っていた...
孟浩然は長安の優秀な学者と競争し、二行の詩で相手を負けさせた。
孟浩然は長安で優秀な学者と競争しましたが、2行の詩で敗北を確信しました。この詩は有名な「破文」です。...