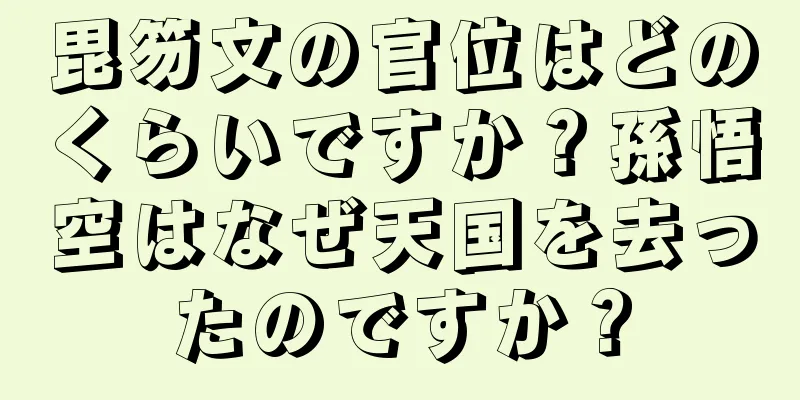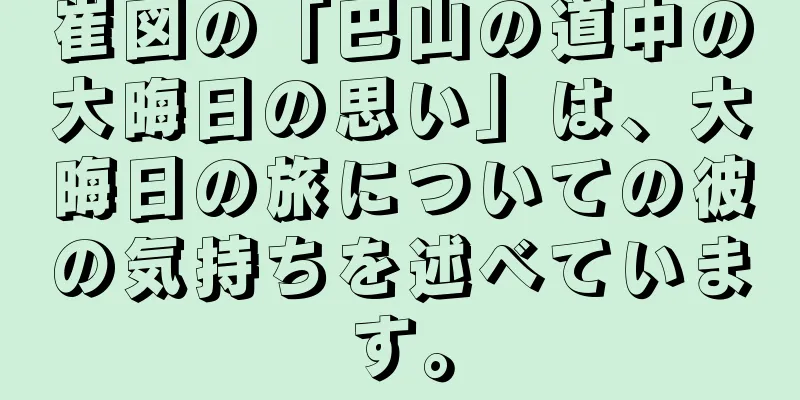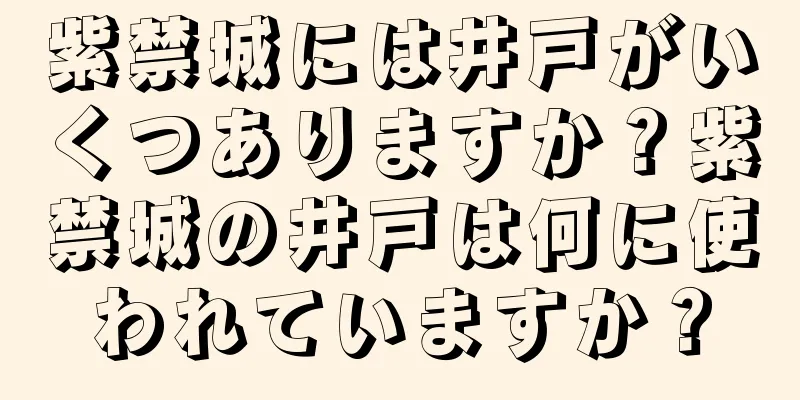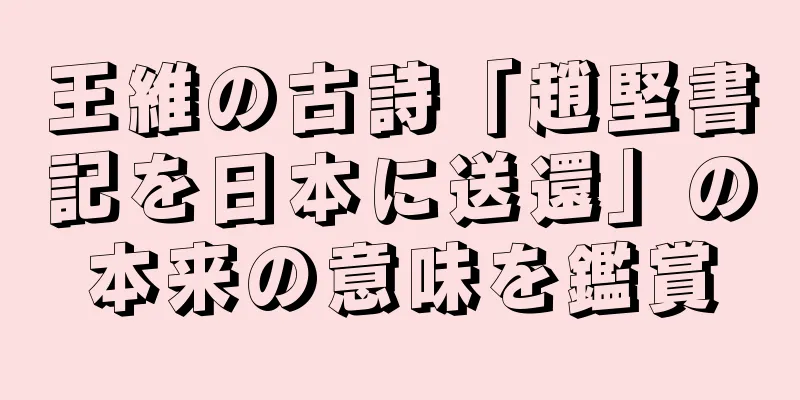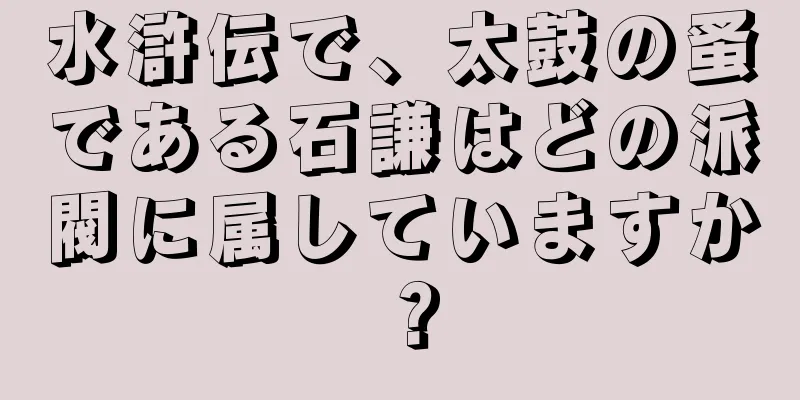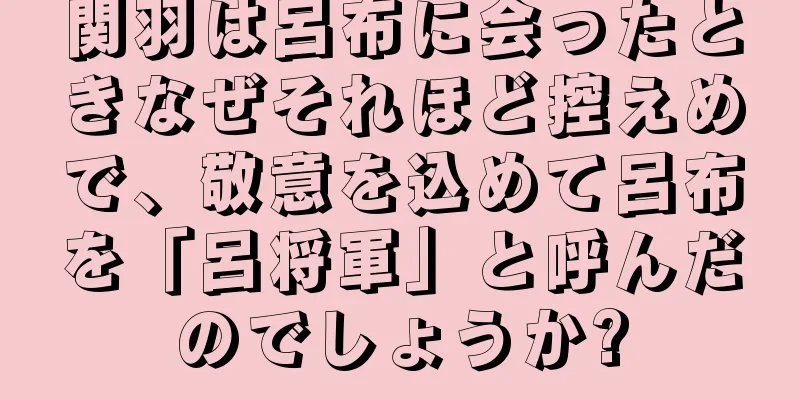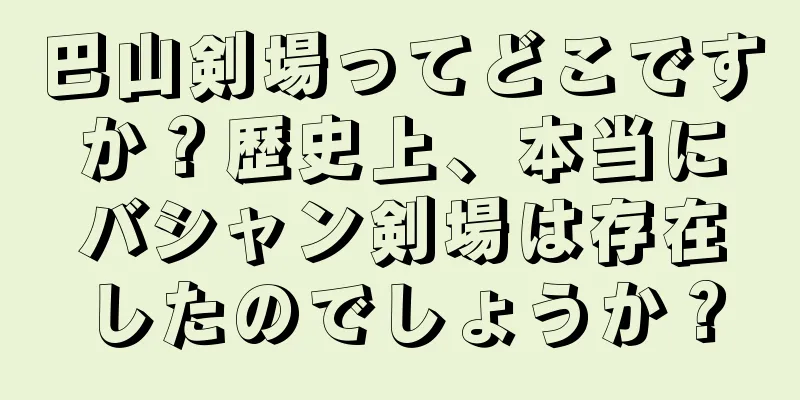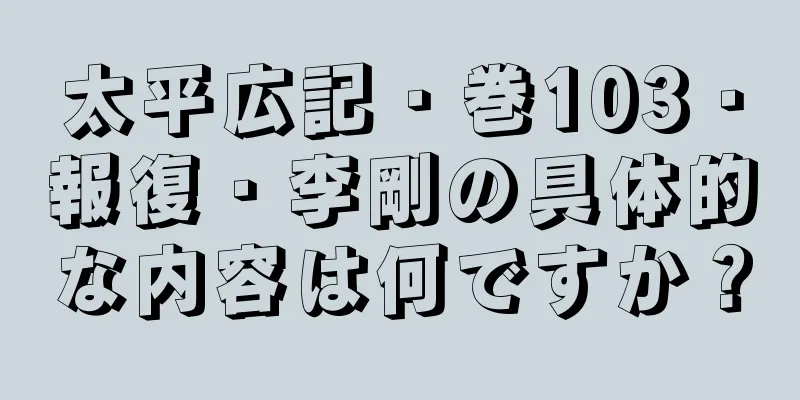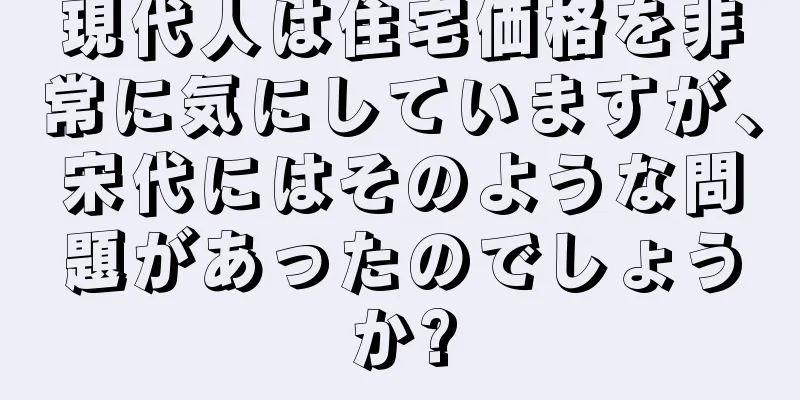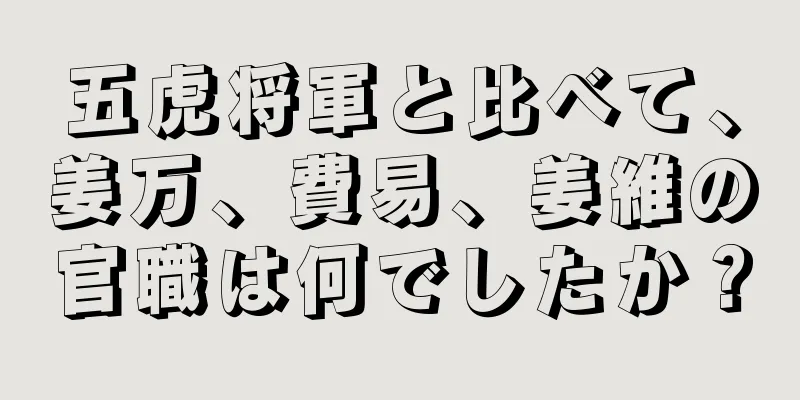なぜ蘇澈は道教を信じたのでしょうか?蘇澈と道教の関係は何ですか?
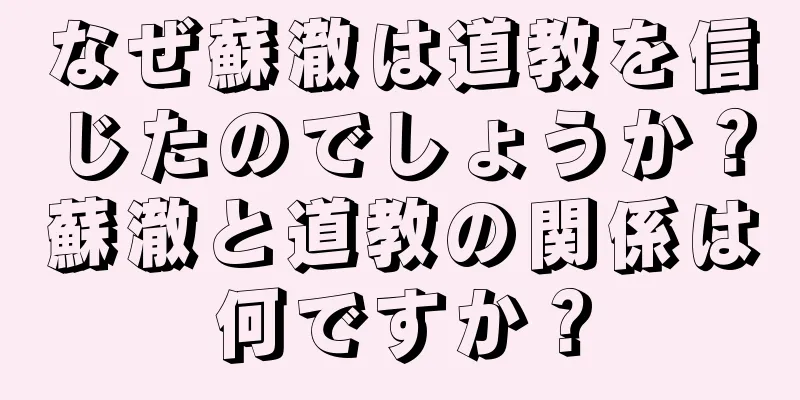
|
道教は私の国に固有の宗教です。その始まり以来、数え切れないほどの信者がいます。偉大な詩人である李白も道教を疑いなく信じ、何度も杜甫を連れて仙人を探したり、魔法の薬草を掘ったりしていました。李白の他に、道教を信仰したもう一人の偉大な作家がいました。それが蘇哲です。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 唐宋の八大師の一人である蘇哲の兄は蘇軾です。蘇哲が道教を信仰したのは蘇軾と大きく関係していますが、蘇哲は蘇軾よりも道教に熱心で、生涯を通じて道教と切っても切れない関係でした。 蘇澈は幼い頃に兄の蘇軾の影響で宗教に改宗したが、すぐに奇妙なことに遭遇した。蘇澈はかつて重い病気にかかっていました。多くの名医を招きましたが、病気はなかなか治りませんでした。ついに道士がやって来て、蘇澈に秘法を処方し、病気は治りました。 古代の道教徒は基本的に全員、何らかの錬金術を学んでいました。錬金術の原理の多くは伝統的な中国医学の原理と同じであるため、偉大な道教徒の多くは病気の治療にも優れていました。蘇哲が真に道教を心から信じるようになったのはこの頃でした。 それ以来、蘇澈は道教の経典『包朴子』を熱心に研究し、そこから錬金術とも呼ばれる黄白書を学び、自らの知恵と才能で不老不死の薬を作る炉を作り、蘇澈はそれを不老不死の薬と呼んだ。 しかし、実際には、この世に不老不死の薬は存在しません。蘇澈が作った不老不死の薬は、伝統的な漢方薬と同じように、複数の成分を混ぜ合わせたものです。病気の治療には役立ちますが、不老不死は絶対に不可能です。 『孫公譚譜・第2巻』には、その後蘇澈が再び仙薬を作り始めたことが記録されている。火をつけようとしたとき、閉ざされた部屋に突然大きな猫が現れた。猫はストーブの上に立っていたが、すぐにストーブの中に飛び込んで姿を消した。 蘇澈はすぐに火を起こすのをやめた。これは、この技があまりにも強力で、自分はそれを後世に伝える資格がないという神の警告だと考えた。そのため、彼はそのことについて二度と口にしなかったが、神が自分の才能に嫉妬しているのだと思い、少し自己満足していた。 錬金術の作業が完了して間もなく、蘇澈は別の奇妙な男と出会い、彼の伝記「乞食趙公伝」を書いた。当時、蘇澈は路上で趙勝という名の乞食に出会った。彼は狂っていて、少し済公に似ていたが、彼と注意深く会話を交わすうちに、趙勝が単純な人物ではなく、特に道教について多くの知識を持っていることが分かった。 蘇軾も道教を信仰していたため、蘇哲は趙勝を蘇軾に紹介した。趙勝は黄州で蘇軾のもとに半年以上滞在した。その後、蘇軾が北に戻ると、趙勝は興国に逃げ、地元の軍知事楊慧に引き留められた。 その結果、間もなく趙勝は飼っていたラバに蹴られて死亡し、楊慧は彼をその地に埋葬した。これを聞いた蘇哲もまた感極まった。 数年後、蘇哲と蘇軾の兄弟は首都に戻り、法真という古い友人に会いました。会話の中で、法真は蘇哲に、少し前に雲安で乞食に会ったこと、そしてその乞食が蘇哲に挨拶の手紙を届けてほしいと頼んだことを話しました。 蘇澈は晩年になってもこの物語に執着し、わざわざ書き記した。ある年、ある都市の中学入試問題に選ばれたほどだ。しかし、よく考えてみると、死者は生き返らないし、蘇澈の言ったことは少し誇張されているかもしれない。確かに趙勝のような人物はいたが、彼には絶対にそのような超能力はなかった。蘇澈は芸術的な手法を使って、趙勝を通して道教への憧れを表現しただけだったはずだ。 蘇哲は人生の後半に道教文化を研究し、それに関する詩を書いた。例えば、『老子』を深く理解した後、蘇哲は『老子街道』を著し、その中で当時の多くの新しい思想と伝統的な理論を組み合わせ、『道徳経』がそれほど退屈で理解しにくいものではなくなった。執筆後、蘇哲はそれを特別に蘇軾に渡して校閲させ、蘇軾はそれを高く評価した。 しかし、後世の朱熹は蘇哲の著作を嘲笑し、蘇哲が儒教を侮辱したと考えました。しかし、これは蘇哲の著作が下手だったということではなく、彼らの見解に矛盾があったということです。蘇哲は道教に基づいて儒教を統合しましたが、朱熹はその逆でした。 また、蘇哲は道教に関する詩も数多く残しており、「上清慈」「樓観」など十数編の詩が記録されている。しかし、この点では蘇哲の著作は兄の蘇軾の著作にはるかに劣る。道教思想の影響を受けて蘇軾が著した「丁風波」は、今もなお代々受け継がれてきた傑作である。 |
<<: 蘇哲と蘇軾の類似点:二人は同じ科挙の進士であり、同じ王朝に仕えた。
推薦する
なぜ李婉ではなく鳳傑が栄果屋敷を管理しているのですか?
なぜ李婉ではなく馮姉さんが栄果邸の長なのですか?王夫人は無能な人物であり、高齢であったため、広大な栄...
隋の建国以来、古代の科挙において学者はどのような役割を果たしたのでしょうか?
隋代に確立されて以来、科挙制度は発展を続け、官吏採用のための完全な制度を形成し、通勝、秀才、居人、公...
伝統的な中国のアーチェリーと現代の西洋のアーチェリーの違いは何ですか?
古代ギリシャを10年間学び、古代中国を10年間学ぶ。これが私が入学したときの願いでした。残念ながら、...
曹植、曹操、曹丕は総称して「三曹」と呼ばれています。彼の文学と芸術における功績は何ですか?
曹植の代表作には『洛河女図』『白馬図』『七悲歌』などがある。後世の人々は、曹操と曹丕の文学的才能から...
易碩の紹介 歴史上唯一の女性皇帝医師、易碩の伝説的な生涯
易碩は漢の武帝の時代には河東の人であったが、現在は永済の人である。彼女は中国史上初めて記録された女性...
黄景仁の有名な詩句を鑑賞する:長考は尽き、残った繭は引き抜かれ、バナナの葉を剥いた後に心は傷つく
黄景仁(1749-1783)は清代の詩人であった。号は漢容、別名は鍾沢、号は呂非子。楊湖(現在の江蘇...
『楚科派安経記』初版第七巻:唐の明皇は道教を好み、異能の人を集め、呉慧妃は禅を崇拝し、異能の手段と戦った。
『楚科派安経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。この本は、一般大衆に人気のある「疑似...
清朝の康熙帝の治世中にロシアとどのような外交関係が確立されましたか?
康熙帝の治世中、侵略してきたロシア軍を追い出すために鴨緑江の戦いが2回組織されました。清政府はロシア...
山鞭と老君山に関する神話と老子に関するいくつかの神話
甘山鞭と老君山の神話的物語:鹿邑城の東門内には、高さ 39 フィートを超える老君台地があり、台地の頂...
馬志遠の「首陽曲江空夕雪」:作者の「小湘八景」組曲の一つ
馬志遠(1250年頃 - 1321年 - 1324年秋)は、東麗とも呼ばれ、大渡(現在の北京、身元を...
孟子:李楼第2章第31節原文、翻訳および注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
呉維也の『人江紅・算山懐古』:作者は悲劇的で緊張した気分で書いた
呉衛野(1609年6月21日 - 1672年1月23日)は、雅号を君公、号を梅村といい、陸喬生、観音...
「大理王国」は本当に歴史上に存在したのでしょうか?大理王国とはどんな国だったのでしょうか?
「大理王国」は歴史上に本当に存在したのか?大理王国とはどんな国だったのか?『おもしろ歴史』編集者が詳...
『太平光記』第385巻「転生11」の登場人物は誰ですか?
崔紹新娥 陳燕仙崔紹崔紹は毗陵王玄威の曾孫であった。彼の曽祖父の呉氏はかつて桂林で働いていた。彼の父...
楚国はそれほど強大だったのに、なぜ秦国によって滅ぼされたのでしょうか?
第一に、楚国が参加した戦争が多すぎ、規模が大きすぎたことです。紀元前506年は楚国にとっての転機と言...