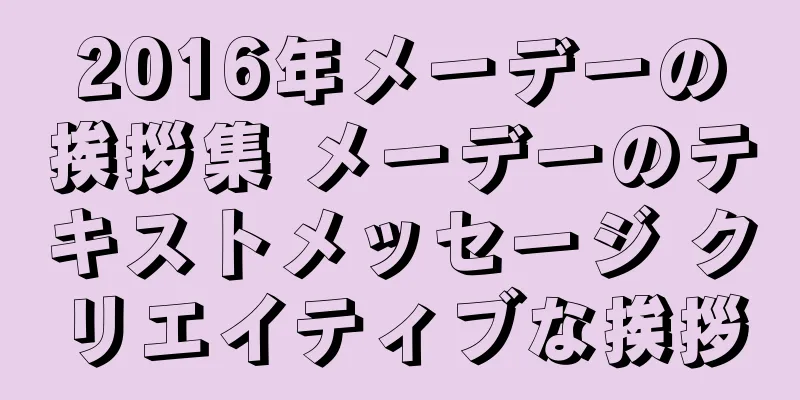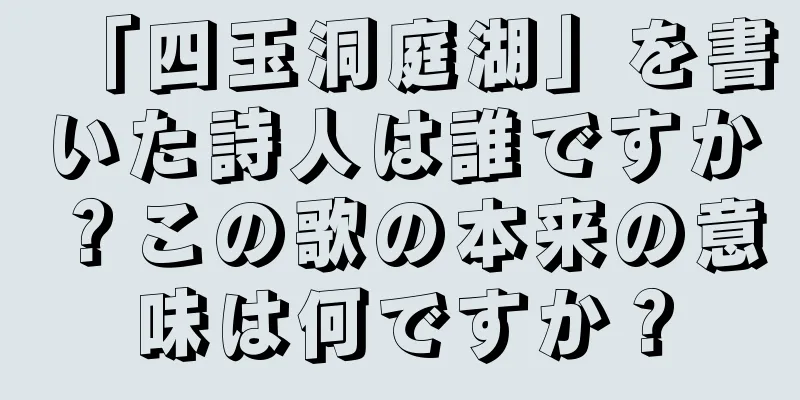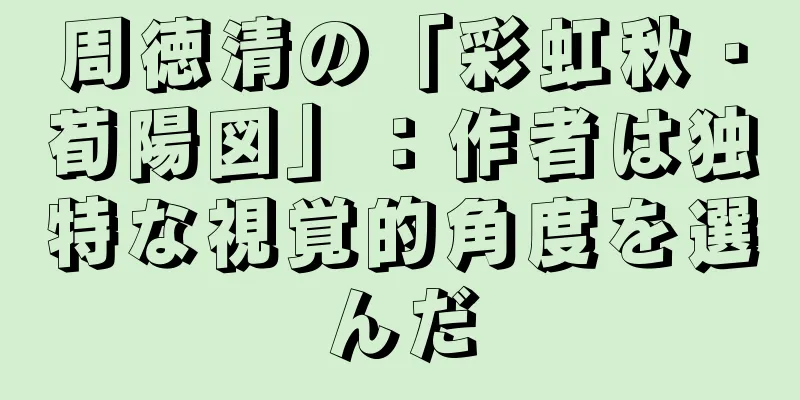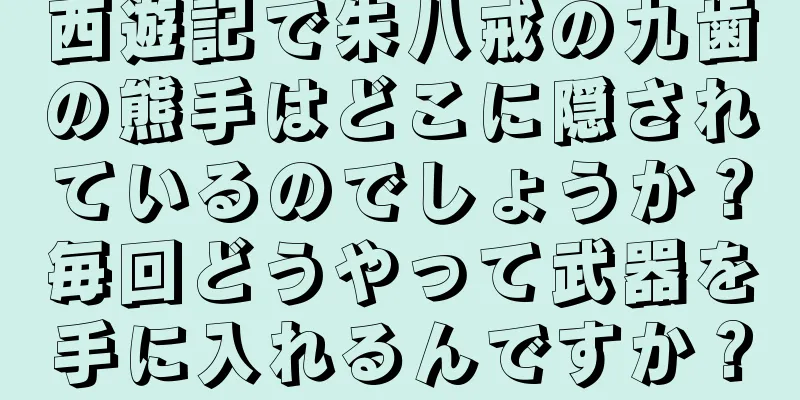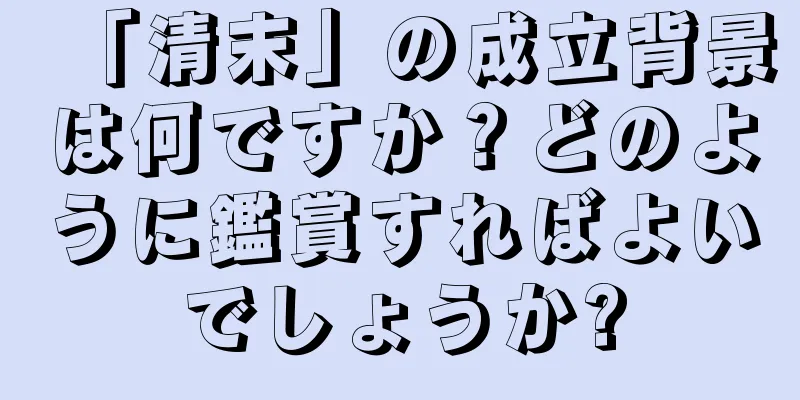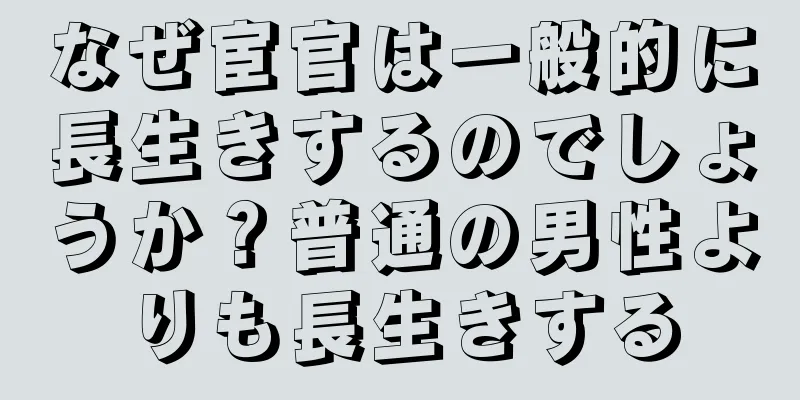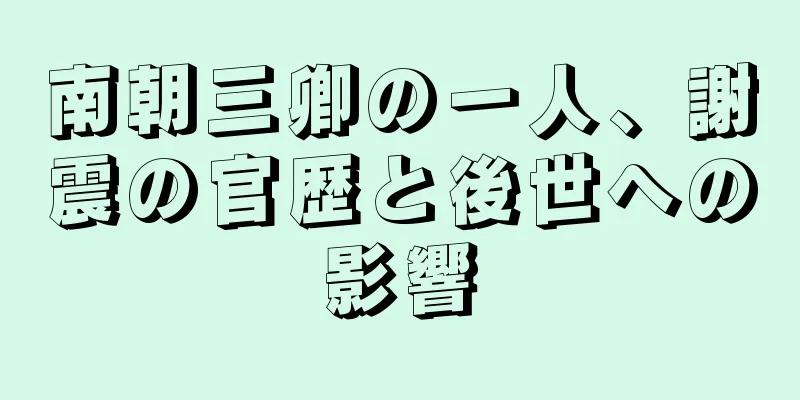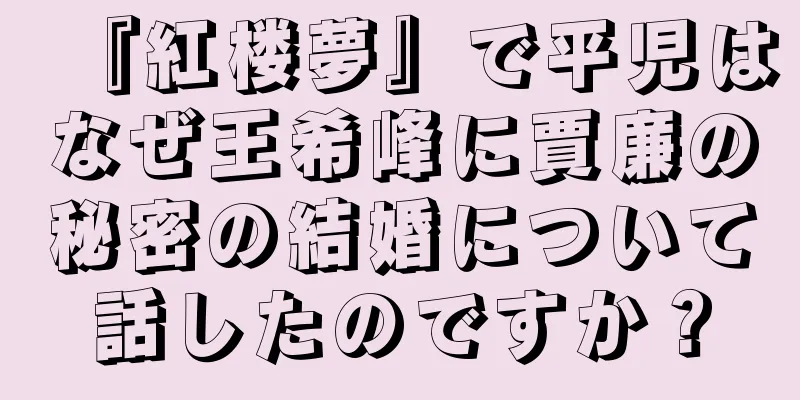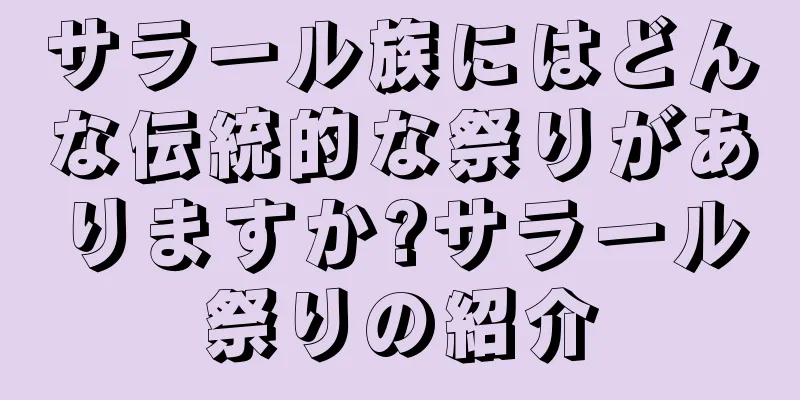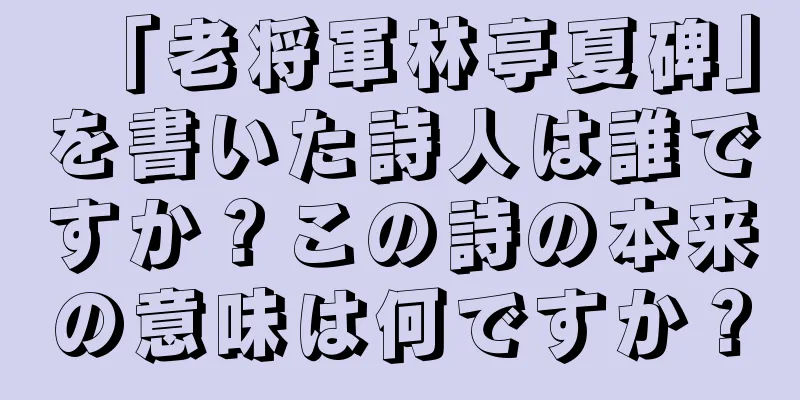なぜ趙匡胤は「一杯の酒のために武力を放棄する」という大胆な行動に出たのか?彼は勇敢な将軍たちが反乱を起こすことを恐れていないのでしょうか?
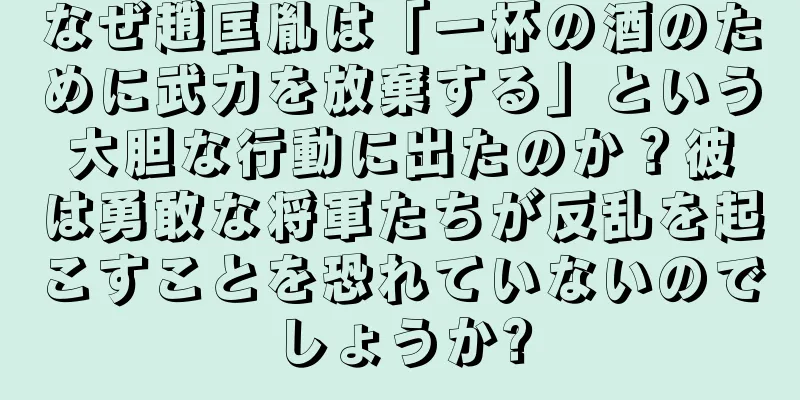
|
趙匡胤は陳橋の乱を経て宋王朝を建国したので、当然軍事力の重要性を理解しており、即位後は属国の勢力を弱めることに着手した。 「一杯のワインを飲みながら軍事力を解放する」というのは、このような状況で起こったことだ。歴史の記録によると、趙匡胤は宴会を利用して功績のある役人たちを脅迫し、賄賂を渡して自発的に軍事力を譲らせたとされています。後の政治戦略に関する書物はこれを引用して、趙匡胤の優れた政治戦略を称賛しています。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 実際、五代時代の中央政府は地方政府よりわずかに強力であっただけで、地方の分離独立政権は頻繁に反乱を起こし、中央政府に取って代わるものもありました。 「酒杯武力解放」事件は趙匡胤が即位した2年目に起きた。宋朝の情勢が安定し始めた頃、彼は功臣たちの武力を剥奪するこの時期を選んだ。彼は勇敢な将軍たちが反乱を起こすことを恐れなかったのだろうか? まず、趙匡胤は優れた軍事的、政治的才能を持っていました。 五代時代には様々な小王朝が樹立され、血と野蛮さに満ちていた。簡単に言えば、より大きな拳を持つ者が王座に座るのです。しかし、趙匡胤の権力の掌握は、綿密で慎重な計画の結果であり、彼は好機を捉えて致命的な行動を取り、非常に短い期間で後周の軍事力を掌握し、権力を掌握する過程で流血はほとんどなかった。宋朝が成立した後、李雲と李崇進による反乱が起こったが、趙匡胤は自ら策略を巡らし、短期間で反乱軍を鎮圧した。この 2 つの点だけをとっても、趙匡胤の才能は、彼の指揮下にある勇敢な将軍たちを怖がらせるのに十分でした。 第二に、李雲の反乱が鎮圧された後、趙匡胤は中央の近衛軍を再編成し、地方の勢力を弱め始めた。 まず、近衛兵と近衛兵の兵力を整理し、最も優秀な兵を選抜し、最も劣悪な兵を淘汰し、勇敢な兵を選抜して上軍に編入した。次に、地方軍の精鋭兵も中央近衛兵に選抜した。最後に、「模範兵」を各地に派遣して新兵を訓練し、訓練後に最も優秀な兵を選抜して中央近衛兵を補充した。 さらに趙匡胤は近衛兵の一部を重要な地域に駐屯させるために派遣した。その結果、中央近衛軍の勢力が強まり、地方はこれに抵抗することができなくなった。もちろん、守備隊交代制は、封建領主を弱体化させるための重要な手段でもありました。歴史の記録によれば、この一連の措置は「将軍が軍隊を独占することを防ぎ、兵士が傲慢で怠惰になることを防ぐ」効果を達成した。 中央禁軍の再編が完成した後、趙匡胤はまず慕容延昭と韓霊坤に目を向けた。二人は地方に駐留し、中央禁軍の高官の肩書きを持っていた。彼らを解任しても民衆の疑いを招かないだろう。その時から彼らは中央禁軍の実権を握ることになる。もちろん、これらの英雄たちはまだ皇帝に従う喜びに浸っていました。周囲の殺意に直面した功臣は、近衛兵との人脈が断たれたことに突然気づき、軍事力を手放すしかなかった。さらに、軍事力を手放せば、残りの人生は裕福で豊かな生活を送ることができるのです。 |
<<: 梁基は「暴君」として知られ、朝廷で大きな権力を持っていました。なぜ彼は漢の弱い桓帝によって滅ぼされたのでしょうか?
>>: 漢の宣帝は死ぬ前から劉弈の弱点に気づいていたのに、なぜ彼を皇太子にしたのでしょうか。
推薦する
墨子第70章の秩序(3)をどのように理解すべきでしょうか?原文の内容は何ですか?
『墨子』は戦国時代の哲学書で、墨子の弟子や後世の弟子たちによって記録、整理、編纂されたと一般に考えら...
『王家の華 青春の最高の景色はどこにあるのか』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
ロイヤルフラワー·若者にとって最高の景色はどこにあるか欧陽秀(宋代)青春を楽しむのに最適な場所はどこ...
哲学書:墨子:第5章:七つの悪、原文、注釈、翻訳
『墨子』は戦国時代の哲学書で、墨子の弟子や後世の弟子たちによって記録、整理、編纂されたと一般に考えら...
魏傑の形而上学的業績:当時の社会文化の進歩を促進した
魏傑は、号を叔宝といい、晋の時代の神秘家であった。魏晋時代には何厳や王弼に次ぐ有名な文人、神秘家であ...
『紅楼夢』の四大家の中で最も成功した男は誰ですか?
『紅楼夢』の四大家の中で最も成功した男は誰でしょうか?この男は賈牧の父、史氏であり、まさに高官です。...
蘇軾の目に杭州西湖はどんなところですか? 「西湖と西施を比べると、薄化粧でも濃化粧でも似合う」
蘇軾の「湖水を飲むと、最初は晴れ、その後雨」は、興味深い歴史の編集者が関連するコンテンツをお届けしま...
『紅楼夢』で林黛玉の隣の女中「春仙」とはどういう意味ですか?
『紅楼夢』では、清虚寺で儀式が行われた際、他の全員が2人の侍女を連れてきましたが、岱玉は子娟、春仙、...
若くして名声を得た賈靖は、なぜ世襲した爵位を一人息子の賈震に譲ったのでしょうか。
賈靖が賈真を無視し、道士と争った理由をご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。『おもしろ歴史』の編集...
『紅楼夢』の薛宝琴はなぜ「桃花歌」を自分が書いたと言ったのですか?
薛宝才は『紅楼夢』のヒロインの一人です。林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。『おも...
三国時代後期に張郃が強大な権力を握っていた主な理由は何ですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
プミ族の葬儀の習慣 プミ族はなぜ二度葬をするのでしょうか?
プミ族は火葬後、骨壷を墓山(カンカン山)の麓に送り、二次葬の儀式を行いますが、二次葬の時期や規模は場...
万秀の発音は?雲台の二十八将軍の一人である万秀はどのようにして亡くなったのですか?
万秀秀説明: 「高い」と「長い」の意味は、「遠い」と「美しい」という意味にまで広がります。昔は、教師...
老子の『道徳経』第49章とその続き
『道徳経』は、春秋時代の老子(李二)の哲学書で、道徳経、老子五千言、老子五千言とも呼ばれています。古...
人の使い方をよく知っていた劉備は、趙雲を「衛兵長」に任命しました。彼の配慮は何でしたか?
歴史上、人を知り、人を活かすというと、たいていは漢の初代皇帝・劉邦を思い浮かべるでしょう。しかし、人...
六つの王国はどのようにして衰退したのでしょうか?どの 7 つの戦いがすでに答えを出していたでしょうか?
戦国時代、商鞅の改革により秦国は徐々に強くなっていったものの、他の六つの国、特に楚、斉、趙の三国は非...