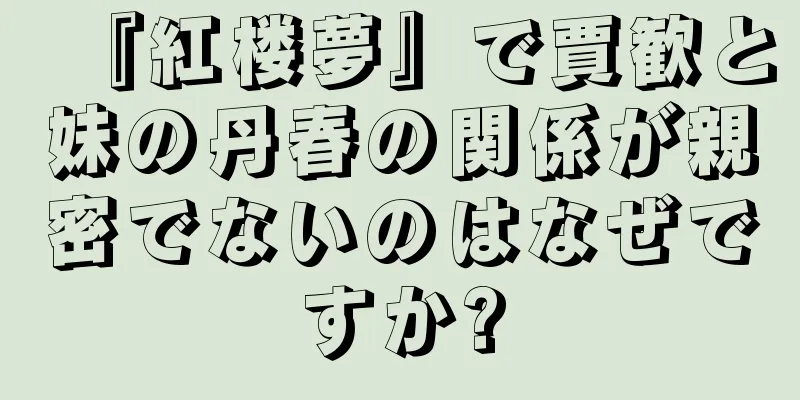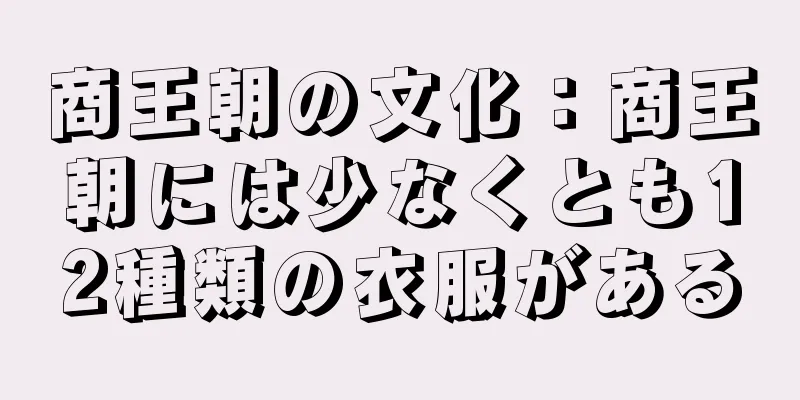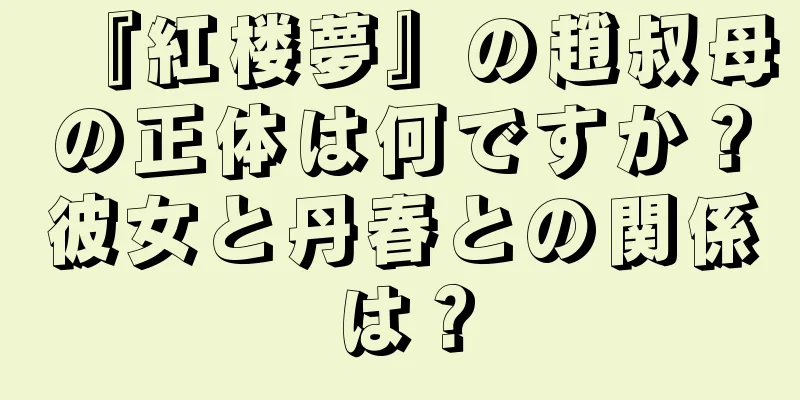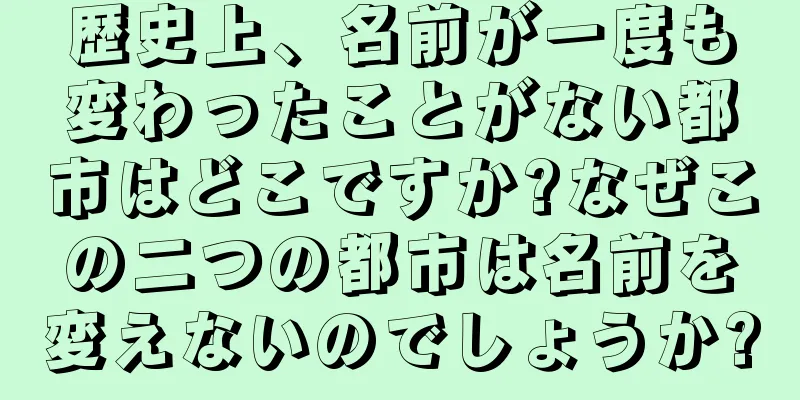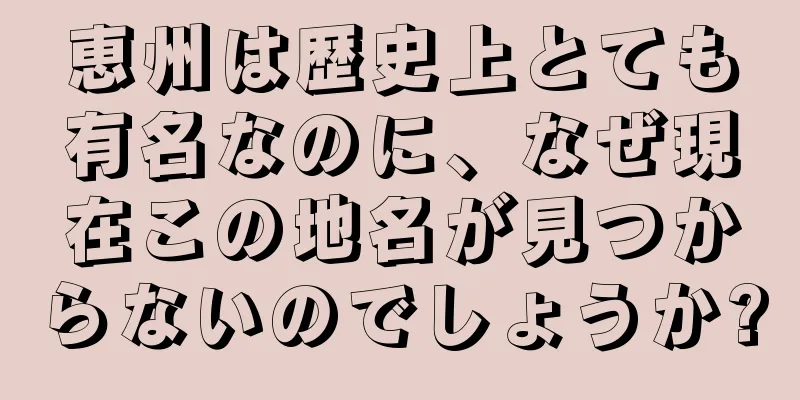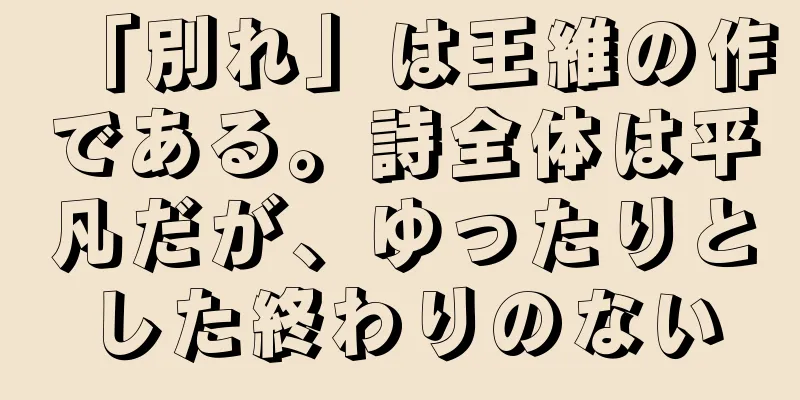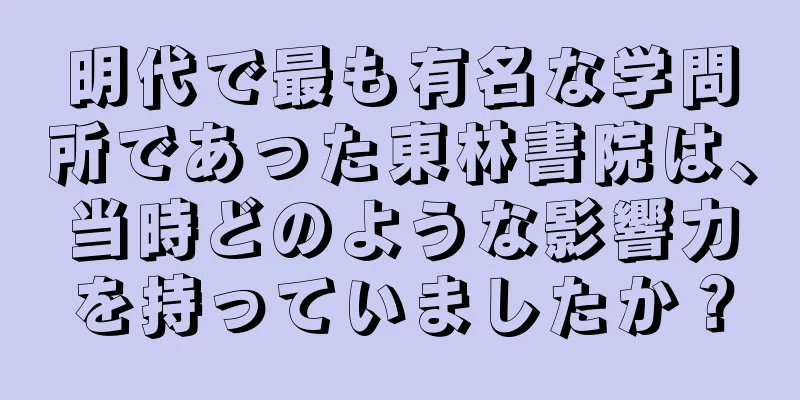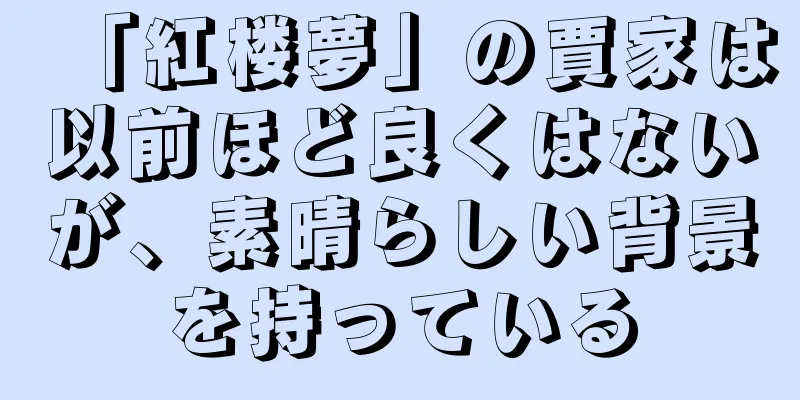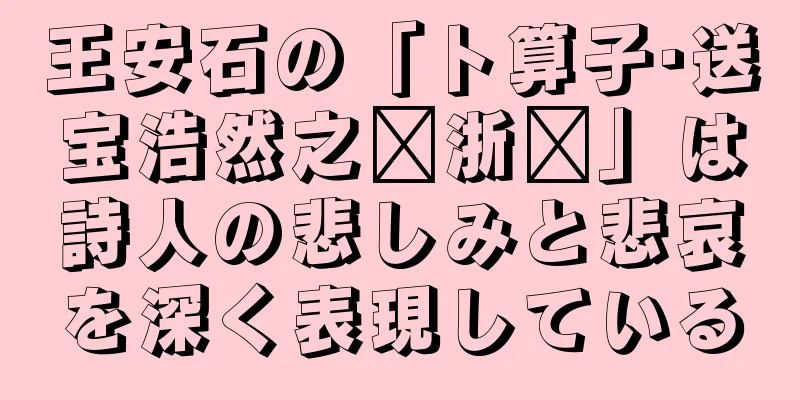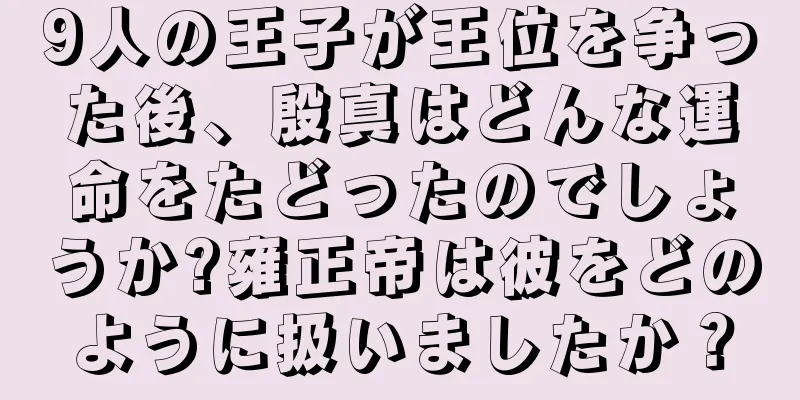康熙帝は即位後、どのようにして十三衙門を内務省に改めたのでしょうか?
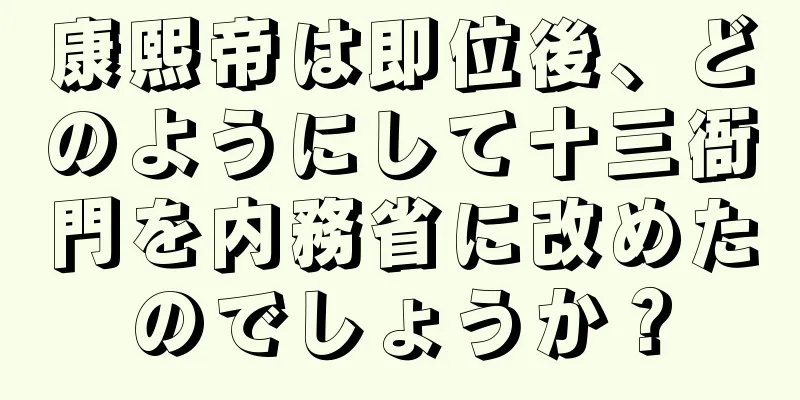
|
宮内省は清朝において宮廷の事務を担当した官庁の名称であった。チーフオフィサーは、マンチュの大臣によって同時に任命されましたSiは県の刑務所を担当していましたFang Rent Treasuryは、Yangxin Hallの建設事務所を担当していました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 雍和宮と寧寿宮の官吏は、調度品の設置や掃除、宮廷の監督官の勤勉さの検査を担当し、書道局は書の彫刻を担当し、茶食局は食事の提供を担当し、薬局は薬品を担当し、祭祀局は牛の飼育を担当し、工務局は陣営の仕事を担当した。また、宮殿の管轄下にある尚思院は宮殿で使用する馬を管理し、五北院は宮殿で使用する武器、鞍、鎧、寝具などを管理し、鳳辰院は庭園に関する事項を管理しています。内務部は外廷の官吏とは関係のない独立した組織で、50以上の下部機関と3,000人以上の官吏を抱え、上三旗の臣下の管理と宮中の諸事を担当していた。 歴史 順治年間、黄太極年間に設置された内務省は十三衙門に改められたが、康熙帝が即位した後、廃止され、内務省が再び設置された。当時、内務省は「内務省殿」(略称「殿」、別名「本府」)とその傘下の「七部」と「両廷」に分かれ、本部は「内務省総局」と呼ばれていた。その最高位の役人は「宮内省総監」であった。 その下の「7つの部門」は、財務省と帝国のキッチン部門の総支出を担当する帝国の家事部門でした。 Unchsは、Shunzhi(1656)の13年目にエチケット部門に変更され、Shunzhi(1660年)のエチケットコートと改名されました、宮殿の修理プロジェクトを担当していました。 順治18年(1661年)、内務省に改称され、三旗牛羊牧場は牛と羊の飼育事務を担当し、上方司は三旗に提出された刑事事件の審理を担当した。順治11年(1654年)に設置され、12年に上方院に改称された。二つの下部組織は、皇帝の馬を管理する皇馬部で、順治18年(1661年)に「阿墩衙門」(阿墩は満州語で馬の群れを意味する)に改名された。安楼は武器や装備の準備を担当する機関で、順治11年(1654年)に兵章居に改名され、順治18年(1661年)に五北院に改名された。 宮殿の財政は主に内務省が所有する皇室農場からの収入で賄われていた。もちろん、東北地方のクロテンの毛皮や高麗人参は王室が独占していたため、内務省も宮殿に残っていたこれらの品々を売って利益を得ていた。また、宮内省は公邸の売買や賃貸などの商業活動も行っていました。しかし、宮内省が設立された当初は、その財源は十分ではありませんでした。 1911年の辛亥革命後も、廃位された皇帝溥儀は宮殿に住み続け、皇帝に仕える皇室部も1924年に溥儀が宮殿から追放されるまで維持された。 組織機能 内務省は清朝独自の機関で、最も多くの事務を所管していた税務部の10倍以上の3,000人もの職員を抱え、清朝最大の機関であったといえます。宮内省の主な機能は、王室の日常の食事、衣服、貯蔵、礼儀、土木、農場、家畜、警備と護衛、山沼での狩猟など、王室の事務を管理することでした。また、塩の管理、関税の徴収、貢物の受け取りも管理していました。宮内省の主な機関としては「七部三朝」がある。 宮内省の組織は満州社会の保易(奴隷)制度に由来し、満州八旗の上位三旗(黄旗、平黄旗、平白旗)の保易が主な職員であった。最高位の官吏は内務大臣で、当初は三位であったが、雍正13年(1735年)に二位に昇進した。皇帝は満州族の王子、内務大臣、宰相、副大臣の中から特別に選抜し、あるいは満州族の衛兵、地方政府の医師、三朝の大臣の中から昇進させた。天皇の衣服、食事、住居、交通などに関するすべての事柄は宮内省によって取り扱われました。 内務省直轄の内務省には7つの部局と3つの研究所がある。主な内部機関には、広挙、都于、張儀、経理、築城、神興、清豊があり、それぞれ王室の財政、貯蔵、警備と護衛、山や沼地での狩猟、礼儀作法、皇室農場の賃貸料と税金、工学、刑罰、畜産を担当していました。また、皇帝の馬を管理する上思院、傘、鞍、鎧、刀、槍、弓矢の製造と保管を担当する五北院、さまざまな庭園の管理と修復を担当する鳳辰院もあり、これらは総称して七部三朝と呼ばれていました。 宮内省には三機所をはじめ30以上の付属機関もあった。また、宦官や宮女、宮中の諸事を管理する経師房も内務大臣の管轄下にあった。 また、内務省は三大宮殿も管轄しており、慈寧宮、寿康宮、皇薬局、寿薬局、文源閣、武英宮書籍修繕所、皇書所、陽心宮製造所、仙安宮官学校、景山官学校、景時坊などを管理している。その中で、景時坊は宮廷内の宦官を管理する責任を負っていた機関でした。 |
<<: 清朝のどの皇帝が内閣を改革し、それを真の政府機関にしたのでしょうか?
>>: 明代の『同正世史』の成立から清代にかけて、どのような歴史的発展があったのでしょうか。
推薦する
陶淵明の有名な詩の一節を鑑賞する:部屋に日が沈むと暗くなり、薪がろうそくの代わりとなる
陶淵明(365年頃 - 427年)は、字は元良であったが、晩年に名前を銭、字を淵明と改めた。彼のあだ...
古代の医療機関である帝国医局という名前はどの王朝から始まったのでしょうか?
古代の医療機関である「医局」という名称は、唐・宋の「医局」と「医府」から受け継がれ、晋の時代に始まり...
丁鋒波の『林葉吹く音を聞かず』を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
丁風波:森を吹き抜ける葉の音を聞かないでください蘇軾(宋代) 3月7日、沙湖への道で雨に遭遇しました...
元代の画家で四大学者の一人である黄熙には、どんな優秀な弟子がいましたか?
黄熙は元代の画家で、字は文謙、浙江省義烏の出身です。元代の画家、黄熙の生涯を知ると、黄熙が西暦127...
鮑昭の「大方歌行」:この詩は意味に満ち、冷たく、そして深い
鮑昭(416?-466)は、号を明遠といい、唐の人々が武帝の禁忌を避けるため「鮑昭」と書いたと思われ...
「遼東山の秋の夜」は李世民によって書かれ、詩人の精神的な静けさを反映している。
唐の二代皇帝・李世民は文学や書道を好み、多くの作品を残しました。興味深い歴史の編集者と一緒に、李世民...
明代の魏索制度とはどのような制度だったのでしょうか?どのようにしてWeisuoシステムは完全に崩壊したのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が明代の魏索制度についての記事をお届けします。...
皇帝の死後、側室も皇帝とともに生き埋めにされる制度!どのような妾が生き埋めにされるのでしょうか?
みなさんこんにちは。Interesting History の編集者です。今日は、古代に側室が愛する...
人間には7つの感情と6つの欲望があると言われています。「7つの感情」と「6つの欲望」とは何でしょうか?
「人間には7つの感情と6つの欲望がある」とよく言われます。では、七情六欲に含まれる「感情」や「欲求」...
辛其の『莫余児』はどのような背景で作られたのでしょうか?どのように鑑賞しますか?
辛其の「莫耶児:あと何度の風雨に耐えられるか?」に興味がある読者は、Interesting Hist...
洛因の「オウム」:作者はオウムに話しかけるという形式を使って自分の内なる思いを表現している
洛隠(833年2月16日 - 910年1月26日)は、元の名は洛衡、字は昭建で、浙江省杭州市阜陽区新...
道教の書物『関子八意』の原文は何ですか?関子入門:八観
『管子』は秦以前の時代のさまざまな学派の意見をまとめたものです。この本には、法家、儒家、道家、陰陽家...
唐代の張文公の絵画「鏡美人図」には疲れた顔をした女性が描かれている。
「鏡の中の美人」は唐代の張文公によって書かれたものです。次の Interesting History...
司馬昭とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は司馬昭をどのように評価したのでしょうか?
司馬昭(211年 - 265年9月6日)、字は子尚、河内省温県(現在の河南省温県)の人。三国時代の曹...
『紅楼夢』では、蔡霞は王の右腕でした。なぜ王は彼女を結婚させたのですか?
蔡霞は『紅楼夢』の登場人物で、王夫人のメイドである。次回は、Interesting History編...