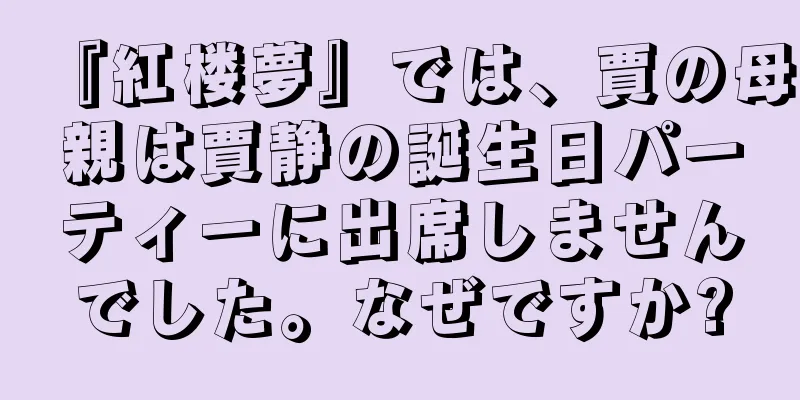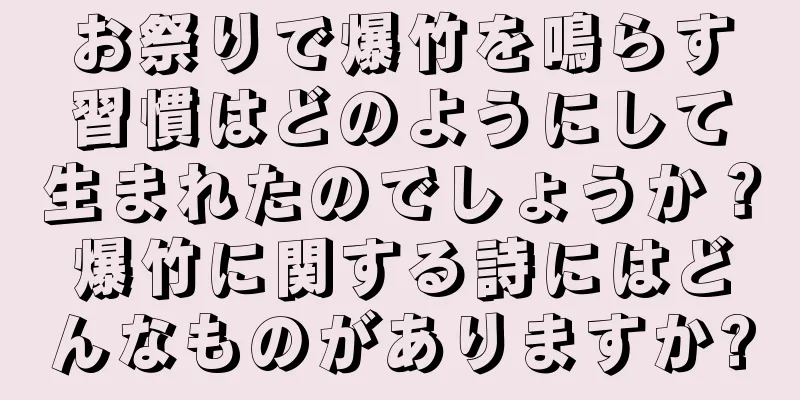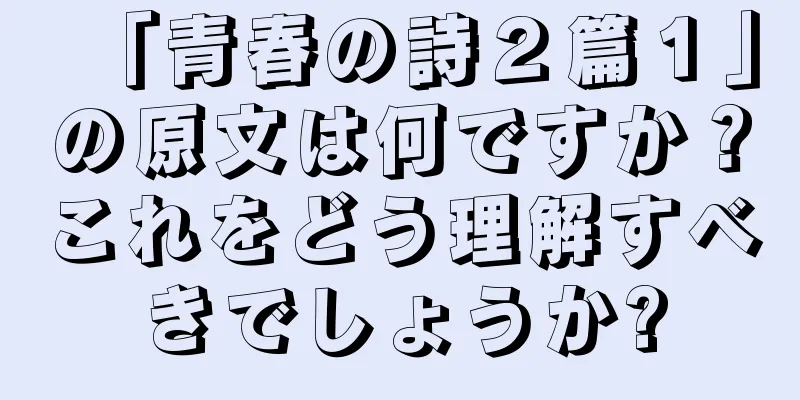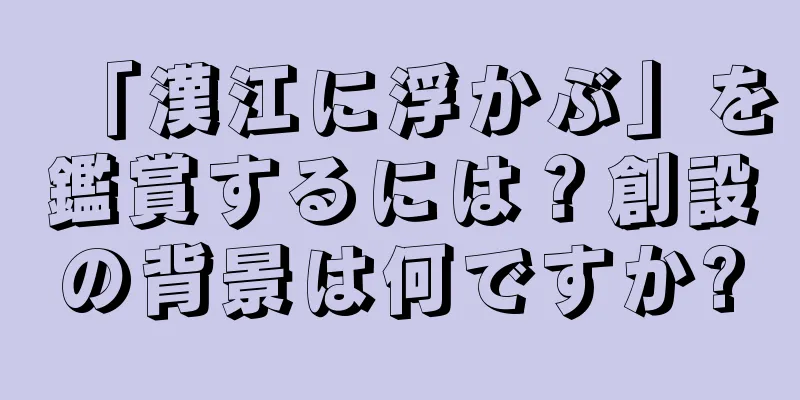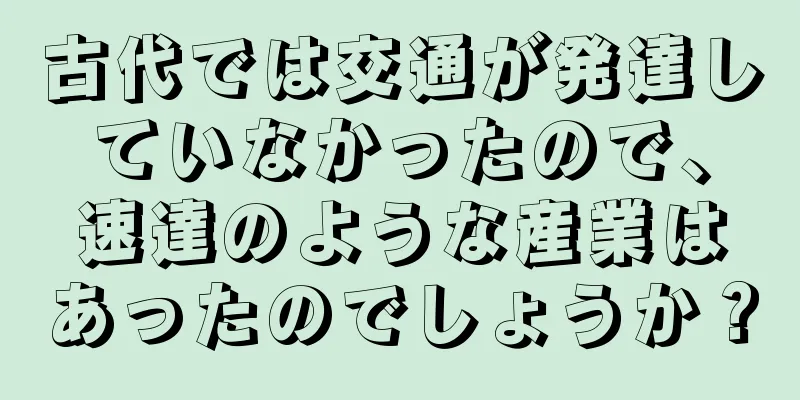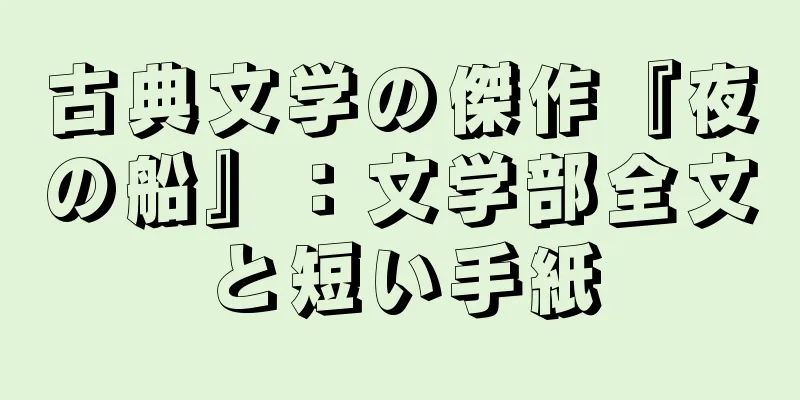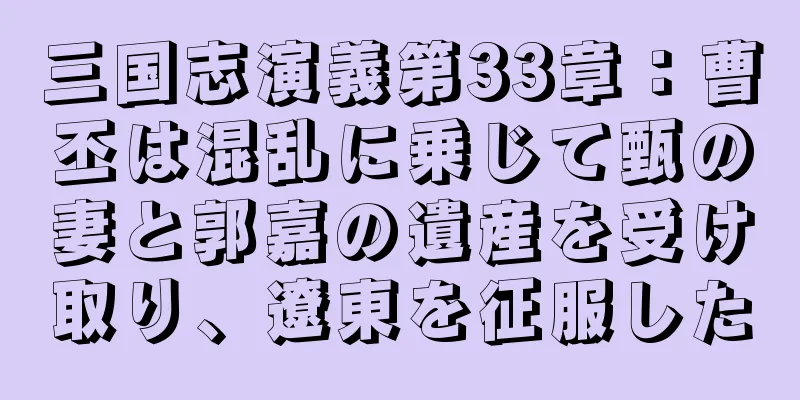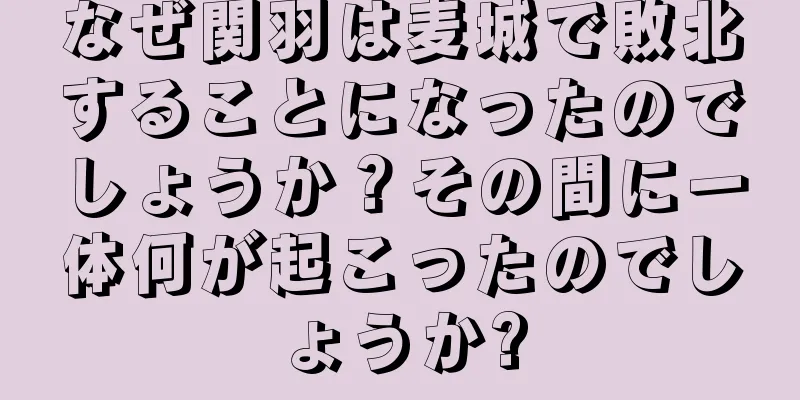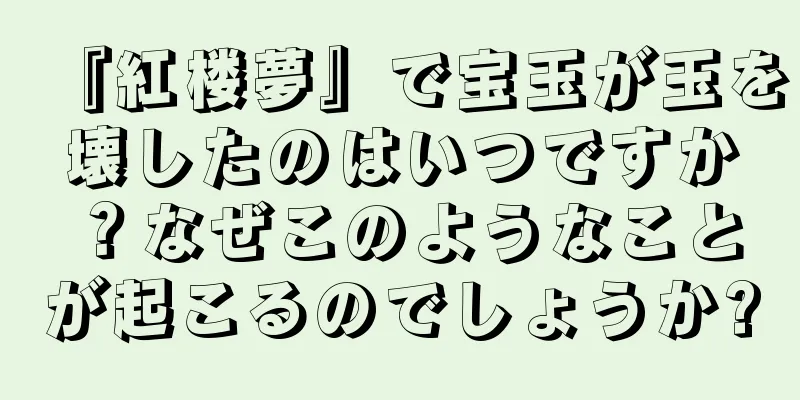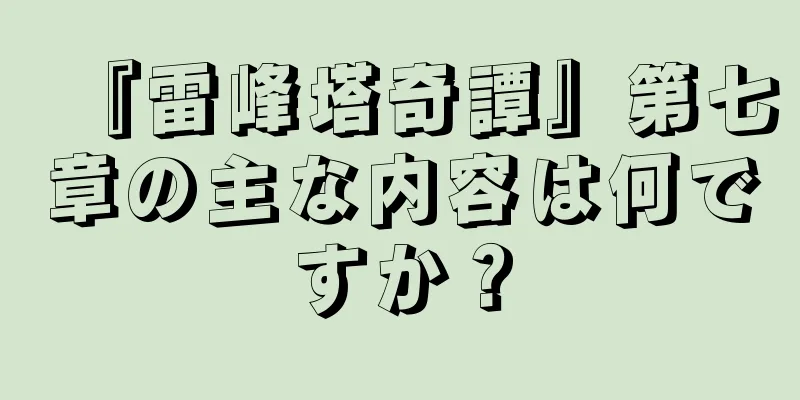演音は古代の世襲制度の変形です。どの王朝で最初に現れたのでしょうか?
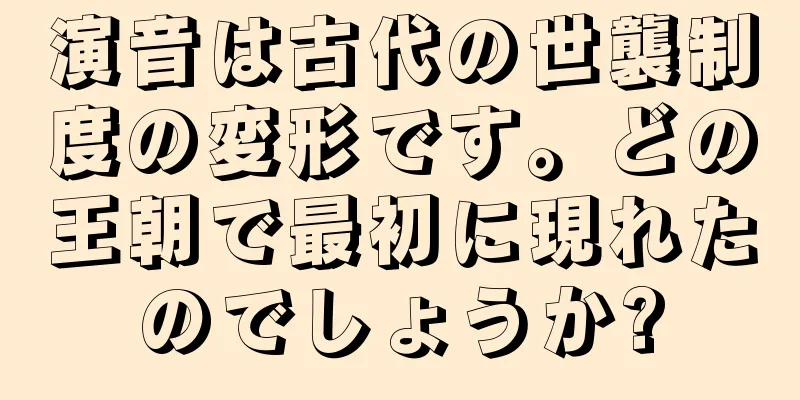
|
演音は、人子、面音、陰部、世商とも呼ばれ、古代中国の世襲制度のバリエーションです。これは、上の世代の功績により、下の世代が学校に通い、官吏になれるように与えられる待遇を指します。広義では、縁陰とは封建制度下での先祖や親の身分により、子孫が学校への入学や官職への就任に関して特別な待遇を受けることを指し、「縁陰」と呼ばれます。狭義の「縁陰」とは、宋代以降に出現した「退縁陰部」と呼ばれる独特の家系制度を指し、宋代には「縁陰」と略称されていました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 歴史的進化 広義の「恩給」:封建制度下では、祖先や父母の身分により、子孫は学校への入学や官職への就業において特別な待遇を受けることがあり、これを「恩給」と呼ぶ。類似の用語にはmenyin、yinbuなどがあります。 狭義の「縁故」とは、宋代以降に生まれた「推縁部」と呼ばれる独特の家系制度を指し、宋代には「縁故」と略称されていました。 宋代の「恩音」:朝廷の重要な祝賀行事の際、官僚の子孫に国立学院で学び、官吏となる許可が与えられた。 清朝の「恩音」:北京の四位以上の文官、首都以外の三位以上の官吏、二位以上の武官は、息子を一人だけ学問所に送ることが許され、恩音と呼ばれた。また、宋代と同様に、祝賀行事により牢に入れられる者も特権を与えられたとみなされた。 その結果、知事と首相は皆、クリケットの支持を得た。 ——中国のスタジオからの奇妙な物語:クリケット 漢王朝 漢代に一般的に「人子」制度と呼ばれた世襲任命制度は、高官が自分の息子を官職に任命できることを意味していた。これは秦以前の世襲官吏制度の名残であり、秦漢時代の貴族特権制度の変形である。世襲任命制度は秦の時代に始まり、漢の文帝の治世中に慣習となり、その後急速に発展したと考えられる。任命の対象は息子、兄弟、孫に加え、一族、従者などにも拡大され、人数も1人から2人、3人と増加した。 世襲任命制度は、役人を選出する制度としては後進的で閉鎖的なものである。なぜなら、官吏を選ぶ基準は才能ではなく、父や兄弟、家族の政治的地位、血縁関係だからである。仁子体制下では蘇武や霍光など有能な官僚も現れたが、大多数は凡庸で無能だった。レンツィ体制は、社会は有能な人々と腐敗した官僚によって運営されるべきであるという原則に反しており、当時の正義の心を持つ学者から批判された。しかし、地主と官僚の特権と既得権益を保護するため、存続した。 唐代 面音は唐代に流行し、唐代には音音とも呼ばれていました。唐代には皇族から与えられる補助金の数は限られており、補助金が支給されることは一般的ではなかった。 宋代 宋代には、当時の科挙のほかに官職に就く方法であった陰陰制度が実施され、中級・高級の文武官僚の子弟、親族、従者たちがこの特権を享受した。 贔屓制度は「面陰」制度の拡大であり、範囲が広い。宋代には多くの種類の贔屓があった。大中奎復8年(1015年)正月、宋真宗の趙衡定は承天節(毎年の誕生日)と南郊節(3年に一度の節)に、息子や甥に贔屓の先例を報告し、これが贔屓の扉を開いた。それ以来、贔屓はますます横行するようになった。嘉祐元年4月、勅令で「乾元節に与えられた特権はすべて廃止される」と定められた。 Enyin システムの機会には以下が含まれます。 1. 聖なる日、年に一度の天皇誕生日 2. 郊外祭祀の期間中、3年に一度行われる大祭礼 3. 官吏が引退すると、相続によって給与が与えられます。明代初期には、元朝に倣って息子を任命する制度が採用されました。七位以上の官吏には、代々給与を受け取る息子を持つことが許されました。これを「延銀生」と呼びました。 4. 死後任命状は、官吏が死亡したときに一度提出される。功績のある役人が亡くなった後、恩恵は20人以上に及ぶ可能性がある 明代 明代初期には、元代の子弟登用制度が踏襲され、七位以上の官吏には世襲給与を受ける息子を持つことが許され、これを嫡子と呼んだ。 清朝 清朝の制度では、首都の文官第四位以上、地方の官吏第三位以上、武官第二位以上は、それぞれ一男一女を学問所に留学させることが認められており、これを「封封」と呼んでいた。また、祝賀行事を理由に刑務所待遇を受ける者も好意的に受け止められる。 |
<<: 北宋時代にも正月は祝われていました。呉子牧は『南宋の夢』でどのような記述を残していますか?
>>: 玉書は清朝の歴代皇帝の家系図です。玉書の編纂には何年かかりましたか?
推薦する
『西遊記』では、比丘王は長寿の神から贈り物を受け取りました。彼は不老不死を達成できるのでしょうか?
西遊記では、人間、仙人、鬼、皆が不老不死を求めています。誕生日の星から贈られた3つの日付は、彼の不老...
『紅楼夢』で劉おばあさんが賈屋敷に滞在していたとき何が起こりましたか?
『紅楼夢』は主に裕福な貴族の生活を描いていますが、田舎の老婦人である劉おばあさんの描写も含まれていま...
目録: 「神々の叙任」における神話化された物語とは何ですか?
1. チ・チャンが息子を食べる周の文王が周王に捕らえられたとき、長男の白一高が贈り物を持って救出に向...
厳書の「蘇中清・東風柳青」:この詩は感情と情景が融合しており、独特のスタイルを持っている。
顔叔(991年 - 1055年2月27日)、号は同叔、福州臨川県江南西路(現在の江西省臨川市)の人。...
唐代の重要な軍事書『太白陰経』全文:人的戦略と作戦
『神機滅敵』は『太白陰経』とも呼ばれ、道教の著作です。古代中国では太白星は殺生の達人であると信じられ...
孟子:高子第1章第7節原文、翻訳および注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
于遜玲の著作は、清朝の歴史を研究する後世の人々にとって大きな助けとなるでしょうか?
于遜玲の伝記によると、于遜玲は清朝末期に生き、満州族に属していたとされています。彼は非常に恵まれた家...
漢の武帝の通貨改革の影響 漢の武帝の通貨改革が成功した理由
漢の武帝の貨幣改革の基本内容の中で、三梵銭の発行は最も早いものでした。半良は秦の時代から受け継がれた...
古典文学の傑作『太平楽』:伏儀篇第16巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
「彭公安」第99章:英雄たちは共同で花春園に侵入し、劉芳は勇敢に盗賊と戦う
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
雲岡石窟の歴史:雲岡石窟の彫刻にはどれくらいの時間がかかりましたか?
北魏時代、雲岡石窟の発掘は文成帝の和平年間(460年)の初めに始まり、孝明帝の正光5年(524年)ま...
アファン宮殿を焼き払ったのは誰ですか?本当に項羽によって焼かれたのでしょうか?
誰がアファン宮殿を焼き払ったか知っていますか? 知らなくても大丈夫です。Interesting Hi...
『三朝北孟慧編』第182巻の主なストーリーは何ですか?
延星第82巻。紹興七年十一月十八日より。三省三委員会は、勅命に従い辞退したが、結局は重責を託された。...
荘子の『世界論』はどんな物語を語っているのでしょうか?どのような考えが表現されていますか?
荘子は古代我が国の有名な思想家です。それでは彼の『天下』はどんな物語を語りますか?どんな思想を表現し...
涼山の英雄の多くは武術の達人です。陸智深は武術の面でどの位にランクされるでしょうか?
涼山湖の百八将は朝廷さえも恐れるほど有名だった。そのとき初めて、彼は涼山の英雄たちを雇って方拉の反乱...