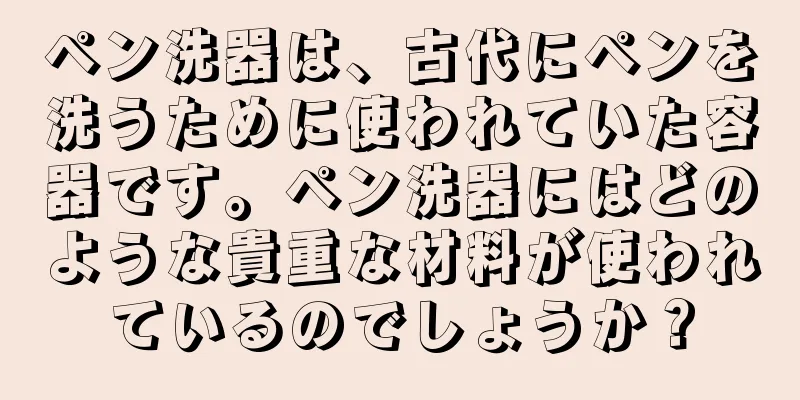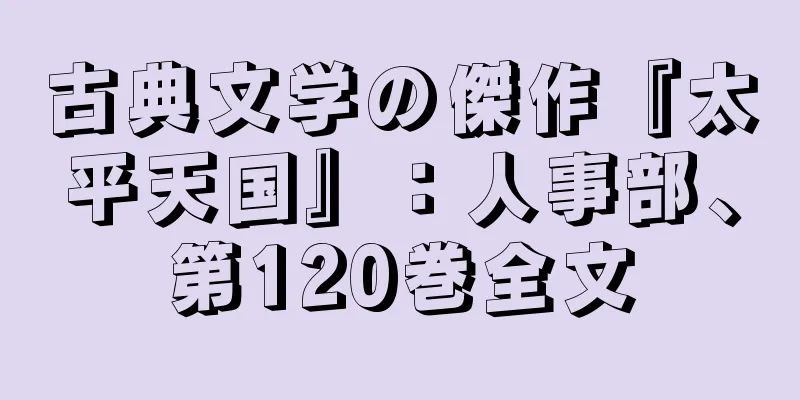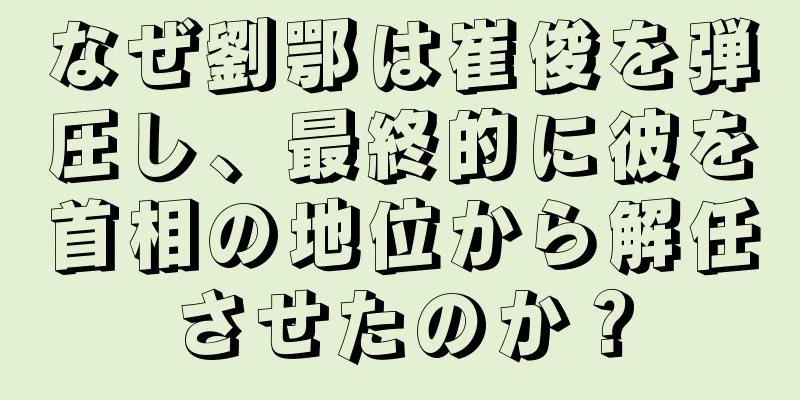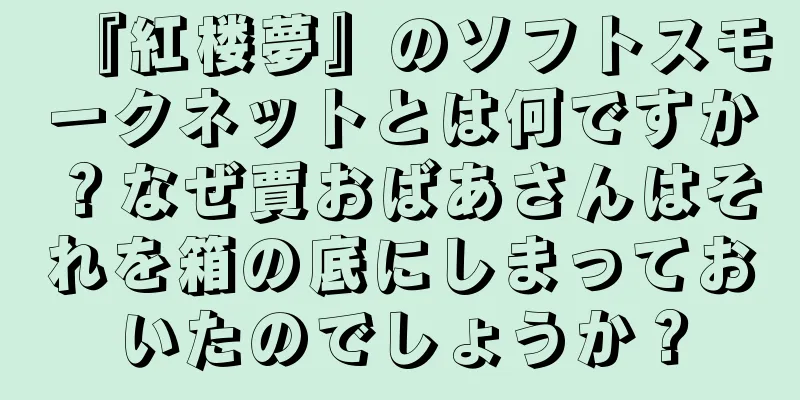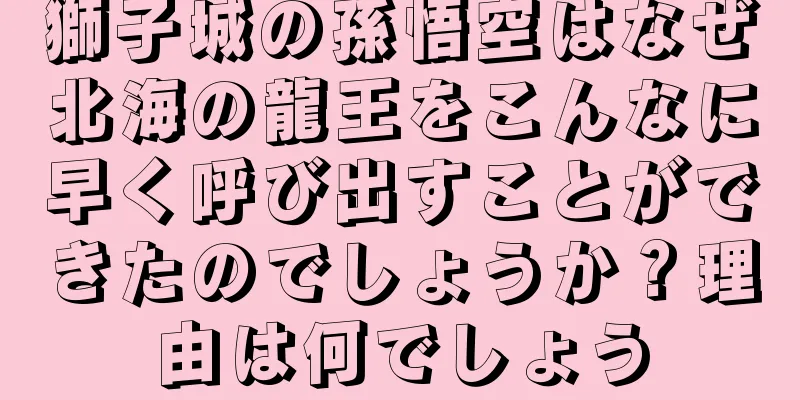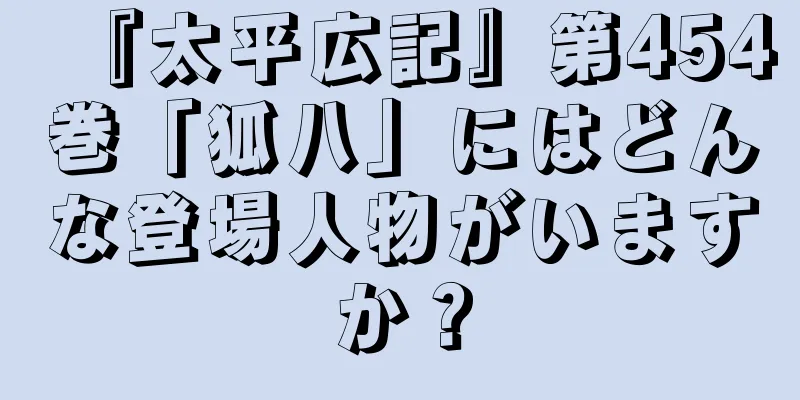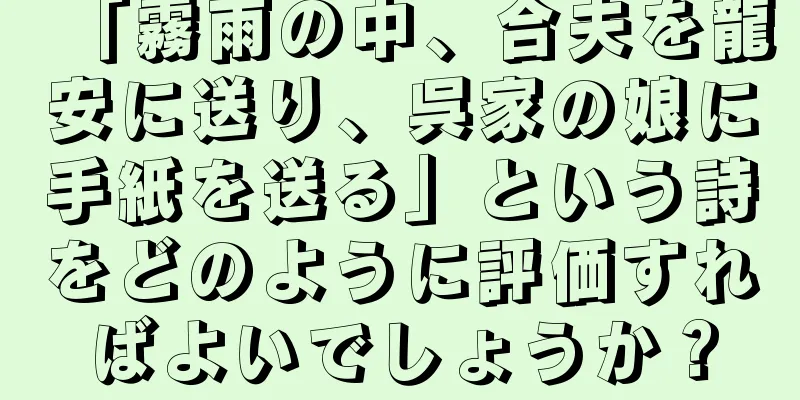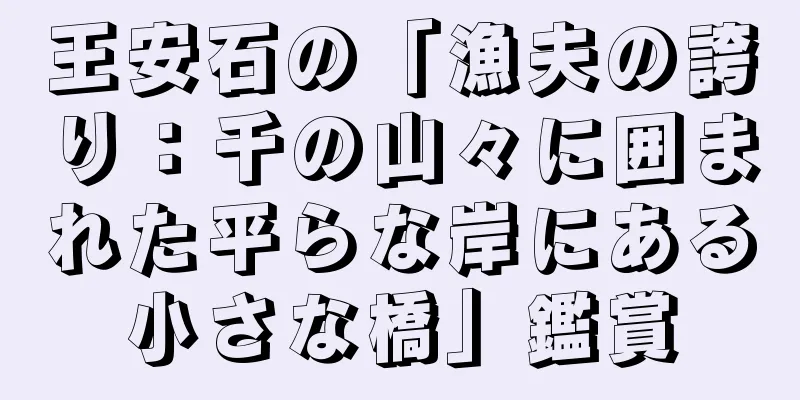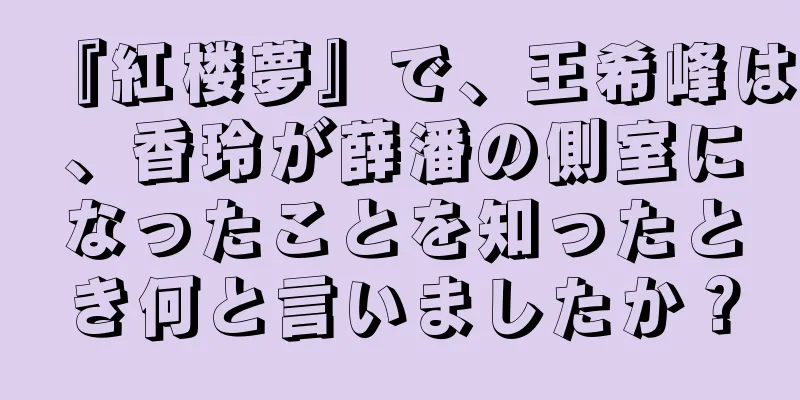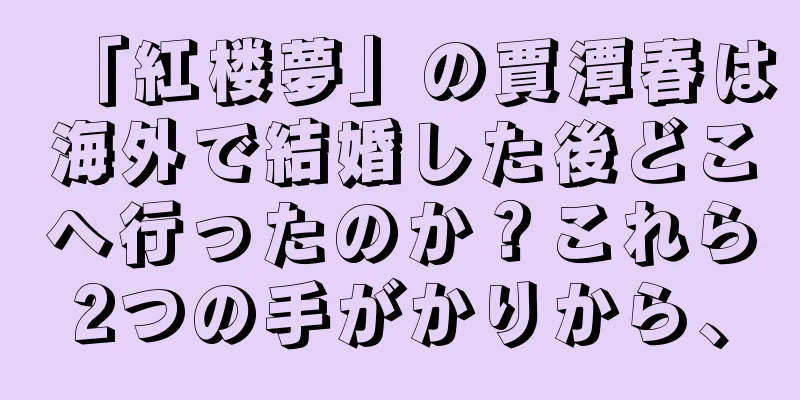司馬光が王安石の改革に反対したのは、主に王安石のどのような考えに関係していたのでしょうか。
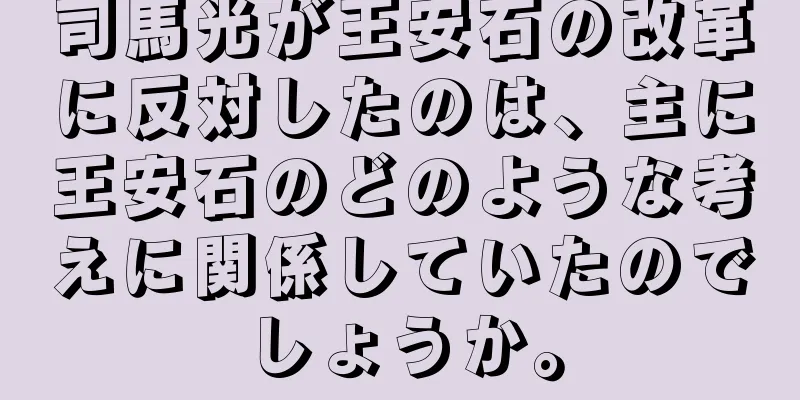
|
司馬光は主に思想上の理由で王安石の改革に反対した。司馬光の最大の功績の一つは、約400万字の『至志通鑑』を編纂したことである。『至志通鑑』は後世の我々歴史愛好家に非常に良い情報を提供したと言える。それは常に歴史学の重要な基準であったが、それだけである。司馬光は400万字の『至志通鑑』を使って歴史上の政治の損得を語ったが、それを全く実践しなかった。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 司馬光は宋代の仁宗皇帝の時代に免税法を提唱しました。論理的に言えば、彼の思考様式と思想は王安石のものと似ていました。第二に、司馬光は范仲厳の改革を支持しており、保守的な人物ではありませんでした。なぜ彼は真の改革に反対したのでしょうか。これにはさまざまな理由があります。次の3つの点を参考にしてください。 声明1: 司馬光は、この改革で施行された新しい法律には利点よりも欠点の方が多いと考え、改革の必要はないと感じました。 声明2: 司馬遷は封建社会に生き、幼少の頃から『四書五経』に親しみ、儒教の影響を深く受けていました。このような封建社会に生きていると、新しい考えや考え方を受け入れるのは明らかに不可能です。司馬光は保守派に属していたため、改革には反対しましたが、それは考え方の違いによるものでした。 声明3: 司馬光は自分の利益を第一に考えていた。王安石の改革で最も苦しんだのは官僚と地主たちだった。北宋中期、官僚組織は肥大化し、巨大化していた。この体制のもと、多くの官僚が高給取りで国家から優遇され、金を稼げば何もしなくてもよく、文武両道の官僚の生活は極めて幸福であった。王安石が新しい法律を施行したとき、彼はまず官僚と地主を標的とし、官僚の特権を大幅に抑圧し、彼らの経済的利益を損ないました。 司馬光は当時『至志同鑑』を執筆中だった。この作品を完成させるのに30年近くかかり、完成させたとき司馬光はすでに66歳の老人だった。司馬光は歴史書の編纂にしか興味がなく、政治に野心はなかった。利己的な動機から改革に反対した。当時、役人の給料は高く、仕事も少なかった。安心して本を書き、家族を養うお金が欲しいなら、役人になるのが最良の選択だった。毎月給料をもらって、自分のやりたいことができる。なぜそうしないのか? 王安石の改革は、生産を発展させ、国を豊かにし、軍隊を強化し、宋朝を政治的危機から救うことを目的としており、「財政管理」と「軍隊の再編成」を中心に、政治、軍事、社会、文化のすべての側面に関与し、商鞅の改革に続く古代中国史上の大規模な社会改革運動であった。この改革は、北宋時代の貧困と弱体化をある程度改善し、政府財政を豊かにし、国防を強化し、封建地主階級と大企業家による不法な暴利行為を取り締まり、制限した。しかし、改革の実施が不十分だったため、国民の利益が損なわれました。 しかし、彼らの主張は本質的には、真の紳士は国と国民のために働くということであり、決して自分たちの利己的な利益のためではなかった。王安石自身も後に、司馬光は人を行為で判断しない真の紳士であったと認めた。おそらくそれは司馬光の時代の歴史的条件によるものでしょう。司馬光は近代的な経済理論を欠いており、改革の欠点を効果的に説明することができず、経験と感覚に頼ることしかできませんでしたが、それが不適切であると感じていました。その後、司馬光は議論を続けることを望まなくなり、自ら退くことを決意した。彼は非常に有名な『紫禁城同鑑』の執筆に専念しました。 |
<<: 宋真宗の息子として、宋仁宗は生涯でどのような功績を残しましたか?
>>: 趙匡胤は陳橋の乱を起こして皇帝になったが、後周の柴容にふさわしい人物だったのだろうか?
推薦する
唐代前編第12章:李耀思が災難を予言、チェシャー・マーが衣装を披露
『唐代全物語』は清代の長編英雄伝小説で、『唐物語』と略され、『唐代前編』、『唐代物語』、『唐代全物語...
「紅楼夢」の賈おばあさんは何歳ですか?賈牧80歳の誕生日祝賀会の詳細な説明
『紅楼夢』第71話では、8月3日に賈家は突然、賈祖母の80歳の誕生日を盛大に祝った。一体何が起こって...
「八九竹枝詩」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
竹枝詩第八番劉玉熙(唐代)五峡が霧と雨に覆われると、澄んだ猿が山の一番高い枝で遠吠えします。悲しんで...
第59章: 玉池公は災難を逃れて農耕に戻る; 劉黒太は軍を率いて首都を侵略する
『唐代全物語』は清代の長編英雄伝小説で、『唐物語』と略され、『唐代前編』、『唐代物語』、『唐代全物語...
『紅楼夢』の妙玉の最終結末は何ですか?劉おばあさんとはどんな関係があるのですか?
妙豫は『紅楼夢』の主人公で、髪を切らずに仏道を修行する尼僧です。次の『おもしろ歴史』編集者が詳しい答...
「張少富への返答」の著者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
繁栄した唐代の王維の『張少福への返答』老後は、ただ平穏と静寂が好きで、何も気にしません。私には自分自...
薛宝琴の「柳の尾状花序」鑑賞 薛宝琴の「柳の尾状花序」の秘密は何ですか?
『紅楼夢』の第 17 章では、グランド ビュー ガーデンでの最後の詩会について説明しています。この集...
『清代名人逸話』文学芸術編第4巻には何が収録されていますか?
◎鄭板橋のケーキ鄭板橋は偉大な師匠です。彼の作品はシンプルで奇抜、書画は奇抜さに満ちています。世界中...
史公の事件 第125章: 費山虎は捕らえられて殺され、蔡元達は撃たれて落馬した
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
「九歌」:戦国時代の楚の屈原が楚の民謡を翻案した
「九歌」は『楚辞』の一章の題名で、もともとは中国の神話や伝説に登場する古代の歌の名前です。戦国時代の...
方干の「従兄弟の高との別れ」は、作者が従兄弟との別れを強く惜しんでいることを表現している。
方干(836-888)は、号を熊非、号を玄英といい、死後、弟子たちから玄英先生と名付けられました。彼...
古典文学の傑作「太平天国」:道教第21巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
和碩和佳公主の簡単な紹介 和碩和佳公主はなぜ仏手公主と呼ばれるのか
和碩和佳公主(1745-1767)は、乾隆帝の治世10年(1745年)12月2日に生まれました。彼女...
諸葛亮はなぜ北伐を開始したのでしょうか?
周知のとおり、北方の曹魏を征服し、国を統一することが諸葛亮の生涯の目標でした。劉備と初めて世界情勢を...
古典文学の傑作『太平記毓覧』:文物部第10巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...