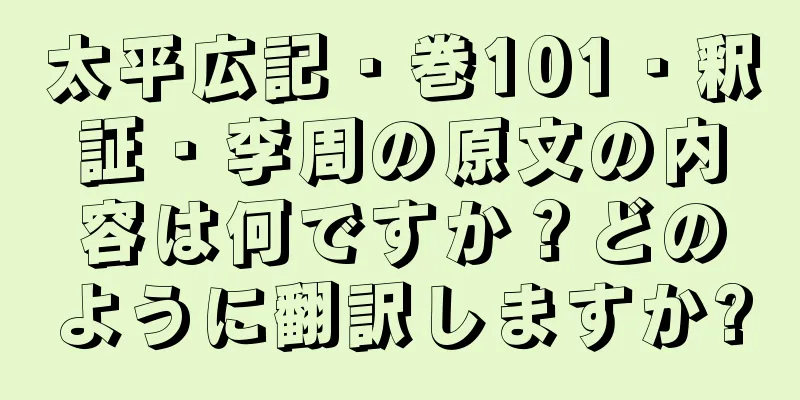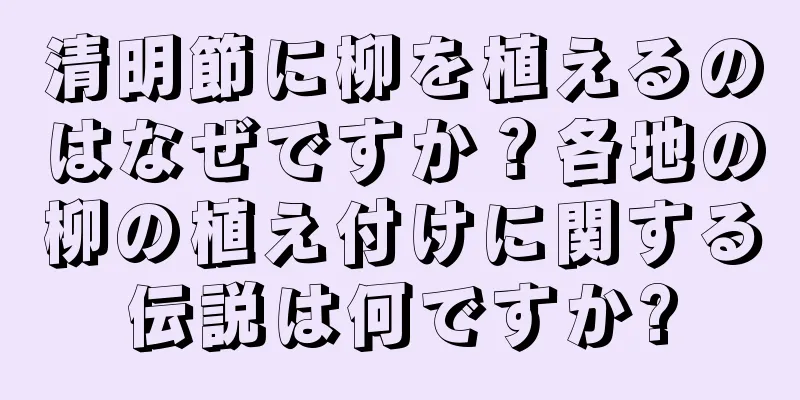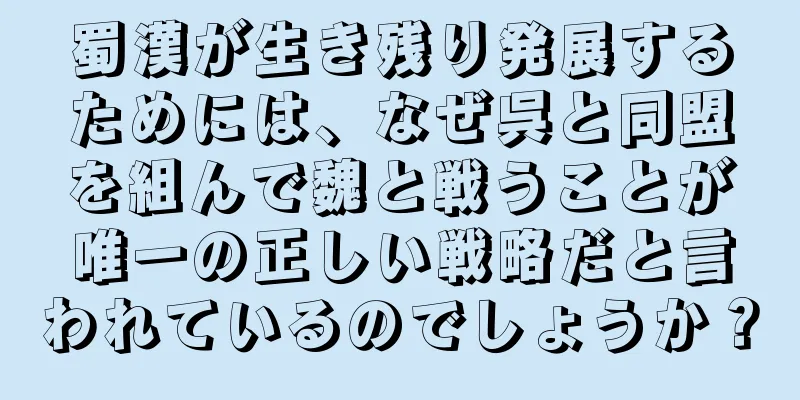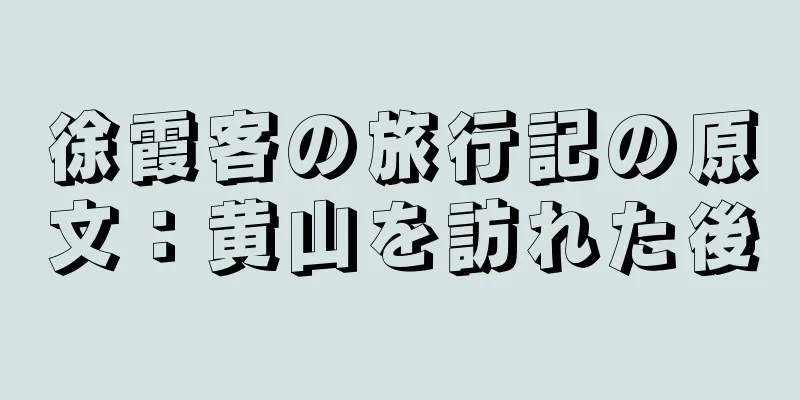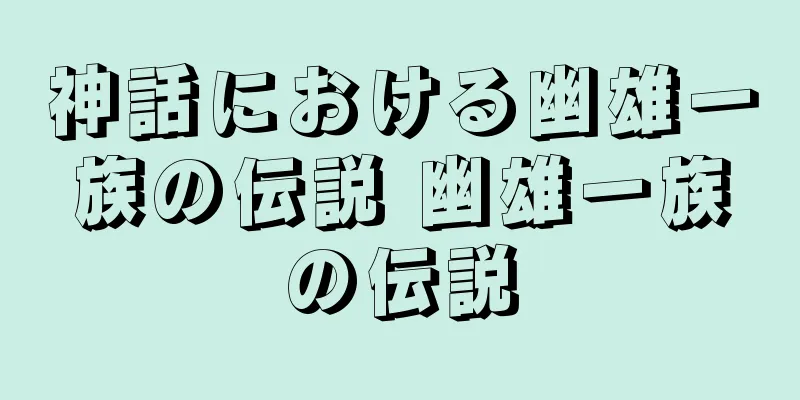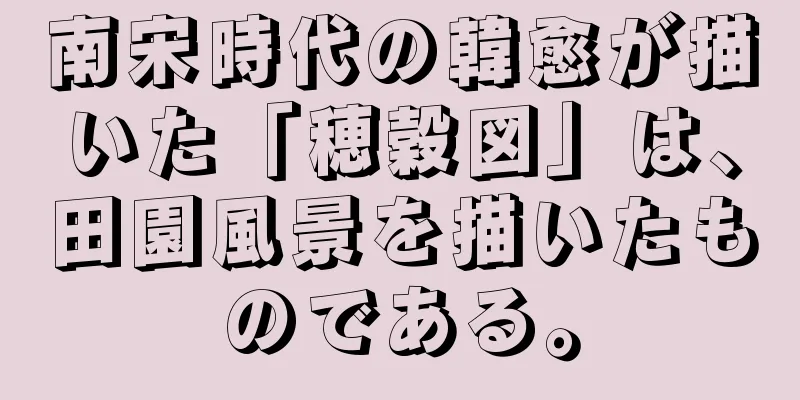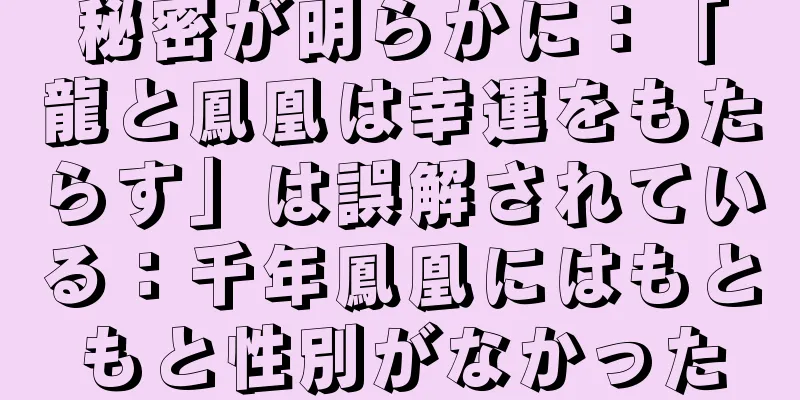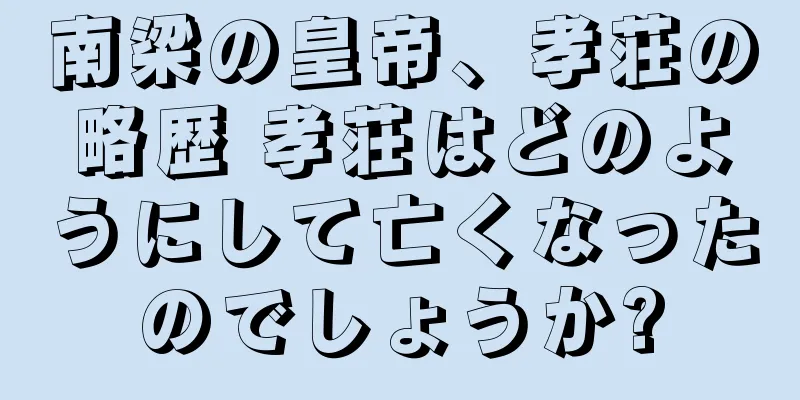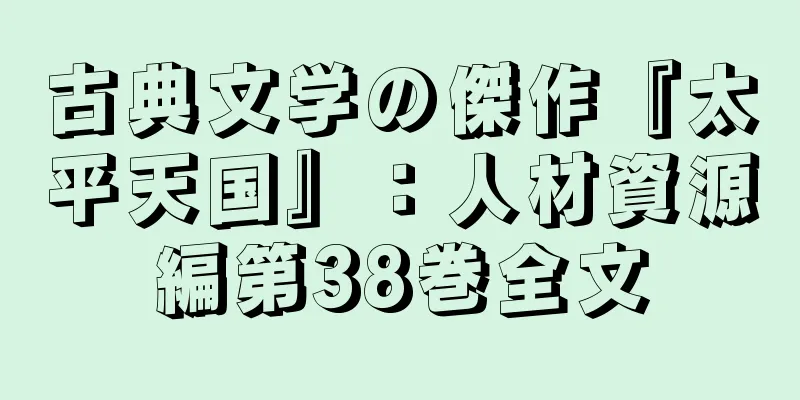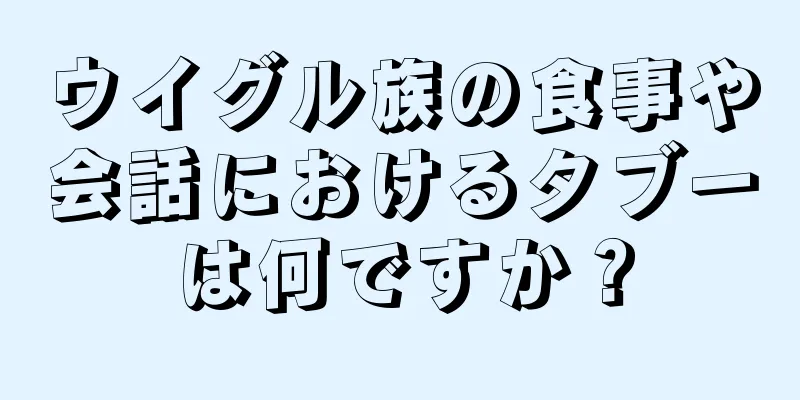秦国は六国にとって大きな脅威となった。それは張儀が蘇秦より優れていたからだろうか?
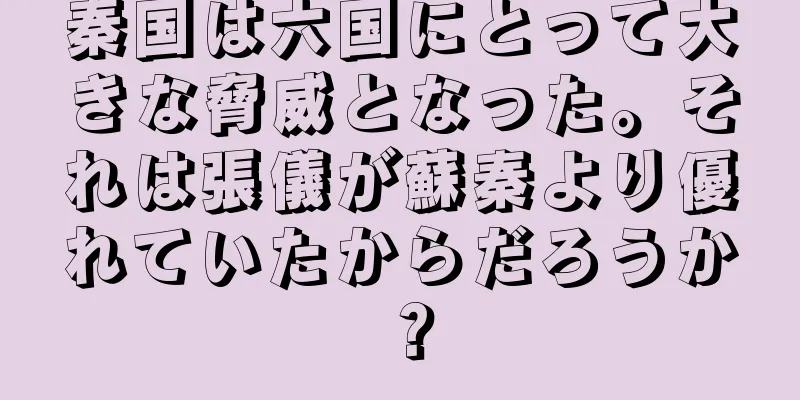
|
蘇秦と張儀、「衡宗」と「連衡」の戦略は、それぞれ異なる考えと実践で頂点を極めた。蘇秦は「衡宗」の戦略を提唱し、六国の力を結集して秦と戦ったが、張儀は「衡宗」の戦略を打ち破り、「連衡」を利用して六国の同盟を崩壊させた。最終結果も明らかで、「連衡」が勝利し、秦は六国にとって大きな脅威となった。しかし、なぜ連衡は賀宗を打ち破ることができたのでしょうか?張儀が蘇秦より優れていたからでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう! 1. 張毅と蘇秦のどちらが優れているか? 歴史上、秦は春秋戦国時代において最も安定した属国であった。辺境の地に位置していたが、賢明で聡明な君主が多く、肥沃な関中地域を擁し、常に東方への拡大を企図していた。秦がますます強くなり、大きくなっているのを見て、古くからの隣国である趙、魏、韓、楚は不安になり始め、苦境から抜け出すための戦略を緊急に必要としていました。 こうして、偉大な人材である蘇秦が誕生しました。蘇秦は他の6つの国に働きかけて縦の同盟の流れを促し、秦の東進を防ぐための「結界」を築きました。こうして、6つの国が団結して秦に抵抗する道が開かれました。 蘇秦は草の根の出身で、幸運にも桂谷子の弟子となり、「毗河の芸術」を学んだ。学業を終えて山を下りてきたばかりの蘇秦は、自信に満ち溢れて秦に加わった。彼はもともと大国の舞台で自分の才能を発揮できると考えていたが、秦の恵文王が蘇秦の申し出を受け入れないとは予想していなかった。失望した蘇秦は、遠く離れた六国へ旅するしかなく、当初の「水平統一」という戦略を「垂直統一」に変更した。 やがて蘇秦は政治的な相棒である燕の文公を見つけた。二人は長い会話を交わし、すぐに意気投合したが、出会うのが遅すぎたことを二人とも嘆いていた。蘇秦は燕の文公の支援を得て、趙、韓、魏、斉、楚に次々に出向き、諸侯に働きかけることに成功した。偉人は偉人である。蘇秦は六国の王への働きかけに成功しただけでなく、同時に六国の宰相にもなった。この時点で、縦横の同盟の流れが形成された。 蘇秦の「縦連の戦略」には2つの核心があります。1つは秦を抑えることです。秦がますます強大になるにつれて、各君主は秦の自由な発展を許すことができず、秦の成長を抑える戦略を採用しなければなりませんでした。2つ目は団結することです。秦が強くなるにつれて、必然的に東進の道を進むことになります。どの君主も強大な秦に対抗することができず、暖をとるために団結しなければなりませんでした。 張毅はもともと魏の貴族の末裔であったが、家が貧困に陥った後、桂谷子の弟子となり、蘇秦とともに「毗和の術」を学んだ。同級生だった頃から、蘇秦は張毅の聡明さを常に尊敬し、張毅が将来偉大なことを成し遂げると信じていた。蘇秦の心は張毅に対する「尊敬と嫉妬」の矛盾で満ちていた。蘇秦が初めて各国に働きかけていたとき、ちょうど秦が趙を攻撃していたときだった。蘇秦は独自の「縦横同盟戦略」を編み出し、秦が先に趙を攻撃するのを防ぐため、古い友人の張儀を招いて趙を辱めた。彼は挑発行為を利用して張儀を促し、秦に行って秦の恵文王に働きかけ、自身の「衡宗」の目的のために時間を稼いだ。 予想通り、張儀は屈辱を受けた後、復讐のために秦の恵文王の支持を得ることに成功した。当時、秦国は張儀の指導の下、「諸国を繋ぐ戦略」の立案に忙しくしていた。蘇秦が予想していなかったのは、弟の張儀が本当に並外れた人物だったということだ。張儀は秦の宰相になっただけでなく、斉と楚の二国を巧みに操り、「諸国を繋ぐ戦略」を考案し、蘇秦が長年苦労して築き上げてきた縦横の同盟関係を崩壊させることに成功した。張儀は雄弁なロビー活動を駆使して、斉、楚、韓、魏といった近視眼的な属国を操り、服従させた。 張儀の「同盟の戦略」にも2つの核心的な考えがあります。1つは弱者を脅迫し、一日中弱い属国に秦の強さを宣伝する使者を派遣し、小さな属国に領土を要求する機会をとらえることです。2つ目は強い者を誘惑し、斉や楚などの強力な属国と友好関係を築き、同盟を結び、周囲の小国を分割することで密かに合意し、中立の姿勢を選択するようにすることです。 2. なぜ連衡はいつも和宗を破ることができるのか? 戦国時代の外交の舞台では、2つの主要な戦略が流行していました。1つは「横宗」の戦略であり、もう1つは「連衡」の戦略です。この2つの戦略は実際には互いに矛盾していました。「横宗」は主に弱い国が団結して強い国に対処するために使用され、「連衡」は強い国が他の国の同盟を解体するために使用されました。はっきり言えば、一つは皆が一緒に戦う方法を見つけることであり、もう一つはグループを形成したこれらの国々を分裂させてから戦う方法を見つけることです。では、この2つの戦略のどちらが良いのでしょうか?実際、戦国時代の発展において、「連衡」の戦略は常に優位に立っており、「合宗」の戦略に勝ったと言えます。 最も典型的な例は、秦と他国との関係です。秦が首尾よく台頭した後、他国は秦に対処するために何度も同盟を組みましたが、どれも本当に秦を打ち負かすことはできませんでした。その代わりに、秦は「衡連」の方法を使用して、何度も同盟を解体しました。唯一本当に成功した連合は、広東地域の国々が蜂起して斉を倒したときです。連合は戦況全体に期待された影響を与えなかったと言えます。その代わりに、秦は同盟を形成する方法に頼って、東のこれらの国々をうまく分離し、その後、それらを一つずつ処理して最終的に勝利を収めました。 なぜ合作は最終的な勝利を収めることができなかったのか?実は、この質問は非常に単純です。合作自体に致命的な欠陥があり、各国にとって真に強い国が存在しないからです。秦と斉は常に東西のトップの勢力でしたが、七英雄のいずれかを直接排除する力を持っていません。結局のところ、これらのバランスの取れた状況では、一度そのような動きがあれば、すぐに他の国からの共同攻撃が引き起こされます。 これらの国々自体の力は非常に限られているため、同盟の目的は最初から非常に不明確でした。特定の国や特定の環境を対象としたものではありませんでした。次に、同盟には別の問題があります。つまり、これらの国々の同盟自体に問題があるということです。結局のところ、これらの国々は互いに戦うことが多く、それらの間の対立は非常に深刻です。彼らは自らの保存のためにも、自分たちの利益のために互いに譲歩することはありません。これにより、これらの国々の同盟自体が非常に緩やかになります。 これは、和衡戦略にとっては非常に簡単に破れるものです。これらの国々の対立や利益を利用する限り、同盟を簡単に解消することができ、そうなると和衡戦略は失敗します。したがって、戦国時代には真の同盟はほとんどありませんでした。代わりに、各国は互いに戦い、和衡戦略の失敗は当然避けられませんでした。 3. 蘇秦と張毅のどちらが優れているか? 官歴の面では張儀の方が蘇秦より強かった。蘇秦は張毅より後に桂谷子の弟子となった。二人は同じ流派の出身であったが、二人とも雄弁で才能に恵まれていた。しかし、彼らの状況は大きく異なっていた。張儀は「衡廉」外交政策の先駆者であり、秦周辺の国々を説得して秦に従属させ、自分たちより強い他の国からの攻撃から保護を得た。彼の政治的意見は秦の恵文王に評価され、後に官職を与えられた。 蘇秦の官職は張儀ほど順調ではなかった。出世後、何度も挫折し、才能を発揮する場もなかった。挫折して落胆した後、彼は『殷賦』を熱心に研究し、縦横の同盟戦略で六国に共同で秦を攻撃するよう働きかけた。その時初めて彼の名声と立場は改善した。二人の経歴は運に関係しているようだ。張儀は運が良かった。彼は早くからチャンスを掴み、それをうまく利用した。彼の「同盟を組んで諸国を統一する」政策は秦国に大きな利益をもたらし、秦の恵文王に重宝された。この頃、蘇秦は職を辞して各地を回っていたが、誰も彼に注意を払わなかった。彼が文献を研究して「同盟を組んで諸国を統一する」政策を提唱し、それが当時の情勢に合致していたとき、彼は多くの国々から賓客として扱われるようになった。 一見、何も問題がないように見えます。実は、張毅と蘇秦のコミュニケーション方法と表現力を深く理解すると、彼らのキャリアは、ロビー活動の出発点とロビースキルなど、他の要素と関係があることに気付くでしょう。 では、蘇秦と張毅のどちらがロビー活動のスキルに優れているのでしょうか? 答えは、張毅のほうがロビー活動のスキルに優れています。張毅は、国の利益のためのロビー活動と自身の成功への願望を巧みにバランスさせた。彼のロビー活動は彼が属する国の利益に基づいており、国家指導者に感銘を与え、具体的な利益をもたらすために徹底的な分析を行っています。 彼は秦の利益を積極的に考慮し、秦を強国の道へと導きました。彼の「衡廉」戦略は、韓と魏に朝貢を強い、秦が近隣諸国と結束して弱い国を攻撃することを可能にしました。こうして秦は豊かな土地を占領し、この肥沃な土地は秦のその後の征服に強力な兵站支援を提供しました。 対照的に、蘇秦は自分自身の利益をより重視していました。諸国を旅していたとき、彼は君主に評価され、再利用されることを願っていました。ある国の主賓になった後、彼の願いは大きくなり、より多くの人々に再利用されることを望みました。彼には独自の考えがあり、長所と短所を分析しながら、物事を自分の望む方向に進めるためにいくつかの小細工をしました。たとえば、蘇秦が斉の官僚だったとき、彼は燕と共謀して斉を併合しようとしましたが、陰謀は暴露されて失敗し、彼自身も裏切りの罪で斉王に処刑されました。 これはぞっとする話です。あなたの部下が、表面上はあなたのために働いているが、実は他の人と共謀してあなたの国を滅ぼそうとしていると想像してください。彼を十分に信頼すれば、あなたの国は本当に滅びるでしょう。このような人が多すぎると、大きなグループや国がどうしてより良い方向に発展できるでしょうか。 蘇秦と張毅の才能に関しては、蘇秦が形勢を逆転させることに成功した。張毅は長年旅をし、ある程度のコネもあった蘇秦に助けを求めたが、蘇秦は拒否した。張毅は怒って秦に亡命し、その後秦で大きな功績をあげ、ますます評価されるようになった。これは蘇秦の挑発的なやり方なのかもしれない。 誰もが知っているように、一つの山に二匹の虎はいない。同じ師を持ち、同じ才能を持つ二人が同じ国に仕えると、二人とも一定の制約を受け、一方は故意に、あるいは無意識に引き立て役となり、抑圧される。二人が同じ国にいないと、才能はより発揮される。おそらくこれが、蘇秦が張毅を助けることを拒否した理由であり、張毅も彼の拒否のおかげで自分に仕えるのにふさわしい君主を見つけたのである。七王国の乱闘の中期から後期にかけて、蘇秦は六王国の印章を手に入れた。六つの国が統一して秦に抵抗した後、蘇秦の地位は脅かされました。 彼がこのような高い地位に就けたのは、七国の力の不均衡と、秦が他国を併合しようとする野望を強めていたためである。六国が団結して秦と戦った後、七国の間には大きな争いが一つだけ残っていた。この状況では、蘇秦の役割ははるかに小さかった。蘇秦は自分の地位を維持するために、張毅が「横廉」の戦略をよりうまく実行できるように策略を巡らしたり、燕猛奇との内乱を扇動したりするなど、対立を引き起こし始めた。敵と同盟を結ぶ戦略は蘇秦の指導の下で順調に実行されたように見えた。張毅の行動も蘇秦の計画の一部だった。しかし、蘇秦の計画は大きすぎたため、結局は裏目に出て悲惨な結末を迎えた。 蘇秦と張毅の二人の外交官のうち、どちらが優れているでしょうか。この質問には、さまざまな観点からさまざまな答えがあります。人との付き合い方という点では、張毅の方が蘇秦より優れていますが、戦略という点では蘇秦の方が優れているようです。人生では、多くの人と仲良くなり、多くの摩擦や衝突が起こります。これらの衝突を適切に解決し、他の人とより友好的に付き合うことが特に重要です。一方、張毅は争いを処理するのがはるかに上手でした。この点では張毅は蘇秦よりも優れていたと言えます。誰もがそれぞれの輝かしい点を持っており、蘇秦と張毅の能力を比較することは結論づけられない、とだけ言える。 |
<<: なぜ魏国は秦の始皇帝によって滅ぼされなかったのですか?戦国時代の魏の国の有名人は誰だったのでしょうか?
>>: 周の平王は東の諸侯を効果的に統制するために、どこに都を移すことにしたのでしょうか。
推薦する
飛竜伝説第33章:李太后が皇太子を探し、郭元帥が王位に就く
『飛龍全篇』は清代の呉玄が書いた小説で、全編にわたって趙匡胤が暴君に抵抗する物語を語っています。物語...
前漢の大臣、黄覇の略歴 前漢の大臣、黄覇はどのようにして亡くなったのでしょうか?
黄覇(紀元前130年 - 紀元前51年)は、愛称慈公で、淮陽県楊夏(現在の河南省太康)出身の漢人であ...
明代読書資料『幽学瓊林』第4巻:仏教と道教の鬼神全文と翻訳注釈
『遊学瓊林』は、程雲生が書いた古代中国の子供向けの啓蒙書です。 『遊学瓊林』は、明代に西昌の程登基(...
水滸伝で方洛との最初の戦いで亡くなった3人の涼山の英雄は誰ですか?
水滸伝の魯莽遠征における最初の戦いは、潤州の戦いであった。多くの読者が気になる疑問です。次は、Int...
古代詩の鑑賞:詩集:飛鋒:吹くのは風ではなく、歌うのは車ではない
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...
西遊記 第21章:守護者は大聖人を守るために村を設立し、徐海霊基は風の悪魔を鎮める
『西遊記』は古代中国における神と魔を題材にした最初のロマンチックな章立ての小説で、『三国志演義』、『...
『偽証の術』:唐代武周時代の残虐な官僚、頼俊塵が書いた本ですが、どのような本ですか?
『虚実書』は唐代武周年間の残酷官僚頼俊塵が著した書物で、主に当時の宮廷内の複雑かつ残酷な政治闘争を描...
明代で最も強力な戦略家は誰でしたか?彼は朱元璋の天下統一を助けた
文人や学者といえば、寧才塵や張勝のような、礼儀正しくて温厚で丁寧な印象が基本です。要するに、彼らはみ...
曽公の古詩「連安二弟子序」の本来の意味を理解する
古代中国の散文「李安二生序文」著者: 曽功オリジナル:昭君の蘇軾は私と同い年の友人です。蜀から都に届...
曹操が犬のように3回吠えた後、なぜ許褚は突然笑い出したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
黄尚の「縮図ムーラン花・ドラゴンボートレース」:当日のドラゴンボートレースの光景を忠実に再現
黄尚(1044-1130)は、号を綿中、号を延山、子玄翁といい、延平(現在の福建省南平市)の出身であ...
「初夏のお昼寝から目覚めて」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
初夏のお昼寝からの目覚め(パート1) [宋代・楊万里]プラムは酸味を残し、歯を柔らかくします。バナナ...
昭公元年の儒教古典『春秋古梁伝』の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
宝安祭 宝安祭の秘密
イード・アル=フィトル。これはイード・アル=フィトル、イード・アル=フィトルとしても知られています。...
宋江は降伏後、どのような公的地位に就いたのでしょうか?今はどのレベルに相当しますか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が宋江の降伏...