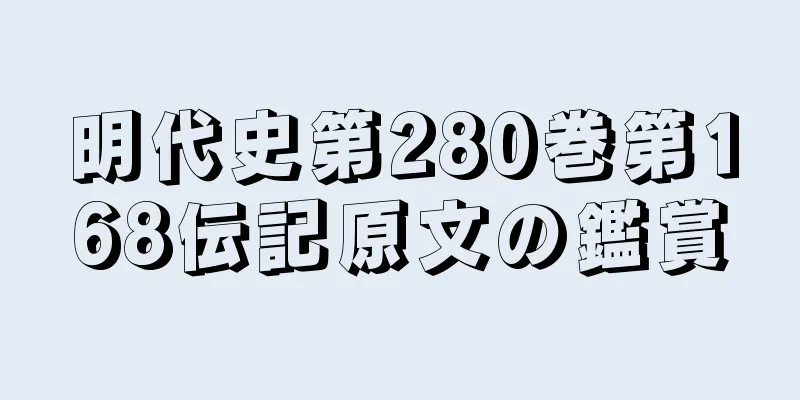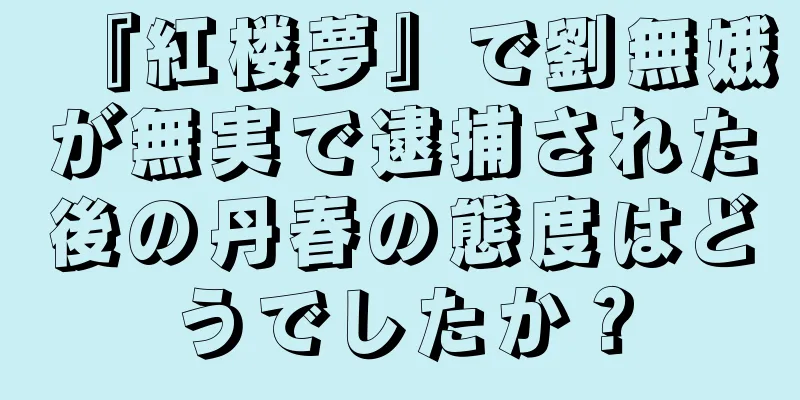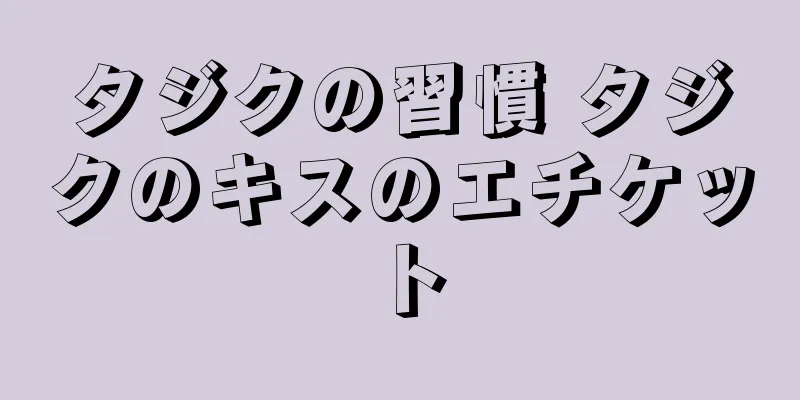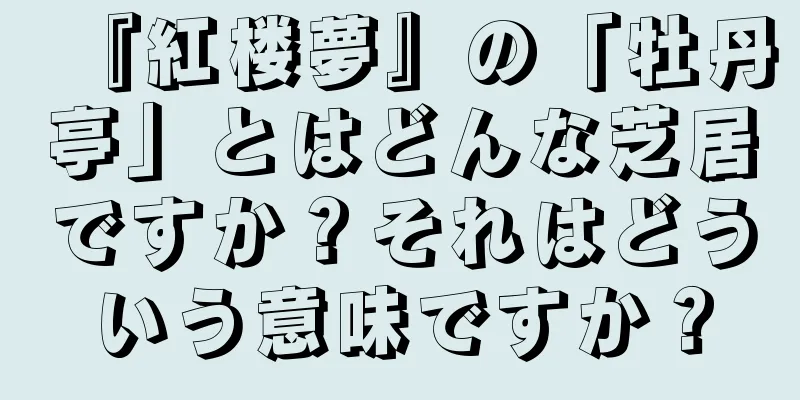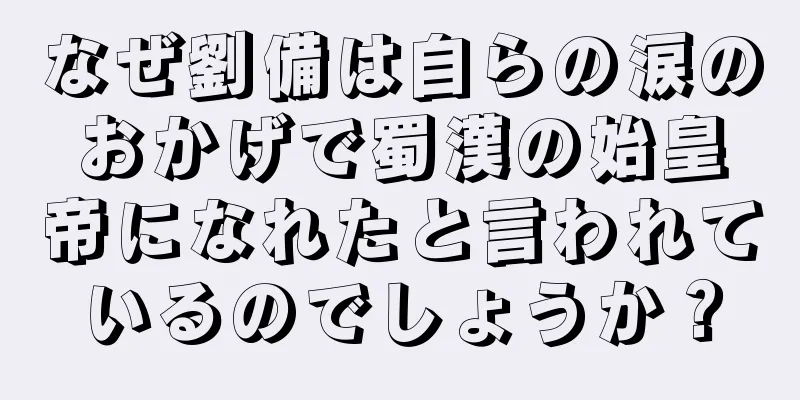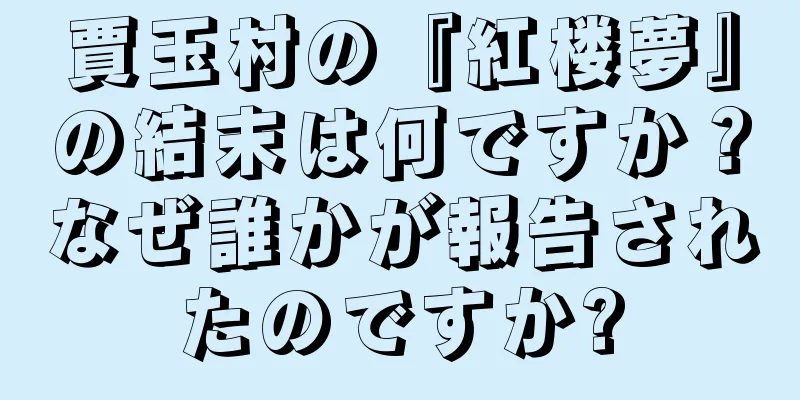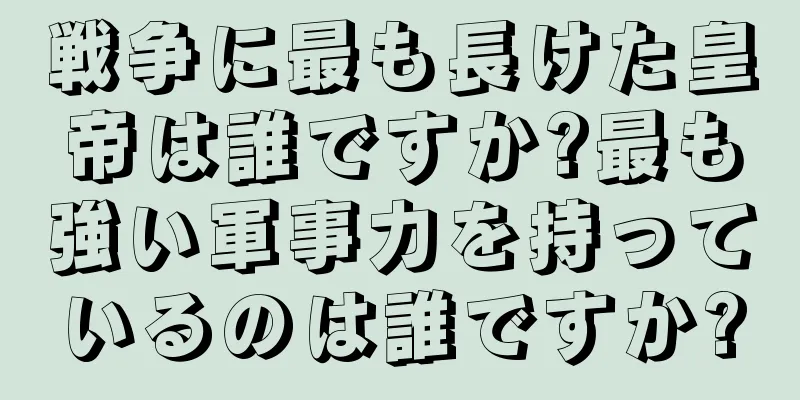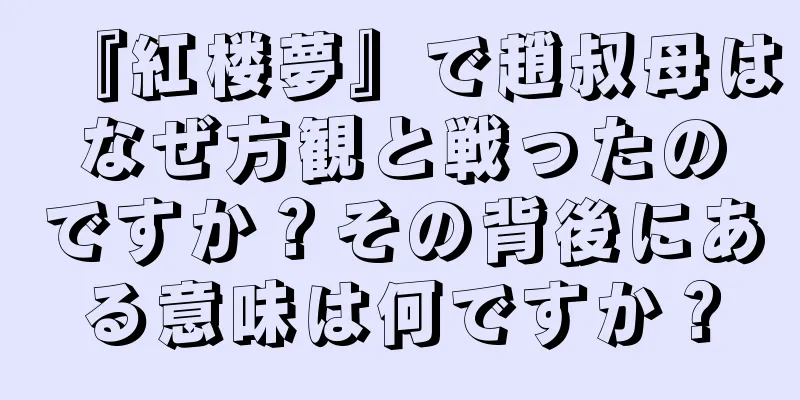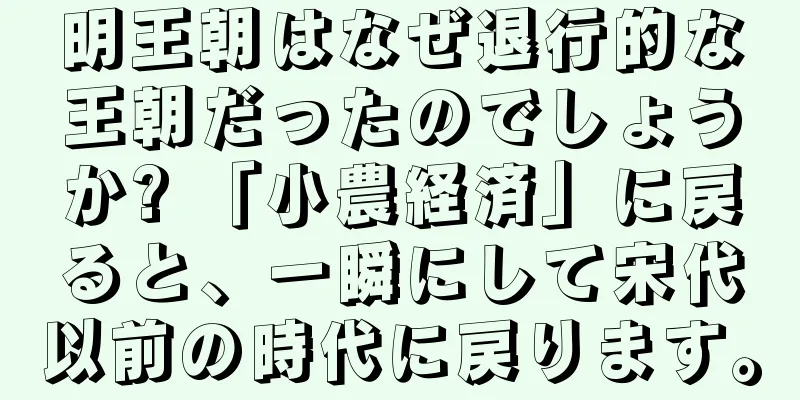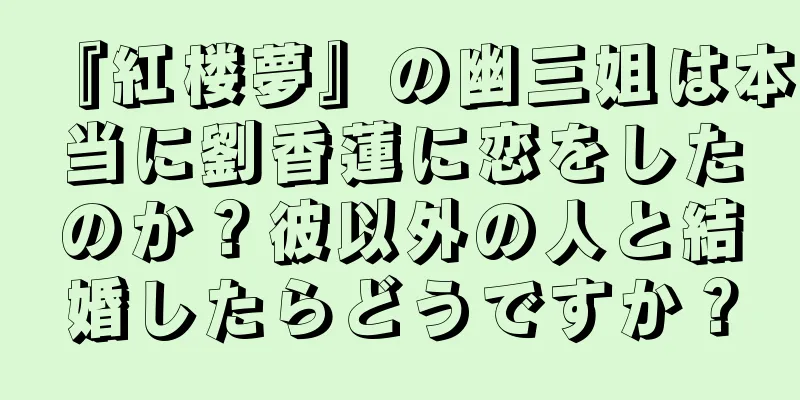「六策」は「太公六策」としても知られています。この本の最も興味深い部分は何ですか?
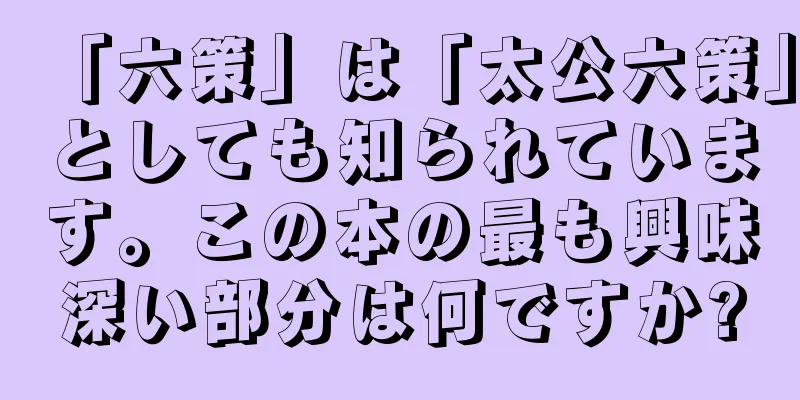
|
『六兵法』は、『太公六兵法』や『太公兵法』としても知られ、古代中国の有名な道教の軍事書です。これは中国漢代軍事文化遺産の重要な部分であり、その内容は奥深く広大、思想は洗練され豊か、論理は緻密かつ厳格で、古代漢代軍事思想の真髄が凝縮して体現されている。この本は全6巻で、全部で60章あります。 「六策」の内容は非常に広範囲にわたり、戦争に関するほぼすべての問題とさまざまな側面を網羅しています。最も興味深いのは、その戦略と戦術の理論です。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 『戦国の兵法』第22巻「魏一の兵法」:「蘇子は『周書』を引用して言った。『事は延々と続く、我々に何ができようか? 髪の毛一本でも抜かなければ斧になる。未来を確信しなければ、将来大変なことになる、我々に何ができようか?』」蘇子は蘇秦であり、ここでの『周書』は「太公金奎」または「太公謀謀」を指している。 『開元展経』第6巻と第11巻には上書金奎が引用されている。姚真宗の『隋書経事志高正太公金奎』によると、厳克君は「太公金奎の別名ではないかと疑われる」と述べている。 『戦国兵法』巻3「秦の兵法」には「(蘇秦は)太公の殷府兵法を手に入れ、隠遁してこれを誦し、その要旨を以て思索した」とある。『太公の殷府兵法』は『史記・蘇秦伝』では「周の殷府兵法書」と記されている。 『荘子・許五帰』の注釈では、司馬彪と崔伝が「『金本』と『六道』はともに『周書』の章題である」と述べていると引用されている。『銀雀山漢墓簡』でも「太公の書は古代には周書とも呼ばれていた」とされ、その証拠として「『六兵』の敦煌本には『周二十八州』という章があり、その文面は『周書・史記』の文面に似ている」と引用されている。古書に引用されている『周書』の文面も、太公の『六兵』『謀略』『金堂』とはかなり異なっている(閻克君『三代全書』第七巻参照)。 『呂氏春秋』のいわゆる『周書』は、太公書を指している可能性もある。 (閻克鈞注:殷封は殷封の陰謀を指す。戦国策では「蘇秦が太公殷封の陰謀を手に入れた」とあり、『史記』には「周書の殷封」とあるが、これは漢代の『史記』太公墨81篇を指していると思われる。「周書」は周代の歴史家の記録を指し、六秘経が周史を指すのと同じである。周書の殷封の言及は単に「周書」と呼ばれることもあり、これは失われた周書ではない。太公末に収録されており、六秘経、秘経、金堂と矛盾しないので、改めて見ても問題ない。) 『太公金魏』『隋書経』『易林』『旧唐書経』『同志略』はいずれも2巻本に収録されている。 『太公謀』『隋書経』:「太公謀」1巻(梁6巻。梁には『太公謀』3巻もあり、魏の武帝が解説している)。『旧唐書経』『新唐書文芸書』3巻、『通史文芸書』:「太公謀」1巻、3巻(魏の武帝が注釈)。 『太公金攀』と『太公謀謀』に関する最も古い明確な記録は『隋書経事志』に見られるが、実際には『斉洛』と『漢書易文志』に収録されている。 『漢書・易文志』の『冰舒歷・冰泉神』には、「冰泉神は13の流派、259章から成る」とある。小さな注釈には、「『易音』『太公』『管子』『孫清子』『何管子』『蘇子』『会統』『陸甲』を除いた『淮南王』には259章があり、これは『司馬法』から派生したもので、儀式に含まれている」とある。 西漢の国家蔵書目録『漢義文志』『諸哲人道教略』には、「太公には237篇ある。(呂王は周の師であり祖父で、もともと道教を持っていた。現代では太公の術を書いた人が付け加えたと考える人もいる。)『蒙』には81篇、『炎』には71篇、『兵』には85篇ある」とある。清代の沈欽漢は、「蒙」は太公の『謀略』を指し、「炎」は太公の『金閣』を指し、「兵」は太公の『兵法』を指すと言っている。 『漢書・易文志』の「兵法」の注釈には「『太公』を抄」とあるので、「兵法」の内容の一部は『斉楽』に収録されている「太公」から来ていることは間違いない。顧氏は「原典では『太公謀』は81章、『兵』は85章である。現在の『管子・兵法』、『乾環』、『荀子・易兵』、『淮南子・兵略』などの章は、すべて259章の中に入っているはずだ」と述べている。先人たちは、『漢書・易文志』に記された「謀」は「明帰」であり、これはまた「太公謀」であり、「炎」は「太公金奎」であり、「兵」は「太公兵法」あるいは「六計」あるいは「太公六計」であることを証明している。 Qian Dazhaoは、「Taigongの237の章は「Mou」、「Yan」、「Bing」と呼ばれています。 Uai Nanzi 'と「Shuo Yuan」はすべてそれらを指します。 Angziは「6つのゴールデンプレート」と呼ばれ、「Huai Nanzi」は「黄金のヒョウ戦略」にも言及しています。」 『漢書・義文志』の「各哲儒略」には、もう一つの「『周史六道』六章」があり、脚注で「慧と襄の間、献王の時代に書かれたという説もあれば、孔子が出したという説もある」とある。顔時固は「それが現在の『六兵法』である」と信じた。『四庫』の役人たちはこれに反対し、これらは2冊の別の本であると信じた。清代、沈涛の『同隠斗寨論』は、『韓志』の「六涛」は「大涛」であることを証明した。孔子が『荘子沢要』で歴史家大涛に尋ねた人物は、この人物だった。「現在の『六兵法』は『太公』237章の中にあるはずだ」。姚真宗の『隋書経事志考正』は、「この証拠は極めて正確だ」と信じていた。『太公金魏』、『太公謀』、『太公兵法』、『六兵法』はすべて道教の『太公』から来ていることがわかる。 『史記・斉太公家』には、「周の王羲伯昌が幽里から脱出した後、戻って呂尚と共謀して徳を積んで商の政権を倒そうとした。その功績の多くは軍事力と並外れた戦略を伴うものであった。そのため、後世の周の軍事と隠された権力について語る人々は皆、太公を元祖の戦略家とみなした」と記されている。『崑学集文』第11巻では、葉孟徳の次の発言も引用されている。「この説はおそらく『六計』から来たものであろう」。宋代志の『書譜』第2巻には、「文王と太公が共謀して商の政権を倒そうとしたという主張については、彼らの功績の多くは軍事力と並外れた戦略を伴うものであった。しかし、『漢書・義文志』には、「呂王は周の商の父であり、元祖である」と記されている。中には義理の者もおり、太公の技巧を駆使して近世に加筆した者もいる。「漢代には疑われていたが、今では正典として研究すべき対象になっているではないか」。宋何厳の『春秋集文』巻五「古書名有」には「先祖は『六道』は太公の著作ではないと言っているが、その中には検証の跡もある。」とある。明胡英林の『漢志』の「四書訂正」には「『六道』は『漢志』にあるが、最初は太公の著作とは言われていなかった。東漢末期に本は失われ、魏晋の軍学者が残りの部分を拾い集めてこの本にしたのが『隋志』の『六道』である。」とある。 『史記 劉邦伝』には、張良が橋の上で父から一冊の本を受け取ったと記されており、「その本を見ると、太公の兵法であった」とある。また、前述の『戦国兵法 秦の兵法』には、蘇秦が「太公の殷府兵法」を受け取ったと記されている。 『太公』を楚漢時代、あるいは漢代の著作とみなすのは、やや保守的であるように思われる。歴史上、『六兵法』はその内容から戦国時代の著作であると判断した学者もいる。 宋代の葉舒は『西学集論』第46巻「六秘経」で「正殿を避けるという書は戦国時代のもので、孫子より後のものであろう。」と書いている。『崑学集文』第5巻「古代、人々は戦車で戦った。春秋時代には、鄭と晋には歩兵があり、騎兵は戦国時代の初めに始まったと思われる。屈礼以前にも戦車と騎兵があり、『六秘経』は騎兵戦について語っているので、その書は周代末期に書かれたはずである。」 陶仙はかつて『漢書・易文志』について次のように評している。「『淮南王』に重複している259章は、『易隠』、『太公』、『管子』、『孫清子』、『何管子』、『蘇子』、『会統』、『陸甲』を除いたもので、『七類』の『易隠』以降の9章である。本書には儒家、道家、外交家、雑家などの流派がすべて含まれており、その中で軍事戦略について語るものを選んでここに収録しており、合計259章となっている。」著者はかつて次のように述べている。「秦以前の時代には軍事戦略家はいなかった。」戦国時代、戦争は各国の政治思想や教義の主要テーマでした。儒教、道教、墨家などの宗派はそれぞれ独自の兵法書を持っていました。『六兵法』や『太公兵法』は間違いなく道教の『太公』の兵法書の一部です。 『太公』は文王、武王、太公の問答から成ります。太公呂望は周の人民戦争の軍司令官で、商王朝を滅ぼしました。斉公の称号を授けられたので、『太公』は斉から来た作品です。 『太公』は戦国時代の斉国の道教作品です。 太公呂望は『太公金魁』の「金人銘」でも黄帝の理論を引用している。李凌氏は黄帝の著書は「主に数学や医術などの実用書、軍事科学における数学の一分野である軍事陰陽に分布しており、各学派では主に陰陽、道教、およびその小説や雑記である」と考えている。黄帝の著書には『黄帝戦蚩尤』などの数学書や『黄帝と蘇女問う』などの医術書がある。『太公謀略』と『太公金魁』は有名な聖人による国を治め、軍事力を利用する陰謀書で、道教の黄老の著作である。 つまり、『太公金魁』、『太公謀』、『太公冰法』あるいは『六密教』はすべて『太公』の内容であり、『太公』は戦国時代の斉国の道教黄老書である。 |
<<: 『六兵法』は周の時代の蒋太公が著した本です。この本にはどのような国を治める考えが書かれているのでしょうか?
>>: 蒋子牙の生涯にわたる業績を見て、歴史上誰が彼についてコメントしたでしょうか?
推薦する
胡三娘はなぜ「易張青」と呼ばれているのですか? 「一丈青」とはどういう意味ですか?
胡三娘はなぜ「易張青」と呼ばれているのでしょうか?「易張青」とはどういう意味ですか?興味のある読者は...
西涼政権の君主、李勲の略歴。李勲はどのようにして亡くなったのでしょうか?
李勲(?-421)は、隴西省城邑(現在の甘粛省秦安市)の出身で、西涼の武昭王李昊の息子であり、西涼最...
「人間に生まれてごめんなさい」という言葉はどこから来たのでしょうか? 『No Longer Human』という本はどんな内容ですか?
「人間に生まれてごめんなさい」という言葉はどこから来たのでしょうか?『人間失格』はどんな内容の本なの...
丁風波の鑑賞:3月7日、詩人蘇軾が黄州に流された後の3年目の春に書かれた
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
契丹騎兵に対抗するための北宋の最終兵器、「水の長城」とはどのようなものでしょうか?
北宋が契丹騎兵に対抗するための最終兵器「水長城」とは? 以下に、興味深い歴史の編集者が関連内容を詳し...
『環西沙・桂清』鑑賞、当時詩人李清昭はまだ少女だった
李清昭(1084年3月13日 - 1155年)は、易安居士とも呼ばれ、宋代の斉州章丘(現在の山東省章...
王莽は改革政策をどのように実行したのでしょうか?反乱を起こした軍隊は誰でしたか?
王莽は先見の明があったものの、残念ながら実行力に欠けていた。また、学識に富み、制度さえ変えれば世の中...
『明代史』第217巻第15伝記原文の鑑賞
王家平、陳玉弼、沈麗、于沈、李廷吉、呉道南王嘉平、名を中波、大同市山陰出身。龍清二年に進士となった。...
辛其記の詩「何心朗・龍亭酒談」の鑑賞
【オリジナル】何新朗:パビリオンで飲み語り長いパビリオンでお酒を飲みながらおしゃべりしましょう。円明...
朱高祚の最初の妻、張皇后の簡単な紹介
張承孝皇后(? - 1442年11月20日)は、名前は不詳、河南省永城市高荘鎮張大廠村の人である。彼...
貧しい少年のおとぎ話
魏の時代、吉北県に仙超という名の男がいた。名は易奇。嘉平年間のある夜、彼が一人で留守番をしていたとき...
朱元璋は字が読めなかったのにどうやって記念碑を視察したのでしょうか?この記念碑は清朝の順治年間に建てられました。
記念碑は清の順治年間に現れ、記念碑が正式に固定された制度になったのは康熙年間になってからでした。つま...
張元安著『水の旋律・追歌』の何がそんなに良いのでしょうか?
張元安の「水条歌頭追歌」は彼の代表作の一つです。では、この詩の何が良いのでしょうか?次の興味深い歴史...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源編第4巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
秦観の春の悲しみについての詩は、読むととても悲しい
秦貫は北宋時代の詩界における重要な人物であった。彼の宋代の詩は優美で優雅な傾向があり、主に男女の愛や...