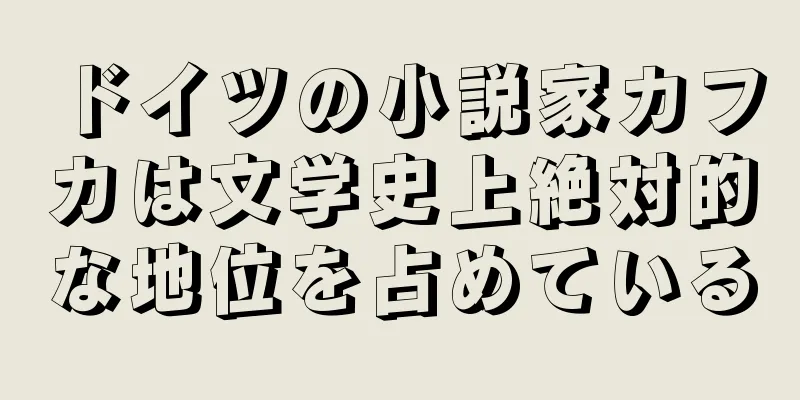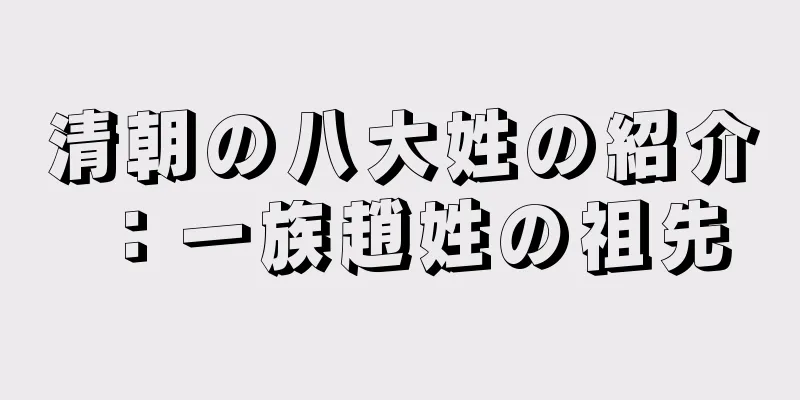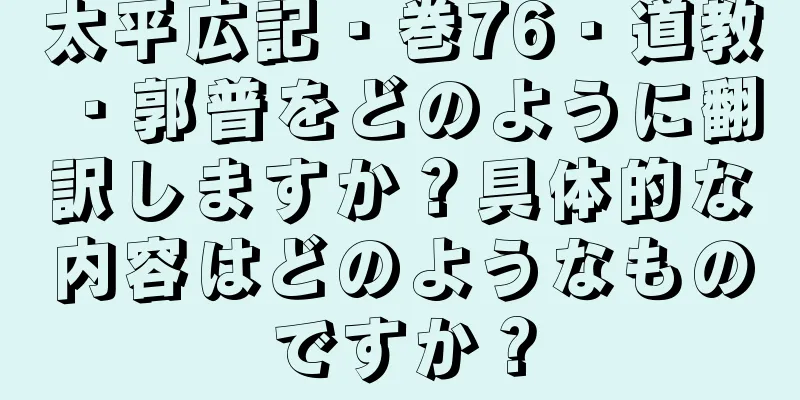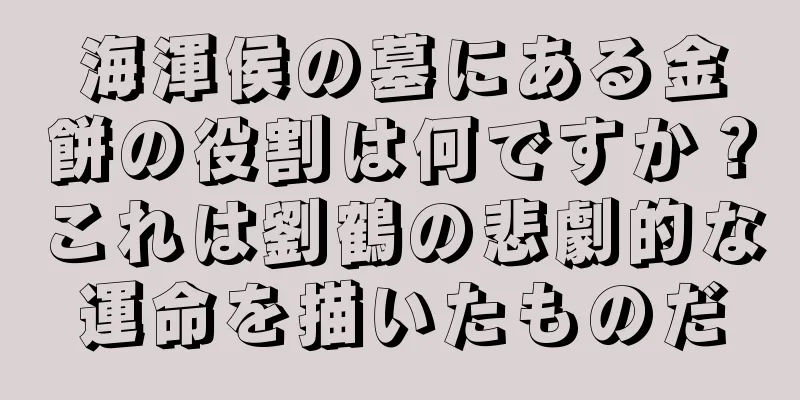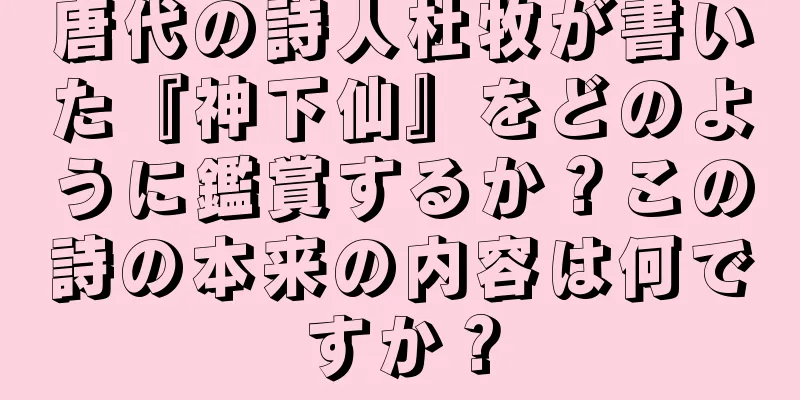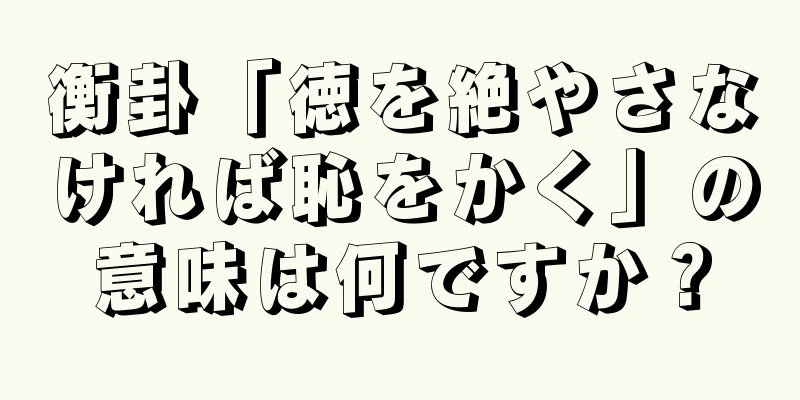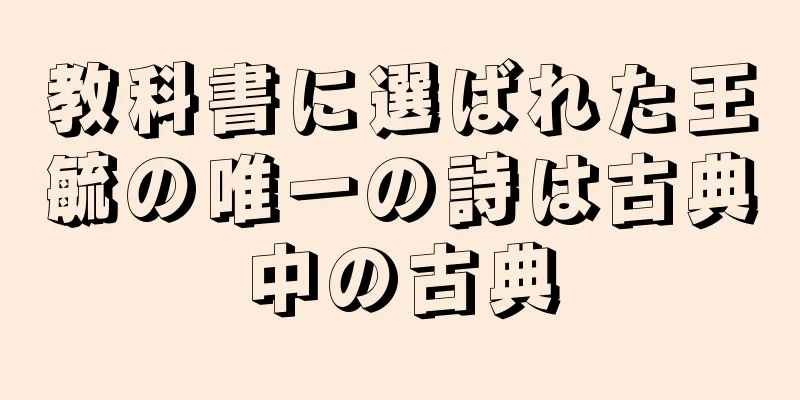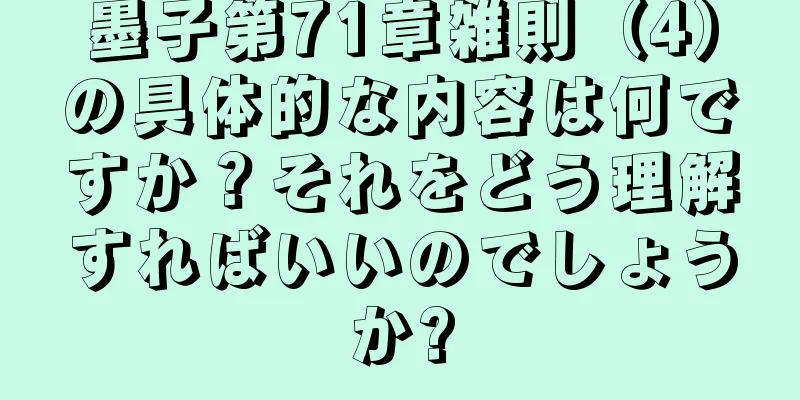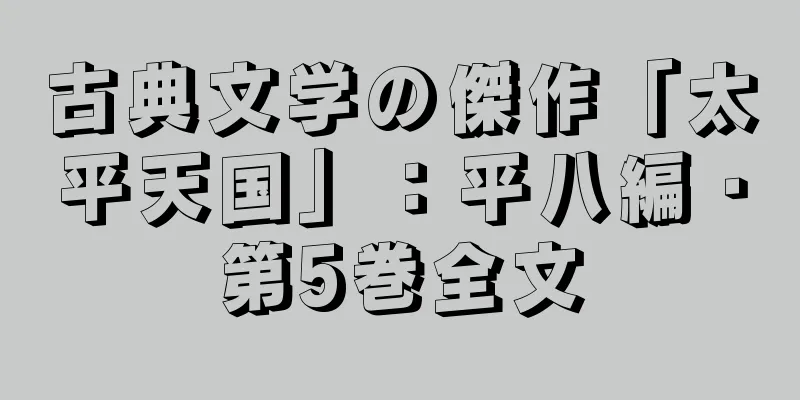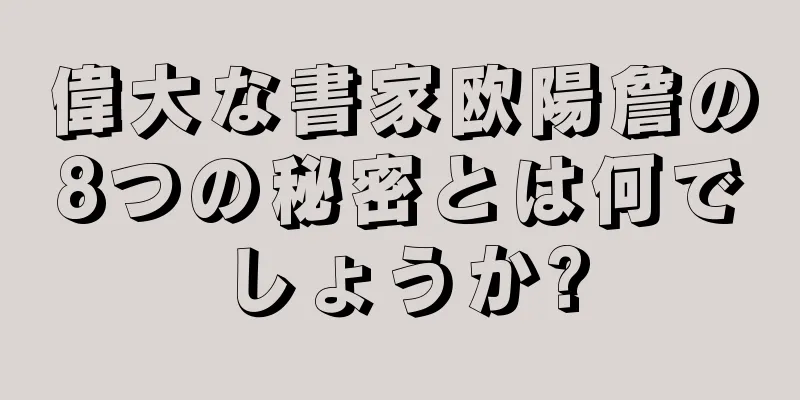韓信は股間を蹴られる屈辱に耐えるつもりだったのに、なぜ剣を抜かなかったのか?
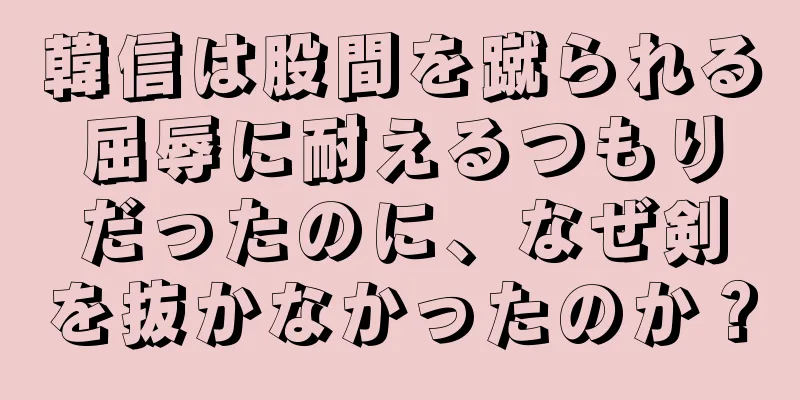
|
『秦の月』は近年中国で大人気のアニメで、国内アニメの最高レベルをほぼ代表しています。『秦の月』では、韓信が常に刀を携帯しているのがわかりますが、不思議なことに、彼がこの刀を使う場面は一度も見られません。実は、アニメだけでなく歴史上でも韓信は刀を所持していました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 西漢の歴史家、司馬遷は『史記』の「淮陰侯伝」の中で、「淮陰侯韓信は淮陰の人であった。庶民になった当初は貧しく、剣を好んで持っていた。」と述べています。これは、韓信が淮陰の人であったことを意味します。庶民になった当初は貧しく、剣を好んで持っていたということです。 戦国時代は冶金技術があまり発達しておらず、刀を鍛造するのは非常に困難でした。 韓信は幼い頃は食べることさえままならず、刀を買うお金も、刀を鍛造する人を雇うお金もありませんでした。 そのため、この刀は韓信が生まれたときにすでに存在していた可能性が高いです。 では、韓信の剣の起源は何でしょうか?現在の史料には韓信の両親に関する記録はありませんが、易仲天の推測によれば、韓信は貴族の末裔である可能性が非常に高いです。つまり、韓信の先祖はかつて貴族でしたが、韓信の時代になると衰退したということです。もしこれが本当なら、韓信の剣の起源を説明するのは難しくない。結局のところ、当時の貴族が剣を所有するのは非常に一般的だったのだ。 韓信の剣の由来がわかったところで、もう一つの疑問について考えてみましょう。なぜ韓信は剣を持っていたのに、一度も使ったことがないのでしょうか? 多くの人がドラマ「楚漢の戦い」を見たことがあると思います。このドラマでは、韓信の剣はほとんどいつも持ち歩いていますが、不思議なことに、彼は一度もそれを使いませんでした。いじめられたときでさえ、韓信は剣を抜くよりもむしろ屈辱を受けることを好みました。それはなぜでしょうか? 実は、韓信の経験から言えば、韓信は単なる戦略家ではなく、武術に長けているはずです。なぜそう言うのですか?考えてみてください。誰であっても、子供の頃から剣を持ち歩いていたら、それを取り出していくつかの動きを練習したのではないでしょうか。特に戦国時代はそうです。たとえ韓信が達人ではないとしても、武術を知っていることは間違いありません。この場合、なぜ韓信は剣を使わなかったのでしょうか? 実は、可能性は一つだけあります。つまり、この剣の起源は単純ではなく、韓信が簡単に使うことはないということです。前述のように、韓信は没落した貴族の子孫である可能性が高いため、韓信の剣は家宝であった可能性が高い。一般的に、祖先の剣は非常に重要であり、特別な象徴的な意味を持っています。おそらくこれが、韓信がこの剣を一度も使用しなかった理由です。 |
<<: 劉備は漢の献帝の退位をはっきりと聞いていたのに、なぜ急いで自ら皇帝を名乗ることを選んだのでしょうか?
>>: 劉邦と項羽の顧問として、張良と范増のどちらがより有能でしょうか?
推薦する
『康倉子』第七巻順々道の原文には何が記されているか?
閔子謙は孔子に尋ねた、「道と孝行の違いは何ですか?」孔子は言った。「道は自然の素晴らしい働きであり、...
東漢の皇帝舜劉舜には何人の子供がいましたか?
漢の舜帝劉豹(115年 - 144年9月20日)は、漢の安帝劉虎の息子であり、母親は李という名の宮女...
学者第53章:雪の夜に公爵邸宅が客をもてなす。客棟の明かりが人々を夢から覚ます
『士人』は清代の作家呉敬子が書いた小説で、全56章から成り、様々な人々が「名声、富、名誉」に対してど...
宋萬の「獄中月向」:詩全体が感情と情景を融合し、全体を構成しており、深く感動させる。
宋萬(1614-1673)は清代初期の有名な詩人で、清代八大詩人の一人である。名は玉樹、理尚。漢族で...
中国古典文学の原典の鑑賞:易経・第五十五卦・風水卦
風水六十四卦は豊かさと大きさを象徴します。離は稲妻と火を表し、震は雷を表します。雷と稲妻が同時に現れ...
『封神演義』で魏虎はどんな人物ですか?
禅宗十二金仙の一人、道興天尊の弟子である衛虎は、魔を鎮める杵を振るう。彼は第59章で初めて登場し、そ...
紅楼夢63話:一紅の誕生日の夜の宴、金丹の家族の葬儀
『紅楼夢』は、中国の四大古典小説の一つで、清代の章立て形式の長編小説です。通俗版は全部で120章から...
古典文学の傑作「太平天国」:人材資源第99巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』で西仁の腰に巻かれた赤いハンカチにはどんな特別な意味があるのでしょうか?
『紅楼夢』では、誰もがハンカチを持っています。今日は、Interesting History の編集...
周邦厳の「曼亭坊・麗水五郷山夏詩」:この詩は稀少で貴重な傑作である
周邦厳(1057-1121)、号は梅成、号は清真居士、銭塘(現在の浙江省杭州市)の人。北宋時代の作家...
『半兵衛』の執筆背景は?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】元和帝は神々しく威厳のある姿をしています。彼らは誰でしょうか?玄と羲です。私は歴代皇帝...
唐延倩の「春は終わる」は、春が終わるときの名残惜しさや別れを惜しむ気持ちを表現しています。
唐延謙は、字を茂業、号を路門先生といい、唐代の官吏、詩人であった。博識で多芸、文章が素晴らしく、書画...
『紅楼夢』で黛玉はなぜ北京太子の贈り物を拒否したのですか?理由は何でしょう
中国の古典『紅楼夢』のヒロインである黛玉は、金陵十二美人本編の最初の二人の登場人物の一人です。今日は...
陳涛の「隴渓行四詩集 その2」:この詩はあまりにも悲しくて涙が出てくる
陳涛(812年頃 - 885年)、号は宋伯、三教庶人と称し、鄱陽江埔の人であった(『唐詩全集』では嶺...
『詩経・小夜・狄度』原文、翻訳、鑑賞
エウパトリウム匿名(秦以前)柄杓を持った杜があり、提灯を持った本物の杜もあります。王の務めには終わり...