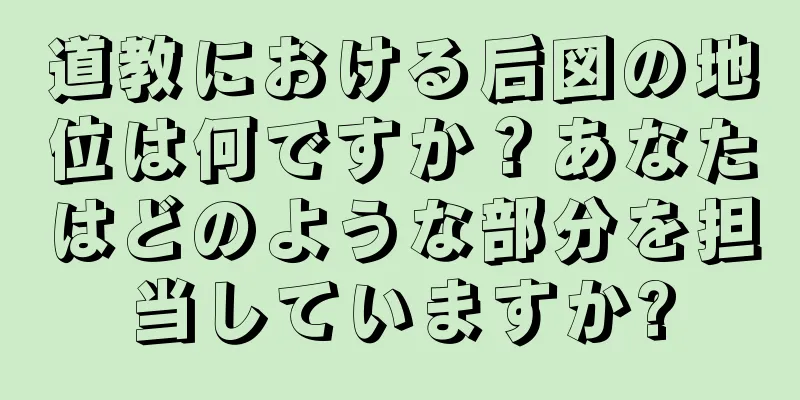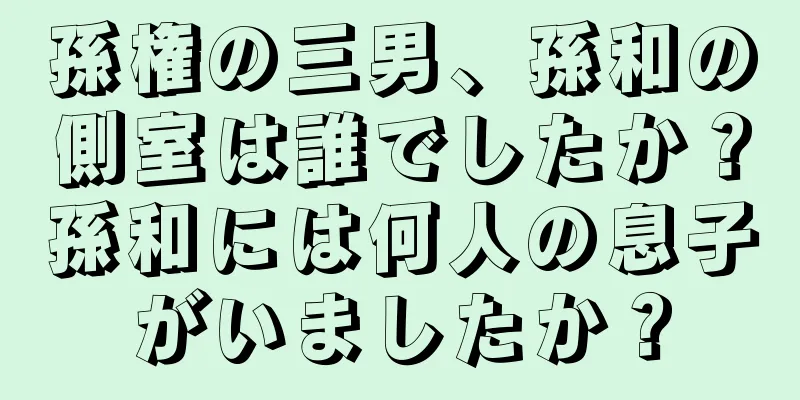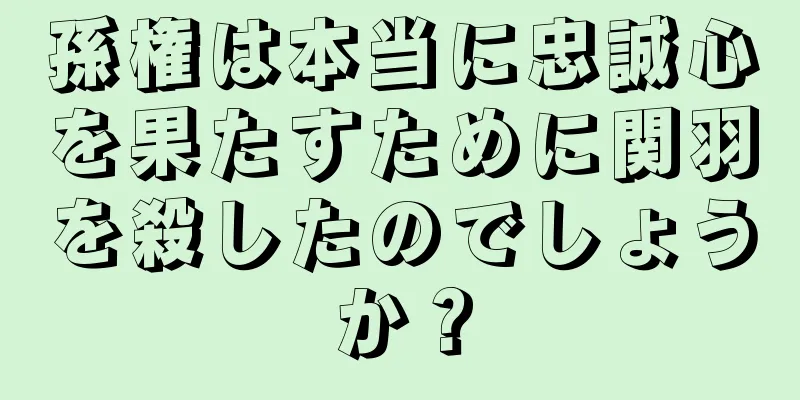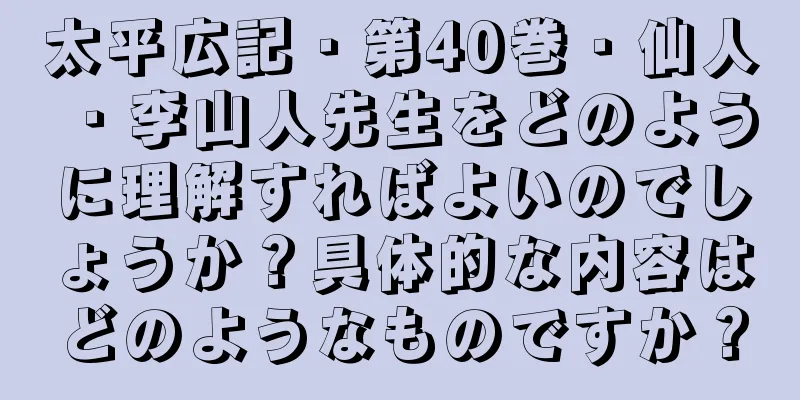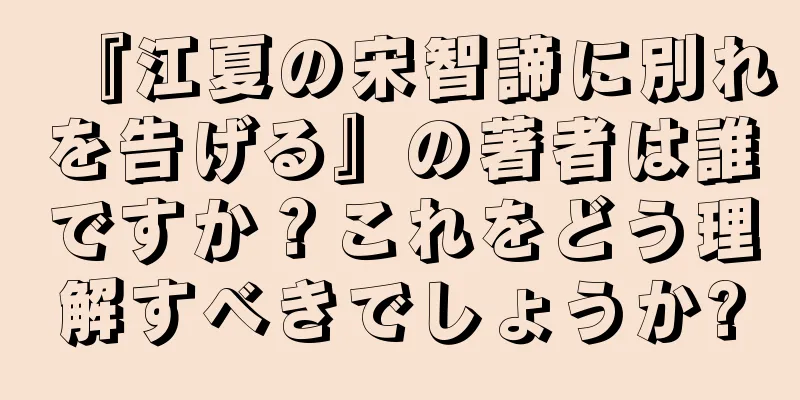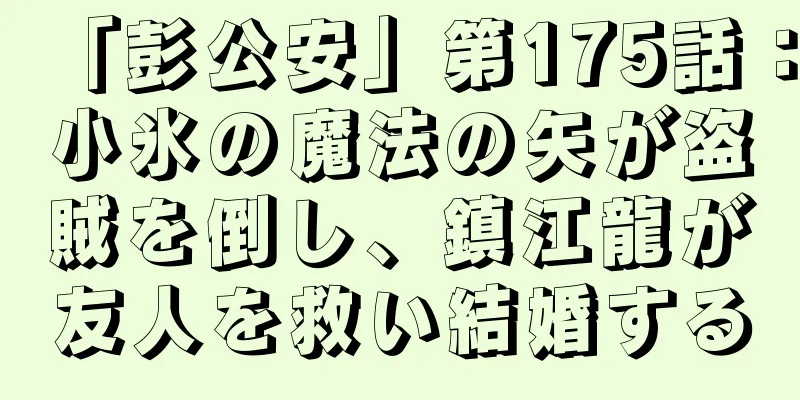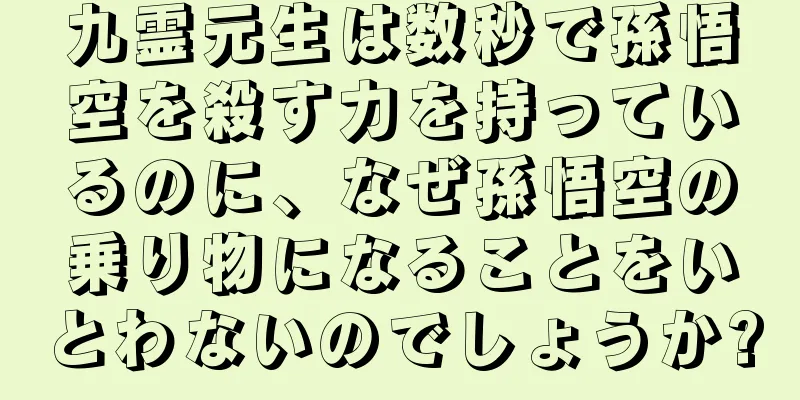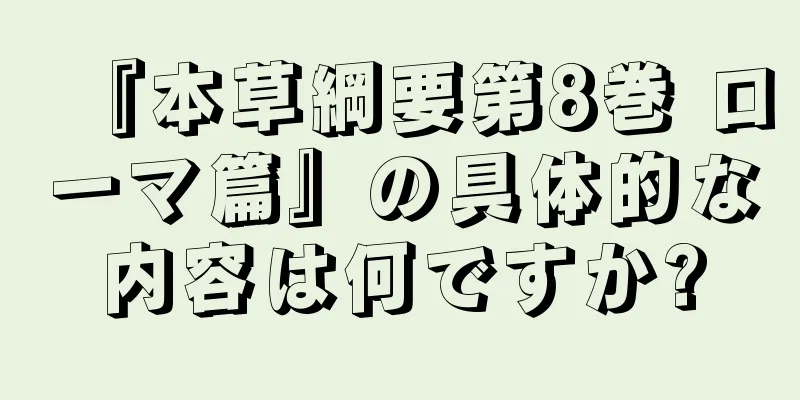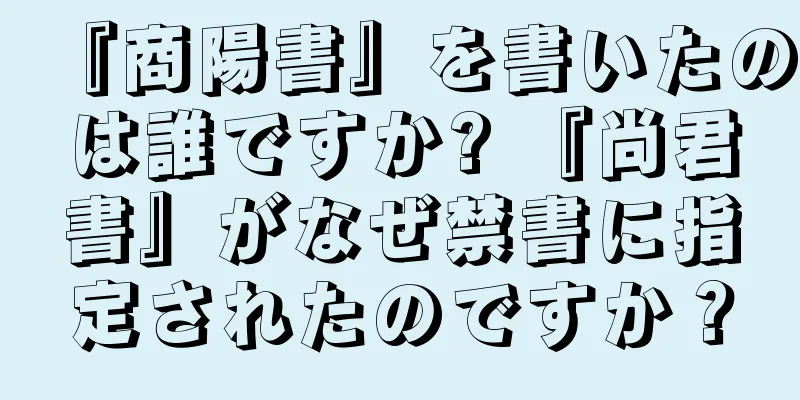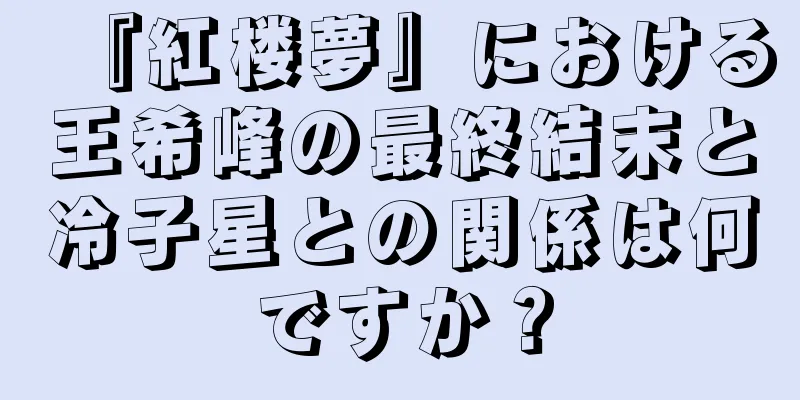有名な曹魏の将軍、張郃が諸葛亮に待ち伏せされたとき、司馬懿は何をしたでしょうか?
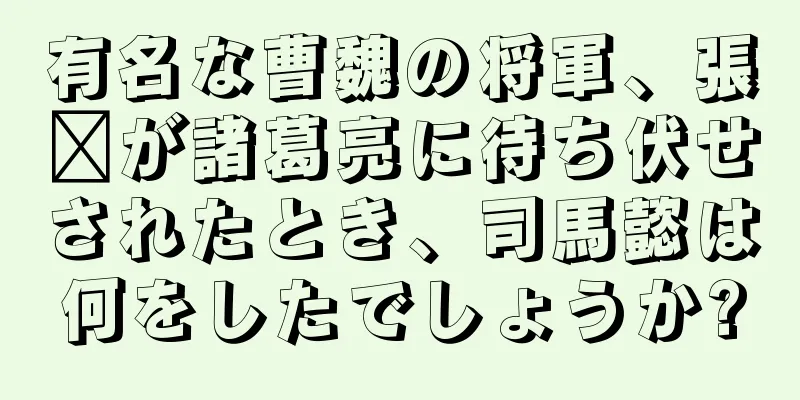
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、張郃の死が司馬懿による意図的なものであったかどうかについて詳しく紹介します。見てみましょう! 諸葛亮の第四次北伐の終わりに、諸葛亮は撤退中に曹魏の名将張郃に追われ、木門路で諸葛亮の待ち伏せ部隊に射殺された。張郃の死は曹魏にとって大きな損失でした。曹魏の皇帝である曹叡もその知らせを聞いて非常に悲しみました。当時張郃の直属の上司であった司馬懿は、張郃の死に対して逃れられない責任を負っている。それで、司馬懿は張郃の死後何をしたのでしょうか? 1. 張郃の死。 『三国志演義』では、司馬懿は経験豊富で慎重な指揮官として、張郃は衝動的で勇敢な将軍として描かれています。彼は敵を過小評価し、無謀な行動をとったため、戦場で何度も敗北を喫し、張飛、黄忠、趙雲、馬超に次々と敗れた。諸葛亮との戦いの間、彼の勇敢さは諸葛亮の注目も集め、諸葛亮はこの敵を排除しようと決意した。 諸葛亮の第四次北伐の際、張郃は再び諸葛亮と戦った。この戦いの間、司馬懿は諸葛亮を非常に恐れ、どこでも屈服したため、張郃は非常に不満でした。諸葛亮が退却するとき、張郃は司馬懿の反対にもかかわらず、諸葛亮の追撃を主張した。諸葛亮が派遣した魏延と関行は、張郃を敗れたふりをして木門道へと導いた。待ち伏せしていた軍勢の矢の集中砲火により、張郃とその将軍たちは木門の中で射殺された。 実際には、張郃は諸葛亮を追跡中に蜀軍との戦いで太ももを撃たれて死亡した。しかし、張郃が諸葛亮を追いかけたのは、自ら進んで求めたからではない。三国志演義の記述とは異なり、張郃は蜀軍の追撃に反対していたが、張郃に蜀軍の追撃を主張したのは司馬懿であった。 諸葛亮が撤退したとき、司馬懿は張郃に追撃を命じたと歴史書に記録されている。張郃は司馬懿に反対し、「軍法によれば、城を包囲するときは、包囲された者が脱出できる道を用意しなければならず、退却する敵軍を追撃してはならない」と言った。しかし、司馬懿は張郃の忠告に従わなかった。張郃は前進して追撃するしかなかった。その結果、蜀軍は高台に待ち伏せし、無差別に弓や弩を放ち、張郃は射殺された。 2. 司馬懿と張郃の対立する協力。 諸葛亮が第四次北伐を開始したとき、曹魏の総大将である曹真が重病に陥った。諸葛亮の攻勢に抵抗するため、曹叡は曹真に代わって司馬懿を任命した。張郃は曹真のもとで最も有能な将軍であり、その後は司馬懿のもとに仕えた。しかし、両者の協力は快いものではなく、当初から多くの対立がありました。 諸葛亮の第四次北伐に対する防衛の全過程において、張郃は司馬懿が提案したあらゆる指揮方針に反対を表明した。諸葛亮が最初に岐山を包囲したとき、張郃は漢中に残っていた諸葛亮の軍隊の攻撃を防ぐため、軍隊をいくつかの場所に分けた。司馬懿は、前線の軍隊が諸葛亮の攻勢に耐えられるかどうか判断できず、諸葛亮が軍隊を一人ずつ倒せるように軍隊を分散させることもできないとして、張郃の提案を拒否した。 司馬懿は上桂で諸葛亮と遭遇した後、諸葛亮と戦わず、陣営の防衛のみを行った。諸葛亮が軍を撤退させた後、司馬懿は率先して諸葛亮の居場所を追跡した。張郃はこの時も、戦場の状況から判断して、自らは戦わず、その場で防御し、奇襲部隊を派遣して諸葛亮の背後を攻撃する方がよいと再度提言した。諸葛亮を追うべきではなかったが、敢えて彼に近づいて戦うことをしなかったため、皆の自信が失われてしまった。諸葛亮の軍隊は食糧が不足しており、すぐに撤退しなければならないだろう。司馬懿は再び張郃の提案を拒否した。 その結果、司馬懿は諸葛亮に追いついた後も、昔のやり方を繰り返し、依然として戦うことを拒否した。この時、張郃の予想通り、配下の将軍たちは皆興奮し、諸葛亮との決戦を要求した。司馬懿は諸葛亮を虎のように恐れていると誰もが思っていたため、彼は世間の笑いものになった。司馬懿は部下の要求を抑えることができず、諸葛亮との決戦に軍隊を派遣せざるを得ず、呂城の戦いで惨敗を喫した。 この戦いで司馬懿は大きな損失を被り、一方張郃は力を温存したまま撤退した。当時、張郃の任務は蜀軍の主力の背後から南威を攻撃することだった。司馬懿が敗れた後、張郃は蜀軍に三方を包囲された。しかし、張郃はこのような困難な状況下でも無事に撤退することができた。この点から見ると、張郃の戦場指揮能力は司馬懿よりわずかに優れていると言える。 しかし、司馬懿は依然として張郃の忠告に耳を傾けず、司馬懿は張郃に追撃を強要した。張郃は諸葛亮の追撃に反対したが、司馬懿の厳命により戦闘を強いられ、木門路で諸葛亮の奇襲部隊に射殺された。以上の状況から、司馬懿と張郃の間の対立が非常に深かったことがわかります。それで、張郃の死は司馬懿が借りたナイフで人を殺したという故意のものだったのでしょうか? 3. 司馬懿はなぜ張郃を諸葛亮の追撃に派遣したのですか? 以上の状況から判断して、張郃は司馬懿の強制により諸葛亮を追撃した。張郃は当初追撃する気はなかったが、司馬懿は頑固で張郃に軍を率いて攻撃するよう主張し、結果的に張郃は待ち伏せされて殺された。では、なぜ司馬懿は張郃を派遣して諸葛亮を追撃させたのでしょうか? 司馬懿と張郃の対立から判断すると、陰謀の影があるようだ。曹叡が曹真に代わって司馬懿を任命したとき、彼は内部の反対に遭遇した。ある人は、諸葛亮の軍隊には荷物がなく、戦うには上桂の小麦に頼るしかないと彼に示唆した。上桂の麦が収穫されれば、諸葛亮は当然食糧もなく撤退し、大軍を送って対処する必要もなくなるだろう。 曹叡はこの提案には動じず、曹真に代わって司馬懿を関龍軍の司令官に任命した。もし曹叡が司馬懿を関龍軍の指揮官に派遣していなかったら、張郃が曹真の後を継いだであろうことは想像に難くない。これは、曹魏の中に司馬懿に反対する勢力があったことを示しています。彼らの目には、張郃は曹魏に忠実であり、司馬懿の強力な競争相手でした。 この前提からすると、張郃と司馬懿が調和的に協力しないのは当然です。司馬懿と張郃はお互いを対立するグループの競争相手とみなしていたため、何事においても口論や対立を繰り返し、意見も常に異なっていました。張郃は関龍軍団内で名声を博していたため、司馬懿が関龍軍団を支配したければ張郃を排除しなければならなかった。そのため、司馬懿は張郃を強制的に戦闘に送り込み、借りた刀で諸葛亮に人を殺させることが可能になった。 しかし、軍の指揮官として、司馬懿が最も有能な将軍を密かに攻撃するのは、少し行き過ぎのように思われた。張郃の死にはもう一つの理由がある。それは、張郃が司馬懿の戦略を試した犠牲者だったということだ。諸葛亮の第四次北伐の際、司馬懿は諸葛亮との戦いで経験と教訓を得て、次の防衛計画を立てた。張郃の攻撃はこの試練の重要な部分であった。 司馬懿は諸葛亮との戦いにおいて非常に慎重であり、明確な目的を持っていたことがわかります。彼はまず緊迫した戦法を採用し、常に主力を率いて諸葛亮の軍の近くに留まり、諸葛亮の行動範囲を狭め、可能な限り主導権を握った。諸葛亮との野戦では、呂城の戦いで惨敗し、曹魏の軍が蜀軍に敵わないことを悟った。 諸葛亮が食糧を使い果たして撤退を決意したとき、司馬懿は張郃に蜀軍を追撃させるよう主張した。これは諸葛亮の撤退の特質を試すためでもあった。なぜなら、これまでの戦闘で、魏軍は不適切な追撃により多くの敗北を喫し、王爽のような優秀な将軍も失っていたからです。諸葛亮の軍事行動を自ら判断することによってのみ、司馬懿は貴重な経験を得ることができた。 司馬懿は諸葛亮との戦いで、彼に対抗するための戦略と戦術を編み出した。この戦略と戦術は、すぐに司馬懿によって諸葛亮の第五次北伐に対する防衛に利用されました。この戦略と戦術は、諸葛亮と野戦をするのではなく、持ちこたえて前進しない戦術を採用し、諸葛亮が長旅で疲れているのにつけ込み、食料や草が尽きて撤退するまで待ってから、敵を追撃して倒すというものでした。 この一連の計画は、司馬懿が諸葛亮の第四次北伐に抵抗した経験から生まれたものであることがわかります。これらの経験は張郃の死を含め、血を流して得られたものであった。張郃の死により、司馬懿も後遺症に苦しんだ。蜀軍が撤退すると、司馬懿は追撃した。蜀軍は反撃の準備を整え、司馬懿は恐怖のあまり慌てて逃げ去った。 司馬懿の行動から、張郃を殺す必要がなかったことがわかります。しかし、張郃に軍を率いて諸葛亮を追わせたのは少々やりすぎだった。蜀軍追撃の経験を積むために、最高の将軍を派遣する必要はないからだ。普通の将軍を送ってください。ちょうど夷陵の戦いのとき、陸遜が情報を得るために劉備の陣営を攻撃するために軍隊を派遣したとき、彼は無名の将軍だけを派遣した。 したがって、司馬懿が張郃を派遣して諸葛亮を追撃させるという決断は、一石二鳥の策だった。彼は蜀軍追撃の経験を積み、自身の戦闘計画を改善しただけでなく、借りたナイフで人を殺し、敵の張郃を排除することもできた。もちろん、最初の目標は司馬懿の主な目標であり、2番目の目標である張郃の死は予期せぬサプライズでした。 結論: 張郃は曹魏の「五大将軍」の中で唯一生き残った人物の一人であり、諸葛亮との戦いで多大な貢献を果たし、諸葛亮にとっては大きな脅威とみなされていた。しかし、このような功績のある武将は、諸葛亮の第四次北伐の混乱の中で亡くなりました。彼は司馬懿に強制されて軍を率いて蜀軍を追撃したが、諸葛亮に待ち伏せされ、矢に射殺された。 張郃は曹真が辞任した後、関龍軍を引き継いだ将軍の中で最も人気があった。しかし、曹仁が張郃を任命した後、司馬懿が関龍軍を引き継いだ。二人の協力関係の中で、多くの対立があった。司馬懿は自身の作戦を試すために張郃に追撃を命じた。予想外にも張郃は死亡し、司馬懿は一石二鳥の作戦を立てることができた。その後、司馬懿は関龍軍の訓練に尽力し、この強力な軍隊を司馬家の基盤とした。 |
<<: 劉邦が軍陣に入るのは簡単だったのに、なぜ漢の文帝が秀里陣営に入るのを阻止されたのでしょうか?
>>: 長板坡の戦いで張飛が趙雲を追撃した本当の目的は何だったのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』で、丹春が賈家の管理を引き継いだ後、趙叔母さんはなぜ大騒ぎをしたのですか?
「家政婦タンチュン」の物語は主に『紅楼夢』第45章で展開されます。以下の記事はInteresting...
曹操には本当に配下に優れた将軍がいないのでしょうか?なぜ誰も当陽橋で張飛と戦う勇気がなかったのか?
三国志には、勇猛果敢な張飛が叫び声をあげて、当陽橋の前で曹操の百万の軍勢を追い払ったという、とても感...
グリーンピオニー完全ストーリー第59章:忠臣が隠者に敬意を表す
『青牡丹全話』は清代に書かれた長編の侠道小説で、『紅壁元』、『四王亭全話』、『龍潭宝羅奇書』、『青牡...
「パパイヤ山を眺めて」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
王木瓜山李白(唐)早起きして日の出を眺め、夕方には鳥が巣に戻る様子を眺めましょう。ゲストはパパイヤ山...
斉の桓公の最終的な運命は何だったのでしょうか?斉の桓公にとって管仲はどれほど重要だったのでしょうか?
斉の桓公の最終的な運命は何だったのでしょうか? 斉の桓公にとって管仲はどれほど重要だったのでしょうか...
古代史において科挙受験生が飛び越えた「龍門」はどこにあるか詳しく教えてください。
はじめに:学者が科挙で最高点を取ることができれば、鯉が龍門を飛び越えるようなもので、死すべき肉体を離...
孟子:高子第1章第8節原文、翻訳および注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...
呂植は後漢末期の貴族階級の代表的な人物です。劉備はなぜ彼に従って学んだのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『西江月:汝の人生を滅ぼす』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
西江月·人生を台無しにする黄庭堅(宋代)私はお酒をやめたので、宴会では私だけがシラフでいられるでしょ...
女媧が石を精錬して天を修復し、黄土で人間を作ったという物語
女媧に関する伝説は数多くあり、それらは今日まで広範囲な影響力を持って伝えられています。中国の歴史、神...
唐の太宗皇帝はなぜ均田制を改革したのでしょうか?国民に安定した生産と経済の発展を
唐の太宗皇帝は、人民の生産を安定させ、経済発展を促進するために、隋の時代を基礎として均田制度を改革し...
水滸伝で孟康はどのように死んだのですか?玉芳根夢崗の紹介
水滸伝の玉方干で孟康はどのように死んだのですか?孟康の最後はどうなりましたか?玉方干における孟康の紹...
姜逵の『定衛冬越し呉淞』はどのような感情を表現しているのでしょうか?
蒋奎の『定衛冬呉淞典江春』はどのような感情を表現しているのでしょうか。詩人は真の隠者になりたいと願っ...
西遊記第97章:雇われた警備員が悪魔に刺され、聖霊が現れて元通りの警備員を救う
『西遊記』は古代中国における神と魔を題材にした最初のロマンチックな章立ての小説で、『三国志演義』、『...
宋代の詩「定風博・晩春満星」を鑑賞します。この詩はどのような感情を表現しているのでしょうか。
丁鋒伯:晩春満行[宋代] 辛其記、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみま...