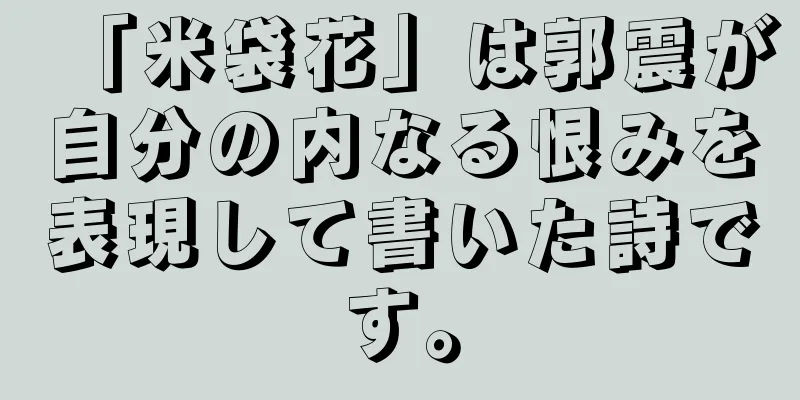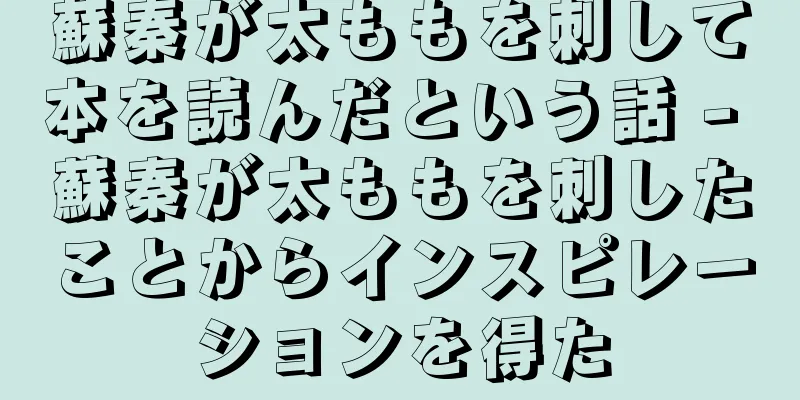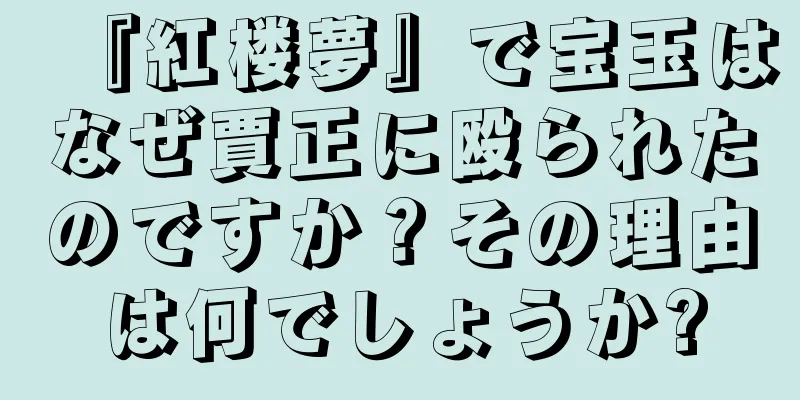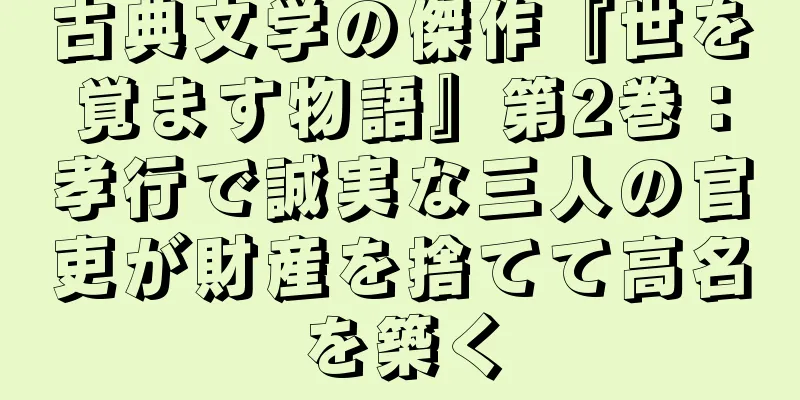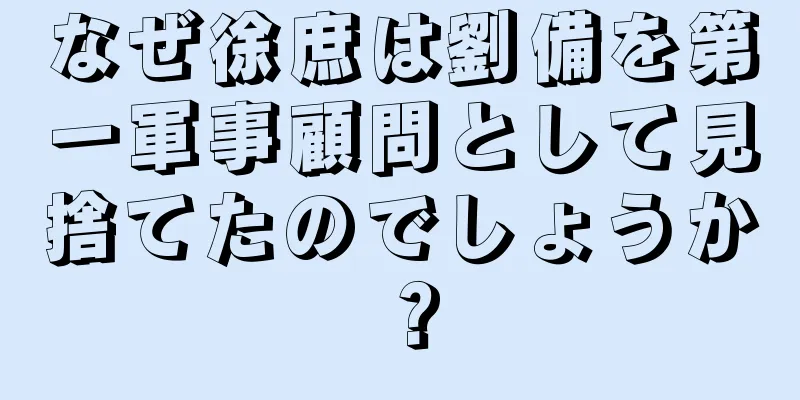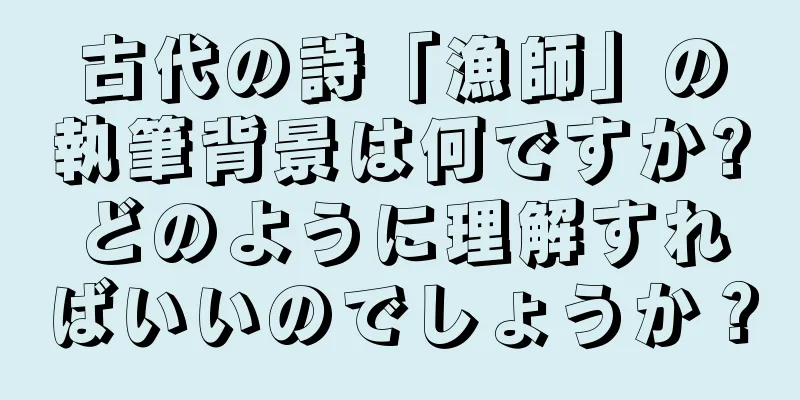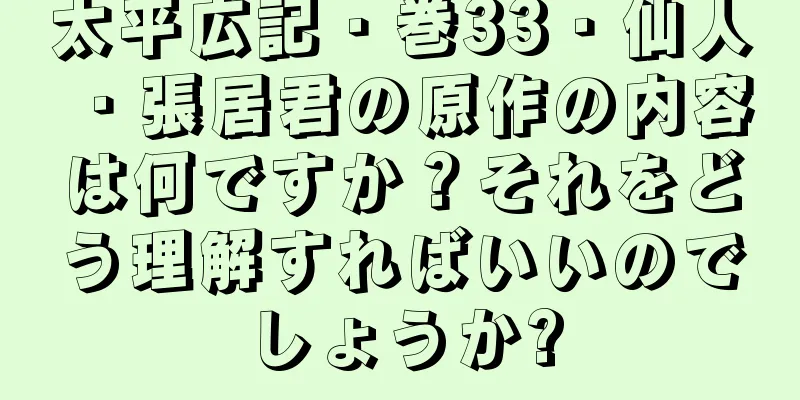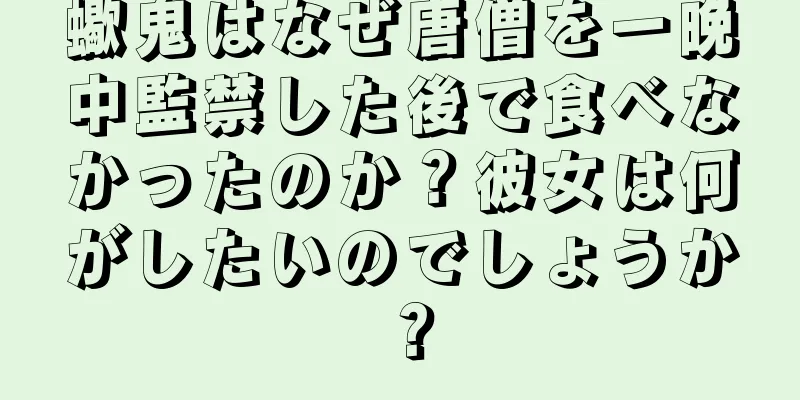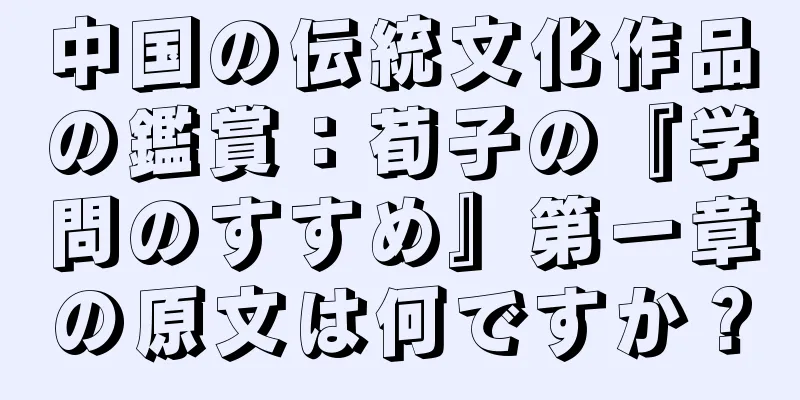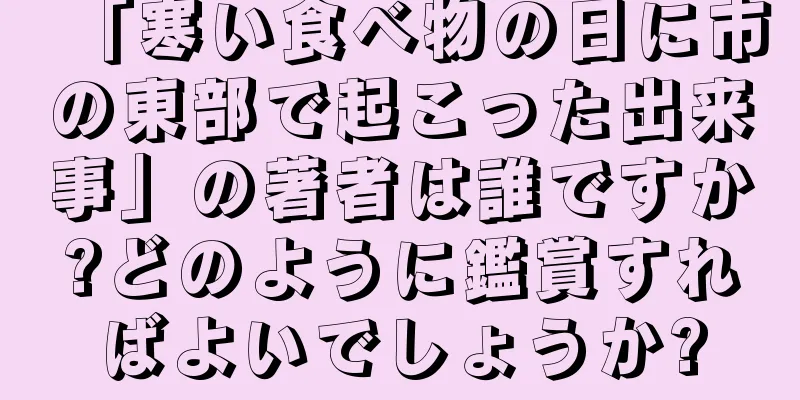古代史において科挙受験生が飛び越えた「龍門」はどこにあるか詳しく教えてください。
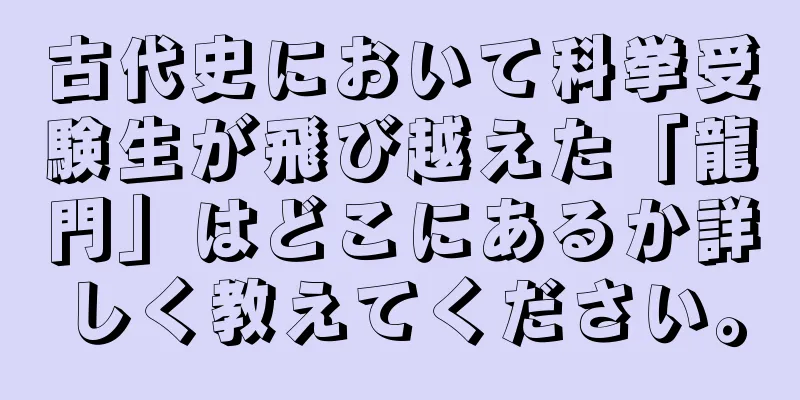
|
はじめに:学者が科挙で最高点を取ることができれば、鯉が龍門を飛び越えるようなもので、死すべき肉体を離れて高みに昇ることになる、とよく言われます。これはまさに、科挙に合格して官僚となり運命を変えた学生たちの鮮やかな比喩である。では、北京にはそのような「龍門」があるのでしょうか? 北京には城外都市と城内都市があり、建築レイアウト上、内外都市を結ぶ城門は極めて重要な施設となっています。北京には数多くの城門がありますが、その中には「龍門」と呼ばれる門があります。もちろん、これは封建時代の科挙制度と切り離せないものです。 隋の時代に確立された科挙制度は、それまでの世襲制度に取って代わりました。その結果、学生は試験を受けることで運命を変える機会を得ることができ、社会的才能を養成する比較的公平な機会となりました。これにより、封建王朝はかなりの期間安定を保つことができました。科挙は多くの段階に分かれており、各地で行われる試験を経て、選抜の段階を通過した合格者は首都で全国統一の試験を受ける機会が与えられます。都には、合科と宮中科の2つの試験があり、最終的に宮中科に進み、順位を獲得した者は官職に就き、国の柱となる切符を手に入れることができる。つまり、本来は普通の鯉だったものが「龍門」を越えて龍族に進出したということであり、「一歩で天国に到達した」ともいえるのです。 この象徴的な戴冠式を完結させたのは長安門でした。長安門は長安左門と長安右門に分かれており、明の永楽18年(1420年)に初めて建てられました。長安左門は大明門(清代に大慶門と改められ、辛亥革命後に中華門と改められ、1959年に取り壊された)の北東隅(現在の労働人民文化宮殿正門のやや東)に位置し、長安右門は大明門の北西隅(現在の中山公園正門のやや西)に位置していた。長安左門と長安右門は、皇城から中央官庁へ通じる正門です。門の前には「官吏、ここで下馬せよ」と刻まれた巨大な石碑があり、衛兵が警備に立っています。平日に朝廷に赴くすべての官吏は、長安の左門または右門から入らなければなりませんでした。官吏の身分や肩書に関係なく、馬や輿から降りて長安門まで歩き、天街(現在の天安門前の長安大道)を通り、金水橋を渡り、承天門(現在の天安門)に入り、その後武門から入って朝廷に赴き、皇帝に謁見しなければなりませんでした。 両方の門が「龍門」と呼ばれているわけではなく、長安の左側の門だけが「龍門」と呼ばれています。明代初期には、宮廷試験は承天門(現在の安門)の外の金水橋のほとりで行われ、後に太和殿に移されました。清朝もこの形式を継続したが、後に宮廷試験の会場は保河殿に変更された。宮廷試験の後、試験に合格した者全員の名前がホールに広く掲示され、その名前は「皇帝名簿」に記され、太鼓、音楽、皇帝の棒の音に導かれて正午の門から運び出され、広場の向こうの成天門を通って左側の「龍小屋」に掛けられました。宮廷試験に参加した貢学生は名簿を見るためにここに集まり、合格したかどうかに関係なく、長安左門から出国した。そのため、長安の左門は「龍門」または「勝門」と呼ばれ、科挙に合格した者は「登龍門」となった。新しく戴冠した第一学者は、赤い服と花を身に着け、皇帝から与えられた大きな馬に乗って、この門をくぐり「天街」(現在の長安街)に行き、「皇帝の恵み」を示しました。もちろん、これは「天街」で馬に乗ることが許された唯一の時でもありました。その後、名簿に載った合格者は順天府衙門(現在の安鼎門内街の西、東宮街に位置する)に招待され、祝賀宴が催される。この儀式は「合格者金宮発表」として知られている。 「龍門」を通過した学生たちは、長年の厳しい勉強の成果を遂に発揮し、世界中で有名な新たな高官となった。 長安左門の向かいにある長安右門は、司法省が国家の「秋裁判」と「朝裁判」を主宰した場所で、「虎門」と呼ばれています。毎年、旧暦の8月中旬になると、皇帝は司法省の役人を大理寺、検閲所、あるいは九大臣、王子、大臣らと協力させ、ここで「秋の裁判」を開き、共同で囚人を裁いた。当時、東から西にかけて、赤い絨毯で覆われた巨大な八仙卓が何十台も並べられていました。裁判官は北を向いて座り、各囚人の判決を審査しました。判決はその後皇帝に提出され、皇帝は赤ペンでチェックマークを付けるだけで、囚人に死刑が宣告されました。 「法廷審理」の最中、兵士が派遣され、法務省刑務所の死刑囚全員を連れ出し、長安右門まで護送し、整然とした列に並ばせ、長安右門南門から入り、「法廷審理」の机の前で一列にひざまずいて尋問を待った。この期間中、囚人は誰も不満を口にすることは許されなかった。その年の冬至の早朝、囚人たちは監獄車に乗せられて処刑場に連行され、斬首された。囚人は長安の右門から広場に連れ出され、まるで虎の口の中に入っていくような気分で泣き叫ばずにはいられなかった。そのため、長安の右門は「虎門」と呼ばれました。新中国の建国後、長安大街の交通問題を解決するために、1952年8月に長安の左右の門が取り壊されました。長安門はもう見られませんが、人々の運命を変えた「龍門」と「虎門」は、歴史に永遠に伝説を残しました。 |
<<: なぜオランダは風車の国と呼ばれるのでしょうか?風車の国はどこの国ですか?
>>: 崇禎帝朱有堅はどのようにして亡くなったのでしょうか?崇禎帝朱有堅の墓はどこにありますか?
推薦する
『紅楼夢』で趙おばさんはなぜ黛玉を嫌っていたのですか?理由は何でしょう
黛玉は『紅楼夢』のヒロインであり、『金陵十二美女』本編の最初の二人の登場人物の一人です。以下、興味歴...
チャン族の珍味の紹介 チャン族特産のクルミの花とは何ですか?
3月になると、山野一面に咲き誇る桃の花が羌族の村をピンク色の世界に包み、その後に咲くリンゴの花、梨の...
『紅楼夢』では、召使が主人をいじめるという現象が頻繁に登場します。林黛玉と賈丹春はそれをどのように解決したのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
中国の知恵物語:楚王が馬を埋葬する。この物語にはどのような哲学的啓蒙があるのでしょうか?
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日は楚王が馬を埋葬した話を...
辛其記の『西江月仙行』はどのような背景で作られたのでしょうか?どのように鑑賞しますか?
辛其記の『西江越仙行』、興味のある読者はInteresting Historyの編集者をフォローして...
李龍基の政権初期における彼の2つの利点のうち、どれが開元の繁栄を達成する能力と関係がありましたか?
「開元の繁栄した時代を思い起こすと、小さな町にも数万世帯が住んでいた。米は豊かで、粟は白く、公蔵と私...
『晋書』巻第十八第八章の原文は何ですか?
◎法律と暦Yang Wei, the official in charge of the imper...
シャオ・フアンの父親は誰?シャオ・フアンの父親シャオ・トンの人生について簡単に紹介
孟孫は蘭陵南の中都村の出身であった。梁の武帝蕭延の孫で、昭明王蕭同の長男。母は蔡で、薛によって「昭徳...
『紅楼夢』で包爾佳はどうやって死んだのですか?この事件と賈家とのつながりは何でしょうか?
鮑二佳は『紅楼夢』の登場人物の一人です。 今日は、Interesting Historyの編集者が皆...
呂兆霖の「曲池の蓮」:この詩は物を通して彼の考えを表現しており、感情は誠実で自然である。
呂兆林(?-?)、雅号は盛之、号は有有子、渝州樊陽(現在の河北省涛州市)の人であり、唐代の詩人である...
朱棣の明長霊の特徴は何ですか?なぜこんなによく保存されているのでしょうか?
周知のように、明長陵は明朝の3代皇帝である成祖文殊(在位:永楽帝)とその王妃徐嫡の共同墓地です。では...
王維の詩「玉山寺歌」の本来の意味を理解する
古代詩「玉山の女神の神殿の歌」時代: 唐代著者 王維【一つは玉山の女神、智瓊祠についての二つの詩】 ...
『西遊記』で、なぜ真元子は如来を恐れず、観音に頭を下げるのでしょうか?
周知のように、『西遊記』の真元子はずっと傲慢な人物ですが、なぜ真元子は如来を恐れず、観音に頭を下げる...
賈宝玉は、シキが連れ去られるのを見て、なぜ何も言わなかったのですか?
みなさんこんにちは。賈宝玉さんといえば、みなさんも聞いたことがあると思います。王夫人が周睿の妻に大観...
明代末期から清代初期の思想家、顧延武:「天下諸県及国家得失書」の内容と貢献についての簡単な紹介
『諸国勝敗記』は、明代中国各地の社会、政治、経済状況を記録した歴史地理書で、全120巻あります。明代...