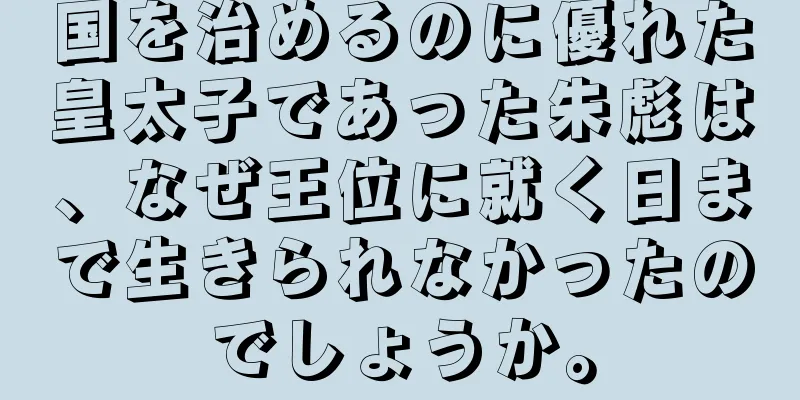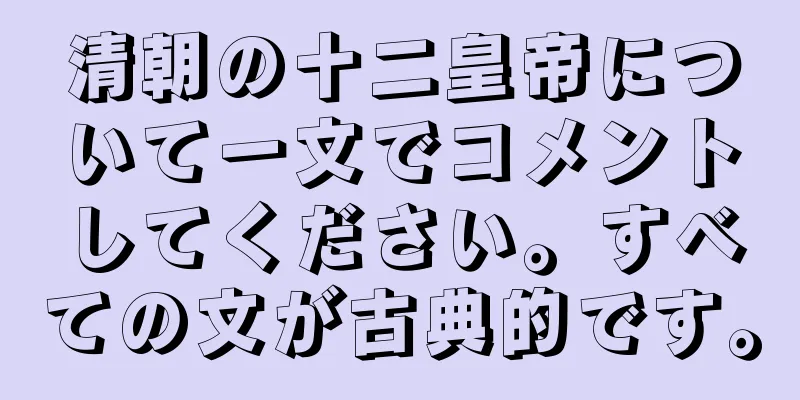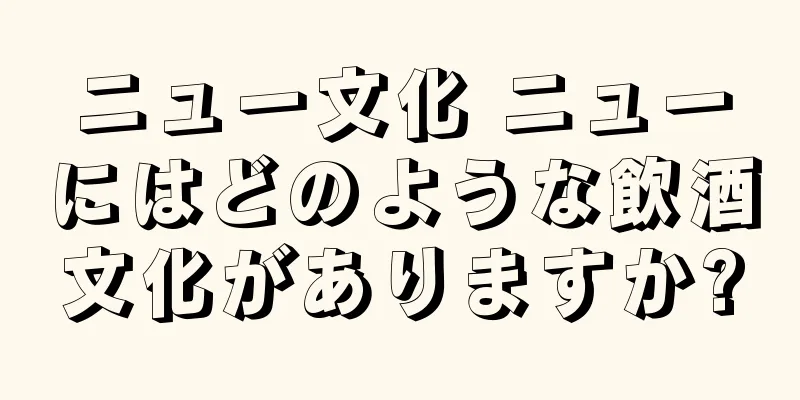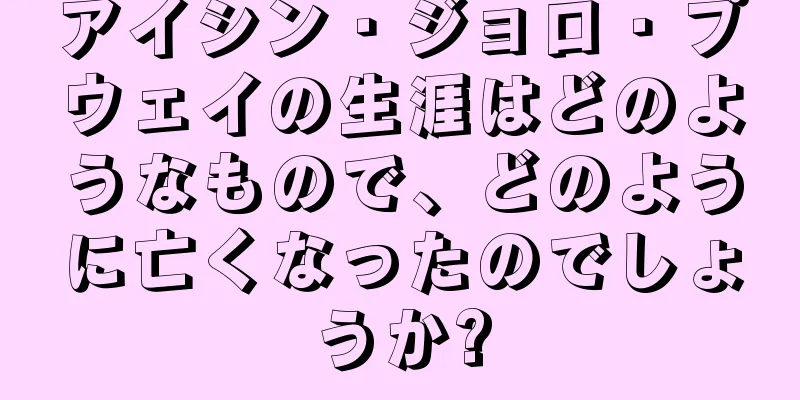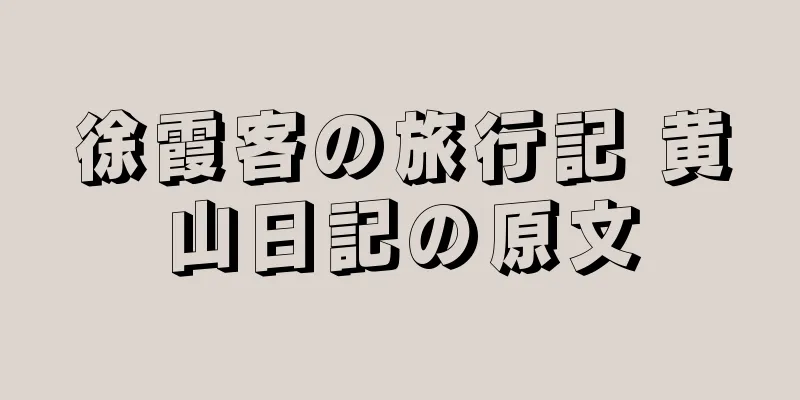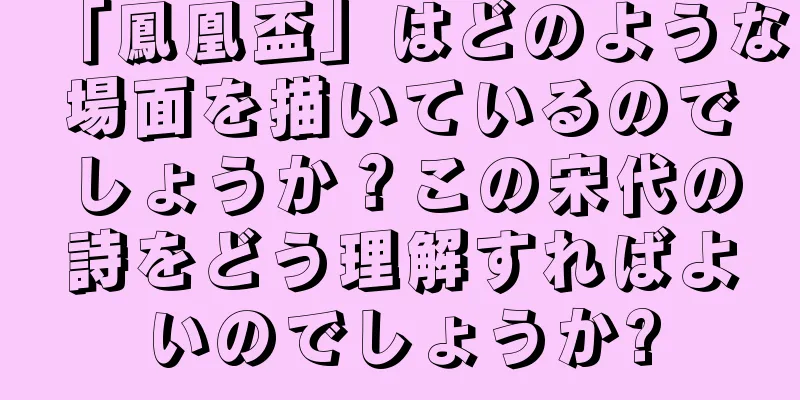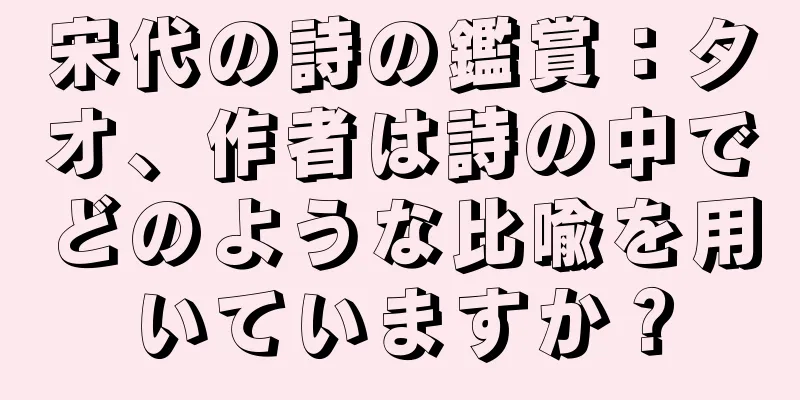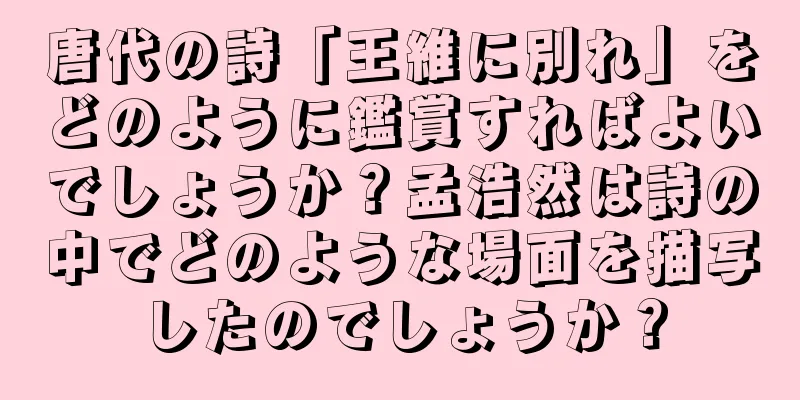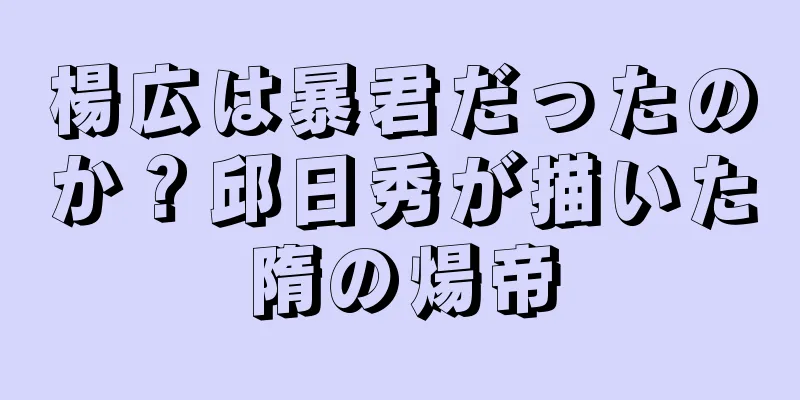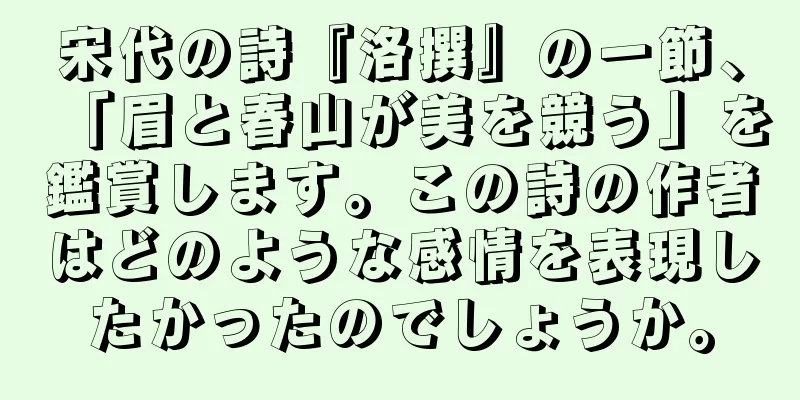蜀漢末期、魏延の他に蜀軍で張郃の敵となり得る人物は誰でしょうか?
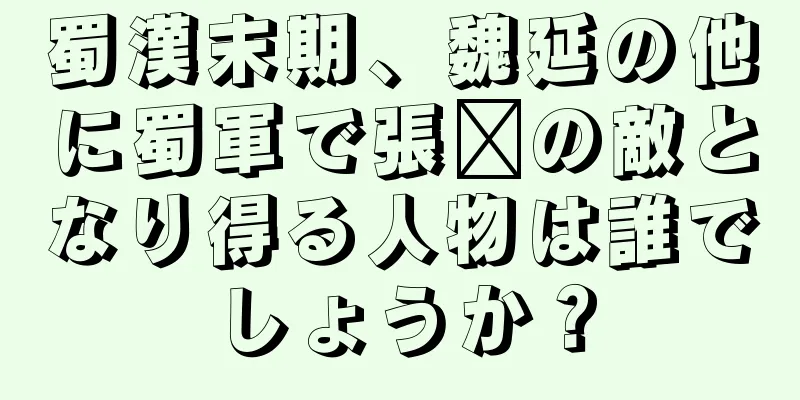
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が諸葛亮の時代、張郃が曹魏の最強の将軍だったこと、そして蜀漢で魏延以外に誰が彼の敵だったかについての詳細な紹介をお届けします。見てみましょう! 三国時代、劉備陣営はもともと「龍中作戦」の戦略に従って北伐のための二つの主力軍を準備していました。しかし、荊州の戦いと夷陵の戦いでの敗北により、この2つの主力はほぼ完全に失われました。諸葛亮の治世中に新しい軍隊が再編成されたが、訓練だけでは経験豊富な将軍を獲得することはできない。そのため、漢中を守っていた魏延は、この軍で最高の将軍となった。彼は諸葛亮の軍に転属し、前線の指揮官を務め、蜀軍の先鋒となった。 諸葛亮の北伐の際、曹操軍の中で彼が直面した最も手強い敵は張郃でした。張郃は三国時代初期にはあまり目立った人物ではなかったが、五大将軍の中で唯一生き残った人物として、蜀軍の北伐の最大の障害となった。街亭の戦いで馬謖を破ったのは彼の素早い勝利であり、諸葛亮の最も近かった北伐は失敗に終わった。こうして、魏延と張郃は関龍地域における蜀と魏の最強の敵となった。それで、彼らの実力はどう比較されるのでしょうか? 魏延の他に、蜀軍で張郃の敵になり得るのは誰でしょうか? 1.『三国志演義』の魏延と張郃。 三国志演義では、魏延は張郃と2度だけ戦った。これは、魏延が蜀軍の数少ない名将の一人であり、諸葛亮が彼を使うことに非常に慎重で、簡単に危険を冒させなかったためです。魏延は蜀軍の先鋒として知られていましたが、彼の任務のほとんどは敗北を装い、敵を誘い出すことであったことがわかります。このような任務は魏延にとって何の問題もなく、魏延の安全は最大限に保証された。 魏延と張郃が初めて戦ったのは街亭の戦いであった。この戦いで、諸葛亮は馬謖を街亭の守備に派遣したが、魏延を街亭の背後に配して援護任務に就かせた。諸葛亮は魏延を派遣する前にすでに高翔を連柳城の守備に派遣していたが、高翔は張郃に敵わないと考え、魏延も派遣した。諸葛亮の意見から、諸葛亮は魏延が張郃に抵抗し、張郃のライバルになれると信じていたことがわかります。 街亭の戦いでは、両者は数回にわたって戦闘を行った。この戦いで魏延と張郃の最初の戦いが起こった。この戦いで、馬謖は南山を占領していたため、魏軍に敗れた。魏延は援軍に駆けつけ、敗れた馬謖の軍を逃がし、追撃してきた張郃と戦った。しかし、この戦いの間、張郃は魏延と戦うことはなく、引き返して立ち去った。 その後、魏軍は追撃してきた魏延を包囲したが、張郃は兵をおびき寄せる戦略をとり、王平の援護により魏延は包囲を突破することができた。この戦いで、魏延らは再び街亭を攻撃したが、それでも事態は収拾できず、ついには楊平関まで撤退した。 魏延と張郃が二度目に戦ったのは木門路の戦いであった。この戦いで諸葛亮は軍を率いて撤退し、張郃に追われた。諸葛亮は巧みに軍隊を配置し、張郃を待ち伏せした。この戦いでは、魏延と関平が交互に張郃と戦い、十数ラウンド戦った後、両者とも退却し、張郃を一歩ずつ木門の入り口へと導いた。 木門関で、魏延は再び張郃と戦った。今回、魏延は十数ラウンド戦った後、敗北して逃走した。魏延は逃げるために衣服、鎧、兜を捨て、敗れた兵士たちを率いて木門の中に入った。張郃は木門路に追い詰められたが、木と石で待ち伏せした諸葛亮の軍勢に阻まれた。この時点で張郃は罠にかかったことに気づいたが、時すでに遅し。木門で諸葛亮の待ち伏せ部隊に射殺された。 魏延と張郃の戦いから判断すると、張郃は常に自分が魏延よりも強いと考えていた。張郃が街亭の戦いで恥じることなく撤退したのはこのためである。木門路の戦いでは魏延を執拗に追撃した。魏延が負けたふりをしたとき、張郃はまったく疑わなかった。張郃が魏延の能力を正しく判断していたなら、魏延の過度に不自然な行動に疑念を抱いたはずだ。わずか十数ラウンドで敗北し、鎧と兜を捨てて逃げ去る魏延の行動に彼は疑念を抱くだろう。こうすれば、張郃は木門路で死ぬことはなかっただろう。 このことから、蜀軍の中で張郃に正面から対抗できる将軍は魏延であったことがわかります。諸葛亮は張郃の魏延に対する軽蔑を利用して、張郃を騙す任務を魏延に託した。実際、諸葛亮も心の中では、魏延の能力があれば、たとえ張郃を倒せなくても、張郃に負けることはないだろうとわかっていた。魏延も張郃の能力を知っていたので、喜んで諸葛亮の任務を引き受けた。 したがって、張郃と魏延の二度の遭遇から判断すると、張郃と魏延のレベルは基本的に同じです。しかし、両者のレベルに対する認識には違いがある。張郃は自分が魏延より強いと考えていたが、魏延はそうは思わなかった。 2. 三国志演義の張郃と王平。 では、蜀軍には魏延の他に張郃に抵抗できる将軍はいるのでしょうか? 『三国志演義』の記述によると、蜀軍の一人の将軍が張郃と二度戦い、二度とも負けなかった。その将軍とは王平である。 王平と張郃の最初の戦いも街亭の戦いで起こった。街亭の戦いの間、馬蘇は王平の忠告を無視し、南山に陣取ることを主張した。王平は仕方なく、一団を率いて自ら山のふもとに陣取り、挟撃作戦を立案した。しかし、魏軍の強大な力により、王平は軍を率いて救出に向かったものの、魏軍の包囲を突破することはできず、馬蘇が敗北するのをただ見ているしかなかった。 その後、魏延が張郃に騙されて魏軍に包囲されたとき、王平は軍を率いて両側から魏軍を攻撃し、魏延を救出した。街亭の夜襲の際、魏延と高翔が再び包囲されたとき、彼らを救ったのは王平だった。そのため、王平と張郃の最初の戦いでは、王平が知恵と勇気で優位に立った。 諸葛亮が武都隠平を占領した後に、王平と張郃の二度目の戦闘が起こった。当時、諸葛亮は司馬懿と戦っており、司馬懿の死ぬまで自分の立場を守る戦略に直面していました。司馬懿を戦いに誘い込むために、諸葛亮は毎日30マイルずつ後退するという段階的な撤退戦術を採用した。部下からの圧力により、司馬懿は軍隊を派遣するしかなかった。諸葛亮の待ち伏せを防ぐため、彼は部隊を二つのグループに分けた。一方のグループは張郃が先頭に立ち、もう一方のグループは張郃自身が後方を率いた。 諸葛亮はこの状況を利用し、張郃と司馬懿の間に待ち伏せ部隊を送り、双方からの攻撃に耐えた。その後、諸葛亮は司馬懿の計画を妨害するために司馬懿の陣営を攻撃し、司馬懿が陣営を救出するために軍を撤退させたときに司馬懿を打ち破った。しかし、この戦いに勝つためには条件があり、それは司馬懿の軍に投入された蜀軍が張郃と司馬懿の挟撃に耐えなければならないということである。 当時、諸葛亮は魏延をこの軍の指揮官に任命したかったが、魏延は彼を無視した。諸葛亮が困惑していたとき、王平は自ら進んで助けを求め、諸葛亮の切実な問題を解決した。しかし、諸葛亮は王平が張郃に匹敵するとは思わず、張毅を王平の補佐官として派遣し、二人でこの任務を遂行した。 戦闘中、王平と張儀は張郃と司馬懿の攻撃に耐えた。その中で、王平は張郃や戴凌と戦い、張毅は司馬懿と戦いました。彼らは張郃と司馬懿を抑え、仲間たちにチャンスを与えた。この戦いでは、終盤で状況が危機的であったにもかかわらず、王平は張郃の攻撃に耐えることに成功した。 もしこの戦いが諸葛亮の計画通りに行われていたなら、張郃と司馬懿の共同攻撃に抵抗したのは魏延であったはずだ。しかし、魏延はその任務を引き受けることに同意しなかった。このため、諸葛亮の計画は当面実行が困難となった。王平の志願のおかげで、諸葛亮の計画は成功した。この観点から見ると、王平は魏延ほど有能ではないものの、蜀軍の中で張郃と正面から戦う勇気のある将軍です。 3. 歴史上の魏延、王平、張郃。 上で見たのは三国志演義の記録です。三国志演義は歴史小説なので、当然現実とは多少のギャップがあります。しかし、歴史小説なので、本の内容を現実と比較する必要があります。歴史上、この3人の間の交流の記録が残っています。 魏延と張郃は互角の武将であったが、歴史上彼らが戦った記録はない。これは主に諸葛亮が魏延を高く評価しており、簡単に失いたくないと思ったためである。そのため、魏延はほとんどの時間、諸葛亮の直接指揮下にあり、張郃と単独で戦うどころか、魏軍と戦う機会もありませんでした。 魏延が張郃に遭遇したのは、西の羌中へ向かったときだけだった。その戦いで、魏延は諸葛亮によって羌中に派遣され、兵士を募集して軍の力を拡大した。この戦いでは、魏延と呉毅が漢中から軍を率いて出撃した。彼は機転が利き、柔軟で、魏軍の奥深くを行き来した。魏延の敵である張郃、郭淮らは彼の意図を理解できず、自らの立場を守らざるを得なかった。 魏延が羌の領土に入ったとき、張郃らは彼の真意に気づいたが、時すでに遅く、追いつくことはできなかった。この散発的な作戦で、魏延は軍事力で張郃、郭淮らを打ち破ったと言える。魏延が軍を率いて撤退したとき、郭淮に阻まれた。 魏延の指揮の下、蜀軍は郭淮らを打ち破り、有名な楊西の勝利を収めた。この戦いでの功績により、魏延は西伐将軍に昇進し、臨時の権限と南鄭侯の称号を与えられました。こうして魏延は諸葛亮の下で最高の将軍としての地位を確立し、張郃に劣らない軍事的才能も発揮した。 歴史上、王平と張郃は何度も戦った。一度目は街亭の戦いでした。この戦いで、王平は将軍として何度も馬蘇に助言を与えましたが、馬蘇は聞く耳を持ちませんでした。その結果、馬蘇の部隊は全員敗北したが、残ったのは王平率いる千人以上の部隊だけだった。王平は軍勢を再編成し、太鼓を鳴らして防御したため、張郃は待ち伏せを疑い、前進することをためらった。王平は散り散りになった軍隊を集めて撤退することができた。 街亭の戦いでは、主力が大敗したにもかかわらず、王平は冷静さを保ち、勝利した張郃を追い払うことができた。この軍事的功績により、諸葛亮は王平を将軍に昇進させ、賊を鎮圧するとともに馬蘇を処刑し、敗れた将軍を罰した。その後、諸葛亮は蜀軍の中でも最も精鋭の武当飛軍も王平に指揮させました。 王平と張郃が二度目に戦ったのは鹿城の戦いであった。この戦いで諸葛亮は機動戦術を採用し、司馬懿の軍隊を動員して野戦で敵を殲滅しようとした。司馬懿は戦う気はなかったが、部下の圧力により軍隊を率いて諸葛亮の陣営を攻撃しなければならなかった。司馬懿は自ら魏軍を率いて諸葛亮の陣地を攻撃し、張郃に蜀軍陣地の背後にある南衛を攻撃させた。南衛を守っていたのは武当守護の王平であった。 この戦いで、司馬懿の軍隊は、魏延、高襄、呉班が率いる蜀軍に敗れた。張郃は王平の陣営を攻撃したが、王平の頑強な抵抗に遭遇した。王平は持ちこたえ、張郃は城を占領することができなかった。司馬懿の敗北を知ると、張郃は軍を撤退させるしかなかった。 歴史の記録を見ると、基本的には『三国志演義』と同じ結論に達することができます。つまり、魏延は張郃と同じくらい賢く、勇敢なのです。王平は魏延より若干劣っていたものの、実際の戦闘では張郃の攻撃に耐えることができた。張郃を攻撃で倒すことができたのは、魏延だけだった。 結論: 張郃は長生きしたため、歴戦の将軍たちが次々と亡くなった後、曹魏軍で最強の将軍となった。彼は街亭の戦い以来、関龍地方で戦い続け、諸葛亮の北伐の強敵となった。諸葛亮の軍隊では、敵となるのは魏延だけであり、彼以外には王平しか残っていなかった。 王平は教育水準が低く、読み書きもあまりできなかったが、軍人出身で、豊富な戦闘経験を持っていた。この尊敬の念により、諸葛亮は彼が組織した軍隊の他の将軍たちよりも際立った存在となった。張郃との二度の戦いでは、王平が優勢だった。しかし、王平はどちらの試合でも守備的な姿勢を取った。この観点から見ると、王平の軍事レベルはまだ張郃よりも低いです。 諸葛亮の死後、魏延は軍事力を競い、楊儀と衝突した。王平が前に出て魏延を倒した。その後、王平は再び漢中を占領した。興市の戦いでは、王平は曹爽の10万以上の軍を破り、蜀漢の北門の安全を守った。王平は魏延に次ぐ蜀漢の最も優れた将軍であり、張郃のライバルとも言える人物であった。 |
<<: なぜ龐徳と徐晃は関羽を恐れなかったのでしょうか?私は関羽と競争しなければならない
>>: 蜀漢の滅亡後、なぜ蜀の反乱は鍾会のせいで起こったと言われるのでしょうか?
推薦する
白族の伝統的な祭り「ラオサンリン」の歴史は何ですか?
饒三霊は大理の白族の伝統的な祭りです。白族の人々が閑散期に自分たちの娯楽として神々を迎える祭りで、千...
張九玲の「湖口から廬山の滝を眺める」:この詩の芸術は独特で成功している
張九齢(673-740)は、雅号は子首、通称は伯武で、韶州曲江(現在の広東省韶関市)の出身である。唐...
『清代名人故事』第13巻原文の「学問と行状」の項には何が記されているか?
◎朱高安の学問と行い朱高安は幼い頃から勉強が好きで、全力を尽くす決意をしていました。一度、家庭教師が...
「西江月・心秋行」鑑賞、詩人劉晨翁は冷静な愛国者
劉晨翁(1232-1297)、雅号は慧夢、号は許熙としても知られる。彼はまた、徐喜居士、徐喜農、小娜...
「集門を見る」は祖勇の唯一の七字詩であり、自然の風景と国境の戦争を融合させた詩である。
祖勇(本名は和勝)は洛陽出身で、「詩仏」王維の良き友人であった。彼の詩は主に、贈り物と返答、旅行、風...
長楽宮の建築レイアウトはどのようなものですか?前漢時代の長楽宮は誰の住居でしたか?
長楽宮は、秦の皇宮である興楽宮を基礎として再建された、西漢時代の最初の正式な宮殿です。西漢の長安城の...
太平広記・第44巻・神仙・家屋建築をどう理解するか?具体的な内容はどのようなものですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
李白の『清平貂・第一』:この詩は、何の不自然さもなく、楽々と書かれている。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
呉敬子はなぜ『士大夫記』の中で范進が科挙に合格する物語を書いたのでしょうか?
「范錦が科挙に合格する」という話は、清代の小説家呉敬子の『士大夫記』に由来する。この一見単純な物語は...
「小五英雄」第34章:衛昌の宿で義人江平に会う、古寺で龍涛に会う
『五人の勇士』は、古典小説『三人の勇士と五人の勇士』の続編の一つです。正式名称は『忠勇五人の勇士の物...
清代の健康書『仙清皇記』:器官編の第一部は全文
清代の李毓が著した『悠々自適』は養生に関する古典的著作である。 「歌詞と音楽」「運動」「声と容姿」「...
南宋の滅亡は軍事力の弱さが原因だったのか?しかし、実際には多くの理由があります
南宋の滅亡は軍事力の弱さが原因だと多くの人が信じているが、実際には南宋の滅亡はさまざまな要因が重なっ...
元朝の省は、その傘下の県、郡、地区に対してどのような行政統制と従属を実施できたのでしょうか?
元代には、各地の地代や税金の徴収は主に県級の政府によって行われ、県は県から税金を徴収し、県は郡から税...
『紅楼夢』の実際の邢夫人はどんな人ですか?彼女はどれくらい賢いですか?
『紅楼夢』の登場人物、邢夫人。賈舍の2番目の妻。本日は、Interesting History編集長...
明代史第181巻第69伝の原文
徐普、秋俊、劉建、謝謙、李東陽、王澳、劉忠徐普は、雅号を世勇といい、宜興の出身であった。瓊州の知事で...