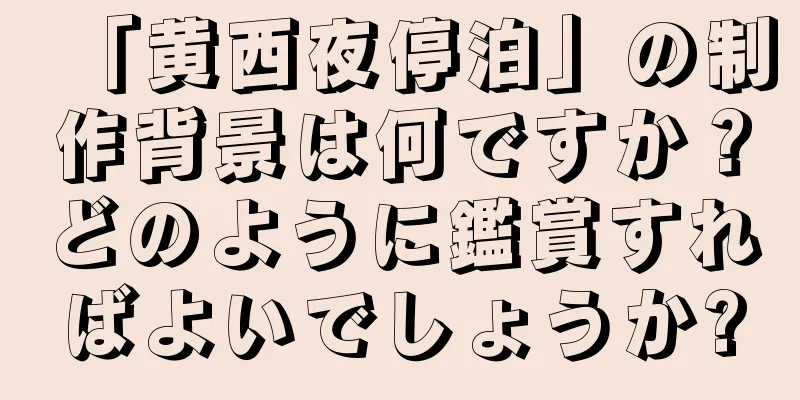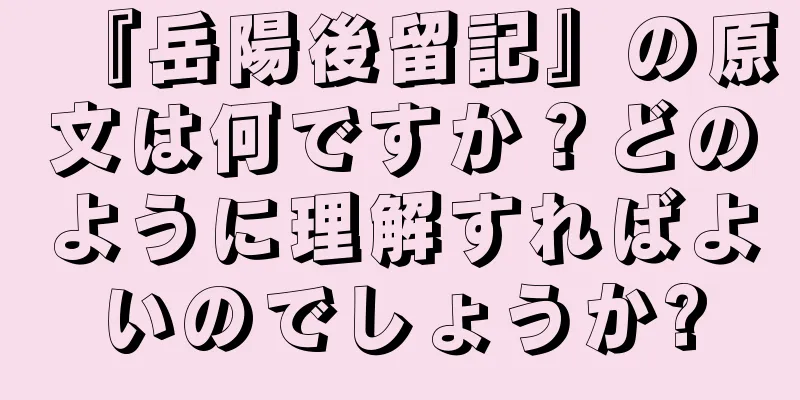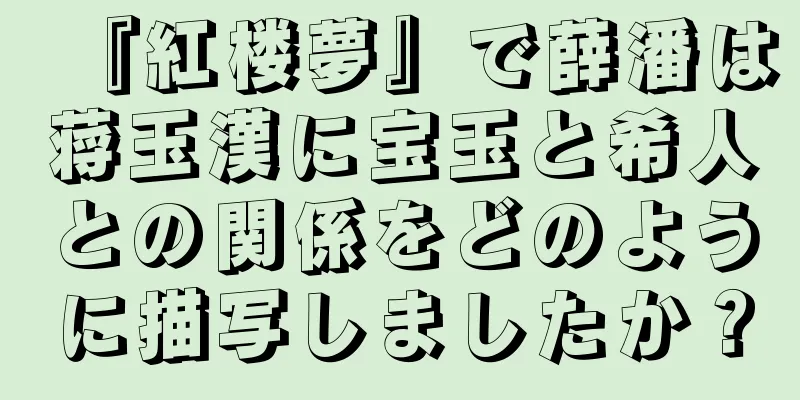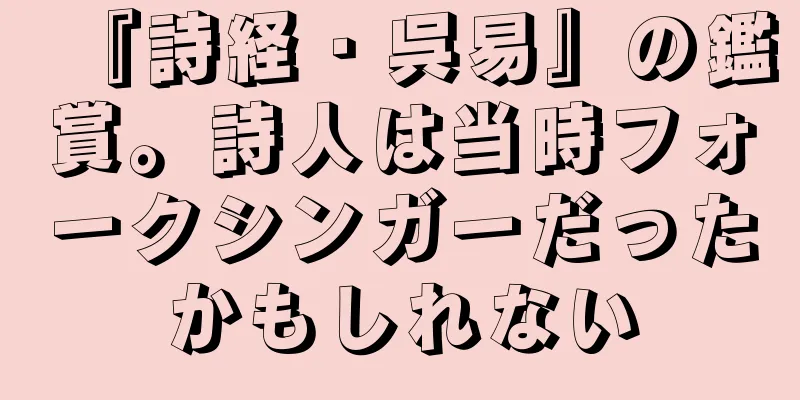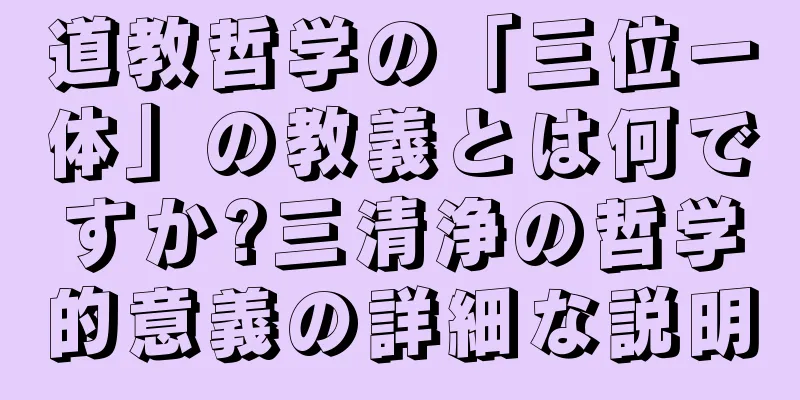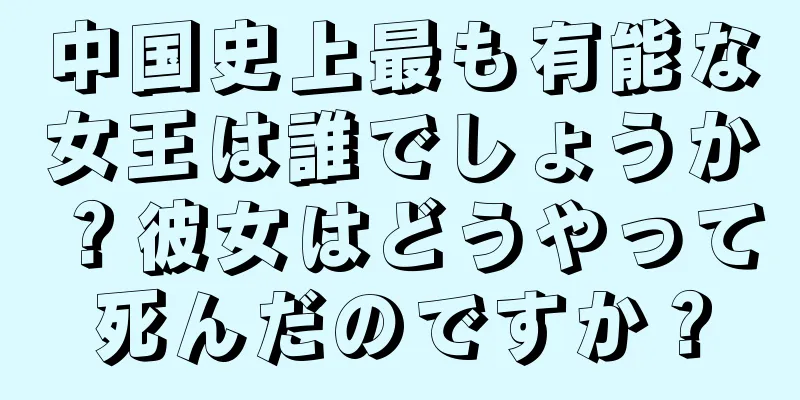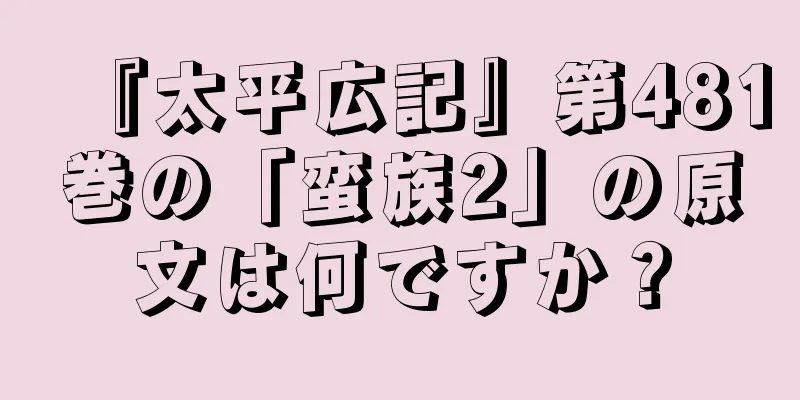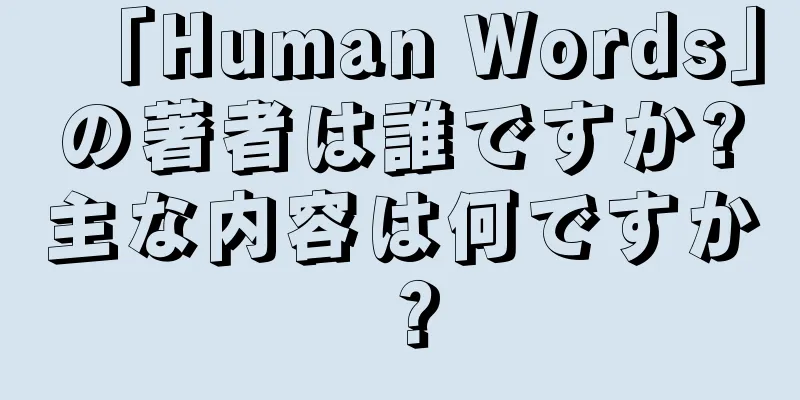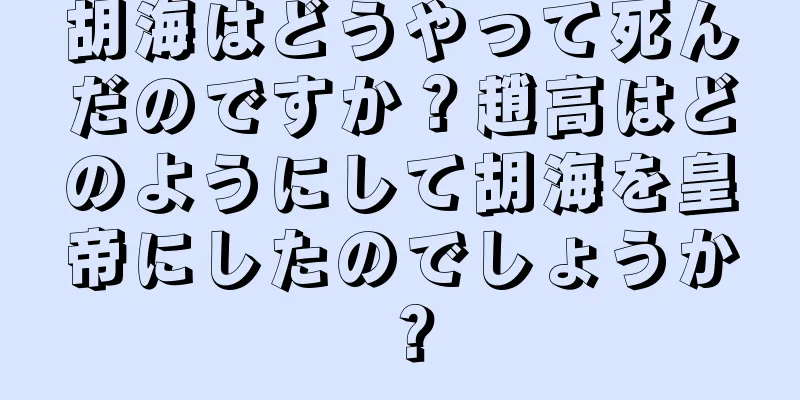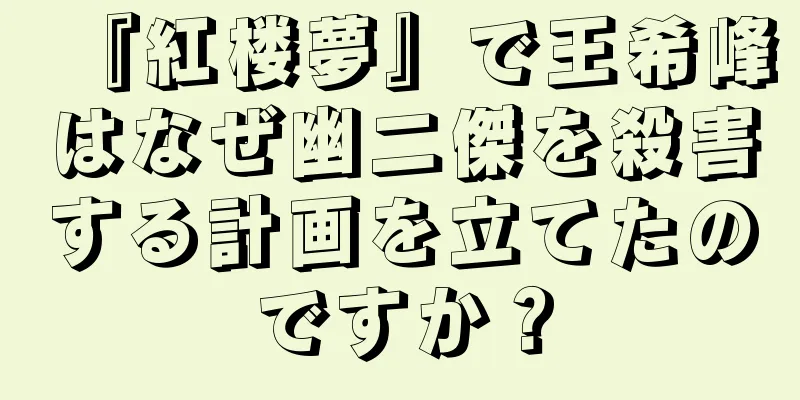漢中の戦いの後、張飛が戦闘に参加したという記録がないのはなぜですか?
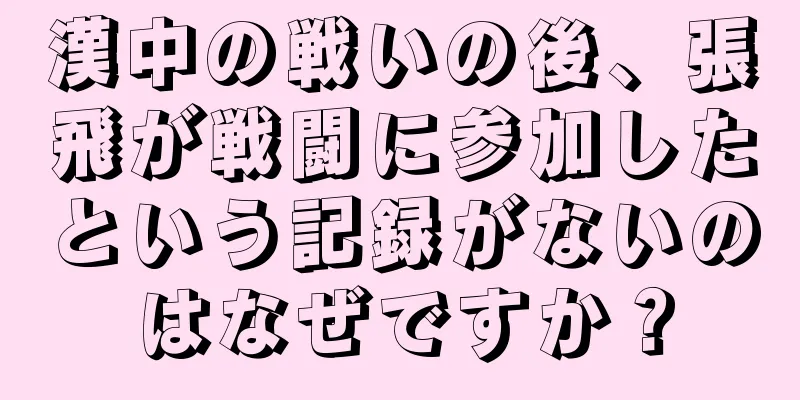
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、劉備が西の益州と北の漢中を占領した後、張飛が殺されるまで閩中に「放置」していた理由について詳しく紹介します。見てみましょう。 歴史の記録から判断すると、張飛は建安22年(217年)の漢中の戦いに参加した後、章武元年(221年)の夷陵の戦いの前に部下の張大と樊強に殺されるまで、漢中の戦いに参加したという記録はありません。彼は確かに「怠惰」だったように見えますが、実際にはそうではありませんでした。さまざまな兆候は、張飛が再び軍隊を率いて戦いに出場しなかったにもかかわらず、彼が依然として劉備の右腕であったことを示しています。 1.蜀漢の軍事構成では、張飛が単独で軍を率い、高い地位にあった。 文学作品や映画、テレビ作品に出てくる数十万の軍隊に比べると、実際の歴史ははるかに「貧弱」です。蜀漢の軍事力は最初から最後まで大きくなく、特に漢中を占領する前後はそうでした。その直属軍は実際には10万人程度に過ぎませんでした。当時占領されていた荊州、益州、漢中に比べると、この兵力は本当に十分ではありませんでした。 当時、劉備の軍は主に4つの部分から構成されていました。1つは荊州軍団で、約3万人の兵力でした。2つ目は劉備と張飛がそれぞれ率いる劉備直下の2万人の軍団でした。3つ目は趙雲が貴陽を占領した後に再編された2万人の軍団でした。4つ目は荊州南部の4つの県を占領した後に募集された2万人の軍団で、それぞれ黄忠と魏延が率いていました。益州から降伏した5万人の軍隊については、劉備は短期的には使用しようとはしなかった。 関羽は西の巴蜀と北の漢中を占領した後、軍を率いて荊州に駐屯し、魏延と黄忠の率いる2万の軍は漢中の守備を担当した。易州の降伏軍5万は各所に分かれて駐屯した。その結果、益州守備軍全体は実際にはわずか4万人にまで減少し、そのうち1万人は劉備が直接指揮し、趙雲の2万人の軍は成都の各所の守備を担当し、残りは張飛が1万人の軍を率いて閩中に守備した。 前述のように、益州、漢中を次々と占領した後、蜀漢グループは急速に勢力を伸ばしたが、基盤が弱かったため、劉備自身の軍隊の数は多くなく、劉備が単独で軍を率いることができると信頼できる将軍は数人しかいなかった。張飛は一人で1万人の軍隊を率いることができ、その地位はすでに高かった。 2. 張飛がいた閔中の戦略的な位置は、実は蜀漢の要衝だった。 建安24年(219年)、劉備は漢中を占領するとすぐに漢中王を名乗った。当時、蜀漢は漢中守備のために将軍を残す必要があった。大抵の人は張飛が漢中の太守になると信じていた。しかし、劉備は魏延を昇進させ、張飛を引き続き閩中に留まらせることにした。この取り決めの理由は、張飛が評価されなかったからではなく、まさに閔中があまりにも重要だったからである。 張飛が駐屯していた閘中は、前線にある漢中や荊州に比べると重要性が低いように思われた。しかし、実はそうではなかった。閘中は蜀漢にとっても重要な場所だったと言える。まず、閘中は成都から遠くなく、漢中と三県が成都に進軍する主要交通路に位置しているため、成都外の最後の防衛線とも言えます。重要性で言えば、閘中は江閣よりも上です。 第二に、閘中は交通の要衝にあり、益州が兵を派遣する辺境の地である。閘中から北は漢中へ直行でき、東に川を下れば江州へ直行できる。漢中や荊州でどちらが勃発しても、戦が緊迫すれば閘中軍はすぐに援軍に向かえる。 最後に、閔中は益州の地方貴族を威嚇する役割も担っていた。当時、蜀漢には荊州、東州、益州の3つの勢力があり、劉備の戦略は荊州を基盤として東州と結束し益州を制圧することだった。そのため、益州の地方貴族を威嚇することは重要な任務だった。魏延も孟達もこの任務を遂行できず、関羽も手の届かないところにあった。益州に駐屯し、劉備の深い信頼を得ていた張飛だけがこの任務を遂行することができた。 3. 蜀漢の状況の発展と張飛が軍を率いて戦争に向かわなかったのは張飛自身のせいではない 蜀漢は益州と漢中を次々と占領した後、特に「漢中の戦い」で急速に勢力を拡大しました。劉備は曹操から漢中を奪取することに成功しましたが、資金力の乏しい劉備にとって内部の状況は極めて厳しいものでした。そのため、蜀漢はこれまでの業績を早急に回復し、強化する必要がありました。 そのため、蜀漢は漢中の戦いの後、実際にはもはや率先して攻撃することができず、戦略的な防御に重点を置くべきであった。魏延は漢中の防衛に力を入れ、この点では優れた働きをした。そのため、曹魏はその後何度も漢中を攻撃したが、一度も成功しなかった。 しかし予想外だったのは、「漢中の戦い」の終結直後に、関羽が荊州で「襄樊の戦い」を開始したことだ。実は、荊州は戦略上重要な位置にあったため、荊州をめぐって魏、蜀、呉の間で小摩擦が頻繁に発生していた。そのため、蜀漢は戦争の初期段階ではそれにあまり注意を払わなかった。また、戦争の初期段階では関羽が常に優勢であったため、蜀漢は張飛を派遣して彼を支援させた。その結果、東呉が関羽の背後を奇襲したため、戦場の状況は急激に悪化し、関羽は最終的に敗れて殺害され、荊州は東呉の手に落ちました。 荊州の陥落と関羽の死は蜀漢に大きな損害を与えたが、「漢中の戦い」を終えたばかりの蜀漢は軍隊を送ることができなかった。劉備が「関羽の復讐」の名の下に蘇州に軍隊を送ったのは、章武元年(221年)7月になってからだった。張飛は鄧中から江州に軍隊を送るよう命じられたが、軍隊が出発する前に亡くなった。 まとめると、張飛が閩中に長期駐留していたのは、実は「怠惰」だったわけではなく、劉備の信頼を反映していた。「漢中の戦い」後、張飛が軍を率いて戦争に向かわなかったのは、蜀漢の情勢の発展によるもので、張飛の個人的な理由によるものではない。 |
>>: 秘密を明かす:なぜ端節は水族にとって春のお祭りなのでしょうか?
推薦する
『太平広記・巻99・石正・慧祥和尚』の具体的な内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
清朝時代の昇進制度はどのようなものだったのでしょうか? 「壬氏」と「受連」ではどちらの方が昇進しやすいでしょうか?
清朝時代の昇進制度はどのようなものだったのでしょうか?「進士」と「従人」ではどちらが昇進しやすいので...
なぜ張居正は海瑞の再利用に失敗しただけでなく、海瑞の昇進を何度も阻止したのでしょうか?
海叡(1514年1月22日 - 1587年11月13日)は海南省瓊山(現在の海口市)に生まれた。明代...
司馬彪の『続漢書』にはどのような倫理観が含まれているのでしょうか?
本日は、『Interesting History』の編集者が司馬彪をご紹介します。ご興味のある読者は...
隋の滅亡につながったのは明らかに高句麗への3度の遠征だったのに、なぜ李世民はそれを貫いたのだろうか?
中国の歴史上、華々しい時代として、繁栄した唐の名は人々の心に深く根付いています。唐の皇帝の中で最もよ...
劉備は張任の才能を高く評価していたが、なぜ諸葛亮は張任を処刑しようとしたのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
科挙における「進士」とはどういう意味ですか? 2位の次の4位は何と呼ばれますか?
科挙における「進士」とはどういう意味でしょうか? 次点に続く4位は何と呼ばれますか? 興味のある読者...
『左盛春夜』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
チュンス・ズオシェン杜甫(唐代)夕暮れには花が壁の後ろに隠れ、鳥が飛びながらさえずります。どの家の上...
『紅楼夢』で賈舍はどこに住んでいたのですか?なぜ別のゲートがあるのですか?
賈與は容公の孫で、号は延侯。長男なので、容公の爵位を当然継承した。 Interesting Hist...
『呉越春秋』第四巻『河路内伝』原文の鑑賞
ヘルーの治世の最初の年に、彼は高潔で有能な人々を重要な役職に任命し始め、親切を示し、善行を行い、その...
謝謝の「鵲橋仙人・月は霞み星は薄暗い」:スムーズな移行があり傑作です。
謝科(1074-1116)は、雅号を有伴といい、朱有居士とも号した。彼は福州臨川(現在の江西省福州市...
林黛玉はなぜ青文の死を悲しまなかったのか?林黛玉の死生観の詳細な説明
なぜ林黛玉は青文の死を悲しまなかったのでしょうか?『紅楼夢』では、青文は大観園から追い出された2日後...
「五英雄伝」第6章:襄陽王とその部下は英雄的な戦士白虎衛の死体を見て張華の首を切った
『五人の勇士』は、古典小説『三人の勇士と五人の勇士』の続編の一つです。正式名称は『忠勇五人の勇士の物...
明代の数秘術書『三明通会』第5巻:官吏と悪霊の排除と留置に関する雑論
『三明通卦』は中国の伝統的な数秘術において非常に高い地位を占めています。その著者は明代の進士である万...
魏夫人は生前、国内外で有名でした。彼女は王羲之に書道をどのように教えたのでしょうか?
魏夫人は東晋時代の有名な女性書家でした。彼は生前、国内外で名声を博し、若い頃は書家の王羲之に師事した...