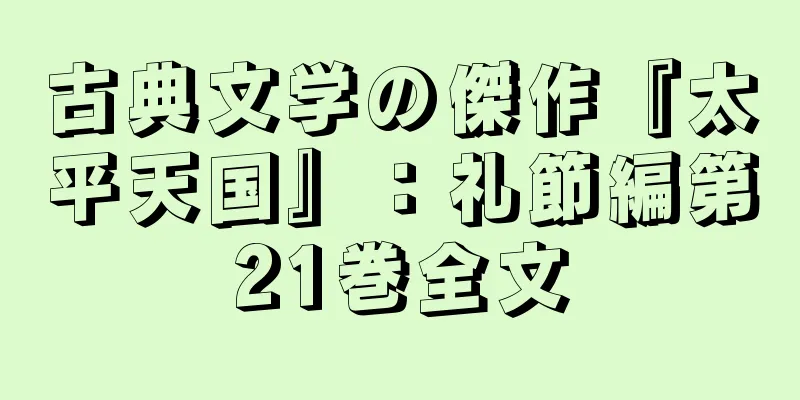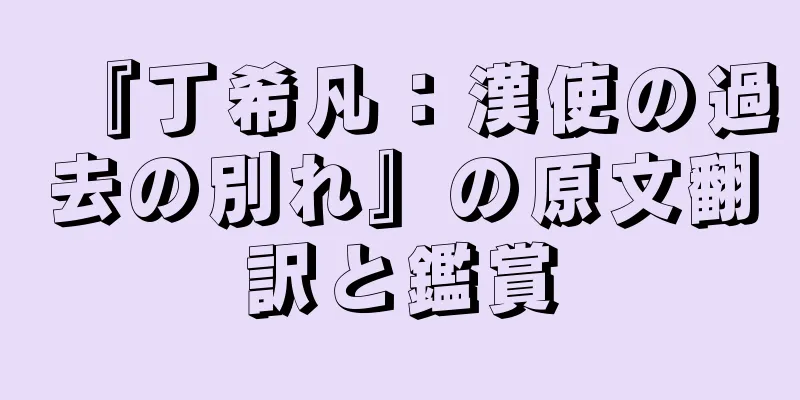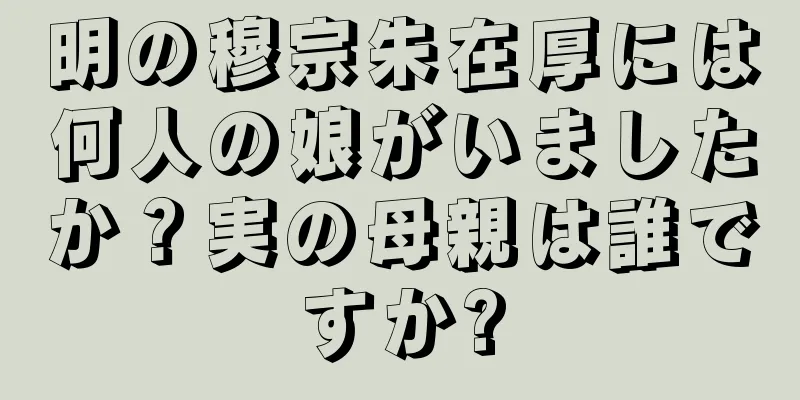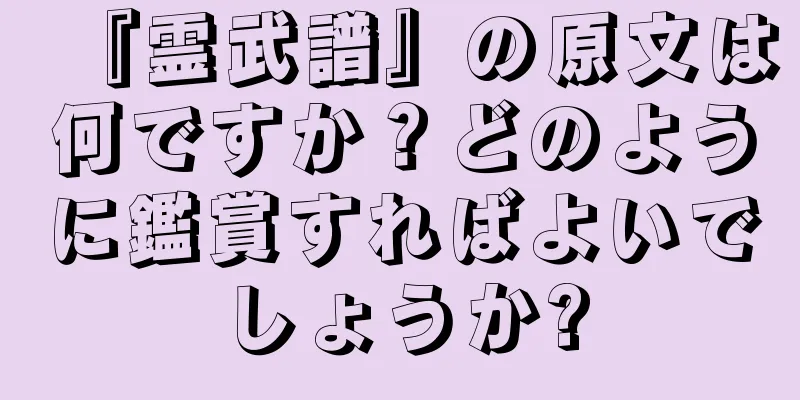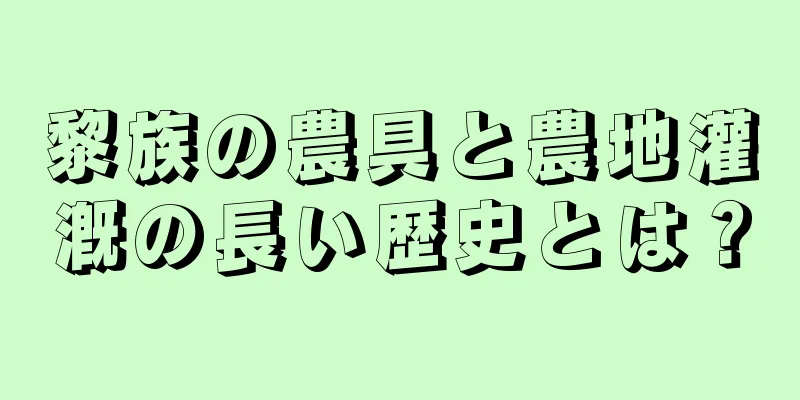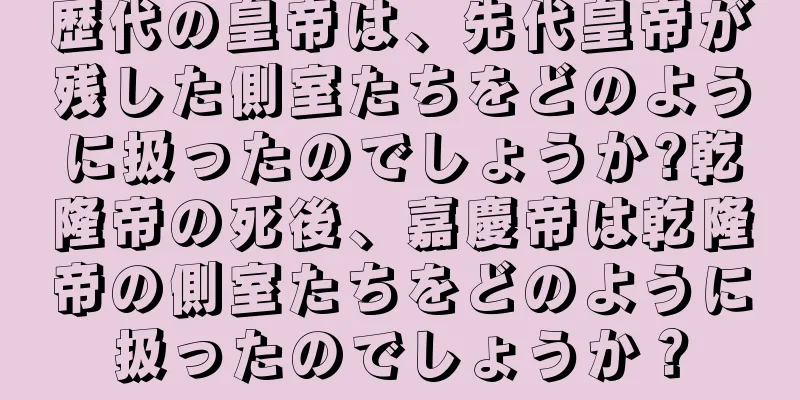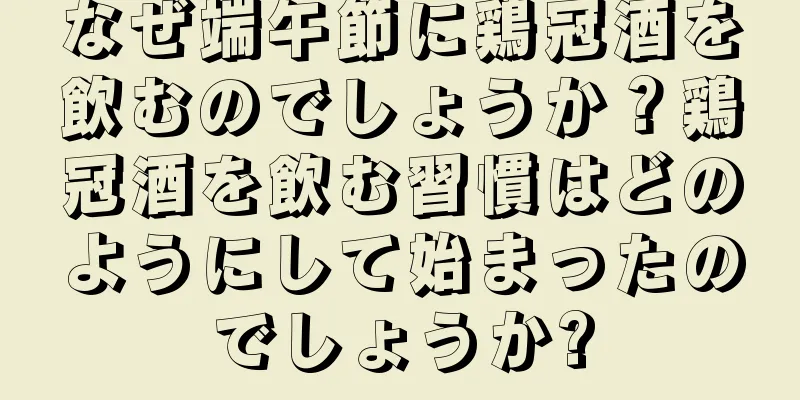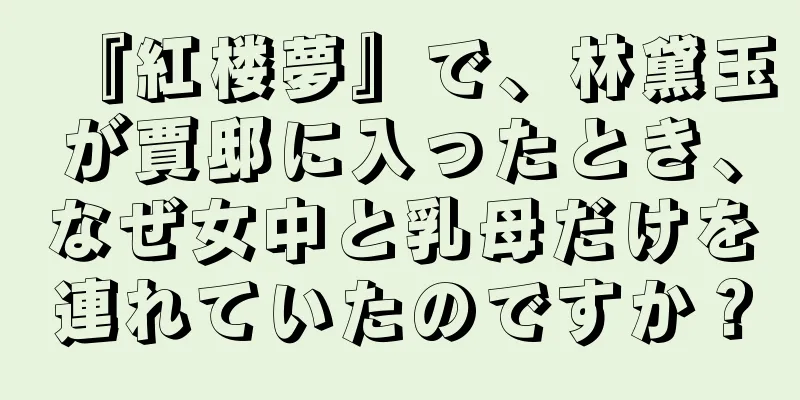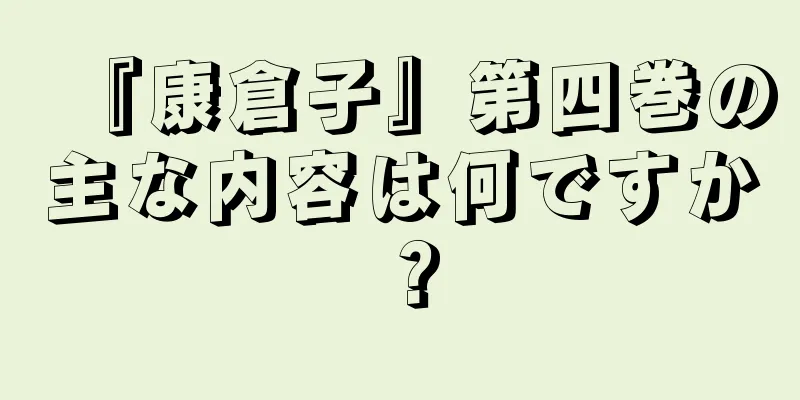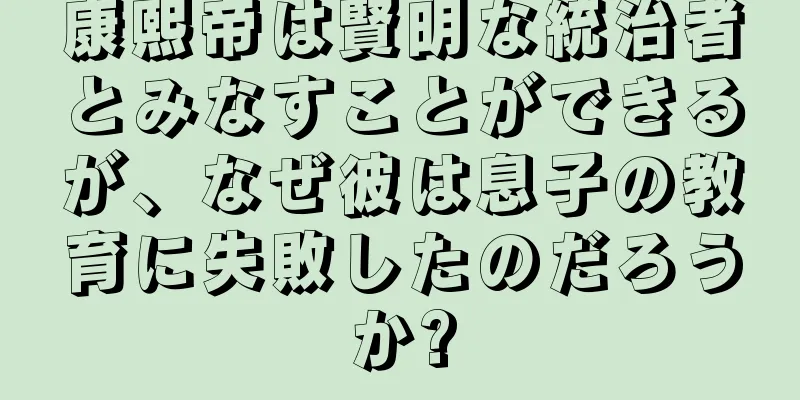「東湖新竹」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
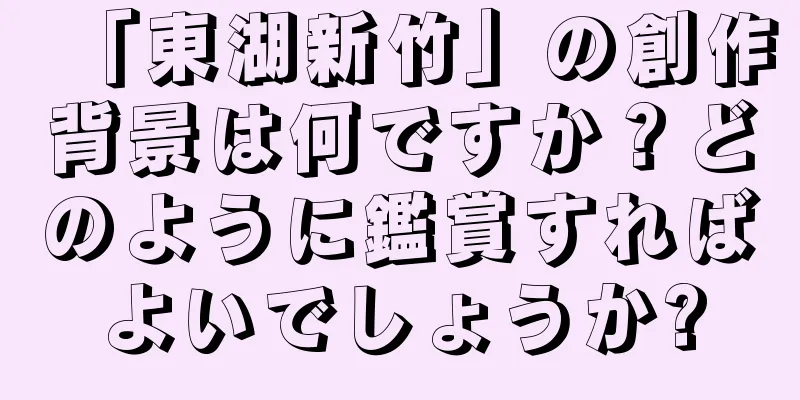
|
新竹東湖 陸游(宋代) 棘を植え、生垣を編むことで慎重に保護し、波紋を映す冷たい緑を育てます。 穏やかな風が大地を吹き抜けるとともに秋が訪れ、灼熱の太陽が空を横切る前に正午が訪れます。 鞘を解くとカサカサという音が聞こえ、先端を開くと葉がバラバラになり始めます。 仕事が休みの時はここに頻繁に来たいですし、どこへ行くにも枕とマットを持っていきたいです。 翻訳 竹を植えるときには、新しい竹を慎重に保護するために、とげのある竹紐で柵を作ります。新しい竹が成長するにつれて、その青々とした緑の影が水面に波紋として映ります。 まるで秋が早く到来したかのように、夏のそよ風が地面を吹き抜け、空には太陽が明るく輝いているにもかかわらず、真昼の暑さは感じられません。 竹の子が落ちるとカサカサという音が聞こえ、竹が成長するとまばらで美しい影が現れ始めます。 退職して時間ができたら、よくここに来ます。ここに来るときは、どこでも寝られるように枕と竹マットを持っていきます。 簡単なコメント 詩のイメージは非常に重要であり、これは頌歌の場合に特に当てはまります。木、竹竿、花などは、静的で平凡なものに見えるかもしれませんが、才能のある詩人は、芸術的な言葉と適切な描写を通じて、あらゆる角度からそれを生き生きと表現することができ、それによって風景に命を吹き込み、「静的」なものに命を吹き込むことができます。陸游の竹に関する詩は、「多面的な」比喩的描写を通じて「東湖の新竹」に命を吹き込んでいる。詩の最初の文は竹を植える場面を描写しています。次の 5 つの文はすべて、新しい竹をさまざまな角度から生き生きと描写しています。 2 番目の文「冷たい青が波紋を映し出す」は、水を通してまばらな影を映し出しています。ここでは、竹の「冷たい緑」と水の「さざ波」が互いに響き合い、どちらも「冷たい」「涼しい」という意味を持っています。 3番目の文「風が地面を吹き抜けると秋が来る」は、「風」を使って竹の穂先の敏感さと風に揺れる竹の穂先を表現しています。「秋が来る」という3つの言葉は非常に正確で鮮明で、「新しい竹」の細い枝が風に揺れる特徴を生き生きと表現しています。 4番目の文「真昼に灼熱の太陽が誰にも気づかれずに空を横切る」では、「光」を使って緑豊かな風景を表現しています。第5文と第6文の「ざわめく音」と「散らばる葉」は、動と静を組み合わせ、新竹の成長過程の特徴を生き生きと描写しており、読んだ後にはまるでそれが見えたり聞こえたりするように感じられます。最後の 2 行は叙情的で、竹林に対する作者の愛と憧れ、そして仕事が休みのときにここに来て「枕とマットを敷く」ことができるという希望を表現しています。竹ひごで作られた「マット」は、テスト問題にある「竹」という言葉を反映しています。この詩はイメージを重視しているため、詩がより新鮮で生き生きしたものになっています。 |
<<: 「君を慕って・カングランとともに」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
>>: 「酔った気持ち」の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
推薦する
ラクシュミ:ヒンドゥー教の幸福と富の女神、毘沙門天の妹
ラクシュミは、バラモン教とヒンズー教における幸福と富の女神です。伝説によると、彼女はヴァイシュラヴァ...
清朝の道光帝はどのようにして亡くなったのでしょうか?
愛新覚羅民寧(1782年9月16日 - 1850年2月25日)は、清朝の玄宗皇帝としても知られ、歴史...
水滸伝における朱同と李逵の間の恨みとは何ですか、そしてなぜ彼らは和解できないのですか?
なぜ朱統と李逵は和解しがたいのか?次は、おもしろ歴史編集長が歴史の真実を詳しく解説します。さっそく見...
呂布はたった二人の一般将軍を殺しただけなのに、なぜ人々は彼が最強の軍事力を持っていると考えるのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
清朝時代の鄭板橋の息子への教育物語
鄭板橋は清朝時代の有名な書家、画家、詩人でした。彼の書画はいずれも高い評価を受けており、三大奇観とし...
なぜ司馬懿は有名な司馬昭ではなく司馬師を後継者に選んだのでしょうか?
司馬師は淮南の乱を鎮圧していたとき、文洋に脅されて目玉が飛び出し、結局は死んでしまい、歴史に無能の汚...
『紅楼夢』で賈夫人は何回病気になったのですか?それぞれいつでしたか?
賈おばあさん(別名施夫人)は『紅楼夢』の主人公の一人です。『おもしろ歴史』編集者が歴史の霧の中を抜け...
「お正月作品」の執筆背景は?どのように理解すればいいのでしょうか?
【オリジナル】新年を迎え故郷が恋しくなり、空を見ながら一人涙を流す。年老いたら他人の下で暮らすが、春...
『紅楼夢』で霊官は結局どこへ行ったのでしょうか?なぜ消えてしまったのでしょうか?
霊官は賈家の12人の小役者の一人です。容姿も性格も黛玉に最も似ています。興味のある方のために、「おも...
文字の説明: 左側の 1 画と右側の 1 画で数字の「8」が形成されるのはなぜですか?言葉の意味がとても豊かですね!
今日の漢字(548): 八文字の本来の意味は「分ける」。まず、この言葉がどのようにして生まれたのかを...
武姓の祖である武尚(武子霞)の6代目の孫
家族研究布施は、布姓の祖先である布尚(布子霞)の6代目の孫でした。 「布石」という人物については、『...
「九日目に望仙台に登り劉明福容に献上」という詩を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】漢の文帝は高い壇を持っており、この日、夜明けにそこに登りました。三晋の雲と山はすべて北...
三国志の正史において、東呉における関羽の地位はどのようなものだったのでしょうか?
後漢末期から三国時代の有名な将軍、関羽について、Interesting History の編集者が書...
唐代の詩人、魏応武の『仙居集段と重陽』の原文、注釈、翻訳、鑑賞
『仙居集段集重要』は唐代の魏応武によって著されたものです。次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届け...
古典文学の傑作『太平天国』:食品飲料第21巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...