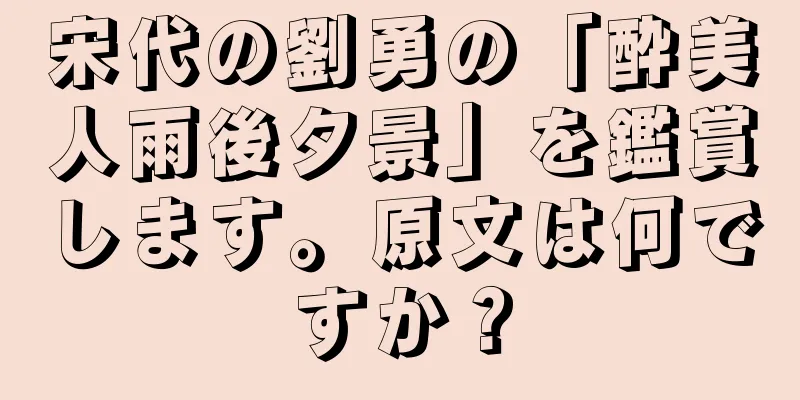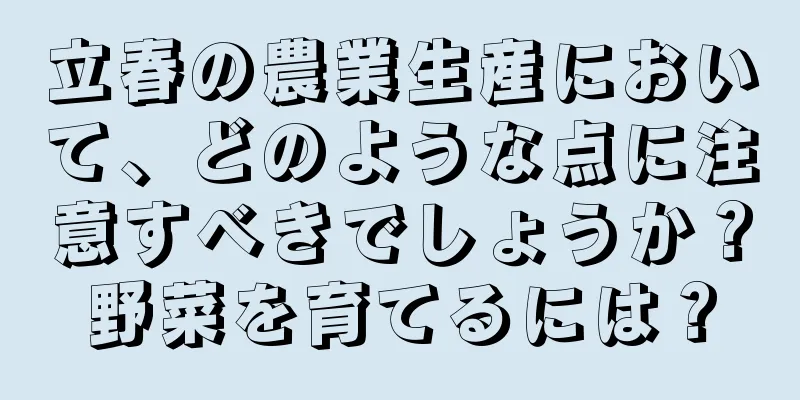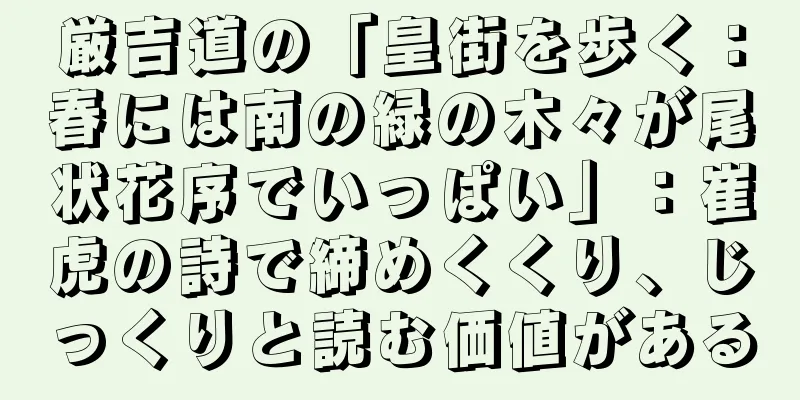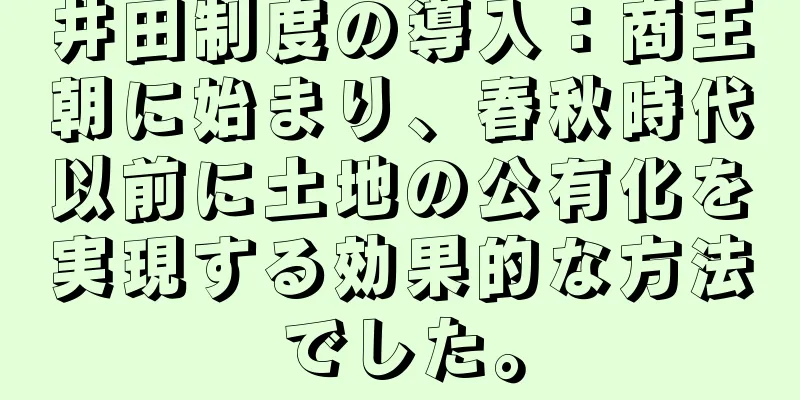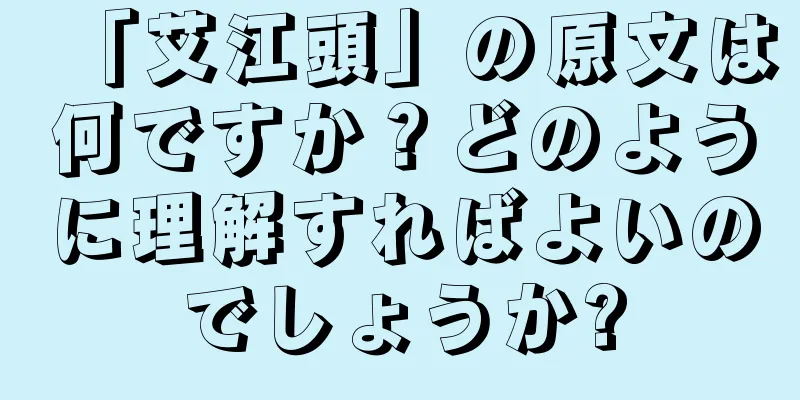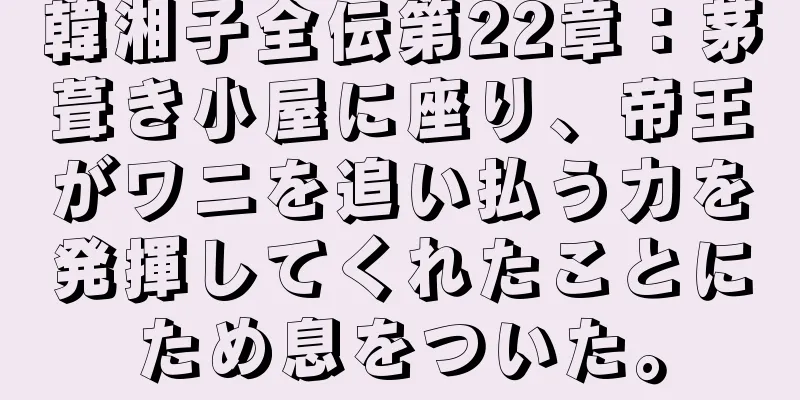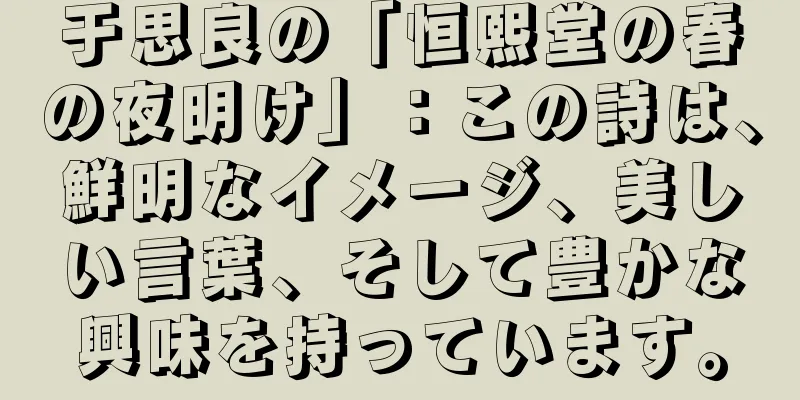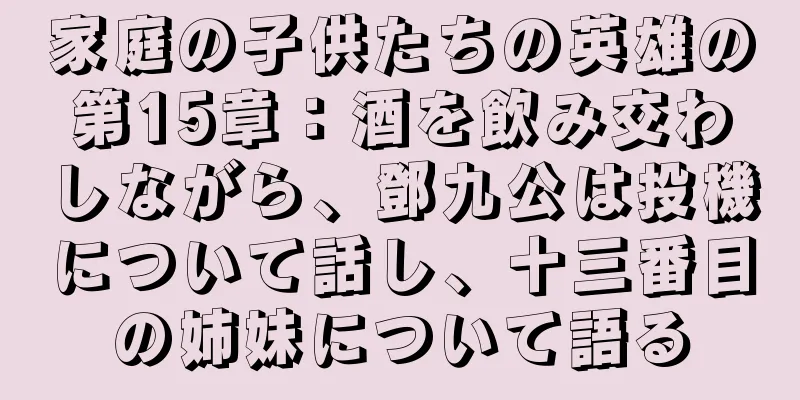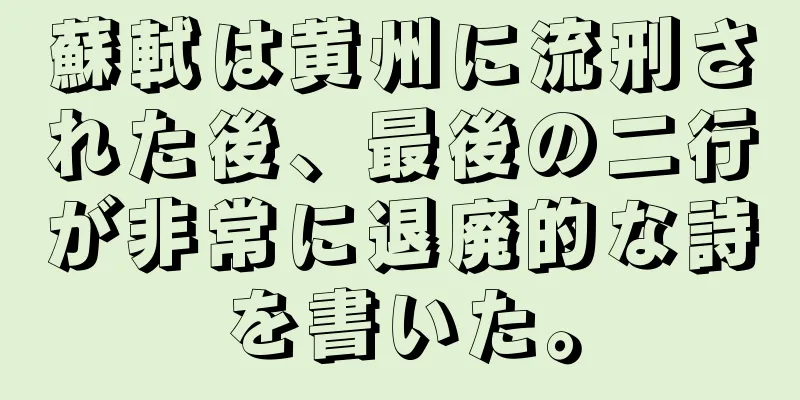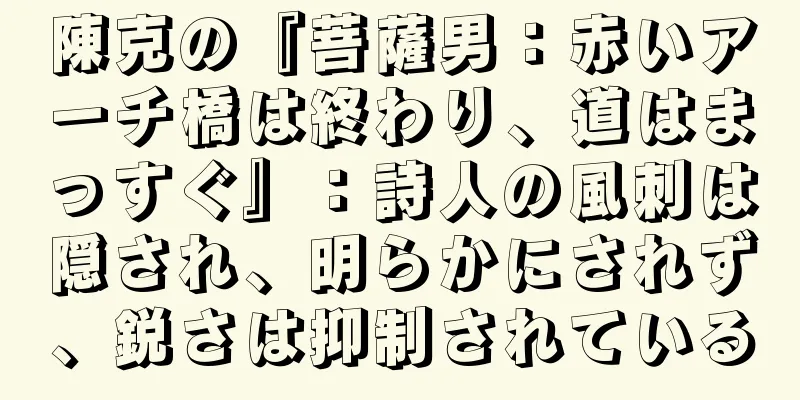混乱した三国時代になぜ外国からの侵略がなかったのでしょうか?この文は今でも使われています!
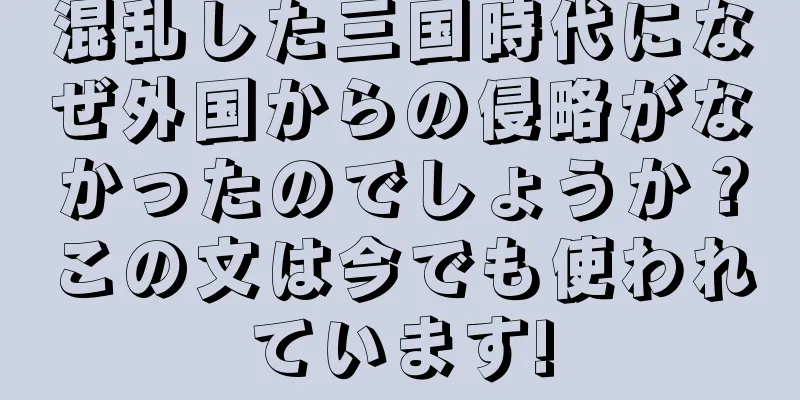
|
混乱の三国時代になぜ外国の侵略がなかったのか?この言葉は今でも使われています!興味のある方は編集者をフォローしてご覧ください。 三国時代、多くの英雄が立ち上がって覇権を争い、とてもエキサイティングでした。魏、蜀、呉の勢力は対立し、互いに譲り合いませんでした。しかし、豊かで美しい中原には、魏、蜀、呉が手放したくないという気持ちに加えて、当然、それを貪欲に狙う異民族がいました。これらの異民族は文化教育のレベルが比較的低く、その力は三国よりもはるかに弱かったです。しかし、北方のフン族は地理的な位置から、騎馬民族であり、比較的勇敢で戦闘が得意であり、依然として中原の支配にかなりの脅威を与えていました。 では、なぜ100年続いた三国時代に外国の侵略が成功したというニュースがなかったのでしょうか。この言葉は今でも人々の怒りをかき立てます。漢民族を怒らせた者は、どんなに遠くにいても罰せられるのです。今は中華人民共和国ですが、「中国を侮辱する者は、どんなに遠くにいても処罰される」という話をよく聞きます。どちらの文も同じ意味を持ち、自分の領土は神聖で侵すことのできないものであることを表現しています。しかし、これはあくまでも自国の力による発言です。弱い国には外交力はなく、いじめられることしかできない。これは歴史が物語っています。 少数民族は辺鄙な地域に散在していた。地理的な位置の違いにより、魏、蜀、呉の三国はそれぞれ異なる少数民族と対峙していた。三国時代になると、匈奴はもはや脅威ではなくなったが、他の少数民族が再び台頭してきた。強大な魏にとって、少数民族問題への対処は自らの責任となった。この点で、曹魏は皆の期待を裏切らず、素早く戦略を駆使して落ち着きのない鮮卑族を排除した。 蜀国が直面していた羌族と容族は、諸葛亮に七度捕らえられ、解放された後、逆に蜀国を大いに尊敬していた。その時、孟獲は諸葛亮の機転に衝撃を受け、自分と他人との差を悟った。彼は騒ぎを起こすのをやめ、蜀国のそばに静かに留まり、用事がない時には蜀国を助けさえした。孫権は白越族も滅ぼし、呉王国全体が蜀や魏との覇権争いにさらに全力を注ぐことを可能にした。 三国志の覇王と諸侯の間には、一方が異民族に侵略されたとき、一方が異民族に抵抗しているときは、他がその状況を利用して他方を裏切ることはできないという暗黙のルールもあります。当時の指導者たちは皆、お互いを知っており、中には互いに人材を推薦し合う者もいて、関係も非常に良好で、皆が外国の侵略を心配していたため、このような規制は皆に暗黙のうちに認められていました。 長い歴史の流れの中で、すべてのものは絶えず変化しています。唯一変わらないのは変化です。三国時代、魏、蜀、呉は外国の侵略に抵抗しました。100年も経たない前、日本は我が国を占領しようとし、我が国の領土であらゆる種類の残虐行為を犯しました。8年間の戦いの後、賢明な共産主義者は日本を降伏させ、中国の土地を守りました。 |
<<: 「貧しい人は水に行ってはいけない、金持ちは売春をしてはいけない」ということをどう理解しますか?そこにはどんな真実が含まれているのでしょうか?
>>: 魏荘は65歳のとき、ある女性の道士に詩を書いた。なぜその道士はそれを読んだ後、餓死したのか?
推薦する
袁曲華の『水歌・定王台』:絵は壮大で荘厳、音色は荒涼として悲しい
袁曲華、号は玄清、江西省豊新(毓章とも呼ばれる)の出身。生没年は不明。宋代高宗紹興末期の人物。彼は紹...
清朝内閣と明朝内閣の違いは何ですか?二人のうちどちらが力を持っているでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が清朝内閣と明朝内閣の違いについて紹介します。...
冬至にまつわる4つの詩の解説
冬至に関係する詩はどれでしょうか?これは多くの読者が気になる質問です。一緒に学んで参考にしてみましょ...
なぜ宋仁宗は歴史上最も繁栄した時代を築くことができたのでしょうか?
西暦1063年3月、54歳の宋仁宗が亡くなりました。朝廷と国中の誰もが泣き悲しんでいました。 『宋史...
古代の科挙にはどれくらいの時間がかかりましたか?なぜ9日間と6泊なのでしょうか?
古代の科挙はなぜ9日6晩も続いたのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみま...
『水滸伝』で武松が涼山に行く前と後でどのような変化がありましたか?他にはどのような貢献がありましたか?
武松は、史乃安の古典小説『水滸伝』の重要な登場人物です。このことが言及されるたびに、編集者は詳細に説...
古典文学の傑作『太平天国』:陸軍省第82巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
宋哲宗昭慈皇后と宋哲宗孟皇后元有の生涯についての簡単な紹介
元有皇后(1073-1131)は宋代の人物。姓は孟であったため、元有皇后孟とも呼ばれる。明州(現在の...
水滸伝の涼山における段静珠の順位は何位でしたか?彼の能力は何ですか?
段静珠は涛州の出身で、赤い髪と黄色いひげを持っていたことから「金犬」と呼ばれていました。 Inter...
『紅楼夢』では、鳳凰尾糸と芙蓉の敷物は林黛玉に似合うのに、なぜ薛宝才に与えられたのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
「慕容」という姓はいつ生まれたのですか? 「慕容」という苗字の素敵な赤ちゃんの名前をご紹介します!
今日は、Interesting Historyの編集者が、慕容という姓を持つ素敵な赤ちゃんの名前をい...
西洋史第13章:張天石の祭壇は金宮の隣にあり、金色の峰と水が天門に溢れている
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
蓋炎の物語 雲台二十八将軍の中の蓋炎に関する逸話は何ですか?
蓋岩(?-39年)、愛称は聚清、東漢初期の将軍。漢民族、余陽市耀陽(現在の北京市平谷県)出身。蓋岩は...
戦国時代の楚の詩人、屈原の作品:「九章淮沙」創作の背景と評価
『九章淮沙』は、中国戦国時代の楚の詩人、屈原の作品です。この詩は屈原の死の前に書かれたもので、詩人の...
清朝の皇室は一年間に何回祭祀を行ったのでしょうか?どのようなエチケットがありますか?
清朝の王室は年間に何回祭祀を行ったのでしょうか?どのような作法があったのでしょうか?これは多くの読者...