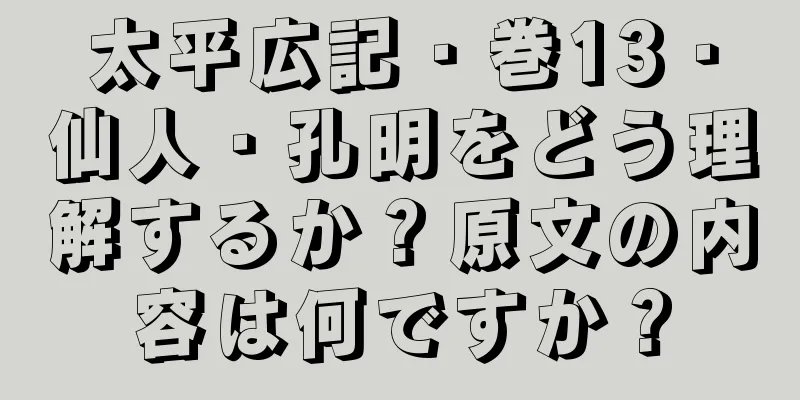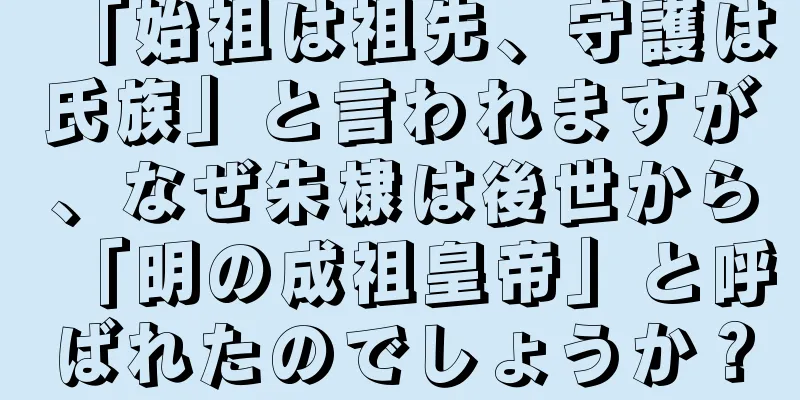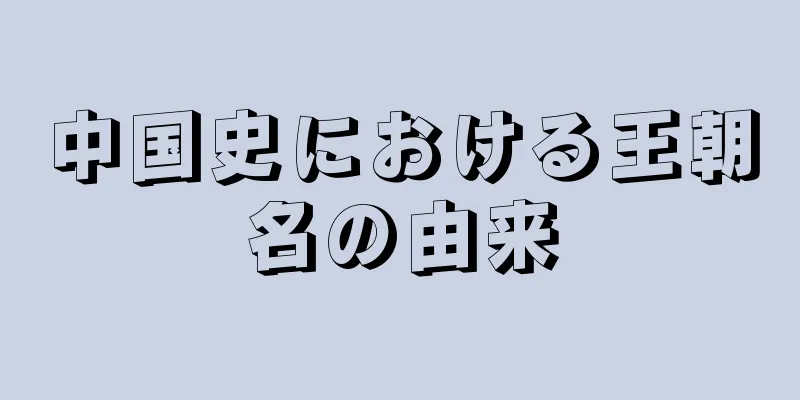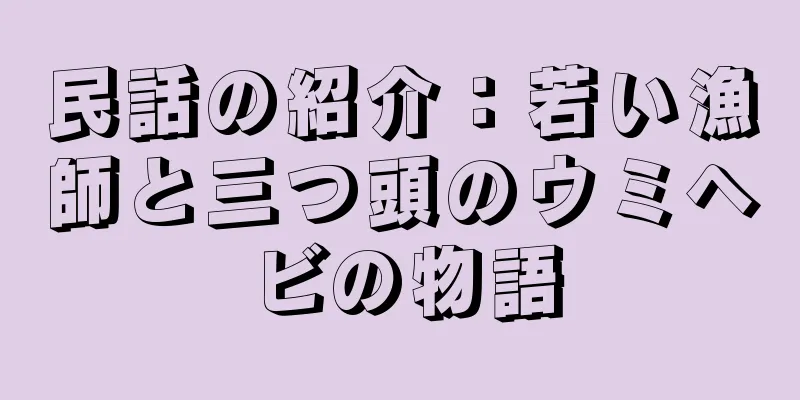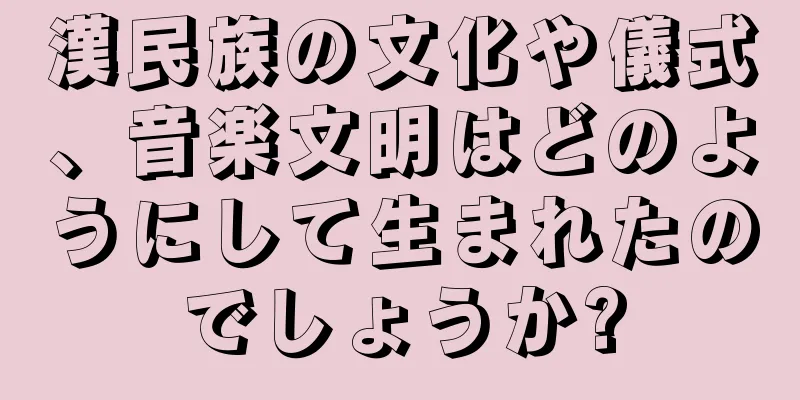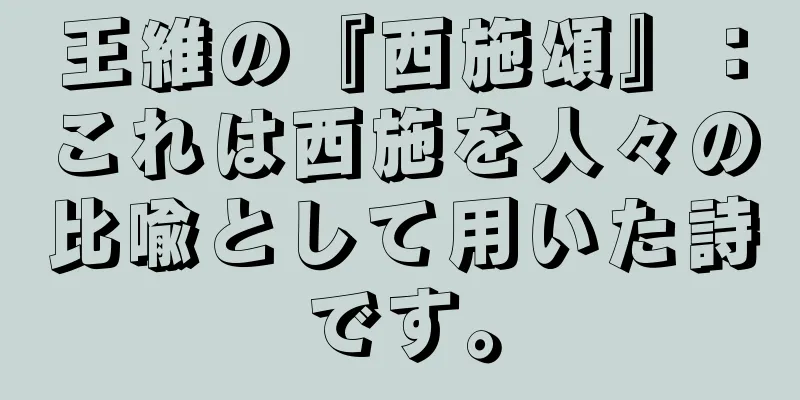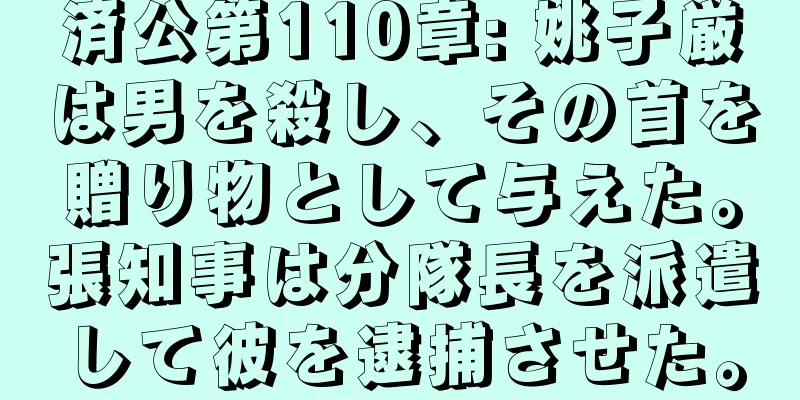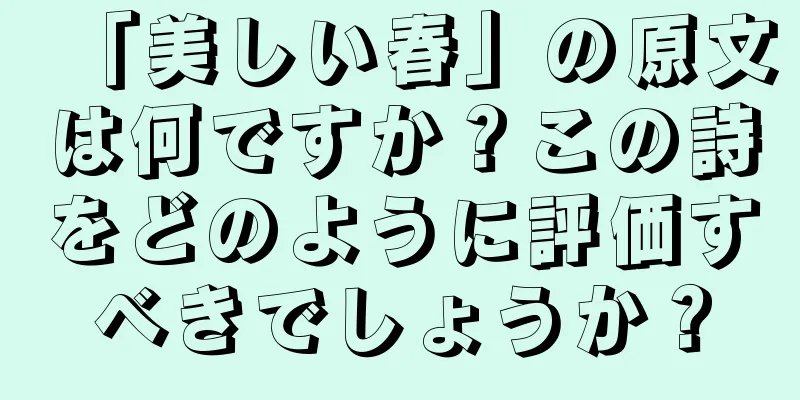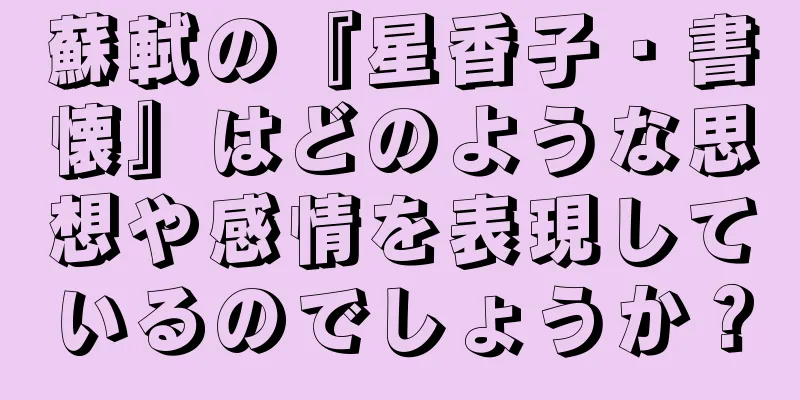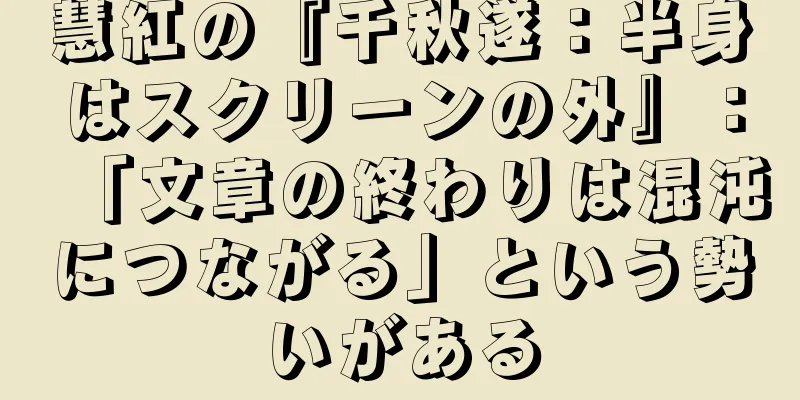唐代の詩「武克先生に告ぐ」をどのように鑑賞するか?賈島はどんな感情を表現したのでしょうか?
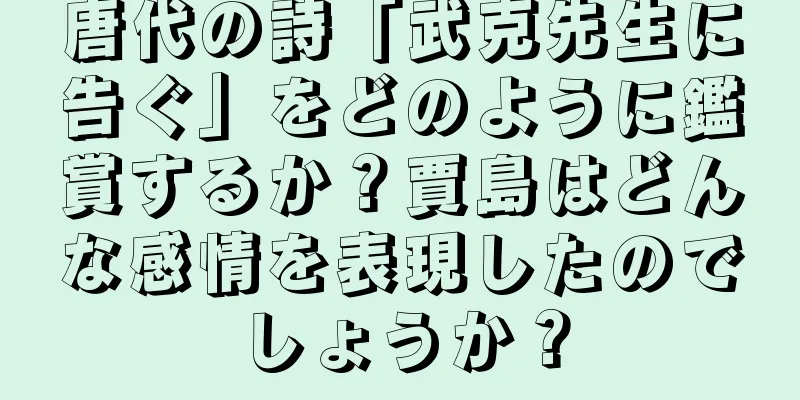
|
唐代の武克賈道先生をお送りして、次の興味深い歴史編集者が詳しい紹介をお届けしますので、見てみましょう! 桂峰山の澄んだ空がここにあり、私はこの茅葺き屋根の小屋の人々を送り出しています。 私たちは、筍たちと一緒にお寺を出て、コオロギの鳴き声を聞きながら、愛する人たちに別れを告げました。 一人で歩いていると、池の底に影が落ち、木の横で呼吸を数えている。 ついに霧と雲との約束があり、天台が私たちの隣人になります。 秋の雨がちょうど止んだとき、詩人は従兄弟を天台に遣わして質問をさせました。 「晴れた空と新しい晴れた空」に続いて「コオロギが鳴く」が雨上がりの様子を示し、「一緒に寺を出る」は次の文から来ています。 3 番目と 4 番目の文は前の文をつなげたもので、1 つは別れを、もう 1 つは別れを表現し、こうして「一人で歩く」という 2 つの文に移行します。 「池の底に影を落としながらひとり歩き、木の傍で息を数える」は、時代を超えて語り継がれてきた有名な一節です。最初の行は、いとこが池のそばを一人で歩いている様子を描いています。澄んだ水が彼の孤独な姿を映し出し、孤独と影の芸術的概念の中で人々に孤独感を与えています。2行目は、いとこが途中で疲れ、休むために木に寄りかかっていることを描いており、孤独感にホームレスの悲しみが加わっています。この詩は巧みに平行法で書かれており、言語は自然で独特であり、芸術的概念は冷たく奇妙である。この二行は賈島の生涯で最も誇らしい言葉だ。彼はメモにこう書いている。「この二行を書くのに三年かかりました。これを朗読すると涙が出てきます。もし私の心の伴侶がこれを喜ばないなら、私は故郷に帰って秋に眠ります。」表面的には、この二行は前の別れの言葉を引き継いでおり、賈島の孤独を表現している。従兄弟が去ってから、池のそばを歩くとき、従兄弟の影だけが彼についてくる。休憩所で何度か立ち止まったときも、木だけが彼についてくる。しかし、より深いレベルでは、この連句は作者の仏教に対する理解を体現している。池のほとりを一人で歩いていると、池の上の人物と池の底の影は一と二であり、一でも二でもなく、一であり二でもある。それは必然的に人々に、池の底の影を見て悟りを開いた東山良傑の物語を思い出させます。そして木のそばに休んでいるのは、肉体に他なりません。だから、別れをあまり深刻に考えないでください。しかし禅師たちは環境を受け入れるがそれにとらわれないことを説き、結局心の中の感情を消すことができず、ついにこう言った。「最後には霧と雲との約束があり、天台は近い隣人となるだろう。」 この詩の中で作者は、世の中に対する嫌悪感、仏教の静けさへの憧れ、そして従兄弟に対する郷愁を表現しています。第一連句では別れの場所、物、風景を描写し、第二連句では別れの場面を描写し、代表的な物を使って別れ、雰囲気、感情などを書いています。二連句は、別れた後の詩人の孤独な外面と冷たい内面の感情を強調しており、それが賈賈の詩の本質である。最後の連句は別れへの憧れを表現しています。この詩は明確な層を持ち、別れの全過程を描写しています。言語はシンプルで自然であり、歌詞の意味は深く豊かです。まさに「平易」と言えます。 「一人歩き」という2つの文章は、必ずしも「3年」かかるわけではないかもしれませんが、登場人物の心理状態を非常に正確に表現しています。 |
<<: 唐代の詩「鄒明甫霊武往往」をどのように鑑賞するか?賈島はどんな感情を表現したのでしょうか?
>>: 何九の『懿社唐詩集』をどう鑑賞するか?王長玲はどのような感情を表現したのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』の賈歓は不良少年ですか?彼は実は貧しい子供です。
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
古代では銀一両はいくらの価値があったのでしょうか?清朝時代の現在の10万元はいくらぐらいの価値がありますか?
清朝時代の10万元は今やいくらになるのでしょうか?以下、Interesting History編集長...
『陸淑寨水仙西湖図』の執筆背景は何ですか?
【オリジナル】人々は静かで、月は明るい。翡翠色の梅の花が紗窓の外に斜めに映っています。梅の花は人々に...
ひざまずいてお辞儀をする儀式は古代社会で長い間続いてきました。その性質が根本的に変化したのはいつでしょうか?
時代劇を見ると、当時の人々は、同僚、君主と大臣、父と息子、異なる階級の人々に会うとき、基本的にひざま...
『西遊記』に登場する七人の聖人とは誰ですか?孫悟空
はじめに:孫悟空としても知られる孫悟空は、中国明代の小説家、呉承恩の作品『西遊記』の登場人物の一人で...
龐徳は、かつての主君である馬超が曹操に降伏した後、なぜもはや彼に従うことを望まなくなったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
唐代に最年少で第一の学者となったのは誰ですか?彼はなぜあまり有名ではないのでしょうか?
実際、唐代には優秀な学者がたくさんいましたが、私が一番感銘を受けたのは最年少の学者でした。彼は最年少...
「ジンメンを訪ねて 秋の想い」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
金門を訪ねて:秋の気分蘇軾(宋代)今夜は雨が降ります。今年の残りの夏の暑さを無駄にする。座ってビエプ...
明朝の「建国論争」とは一体何だったのでしょうか?それは明代の政治情勢にどのような影響を与えたのでしょうか?
明代における「建国闘争」とは実際どのようなものだったのでしょうか。それは明代の政治情勢にどのような影...
『西遊記』のキツネの王はなぜ長生きできるのでしょうか?玉面狐はなぜ牛魔王を探し求めたのか?
今日は、Interesting History の編集者が、「西遊記」のキツネの王がなぜそんなに長生...
袁浩文の「江城子:鶏の鳴き声に酔って長袖で踊る」:この詩は大胆で力強く、率直で率直である。
袁浩文(1190年8月10日 - 1257年10月12日)、号は毓之、号は易山、通称は易山氏。彼は太...
晋楚和平会議:春秋時代最大の和平会議
紀元前582年のある日、晋の景公が軍政を視察していたとき、南方の帽子をかぶった囚人を見つけました。晋...
『竇鄂の悪徳』の蔡昊はどんな人物ですか?蔡英文のイメージをどう分析するか?
近年、「竇鄂の不義」の証拠や法的問題について議論され、論争が巻き起こった。当時の尋問方法と、強力な自...
古典文学の傑作『景世同言』第14巻:幽霊の洞窟と癩病の道教の祓魔師
『景世同言』は、明代末期に馮夢龍が編纂した俗語短編小説集である。天啓4年(1624年)に完成し、宋代...
孟子:第1章第8節原文、翻訳および注釈
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸...