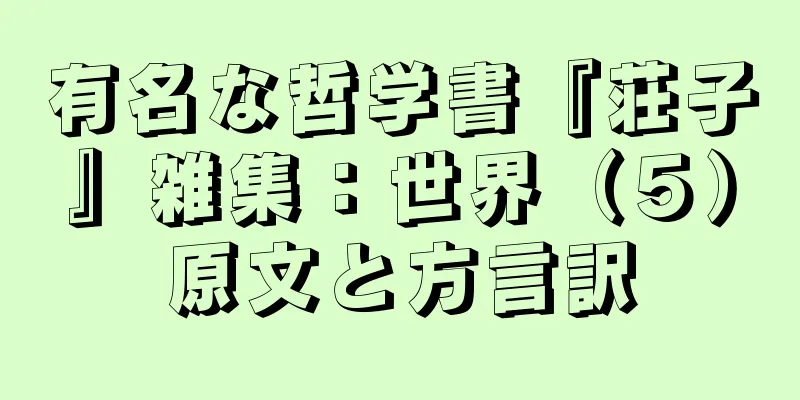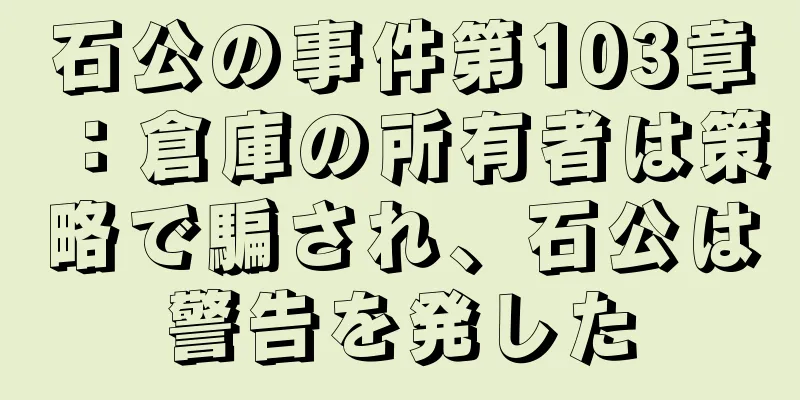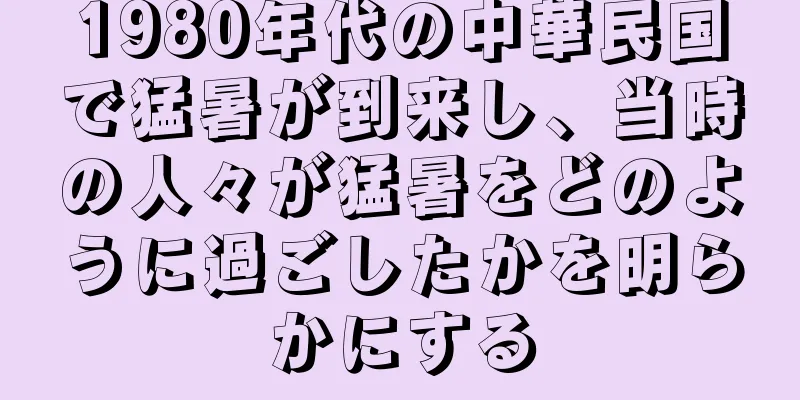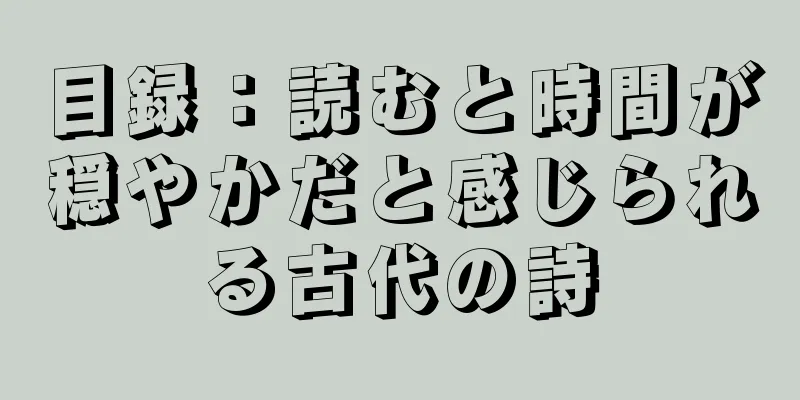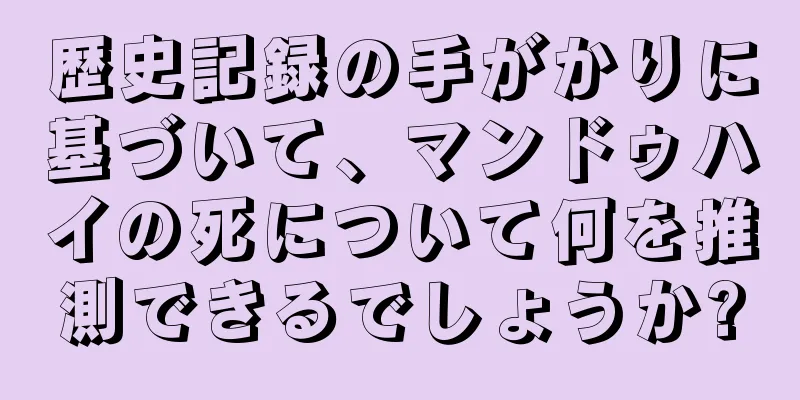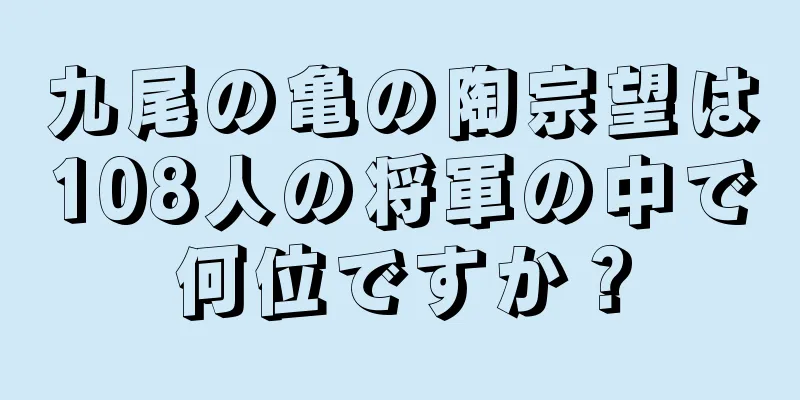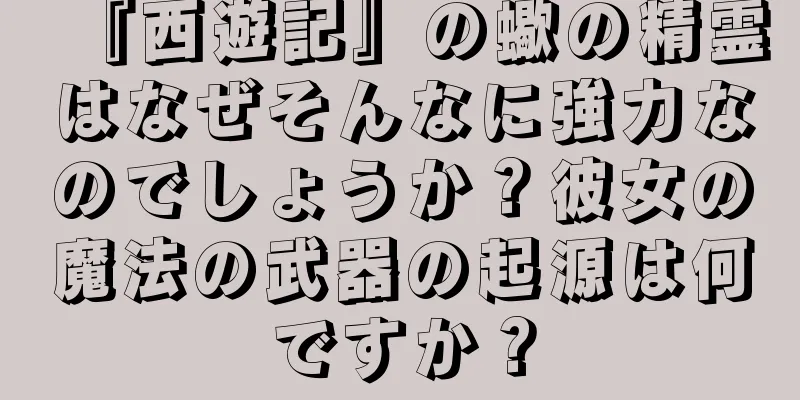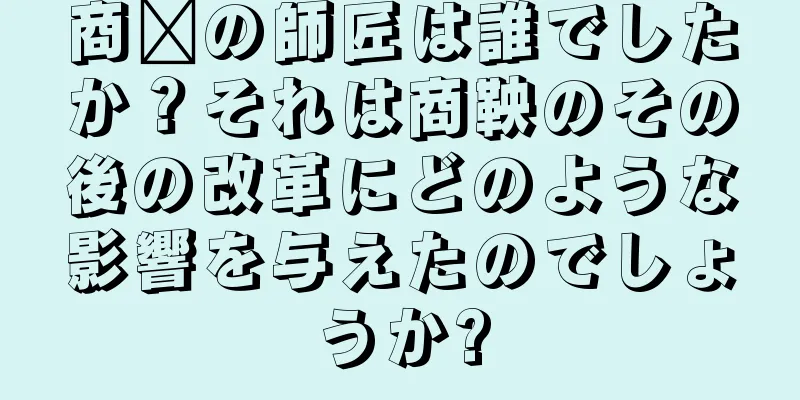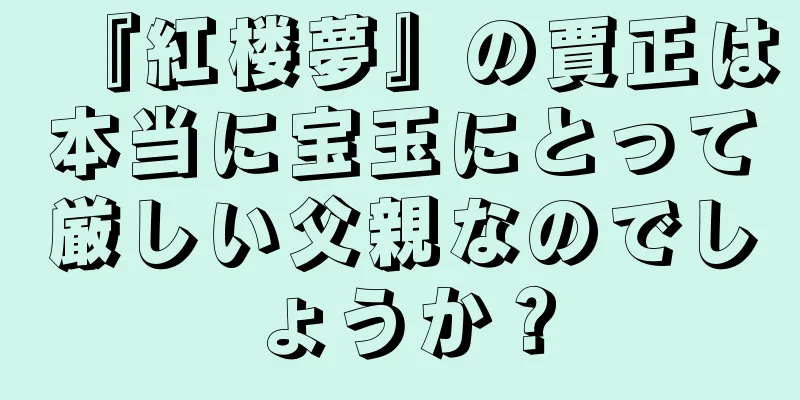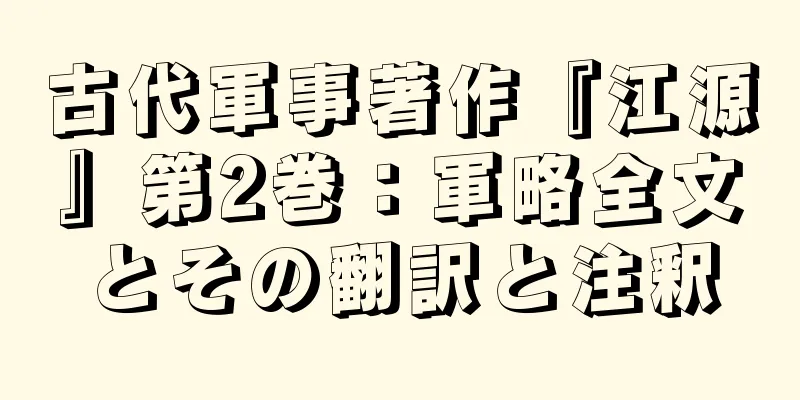宋代の詩「六州歌頭」の鑑賞 - 若者の騎士道精神。作者は詩の中でどのような比喩を使用しているか?
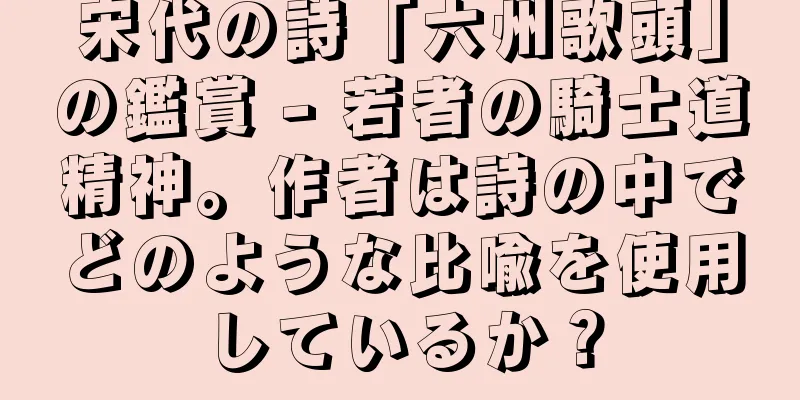
|
宋代の何朱による『六州歌 青年の騎士道』。以下、Interesting Historyの編集者が詳しく紹介します。さっそく見てみましょう! 若者は騎士道精神にあふれ、5つの都市の英雄たちと友達になります。肝臓と胆嚢は空洞になっており、毛が逆立っています。話している間は、生と死は同じです。約束は千枚の金貨の価値がある。彼は勇敢で傲慢だ。軽い傘と空飛ぶ鞍を持って、彼らは街の東で戦います。ワインショップでお酒を飲み、冷たい瓶に浮かぶ春の風景、海から虹を吸い込む。鷲が犬を煽るために呼ばれ、彫刻された弓から白い羽が引き抜かれ、狡猾な穴は突然空になります。急いで幸せ。 (カジュアルコールの別のバージョン:断続的なコール) 黄粟の夢のように、鳳凰に別れを告げ、明るい月を分かち合い、タンポポの上に一人浮かんでいる。役人は多くて忙しく、仕事は埃まみれで書類も山積みです。たくさんのオオヅルがいるので、手荒な仕事をしても、突然、驚くべき成果を上げます。スオナと太鼓が鳴り、夕陽の曲が悲しい老人を思い起こさせます。長い縄を求めず、天の精霊を奪い、西風に剣を響かせよう。私は山に登って水辺に立って、七弦の桐の木を持ち、野生のガチョウが飛び去るのを眺めるのが嫌いです。 この詩の最初の部分は、彼が十代の頃に首都で過ごした遍歴の騎士としての生活を回想しています。 「この若者は騎士道精神にあふれ、国中の英雄たちと親交を深めた」というのが、この時期の人生の概要である。以下は2層で書かれています。「高潔で勇敢、...傲慢で奔放」は1層で、若い戦士の「騎士道的な」性格に焦点を当てています。彼らは同じ考えを持ち、互いに忠誠を誓い合います。彼らはほんの数語で生死を共にする友となります。彼らは正義を心に持ち、恐れることなく悪に立ち向かいます。彼らは金銭よりも正義を重んじ、約束を守ります。彼らは勇気を称賛し、騎士道精神と奔放な精神を重んじます。これらはすべて、道徳的資質と行動基準の観点から、若い戦士のグループの精神的見解を描写しています。 「会話の中では、生と死は同じです。約束は千金の価値があります」という典型的な詳細の選択により、文章は生き生きとしていて、空虚ではありません。 「光の覆いは抱かれ、...狡猾な穴は空いている」は、若い戦士たちの日常の行動の「英雄的」性質を描写することに焦点を当てたもう1つの層です。彼らは軽快な馬車を駆り、立派な馬に乗り、友人を呼び、都の内外で活動した。斗城:漢代の長安は北斗七星と北斗七星の形で建てられたためこの名がつけられた。これは北宋代の東京を指している。彼らはいつでもバーで大量に飲酒しており、彼らのアルコール耐性は海を吸い込む虹のように非常に大きい。ここでの「春の色」とはワインのことです。時には弓矢を持ち、タカや犬を呼び、郊外に狩りに出かけ、さまざまな野生動物の巣をすぐに一掃しました。彼らの優れた武術のスキルは、彼らの英雄的で頑丈な性格をさらに際立たせます。この二つの層は互いに補完し合っています。「騎士道的」な性格について書くことは「英雄的」な行動を暗示し、「英雄的」な行動について書くことは「騎士道的」な気質を体現することにもなります。自分の経験なしに、これほど生き生きと生き生きと書くことは難しいでしょう。文体は極めて緻密で、まるで手の甲に宝物を列挙しているかのようだ。そして、最初の部分を「乐匆匆」という3語で軽く締めくくっている。何卓はまさに文章の達人である。 詩の後半の冒頭「それはまるで黄粟の夢のようだ」への移行は自然である。前編の過去の思い出を引き継ぐだけでなく、過去の思いを今日の現実に呼び戻します。過去の人生は幸せだったが、夢のようにあまりにも慌ただしく短かった。都を離れてから10年以上が経ち、私は中年となり、状況は満足できるものではありません。彼は長い間、漢の時代で言えば余剰人員に相当する低い官職に就いており、生き残るために、明るい月だけを伴い、一人で船で漂流していた。年月はあっという間に過ぎていきますが、私は檻の中に閉じ込められたワシのように何もすることができません。彼は毎日、雑なデスクワークしかできず、祖国を守ろうという大志や、並外れた功績をあげる才能は完全に埋もれてしまった。さらに、この詩人は、このように欲求不満を抱えた下級軍人の中で唯一の人物ではなく、「彼のような人は他にもたくさんいた」。これはこの現象の社会的理由を見出し、北宋の統治者が才能を浪費し、軍事よりも文化を重視していることを批判した。 「梵琴と太鼓の音、毓陽の音楽」は宋代が国境危機に直面していたことを示している。 「思北翁」は二重の意味を持つ。漢代の戦争に関する楽曲の名前であると同時に、詩人の自称でもある。 40歳にも満たないのに老いを感じていた。人生の半分を何の成果も上げずに無駄に過ごしてきたことに対する彼の気持ちを、「考える」という言葉が十分に表していた。かつて英雄たちと友情を結び、高い志を抱いていた若き戦士は、今ではその鋭さをかなり失っているが、大きく成長もしている。彼は心の奥底に、祖国に仕えるという野望を今も抱いており、その身に帯びた剣も西風に唸りをあげている。しかし、平和を標榜する政治環境の中で、「才能のある人と結婚するために長いロープを願う」という彼の願いは打ち砕かれるしかなかった。 「招待しない」のではなく、「招待できない」、または「招待するが利用しない」のです。そこで詩人は、悲しみと憤りに満たされながら山に登り、水辺に立って、琴の弦に悩みを託し、空飛ぶ雁に野心を託すことしかできなかった。ピアノの音色と静かな視線の中に詩人のさまざまな感情が込められており、その悲しみと憤りは極めて深い。なぜなら、これは祖国と国民を思いながら祖国のために尽くす術のない愛国者の無力感と憤りであり、その時代の悲しみだからである。 この詩に描かれた遍歴の武士のイメージは唐の詩では一般的だが、宋の詩では前例がない。この詩は、祖国に仕えたいが、その方法がない「異人」のイメージを初めて表現した詩であり、降伏主義者を攻撃し、敵を殺した兵士を称賛する、宋代詩の中で最も古い愛国詩であり、蘇軾の詩と南宋の愛国詩の間の移行的な役割を果たしている。 詩全体のスタイルは荒涼と悲劇的で、物語性、議論性、叙情性が密接に結びついています。文章は力強く、活気があり、精神は高く、リズムは厳格で、文は短く、韻は密です。情熱的な声と感情は跳躍的な旋律に反映され、両者は完全に一体化しています。 |
<<: 「ブドウの絵のタイトル」の作者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
>>: 『上林春令:十一月三十日の雪』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
推薦する
『後漢書 光武帝紀』第1巻より抜粋した原文と翻訳
『後漢書』は、南宋代の歴史家・范業が編纂した年代記形式の歴史書である。『二十四史』の一つで、『史記』...
「錦琴」は李尚鑫が作曲した作品で、琴を隠れた題名にした「無題」の作品です。
李尚鑫(813年頃 - 858年頃)は、字を易山、号を毓曦生といい、淮州河内(現在の河南省沁陽市)の...
北宋時代の軍事著作『武経宗要』第二巻全文:北宋時代の軍事著作『武経宗要』第二巻全文
『武経宗瑶』は北宋の政府が編纂した軍事書である。著者は宋の仁宗の治世中の文官、曾公良と丁度である。二...
宋代に武松の領主はどのような役職に就いていましたか?なぜ武松は西門青を殴ろうとしたのか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、宋代に武松の軍長がどのような役職に就いていたかをお伝えします。皆さん...
古代の詩「川を渡って蓮を摘む」の内容は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
川を渡って蓮を摘む [漢代] 匿名さん、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきますので...
『朱英台:蓮華』をどのように理解すればよいのでしょうか?創作の背景は何ですか?
蓮華の近くの朱英台高光国(宋代)赤いメイクと緑のベールをまとってポーズをとると、花の影がサウスバンク...
『紅楼夢』の薛宝才はどの程度功利的ですか?どうすればわかるのか
古典小説『紅楼夢』のヒロインの一人であり、金陵十二美女の一人でもある薛宝才について、皆さんは聞いたこ...
水滸伝で方羅を倒した後、武松はなぜ最終的に僧侶になることを選んだのでしょうか?
武松は『水滸伝』の重要な登場人物です。 Interesting Historyの編集者が関連コンテン...
陳衛松の『南湘子・行州路著』:この詩は、非常に寛大で力強く書かれており、その力は紙を通して感じられるほどです。
陳衛松(1625-1682)、号は秦年、通称嘉陵、常州府宜興県南芝里(現在の江蘇省宜興市)の出身。明...
『紅楼夢』で、宝玉が僧侶になるという最終決断は宝仔と何か関係があるのでしょうか?
夫がどんなに才能があっても、妻がどんなに美しかったとしても、宝玉と宝仔の結婚は完全な悲劇です。 In...
唐代全盛期の漢民族は実は漢民族ではなく「新漢民族」だったことが判明
では、この「新漢魂」は漢民族にどのような変化をもたらしたのでしょうか?注目すべきは、李唐王朝が成立す...
太平広記・巻70・女仙・裴玄静の具体的な内容は何ですか?どのように翻訳しますか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
オロチョン族の地理的位置はどこですか?オロチョン族は山岳地帯に住んでいる
全国プロフィール「オロチョン」という名前は、清朝初期の文書に初めて登場しました。 「二屯」は『清朝太...
安史の乱後の皇帝は誰でしたか?安禄山はなぜ皇帝にならなかったのでしょうか?
安史の乱の後に誰が皇帝になったかご存知ですか? Interesting History の編集者が解...
項羽の『蓋下歌』は古今東西に衝撃を与えた。なぜ項羽は呉江に逃げて自殺したのか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、項羽が呉江に逃げて自殺した理由をお話ししま...