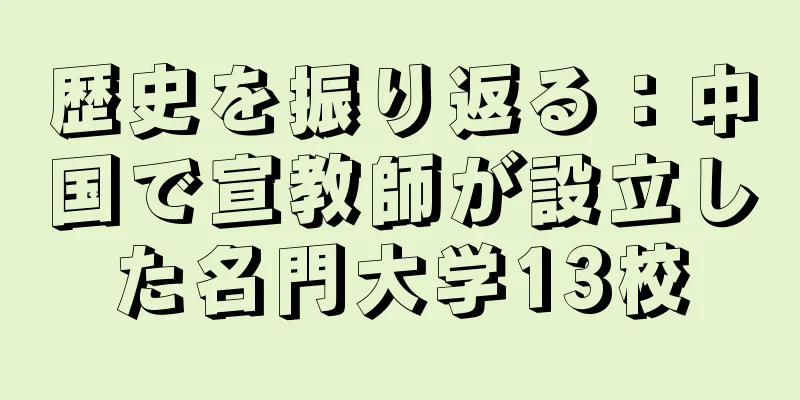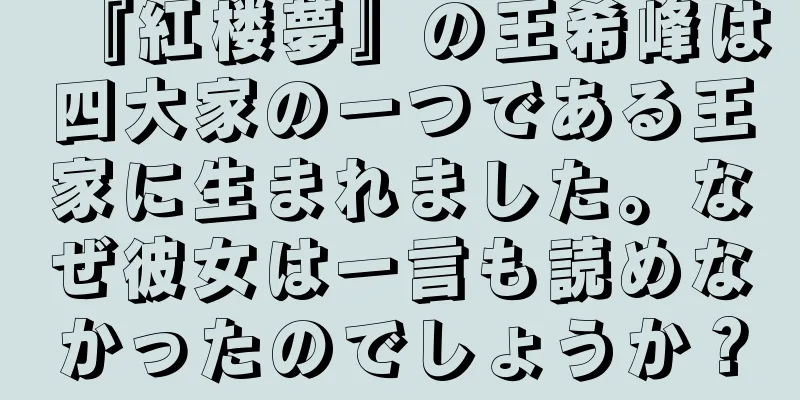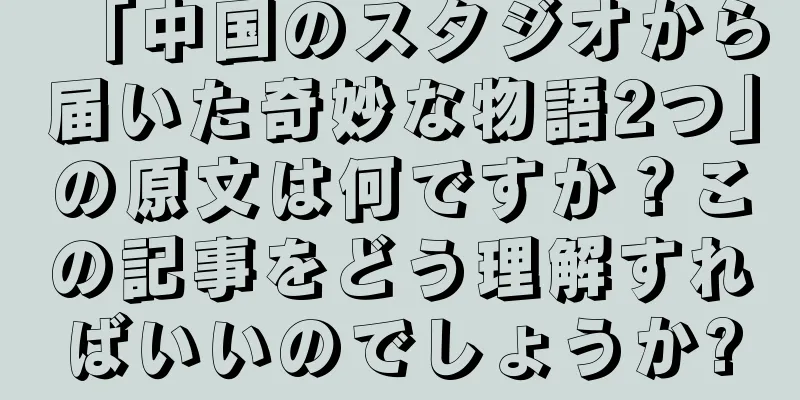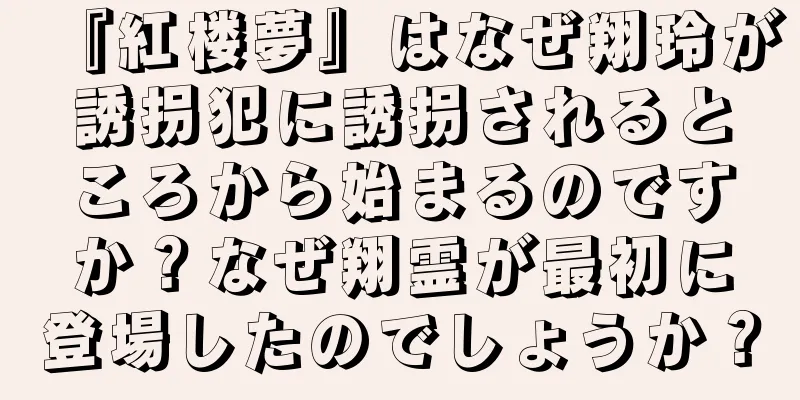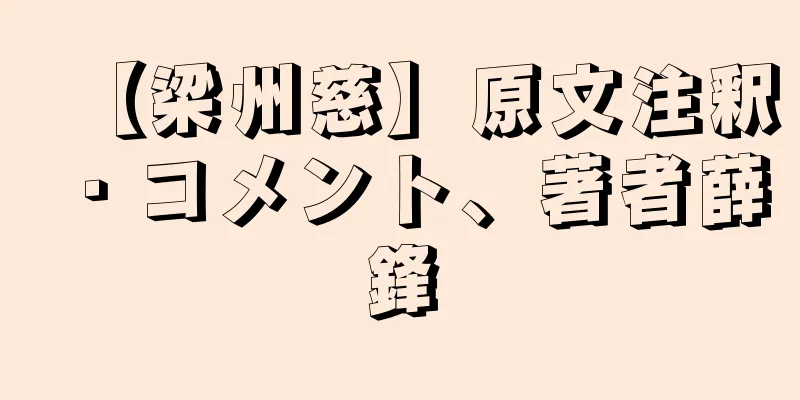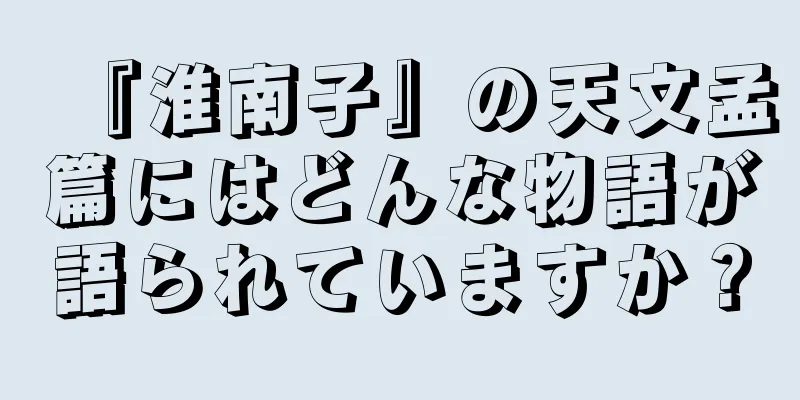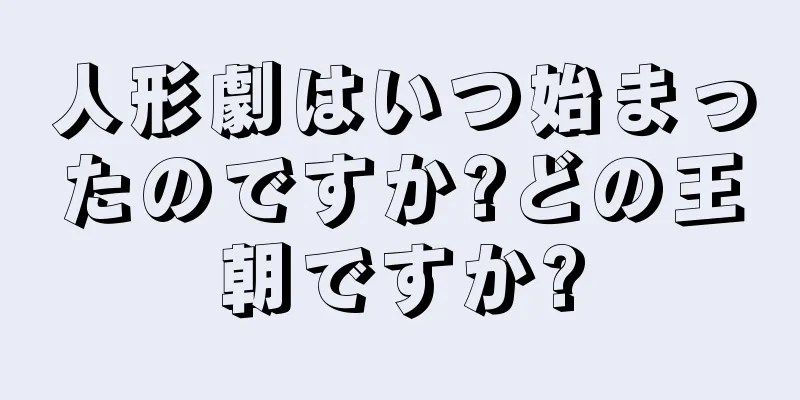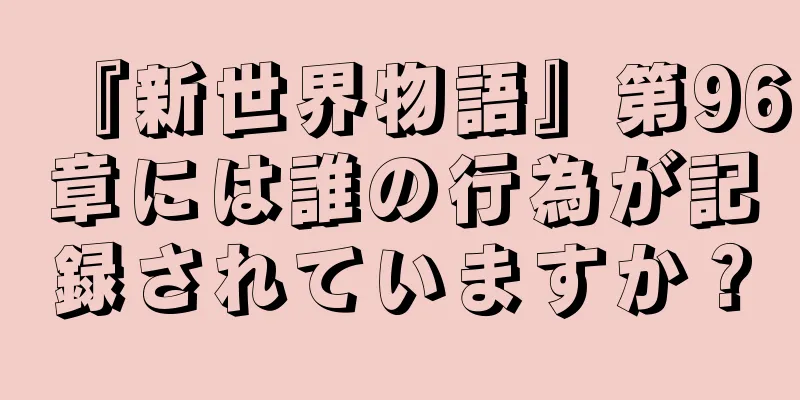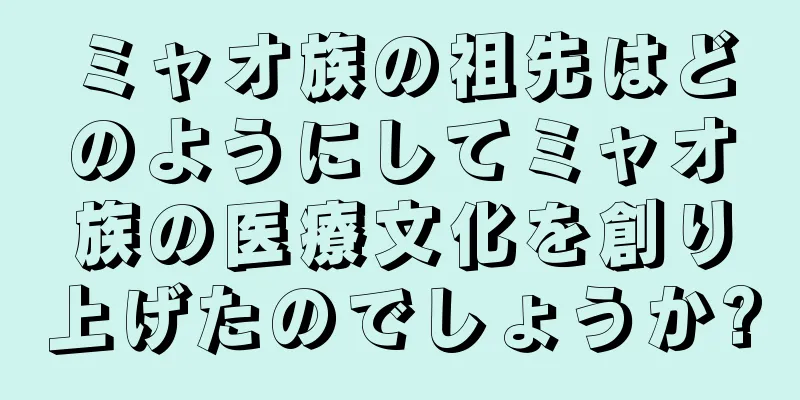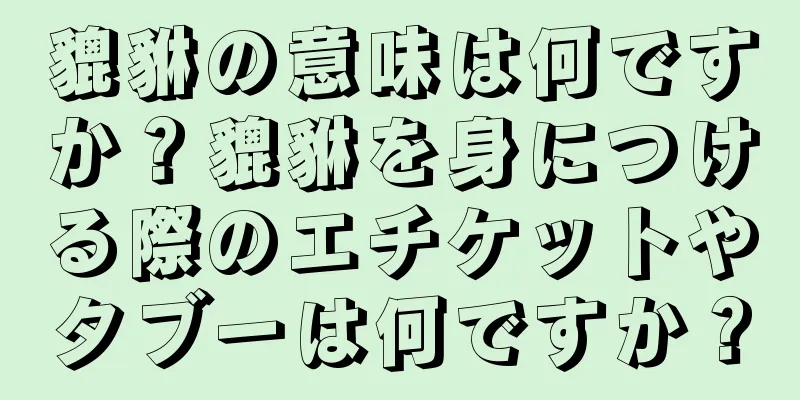朱敦如の『菜桑子・彭浪記』:詩人は時代の悲しき音を歌う
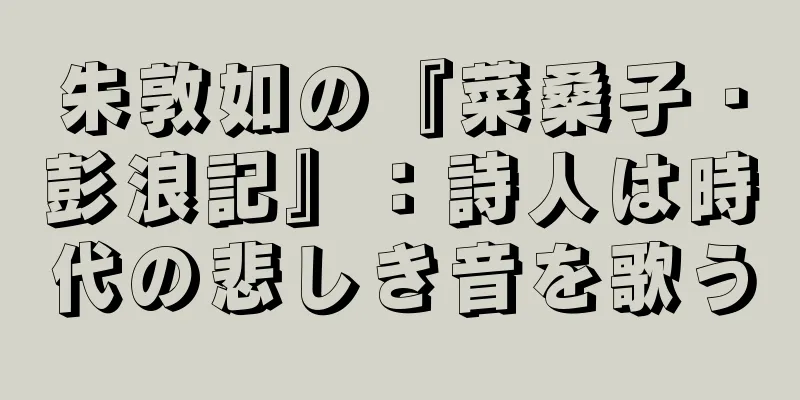
|
朱敦如(1081-1159)、号は熙珍、通称は延和、沂水老人、洛川氏としても知られる。洛陽から。陸軍省の郎中、臨安州董班、郎書記、首都官部の外連郎、良浙東路の長官を歴任し、退役後は嘉河に居住した。彼は紹興29年(1159年)に亡くなった。 「木こりの歌」と題された歌詞集は3巻ある。朱敦如は「詩の達人」として知られ、「詩の達人」陳毓易らとともに「洛陽八大師」の一人と称された(婁瑶『朱延和の鶴譜追記と陸丘詩君への送別詩』)。朱敦如は『延河老人詩随筆』を著したが、これは失われている。また、『太平樵詩』とも呼ばれる歌詞集『樵歌』があり、『宋史』第445巻に朱敦如の伝記がある。ここに9つの詩があります。それでは、次の興味深い歴史編集者が、朱敦如の『菜桑子彭郎記』をお届けしますので、見てみましょう! 蔡桑子・彭郎子 朱敦如(宋代) 私は渡り鳥や孤独な雲のように、小さな船に乗って揚子江の南へ出発します。何千マイルにも及ぶ煙と塵。中原を振り返ると、ハンカチに涙が溢れてきます。 夕方には、緑の山々がカエデの葉と葦の根とともに冷たい砂州に面します。夕焼けの波は平らです。故郷と同胞を離れるのは悲しいです。 最初の節では、詩人が故郷を離れる時、「渡り鳥や孤独な雲」のように惨めな気持ちになったと述べている。戦争で荒廃した中原を振り返り、彼は涙を流さずにはいられなかった。 最初の 2 つの文は場面を語り、著者の人生経験を表現しています。私は避難するために小船に乗って揚子江の南に向かいました。迷子になった渡り鳥と空に浮かぶ孤独な雲を見上げながら、自分の状況もまさに同じであると感じずにはいられませんでした。二つの文章は、物語性、描写性、叙情性が一つに融合しており、賦、隠喩、暗示のいずれもが含まれ、包括的かつ自然である。 「数千マイルに渡る煙と塵、涙をハンカチに溜めながら中原を振り返る」この2つの文章は、北を振り返ったときに見えるもの、感じるものを表現しています。中原が陥落したとき、すべての国民は嘆き悲しんだ。この二つの文章は、大まかな情景と悲劇的な調子で、装飾を一切せずに感情を直接的に表現しています。 2番目の節では、目の前に広がる荒涼とした秋の風景が描かれており、旅人が故郷を離れる悲しみがさらに増しています。 移行後の2行、「夕方の緑の山々は冷たい砂州に面し、カエデの葉と葦の根」は、現在の情景を思い起こさせます。夕暮れ時、私たちはサンゴ礁のそばに船を停泊させましたが、川の緑の山々は夕霧に包まれていました。サンゴ礁のそばの砂州には、まだ葦の根と落ちたカエデの葉が残っていて、荒涼とした人影のない景色でした。ここでの岩礁の秋の夕景の描写は荒涼とした陰鬱な色彩に満ちており、国が荒廃し、故郷を追われた詩人の心情を反映している。 「日が沈み、波は静まり、故郷と祖国を離れるのは悲しい」この2つの文章は、作者が故郷と祖国を離れてからの気持ちを要約したものです。日没は、旅人が故郷を懐かしむ時間であることが多い。著者のように急いで避難場所を探している旅人にとって、孤独感や寂寥感はさらに強くなることは言うまでもない。徐々に静まっていく川の波が、詩人の不安な気持ちを完璧に表現しています。 作品全体は、動きと静寂、そして暗い色調が織り交ぜられた風景を通して感情を表現しています。 「小舟」「渡り鳥」「寂しげな雲」「冷たい砂州」「紅葉と葦の根」など晩秋の代表的な風景は詩人の悲しい気持ちを強調するのに使われ、同時に国情に対する深い憂慮を明らかにし、時代の悲哀を歌い上げている。 |
<<: 朱敦如の「淮音水歌」:この詩は読むと大きな力があるようだ
推薦する
本草綱目第8巻の原文の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
もし趙雲が街庭に代わっていたら、馬蘇と同じレベルの失敗を犯すだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
偉大な書家孫国亭の書道と黄庭堅の書道のどちらが優れているでしょうか?
孫国廷は646年に浙江省阜陽で生まれました。彼は中国の歴史上有名な書家でした。書道で高い業績を残した...
漢の武帝は約 55 年間統治しました。なぜ彼は 44 年間もフン族を攻撃したのでしょうか?
諺にもあるように、遅れた者は負けるが、漢王朝は非常に強大であった。漢の武帝は、外国の侵略に一寸の領土...
『紅楼夢』に劉おばあちゃんという田舎娘が登場するのはなぜですか?
劉おばあさんは『紅楼夢』に登場する田舎のおばあさんです。今日は『おもしろ歴史』の編集者が記事をお届け...
公爵と王子の違いが分からない?王子の称号を授けられるのは誰でしょうか?
郡の王子と親戚の王子の違いが分かりませんか? 王子の称号を授けられるのは誰でしょうか? よく分からな...
千怡とは誰ですか?銭易はどんな作品を書いたのですか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が、銭易につ...
古代の人たちは、父親ほど優秀でない息子は国を滅ぼす大臣だと言ったが、それはどういう意味だったのだろうか。
晋の時代の人、蘇景(239-303)は中国史上有名な書家です。張草を得意とし、代表作に『蘇子』『草書...
『紅楼夢』で賈夫人が薛宝琴をそんなにも可愛がる本当の理由は何ですか?
『紅楼夢』に登場する宮廷商人の娘、薛宝琴は幼い頃、父親とともに様々な場所を旅した。今日は、Inter...
もし劉備が夷陵の戦いに勝利していたら、三国間の状況はどうなっていたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
東晋の葛洪著『包朴子』内章精励全文と翻訳
『包朴子』は晋の葛洪によって書かれた。包埔([bào pǔ])は道教の用語です。その由来は『老子』の...
学者第18章:クアン・アーと一緒に有名な詩人を詩の集まりに招待し、友人の書店を訪れてパン・サンに会う
『士人』は清代の作家呉敬子が書いた小説で、全56章から成り、様々な人々が「名声、富、名誉」に対してど...
『紅楼夢』で苗豫が劉おばあさんと宝豫に対して全く異なる態度をとるのはなぜですか?
『紅楼夢』で、苗嶼はなぜ劉おばあさんと宝嶼に対して全く異なる態度をとっているのでしょうか?今日は、興...
劉 璋【長門元】著者紹介と作品鑑賞
長門の訴え(第1部)劉 璋秋の長い夜、長門に雨粒が落ち、悲しい心と雨が昭陽に届く。あなたの優しさのた...
古代の監獄が天空の監獄と地下の監獄に分かれていたのはなぜですか?そこにはどんな囚人が収容されているのですか?
監獄の概念には長い歴史があります。この道具の最も古い登場は夏王朝でした。当時は「夏台」または「元」と...