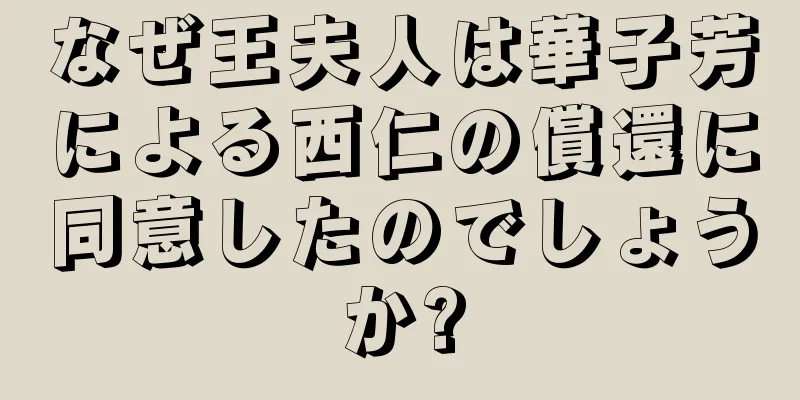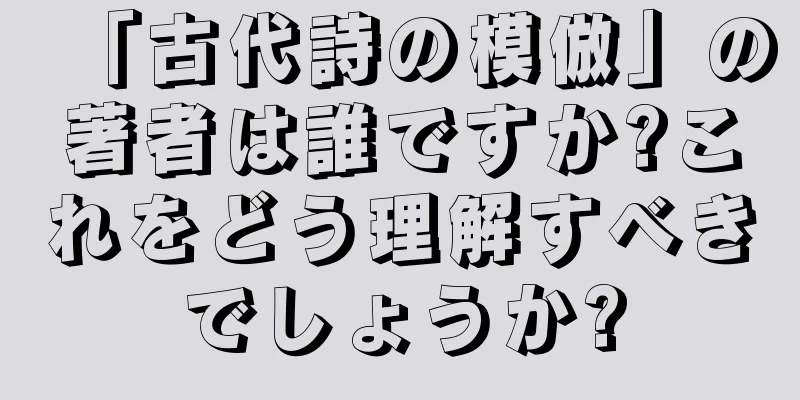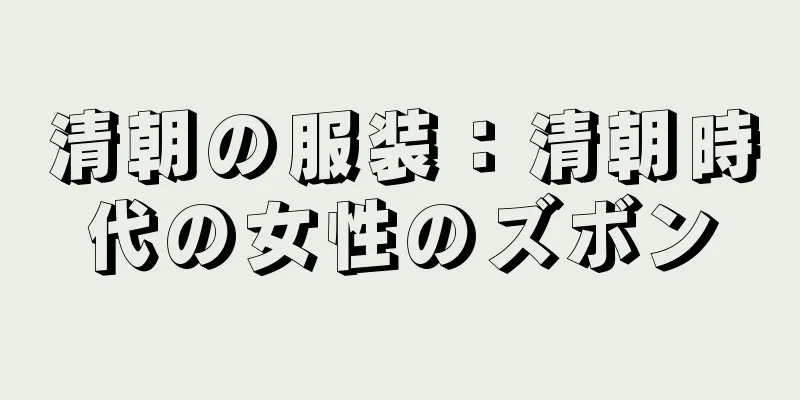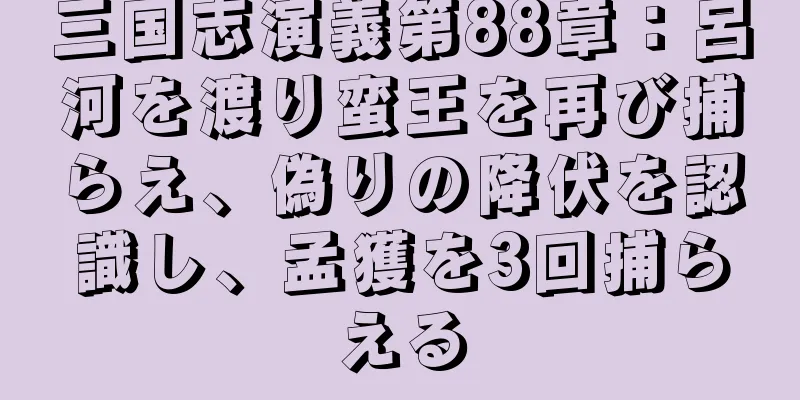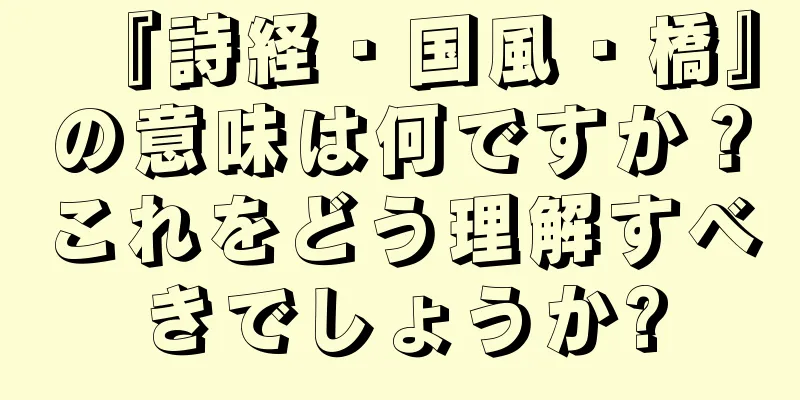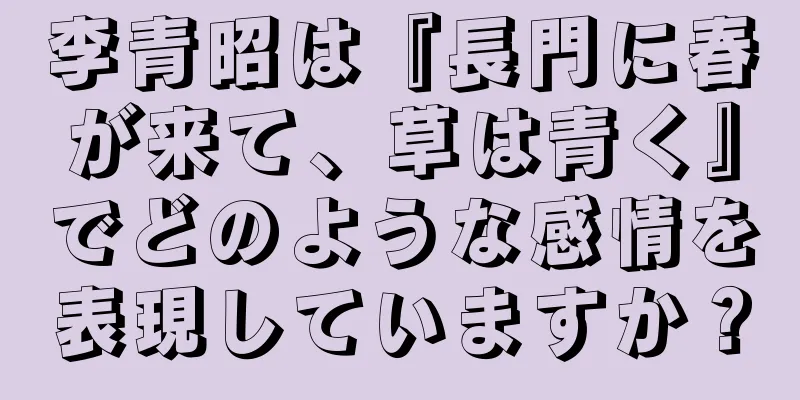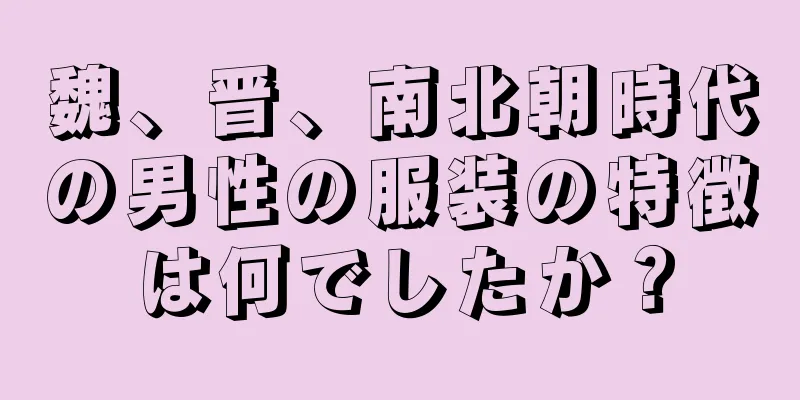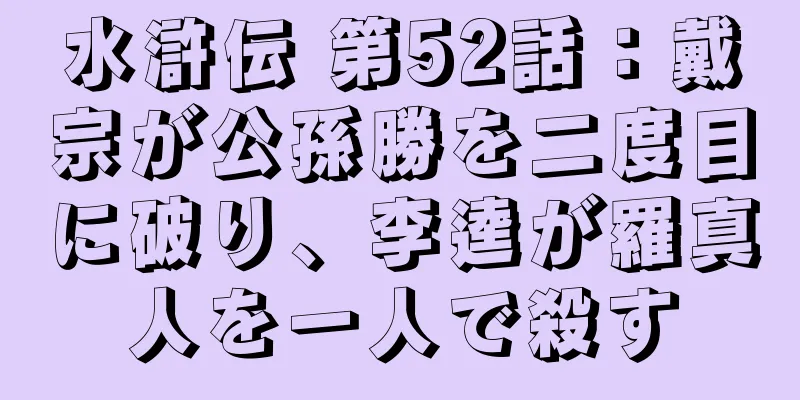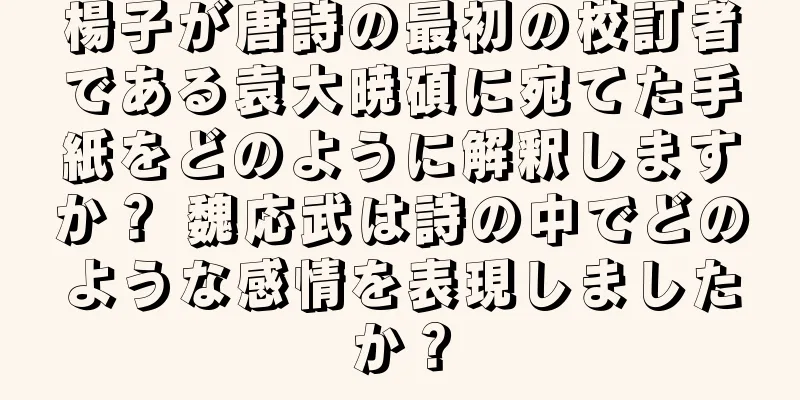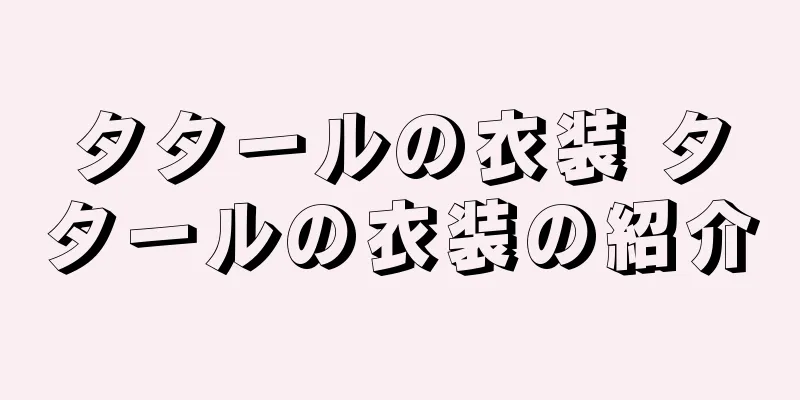徐在思の「東風に酔う:溪寨の竹画」:形、色、香りの感覚的楽しみの組み合わせ
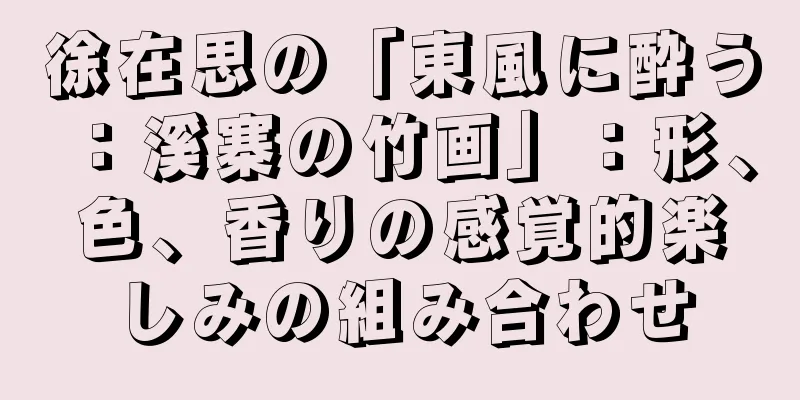
|
徐在思(1320年頃生きた)は元代の紀書家である。彼の礼儀名は徳科であり、かつて嘉興の役人を務めていた。彼は甘いものを食べるのが好きだったので、天寨と呼ばれました。彼は浙江省嘉興市出身です。生没年は不明。関雲師と同時代人。約100編の短い歌が現存する。彼の作品は、当時は算斎と名乗っていた関雲石の作品と同じく有名で、「酸甘月譜」として知られています。その後、任娜は2人の曲を1つにまとめ、103曲の短い歌を収録した「甘酸っぱい月譜」をリリースした。それでは、次の興味深い歴史編集者が徐在思の『東風に酔う・西寨竹画』をご紹介します。見てみましょう! 東風に酔う · 西寨竹画 徐在思(元代) ゲピ山には神龍が幸せに佇み、紅山には色鮮やかな鳳凰が休息しています。風が花鞘の香りを吹き、雨が苔を冷たく洗い流し、仙人の筆の下で春が生き生きと訪れる。明るい月がバルコニーに輝き、私は酔いから半分目覚め、小湘の緑の影を見つめていた。 この記事のタイトルは「西寨の竹画」だが、著者は竹の絵の上手さについては直接言及していない。その代わり、まずは2つの伝説的な暗示を巧みに用いている。1つは、東漢の仙人である費長芳が青竹の棒を投げて龍に変身したという話だ。作者は絵の中の竹を「脱皮した龍」に例えており、竹がいかに力強く生き生きしているかを示している。 2つ目は、鳳凰が竹を食べるという話です。 「丹山」は鳳凰の巣で、鳳凰は竹の実以外は食べません。今、鳳凰は描かれた竹に誘われて「庭に巣を作る」ために飛んでいます。李厳が描いたのは壁画だったことがわかります。 「神龍」と「色とりどりの鳳凰」は見事に対照的である。その美しさは、前者が竹画そのものの比喩であるのに対し、後者は作者が竹画を見た後に思いついた独特の連想である点である。この二つの文章はどちらも神話や伝説を用いており、作者はそれを自分の気持ちとして引用し、実は李厳が仙界の仙境で不朽の名作を描いたことを賞賛している。 3 番目と 4 番目の文では、画像の内容がさらに詳しく説明されています。李厳の竹画では、中央に新しい竹が点在し、竹の先端が「粉状の鞘」から現れ、竹の下には苔が点在している。竹皮に細かい粉を塗るだけでも十分驚きです。その鮮やかさは言うまでもなく、そよ風が吹くと香りが漂ってくるようです。苔は濃い緑色で、色を混ぜるのは簡単ではありませんが、不思議なのは、絵の中の苔がまるで雨に洗われたかのように「冷たい」感じを与えることです。この二つの文章は芸術的美学の連想を全面的に動員し、形、色、香り、感触の感覚的楽しみを一体化し、「西寨画竹」の風貌と気質を生き生きと再現している。もし作者が「老仙人の筆の下に春が生まれる」という一文を加えていなかったら、人々はおそらくそれを本物の竹の茂みと間違えただろう。 最後の 2 つの文は、「西寨の竹を描く」という全体的な効果を示しています。李厳が壁に描いたこの傑作は、庭に植えられた青竹の塊のようで、月と酒にぴったりで、まるで小湘地域の自然の美しさの中にいるような気分にさせてくれます。この二つの文章は詩情と絵画的な雰囲気に満ちており、欠けていく月、酔い、霞んだ湘江など、霞んだ美しさに満ちた風景を背景に、絵画の優美な精神を表現しています。 「竹を描く」という言葉は記事全体には出てきませんが、すべての文章が主題に沿っています。文章による判断はなく、代わりに一連の画像を使用して最良の説明が提供されています。 |
<<: 徐在思の「西湖」は、小さくて精巧ではなく、パノラマ的で遠景が中心です。
>>: 喬記の「手すりに寄りかかる:金陵への道」:鳥に劣る旅人であることの悲しみを表現する
推薦する
『紅楼夢』で秦克清の死後すぐに亡くなったのは誰ですか?意味は何ですか
秦克清は『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人である。これに非常に興味がある人のために、In...
唐代の李世民著『帝典』の内容を簡単に紹介します。『帝典』はいつ書かれたのでしょうか?
「皇帝のモデル」は政治に関する古代の著作です。唐代の李世民によって書かれた。この本は唐の太宗李世民が...
ワニドラゴンとミラージュドラゴンとは何ですか?クロコダイルドラゴンとミラージュドラゴンの違いは何ですか?
ワニドラゴンとミラージュドラゴンの違いは何でしょうか?次のInteresting History編集...
陳子昂の『春夜別れ二詩一』の原文は何ですか?どう理解すればいいですか?
陳子昂の『春夜別れ二句一』の原文は何ですか? どのように理解しますか? これは多くの読者が関心を持っ...
古典文学の傑作『前漢演義』第78章:漢王の軍が城澳から出撃
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣批判東西漢通志演義』というタイトルで、明代の中山の...
宝玉の絶え間ないからかいに直面して、金川児は返事をするのが面倒でした。なぜ王夫人は怒っていたのでしょうか?
宝玉の絶え間ないからかいに直面して、金川児は返事をするのが面倒でした。なぜ王夫人は怒ったのですか?こ...
『歓楽雨亭』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
歓楽雨亭蘇軾(宋代)このパビリオンは喜びを表す雨にちなんで名付けられました。古代では、人々は幸せなと...
『太平広記』第480巻「夷狄」にはどんな登場人物がいますか?
ニザ国、ランキウルフ国、フゼ国、ピンシウミン国、ヌマン国、ドゥボ古里突厥族、吐蕃族、中国北西部、鶴人...
デアン族にとってお茶はどんな特別な意味を持つのでしょうか?デアン族のお茶文化!
デアン族にとってお茶はどんな特別な意味を持っているのでしょうか?デアン族のお茶文化!これが皆様のお役...
雍正帝の五男、洪周の紹介 愛心覚羅洪周はどのように亡くなったのか
愛新覚羅洪州(1712年1月5日 - 1770年9月2日)は、雍正帝の5番目の息子で、康熙帝の治世5...
「彭公事件」第95話:徐光志が泥棒を侮辱し、強盗を叱責し、高通海が死を免れて生き返る
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
李青昭の「漁師の誇り:空は雲と朝霧につながる」:ロマンチックな雰囲気に満ちている
李清昭(1084年3月13日 - 1155年)は、易安居士とも呼ばれ、宋代の斉州章丘(現在の山東省章...
歴史上、この人物は三度の朱家荘攻撃で多大な貢献をしたが、結末は悲痛なものでした。
この男は何度も不審な点を発見したが、やはり悲劇的な死を遂げた。梁山は朱家荘に二度敗北していたが、孫礼...
千家学校とは何ですか?千家学派の代表的人物は誰ですか?
千家学派は、清朝の乾隆・嘉慶年間に思想と学問の分野で生まれた学派で、文献研究に重点を置いていました。...
劉宗元の「初春の農民との出会い」:詩全体は、彼が早春の外出中に見たものや感じたものを表現している。
劉宗元(773年 - 819年11月28日)は、字を子侯といい、河東(現在の山西省運城市永済)出身の...