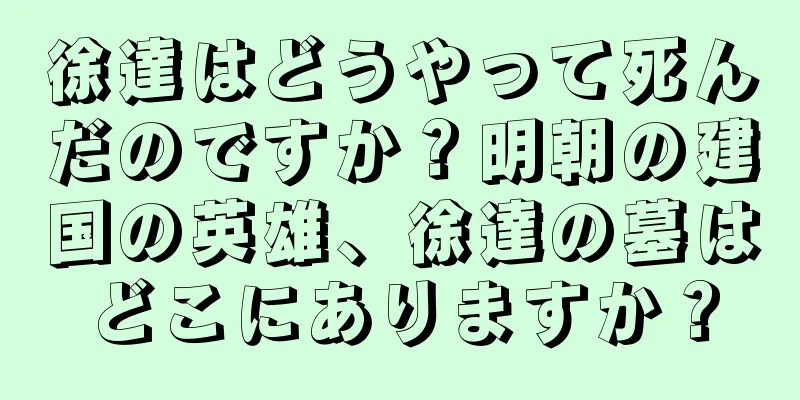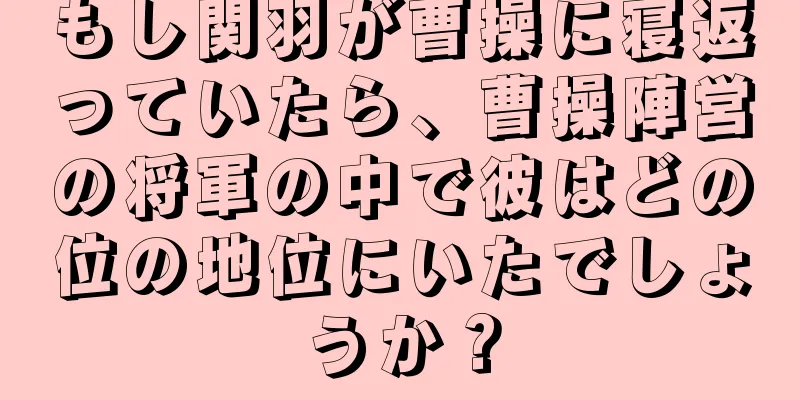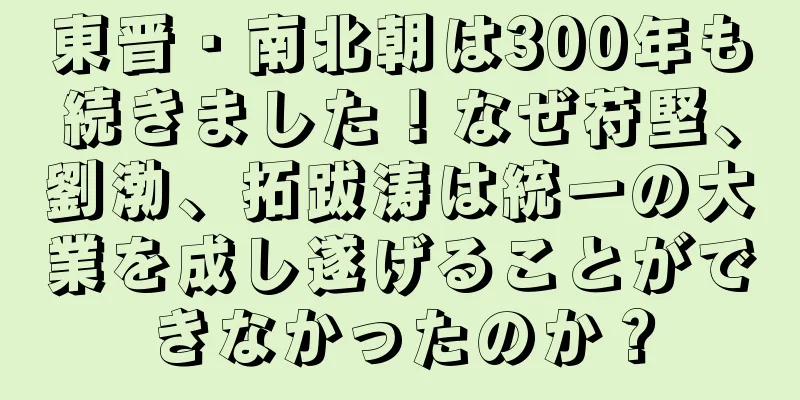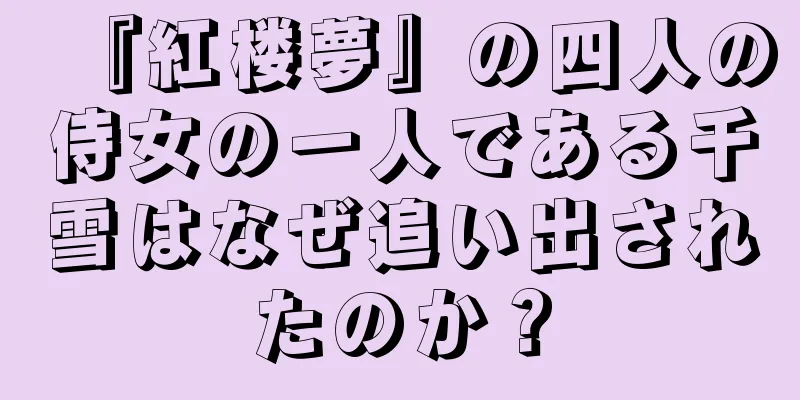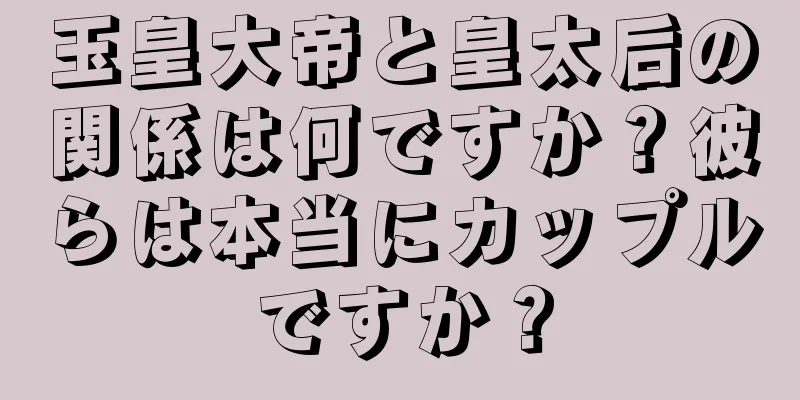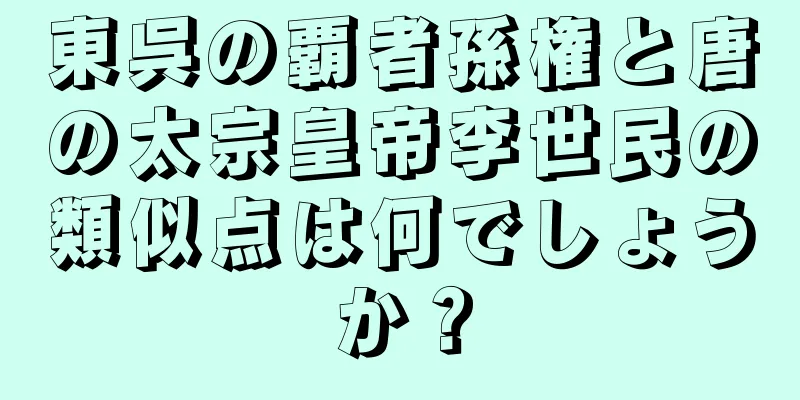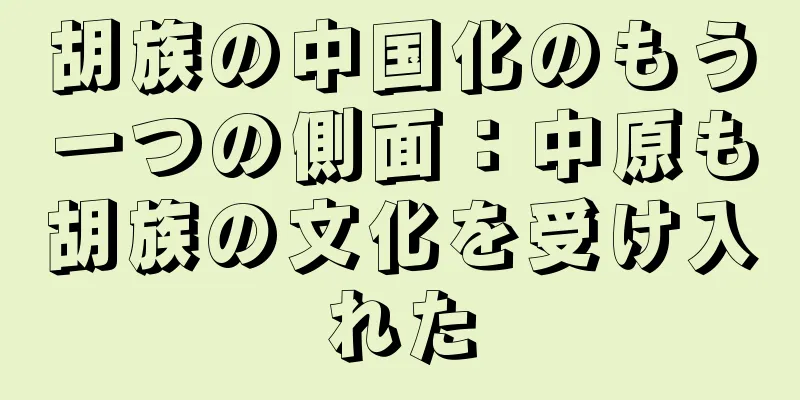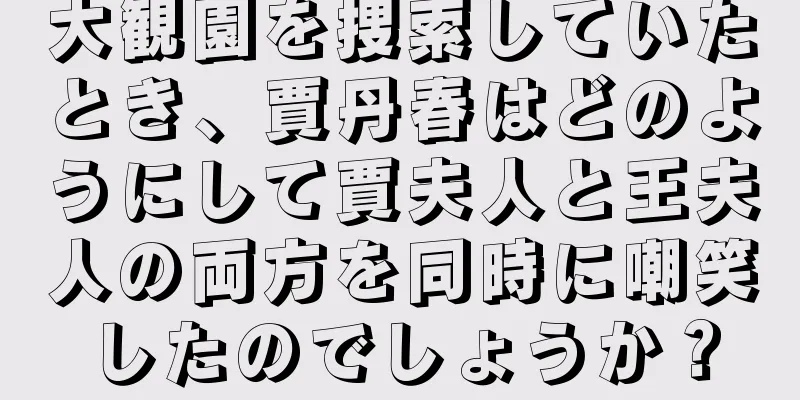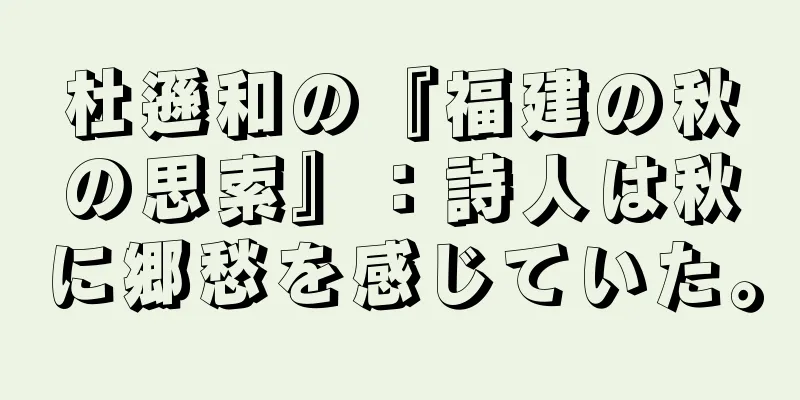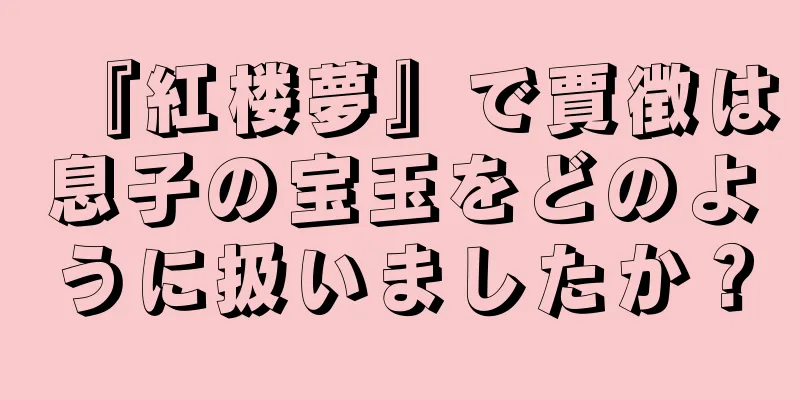于子之の有名な詩行の鑑賞:通りすがりの人は王子が去るのを落胆して見、金のかんざしの十二の悲しみを買い取る
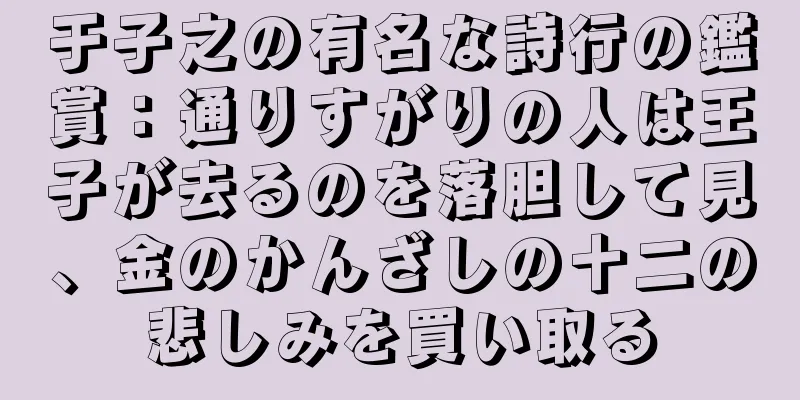
|
于子之(?~1086)、号は秀老とも呼ばれる。彼は金華(現在の浙江省)の出身で、揚州(現在の江蘇省)に住んでいました。彼は若い頃から高潔な性格の持ち主でした。敬虔な仏教徒で、仏教の教えを学びました。結婚もせず、公職に就くこともありませんでした。王安石は晩年、江寧(現在の江蘇省南京)に住んでいた。于子之と弟の于子忠(号は青老)は王安石に同行し、高く評価されていた。王安石は晩年に多くの優れた客人を迎えたと主張しており(李知義『于秀老の詩を書いてから』)、于兄弟はその代表であった。それでは、次の興味深い歴史編集者が、于子之の「草詩」をお届けします。見てみましょう! フェリーから見える景色は緑がいっぱいで、悩みを忘れさせてくれるものがあるのかな? パビリオンに流れ込む緑の水を追い、遠くの島に沈む太陽を運びます。 荒涼とした神宮庭園には月が映り、石の都の下には秋の緑が続く。 旅人は王子が去っていくのを落胆して見つめ、12の悲しみとともに金のかんざしを買い戻しました。 【注意事項】 ①千千、青々とした草の様相。 ②もし、どれか。 ③ホテル、ヴィラを出発します。 ④金の時代の富豪、石充の別荘、金谷園。趙王倫は孫秀を遣わして趙王倫の家を襲撃させ、趙王倫を殺させ、また趙王倫の愛妾である陸珠を捕らえさせた。陸珠は拒否し、倒れて死んだ。 ⑤王孫(おうそん)は古代の貴族の別名。 ⑥ 12個の金のかんざしは美しい女性を表します。 【感謝】 この詩は「草への頌歌」と題されていますが、実際には草について書かれたものではありません。草を使って感情を表現しているだけです。発想がユニークで、独特の味わいのある詩です。 古代の詩人たちは、別れの気持ちや別離の悲しみを表現するために草書をよく使用しました。白居易の「草には別れの気持ちが満ちている」はその典型的な例です。 この詩の最初の連句は、魏英武の『滁州西渓』の「渓畔に生える草を哀れむ」と「荒々しい渡し場で船がひとり漂う」という最初の行と最後の行を組み合わせたものと思われる。この状況に直面して、詩人は「悩みを忘れる方法は誰か知っているが、答えはないようだ」という奇妙な疑問を提起した。実際、答えは必要ではなく、「草」である。 二連句は「遠き香は古路を侵し、澄んだ緑は廃城に繋がる」と意味が似ているが、白居易の二連句よりも文章が優れている。「緑の水」と「斜陽」はより具体的であるだけでなく、より鮮明なイメージでもある。「従う」と「導く」という二つの動詞も「侵す」と「繋ぐ」よりも優れており、より擬人化され、より躍動感がある。 二番目の連句は反転しており、「草」に別の感じを与えています。神宮の庭では、「流れる水は容赦なく、春には草が生える」は、「神宮の建物から落ちた人を哀れんでいる」のでしょうか?石城の下では、「冷たい煙と枯れた草だけが青々としている」は、「月明かりの下で故郷を振り返るのは耐え難い」のでしょうか?ここで、「草」には、「国が滅び、家族が破滅したとき、どこへ行くのか」という無限の憂鬱があります。草は強靭な生命力を持ち、「山火事にも焼かれず、春風に吹かれてまた生える」が、死んだ人々や荒廃した国は決して再生し再建することはできない。 最後は気持ちを繋ぐ。詩人は「王子は旅に出て二度と帰らず、春の草は青々と茂る」と憂鬱に世の中を眺め、ずっと前に「灰になってしまった」富豪の石充や「跡形もなく死んでしまった」絶世の美女の陸珠を思い浮かべた。詩人は「人生は短く、秋の枯れのように」という終わりのない感情を感じずにはいられなかった。しかし、もっと深く考えてみると、人は草ほど良い存在ではない。名声、富、栄光、名誉はすべて捨て去ることができる。そう思うと、詩人の心はだんだんと落ち着いてきました。 |
<<: 呉文英の有名な詩の鑑賞:私はその時ザクロのスカートについて書き、赤い紗の花びらが色あせてしまったことを悲しく思いました
>>: 蒋魁の有名な詩句を鑑賞する:文君のことを思いながら、私は長い間彼女を眺め、竹に寄りかかり、心配し、絹の靴下を履いて歩いていた
推薦する
漢中の戦いの後、張飛が戦闘に参加したという記録がないのはなぜですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
紅楼夢で青文と宝玉が最後に会ったのはいつですか?どうしたの?
賈宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公です。多くの人が理解していないので、Interesting ...
秦の始皇帝はなぜ黒龍のローブを着ていたのでしょうか?皇帝の龍のローブには他にどんな色がありますか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が秦の始皇帝の...
孫子の兵法三十六策にある「桑の木を指差して槐の木を呪う」の簡単な紹介。これはどの物語から来ているのでしょうか?
今日は、おもしろ歴史の編集者が「桑の木を指差して槐の木を呪う三十六計」についての記事をお届けします。...
黛玉は青文の死後どのように反応しましたか?本当に全然悲しくないんですか?
以下は、清文の死後、黛玉がどのように行動したかについての興味深い歴史の編集者による物語です。興味のあ...
北宋時代の詩人、顔継道の詩「庭に苔が生い茂り、紅葉が茂る」を鑑賞
以下、面吉道の『庭に苔が生い茂り、紅葉が生い茂る』の原文と感想を『面吉道』編集者が紹介します。興味の...
諸葛亮はなぜ、より英雄的な曹操ではなく劉備に加わることを主張したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
中華民族の祖先である黄帝の物語
黄帝は古代中国の部族連合のリーダーでした。彼は少典と幽丘の息子でした。彼の姓は公孫でしたが、冀河で生...
『新雁又更衣室行来夢想ハイビスカス』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
新ガチョウの通過化粧室·夢からの目覚め呉文英(宋代)ハイビスカスの目覚めの夢。軒先を風が吹き抜け、東...
唐代の重要な軍事書『太白印経』全文:雑儀と配置
『神機滅敵』は『太白陰経』とも呼ばれ、道教の著作です。古代中国では太白星は殺生の達人であると信じられ...
ゴールデンホーン王とシルバーホーン王の関係は何ですか?彼から隠された秘密は何だったのでしょうか?
平頂山の蓮洞の戦いは、『西遊記』に登場する数少ない「24時間戦闘」のひとつです。著者は、土師宮の炉を...
薛定山の西征 第17章:薛定山は宝物を携えて山を下り、劉夫人と息子は再会する
清代の在家仏教徒である如廉が書いた小説『薛家将軍』は、薛仁貴とその子孫の物語を主に語る小説と物語のシ...
穆万卿の父親は誰ですか?穆万卿の父、段正春の簡単な紹介
段正春は、金庸の武侠小説『半神半魔』の登場人物。主人公段羽の養父であり、北宋大理国の鎮南王道百峰の夫...
『史記』第1巻 五帝の年代記
黄帝は少典の息子で、姓は公孫、名は玄元といった。神の精神を持って生まれ、弱いときは話すことができ、若...
済公伝第240章:雷塵は善良な済公を救うよう命じられ、景慈に戻った。
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...