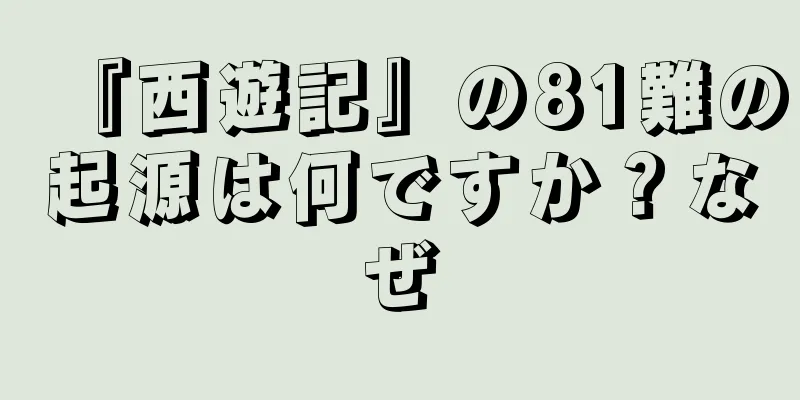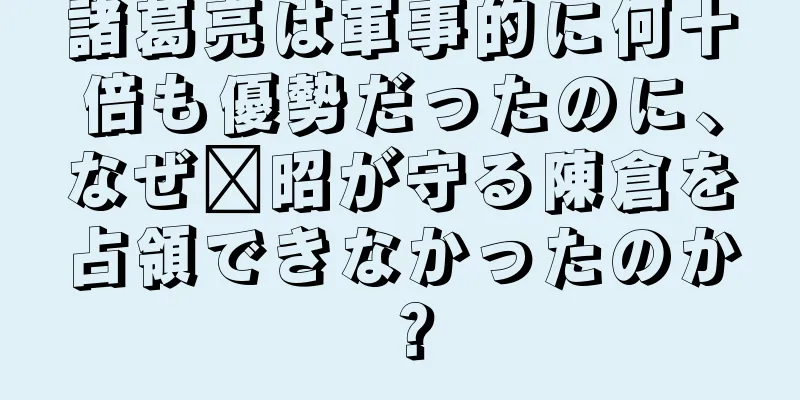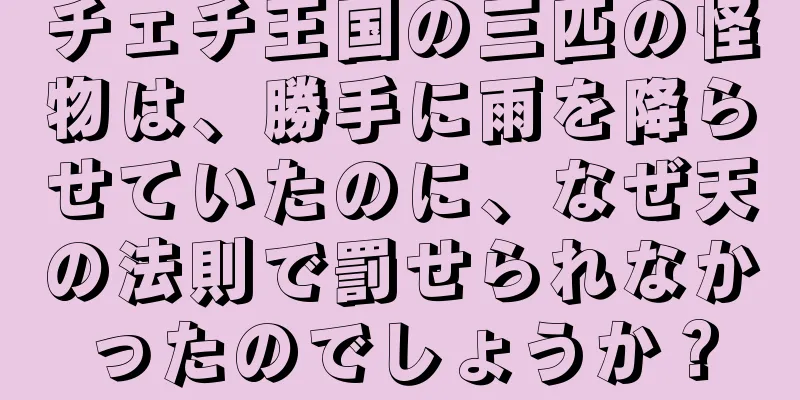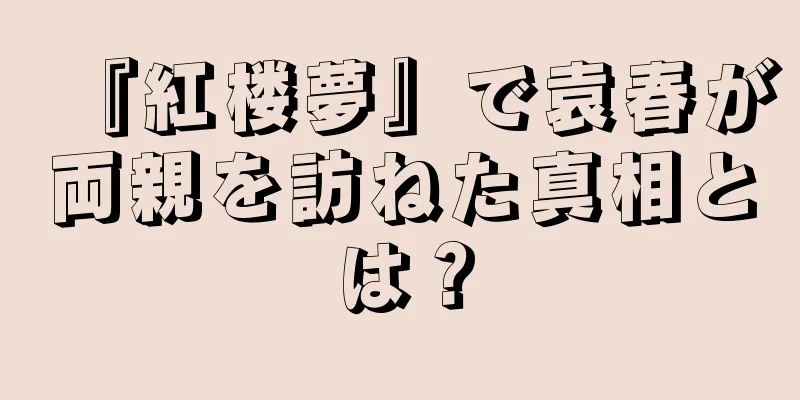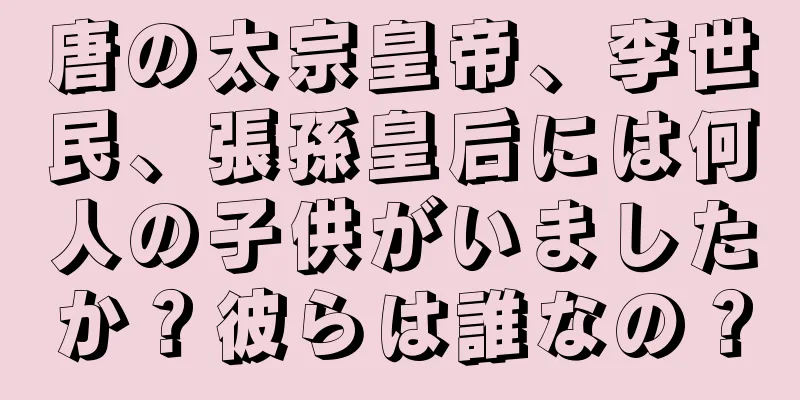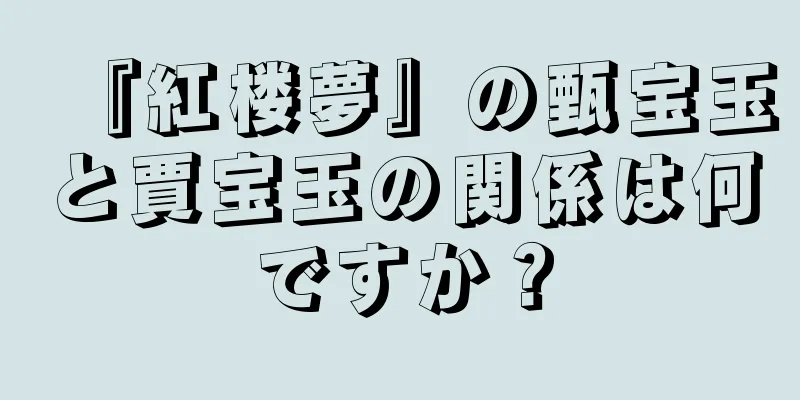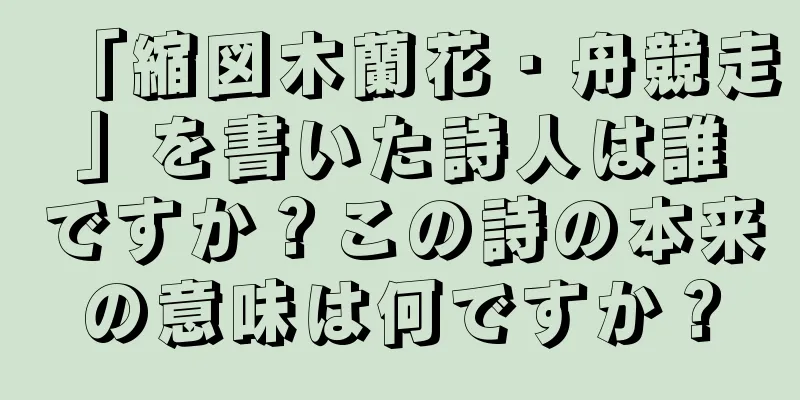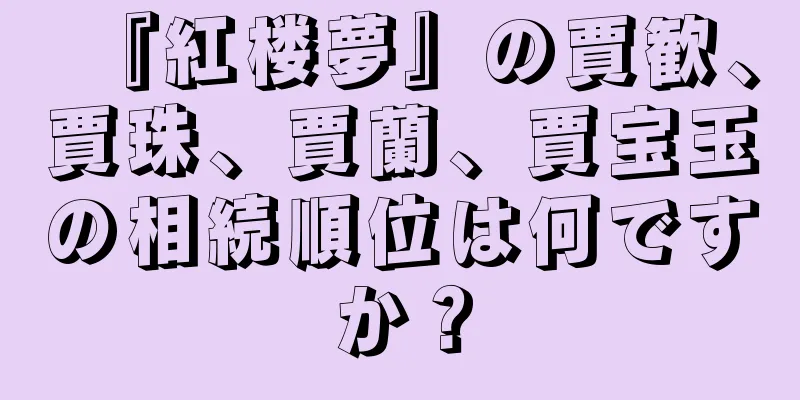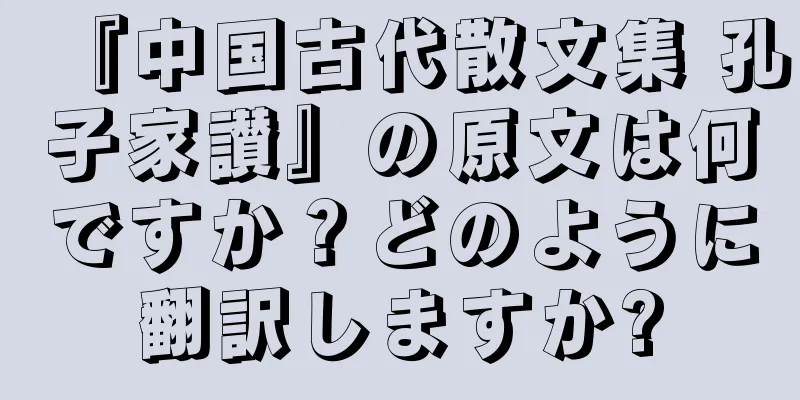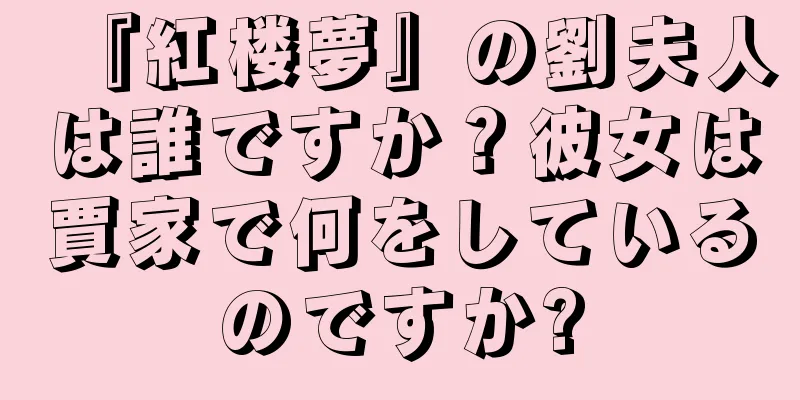王維の有名な詩句の鑑賞:私の考えをどこに送ればよいのか?南風が五梁を揺らす
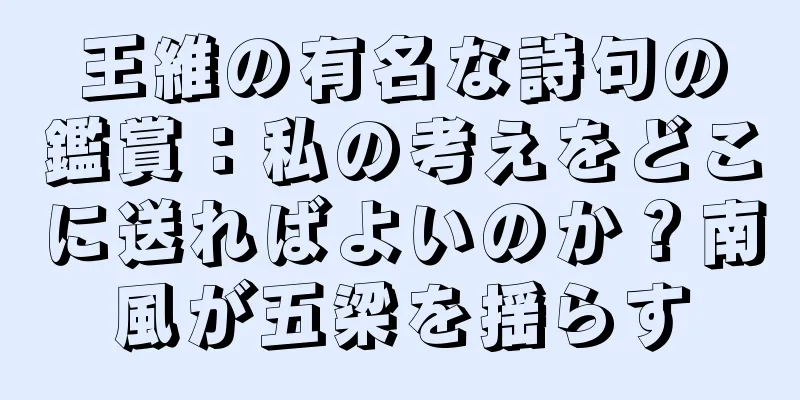
|
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先の故郷は山西省斉県であった。唐代の詩人、画家。王維は禅を修行して悟りを開き、詩、書、音楽、絵画に秀でていた。開元・天宝期の詩作で名声を博し、特に五音詩に優れ、その多くは山水や田園を歌ったものであった。孟浩然とともに「王孟」と呼ばれた。仏教に深く帰依していたため、「詩仏」と呼ばれた。 彼の書と絵画は特に優れており、後世の人々は彼を南派山水画の創始者とみなしました。 『王有成全集』や『画秘』などを著し、約400編の詩を残している。北宋の蘇軾は「王維の詩を味わえば、詩の中に絵がある。王維の絵を見れば、絵の中に詩がある」と評した。そこで、次の興味深い歴史編集者が王維の「宇文太守を宣城に送る」を紹介するので、見てみましょう! 遠くの船上からは雲の向こうの寂しい山々を眺めることもできます。 西河にシンバルが鳴り響き、秋の空は澄んだ音色で満たされます。 古代都市は遠く離れて草木が生い茂り、月は明るく、冷たい潮が広がっています。 その時、彼は景亭神と競って漁網を解いた。 どこに思いを寄せればいいのか。南風が五両の金を揺らしている。 【注意事項】 ①宇文:王族の姓「宇文」から取った複合姓。 ②寂しい:寂しい;寒くて寂しい。 唐元珍の詩『宮殿』には、「古宮は荒れ果て、宮の花は寂しく赤い」とある。 条地:遠い姿。 南宋時代の顔延之の『秋胡詩』には「旅人は遠く、年月は過ぎていく」とある。ある本では「朝瑶」という表現が使われている。 袁公天廷の『范章鶏粟』第二幕:「道は長くて塞がれ、山は遠くて近く、水は重なり合っている。」 「遥遰」とも書く。 「遥逓」とも表記される。 「tiaodi」とも表記される。 ③シンバルを吹く:シンバル、つまりシンバルソング。軍楽。プロパガンダ音楽の一部。シンバルを吹くということは、シンバルの曲を演奏することを指します。梁の建文帝は詩『興業寺朝講』の中で「羽旗は影を運び去り、鐃音は乱れて風に帰る」と詠んでいる。 西江:長江の西側を指します。安徽省では長江が北東に斜めに流れており、この部分が東西左右を決める基準となっている。襄陽はその西側にあるため、西江と呼ばれています。 クリアなサウンド:鮮明なサウンド。唐孟浩然の詩「夏南亭心大想」には、「蓮の風は香りを運び、竹の露は澄んだ音を立てる」とある。 ④土地は広大です。広大とは遠いという意味です。場所が全く違います。清朝の洪良基は著書『地平篇』の中で「天は高く、地は広大である」と記している。 呉:畑は不毛で雑草が生い茂っています。 寒波:寒流。 ⑤ 景亭神:景亭の詩に祀られている神は非常に効果的です。 『太平広記』にはこうある。「景亭神は国の民衆によって崇拝されている。毎年、高貴な者も卑しい者も、必ず彼を崇拝しなければならない。その他の祈りや感謝は決して無駄にならない。だから、誠実な官吏は常に準備を整えている。 お寺に敬意を表します。桂はその頃から病気を患っていたが、秋に回復したので寺を訪れた。 ” 漁師:漁師。 ⑥南風:「王維実録」には、開元28年に王維が41歳で宮廷検閲官に転じたとも記されている。その冬、彼は南の知事に任命され、長安から襄陽、汀州、下口を経由して嶺南に向かった。だから「南風」ということわざがあるのです。 五梁:「五緉」とも表記される。古代の風速計。風向や風力を観察するために、5~8両の鶏の羽を高い棒の先端に結び付けます。 「選択された文献・グオプル」:李シャンのメモを見てください。アンギュ島の詩「Yiyang川を下るボートでShiyuに代わって手紙を書く」:「東風は帆でいっぱいです・Lu Xun」:「彼らのロケットは近くに飛んだ。 【感謝】 740年(唐代開元28年10月初旬)、当時皇帝の検閲官であった王維は、長安から「南方の兵を選抜する」よう命じられました。その時、襄陽を通過し、「漢河に浮かぶ」、「孟浩然を悼む」などの詩を書きました。彼は下口(湖北省武漢市)を通って南下し、「宇文督を宣城に送る」、「康督を送る」、「馮督を送る」などの五字古詩を書きました。その詩は船の航路に沿って書かれた。 最初の4行は逆さまに書かれており、実際には「西江に鐵が鳴り、秋の空は澄んだ音で満たされている。遠くの船からは雲の向こうの寂しい山々を眺めることができる。」とすべきです。詩人の船は西江から出航し、秋の空は澄んだ音を立てました。雲山山脈の外はなんと荒涼として静かなことだろう。詩人は船から遠く離れたところから両岸を眺め、自然の景色を賞賛した。铙吹とは、王維らを見送る際にシンバルや歌を演奏することを指します。遠い、遥かに。当時の『王維紀』にはこう記されている。「王維は…宮中の帝監に異動になった。その冬、長安から襄陽、汀州、下口を経て嶺南に至る南選に任命された。」 次の4行、「地は遠く、古城は草木に覆われ、月は明るく、冷たい潮は広い。景亭神と競い、漁師の網を解く時だ」は、宣城の境界に近い下口に到着した詩人が見たもの、考えたことを表現している。私が見たのは、廃墟となった古城、明るい月、冷たい波でした。宇文太守が宣城に行けば、宣城はうまく治められるだろうと、私は思いました。王維は、州知事宇文を景亭神よりも効力のある人物に例えました。景亭神は景亭の詩の中で崇拝されている神である。太平広記によると、「景亭神は国の民衆によって厳格に崇拝されている。毎年、高貴な者も卑しい者も、彼に犠牲を捧げなければならない。他の祈りと感謝は毎日行われる。そのため、正直な役人はいつも儀式を準備して彼に敬意を表す。桂聡は当時病気で、秋に回復したので、寺に敬意を表した。」歴史の記録によると、当時宣城は5年間干ばつに見舞われており、実際に地元の農民の中には洞窟に逃げて集まった人もいました。国民は貧富の差があり、状況も大きく異なるため、有能な知事が早急に必要である。劉玉熙は「南の知識」であったため、王維は宇文を宣城の太守に選び、自信に満ち、大きな期待を寄せていた。詩人は続けて、宇文太守の到着は漁師の絡まった網を解くのを手伝うようなものだと述べた。事実が証明しているように、宇文太守は宣城に到着した後、秩序正しく宣城を統治し、民衆に愛され、すぐに秩序が回復されました。 最後の二行「私の思いをどこに送るか、南風が五両の金を揺らす」は、詩人が宇文大将に憧れ、彼との友情を表明していることを表現している。詩人は宇文太守を見送った後、嶺南へ引き返した。道中、南風がそっと吹いていた。劉玉曦は、宇文太守と過ごした日々を今でも思い出し、忘れることができなかった。詩人は自分自身に問いかけ、こう答えた。「私の思いをどこに送ればいいのか。南風が五両の銀を揺らす。」ここでの「思い」は「行方不明」という意味です。 5タエルは2個で1組になることを意味します。 『詩経・斉風・南山』:「麻の草履の重さは五両、帽子とリボンは両端が二つ。」朱熹の詩集:「両は二足の靴を意味する。」王夫之の注釈:「これによると、『五』は『五』と同じで、列を意味する。靴を並べるときは、必ず二足が一列に並んでいる。」作者はこの比喩を借りて、友人への思いを表現した。 王維の詩業は多岐にわたり、辺境詩、山水詩、律動詩、四行詩など、広く流布している傑作が数多くある。この詩は友人への別れの詩として書かれたものです。風景はさりげなく取り上げられ、遠くの景色は自明であり、感情は風景を通して表現され、風景によって引き立てられています。この詩は暗示を用いて詩人の本心を率直に表現しており、素朴で奥深い美しさがあり、詩人自身の苦しみも表している。 |
<<: 王漢の有名な詩句を鑑賞する:夜に胡家が柳を折る音を聞くと、人々は長安を懐かしむ
>>: 周密の有名な詩の一節を鑑賞する: 客は商の詩を朗読したいが、まだ恐れている。恨みの長い歌、壊れた翡翠の壺
推薦する
歴史上の反逆王、李自成は病死したのか、それとも殺害されたのか?
李自成は湖北省銅山県九公山で亡くなった。これは数年前に開催された李自成に関する全国学術討論会で専門家...
漢の武帝も秦の始皇帝と同じような過ちを犯しました。なぜ同じ過ちを繰り返さなかったのでしょうか?
前漢(紀元前202年 - 紀元後8年)は、中国史上、12人の皇帝が統治し、210年間続いた王朝です(...
『Whipping the Inspector in Anger』の主人公は誰ですか?三国志演義ではどのように描かれているのでしょうか?
「鞭打警部」は、中国の古典文学の傑作『三国志演義』の中の素晴らしいストーリーです。小説の第二章から抜...
古典文学の傑作『東遊記』第27話:董賓が白牡丹と戯れる
『東遊記』は、『山東八仙伝』や『山東八仙伝』としても知られ、全2巻、全56章から構成されています。作...
『紅楼夢』における甄世銀の背景は何ですか?結局、なぜ彼は馮蘇に追い出されたのでしょうか?
甄世銀は『紅楼夢』に登場する最初の地方官吏であり、神のように自由気ままな生活を送っています。それは本...
李尚胤の古典古代詩からは2つの慣用句も生まれた。
李商隠の古典古代詩からも 2 つの慣用句が生まれました。興味のある読者と Interesting H...
「酔って落胆:鷲への頌歌」の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
「酔いつぶれ 鷲に捧ぐ歌」の原文は何ですか?どう翻訳しますか?これは清代の詩人陳維松が書いた物と感情...
「ロープが落ちたら、眉毛は春の山と美しさを競う」の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
ロープが落ちると、眉毛は春の山々と美しさを競う周邦厳(宋代)眉毛は春の山々と美しさを競っているが、残...
于胥とはどんな人物だったのでしょうか?東漢の名将、于胥は歴史上どのように評価されているのでしょうか?
于胥(?-137年)、雅号は盛卿、愛称は定干。彼は陳国武平県(現在の呂邑武平)に生まれた。東漢時代の...
朱淑珍の名作「清平楽・緊急風景」鑑賞
以下、Interesting History の編集者が、Shuzhen の「清平楽風光集記」の原文...
秦国は殷津の戦いで大きな損害を受けたのに、なぜ魏国は勝利を追求しなかったのでしょうか?
殷津の戦いに関しては、秦国が50万の軍勢を派遣したと言われており、この戦いでは魏国が大勝利を収めたこ...
清朝の経済:手工業は賦役から代用税へと変化した
農業清朝は、生産量を増やすために、荒れ地の開拓、国境地域への移民の定住、新しい作物の促進などの対策を...
「胡曉草氏への返答」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
何虎熙曹は顧澤草に陶淵明(魏晋) 5月中旬、清朝は瑞浜で南雄を開始した。前進も減速もせず、風が私の服...
漢民族の歴史 漢民族の最初の国家、夏王朝
4000年以上前、夏族のリーダーである禹は、治水への貢献により禹順から高く評価され、最終的に部族連合...
ゴールデンカボチャの種の用途は何ですか?清朝の皇帝はなぜ黄金瓜の種を褒美として好んで使ったのでしょうか?
古代の皇帝が与えた褒美は高価なものが多かったことは、皆さんもよくご存知だと思います。しかし、清朝の皇...