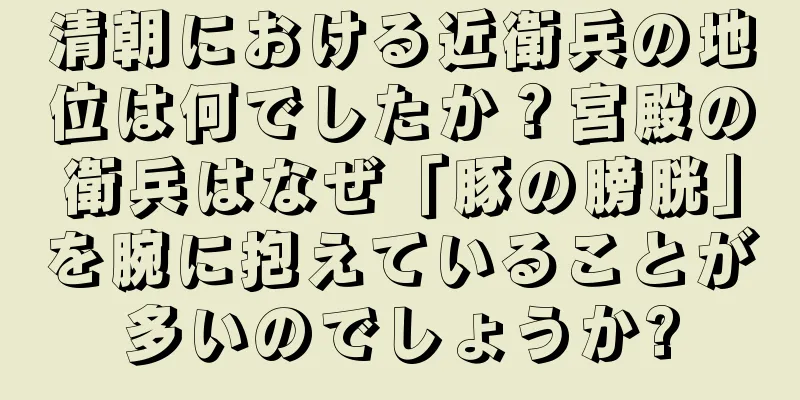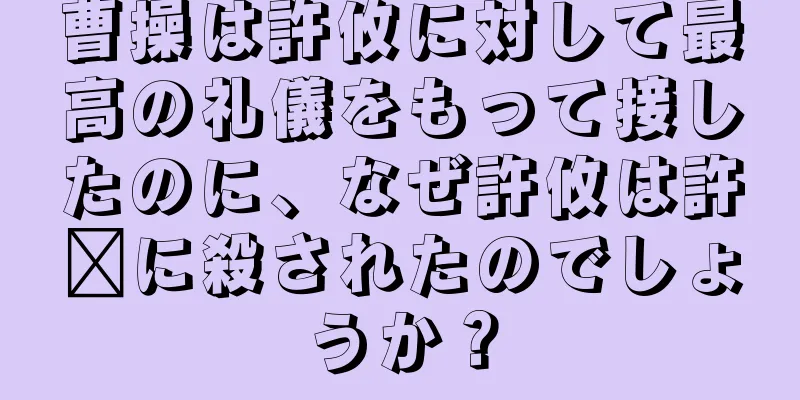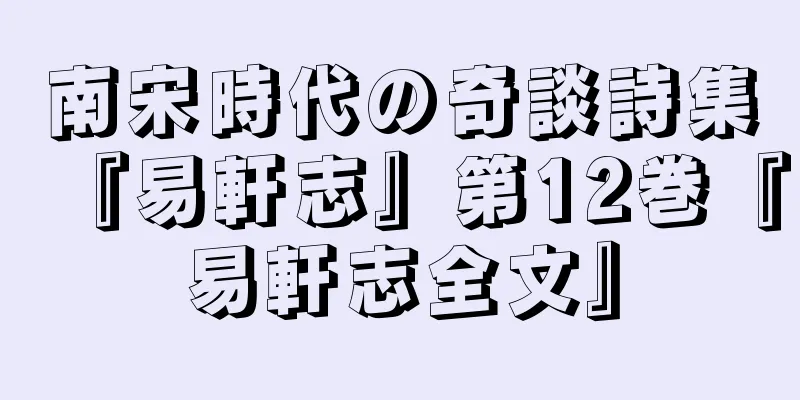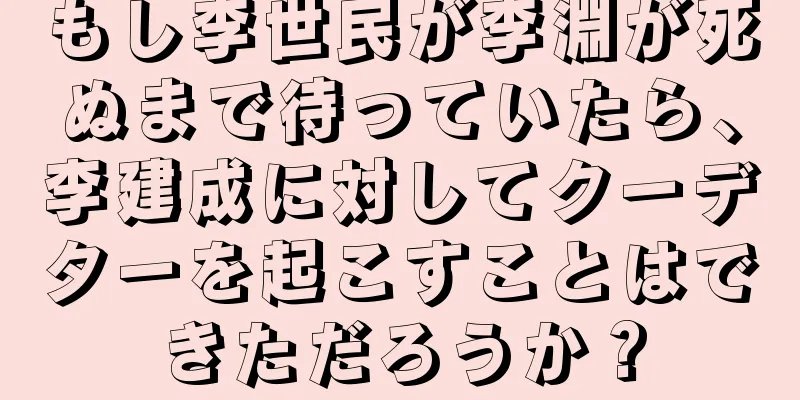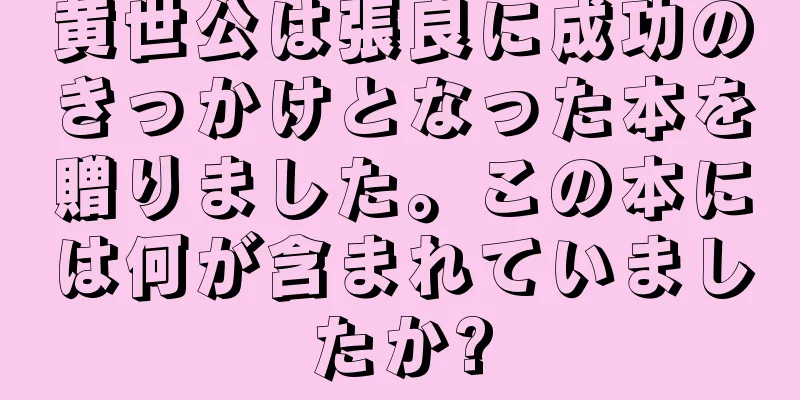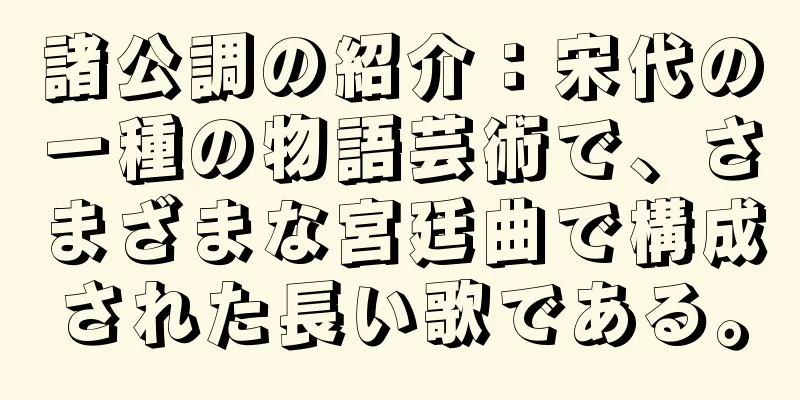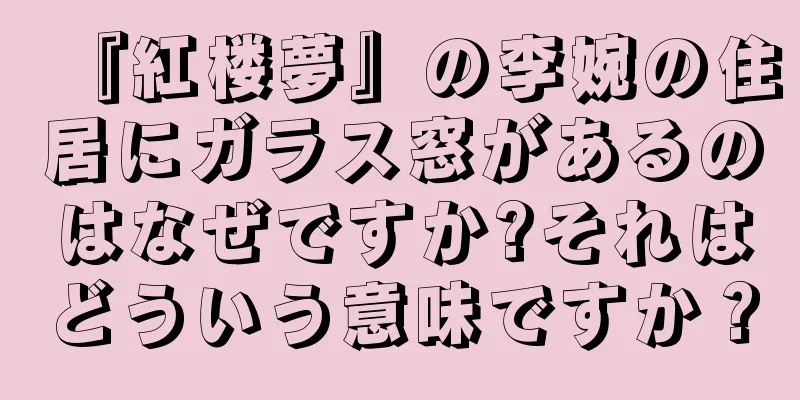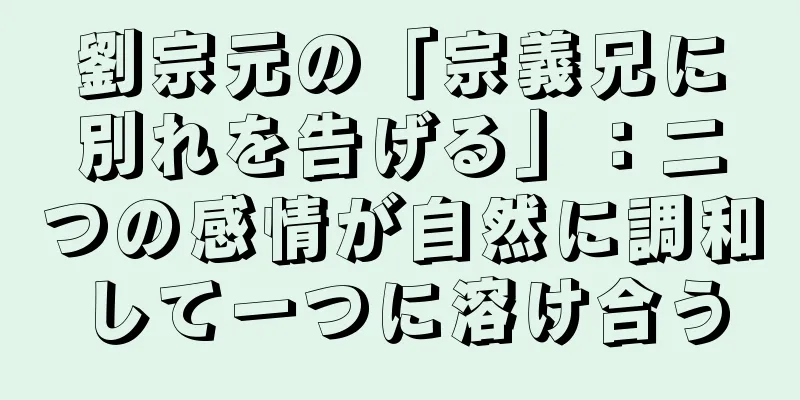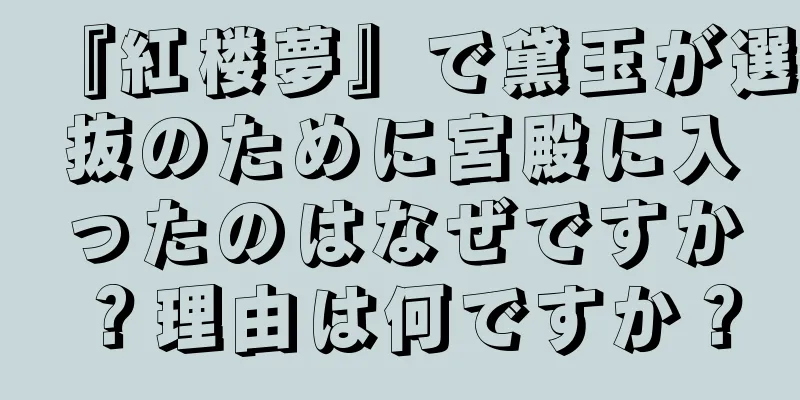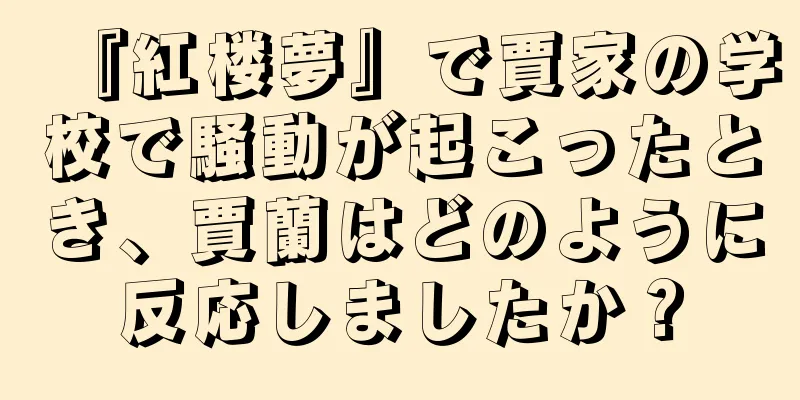道教の伝説における八仙人:八仙人の力のランキング
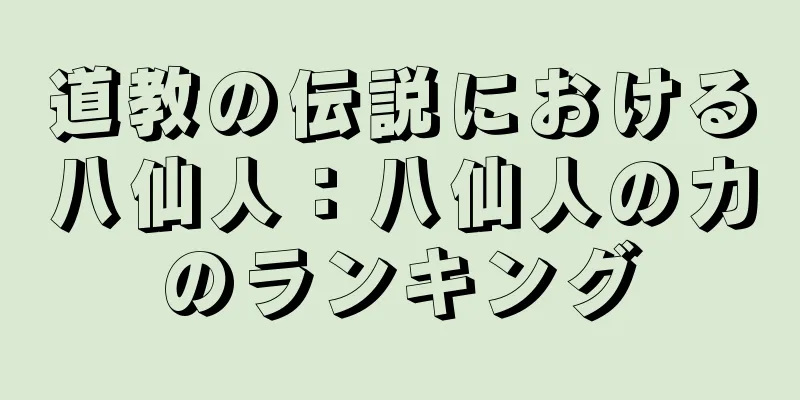
|
八仙人とは、民衆の間で広く信仰されている道教の神々8柱です。明代以前には八仙の名前についてはさまざまな意見がありました。漢代の八仙、唐代の八仙、宋元代の八仙があり、それぞれ記載されている仙人が異なります。明代になって初めて、呉元台の『東遊記』は、八仙人の起源を、李鉄凱、韓鍾離(鍾離権)、呂洞賓、張国老、曹国九、韓湘子、藍才和、何仙姑と確定した。 伝説によると、八仙人はそれぞれ男性、女性、老人、若者、富者、貴人、貧者、卑賤を表している。八仙人は皆悟りを開いた凡人であるため、性格は凡人に近い。近年、道教における神の非常に重要な代表となっている。中国各地に八仙廟があり、神を迎えたり競技会を行ったりする祭りには八仙人が欠かせない存在となっている。八仙人が持つ白檀板、扇、松葉杖、笛、剣、瓢箪、箒、花籠の8つの品は、一般に「八宝」と呼ばれ、八仙人の所有物を表しています。文学・芸術作品の中で最も有名なのは『八仙渡海図』と『八仙供養長寿図』です。神話小説『八仙渡海』は、八卦の五つの要素を借用し、擬人化して表現しています。 NO1. 李鉄貴 まず、李鉄貴についてお話しましょう。民間の伝説では、李鉄貴は八仙人のリーダーです。 彼はまた、李鉄桂とも呼ばれています。伝説によると、彼の姓は李、名は玄です。彼はまた、李寧陽、李洪水、李孔母とも呼ばれています。彼はもともととても背が高くてハンサムだったと言われています。唐山洞で練習中。彼は老君の華山仙会に参加することに同意していたため、出発前に弟子たちに、もし自分の魂が7日以内に戻ってこなければ、自分の体は焼かれるだろうと告げた。それで死体は残され、魂は外をさまよいました。 6日目に、予期せぬことに、弟子の家族から母親の病気が危篤であるとの報告があり、弟子たちは遺体を焼くしかなかった。弟子たちが家に帰ると、李鉄貴の魂はすぐに戻って行き場がなくなってしまいました。突然、彼は森の中で飢えた死体を見つけ、額から入りました。立ち上がった後、彼は自分の調子が良くないことに気づき、急いでひょうたんから老君からもらった霊薬を注ぎ出しました。ひょうたんは突然金色の光を放ち、黒い顔、乱れた髪、巻きひげ、大きな目、そして右足がまだ不自由な醜い姿を映しました。彼は驚きました、そして突然彼の後ろで誰かが拍手しました。振り返ると、それは老君でした。絶望のあまり、彼は魂を飛び出したいと思うようになりました。その時、老君は彼を止めて言った。「道教は容姿に左右されない。容姿さえあれば、十分な技量があれば、真の仙人になれる。」そして、彼に乱れた髪を留める金の輪と、足の不自由な足を支える鉄の松葉杖を与えた。李鉄凱は、不老不死の薬が入っていると言われているひょうたんを頻繁に持ち歩いていました。人間界に降り立った李鉄凱は、そのひょうたんを使って病気を治し、命を救いました。 NO.2 ハン・ジョンリ 八仙人の中で、鉄桂李に次いで名声が高いのは鍾離全である。彼は八仙人の中でも高い地位を持ち、特に道教徒の称賛によりその名声はさらに大きい。元代には金真道が「正陽の祖」として崇められた。この文字の原型は五代から宋代初期頃に現れました。彼の事績は『宣和志』『易建志』『宋史』などの書物に記録されているが、後に誤って韓鍾離と名付けられ、漢代の人物とされた。 『諸代神仙鑑』や『続全文学』などの書物によると、鍾離全の姓は鍾離、字は吉道、号は雲芳子、正陽子であった。彼は東漢の咸陽の出身です。父の張鍾離は東漢の将軍であり、兄の鍾離簡は中央軍の将軍でした。二人とも後に仙人になりました。唐代に鍾離全という人物がいた。彼の詩集『全唐詩』には、短い伝記を添えて、彼の詩集が3編収録されている。「咸陽の人で、老人に会って仙人の秘訣を教わった。また、孔洞山で道を説く華陽仙人、王玄福仙人に会った。雲芳氏と名乗り、後に仙人になった」。彼が残した詩は「長安酒場三編」で、「座るときも横になるときも、いつも酒瓶を持っていて、目に帝都が見えない」「真の仙人に会うのは容易ではない。あなたが帰ってきたら、私もついていきたい」など、まだ「仙人の味」が残っており、彼は道教の愛好家だったに違いない。 韓鍾離は李火の象徴に属します。韓鍾離は気性が激しい男で、魔法の扇を振ると火が出ました。龍宮の火事は韓鍾離が引き起こしたものです。 NO3. 呂東彬 最も多くの伝説が伝わる仙人は呂洞賓です。道教では、全真道教は彼を「清陽の祖師」、別名「呂祖」として崇拝しています。歴史上のほとんどの研究者は、呂洞賓の姓は呂、名は燕であり、唐代末期に生きた人物であると信じてきました。彼の詩は『晋唐詩集』や『慈宗記』に収録されている。宋代の羅大靖の『和林雨録』、洪邁の『易建志』『集仙川』などの書物に記録されている。彼は荊昭(現在の陝西省と西安)の出身で、唐の咸通年間に科挙に合格し、二度県知事を務めたとも言われています。彼は九江出身で、もともと唐の王族であったという説もある。姓は李であったが、武帝の災難を避けるために呂に改姓した。彼の本名は少光。20年以上科挙に失敗したため、諦めて世界中を旅した。後に、鍾離権に悟りを開かされ、道士になった。呂洞賓は八仙の中で最も人間味にあふれ、奔放でユーモアがあり、暴力と戦い、民衆の利益を守る。鬼や怪物を退治し、酒と女も好む。呂洞賓については「呂洞賓が白牡丹を三度遊ぶ」という伝説がある。呂洞賓については多種多様な伝説があるが、それらから、呂洞賓はもともと唐代の道学者であり、後に神格化された仙人であったことがわかる。 呂洞賓は千金のシンボルに属します。乾坤は純粋な陽を表すため、彼は純粋な陽の祖と呼ばれ、彼が使用する剣も純粋な陽の剣と呼ばれています。彼はまた、何仙姑との愛について語り、去ることを躊躇していました。これは、天と地の調和の原則を示しています。 NO4. 張国朗 張果老は八仙の中で最年長です。彼の名前は「張果」です。彼は八仙の中で最年長なので、人々は彼を敬意を込めて「張果老」と呼びます。歴史上、張果という実在の人物がいました。彼の伝記は『新旧唐書』にあります。武則天の時代に、彼は中条山に隠遁していました。当時の人々は皆、彼が不老不死の秘術を持っていると主張していました。彼は数百歳の年齢だと主張しました。武則天はかつて使者を送って彼を呼びましたが、張果老は死んだふりをして行くことを拒否しました。唐の玄宗開元21年、衡州太守の衛済が皇帝にこの不思議な話を報告した。玄宗は衛済を召し上げたが、張果はまたも死んだふりをし、死んでから長い時間が経ってから目覚めた。使者は近づく勇気がなかった。玄宗はそれを聞いて、徐喬を遣わして再び彼を招待した。張果は北京に行くしかなかった。 唐代の玄宗皇帝は噂を疑い、早死や吉凶を占うのが得意な邢和普に張果の吉凶を占わせたと伝えられている。しかし、邢は張果の甲子年を知らなかった。また、幽霊を見るのが得意な「葉光」という道士もいた。玄宗は彼に張果を見るように頼んだが、彼は「張果はどこにいるのか?」と尋ねた。目の前にいるのに見えなかった。歴史の記録から判断すると、張果はただの罪深い老魔術師だった。そうでなければ、なぜ召喚を避けるために何度も死んだふりをしたのか?せいぜい、彼はいくつかの魔法のトリックを知っていただけだった。したがって、彼に関する物語はすべて、道教が民間の噂に基づいて捏造し、宣伝目的で誇張したものである。 『太平広記』には、張国老が堯帝の時代に生きた人物であると主張したとも記されている。唐の玄宗皇帝は、魔術師「葉法山」に張国老の出自について尋ねた。葉法山は「教える勇気はない。教えたら死んでしまう」と答えた。その後、「張国老は乱世の初めからいる白いコウモリの精霊だ」と言った。話が終わると、張国老は地面に倒れて死んだ。玄宗皇帝が嘆願すると、張国老は彼を生き返らせた。 張果老は真木のシンボルに属します。張国老が月宮のサンザシの木を切り倒したので、その木は柔らかい木ではなく硬い木です。 NO5. 何仙姑 何仙姑は八仙人の中で唯一の女性であり、彼女の生涯については様々な説があります。彼女は唐代から来たと言う人もいます。宋代初期の太平広記は『広義記』を引用して、「何二娘」という農民がいたと述べている。彼女は靴を編んで生計を立てていたが、後に家にいるのが退屈だと感じたため、羅浮山に旅行し、山の寺院に滞在し、寺院の僧侶に食べ物を提供するために山の果物を頻繁に集めた。かつて、四百里離れた荀州山寺の僧侶が羅浮山寺に来て、ある日仙女があの山にヤマモモの実を摘みに行ったと話しました。調べてみると、その日は二娘が実を摘んだ日でした。また、二娘がどこでそんなにたくさんの山の実を摘んだのか誰も知らなかったため、人々は二娘が荀州山寺で実を摘んだ仙女だと信じました。それ以来、二娘は遠くまで有名になり、山寺には住まなくなりました。 『徐童考』によると、何仙姑は唐代の武則天の時代に広東省増城県の出身で、生まれたとき頭に六つの光線が現れ、「仙人のような容貌」を持って生まれた。13歳のとき、山中で道士に出会い、道士から仙人の桃を食べた。それ以来、空腹や喉の渇きを感じなくなり、体はハエのように軽くなり、人生の吉凶を予見できるようになった。その後、彼女は北京に呼び出され、途中で去った。一説によると彼女は宋代出身だという。 宋代の文人の記録には、主に北宋時代の雍州(霊陵)の人として記されている。また、幼い頃に不思議な人に出会い、仙桃を食べて仙人になったという説もある。言い伝えによると、彼女は田舎で草を食んでいたとき、見知らぬ人に出会い、不老不死のナツメをもらい、それを食べた後、仙人になったそうです。宋代の人々の記録にも、何仙姑が占いをして災いや福を予言したという記録が残されています。当時、学者や好奇心の強い人々が占いのために押し寄せており、彼女が占いの達人であったことを示しています。 何仙姑は坤土の象徴に属し、八仙人の中で唯一の女性であり、柔らかい土です。呂洞賓との結婚を望んでおり、これは乾と坤の調和を表しています。 NO6. 蘭彩河 八仙人の中には、皮肉屋でほとんど狂気じみた、藍才和という名の乞食道士がいました。彼の功績は、南唐の沈芬の『続仙伝』、宋代初期の『太平広記』、陸游の『南唐史』などの書物に記録されている。彼は唐代末期から五代にかけて生きた人物です。彼は奇妙な行動をしており、酒を飲んだり歌ったりすることが好きで、たいていぼろぼろの青いシャツを着て、片足にはブーツを履き、もう片方の足は裸足でした。さらに珍しいのは、夏は木綿の服を着ていたのに、冬は全身から湯気をたてながら雪の中に横たわっていたことだ(続仙人伝)。彼は通常、3 フィート以上もある拍子木を持ち、道端で歌ったり物乞いをしながら拍子木を叩いていました。彼は多くの歌を歌いましたが、そのほとんどは風景からインスピレーションを得たもので、それはこの世のものとは思えないだけでなく、とても妖精のようでもありました。彼らのうちの一人はこう言った。「藍彩河は歌い踊る。世界はどれほど広いのだろう。美は春の木のようで、時は桝のようで、昔の人は去って二度と戻ってこないが、今日はますます多くの人がやって来る。朝には鳳凰に乗って青い波に向かい、夕方には桑畑に白い波が見える。空には明るい太陽が輝き、金と銀の宮殿は高く雄大だ。」彼の振る舞いは狂気じみていて、人々が彼にお金をあげると、ほとんどが貧しい人々に与えた。藍彩河には定まった住む場所がなく、世界が彼の家だった。この仙人の原型は、もともと放浪者であったが、その狂気じみた行動と貧しい人々を助ける愛情により、人々に愛され、仙人として神格化された。 蘭才和は荀木の象徴に属し、手に蘭を持っており、すべての薬草は軟木です。韓湘子は坎水の要素に属します。小説の中には、ひどい干ばつがあり、韓湘子が人々のために雨を降らせるために笛を吹く場面がある。 NO7. 韓湘子 韓湘子は唐代の有名な作家である韓愈の甥(曾甥という説もある)であると一般に信じられており、『唐書丞相系譜』『邑陽雑録』『太平広志』『仙川世易』などの書籍で紹介されている。ある人は、彼は韓愈の甥の孫だと言いました。歴史的に、韓愈には大理宰相を務めた韓翔という甥の孫がいました。韓愈はかつて「藍観に赴き、甥の孫湘に見せしめ」という詩を書いた。「皇帝に手紙を提出し、夕方に朝陽に左遷され、八千里の旅路をたどる。聖王朝の悪を滅ぼしたいが、老齢の残りの年月を無駄にするつもりはない!秦嶺山脈の向こうに雲が流れ、私の家はどこにある?藍観は雪で塞がれ、私の馬は前に進めない。あなたが何か目的を持って遠くから来たのはわかっているので、どうか私の骨を集めて毒の川のほとりに埋めてください。」彼が仙人になったという伝説は、唐代の段承施の『邑陽雑左』に初めて登場する。その本には、韓愈には幼い遠縁の甥がいて、その甥は軽薄で読書が嫌いだったと書いてある。韓愈は一度彼を責めたが、叔父の要求に従って7日以内に牡丹の花の色を変えることができた。また、それぞれの花には「秦嶺山脈の向こうに雲が見える私の家はどこにあるか…」という詩が書かれていた。韓愈は驚いた。韓湘子は韓愈の甥であり、その功績は『邑陽雑記』に記されているものと似ているという言い伝えもある。韓湘子の原型は五代に神格化された韓愈の甥である。 第8位 曹国九 八仙の中でも最下位に位置する曹国九は、最も遅く登場した人物であり、彼に関する逸話も少ない。彼の生涯については似たような話が数多くあるが、それらはすべて宋仁宗の皇后曹操に関係している。 『宋史』には、曹毅(号は公伯)は曹斌の孫であり、曹皇后の弟であったと記録されている。温和でおおらかな性格で、音楽に精通し、詩を書くのが好きだった。済陽王の爵位を授かり、数々の王朝に順調に仕えた。享年72歳。 『仙人伝』にはこう記されている。曹国九は生まれつき優しく、富や名誉を好まないが、仙人の道を敬愛している。兄は傲慢で無法で、無謀なことをする。曹国九は自分の悪行を深く恥じ、修行のために山に入る。曹国九は鍾離全と呂洞賓に出会い、弟子として迎え入れられる。やがて曹国九は仙人になる。 『東遊記』における曹叔父の描写も上記と同様である。 曹国九は玄土の象徴に属します。書物には、地下にいた弟の魂が彼の体に憑依して悪事を働き、彼の魂を地下に閉じ込めたと書かれています。地下は地球の場所です。しかし、それは硬い地球です。なぜなら、彼は悪霊との決闘を通じて最終的に悪を打ち負かし、精神的な明晰さを取り戻したからです。これらはすべて硬さの象徴です。 |
>>: ギリシャの神々の生息地トップ10:ギリシャの神々はどこに住んでいるのか?
推薦する
文廷雲の『菩薩男:宝箱、金雀、金鶏』:女性の別居への憧れを描写
文廷雲は、本名は斉、雅号は飛清で、太原斉県(現在の山西省)の出身である。唐代の詩人、作詞家。彼の詩は...
諸葛亮の第一次北伐の後、蜀漢は何人の将軍を失いましたか?
偉大な詩人杜甫はかつて「使命を果たさずに死んだ、英雄は泣く」という詩を書き、数え切れないほどの後世の...
仙府宮の建築レイアウトの特徴は何ですか?それはどのような役割を果たすのでしょうか?
仙府宮は明代に建てられた中国の宮殿建築です。仙府宮の建築レイアウトの特徴は何ですか?どのような役割を...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 狂気の道士』の原文は何ですか?どのように理解すればいいのでしょうか?
「クレイジーな道教信者」の原文(中国のスタジオからの奇妙な物語より)本名が不明の典道士[1]は孟山寺...
南宋文芸詩奇譚集第1巻『易堅志全文』
『易軒志』は、南宋時代の洪邁が漢文で書いた奇談集である。本のタイトルは『列子唐文』から来ている。『山...
張吉の詩「蛮族の旧友」全文鑑賞
「失われた友人」時代: 唐代 著者: 張季一昨年、我々が月氏に駐屯していたとき、我々の軍は城の下で全...
私の国の古代における 4 つの驚くべき技術とは何ですか?戦国時代にもオーブンや冷蔵庫は存在していた!
古代我が国の驚くべき4つの技術とは?戦国時代にオーブンや冷蔵庫が存在していた!興味のある読者は編集者...
『紅楼夢』で宝玉と石向雲が鹿肉を食べているとき、李婉は何と言いましたか?
『紅楼夢』の金陵十二美女本編では、李婉は10位にランクされています。以下の記事は、Interesti...
古梁邁が著した『春秋古梁伝』には、熙公8年に何が記されているか?
熙公8年に古梁邇が著した『春秋古梁伝』には何が記されているのでしょうか?これは多くの読者が関心を持っ...
唐詩の鑑賞:岳天の『老年詩』に対する返答、この詩の作者はどのような比喩を表現したいのでしょうか?
岳天老年詩への返答 [唐] 劉玉熙、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみまし...
曹魏の完璧な将軍といえば、なぜ多くの人が張遼を第一候補に選ぶのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
劉茶の『氷柱』の原文は、特に奇怪で奔放である。
唐の徳宗から献宗の時代(真元末から元和の時代)にかけて、韓愈を筆頭とする一群の詩人たちは、大理時代以...
古典文学『南遊記』第17章:華光の三度の豊都訪問
『南遊記』は、『華光大帝五顕現伝』、『華光伝』とも呼ばれ、明代の于香當が書いた神と魔を扱った中編小説...
蘇翔の「ヤマウズラの空:川岸に落ちる紅葉、秋の荒水」:この詩には明確な層があり、言葉は尽きているが、意味は尽きていない。
蘇湘(1065-1147)は南宋初期の詩人であった。雅号は楊志。眼病のため、初めは扁翁と名乗った。彼...
秦の時代の厳しい法律と刑罰は、想像できないほど歪んだものでした。
秦の時代の厳しい法律と刑罰がどれほど歪んでいたかは想像もつかないでしょう。以下、Interestin...