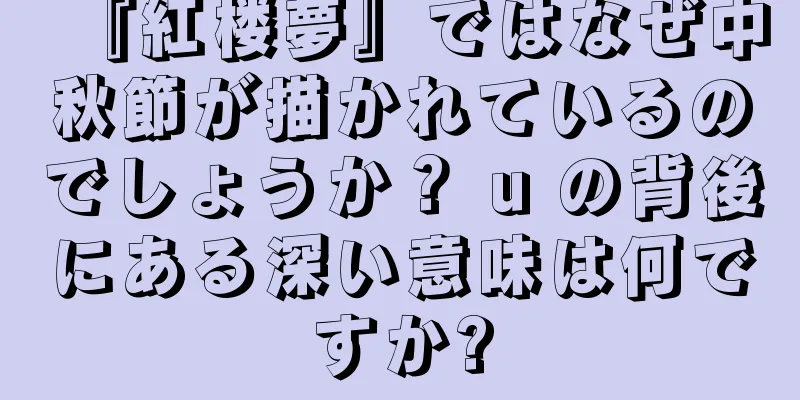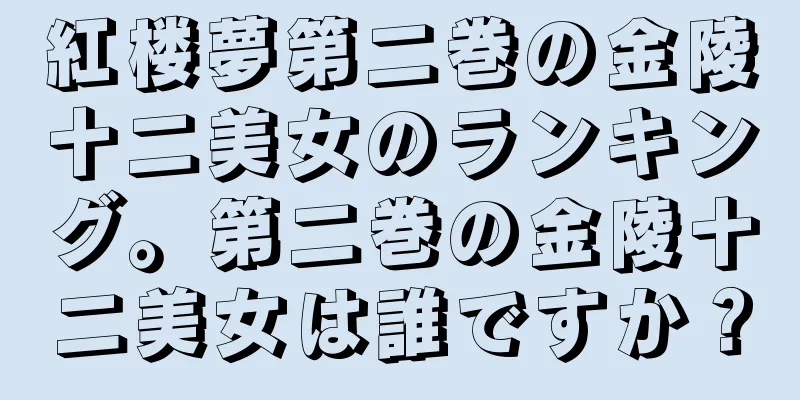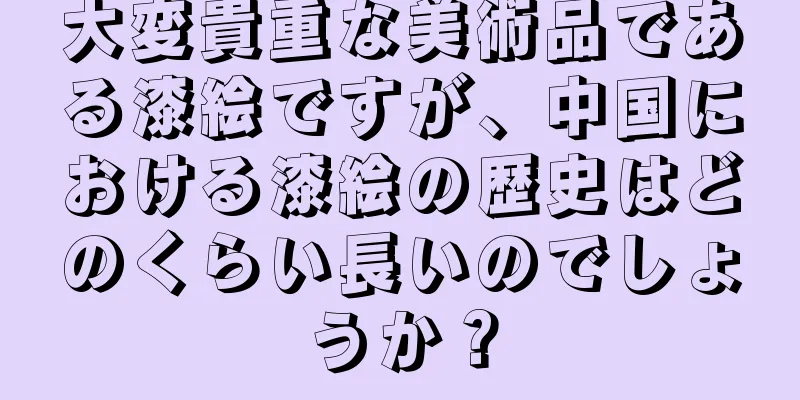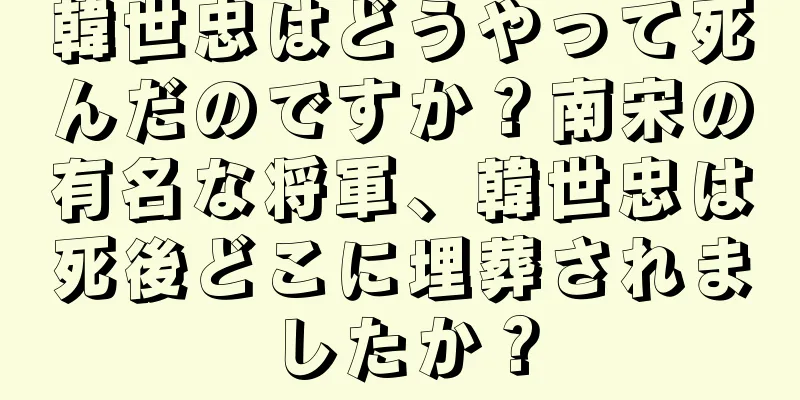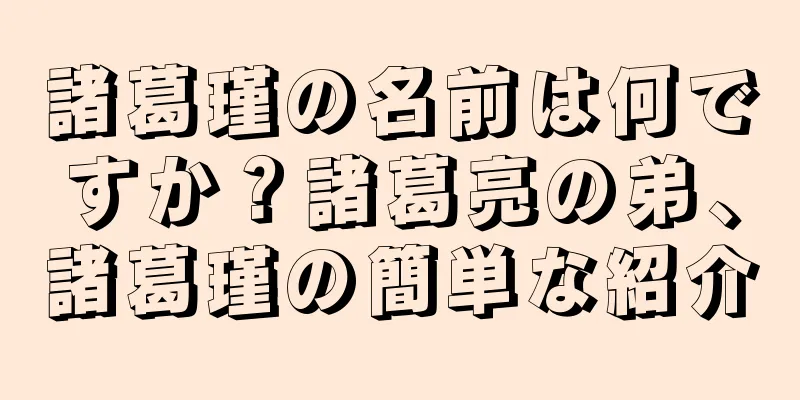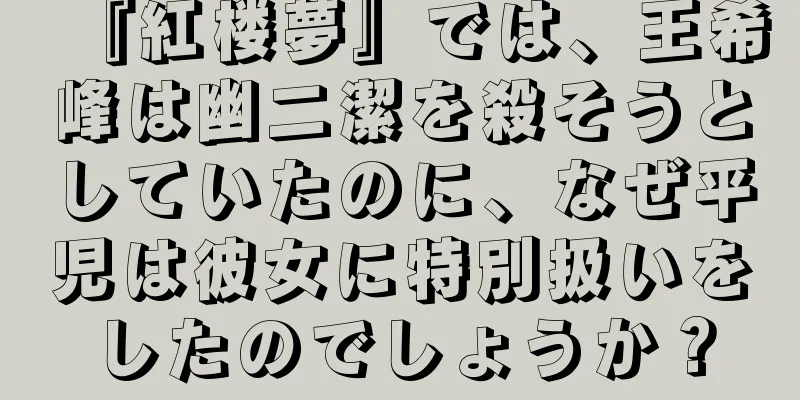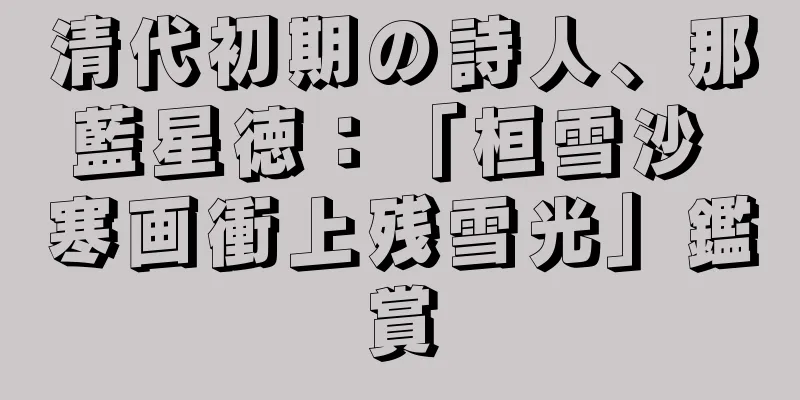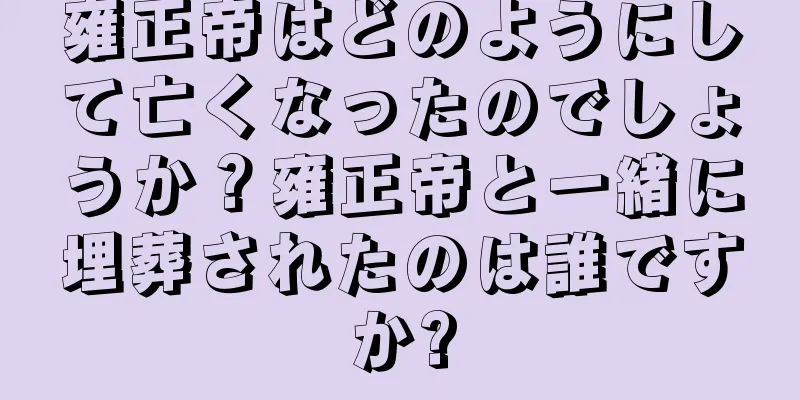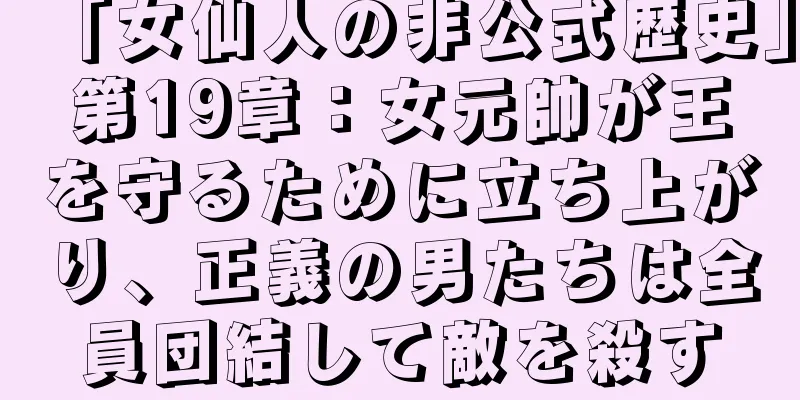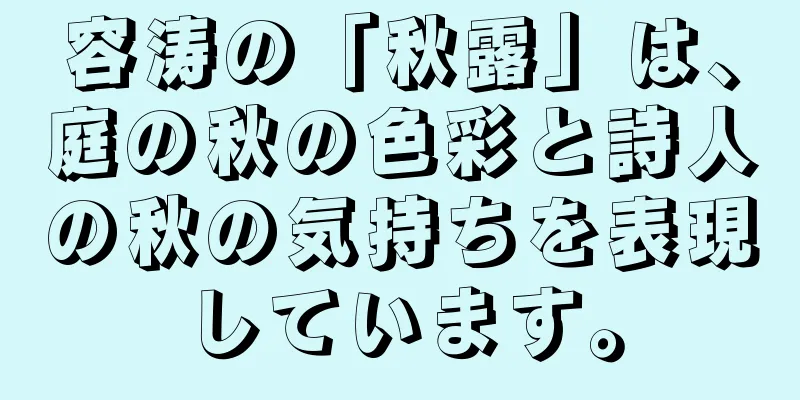諸公調の紹介:宋代の一種の物語芸術で、さまざまな宮廷曲で構成された長い歌である。
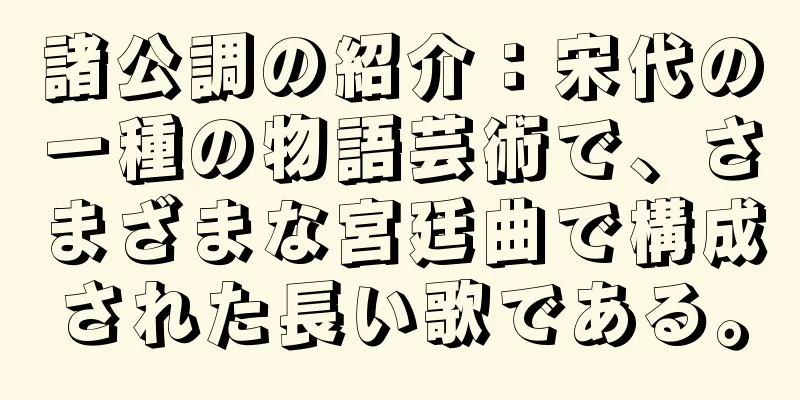
|
諸公調は、中国宋代の物語芸術の一種です。交互に歌われるさまざまな宮廷曲の歌を集めたものなので、この名前が付けられました。銅鑼は古代中国の様々な音階の最初の音です。銅鑼を音階の起点とする音楽を銅鑼曲といいます。複数のモードから構成される長い曲全体を、さまざまなモードと呼びます。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 諸公調は「花本」とも呼ばれています。例えば、『西室志諸公調』巻1では「この物語」は歌われる物語を指しています。『水滸伝』120篇のうち第51篇には、諸公調役者の白秀英の冒頭の発言が書かれています。「今日、秀英の看板には、この物語が『双堅が毓章城から蘇青を追いかける』というロマンチックで優雅な作品であると明記されています。」 これは、さまざまな宮廷音楽と民話が双子の芸術形式であることを示しています。さまざまな宮廷曲作品に登場する代表的形式の現実性と虚構性は、小説や脚本における登場人物の声のシミュレーションと密接に関係している。 さまざまな曲は、これまでの物語、歌、踊りに関連しています。唐代の『汴文』の韻文交替の体系を継承し、同じ旋律を何度も繰り返して間に語りを挟む鼓詞の構造、一詩一語を交互に歌い、歌舞と組み合わせる「伝唱」構造、同じ宮廷旋律を数曲まとめて一組の歌とする「長伝」構造を発展させた。 前述の鼓の歌詞である「笙打」や「長笙来」と比較すると、「笙公調」は長さも大きく、構造も壮大で、より複雑な内容を表現できます。一方で、長編物語詩のように自由に物語が展開され、他方では、歌詞の一部に表現の特徴があり、人物を見たり声を聞いたりする効果を生み出すことができます。 キーや音色の異なる楽曲をインタラクティブに使用することで、より豊かな感情表現の場を提供します。これは、ラップ、歌、ダンスからオペラへの進化における過渡的な形式です。 朱公貂は伝統的なラップ芸術の直系の子孫です。その歌詞は今でも唐宋代の詞体系に属しています。そのセリフはスピーチによって影響を受けます。また、鼓詞、打撰、宋代劇、唱霊、長伝などの長所を吸収し、独自の芸術体系を豊かにしました。 孟良禄によれば、初期の宮廷歌曲の歌唱には、太鼓や琴、笛などの伴奏がついていた。宋代に宮廷で様々な曲が演奏される際、通常は歌手自身が太鼓を演奏し、他の人は笛や拍子木などの楽器で伴奏を演奏した(宋代洪邁の『易経志』)。時には水杯だけが伴奏に使用されることもあった。 『水滸伝』第51章には、白秀英という画家が歌を歌うとき、弦楽器から琵琶や筝に替えて、銅鑼や拍子木を鳴らしてリズムをとったと記されている。 さまざまな宮殿の曲には、語りと歌の両方が含まれていますが、歌が主な特徴です。歌詞の各セクションが歌われた後には、次の曲を新しい曲調で歌えるように短いナレーションが入ります。歌詞の各セクションは、二重旋律で歌われる場合もあれば、エンディング付きの二重旋律で歌われる場合もあれば、同じ調でエンディング付きの一連の旋律で歌われて組曲を形成する場合もあります。場所によっては、単一の旋律のみが使用されることもあります。 各節は長くても短くてもかまわず、比較的柔軟性があるため、100組または200組の音楽を連続して歌うことができ、長い物語を語るのに適しています。物体や場面の描写、人物の描写は生き生きとしており、言語は大衆的で活気があります。各章はサスペンスで終わり、観客にとって非常に魅力的であり、芸術の面でこれまでのすべての物語芸術形式を上回っています。 諸公調は、宋代、金代、元代のさまざまな流派の優れた点を統合し、さまざまな宮廷音楽で構成された大規模な物語形式です。諸宮曲の名称は、多様な宮曲を使用し、複数の曲を繋ぎ合わせて壮大な構成を持ち、より複雑なストーリー展開を表現するのに優れていることに由来しています。 残念ながら、『朱公语』のほとんどは継承の過程で失われてしまいました。現在入手できる『朱公语』の本は非常に少なく、断片だけでも宋代の『劉志遠の朱公语』や晋代の董潔遠の『西室の朱公语』などがあります。後者は「董卓の『西室』」と呼ばれ、現在までに最も完全な形で保存されている作品である。テキストのすべてと楽譜の3分の1は現在『九公大成南北辞公诺』に保存されている。 諸公調は韻文と散文の2つの部分から成り、歌と語りを交互に行う。基本的には物語調で、歌詞には表現に近い部分もある。各種宮廷曲は、唐・宋代から北方で流行した大曲、竪曲、長陵、長打、長竪、民謡などを音程やリズムによって宮廷曲に分類し、物語を伝えるために使われています。 『東京夢花録』には、孔三川と舒秀才がかつて首都汴梁(現在の開封)で歌ったと記録されている。さまざまな曲の各セクションが歌われた後には、次の曲を開始して歌い続けることができるように、短いナレーションが入ります。歌詞は長くても短くてもかまいません。柔軟性が高く、1組または2組の音楽で長い物語を連続して歌うこともできます。容量が大きく、物体や場面を生き生きと描写し、シンプルで生き生きとした言葉を使用しています。芸術面ではこれまでのラップアートを超え、人々の愛を勝ち取っています。 さまざまな宮殿の曲が後のオペラ音楽への道を開いた。宋代の『武林九氏・官芸』には『諸公貂八王』と『諸公貂囃子』の二篇が収録されており、当時宋代の劇を歌う際に諸公貂の曲が使われていたことがわかる。 元代になると、様々な説話の旋律は徐々に衰退していったものの、その旋律は北方座の形成に重要な影響を与え、その重要な芸術技法はすべて元の座楽に吸収された。 袁紹は単本と摩本に分かれており、1つのバージョンは最初から最後まで1人の登場人物によって歌われます。組曲の構成と戦争場面を描写する物語技法の使用はすべて、さまざまな宮廷曲から直接影響を受けています。それは中国のオペラ芸術の成熟の基礎を築きました。 公糸の文学的意義は非常に明白です。そのテーマは、歴史テーマ、愛テーマ、家族と結婚テーマの3つに大別できます。これらのテーマのいくつかは、後のドラマや小説に影響を与えました。 『諸公調』は大衆文学の芸術的特徴を備えており、それは言語の大衆化、思想内容の世俗化、審美的嗜好の大衆化に表れている。さまざまな様式で表現されたテーマは後世に大きな影響を与え、文学史上に深い意義を残しています。 |
<<: 『金元本』の紹介:内容、形式、役割は宋代の演劇と一致している
>>: クパイの名前の紹介:古代のクパイは非常に長く、クパイの一部のセクションの名前は
推薦する
歴史上、西太后には子供がいたのでしょうか?慈安皇太后は子供を産みましたか?
歴史上、慈安皇太后には子供がいたのでしょうか?歴史上、西太后は子供を産んでいません。西太后は、孝真憲...
「Jingxi」が誕生した背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
ジンシー杜荀和(唐代)静渓の岩は険しく、人々は非常に用心深いので、年間を通じて転落した人はいません。...
項羽の将軍一覧: 項羽の指揮下にある最も強力な 5 人の将軍は誰ですか?
はじめに:項羽は中国の軍事思想における「勇敢な戦い」派の代表的人物です。彼は中国史上最強の武将であり...
九字龍石進の武術はどれほど優れているのか?彼の主人は誰ですか?
水滸伝の九字龍、史進の主人は誰ですか? 『水滸伝』における史進の順位は高くないが、非常に重要な人物で...
歴史の豆知識:中国の有料公衆トイレは清朝の光緒年間に初めて登場した
電視寨図録の写真には、ズボンのウエストを調節しながら有料公衆トイレに出入りする人々がいる。ドアの内側...
『紅楼夢』の王夫人は本当に賈歓を嫌っているのでしょうか?彼女は何をしたのですか?
『紅楼夢』に登場する宝玉の母、王福仁は、非常に物議を醸すキャラクターである。下記の興味深い歴史編集者...
「古詩集第59巻第38号」の作者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
古代詩集 第59号、第38号李白(唐)雑草に覆われた人里離れた庭に、一輪の蘭が育っています。春の太陽...
唐代末期の詩「楽郷県」を鑑賞します。この詩の作者はどのような場面を描写しているのでしょうか。
唐代末期の楽郷県の陳襄については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう。私の...
「狼煙と狼火」という用語はどこから来たのでしょうか? 「狼煙」はなぜ「狼煙」と呼ばれるのでしょうか?
「狼煙と狼火」という用語はどこから来たのでしょうか? 「狼煙」はなぜ「狼火」と呼ばれるのでしょうか?...
詩人李洵が蓮池を巡る春の少女の情景を描いた「南湘子乗彩舟」鑑賞
李勲(855?-930?)は唐代末期の詩人。彼の愛称はデルンであり、彼の先祖はペルシャ人でした。四川...
『紅楼夢』では賈迎春は木偶の坊と呼ばれています。彼女のもう一つの面はどんな感じでしょうか?
応春は『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人であり、栄果楼の賈奢とその妾の娘です。今日は、興味深...
宋代以前にはキルトは存在しませんでした。古代の人々は何を身にまとっていたのでしょうか?キルトなしで冬を乗り切るには?
今日は、Interesting History の編集者が、古代の人々がキルトなしで冬をどうやって乗...
拓跋扈には何人の息子がいましたか?北魏の明元帝の息子は誰でしたか?
北魏の明元帝、拓跋思(紀元392年 - 423年)は鮮卑人であった。彼は太武帝拓跋扈の父である道武帝...
『紅楼夢』で、平児はなぜ賈玉村を決して餓死することのない野蛮な野郎だと呪ったのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
明代の軍事理論書『頭備復譚』全文:第2巻:武略
『頭備復譚』は明代末期に書かれたもので、古代の軍事理論に関する影響力のある著作である。それでは、次の...