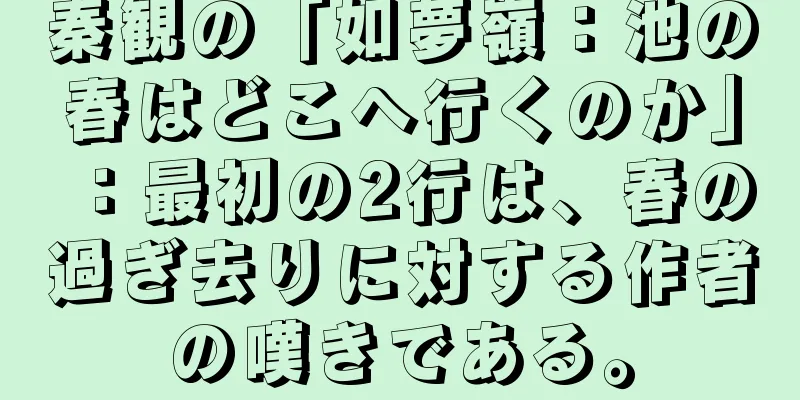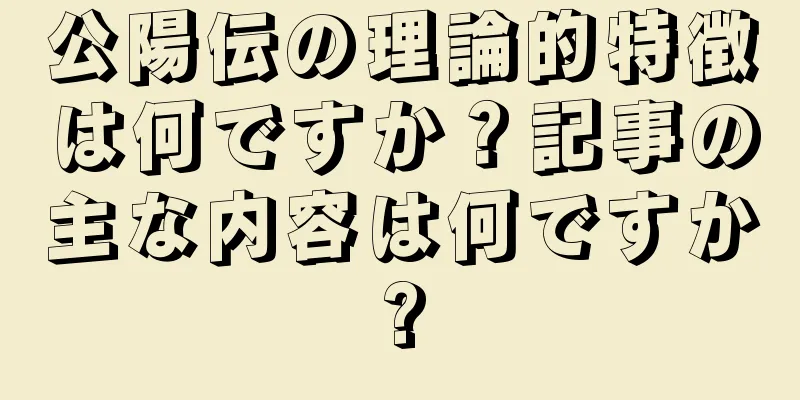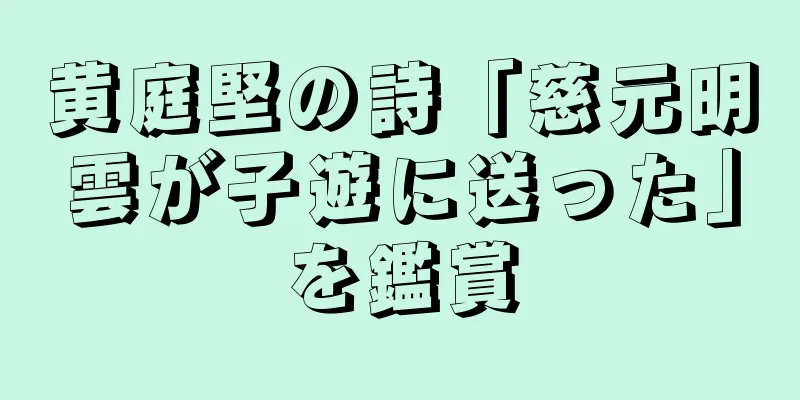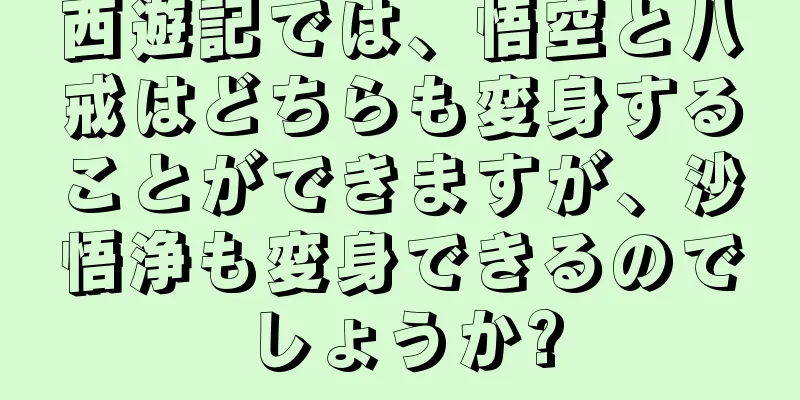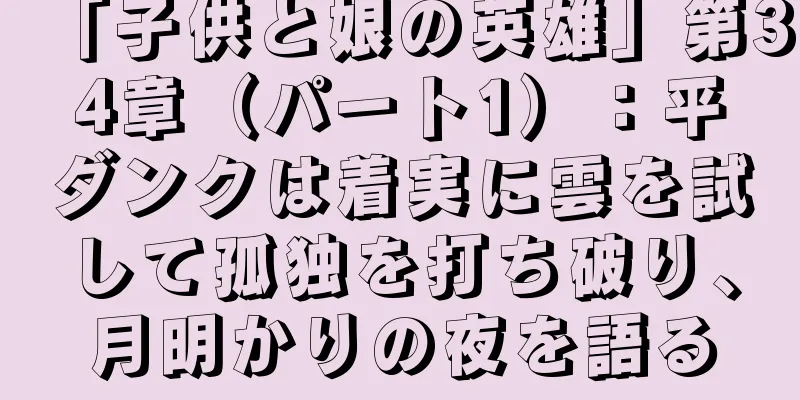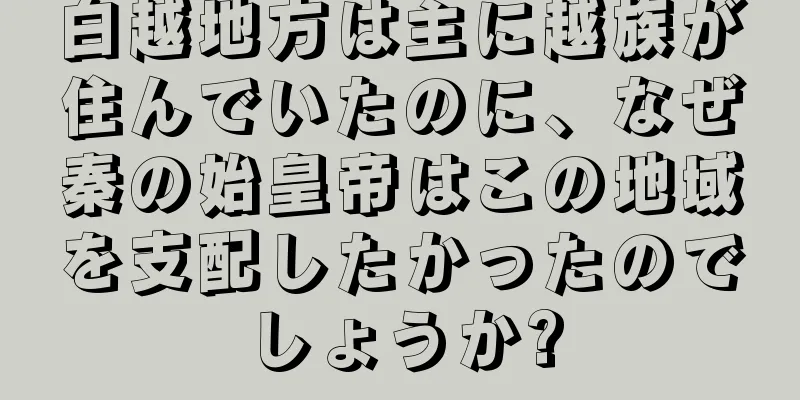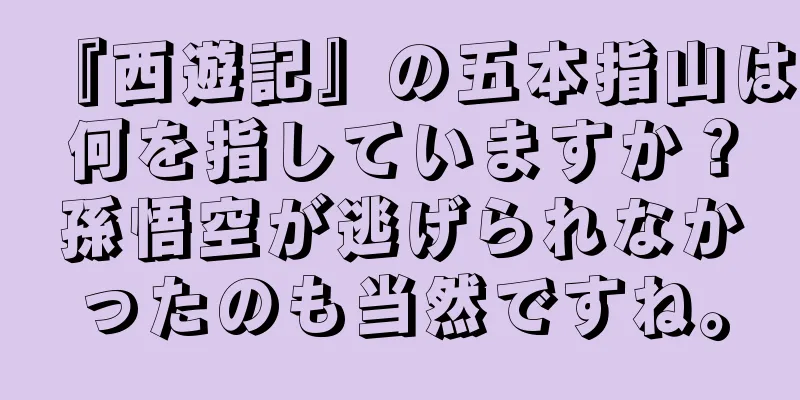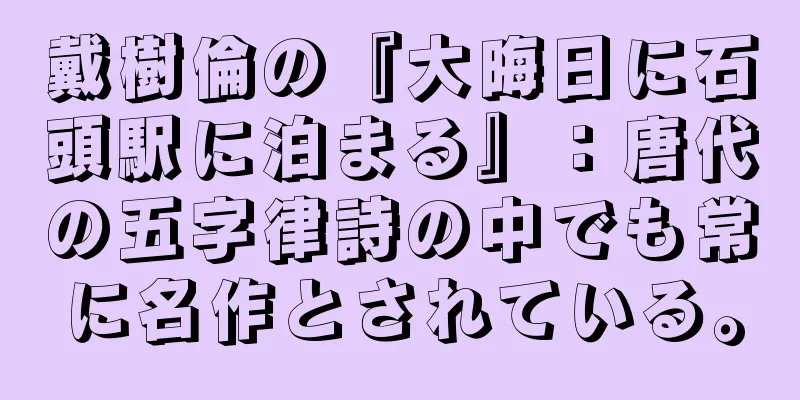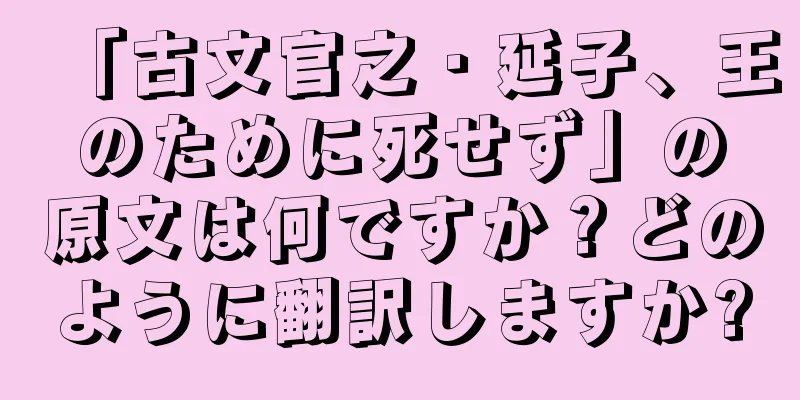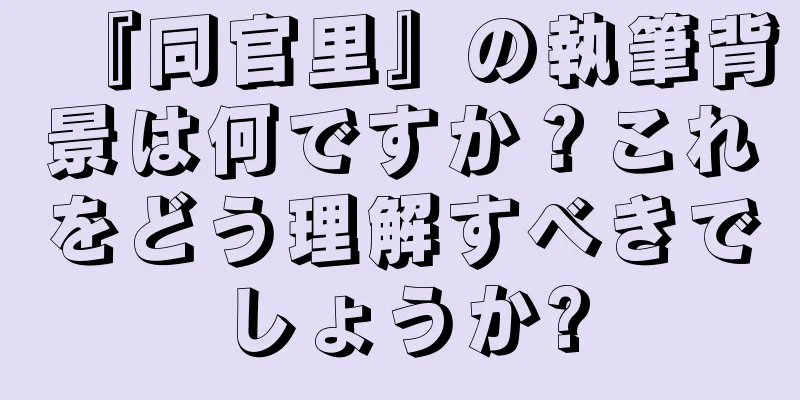「3つの戦略」の著者は誰ですか?主な内容は何ですか?
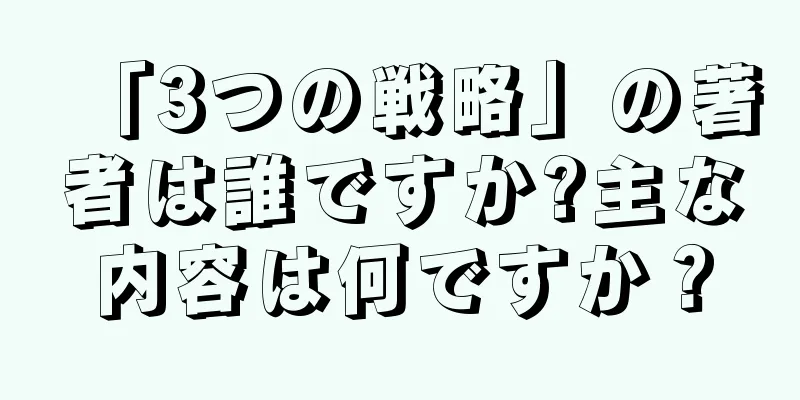
|
『三略』は主に戦略を論じた古代の軍事書です。伝説によれば、この本は秦末期に黄世公によって編纂され、張良に与えられたと言われています。原題は『黄世公記』で、『黄世公三策』とも呼ばれ、黄世公の著作とされた。『隋書・経書』でも「夏邑の神人が書いた」とされているが、どちらも信憑性に欠ける。著者の正体と名前はもはや追跡不可能です。張良の事績を熟知し、黄世公を装った王莽に対抗した、軍事戦術に精通した西漢末期の隠者ではないかと推測されている。いわゆる「三計」とは、上計、中計、下計の3巻からなる軍事戦略を指します。 『三つの戦略』は出版後すぐに社会的注目を集め、広く流布されるようになった。内容の一部は『後漢書・襄公伝』に引用されている東漢光武帝の「勅旨」から抜粋されたものである。この本は『隋書書誌』に初めて記録されて以来、すべての王朝の古代書籍目録に記録されてきました。既存のバージョンは 140 以上あります。これらの多数のバージョンは、大まかに 2 つのシステムに分けられます。 1つ目は「群書志瑶」の体系であり、2つ目は「七兵経」の体系です。 『群書之瑶』は唐代の皇帝の命により魏徴らが著した。唐代以前の多くの古代書物の概要を留めています。 『三略』は彼が選んだ古書の一つで、全23段落から成っています。内容と順序から見ると、『七兵経』版と基本的に一致していますが、文章に若干の違いがあります。いくつかの文章は『七兵法典』の原本には載っておらず、『七兵法典』の編集者によって削除された可能性があります。これは、『群書志瑶』版が『三洛』の本来の姿に近いことを示しています。より古いバージョンが発見されるまでは、これは「三録」の古代バージョンの代表作とみなすことができます。 『七兵経』は北宋元豊年間に朱甫、何曲飛らが編纂した軍事教科書である。そのため、広く流通し、大きな影響力を持っています。このシステムには最も多くの書籍もあります。現存する最古のバージョンは、南宋の孝宗皇帝と光宗皇帝の治世中に出版されました。 1935年、上海の商務出版局は中華学芸会から借りたフィルムを使って作品のコピーを作成し、「古書貴重書続」シリーズに収録しました。これが今日入手可能なより完全なバージョンです。後の『Siku の完全図書館』や『完全コレクション シリーズの初版』など、多くの一連の書籍にこのバージョンが収録されました。国内で最も普及しているこの版から、単巻版、平文版、注釈版など多くの版が生まれました。 『三録』は『上録』『中録』『下録』の三巻に分かれており、約3,800語あります。失われた古代軍事書『軍予言』や『兵力』から多くの文章を引用し、道教、儒教、法家、兵学派の観点を取り入れて、黄老道教の特色を持つ独自の思想体系を形成している。その内容を要約すると、主に 2 つの側面があります。 1. 彼は道徳、仁義礼節を統合した政治哲学を提唱し、軍事弁証法の素朴な精神を持っていた。 『三計』には「道徳、仁義、礼は五つで一つである。道は人が従うものであり、徳は人が得るものであり、仁は人が愛するもの、義は人が行うべきものであり、礼は人が体現するもので、一つたりとも欠けてはならない。故に、早起き遅寝は礼の原則であり、敵を討つことは義の決意であり、慈悲は仁の表現であり、自他を儲けることは徳の道であり、人を平等にしてその地位を失わないことは道の転化である」とある。ここで「道」とは、前漢の黄老思想による世界と物事の成り立ちと法則の説明であり、「徳」とは「道」の理解と具体的な応用である。 「仁」、「義」、「礼」はそれぞれ儒教の社会的規範と道徳的規範です。 『三略』におけるこれらの概念の説明は、基本的には前漢時代の黄老学派や儒教の見解と一致しています。 「道」の重要な地位と基本的な役割を認める一方で、「道徳、仁義、礼」の五つの要素は相互に関連し、切り離すことのできない全体であり、国家を統治する鍵であると信じています。しかし、「三計」の政治哲学体系は、主に道教と儒教の観点が混ざり合ったものである。 三つの戦略はまた、戦争の理解が客観的条件の許容範囲を超えてはならないことを強調しています。彼は「終わりはまだ見ていないので、誰もそれを知ることはできない。天地の神は物事とともに動く。変化は予測できず、敵に応じて変化する。事前に計画することはできず、時流に従うしかない」と信じていました。つまり、戦略と戦術は、敵の状況の変化に応じて策定または変更する必要があります。 「三つの戦略」では、「柔よく剛を制し、弱よく剛を制す」とも考えられています。鍵となるのは、「柔よく適所を、剛よく応用を、弱よく用い、強よく加える」こと、つまり、相反するものが互いに転化できるという弁証法的な関係を利用し、転化の条件を柔軟に把握することです。 『三兵法』は英雄と大衆、将軍と兵士などの関係を論じる際にも、双方の関係に注目し、「英雄は国家の背骨であり、庶民は国家の礎である」「軍を指揮し権力を握るのは将軍であり、勝利を収め敵を倒すのは人民である」と考えていた。これにより、一方的な理解をある程度回避できます。 2. 先人の戦略思考と軍事思想を継承し、発展させた。 「三策」の戦略思考と軍事管理思想の核心は、民心の獲得である。政治戦略の面では、「三計」は「民を重んじる」ことと「国を治める道は賢民に頼る」ことを提唱した。国を豊かにするには、まず民を豊かにしなければならないと強調した。「兵を起こすには、まず恩恵を与えなければならない。国を征服するには、まず民を養わなければならない。」この考えは軍隊の運営にも反映されるべきであり、「貢献した者には報奨を与え、その意思を国民に知らせる」というものである。このようにしてのみ、3 つの軍隊を 1 つにまとめることができます。これらはすべて、『兵法』の「上意に民を同調させる」や『武子』の「民を教えて万人に寄り添う」という戦略思考を継承し、発展させたものである。軍事戦略の面では、「三計」は「兵法」の「荒地には進軍し、攻囲地には計略する」「易きを遠ざけ難きを招来する」という思想を発展させ、戦略上の位置を「堅固」「難」「堅固」の3つにまとめ、それぞれ「防御」「封鎖」「駐屯」の3つの制御戦略を提唱した。軍事管理の考え方としては、秦以前の軍事書のように仁と厳の両立や信憑性のある賞罰を主張するほか、将軍の選抜と活用に特に重点が置かれました。将軍に求められるのは、『兵法』の「智・信・仁・勇・厳」や『武子』の「理・覚・決・用・節」だけではなく、主に道徳的な基準である。将軍に「思慮深く、勇敢で、行動力があり、怒れる」よう明確に訓戒する一方で、将軍には豊富な政治経験、幅広い知識と才能、つまり「明晰で、冷静で、平和で、秩序があり、助言を受け入れ、訴訟を聞き、人々を包摂し、意見を集約することができ」、「国の風習を理解し、山河を描き、危険や困難を指摘し、軍事力を制御できること」も要求している。また、「三策」には、人材を採用し、将軍をコントロールし、人材を採用するという考え方が浸透しており、縁故主義に反対し、強みに応じて人材を採用することを提唱している。これらは今日でも参考資料として役立ちます。 「三計」は古代の軍事学において重要な位置を占めています。宋代の趙公武は『君寨独書志』で「この書は軍略の巧妙さと厳格で明確な決断について論じている。このような明確で素晴らしい決断によって、軍隊は生き残るか死ぬか、国は生き残るか滅びるかが決まる」と述べている。『四庫全書総目録要』でも、この書の主な目的は「戦略の変化を観察し、まず無敵の立場を確立し、敵に勝つことを求める。その戦術は非常に巧妙で、軍師はしばしばそれを使用するかもしれない」とされている。古来、多くの学者が『三略』に注釈を付け、研究してきた。南北朝時代にも注釈本が存在し、宋代から清代末期までだけでも60人以上が注釈をつけた。現存する最古の注釈本は宋代の史子美の『七書講釈・三兵法講釈』であり、最も影響力のあるのは明代の劉隠の『五経七書直説・三兵法直説』で、「各本を比較し、相違点と類似点を注釈し、特に他家の本と比較して詳細である」(『四庫全蔵総目録要』)とされている。また、清代の朱鎔の『七経集釈・三兵法集釈』は、各学者の意見を集めて解説しており、「三兵法」研究の優れた参考資料となっている。 「三つの戦略」は早くから海外でも広まり、研究されていました。少なくとも我が国の唐昭宗以前には、この本はすでに日本に伝来しており、さまざまな写本や印刷版が次々と出版され、日本の『三略』研究の成果も数多く生み出されました。現存する最古の南宋版は現在も日本の岩崎家静嘉堂に保管されている。 『山麓』は日本に伝わった後、韓国にも伝わりました。我が国には、韓国語で印刷された『山麓志傑』が3巻、今も所蔵されています。中華民国以降、中国ではこの本の翻訳と注釈において一定の成果があったものの、体系的な研究論文は多くありません。 1986年に徐宝林が執筆し、人民解放軍出版社から出版された『黄世公の三つの戦略の簡潔な紹介』は、分かりやすく、内容が豊富で、一定の参考価値がある研究書であり、一読の価値がある。 |
推薦する
林布の草詩の傑作:典江口:経姑年々
以下、Interesting History 編集者が林布の『電江口書・金庫年年』の原文と評価をご紹...
桓公三年に古梁邇が書いた『春秋古梁伝』には何が記されているか?
古梁雉が書いた『春秋実録』の桓公三年に何が記されているのか?これは多くの読者が気になる疑問です。次に...
周瑜と魯粛は政治的見解が異なっていました。なぜ周瑜は魯粛を後継者に推薦したのでしょうか。
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』の石向雲は賈家の財産の没収をどのように暗示しているのでしょうか?彼女は何て言ったの?
小説『紅楼夢』に登場する石向雲はとても特別な女性ですが、これについて何を思い浮かべますか? 『紅楼夢...
古代人は時々少し愚かだった。顔嬰は斉の国を安定させるために「2つの桃で3人の男を殺す」ことをした。
三国時代には、才能を見抜く名人がいました。劉紹はこう言っています。「大いなる力は裏切り者のようで実は...
「超然台記」を鑑賞するには?創作の背景は何ですか?
チャオランタイジ蘇軾(宋代)すべて見る価値があります。見るものがあれば、楽しむものがあり、それは必ず...
『紅楼夢』では、孫紹祖はすでにお金を失っていたのに、なぜまだ迎春と結婚したかったのでしょうか?
周知のように、「紅楼夢」の賈応春は孫紹祖と結婚した後、良い生活を送れなかった。これは賈奢が以前に孫紹...
『三朝北孟慧編』第162巻の主な内容は何ですか?
『延行』第二巻は62部構成です。それは紹興4年9月19日に始まり、同日に終わりました。 10月10日...
恵州の三つの彫刻とは何ですか?徽州の3つの彫刻はどの王朝に由来するのでしょうか?
まだ分からないこと:恵州の三つの彫刻とは何ですか?恵州の三つの彫刻はどの王朝に由来するのですか?...
国語:斉語·桓公の君主覇権全文と翻訳注釈
『国語』は中国最古の国書である。周王朝の王族と魯、斉、晋、鄭、楚、呉、越などの属国の歴史が記録されて...
賈憐は林黛玉にとって大きな助けであるのに、どうして重荷になるのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
『木蘭花人・中秋節』をどう理解すべきか?創作の背景は何ですか?
木蘭花人·中秋の名月新奇集(宋代)今夜の哀れな月はどこへ行くのでしょうか?東の光と影が見える別の世界...
「彭公安」第235話:青峰を追いかけて偶然泉真寺に入り、金を生き埋めにする策略を企てる
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
曹魏と蜀漢、どちらが後世の正統王朝だと考えているのでしょうか?
三国時代の正統な王朝は誰だったのでしょうか?曹魏、蜀漢、それとも孫武でしょうか?三国時代、曹魏だと言...
『微笑み誇り高き放浪者』における馮青阳の武術はどれほど優れているのでしょうか?馮青阳はどんな武術を知っていますか?
馮青阳は金庸の武侠小説『微笑矜持放浪者』の登場人物である。彼はもともと華山剣派に属しており、金庸の小...