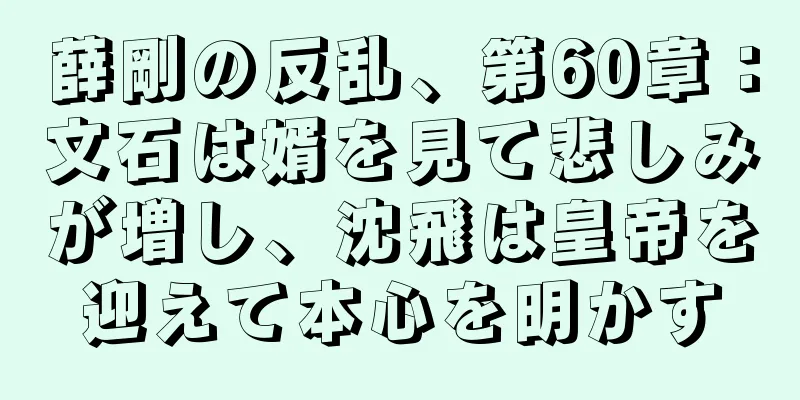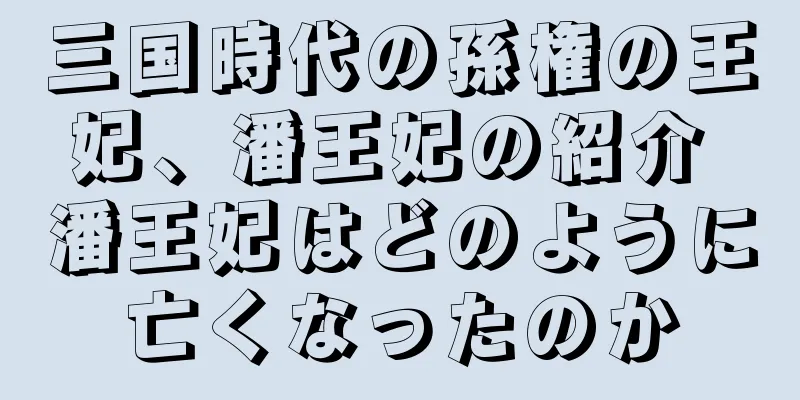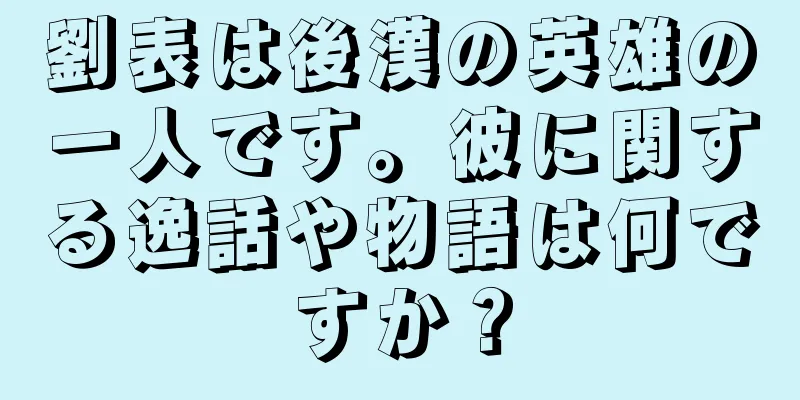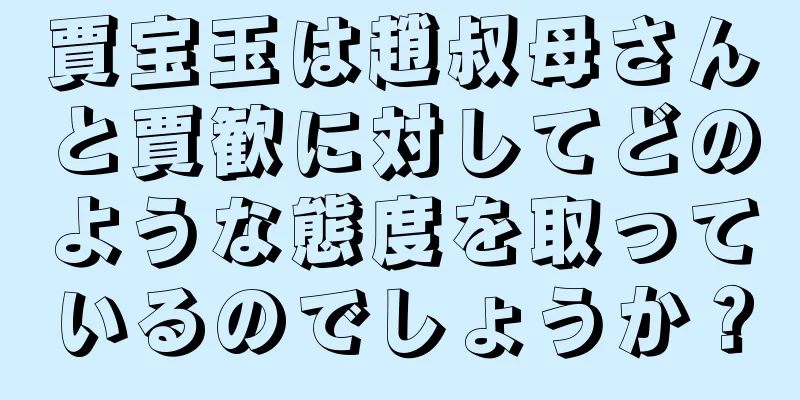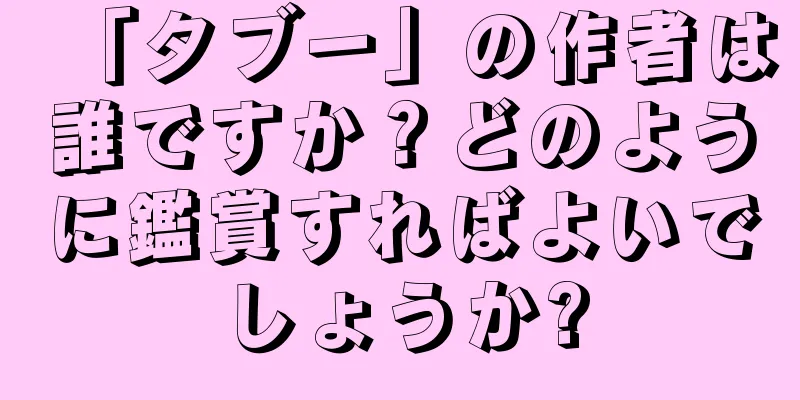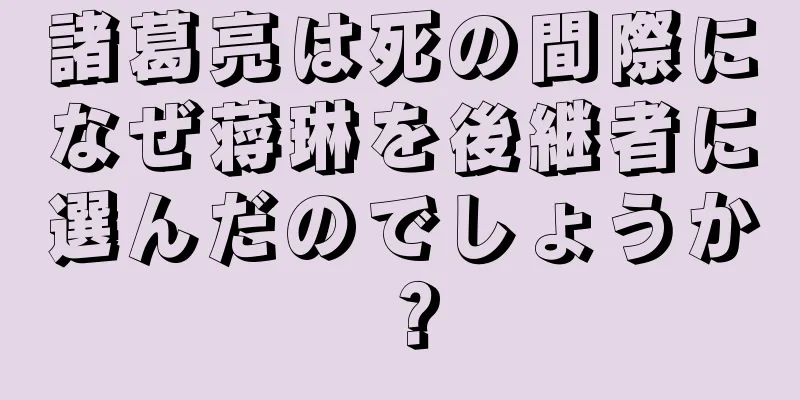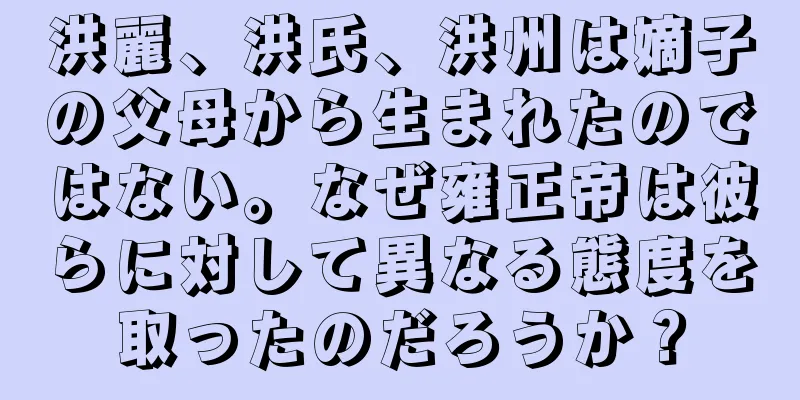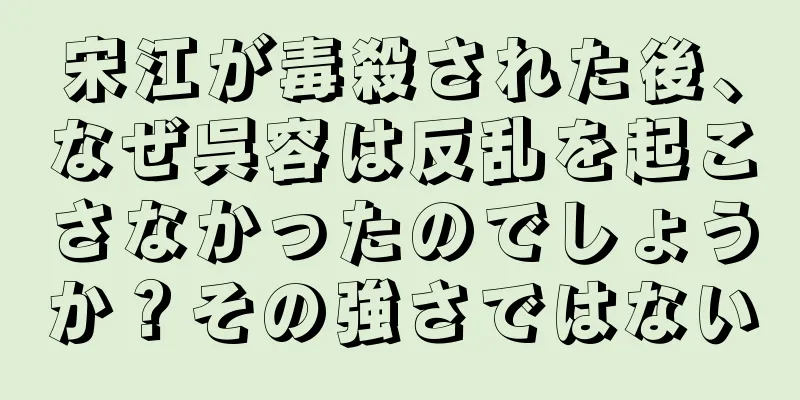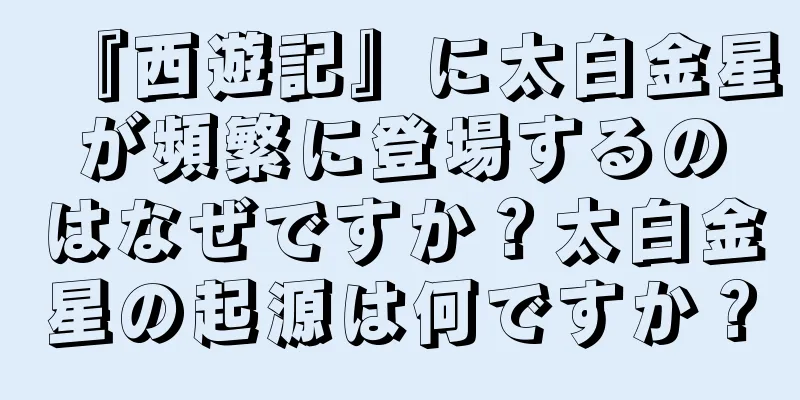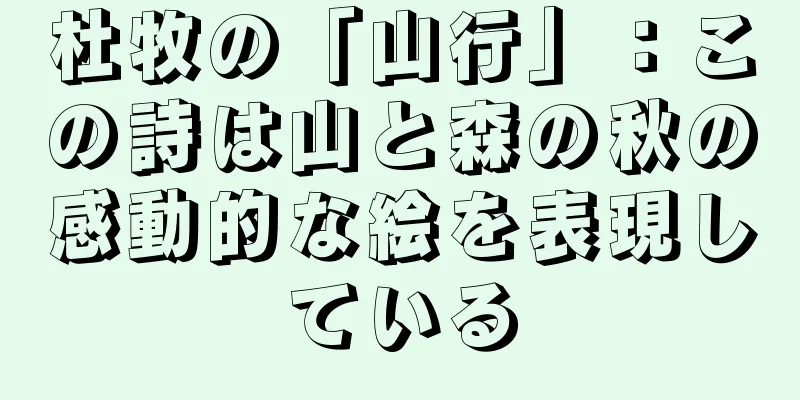孟子:梁慧王第二章第10節原文、翻訳および注釈
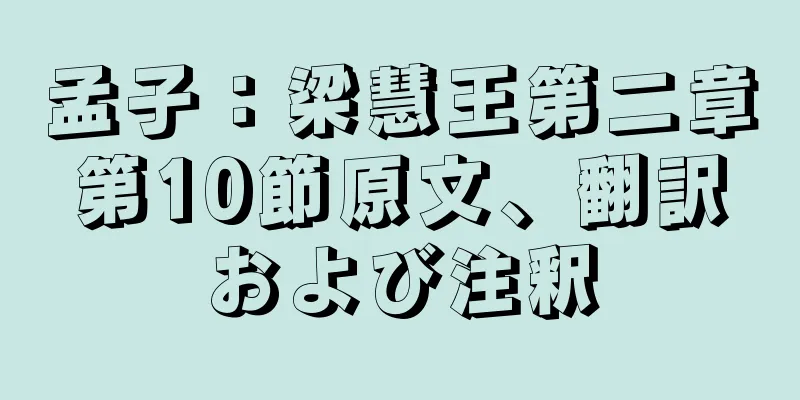
|
『孟子』は儒教の古典で、戦国時代中期に孟子とその弟子の万璋、公孫周らによって著された。『大学』『中庸』『論語』とともに「四書」と呼ばれ、四書の中で最も長く、最後の書である。清代末期まで科挙の必修科目であった。 『孟子』は全部で7章から成り、孟子と他の学派との論争、弟子への教え、君主への働きかけなどが記録されている。彼の教義の要点は、性善説と老人の保護と道徳的統治である。 孟子『梁慧王』第二章第10節 【オリジナル】 斉の民は燕を攻撃してこれを打ち破った。宣王は尋ねた。「取るなと言う者もいれば、取るべきだと言う者もいます。一万台の戦車を持つ国が一万台の戦車を持つ他の国を攻撃すれば、征服するのに50日しかかかりません。人間の力ではそれはできません。私が取らなければ、必ず天から災いが降りてくるでしょう。取ることについてどうお考えですか?」 孟子は答えた。「燕の民が喜んで取るなら、取ってしまえ。武王のように、昔はそうした者もいた。燕の民が喜んで取るなら、取ってはならない。文王のように、昔はそうした者もいた。一万の戦車を持つ国が一万の戦車を持つ他の国を攻撃するとき、他に何ができるだろうか?それは水と火を避けることだ。水が深くなり、火が熱くなるのは、ただ運の問題だ。」 【翻訳】 斉は燕を攻撃してこれを打ち破った。斉の宣王は尋ねた。「燕を併合するなと進言する者もいれば、併合すべきと進言する者もいた。私はこう思った。『一万の戦車を持つ国は、一万の戦車を持つ他の国を50日で征服できる。人間の力だけでは、この目標を達成することはできない。これは神の意志に違いない。併合しなければ、神は我々が神の意志に背いたとみなし、災いをもたらすだろう。併合についてどうお考えですか?』」 孟子は答えた。「もし併合することで燕の民が喜ぶなら、併合すればいい。昔の人はそうしていた。周の武王がその一例だ。もし併合することで燕の民が不幸になるなら、併合するな。昔の人はそうしていた。周の文王がその一例だ。一万台の戦車を持つ国が燕を攻撃しようとしている。一万台の戦車を持つ国が燕を攻撃しようとしているが、燕の民は米籠と酒壺で王の軍隊を迎え入れる。他に意味があるだろうか?ただ深い水と熱い火の苦しみを避けるためだ。逆であれば、水が深ければ火も大きくなり、燕の民はただ逃げ出すだけだ。」 【注意事項】 (1)斉の民が燕を攻めてこれを破った。斉の宣王の5年(紀元前315年)のことである。燕の快王は燕の国を宰相の子治に譲った。燕の民は不満を抱き、将軍の史北と太子の平を派遣して子治を攻撃させた。子治は反撃し、史北と太子の平を殺害した。斉の宣王は、状況を利用して広章を派遣し、燕を攻撃させた。燕の兵士は戦わず、城門も閉じられなかった。燕の快王は亡くなり、斉はすぐに勝利を収めた。 (2)取らなければ天災が起こる:同様の言葉は秦以前の時代の古書によく見られ、当時は流行した概念だったはずだ。 (3)文王:『論語』太伯によれば、周の文王は帝国の3分の2を支配していたが、依然として商王朝に仕えていた。 (4) 丹(石胡醤):丹(石胡醤)は古代に米を入れるために使われた竹籠であり、石(石胡醤)は米から作られた酸っぱい汁を指し、古代の人々はそれをワインの代用として使用していました。 (5)水は深くなり、火は熱くなる:馮斌によれば、この二つの文の「如」は「もし」ではなく「あたかも…のように」という意味である。 「如」は「~のような」という意味で、通常は名詞または名詞句が続きます。たとえば、「金のよう、錫のよう、玉のよう、玉のよう」(詩経、衛鋒、斉澳)などです。この意味の「如」の後に主語と述語の構造が続く場合、通常は主語と述語の間に「之」の文字があります。「川の流れのように、絶え間なく注意深く」(詩経、大耶、張武)しかし、常にそうとは限りません。「王を懲らしめて民を慰めるのは、時宜を得た雨のようだ」(孟子、滕文公下)「水が深くなるように、火が熱くなる」は後者のカテゴリに属します。 「如」が「もし」を意味する場合、それは「如+(非主語述語構造)述語要素」です。詳細は楊鳳斌著『孟子新訳』を参照。 (6) ユン:動く、逃げる、逃れる。 |
推薦する
西遊記第46章:異端者は正義の人をいじめ、猿は神聖さを示してすべての悪を滅ぼす
『西遊記』は古代中国における神と魔を題材にした最初のロマンチックな章立ての小説で、『三国志演義』、『...
唐の詩や歌の歌詞から春の精神を探ると、詩人たちはどのような情景を描いたのでしょうか。
歴史上、春を描写した唐詩や歌の歌詞は数多くあります。Interesting History の次の編...
杜牧は愛する人が他の人と結婚したときに悲しい恋の詩を書いた
おもしろ歴史編集長と一緒に杜牧の詩を鑑賞しましょう!唐代は詩歌の発展が最も栄えた時代であった。唐代末...
『紅楼夢』の慧娘の正体は何ですか?彼女の存在の意味は何でしょうか?
『紅楼夢』を注意深く読まないと、多くの人がその中の脇役たちの一部を見逃してしまうかもしれない。多くの...
唐代の杜甫の最も孤独な詩、ほぼ最後の作品
文部省が編纂した高校の中国語教科書には、古文のテキストが大量に収録されているが、古詩の数は少ない。し...
外交問題は極めて重要です。漢王朝は何をしたのでしょうか?
漢王朝の初期、国力は弱かった。匈奴に敗れた後、他の少数民族は漢王朝に対してさまざまな考えを持つように...
三勇五勇士における武術の本当の順位は?最も強い武術を持つのは誰ですか?
中国の武侠小説には、有名な登場人物や武侠が数多く登場します。中でも『三勇五勇士』は古代中国の小説の古...
『呂氏春秋・直義の価値について』における知識と悟りの内容は何ですか?どのような考えが表現されていますか?
中国の伝統文化は歴史が長く、奥が深いです!今日は、Interesting Historyの編集者が「...
『石のうなずき』:明代の田然智蘇が書いた短編小説集。各巻に短編小説が1編ずつ収録されている。
『石のうなずき頭』は、『世を目覚めさせる第二の奇書』、『今昔五続奇譚』、『鴛鴦の書』としても知られ、...
初版本『楚科派安経奇』第31巻:王大使の部下は脅迫され、李燦俊の不当な復讐は死の前に
『楚科派安経記』は、明代末期に凌孟初が編纂した俗語小説集である。この本は、一般大衆に人気のある「疑似...
張勲の『笛を聞く』は、危険に直面しても恐れを知らない詩人としての姿勢と、死を冷静に受け止める気高い精神を表現している。
張勲(号は勲)は唐代の官僚である。安史の乱の際、彼は必死に綏陽を守り、反乱軍の南進を阻止し、江淮地域...
白居易の古詩「坐詠」の本来の意味を理解する
古代詩「座って詠む」時代: 唐代著者: 白居易彼はかつては都の名客だったが、今では世間では落ちぶれた...
第44章:蜀占は三脚を奪って晋侯に抵抗し、仙高は秦軍に報奨を与えるために偽の命令を出す
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
古代詩作品の鑑賞:『詩経』『周宋』『清妙詩志』
○清寺牧清寺では厳粛で平和な様子が見られました。才能のある人はたくさんいますが、皆徳のある人です。天...
「山中の宰相」陶洪景の詩と書の特徴は何ですか?
陶洪景(456-536年)は、号を同明といい、南朝の人です。宋、斉、梁の三代に仕えました。かつては官...