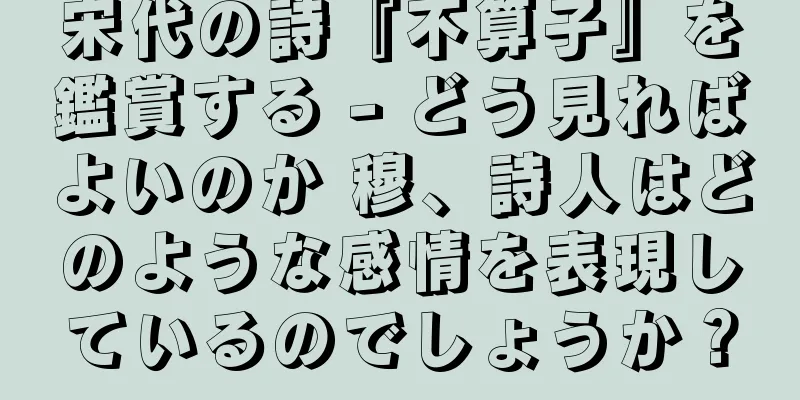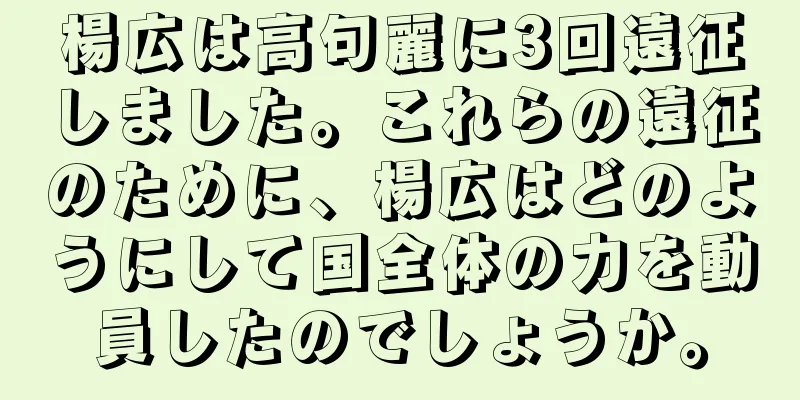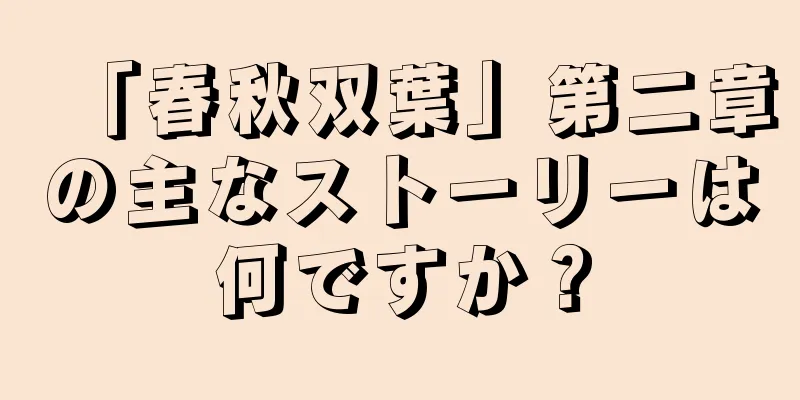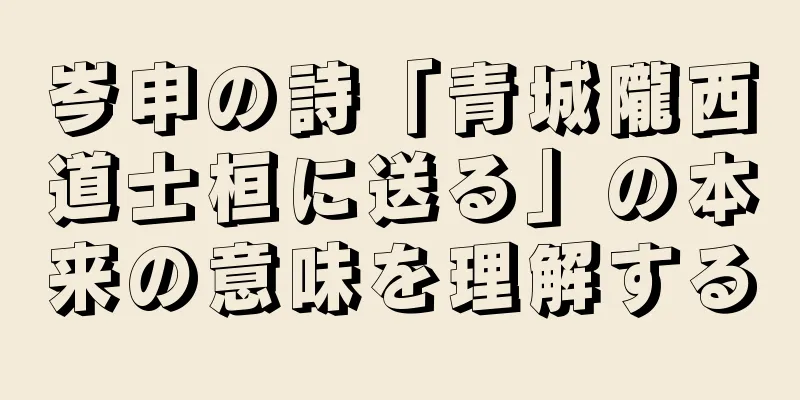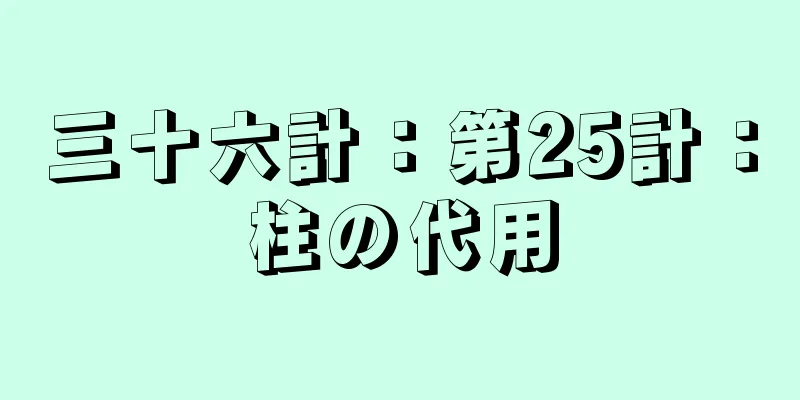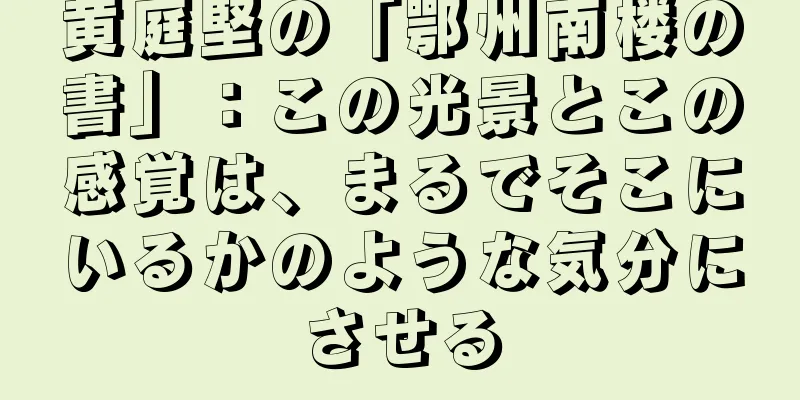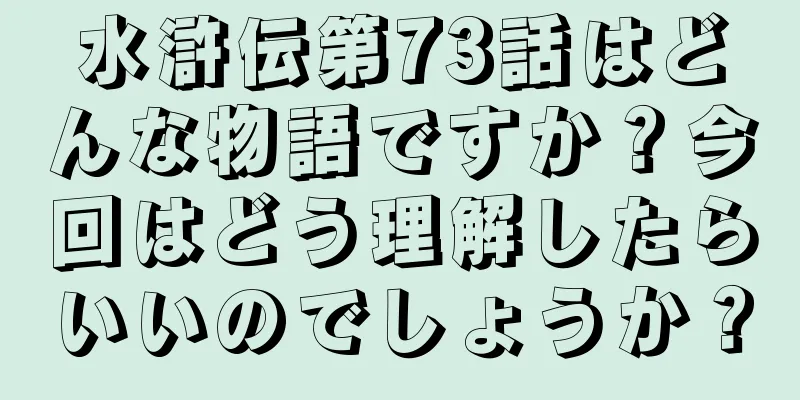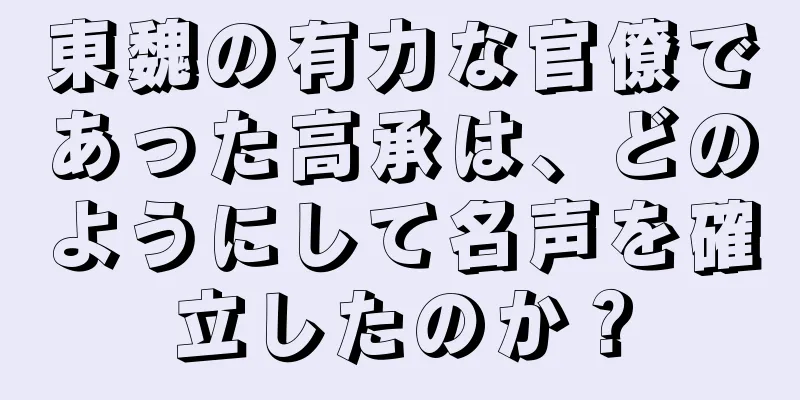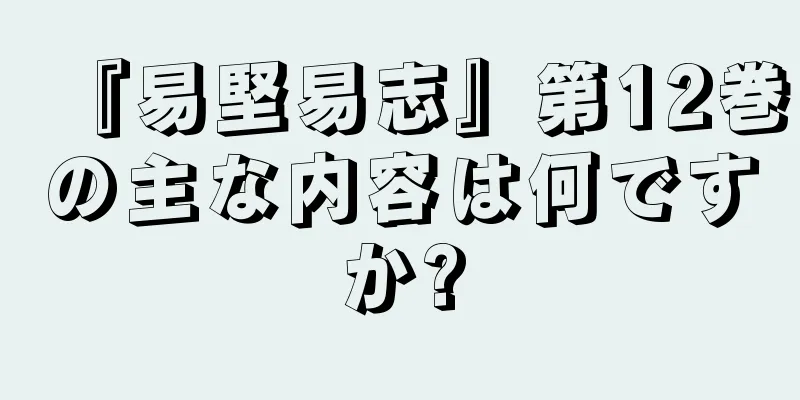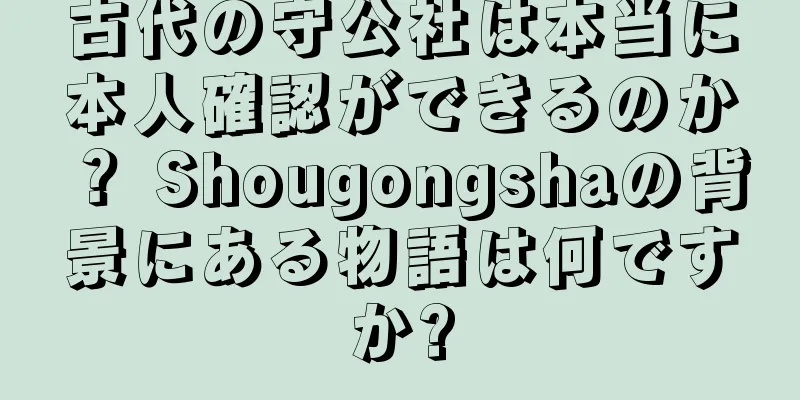『緑氏春秋・中秋記』に描かれた学者たちの愛の真実とは?
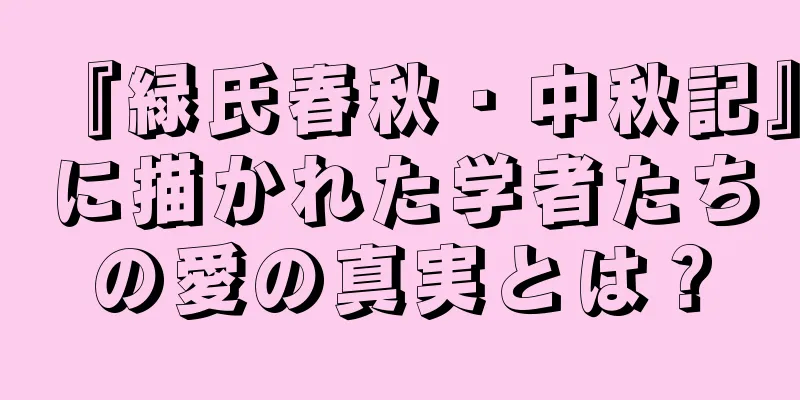
|
『呂氏春秋・中秋記』に書かれた学者の愛に関する真実とは何でしょうか? どのように理解すればよいのでしょうか? これは多くの読者が知りたい質問です。 次の興味深い歴史の編集者があなたに詳細な紹介をします。 見てみましょう。 【オリジナル】 人々は寒いから服を着るし、お腹が空くから食べ物を食べる。飢えと寒さは人類にとって最大の害です。彼を救うことは正義である。民衆の貧困は飢えや寒さと同じくらい深刻であるので、賢明な統治者は苦悩する民衆を憐れみ、彼らの貧困を気の毒に思わなければなりません。このようにして、あなたの名前は有名になり、国民的英雄になるでしょう。昔、秦の穆公が馬に乗っていたとき、馬車が故障し、右の衣服が失われ、野人がそれを盗んでしまいました。穆公は自らそれを探しに行き、祁山の南側で野人たちがそれを食べようとしているのを見ました。 穆公はため息をついて言った。「立派な馬の肉を食べて、それを飲みに返さないと、娘を傷つけるのではないかと心配だ!」そこで、馬の肉を全部飲んで立ち去った。 1年後、漢源の戦いで、金軍は穆公の戦車を包囲した。金の梁有密はすでに穆公の左馬を捕らえていた。金の恵公の右馬車の御者、石芬は槍を穆公の鎧に投げつけ、6回刺した⑤。岐山の南側には馬肉を食べた蛮族が300人以上いた。彼らは馬車の下で穆公のために激しく戦い、金を打ち破り、恵公を捕らえて連れ戻した。 これは『雅歌』の「君主が高貴な人であるときは、清廉にして徳を積むべきであり、君主が謙虚な人であるときは、寛大にして力を尽くすべきである」という意味である⑥。君主が徳を積んで人民を愛するように努めないわけにはいきません。君主が徳を積んで人民を愛すれば、人民は君主に近づきます。人民が君主に近ければ、皆喜んで君主のために命を捨てるでしょう。 【注意事項】 ① 兵士を愛せよ:リーダーは兵士を愛すべきであり、兵士はリーダーのために戦うべきだと主張している。これが戦いにおける生死の鍵である。 ② 右馬車:馬車は4頭の馬で引かれます。真ん中の2頭を左馬車、右側の1頭を右馬車といいます。 ③还:「璇」と同じで、すぐに。 ④飲む:飲み物を与える、飲ませる。 ⑤漢源の戦い:晋の漢源で起こった戦争。梁有密:姓は梁有という晋の高官。左舷:馬車は4頭の馬に引かれます。両側の馬を「舷」、左側の馬を「左舷」といいます。右:車を運転する人、コーチマン。呂氏:御者の名前。 Zha: ジアイエ。 ⑥この二つの文は雅歌からのものではありません。ジュン:王になるには… 【翻訳】 人は寒いから服を着るし、お腹が空くから食べるのです。飢えと寒さは人類にとって最大の災難です。このような苦境から人々を救うのは道徳的義務である。貧困は飢えや寒さよりも悲惨なので、賢明な君主は貧困に苦しむ人々を哀れみ、悲しむべきです。これが達成できれば、君主の名は有名になり、兵士たちからも支持されるようになるだろう。 昔、秦の穆公が乗っていた馬車が故障し、右の馬が暴走して山中の木こりに追いかけられました。秦の穆公は自ら行方不明の馬を探しに行き、旗山の北側で木こりたちが馬肉を焼いているのを目撃した。秦の穆公はため息をついて言った。「立派な馬の肉を食べてすぐに酒を飲まないと、馬肉が体に悪影響を及ぼす恐れがある。」そこで、皆に酒を与えて立ち去った。 1年後、漢元の戦いが起こりました。晋の民衆は秦沐公の馬車を包囲していた。晋の梁有密は秦沐公の左馬を掴んでいた。晋慧公の馬車御者陸舜は渾身の力で竹の物を投げつけ、秦沐公の鎧六枚を撃ち抜いた。 岐山の北には、馬肉を食べて褒美をもらった木こりが300人以上いて、秦の穆公のために全力で戦車の下で戦い、すぐに晋を破り、晋の恵公を捕らえました。詩経にはこうあります。「君子である王ならば、徳の高い政策を実施し、恩恵で報いてもらう必要があります。臣下である王ならば、寛大に接し、最善を尽くしてもらう必要があります。」君主が仁徳のある政策を実施しないわけがありません。君主が仁徳のある政策を実施し、民を気遣うなら、民は上司に近づき、上司に近づいた民は上司のために喜んで犠牲を払うでしょう。 【オリジナル】 趙建子①は二頭の白いラバを飼っていて、とても可愛がっていました。陽城の徐屈は広門の役人であった。夜、門をたたいて言った。「主君の大臣徐屈が病気です。医者は『白騾の肝臓病にかかれば治るが、かからなければ死ぬ』とおっしゃいました。」使者は中に入って報告した。董安宇は彼の横を車で走り、怒って言った。「おい! 徐屈が主君のラバを殺そうとしている。すぐに処刑してくれ。」 姜子は言った。「動物を救うために人を殺すのは非人道的ではないか。人を救うために動物を殺すのは人道的ではないか。」 そこで彼は料理人を呼んで白いラバを殺させ、肝臓を取り出して陽城の徐屈に与えた。 やがて趙は軍を起こして澳を攻撃した。広門の役人たちは、左に700人、右に700人、全員が先に登り、最初の兵士⑥を捕らえました。君主が兵士を愛さないわけがない。敵が来るときはいつでも、利益を求めるためだ。今ここに来たら死んでしまうので、逃げた方が良いです。敵が全員逃げることが有利だと思っているなら、遭遇する可能性はない。したがって、もし敵が私を犠牲にして生き残ることができるなら、私は敵を犠牲にして死ぬことができる。また、もし敵が私を犠牲にして死ぬことができるなら、私は敵を犠牲にして生き残ることができる。もし私が敵の手によって生き残ることができ、敵が私の手によって生き残ることができるなら、どうして注意しないでいられるだろうか?これが軍事作戦の本質である。生存、生、死はすべて、これを知ることだけにかかっています。 【注意事項】 ①趙建子:晋の高官。 ②楊城徐曲:姓は楊城、名は徐曲。場所: 住居。広門:晋の時代の地名。 ③董安宇:趙建子の家臣。 ④愠: 怒っている。 ⑤翟:「狄」と同じで、古代我が国北部の少数民族。 ⑥甲首:鎧を着ている人の頭。 ⑦ 私のせいで敵が生き残る:私が敵を倒せなかったため、敵が生き残っていることを指します。 ⑧敵は私の手で死ぬ:敵を打ち負かし、死なせることを指します。 【翻訳】 趙建子は二頭の白いラバと馬を飼っていて、とても可愛がっていました。広門に住む下級官吏の楊城徐曲が夜訪ねてきて言った。「殿様、臣下の徐曲は病気です。医者が『白ラバの肝臓を与えれば病気は治りますが、そうでなければ死んでしまいます』とおっしゃいました。」門番は報告しに行った。傍らで仕えていた董安宇は怒って言った。「おい!徐屈は主君のラバを狙っている。どうか殺させてくれ。」趙建子は言った。「動物を生かしておくために人を殺すのは非人道的ではないか。人を救うために動物を殺すのは慈悲深い行為ではないか。」そこで彼は料理人を呼んで白ラバを殺させ、肝臓を掘り出して陽城の徐屈に与えた。 その後間もなく、趙建子は軍を率いて狄族を攻撃した。広門の役人たちは左軍700人、右軍700人を率いて真っ先に城壁に登り、武装した兵士たちの首を切り落とした。君主が兵士を大切にしないわけにはいかない。敵が侵略するのは、利益を求めるためだ。今攻撃しても死ぬだけだから、逃げるのが一番だ。敵にとって最善の戦略は逃げることなので、剣で戦う必要はありません。 だから、もし敵が私の手の中で生き残れるなら、私は敵の手の中で死ななければならない。もし敵が私の手の中で死ねるなら、私は敵の手の中で生き残れるのだ。それで、私が敵の陣営で生き残っているのか、それとも敵が私の手の中で生き残っているのか、どうして分からないのでしょうか。これが軍隊を使う微妙なところです。生死はこの真実を知っているかどうかにかかっています。 |
<<: 水滸伝 第61話:燕青は隠された矢を射て主人を救い、石秀は建物から飛び降りて処刑場を奪う
>>: 水滸伝 第62話:宋江の軍が大明城を攻撃、関勝が梁山泊を占領しようと提案
推薦する
「春の詩五篇第二」をどのように理解すればよいのでしょうか?創作の背景は何ですか?
春の詩五篇 第二集秦管(宋代)ある夜、千の雷鳴が響き、澄んだ空の光がタイルの上に緑色に不均一に浮かび...
商王朝のトーテムとは何ですか?黒い鳥とは何ですか?
商王朝のトーテムについては、歴史書や骨骨の碑文などにも多くの伝説や記録があり、そのほとんどは黒鳥によ...
黄庭堅の詩「鶉空」はどのような感情を表現しているのでしょうか?
以下に、興史編集長が黄庭堅の『鷺空:梅山の仙人、石英智が座前韻に居て即興で答える』の原文と評価をお届...
一見大勝利を収めたように見える秋通が、なぜ最も哀れな人物なのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
「忠勇五人男物語」第66話の主な内容は何ですか?
陸震は若き英雄張英のふりをして騙され、平伏させられる。男は恥ずかしさのあまり倒れてしまいました。皆が...
明王朝滅亡の理由:明王朝を滅ぼしたのは李自成か、それとも清王朝か?
もちろん李自成です。崇禎17年(1644年)1月、李自成は東に進軍して北京に向かい、寧武関を突破し、...
閻吉道の「阮朗桂・地平線の金椰子が露を霜に変える」:詩全体の芸術的構想は悲しく冷たい
顔継道(1038年5月29日 - 1110年)は北宋時代の有名な詩人である。名は書源、号は蕭山。福州...
遼・金・元の衣装:元代の金織り錦のローブ
元朝の衣服には、それ以前の王朝よりも大量の金が使われました。布地に金を加える習慣は秦の時代以前に現れ...
紅河沿いに住むハニ族の人々はなぜ「カッコウ」を崇拝するのでしょうか?
紅河沿いに住むハニ族の人々はカッコウを崇拝し、敬意を込めて「ヘボアマ(カッコウの母)」と呼んでいます...
仙府宮の建築レイアウトの特徴は何ですか?それはどのような役割を果たすのでしょうか?
仙府宮は明代に建てられた中国の宮殿建築です。仙府宮の建築レイアウトの特徴は何ですか?どのような役割を...
天子鍾馗:鍾馗が妹と結婚
中南の進士である鍾馗は、検査を受けるために北京へ行ったが、誤って鬼の洞窟に入り、顔に傷を負ってしまっ...
『紅楼夢』で最も愚かな愛人は誰ですか?家族を破滅に導く
『紅楼夢』で最も愚かな女主人は誰でしょうか?それは栄果楼の王夫人です。彼女は忠誠と裏切り、善悪の区別...
蓮の葉スープを作るための銀の型セットは、薛と嘉の違いを区別できる
『紅楼夢』の薛家と賈家はどちらも裕福な家庭です。では、賈宝玉はなぜ一言で薛おばさんの痛いところを突く...
「彭公事件」第184章:諸城の水龍神の水拠点を銃器で戦う(小火祖)
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
石碩新宇の執筆背景とその文学的価値
『世略新語』は、南北朝時代(420年 - 581年)に書かれた書物で、東漢末期から東晋にかけての裕福...