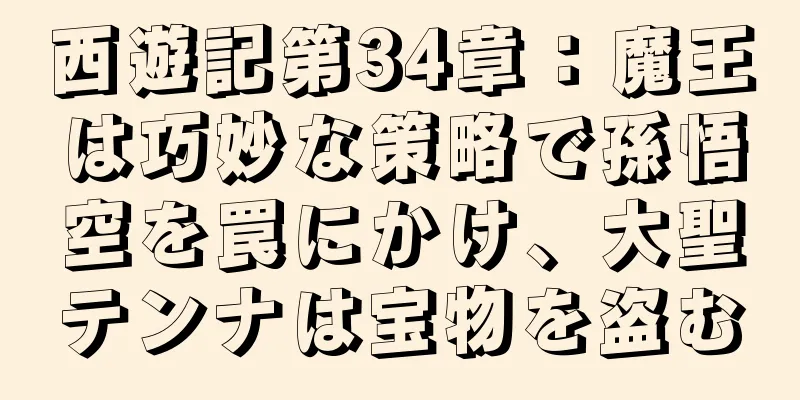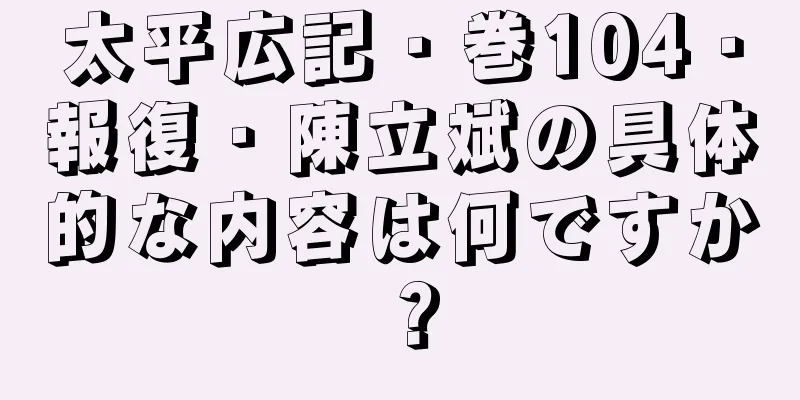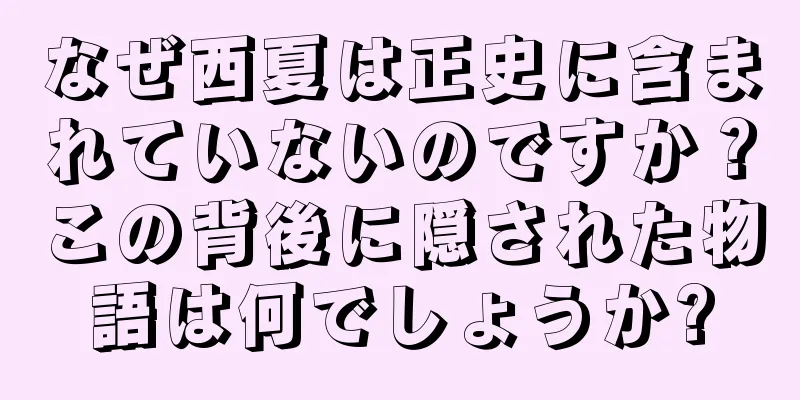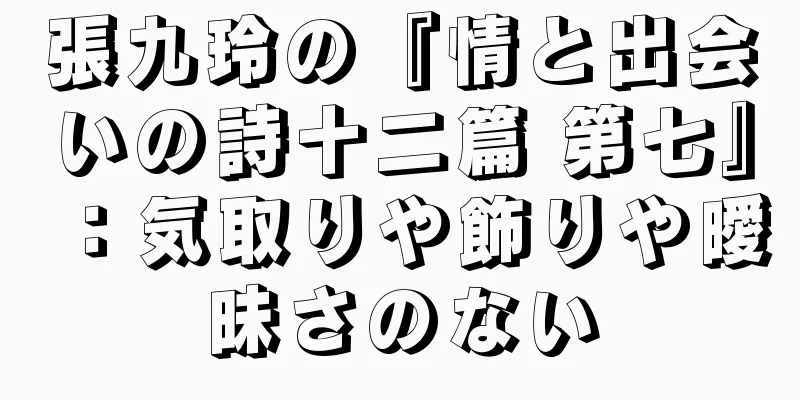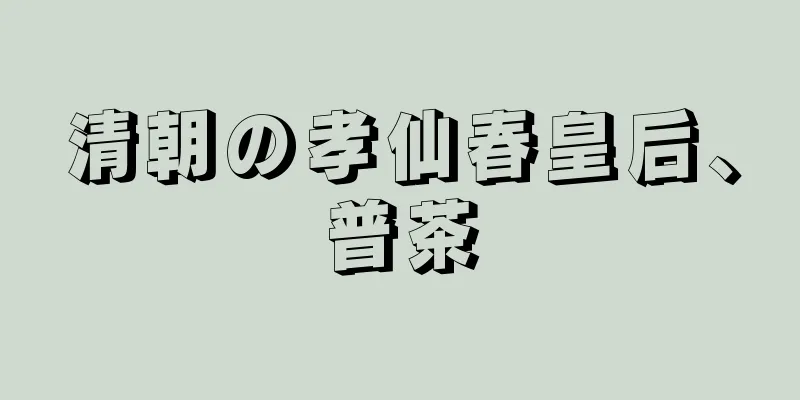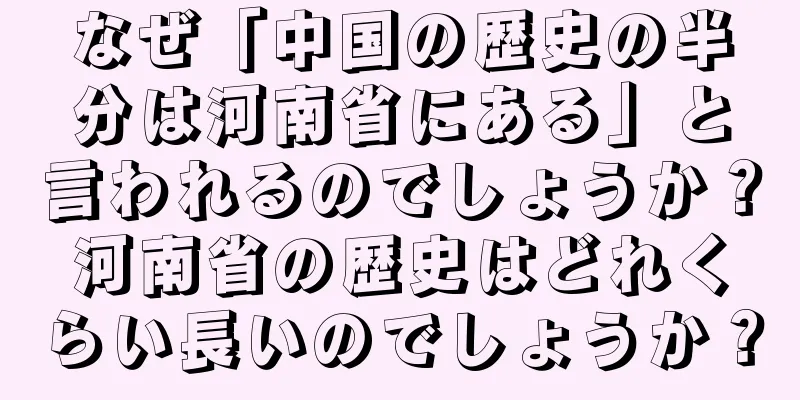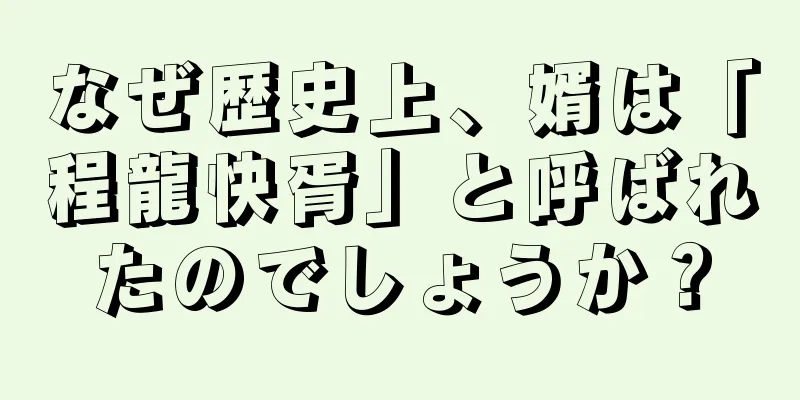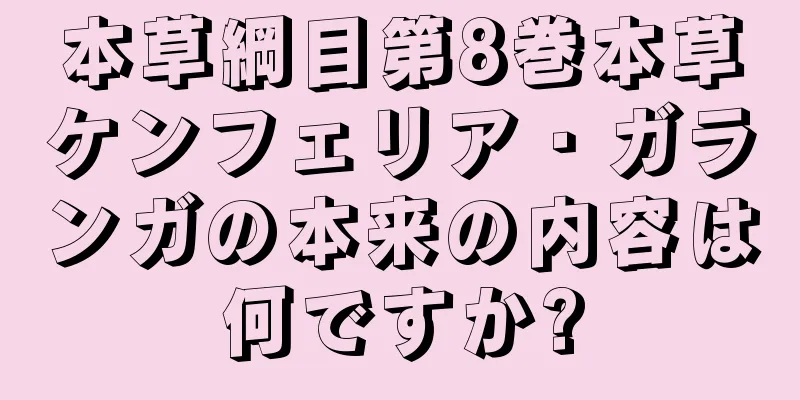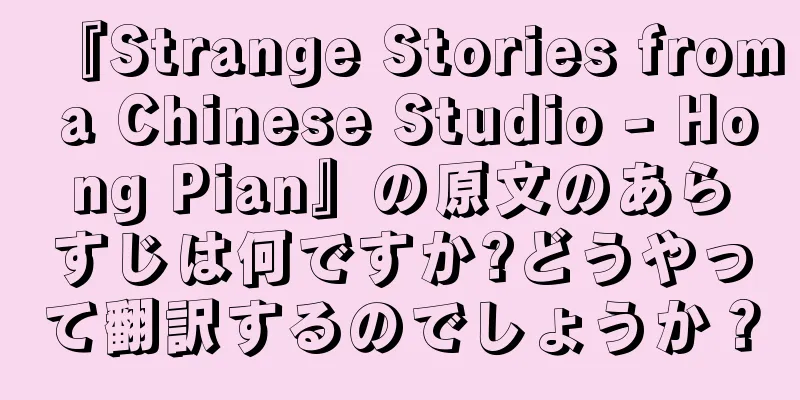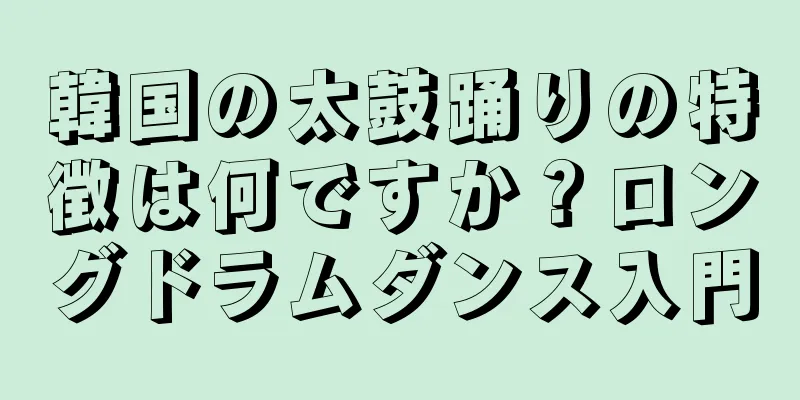本草綱目第3巻万病治癒法腸音の本来の内容は何ですか?
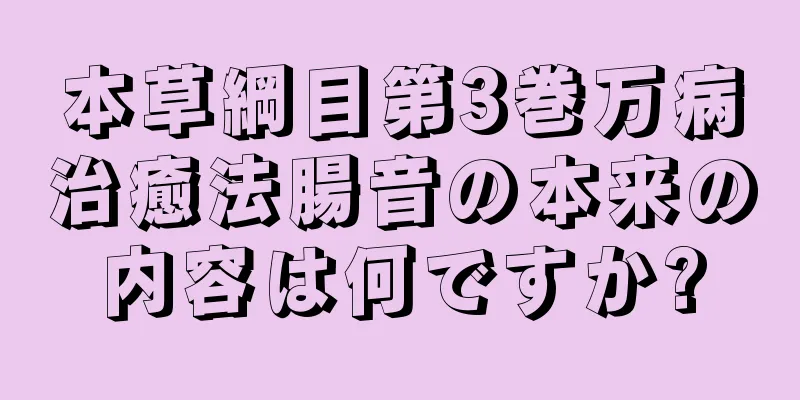
|
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の Interesting History 編集者は、皆さんと共有するために関連コンテンツを用意しました。 この本は「要綱に従って列挙する」という文体を採用しているため、「綱目」と名付けられました。 『正蕾本草』に基づいて改正された。この本には190万語以上が収録されており、1,892種類の医薬品が収録され、11,096の処方箋が収録され、1,160枚の精巧なイラストが掲載されています。16のパートと60のカテゴリに分かれています。本書は、著者が数十年にわたる実践と研究を重ね、これまでの生薬学の成果を継承・総括し、長期にわたる研究と聞き取り調査を通じて蓄積した広範な薬学知識を結集してまとめた傑作です。この本は、過去の生薬学におけるいくつかの誤りを訂正するだけでなく、大量の科学的データを統合し、より科学的な薬物分類方法を提案し、先進的な生物進化の考えを取り入れ、豊富な臨床実践を反映しています。この本は世界的な影響力を持つ自然史の本でもあります。 本草綱目 第3巻 すべての病気の治療 腸音 【名前】 エネルギーが弱まり、水分が滞り、寄生虫が蓄積します。 陳希怡の二十四節気の座禅図 6月の小暑の祭りの座禅 少陽の3つの気は動きによって支配される 時間一致手太陰肺湿土 座禅運動:毎日正陰の時間に、両手を地面に置き、片方の足を曲げ、もう一方の足を伸ばし、強く引っ張る動作を15回繰り返します。歯をカチカチ鳴らし、息を吸ったり吐いたりして、唾を飲み込みます。 治療: 脚、膝、腰、太もものリウマチ、肺の膨張、喉の乾燥、喘鳴と咳、鎖骨上窩の痛み、くしゃみ、へその右側の下腹部の膨張による腹痛、手のけいれん、体重増加、片麻痺、物忘れ、喘息、肛門脱出、手首の脱力、気分のむら。 三十六難には、内臓は腎臓を除いてすべて一つしかないとあります。腎臓は二つあります。しかし、二つとも腎臓ではありません。左が腎、右が命門です。 【腸音】 タンジン、キキョウ、ホンダワラ類:心臓や腹部の邪悪な霊を退治し、流水のような微かな雷鳴を鎮めます。昆布、女夷、女威:いずれも腸内のゴロゴロ音や上下に定位置のないガスを治療します。 Pinellia、Elsholtzia ciliata、Piper longum、Amomum villosum、Yusuan はすべて、虚弱や寒さによる腸鳴りの治療に使用されます。ユーフォルビア:腹部に痰と体液がどくどくと溜まる。みかんの皮とアーモンド:どちらも腸のゴロゴロ音の治療に使用されます。モクレン:腹部の冷えと雷が何年も続く。クチナシ:暑い。本来の蚕糞:腸がゴロゴロ鳴って中が熱い。うなぎ:冷たい空気と腸のゴロゴロ音。 |
<<: 『本草綱目第3巻 諸病虫害治療法』の具体的な内容は何ですか?
>>: 『本草綱目第3巻 諸疾患および心臓と腹痛の治療』の具体的な内容は何ですか?
推薦する
三代にわたる官僚で知られた袁家はいかにして衰退していったのか。なぜ袁紹と関係があると言うのですか?
諺にあるように、敗者には人権はない。袁紹は人権のない敗者だ。袁紹に関しては、陳寿が『三国志』を執筆す...
『長安の一番長い日』の中で唐の玄宗皇帝がなぜ「賢者」と呼ばれているのでしょうか?古代の皇帝の称号は何でしたか?
『長安の一番長い日』で唐の玄宗皇帝はなぜ「賢者」と呼ばれているのでしょうか?古代皇帝の称号は何ですか...
本草綱目第6巻土部霜の原文の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
「聖命に従って尚書楊果公を碩放に遣わす」の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
勅令により、燕の大臣が碩放に派遣された。張九齢(唐代)氏族の大臣たちは遠征に何らかの関係があり、寺院...
「小五英雄」第37章:成雲宮は酒への貪欲さから酔いつぶれ、五雲軒は夢の中で香に毒される
『五人の勇士』は、古典小説『三人の勇士と五人の勇士』の続編の一つです。正式名称は『忠勇五人の勇士の物...
古典文学の傑作『太平天国』:『封封』第10巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
安史の乱から100年経っても、唐王朝はなぜ分離主義政権を真に排除できなかったのでしょうか?
唐代末期において、封建領主たちは大きな潜在的脅威であったと言わざるを得ません。もともと唐代は国防と国...
デアン文化 デアン族の独特な水太鼓の起源は何ですか?
水ドラムの起源人々の間では水太鼓に関する興味深い伝説がたくさんあります。徳安族は古くから私たちの祖国...
武侠小説『夏科行』に登場する老魔人丁不思の紹介
金庸の武侠小説『遍歴の騎士』の登場人物。彼は丁不三の弟であり、冥界での異名は「一日に四つ以下」である...
前漢時代は商業の発展のためにどのような環境を整えたのでしょうか?外国貿易についてはどうですか?
前漢時代には、牛に引かせた鋤や鉄の道具の使用が一般的になり、手工芸産業も大きく発展しました。特に繊維...
呂后に殺されないために、韓信は当時何をすべきだったのでしょうか?
多くの人が、漢代初期の三英雄の一人である韓信について知っています。彼は劉邦が天下を取ったときに多大な...
古代の十大神話の獣の一つである碧牙とは何ですか?神話の獣ビファンの紹介
二方とは何ですか?二方は古代中国の神話における火の象徴です。ビファンの名前は、竹や木が燃えるときに出...
北京語:周游・丁王論が全正を使わない理由について語る全文と翻訳ノート
『国語』は中国最古の国書である。周王朝の王族と魯、斉、晋、鄭、楚、呉、越などの属国の歴史が記録されて...
『緑氏春秋・孟侠記』の孟侠の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
中国の伝統文化は歴史が長く、奥が深いです!今日は、Interesting Historyの編集者が『...
心に残る詩「菩薩男・明るい月は夜の正午に」を読んだ後
以下に、Interesting Historyの編集者が、文廷雲の『菩薩人・明るい月は夜の正午にのみ...