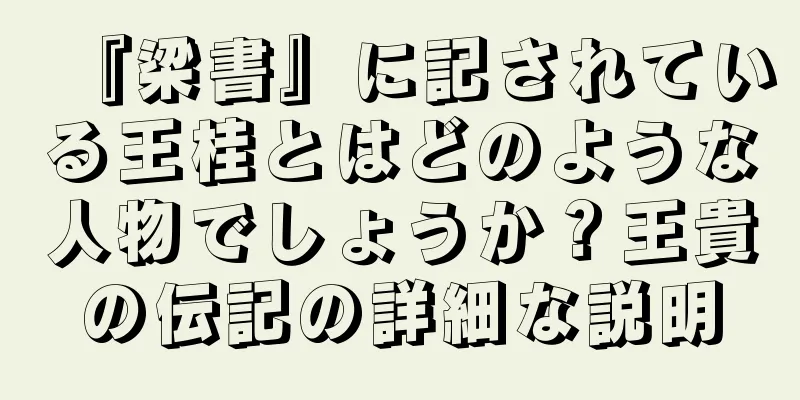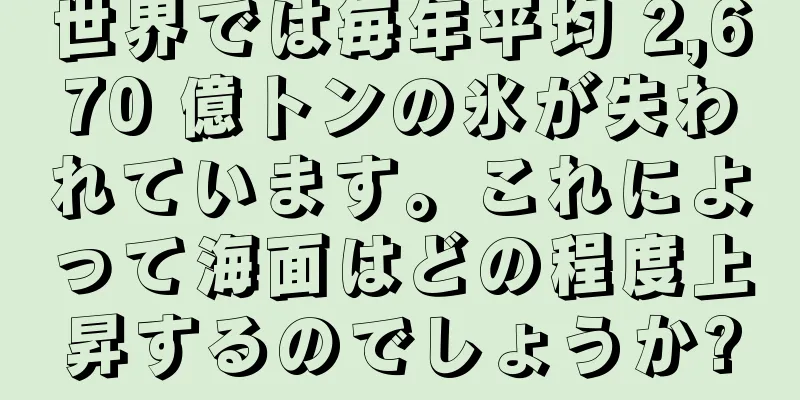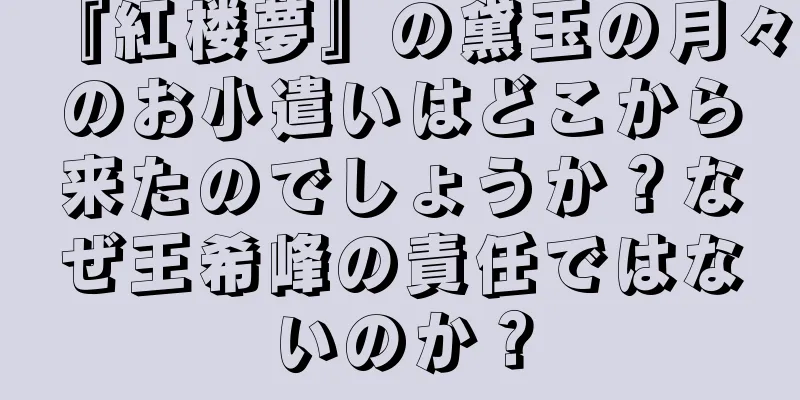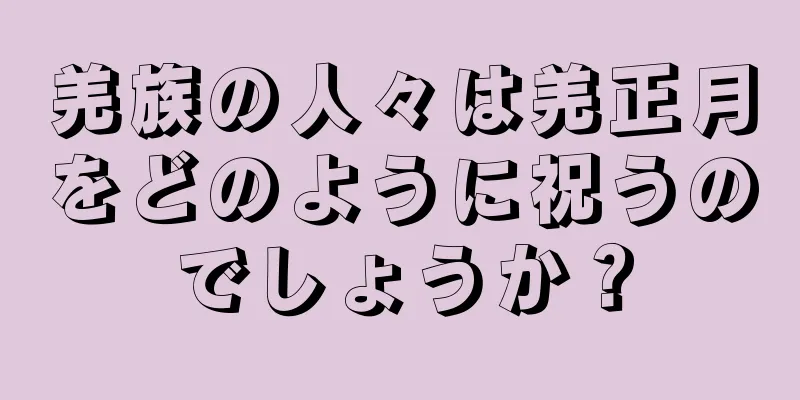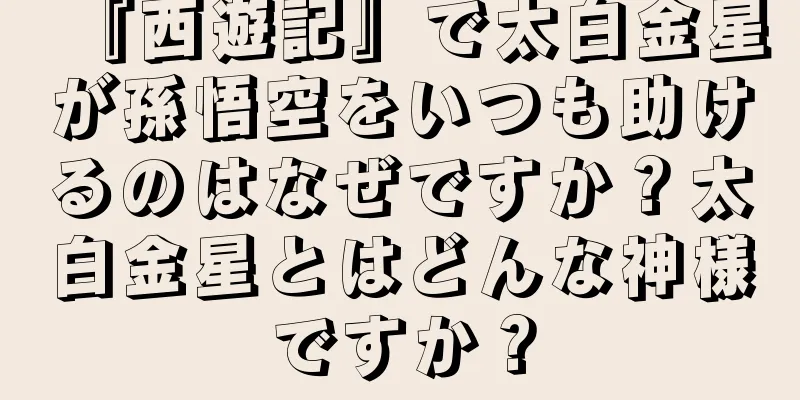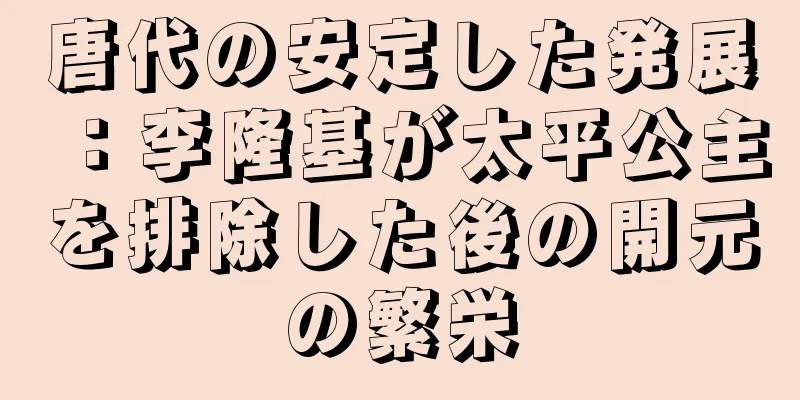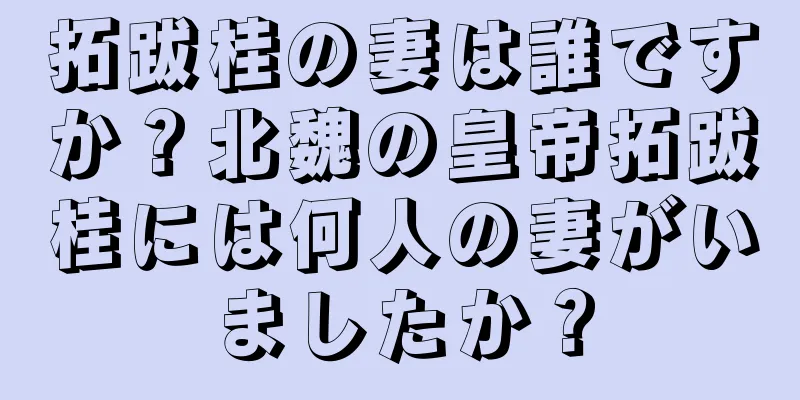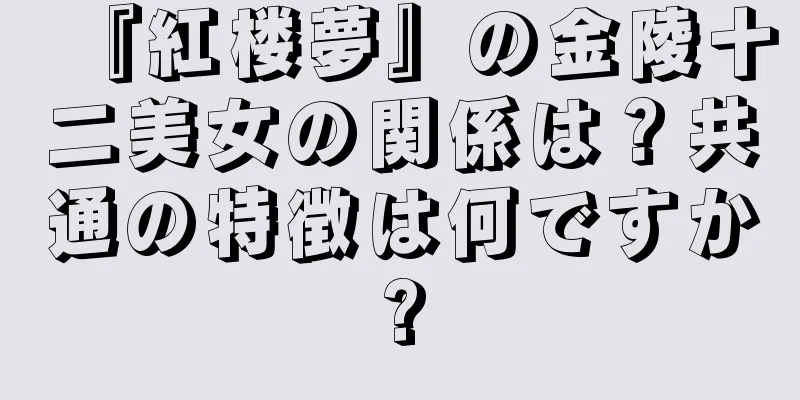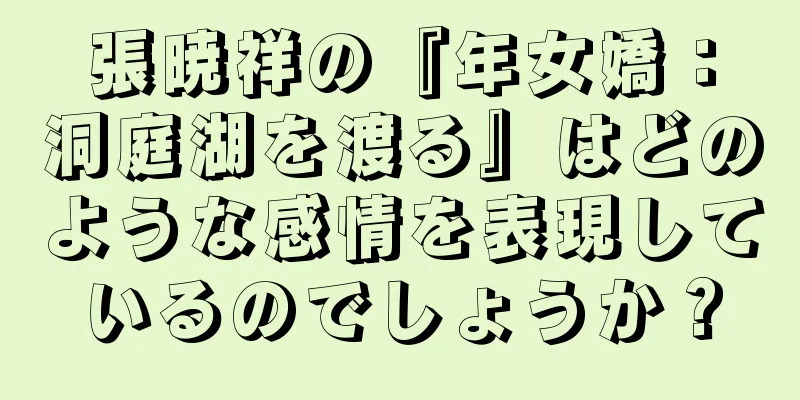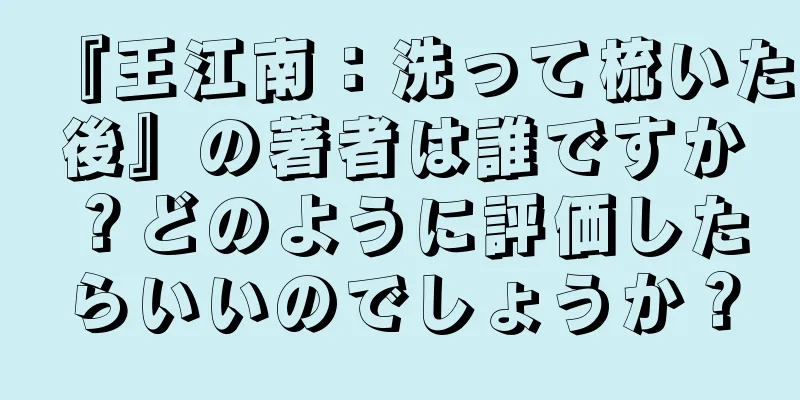古典文学の傑作『太平楽』:白谷篇第6巻全文
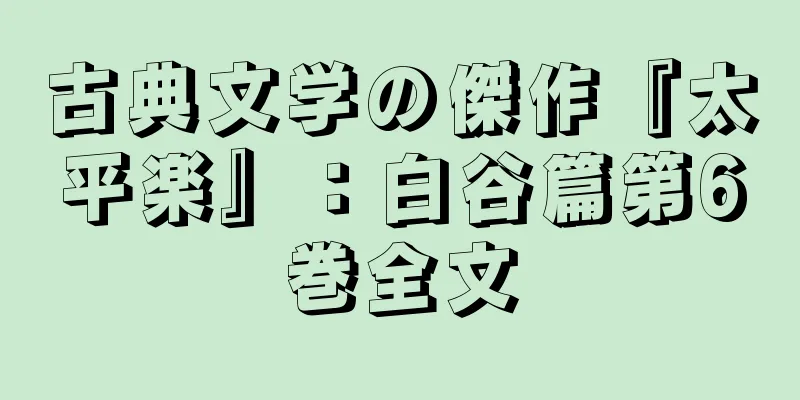
|
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂したもので、太平興国二年(977年)3月に始まり、太平興国八年(983年)10月に完成しました。 『太平毓蘭』は、55部550の分野に分かれ、1,000巻にまとめられた各種書籍のコレクションであるため、もともと『太平宗録』と名付けられていましたが、書籍が完成した後、宋の太宗皇帝が毎日3巻を読み、1年で全巻を読み終えたため、『太平毓蘭』に改名されました。本書は天・地・人・事・物の順に55部に分かれており、古代から現代まであらゆる事象を網羅していると言えます。この本には1000冊以上の古書が引用されており、宋代以前の文献資料も多数保存されている。しかし、そのうち7、8冊は失われており、そのことがこの本の貴重性をさらに高め、中国伝統文化の貴重な遺産となっている。それでは、次の興味深い歴史編集者が百谷第六巻を詳しく紹介しますので、見てみましょう! ○ キビ 『尚書 君臣』にはこうある。「私はこう聞いた。『最上の統治は香りがよく、神々を感動させる。粟は香りがよくないが、光明の徳は香りがよい。』」 「潘庚」はまたこうも言った。「農民が畑を耕さなければ、キビもモロコシもなくなるだろう。」 『文書の大注釈』にはこう記されている。「夏に火が燃え始めると、キビを植えることができる。」 『韓氏外伝・書礼』にはこうある。「あの粟は散らばっている。あれは粟の苗だ。」 (薛俊の注釈:詩人は弟を見つけることができず、どうしたらよいか分からず心配していたので、キビを見てそれがキビだと思った。) 『毛詩』には「『蜀麗』は周王朝についての詩である」とある。キビの種が撒かれ、モロコシの苗がまばらに植えられています。足取りはおぼつかず、心は震える。 『福田』にもこう書かれている。「今、私は南の畑に行く。そこでは、穀物を収穫している者もいれば、雑草を取り除いている者もおり、キビやモロコシを豊かに育てている者もいる。」 (薿薿、栄えある様子。) そして、「魚と藻:キビの苗」にはこう書かれています:キビの苗は青々と茂り、曇りや雨の天候によって養われています。 『礼記:結婚式』には、「ソースの東側にキビを置く」と書かれています。 「供物を捧げる儀式」には、副菜としてキビを巻いて祝福とともに死体に捧げ、その後祝福とともに死体に捧げるとも書かれています。 『祭儀書:月例法要』にはこう記されている。「真夏の月には、農民はキビを収穫する。」 『曲里』にはこうも書かれている。「粟は湘河と呼ばれる。」 「内規」には、キビは羊に適しており、モロコシは豚に適しているとも書かれています。 「左伝・昭公」はこう言った。「氷を貯蔵するとき、彼らは黒牛とキビを使って寒さに供物を捧げます。」 (杜宇注:黒沐は粟です。四寒は北の神、玄明なので、すべてのものは黒いです。氷に関係するものがあるので、粟を神への供物として捧げます。) 『春秋佐助実録』には、粟神は倭倭蘭好と名付けられているとある。 『春秋序』には「精気は火に移りて粟となり、夏に出て秋に変化する」とある。 (杜瑜の注釈には「春は夏のようで、移り変わる」とある。『農書』には「粟は暑さを表すので、暑さが変われば変化し、日陰になって成熟する」とある。)粟は縮むという意味である。そこで、「米」に「禾」という文字を加えて「黍」となり、高齢者を支える酒を意味するようになったのです。 (ワインは年長者と年少者を区別するために使われ、穀物は柔らかい食べ物なので年配者にも適しています。) 「エルヤ」曰く:九は黒キビ。禾不、1禾甫は2メートルに等しい。 (郭普の注釈には、「何布」も黒キビであるが、漢の何帝の時代には別の種類のキビであったとある。漢の何帝の時代には、仁城で黒キビが育ち、時には3粒または4粒、キビ1粒と米2粒で、収穫量はキビ3胡8斗であった。) 『史記 鳳山書』には、管仲が桓公に言った、「昔、鳳山は趙の頂点にあり、粟は豊富であった」とある。 『漢書』にはこう記されている。「冀州の人々は男五人、女三人である。家畜は牛と羊が適しており、穀物は粟と高粱が適している。」 『後漢書』にはこう記されている。「成公は国内で混乱と動乱に遭遇したので、学生全員を連れて漢中に避難した。」その後、彼と妻は孟陰山に行き、そこで農業に専念しました。料理が調理されようとしたとき、誰かが彼に気づいたが、ゴングは参加せず、その人を押しのけた。これによって彼は有名になった。 『晋書』には、劉聡の時代に河東に大きなイナゴがいて、粟と豆しか食べなかったと書かれている。金準は部下を率いて遺体を回収し埋葬したが、その泣き声は10マイル以上離れたところまで聞こえた。その後、地面に穴を掘って飛び出し、再びキビと豆を食べましたが、とてもお腹が空いていました。 崔洪の『十六国春秋記 秦旧記』には、苻堅が釣台で大臣たちを招いて宴会を催したとある。趙政は苻堅が酒を好むと考え、「酒徳」という歌を歌った。「秦の西で粟を採り、斉の東でヒシを摘む。春は閉ざされ、夏は開かれ、鼻は吸い込まれ、心は魅了される。」 『隋書』には、李世謙が隠遁生活を送っていたとき、一頭の牛が畑に侵入したと記されている。世謙はその牛を涼しい場所に連れて行き、飼い主よりも良い餌を与えた。盗賊が自分の作物を刈っているのを見ると、黙って避けた。かつて、彼の家来の一人が穀物を盗んだ男を捕まえた。石謙は彼を慰めて言った。「彼は貧しかったからこんなことをしたのです。彼を責めるのはよくありません。」彼はすぐに男を解放するよう命じた。 また、李世謙は幼い頃に孤児だったため、酒を飲んだり肉を食べたりしたことはなく、殺人について言及したこともなかったと言われている。親戚や客が来ると、彼は酒と食べ物を出して彼らの前でまっすぐに座り、一日中疲れることがなかった。李一族は権力と富を有し、春と秋の祭りの時期には盛大な集まりを開いて大いに喜び、皆が酔って騒いでいました。ある時、彼は石謙を自分の家に呼び寄せ、豪華な料理をテーブルに並べ、まず粟を並べた。彼は弟子たちに言った。「孔子は五穀の中で粟が一番良いと言っていたし、荀子も粟と高粱を最初に食べるべきだと言った。どうして昔の人が重んじていたことに逆らえるだろうか?」若者も年長者も皆畏敬の念を抱き、手を抜く勇気がなかった。二人は別れた後、互いに言った。「あなたに会って、私は徳のある人間ではないと分かりました!」これを聞いた石謙は、「なぜ私は他人に無視され、こんなことになったのか?」と自分を責めた。 『唐書』にはこう記されている。「徳宗皇帝は中和節の際、すべての文武官僚に農書を提出し、穀物の種子を捧げるよう命じた。」当時、百官の官吏は『人民の基本職業』三巻を献上し始め、農相は粟一斗と高粱一斗を献上した。 「韓子」曰く:韓昭侯の時代には、粟の種は非常に高価だった。趙侯は人々に穀倉を覆うよう命じたが、穀倉の番人は実際に粟の種を盗んで売った。 『山海経』にはこう記されている。「広都の野に侯季が埋葬されたが、そこには肥えた粟と肥えた高粱があった。」 また、玉山には少豪の子孫で粟を食べる片目の男がいるとも言われています。 「韓子」は言った:呉起は秦小亭を攻撃した。彼は北門の外の車道に寄りかかりながら、命令を出した。「この場所を南門の外に移動できる者は、良い土地と良い家を報酬として与える。」誰かがそこへ移動すると、彼は命令どおり報酬を得た。すぐに彼はもう一台の赤いキビ一石の車を門の外に置き、「この車を西門の外へ移動させた者には、これまでと同様に褒美を与える」と命令しました。人々は競って車を移動させました。そして彼は命令を出した。「亭主を攻撃するとき、最初に亭主に到達した者には高官として最高の田畑と家屋を与える。」そこで彼らは亭主を攻撃し、一日で亭主を占領した。 『淮南子』には、冬の3月に皇帝は黒い服を着て、黒いラクダに乗り、キビと豚を食べると書かれている。 (粟や豚は水産物なので、この季節にぴったりです。) 三代の人々は徳を積んで王となり、斉桓は王朝を継承して覇者となったとも言われています。したがって、粟を植える者は皆粟を収穫し、親切を示す者は皆その親切に報いるであろう。 渭水は水量が多く、粟の栽培に適しているとも言われています。 『淮南子万備書』には、キビと赤キビを取ってキツネの血に浸し、日陰で乾燥させると書かれている。お酒を飲みたい場合は、1錠を舌の下に置きます。ワインを飲み込めば酔わなくなります。女性の嫉妬を防ぐために、オオバコ、赤キビ、ハトムギを混ぜた丸薬を作りましょう。 『百胡同』にはこう書いてある。「清明に風が来ると、キビやモロコシがよく育つだろう。」昌河からの風が到来すると、小麦とキビを植える時期になります。 『保朴子』は次のように述べている。張子和の仙薬法は、鉛、辰砂、藍石水を一緒に使用し、それを密封し、赤粟で蒸すというものである。 『実録』には、徽成王の治世の8年に粟の雨が降ったと書かれている。 『国語』によれば、子禹は太子に『粟苗』を作曲するよう命じた。 (『粟の苗』『小夜』の詩には「粟の苗は青々と茂り、雨や曇天がそれを養う」とある。)子瑜は言った。「粟の苗が曇天や雨に頼っているように、鍾児もあなたを頼りにしている。あなたが本当に粟を守り養い、良い実を結ばせて祖廟に供えることができれば、それはすべてあなたの努力によるものだ。」(祖廟では、彼が主な供儀者です。) 『家伝』にはこうある。孔子は艾公の前に座り、桃と粟を与えた。艾公はそれを要求したが、孔子はまず粟を食べ、次に桃を食べた。周りの人々は皆口を覆って笑った。公は言った。「粟は桃を嘲るために使われるもので、食べ物ではありません。」孔子は答えた。「私は知っています。しかし、粟は五穀の中で最良であり、郊外や祖先の廟で最も重要視されています。果物は6種類ありますが、桃は最も低いので、祭祀に使われず、郊外や祖先の廟に供えられません。君子は安いもので高いものを嘲り、高いもので安いものを嘲らないと聞きました。今、あなたは五穀の中で最良で、五果の中で最低のものを嘲っています。それは高いものから低いものへのようなものです。私はそれが教えを妨げ、道徳を傷つけると思うので、私はあえてそうしません。」公は言った。「いいです。」 『緑氏春秋』はこう言っている。「旬の時期に育った粟は芒があり、穂も芒が長く、穂先も長い。穂は細かく、すりつぶしやすく、食べると香りがよく、脂っこくない。このような粟は腐らない。」 (発音は「エ」)早生のものは根が大きく茂っていますが、茎は弱く、長くありません。葉は高く、穂は短いです。晩生のものは茎が小さく、長くてふわふわしていて、穂は短く、籾殻は厚く、味は地味ですが香りはありません。 (Lingは新しいという意味です。) 彼はまたこうも言った。「もしあなたが自分の息子に見せるために金貨百枚と粟一片を与えれば、あなたの息子は必ず粟一片を取るだろう。もしあなたが卑しい人に見せるために金貨百枚を与えれば、彼は必ず金貨百枚を取るだろう。」 南シナ海産の雑穀が最高のお米とも言われています。 (秬、黒いキビ) 楊権の『事物論』にはこうある。「梁はキビとモロコシの総称である。」 崔舒の『四種月例令』には、4月はキビを植えるのに最適な時期であると書かれている。 『四聖書』には、キビは暑さを表すので暑い時期に植えなければならないと書かれています。夏至の20日前に雨が降るでしょう。強固な土壌ではキビを栽培することができ、1ムーあたり3リットルの収穫が得られます。粟の心はまだ成長していないが、雨がその心を潤し、傷つき、実体を失わせる。粟を植える人は、米と同じように植えるべきであり、米よりも薄く植えたいのです。 『倪亨伝』には、10月に崇州の船上で黄祖に敬意を表し、粟汁を供えたとある。ヘンは幼かったが、会合に出席していた。キビのスープが運ばれてくると、まずお腹いっぱい食べてから、食べ物に対する敬意を欠いた態度でそれを遊び始めた。 劉湘の『別録』にはこう書かれている。「鄒岩が燕にいたころ、谷があった。そこは美しいが寒くて穀物は育たなかった。」鄒子はそこに住み、暖かい音色の笛を吹いていました。キビはそこで育ち、今でもキビと呼ばれています。 『女性伝』にはこう記されている。「東平河農業管区の管区長が亡くなったとき、農民たちはその場所に逃げたいと思ったが、自分たちで食べるための食糧がなかった。」妻は喜んで私と一緒に行き、自活できるように糸紡ぎや織りをしてくれました。ジュティンに着いたとき、大雨が降っていたので、彼は母親の家に泊まりました。母親の家の裏には空き地がありました。農夫は「この庭でキビを育ててもいいよ」と言いました。そこで農夫は、植えるための土地を分けてもらうよう頼みました。ドゥグの母親は、「この畑は長い間放置されていた。作物がうまく育たず、収穫もあまりないのではないかと心配だ。他の人と分け合っても意味がない」と言った。そこで農夫とその妻はイバラを切り、作物を植えた。粟が実る頃、独孤の母は「粟を分けなさい」と言いました。農は去ろうとしましたが、妻は「粟を集めて彼女に残しておいた方がよいでしょう。そうすれば、彼女は出発する前に満足するでしょう」と言いました。農は彼女の言いつけに従いました。後でドゥグが戻ったとき、ドゥグの母親は農民にキビを与えてしまったので受け取ることを拒否した。 『朔文』曰く:九は黒粟。もち米を作るには、米1グラムと穀2粒を使います。キビは一年で最も暑い時期に植えられる粘り気のある穀物なので、キビという名前が付けられています。孔子は言った。「キビは酒を作るのに使える。」 「Guangya」によると、「粢」はキビです。熟したキビは「禾列」と呼ばれます。 (音の例) 崔豫の『古今記』には、宣帝の元康4年、長安に黒粟が降り、粟は小麦のように大きく育ったと記されている。何帝の元興元年、仁城では黒い粟の穂が一粒に二、三、四粒実り、三胡八斗の粟を収穫し、祖廟に供えた。 『光之』はこう言っています。牛の粟があり、稲穂が美しく見える赤い粟があり、馬の皮ほどもある黒い粟があり、九粟とも呼ばれています。暖かい黄色の粟があり、それを玉王、延韓と名付けています。 『呉の薬物学』には、キビは甘くて無毒であると書かれている。 7月に採取し、日陰で乾燥させます。気を補充する。 景芳の『易瑶占』にはこうある。「空から粟が降ると、大人は逃げる。」 『荊楚歳時記』には、10月1日は粟煮の日であり、一般的に秦の年の始まりとして知られていると記されている。衛湘粟の意味。現在、北部の人々は成人し始めたばかりで新しい食べ物を味わいたいため、この日にゴマスープや豆ご飯などの料理を出します。 「ボウズィ」は言った。「もしこの土地に3年間粟を植えたら、次の7年間には蛇がたくさん発生するだろう。」 ○ 范敖の『後漢書』にはこう記されている。「五環国の土地は稲作に適している。」 『穆天子伝』にはこう記されている。皇帝が赤烏に到着すると、赤烏は百年の間、粟と小麦を捧げた。 「光志」曰く、赤米、白米、黒米、緑米、黄米、燕子米の計5種類があるそうです。 「呂氏春秋」曰く:最高の米は洋山産の粟だ。 『稌文』によると、「稌」はキビを意味します。 (エルクと発音します。) 崔葭の『古今記』には「粟」とある。 ○ 梁 『礼記 瓔珞』にはこう記されている。祖先の廟に供物を捧げる儀式では、米は香醋(シャンジ)と呼ばれる。 『交徳聖』には、米、キビ、モロコシ、白キビ、黄キビとも記されている。 「Er Ya」によると、「虋」は赤い苗を意味し、「芑」は白い苗を意味します。 (郭普の注釈には、新は赤い粟、斉は白い粟で、どちらも良い穀物である。建は赤い苗と白い苗で、味が違う。伯易が食べたのは首陽草だという説もある。) 「Guangya」には、「藋梁はキビの一種である」と書かれています。 『続漢書』には、桓帝の治世の初め、都に次のような童謡があった。「城壁にカラスがいて、その尾は逃げている。公は官吏、子は囚人。一人の囚人が亡くなり、百台の馬車が河間に乗り込む。馬車は一列に並んで河間に入る。河間娘たちは銭を数え、銭で部屋を建て、金で堂を建てる。石の上で黄粟をつく。下に吊るした太鼓があって、叩きたいが宰相は怒っている。」 「城壁にカラスが」とは、高い所に住み、一人で食事をし、下の者と分け合わない人のこと。君主が多くの財産を蓄えることを意味する。 「父は官吏、息子は兵士」とは、蛮族が反乱を起こしたときに、父は軍人であり、息子は兵士となって彼らと戦うという意味です。 「一人の兵士が死んで、百台の戦車が送られた」とは、胡族と戦うために前に戦った人が死んで、その後百台の戦車が胡族と戦うために送られたことを意味します。 「車班班」とは、霊帝を迎えるために河間に入った馬車のことを指します。 「美しい娘がお金を数えている」とは、皇帝が即位した後、母親の永楽皇太后が宮殿を建てるためにお金を集めるのが好きだったことを意味します。 「石に悲しみが満ちている」とは、太后が大金を蓄えていたにもかかわらず、いつも満足できず、食べるために人に黄粟を搗かせなければならなかったことを意味します。 「打ちたい」とは、皇太后が皇帝に官職を売ったり金銭を与えたりすることを教え、世の中の忠誠心の高い人々が憤慨し、太鼓を叩いてあなたに会いたいと願っているという意味です。 「太鼓を吊るす」というのは、また怒って私を止めるという意味です。 『唐書』にはこう記されている。「かつて涼州の太守、季欽明が軍隊を視察するために派遣された。数万人のチベット人がこの都市にやって来た。秦明は長い間抵抗したが、結局は敗北して捕らえられた。賊将秦明が凌州城下に到着すると、大声で叫んだ。「賊の中には酒はないが、城内には美味しいソースがある。高粱二リットル、墨二リットル、棍棒一本をください。」当時、賊の陣地は四方を泥川で塞がれており、入る道は一つしかなかった。秦明は、城中の人々を説得するために、このことを偽って懇願し、兵士を募集し、将軍を訓練して、夜間に奇襲攻撃を仕掛けてくれることを期待した。街の誰も彼の目的を理解しておらず、すぐに殺されました。 淮南子は言う。「畑を耕すことができないのに粟を育てたい、機織りができないのに衣服を作りたいなど、何もせずに成就を求めるのは難しい。」 また、次のようにも言われています。「人々は珍しい珍味を好むが、堯は粗い粟飯と山菜や野菜のスープしか食べなかった。(粝は粗いという意味です)。人々は刺繍の入ったキツネの毛皮や白い絹を好むが、堯は体を隠す布の服と寒さを防ぐ鹿皮のコートしか着なかった。」 『国語』によると、阮伯は王室の役人たちを招待した。公爵はこう言った。「金持ちで裕福な男の性質を矯正するのは難しい。」 『呂氏春秋』には、呉起が鄴の知事であり、人々は「塩沼は常に米と粟を生産する」と歌っていたとある。 楊権の『事物論』にはこうある。「梁はキビとモロコシの総称である。」 『仙人伝』にはこう記されている。呉の孫権の時代に、山に粟を植えていた男がいた。粟は猿に食べられてしまうのではないかと心配していた。彼は桀湘が道を持っていると聞いて、猿を追い払うために道を求めることにした。項は彼に言った。「他に方法はありません。明日、梁に行くとき、猿が去っていくのを見たら、猿に呼びかけてこう言いなさい。『項に白い印を渡してください。そうすれば、猿はもう粟を食べに来なくなります。』」男は急いでいて、項が自分を騙したのだと思いました。翌日、梁山に行ったとき、一群の猿が木から降りてくるところを見ました。象を使って猿に話しかけようとしたところ、猿は皆山に戻って姿を消しました。 『光志』は言う:魏の武帝が粥にした紅高粱には、莆良、閩良、遼東紅高粱がある。 『本草綱目』には、白モロコシは甘くて少し冷たい味がして、無毒で、熱を取り除き気を補給する効果があると書かれています。最も良いのは襄陽竹の根を使ったものです。黄梁は清と冀から来ています。 『楚辞:趙渾』には、米、粟、麦、黄粟とある。 (拏、糅。黄モロコシと混ぜると香りがよく、滑らかになります。) 傅秀義の『雉歌』には「雉は華泉の水を飲み、玄山の粟を食べる」とある。 左思の『衛都賦』にはこう記されている。「雍丘の梁」 ○ 董強 『魏書』には、五環の地は東強に適していると書かれている。 (イースタンローズは雑草のように見えますが、その実はヒマワリの種のようなもので、12月に熟します。) 『光志』にはこうあります。「東方紅は濃い青で、粒はひまわりの種のようで、暗くて涼しく、調和がとれているという特徴があります。」 「西和宇」は言う:「東強を貸して、田良を返せ」 『上林譜』には次のように記されている。「東強は胡を彫った。」 |
>>: 『紅楼夢』で、大観園の探索に直面したとき、賈潭春はこのように美しく言いました!
推薦する
白居易の詩「麦刈りを見る」は、労働者階級の人々に対する詩人の深い同情を表現している。
白居易は、字を楽天といい、別名を向山居士、随音献生とも呼ばれた。写実主義の詩人で、唐代の三大詩人の一...
『紅楼夢』では、趙叔母さんはどんな方法や計画を持っていましたか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
Yelu Yanの叔父は誰ですか?イェルヤンの叔父、チェン・インのプロフィール
チェン・イン(チェン・イン)は、ミス・チェンとしても知られ、金庸の武侠小説『射雁英雄の帰還』の登場人...
「彭公安」第187話:飛雲は秘密を密かに調査し、玉龍は私的な訪問中に泥棒に遭遇する
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
美しい荘族の民謡にはどのような歴史文化があるのでしょうか?
荘山歌は「荘歌」または「荘民歌」と呼ばれ、一般的には荘族が荘語で歌う民謡を指します。チワン族の歌は、...
漢代のどの皇帝が建立したのですか?宮殿のレイアウトはどのようなものですか?
中国の古代宮殿建築である建張宮は、太初元年(紀元前104年)に漢の武帝劉徹によって建てられました。武...
古代の有名な4人の暗殺者は誰ですか?暗殺に失敗した者は誰ですか?
中国史上の四大暗殺者は、荊軻、聶徴、姚立、荘朱である。 次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介します...
最も簡単かつ最も認識が難しい漢字!あなたはこの5つの単語を知っていますか?
今日は、Interesting Historyの編集者が最も簡単な漢字と最も難しい漢字を紹介します。...
「明るい月が私のベッドを照らし、終わりのない夜に天の川が西へ流れる」という有名な一節はどこから来たのでしょうか?
まだ分からない:有名な一節「明るい月が私のベッドを照らし、天の川は果てしない夜に西に流れていく」...
本草綱目第8巻生薬類キプリペディウムの具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
呉秀文の母親は誰ですか?呉秀文の母、呉三娘の簡単な紹介
呉三娘は『射雁英雄の帰還』の登場人物。呉三童の妻であり、呉敦如と呉秀文の母。呉三童のために薬を飲んだ...
『阮朗桂:正王十二弟に贈る』をどのように理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
阮朗桂:正王の12番目の弟に贈られた李嶽(五代)東風が水面に吹き、太陽が山に照りつける。春が来ると、...
実際の歴史では、周瑜の方が強かったのでしょうか、それとも魯迅の方が少しだけ優れていたのでしょうか?
三国時代の東呉には数人の知事がいたが、その中で最も権力を握っていたのは周瑜と陸遜だった。周瑜と陸遜に...
陸俊義ってどんな人ですか?陸俊義の主な業績
陸俊義は誠実な男であり、この性格により、彼は誰と対峙しても自分の信念を貫くことができます。宋江らは彼...
清朝の政治:南書坊は高度な中央集権化を実現する上で重要な一歩であった
国旗と国歌清朝には法的な国旗や国歌がなかった。近代に入り、西洋諸国との交流が進むにつれ、国旗や国歌な...