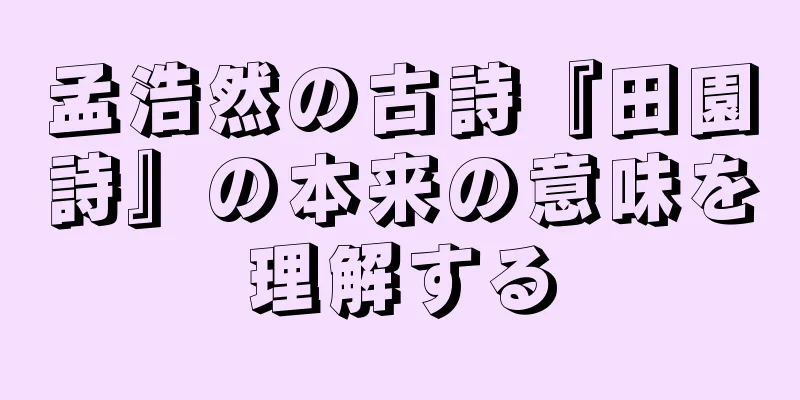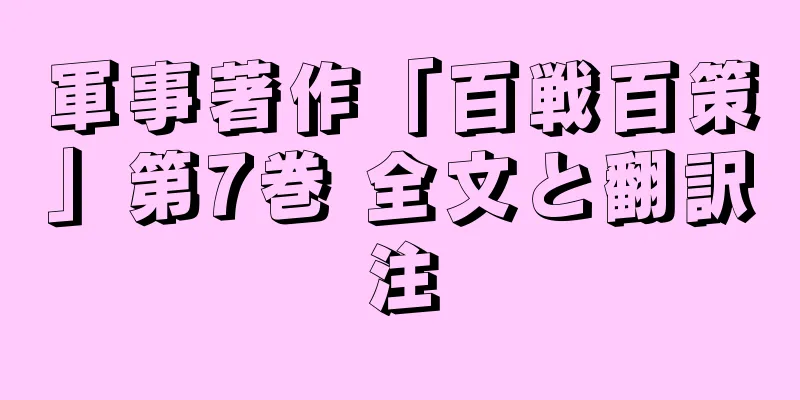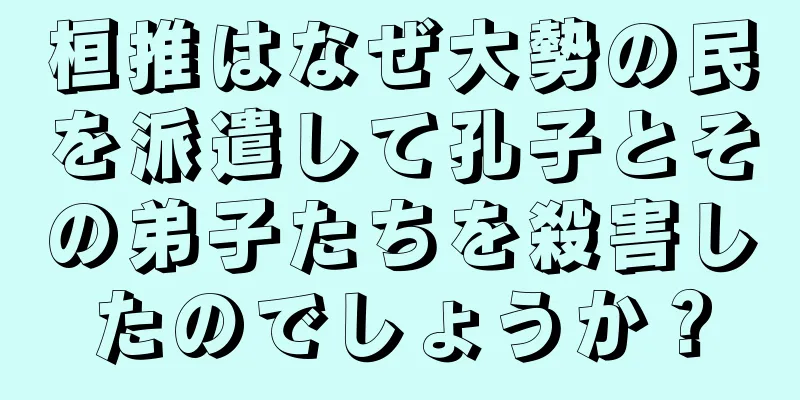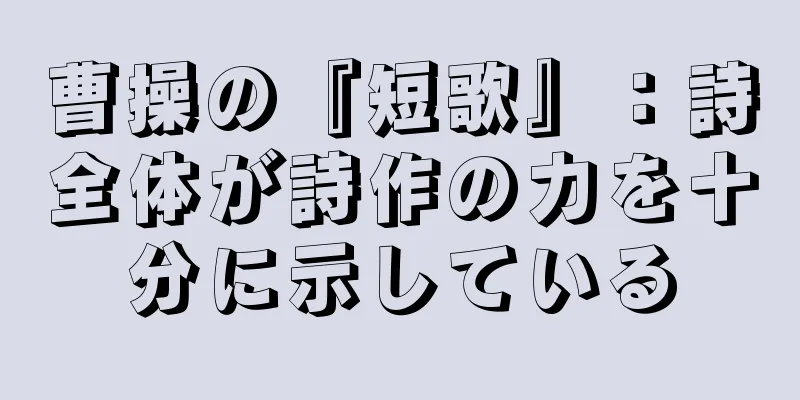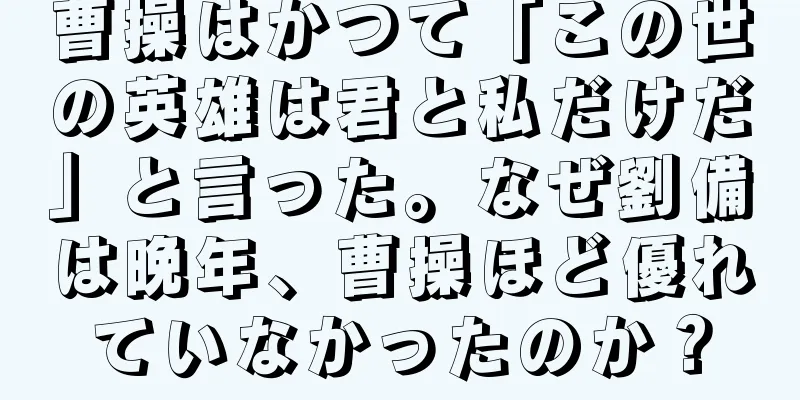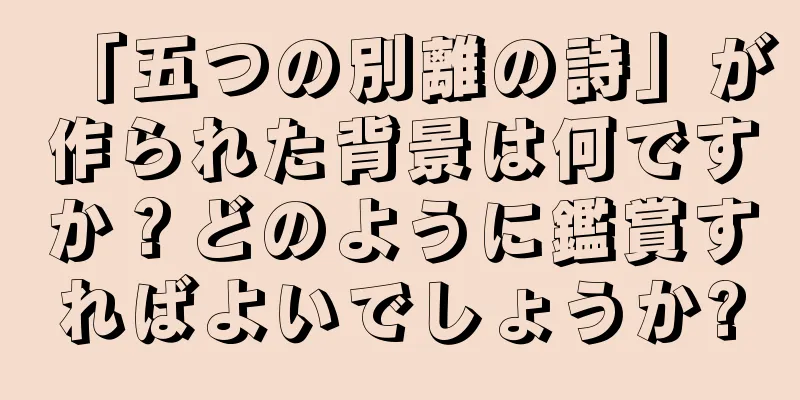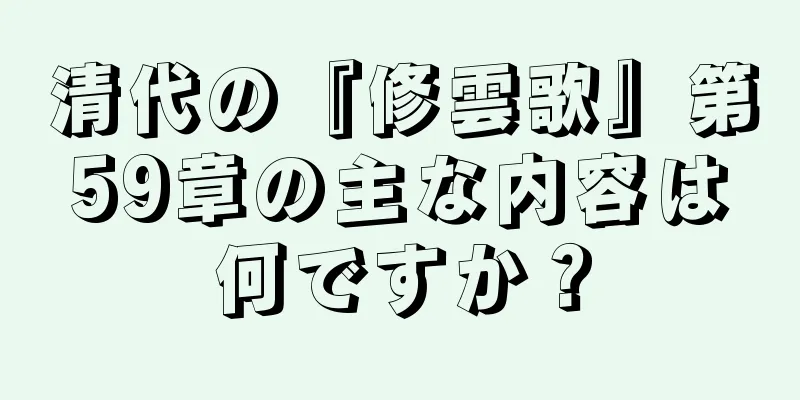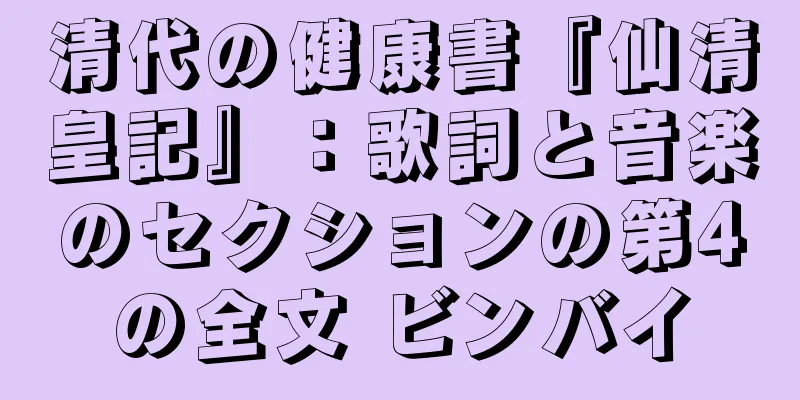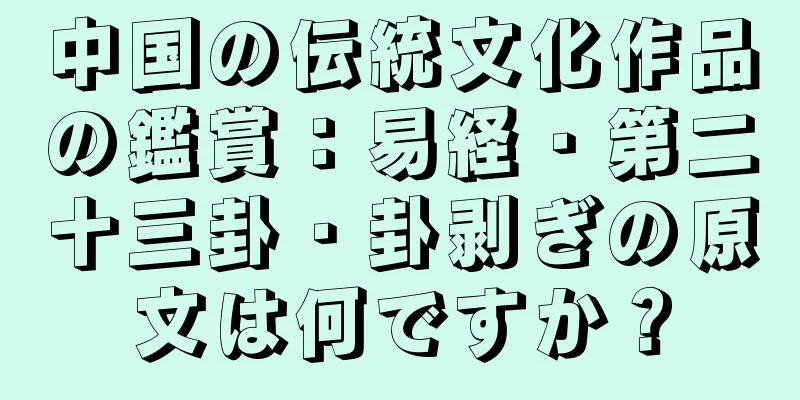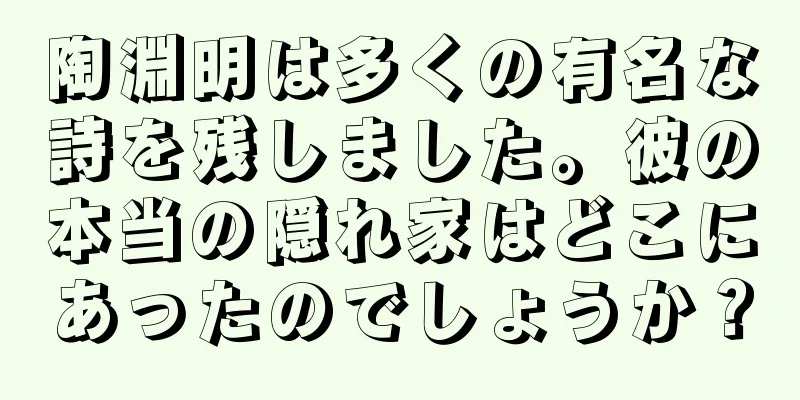廖華が先鋒だったときは関羽よりもずっと危険だったのに、なぜ矢で傷つかなかったのでしょうか?
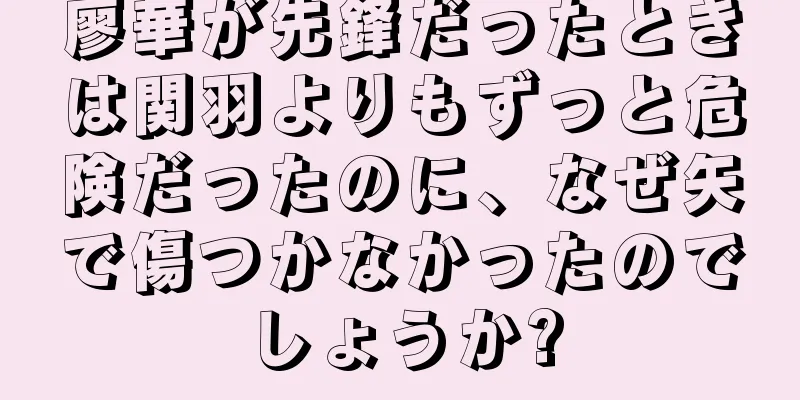
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、廖化が前衛として一度も矢に当たらなかったのに、関羽が矢に当たって負傷することが多々あった理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 東漢末期、皇帝は不正を働き、官僚は腐敗し、民衆の生活は悲惨で、世の中は混乱に陥っていました。古来より、混乱の時代に英雄は現れます。そのため、この時期には多くの傑出した人物が現れ、その能力と知恵で後世の私たちに衝撃を与え、長い歴史の流れに強い足跡を残しました。例えば、関羽はそのような人物です。 関羽の元々の名前は長勝であったが、後に雲昌に改められた。彼は河東郡斌県(現在の山西省運城市)の出身で、「美しい髭の男」というあだ名があった。関羽は若い頃、罪を犯して故郷を離れ、幽州の卓県にたどり着きました。黄巾の乱が勃発すると、劉備と張飛と出会い、軍人としてのキャリアをスタートさせました。その後、劉備、関羽、張飛は各地で戦い、互いに良好な関係を築いていった。 そのため、関羽は後に曹操から好意的に扱われるようになるが、劉備からの知らせを受けて毅然と立ち去り、劉備が領土の大半を征服するのを助けた。関羽は生涯で、敵を恐怖に震え上がらせた七つの軍勢の攻防戦など、数多くの古典的な戦いを戦いました。残念ながら、関羽は後に陸孟と陸遜に待ち伏せされ、米芳と石仁に裏切られ、最終的に敵に殺され、命を落としました。 興味深いことに、人々が関羽のさまざまな戦いに注目すると、関羽は矢によって頻繁に負傷していたことがわかります。例えば、『三国志』には「禹は流れ矢に当たって左腕を貫かれたことがある」と明確に記録されています。麦城で敗れたとき、関羽は龐徳の矢で顔を撃たれた。しかし、他の蜀の将軍にはそのようなことはほとんど起こらなかった。例えば、長阪坡で曹操の軍に突撃し、7回出入りした趙雲は、一度も矢に当たって傷を負わなかった。 何度も蜀の先鋒を務めた廖華は関羽よりもはるかに大きな危険にさらされていたが、無傷だった。それで、疑問は、なぜそうなるのかということです。 関羽の忠実な支持者の中には、関羽が矢によく当たったのは、彼が軍の将軍であり、「率先して行動する」という理念を唱え、常に最前線に駆けつけていたためだと信じている者もいる。しかし、剣やナイフには目がないので、敵の隠れた矢によって負傷する可能性が高いです。例えば、曹操と袁紹が戦おうとしたとき、関羽は張遼の軍に隠れて馬に乗って顔良の元へ行き、数千人の民衆の中で敵将を刺し殺し、無事に帰還した。このことから、関羽が非常に勇敢な人物であったことは容易に想像できる。また、前線に突入したため、当然負傷する可能性も高かった。 もちろん、異なる意見を持つ人もいます。それは、おそらく世間が関羽の能力を過大評価しすぎたためだと考える人もいます。最も典型的な例は、姜維が関羽に与えた「荘妙」という諡号です。 「武術で成功しないことを荘といい、名声にそぐわないことを苗という。」したがって、この諡号は、関羽が矢に射られた理由を最もよく説明している。関羽の技量が他の人より劣り、名声が現実に見合っていなかったためである。 ある意味では、関羽は呂布ほど勇敢ではなく、諸葛亮ほど賢くなく、劉備ほど人を判断する力がなく、趙雲ほど状況の変化に適応する力もありません。そのような人は当然、戦場での自己防衛能力が低く、矢に簡単に当たってしまいます。 ある意味、どちらの発言も理にかなっています。しかし、真実は何でしょうか? 私たちにもわかりません。私たちにできるのは、歴史的な記録に基づいて推測し、独自の考えを述べることだけです。 |
<<: 「愛」という言葉をどう解釈するか?『紅楼夢』に見る深い愛
>>: 白蓮菊詩とは誰ですか?清朝の女性画家、方万宜とその詩画
推薦する
『紅楼夢』で賈宝玉が夢の中で幻の国へ旅する深い意味は何でしょうか?
『紅楼夢』の太虚の幻想世界は、仙女の景環によって支配されている。それは、運命の人である甄世銀と賈宝玉...
『山海経』全文は何巻ありますか? 『山海経』にはどんなバージョンがありますか?
『山海経』が何巻あるかご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。『Interesting Histor...
ロシアの食事 ロシア人は何を食べますか?
ロシア民族の伝統的な食事は主にパスタがベースで、パン「ヘレブ」、卵パンケーキ「ブライン」、発酵パンケ...
宋代の『辞』鑑賞:阮朗桂・小湘門外横敷、作者はどのような感情を表現しているのでしょうか?
阮朗桂・小湘門外横店 [宋代] 秦貫、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見て...
水滸伝 第52話:戴宗が公孫勝を二度目に破り、李逵が羅真人を一人で殺す
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編者は、一般に施乃...
歴史の秘密が明らかに:なぜ明朝の役人は黒い帽子をかぶり、清朝の役人は花の羽飾りをつけていたのか?
明清時代の衣装を扱ったテレビシリーズでは、明清時代の官僚たちが服装が違うだけでなく、帽子も違うことが...
古代における花嫁の輿の要件は何だったのでしょうか?花嫁はなぜ輿に乗るのでしょうか?
古代の花嫁の輿には何が必要だったのでしょうか?なぜ花嫁は輿に乗らなければならなかったのでしょうか?こ...
朱棣はなぜ即位後、首都を北京に移したのですか?主な理由は何ですか?
明朝の建国後、朱元璋は風水の宝地である南京を首都に選びました。これは良い選択です。南京は江南の豊かな...
后燕の慕容宝には何人の子供がいましたか?慕容宝の子供は誰でしたか?
慕容宝(355年 - 398年)は、字を道有、号を孤狗といい、後燕の武成帝慕容垂の四男である。母は程...
水滸伝における張青の強さはどのくらいですか?彼はなぜ殺されたのですか?
張青は『水滸伝』の登場人物で、別名は「梅玉堅」。飛石使いの名手です。今日は『おもしろ歴史』編集長が詳...
日本はいつ出現したのでしょうか?なぜ日本は中国に何度も挑戦したのに、宋代には何もしなかったのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、皆さんのお役に立てればと願いながら、日本と...
合肥の戦いで、なぜ張遼はより少ない兵力で孫権の攻撃を打ち破ることができたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
張建志の『国の善良な人々との2つの夜の歌』は喜びに満ちている
張建之(孟姜)は、唐代の有名な宰相であり詩人であった。彼は神龍の政変を起こした人物である。興味深い歴...
『新唐語』第22巻の「李歌」の原文は何ですか?
武徳9年11月、太宗は自ら政務を執り始め、勅を発して「隋の治世中、政は厳しく、刑罰は複雑で、君主は互...
サラール人の宗教的信仰とシャーマニズムの意識
サラール地方の人々はイスラム教を信仰しており、サラール地方では宗教的な雰囲気が非常に強いです。しかし...