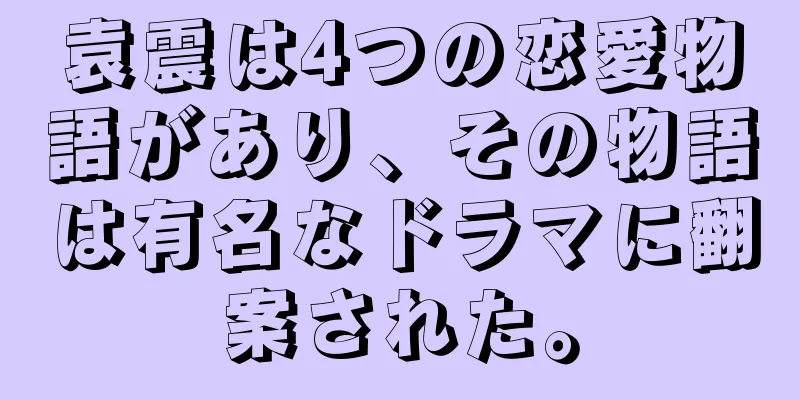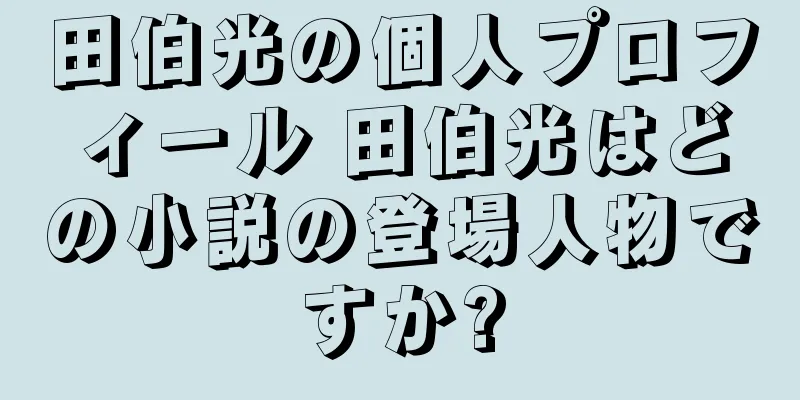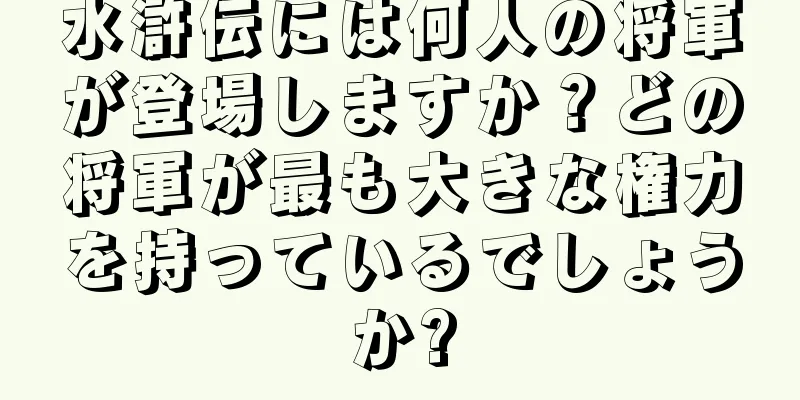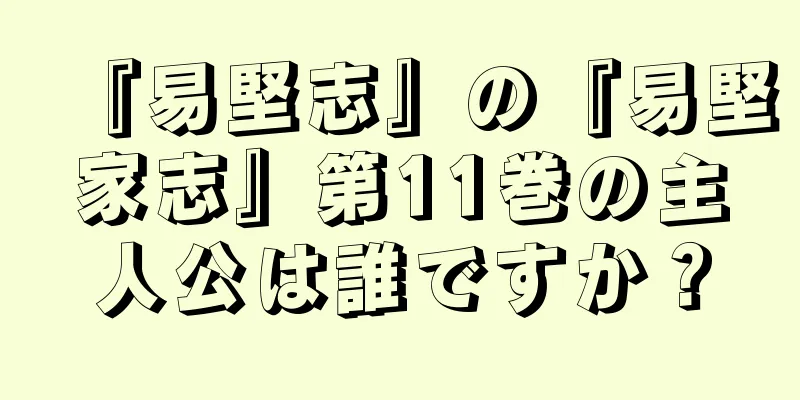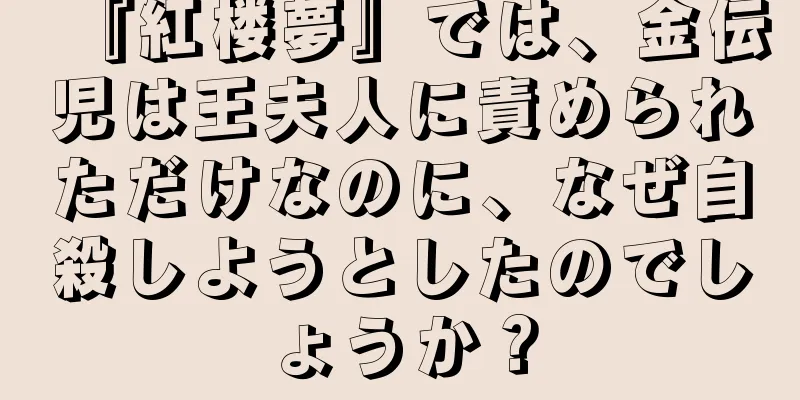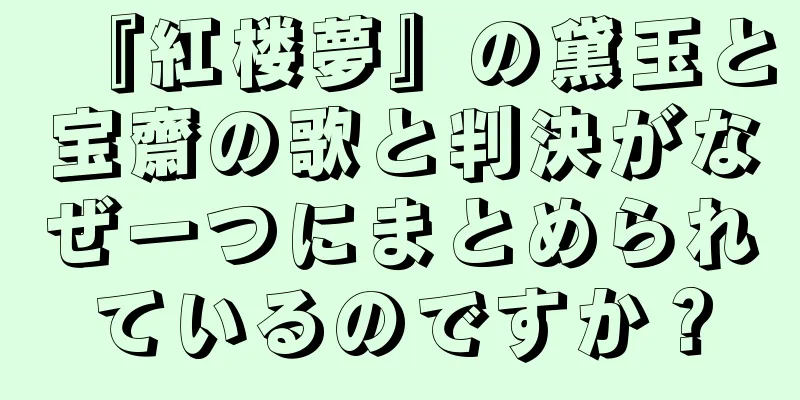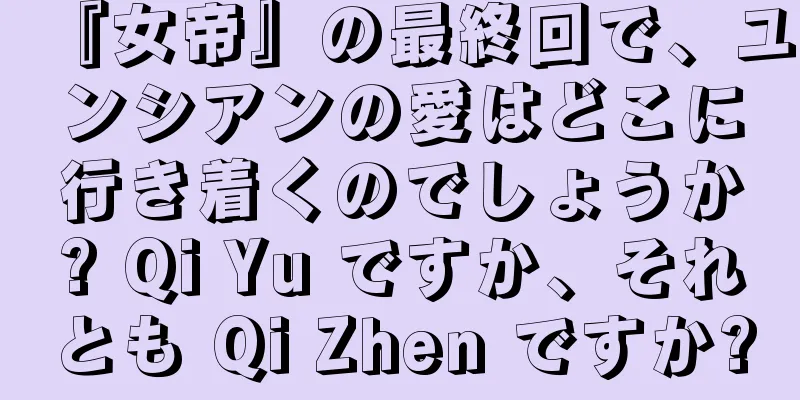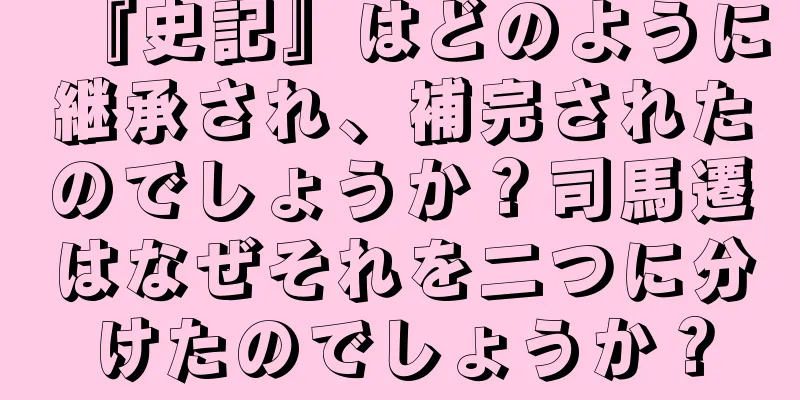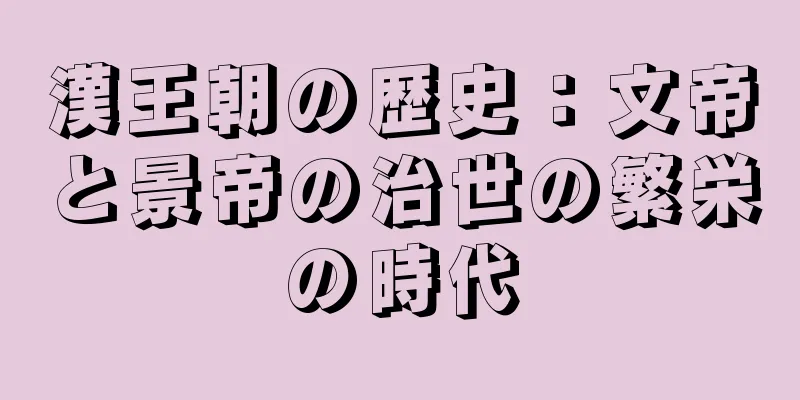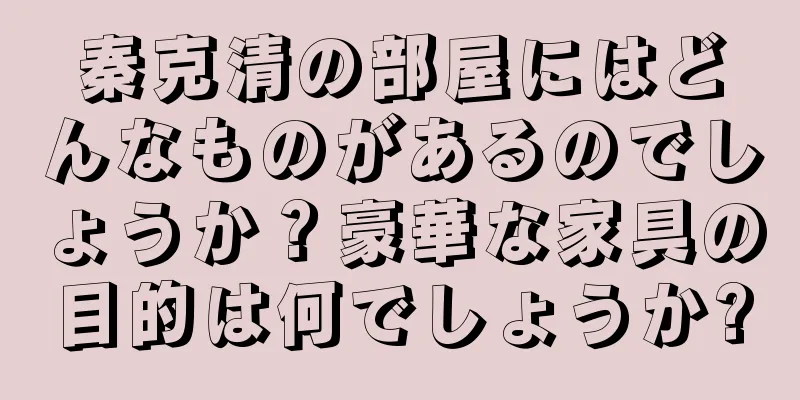最も多くの側室を持った皇帝は誰ですか?三つの宮殿、六つの庭、七十二人の側室の伝説は嘘ですか?
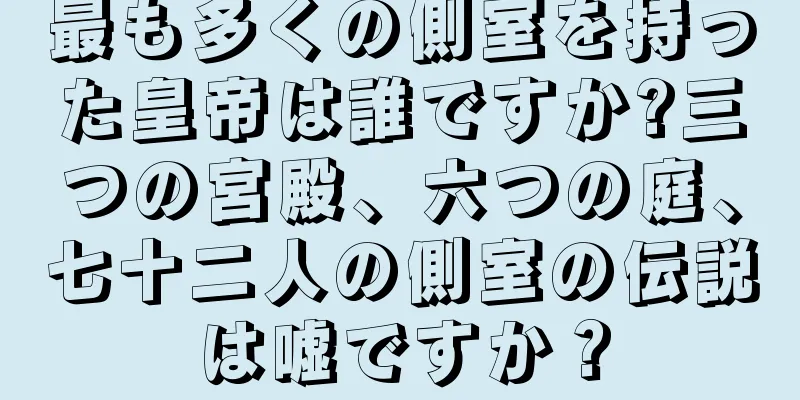
|
最も多くの側室を持った古代皇帝は誰ですか?皇帝の結婚について言えば、「三宮六庭七十二妾」という言い伝えが広く流布している。蘇同の小説『妻妾』が出版されて以来、人々は歴代の皇帝には例外なく妻や妾がいたと考えるようになった。この考えを持つ人々は、知らず知らずのうちに誤解に陥っていた。 中国は古代から清朝末期まで、常に一夫多妻制と一夫一婦制が共存する社会であり、この現象は中華民国時代になってもあまり変わっていません。 誰が一夫多妻制を始めたのかを今となっては特定することは不可能だが、皇帝が最大の受益者であったことはおそらく議論の余地のない事実だろう。 この議論の余地のない事実に基づいて、すべての皇帝には無数の妻と側室がいた、言い換えれば、少なくとも「3つの宮殿、6つの中庭、72人の側室」がいたと推測する人もいます。本当にそうなのでしょうか? 「三宮六苑七十二妾」とはどういう意味ですか? 皇帝が「三つの宮殿、六つの庭、七十二の側室」を持っているかどうかを判断するには、まず「三つの宮殿」、「六つの庭」、「七十二の側室」の正確な意味を理解する必要があります。 「三宮」とは何ですか? 「三宮」の意味は、もともと古代の王子の妻の宮殿を指します。『古梁伝:桓公十四年』には、「穀物は三つの宮殿に送られた」と記録されています。ファン・ニンの注釈には、「三宮は三人の妻を意味する」とあります。楊士訓の注釈には、「礼儀作法によれば、王妃は6つの宮殿を持ち、王子の妻は3つの宮殿を持っているため、三宮は3人の妻の宮殿を意味することがわかります」とあります。 上記の文章から、「三つの宮殿」は皇帝の妻ではなく、王子の妻(最大で女王)を指していることがわかります。 「六つの庭」は「六つの宮殿」から派生したのではないかと考えられています。 「六つの宮殿」はもともと古代の女王の寝室を指し、後に女王や皇帝の他の妻たちを指すようになりました。 『周書 天官 内在』には「殷礼で六つの宮殿を教える」という記録がある。鄭玄は、女王には6つの寝室があり、1つの主寝室と5つの燕の寝室があり、合わせて6つの宮殿を構成していたと説明した。唐代の白居易の『長悲歌』には「一目見て微笑むと、宮中の美女はみな見劣りするほど魅力的」とある。後漢書には「皇后は『この絹は特に染めに適しているので使いました』と言って断った。宮中はみなため息をついた」とある。この二つの「六宮」は広い意味で使われている。 「七十二妾」の由来は不明ですが、「三」の倍数から来ているのかもしれませんし、単に数を表すための数字なのかもしれません。 「三つの宮殿、六つの庭、七十二人の側室」というのは明らかに捏造された言葉です。それで、正しい記述は何でしょうか? 『二十五史記』に目を通すと、どの王朝の『皇后妾伝』の前にも同様の概要があることに気がつくでしょう。 一節を引用しましょう。 古代、皇帝が王妃を娶ると、三国とも側室を置き、その妹や甥も合わせて12人の女性を娶り、王子は9人の女性を娶ることで、側室を規則正しくし、後継者を増やし、嫉妬を鎮め、姦通や悪を防ぎ、災難や混乱を防ぐとされていました。王妃が亡くなった場合、側室が後継の妻となり、それぞれ身分に応じて名前が付けられます。側室が3人いない場合は、妹、甥、姪が後継者となり、それぞれに称号が付けられます。後継者については、内政を担当しますが、地位と称号を変更することはあえてしません。祭祀寺院には棺が2つあっても、同等に敬うことはできません。二人の側室を持つ習慣は魯で初めて行われ、三人の側室を持つ習慣は宋で行われ、斉の管は三人の妻を持っていた。『春秋実録』はいずれも彼らを嘲笑した。 『周書』には内在が記されており、その下には内侍、門番、寺の召使がおり、続いて九人の側室、女房、女官、女僧、女史、女工、絹織、衣服の管理者がいた。 『渾易』には「王妃には6つの宮殿、3人の妻、9人の側室、27人の嫁、81人の皇后がいた」と記されているが、これは『春秋』や『周礼』とは矛盾している。後世の人々も彼の考えに従い、後宮の側室の数は数千人にまで増加した。 (晋の歴史:皇后と側室の伝記) この一節から、皇帝の妻の正式な称号は「六つの宮殿、三人の女官、九人の側室、二十七人の女官、八十一人の皇帝の妻」であるべきであることがわかります。 さらに、次のような他の名前も多数あります。 尚公、尚宜、尚扶、尚氏、尚勤、尚公、順易、順栄、順化、秀易、秀栄、秀化、崇易、崇栄、崇化、傑玉、蔡仁、美仁、趙易、季鄂、八子、崇易、梁仁、蔡奴、舒飛、舒元、桂人、長在、大英、女氏など。 The wives of these emperors were also divided into different ranks. It is recorded in "Book of Sui Dynasty: Biographies of Empresses and Concubines" that in the Sui Dynasty, "the three ladies were the noble concubine, the virtuous concubine and the virtuous concubine, and were of the first rank; Shunyi, Shunrong, Shunhua, Xiuyi, Xiurong, Xiuhua, Chongyi, Chongrong and Chonghua were the nine concubines, and were of the second rank; there were twelve imperial concubines, and were of the third rank; fifteen beauties and talented women, and were of the fourth rank, and were called hermits; twenty-four imperial concubines, and were of the fifth rank; twenty-four imperial maidens, and were of the sixth rank; thirty-seven concubines, and were called imperial ladies, and were of the seventh rank; there were a total of one hundred and twenty, to be recorded at banquets and sleeping arrangements." 明らかに、皇帝の妻たちを「三つの宮殿、六つの庭、七十二の側室」と呼ぶことはできません。では、皇帝の妻たちを「三つの宮殿、六つの庭、七十二の側室」という数で数えることができるのでしょうか。 「妻や妾をたくさん持つ」というのは誇張された神話である 皇帝の妻というのは、広い意味でも狭い意味でもとれる概念です。 大まかに言えば、宮廷の女性(皇帝の実母と娘を除く)は皆、皇帝の妻になることができました。しかし、このような区分は大まかすぎます。実際、宮廷の女性の90%は皇帝の寵愛を受けることができませんでした。唐の詩や宋の歌詞には、宮廷の恨み深い女性に関する記述がたくさんあります。 「涙が絹のハンカチを濡らし、夢を見られない。夜が更けると玄関から歌声が聞こえる。美しさは残っているが、愛は消え去っている。香炉に寄りかかって夜明けまで座っている」(白居易)や「12階の女性たちは朝、着飾っている。王仙楼から王を探している」(蘇鋒)など、例はたくさんあります。 したがって、私たちは、皇帝の勢力圏内にいたこれらの女性を皇帝の妻とはみなしません。私たちは、「歴史的証拠」という基準を採用し、事実から真実を求めるという原則に基づいて、皇帝の妻(「側室」を含む)の数を定義します。事実をそのまま語らせるのが一番です。 統計は依然として西漢時代から始まります。有名な中国の歴史家である伯楊氏は、その大著『中国皇帝皇后王子王女系譜』の中で、秦王朝以前の君主の妻、さらには古代伝説の時代の君主の妻を「皇后」の章に含めています。この記事で議論しているのは皇帝の妻であり、君主の妻ではないため、これは不適切だと思います。 始皇帝の時代から皇帝の妻を数えるべきだったが、始皇帝の時代には王妃の名前も関連する記録もなかった。暫定的な態度で前漢時代から統計を始めるしかない。 西漢には合計12人の皇帝がいましたが、そのうち7人が正史で一夫多妻制を実践していました。彼らは、劉邦皇帝、文劉恒皇帝、景劉啓皇帝、武劉徹皇帝、宣劉勲皇帝、袁劉世皇帝、成劉敖皇帝です。 その中で、Liu Bangは5人の妻でしたu Cheは6人の妻でした。彼らは次のとおりですWang Zhengjun、Xiaoyuan Fu皇帝、Dowager Zhongshan Feng Yuanが4人の妻を持っていました。 公式の歴史記録によると、一夫一婦制だった皇帝は他に5人いる。恵劉英帝、少劉洪帝、趙劉福陵帝、艾劉欣帝、平劉欣帝である。 東漢には9人の皇帝がいたが、全員が一夫多妻制を実践していた。漢の武帝には皇后が2人おり、それぞれ光武皇后郭聖統と皇后広烈殷麗華、明帝には皇后明徳馬と賈妃、章帝には皇后小徳竇、皇后公懐梁、皇后静隠宋、和帝には皇后小河殷と皇后和佳鄧遂、安帝には皇后安慈閻忌と恭愍皇后、順劉豫には2人の妻がいて、順烈皇后梁娜と于妃であった。衡帝には4人の妻がいて、夷仙皇后梁女英、孝衡皇后鄧孟女、衡思竇妙皇后、蔡女天生であった。霊劉洪には3人の妻がいて、宋孝陵皇后、霊思何皇后、霊懐王皇后であった。献帝劉謝には5人の妻がいて、孝仙扶寿皇后、献母曹潔皇后、董妃、曹献夫人、曹華夫人であった。 三国時代、曹魏には5人の皇帝がいたが、そのうち3人は一夫多妻制、2人は一夫一婦制だった。 一夫多妻制を実践した3人の皇帝のうち、文曹丕帝には文昭真洛皇后と文徳皇后郭妃の2人の妻がいた。明曹睿帝には明道茂皇后、明元国皇后、虞夫人の3人の妻がいた。三仁帝の曹芳には真皇后、張皇后、王皇后の3人の妻がいた。 一夫一婦制を実践した人物は、第4代皇帝曹髙と第5代皇帝曹勉の2人です。 蜀漢帝国には二人の皇帝がいたが、どちらも一夫多妻制を実践していた。そのうち、昭烈皇帝劉備には昭烈甘皇后、穆無仙皇后、孫夫人の3人の妻がおり、后劉禅には張静蓋皇后、張皇后、李昭宜の3人の妻がいた。 東呉には4人の皇帝がいたが、そのうち2人は一夫多妻制、2人は一夫一婦制だった。一夫多妻の男性の中で、孫権帝には謝夫人、徐夫人、潘皇后、朱皇后、王大義皇后、王景懐皇后、袁夫人の 7 人の妻がいました。孫昊帝には滕皇后、張美人、張左夫人の 3 人の妻がいました。 2代皇帝孫良と景帝孫秀はともに一夫一婦制であった。 晋の皇帝は15人いたが、そのうち6人が一夫多妻制を実践していた。武帝司馬炎(妻は6人)、恵帝司馬忠(妻は3人)、袁帝司馬睿(妻は3人)、成帝司馬炎(妻は2人)、建文帝司馬瑜(妻は2人)、孝武帝司馬瑶(妻は3人)である。 懐帝の司馬池、閔帝の司馬漢、明帝の司馬紹、康帝の司馬越、穆帝の司馬旦、艾帝の司馬丙、費帝の司馬懿、安帝の司馬徳宗、公帝の司馬徳文はいずれも一夫一婦制であった。 五夷十六国時代の成漢帝国には3人の皇帝がいた。武帝の李雄と墨帝の李世は一夫一婦制で、昭文帝の李寿には2人の妻がいた。 前趙帝国には4人の皇帝がいたが、そのうち3人は一夫多妻制を実践していた。文帝劉淵には3人の妻がおり、昭帝劉聡には14人の妻がおり、墨帝劉堯には4人の妻がいた。 殷劉禅皇帝は一夫一婦制の男性でした。 後趙朝には4人の皇帝がいたが、そのうち2人は一夫多妻であった。明世勒帝には2人の妻がおり、武世虎帝には5人の妻がいた。最後の二人の皇帝、史々皇帝と史尊皇帝はどちらも一夫一婦制でした。 藍薇帝国の両皇帝は一夫一婦制を実践した。 3人の妻がいた玄昭帝の傅堅と2人の妻がいた高帝の傅登を除いて、前秦帝国の他の4人の皇帝は一夫一婦制であった。 後秦には二人の皇帝がいたが、どちらも一夫多妻制を実践していた。武昭帝の姚昌には二人の妻がおり、文衡帝の姚興にも二人の妻がいた。 西秦は皇帝を名乗らなかったため、統計には含まれません。 前燕帝国には3人の皇帝がいたが、そのうち2人は一夫多妻であった。文明帝慕容璋には2人の妻がおり、景昭帝慕容君にも2人の妻がいたが、もう一人の皇帝(游帝慕容■)は一夫一婦であった。 後燕帝国には4人の皇帝がいたが、そのうち3人は一夫多妻であった。武成帝慕容垂には3人の妻がおり、恵民帝慕容宝には2人の妻がおり、昭文帝慕容熙には2人の妻がおり、そのうちの1人(二代皇帝慕容勝)は一夫一婦制であった。 南燕帝国には二人の皇帝がいました。一人は一夫多妻制の二代皇帝慕容超(二人の妻がいました)で、もう一人は一夫一婦制の初代皇帝慕容徳でした。 北燕には3人の皇帝がいたが、そのうち2人は一夫多妻制であった。文成帝の馮覇と昭成帝の馮洪(それぞれ妻が2人いた)。もう1人は一夫一婦制であった。恵義帝の高雲である。 後梁帝国には4人の皇帝がいた。義武帝(呂光)は一夫多妻(2人の妻を持つ)であったが、他の3人の皇帝は一夫一婦制であった。 大夏帝国の両皇帝は一夫一婦制であった。 南北朝時代、南朝の劉宋帝国には9人の皇帝がいたが、そのうち4人は一夫多妻であった。武帝劉裕(妻3人)、文帝劉宜龍(妻4人)、孝武帝劉鈞(妻2人)、明帝劉朔(妻3人)の4人である。残りの5人は一夫一婦制です。 南斉には7人の皇帝がいた。2人の妻がいた6代目の皇帝、孝宝娟を除いて、他の皇帝は一夫一婦制だった。 小梁帝国には5人の皇帝がいた。3人の妻がいた武孝延帝と2人の妻がいた袁孝懿帝を除いて、残りは一夫一婦制だった。 陳帝国には5人の皇帝がいた。2人の妻がいた初代皇帝の陳伯賢と3人の妻がいた第5代皇帝の陳叔宝を除いて、残りの皇帝は一夫一婦制だった。 北朝(東魏、西魏を含む)の北魏には18人の皇帝がいたが、そのうち、妻が3人いた道武帝の拓跋桂、妻が2人いた明元帝の拓跋思、妻が3人いた太武帝の拓跋扈、妻が2人いた文成帝の拓跋鈞、妻が4人いた孝文帝の元弘、妻が3人いた宣武帝、妻が2人いた文元宝舒を除き、全員が一夫一婦制であった。 北斉には8人の皇帝がいた。3人の妻がいた文宣帝の高陽、2人の妻がいた武成帝の高璋、4人の妻がいた后帝の高威を除いて、彼らは全員一夫一婦制だった。 北周には5人の皇帝がいた。北周の武帝宇文雍は2人の妻がいたが、北周の宣帝宇文郁は5人の妻がいたが、それ以外は一夫一婦制だった。 隋には5人の皇帝がいた。3人の妻がいた文洋堅帝と2人の妻がいた楊洋広帝を除いて、他の3人は一夫一婦制だった。 唐代には一夫多妻制を実践した皇帝が21人いた。太宗李世民(妻が2人)、高宗李治(妻が3人)、中宗李献(妻が3人)、睿宗李丹(妻が2人)、玄宗李龍基(妻が5人)、粛宗李衡(妻が2人)、代宗李裕(妻が2人)、徳宗李世(妻が2人)、献宗李淳(妻が2人)、穆宗李衡(妻が3人)、易宗李裕(妻が3人)、昭宗李業(妻が3人)である。残りの皇帝は一夫一婦制であった。 五代十国時代、後梁には三人の皇帝がいた。太祖朱文には三人の妻がおり、最後の皇帝朱有貞には二人の妻がおり、二代皇帝朱有貴は一夫一婦制であった。 後唐には4人の皇帝がいた。荘宗の李存勗には4人の妻がいた。明宗の李嗣源にも4人の妻がいた。閔帝の李従厚と墨帝の李従克はともに一夫一婦制であった。 後金には二人の皇帝がいた。高祖の世景堂皇帝は一夫一婦制であったが、楚の世崇貴皇帝には二人の妻がいた。 後漢には二人の皇帝がいました。高祖劉志遠帝は一夫一婦制で、殷劉承有帝には二人の妻がいました。 後周には3人の皇帝がいた。太祖郭惟には4人の妻がおり、世宗郭容には3人の妻がいたが、恭斎宗は一夫一婦制であった。 前蜀には二人の皇帝がいた。高祖王翦には四人の妻がおり、后帝王延には三人の妻がいた。 南呉の始皇帝楊行密には二人の妻がいたが、楊普帝は一夫一婦制であった。 燕の桀帝、劉有光には2人の妻がいた(皇帝の在位期間は1期のみ)。 南漢帝国には4人の皇帝がいた。2人の妻がいた4番目の皇帝劉基を除いて、残りは一夫一婦制だった。 閩朝には4人の皇帝がいたが、そのうち3人は一夫多妻制を実践していた。徽宗の王延君は2人の妻を持ち、康宗の王継鵬は2人の妻を持ち、景宗の王延熙は2人の妻を持ち、4代皇帝の延正は一夫一婦制であった。 後蜀には二人の皇帝がいました。初代皇帝の孟志襄には二人の妻がいましたが、二代目皇帝の孟仁山には一夫一婦制がありました。 南唐帝国には三人の皇帝がいた。そのうち、李勝帝には二人の妻がいた。李玉帝にも二人の妻がいた。元宗李経帝には一夫一婦制があった。 北宋には9人の皇帝がいた。そのうち、太祖趙匡胤は3人の妻を持ち、太宗趙光義は4人の妻を持ち、真宗趙衡は6人の妻を持ち、仁宗趙守義は8人の妻を持ち、神宗趙旭は5人の妻を持ち、哲宗趙旭は2人の妻を持ち、正宗趙季は8人の妻を持ち、英宗趙叔と欽宗趙桓はともに一夫一婦制であった。 南宋には9人の皇帝がいた。そのうち、高宗趙狗は7人の妻を持ち、小宗趙伯聡は5人の妻を持ち、光宗趙盾は2人の妻を持ち、寧宗趙括は3人の妻を持ち、礼宗趙貴成は3人の妻を持ち、都宗趙孟奇は4人の妻を持ち、残りは一夫一婦制であった。 遼帝国には10人の皇帝がいた。そのうち、世宗耶律武瑜帝には2人の妻がいた。聖宗耶律龍珠帝には2人の妻がいた。道宗耶律弘基帝には3人の妻がいた。興宗耶律宗真帝には2人の妻がいた。天佐耶律延師帝には4人の妻がいた。残りの皇帝は一夫一婦制であった。 晋の皇帝は9人いた。そのうち、太祖阿陀には5人の妻がいた。咸宗の万延丹には2人の妻がいた。4代皇帝の万延良には20人の妻がいた。世宗の万延容には3人の妻がいた。章宗の万延経には4人の妻がいた。玄宗の万延恕には3人の妻がいた。残りの皇帝は一夫一婦制だった。 元朝には14人の皇帝がいた。そのうち、太祖テムジンは44人の妻を持ち、太宗オゴデイは6人の妻を持ち、献宗モンケは5人の妻を持ち、静祖フビライ・ハーンは8人の妻を持ち、成宗テムルは3人の妻を持ち、武宗ハイシャンは6人の妻を持ち、人宗アユルバルワダは2人の妻を持ち、英宗シュオデバラは3人の妻を持ち、太定皇帝イェスン・テムルは11人の妻を持ち、明宗和氏▲は6人の妻を持ち、順帝トフアイ・テムルは3人の妻を持ち、残りの皇帝は一夫一婦制であった。 明朝には17人の皇帝がいた。そのうち、太祖朱元璋には4人の妻がいた、成祖朱棣には3人の妻がいた、仁宗朱高池には3人の妻がいた、玄宗朱瞻基には15人の妻がいた、英宗朱其真には2人の妻がいた、景宗朱秋瑜には2人の妻がいた、献宗朱建深には6人の妻がいた、世宗には6人の妻がいた、穆宗朱在厚には3人の妻がいた、神宗朱義君には5人の妻がいた、光宗朱昌洛には6人の妻がいた、徽宗朱有霄には4人の妻がいた、世宗朱有堅には3人の妻がいた。残りの皇帝は一夫一婦制であった。 清朝には12人の皇帝がいた。そのうち、太祖ヌルハチには12人の妻がいた。太宗黄太極には14人の妻がいた。石祖福麟には18人の妻がいた。聖祖玄野には32人の妻がいた。世宗殷真には7人の妻がいた。高宗弘理には19人の妻がいた。人宗永厳には11人の妻がいた。玄宗閔寧には16人の妻がいた。文宗懿▲には9人の妻がいた。穆宗在淳には5人の妻がいた。徳宗在田には3人の妻がいた。玄統溥儀には5人の妻がいた。 从上面列举的统计资料中我们可以看出:富有四海的皇帝们既有一夫多妻的:富有四海的皇帝们既有一夫多妻的、也有一夫一妻的 - - 本处所说的“一夫一妻”是指在官修的正史中除了“一妻”以外再没有别的妻子记载的、这里面有可能存在着两种情况、这里面有可能存在着两种情况、一种是这些皇帝们真的是一夫一妻、如五代十国时的南吴的让帝杨溥、实际上还不如一个囚徒、实际上还不如一个囚徒、举个例来说、他常常挨打、被其手下的大臣说揍一顿就揍一顿(详情请参见拙著《中国帝王私生活百态》一书)、这种囚徒似的皇帝根本不可能敢娶几个老婆。もう一つの例は、元代の寧宗皇帝、易連芝班が亡くなったとき、彼はまだ7歳でした。彼の妻、大理耶特美師も彼と同い年でした。そのような若さで妻を持つことは意味がなかったかもしれませんし、彼がさらに妻を持つことは不可能でした。もう一つの可能性は、皇帝はもともと一夫多妻制でしたが、正史には多くの美女のうちの1人の名前しか残っていないため、歴史の記録では才能が重要視されるという原則に基づいて、彼らを一夫一婦制の人物として分類するしかないということです。 一夫多妻制における「多」の数は最大で44人です。この「中国記録」を樹立したのは、元朝の創始者であるチンギス・ハーンです。一夫多妻制の最小人数は2人以下です。 「より多く」の意味は王朝によって異なりました。明代以前(明代を含む)は、大帝国の皇帝の間では常に「一夫多妻制」と「一夫一婦制」が共存していた。清代になって初めて、12人の皇帝全員が一夫多妻制を実践した。 昔は「妻が多ければ子供が多ければ祝福も増える」とよく言われていましたが、これには科学的な根拠はあまりありません。言うまでもなく、妻をたくさん持つことは必然的に嫉妬や陰謀を招きますし、妻をたくさん持つことは必ずしも多くの子供を持つことを意味しません。南宋の高宗皇帝趙狗には7人の妻がいましたが、誰も子供を産みませんでした。結局、彼は一族の秀王趙自成から息子を養子として迎え、王位を継承しなければなりませんでした。この養子が南宋の2代目皇帝、孝宗皇帝趙伯聡です。明の僖宗の朱有嬪には4人の妻がいたが、子供がいなかったため、王位は弟の朱有建(崇禎)に継承された。清の穆宗の在淳には5人の妻がいたが、子供がいなかったため、従弟の在天が王位を継承した。 周の儀式を制定したのは「伯周」ではなく周公だったため、一夫多妻制は永遠の常識になったようだと冗談を言う人もいる。しかし、すべての皇后(皇帝の正妻)がこれを容認できたわけではない。最も有名な例の1つは、隋の文帝の正妻である独孤皇后である。彼女は夫と結婚したとき、夫に「他家の子供は産まない」と宣言させた。彼女の夫は皇帝になった後、一度不貞を働き、玉池という宮廷女官と性交した。独孤はすぐに思い切った手段を取り、玉池を処刑し、彼女と夫の間の一夫一婦制を維持した。しかし、彼女が死ぬとすぐに、彼女の夫である文陽堅帝は、さらに数人の妻を聖人にした。この例は、色欲と一夫多妻制が皇帝の一般的な特徴であり、また彼らの本質の一部であることを示しています。 それでも、古代と現代の歴史記録(正史)を調べてみると、「三つの宮殿、六つの庭、七十二人の側室」を持った皇帝は見つかりませんでした。 これまでの大衆文学作品や民間口承文学では、隋の楊広帝や晋の第4代皇帝万延良がいかに淫乱で、妻妾が何千人もいたかが、よく「言及」され、人々に語られていた。一方では、こうした誇張は無知や誤解によるものかもしれないが、他方では、作者の灰色の鑑賞精神を排除するものではない。 |
<<: 武則天はなぜ国名を周に変更したのですか?武則天の国名の由来を解明
>>: 対スパイ活動の物語: 誰が対スパイ活動を利用して岳毅を排除したのか?
推薦する
李毓の抒情詩「滴蓮花・春宵」鑑賞
以下、Interesting History の編集者が、李游の「當連花・春宵」の原文と評価をお届け...
小説『紅楼夢』では寒くて雪の降る日はどのように描かれているのでしょうか?それはどういう意味ですか?
『紅楼夢』は中国四大古典小説の一つで、女性の美しさと古代中国社会のさまざまな側面をあらゆる角度から描...
『紅楼夢』で秦克清が亡くなった後、宝玉はどれほど悲しかったのでしょうか?それはなぜでしょうか?
『紅楼夢』の男性主人公、賈宝玉は、賈家では一般的に宝師として知られています。多くの読者が気になる問題...
「大連花・送春」の原文翻訳と鑑賞
蝶の愛の花 - 別れの春朱叔珍(宋代)建物の外には何千本もの柳の木がぶら下がっています。若さを保ちた...
劉宗元はなぜ劉柳州と呼ばれるのですか?その理由は、劉宗元が柳州知事としての職を終えたからである。
劉宗元(773-819年)は、字を子侯といい、河東(現在の山西省運城市永済)出身の漢人である。唐宋八...
「古口書斎より楊不韵に宛てた手紙」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
【オリジナル】茅葺き屋根の周囲には泉と溝があり、雲と霧が葦のカーテンを形成しています。竹は雨上がりの...
欧陽秀の有名な詩の一節を鑑賞する:鹿車はいつ英東の野に戻ってくるのだろうか?
欧陽秀(おうようしゅう、1007年8月1日 - 1072年9月22日)、字は永叔、晩年は随翁、劉義居...
ヤオ族の宗教 ヤオ族の宗教信仰の紹介
広西ヤオ族の文献『聖書南辞』には100以上の神々が記載されている。ヤオ族の宗教は、異なる歴史的時期に...
王維の「狩猟を見る」:この詩は「狩猟」という言葉に関連している
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
中国の四大発明はどのようにして海外に広まったのでしょうか?
古代中国の四大発明が人類文明史上重要な位置を占めていることは、中国が古代文明となったことの象徴の一つ...
『紅楼夢』で賈祖母はなぜ賈環と賈聡を宝玉ほど好まなかったのでしょうか?
賈おばあさんは寧と容の邸宅の最高責任者で、人々は彼女を「おばあさん」「老祖」と呼んでいます。今日は、...
天子鍾馗が鬼を祓う物語。鍾馗はどうやって鬼を祓ったのでしょうか?
唐代の開元年間、国は平和で民衆は繁栄していました。当時、中南山の麓に「鍾学九」という学者が住んでいま...
赤壁の戦いの際、曹操陣営の誰かが周瑜の火攻めの意図に気付いたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
天皇は皇族や婚姻関係にある親族とより近い関係にあるのでしょうか?
「外縁による権力独占」という現象は漢代にのみ深刻だったのではなく、実は古代社会では常に一般的な現象だ...
荊州を守るために関羽の代わりに諸葛亮と趙雲がいたらどうなるでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...