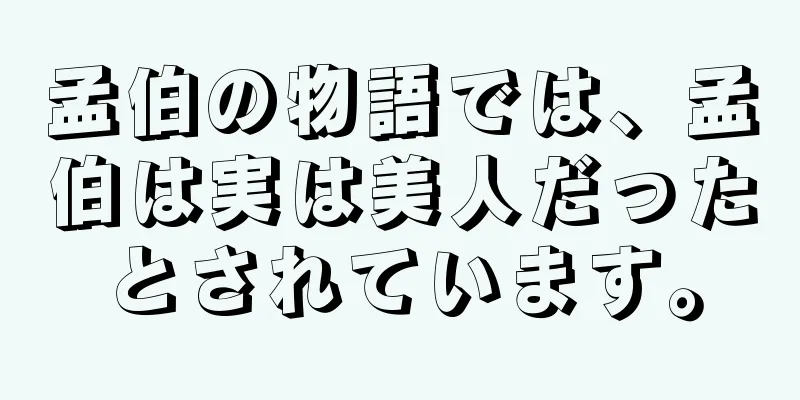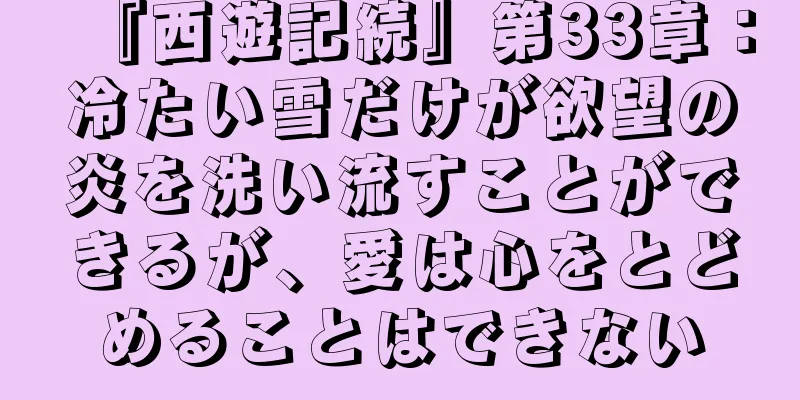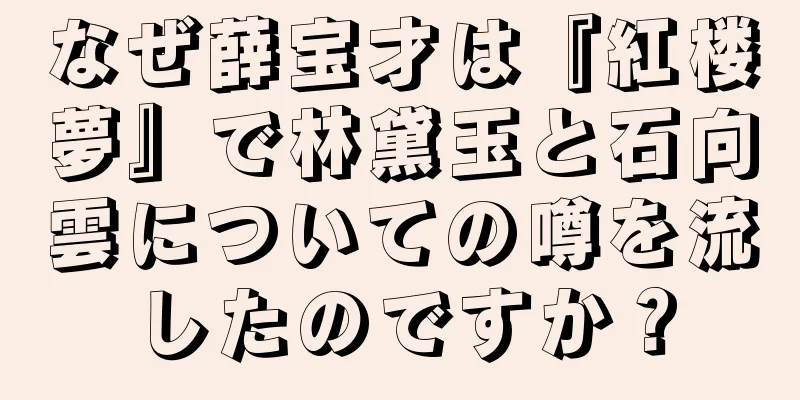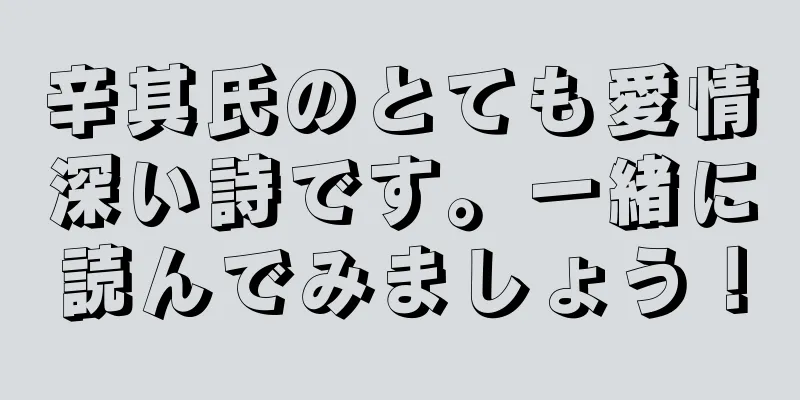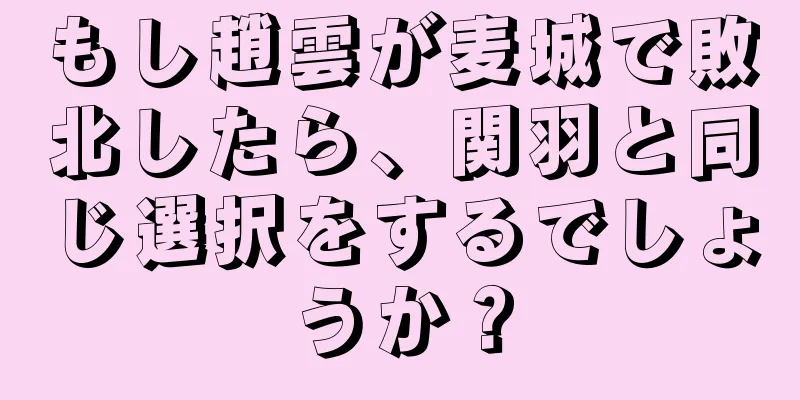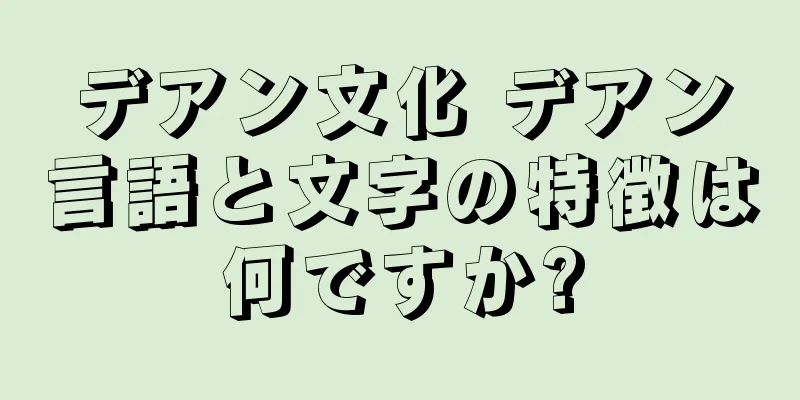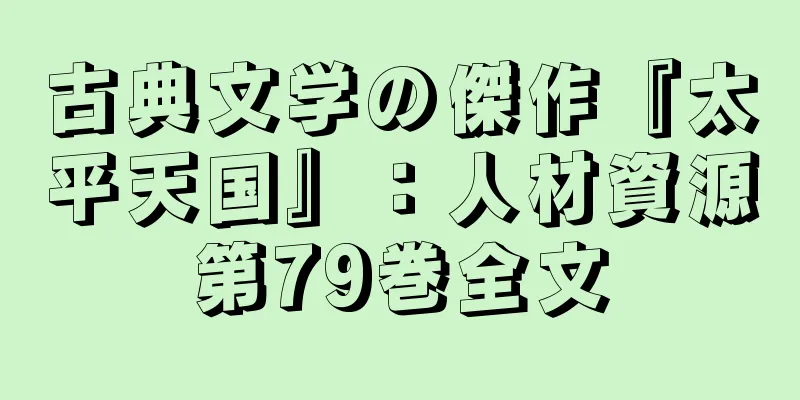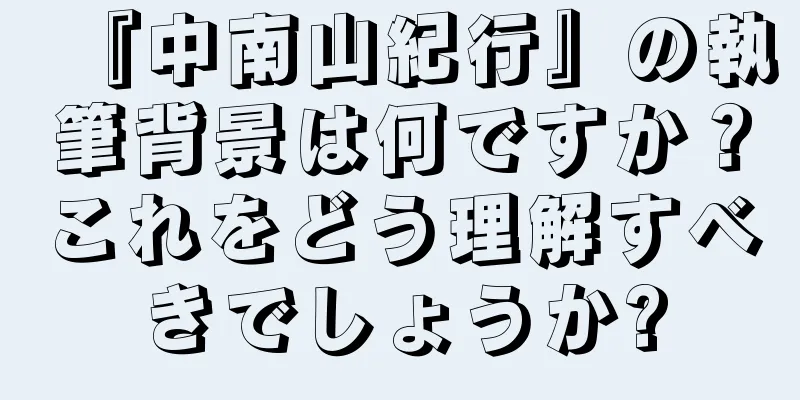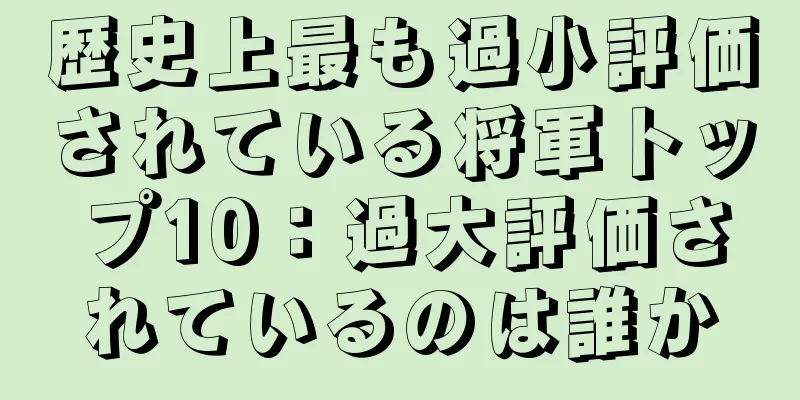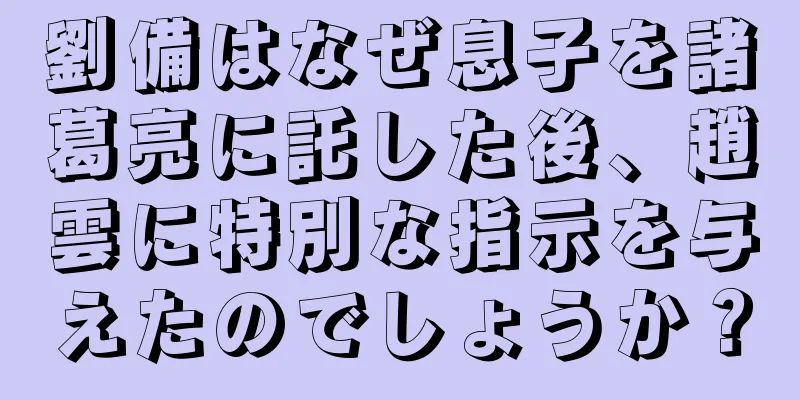「司馬武定」がなぜ「後馬武定」に改名されたのですか?
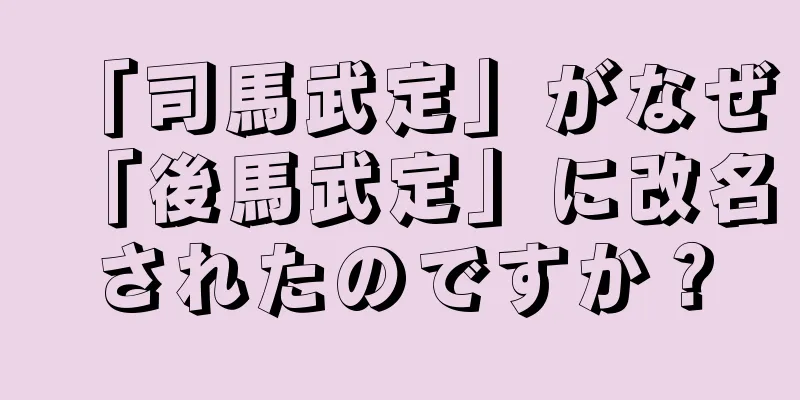
|
2011年3月中旬から上旬にかけて、「思母屋丁」が正式に「後母屋丁」に改名されるというニュースがネットや新聞で報じられ、大きな注目を集めた。それを評価する人もいれば、反対する人もいました。四木屋丁の名称は数十年にわたって使用され、国の教科書にも掲載され、殷沐が世界文化遺産に申請された際に国連に報告されたため、今日変更する必要はないと考える人もいます。四武丁の名前は説明できるので、変える必要はないと言う人もいます。どちらの名前も受け入れられるので、名前を変更する意味はほとんどないと言う人もいます。ここでは、私なりの認識を述べつつ、商王朝の31人の王のうちどの王がこの大鉾を鋳造したのか、そして后母武は誰の母なのかについてもお話ししたいと思います。 (1つ) 1970年代から、Simuwu Dingの名称をめぐって論争が続いてきた。鍵となるのは「Si」という言葉の解釈です。この文字は青銅の碑文に属します。 漢字の発展段階には、一般的に次の 5 つの段階があると考えられています。 甲骨文字、銅文字、篆書、隷書、楷書。 しかし、書くことの発達段階は明確に分けられていません。甲骨文字が使われていた頃にはすでに青銅銘文が登場していた。司馬屋丁の青銅銘文は最古の青銅銘文であり、甲骨文と同時代のものである。 甲骨文字には、陽と陰が共存する現象があり、つまり、文字は陽にも陰にも書かれることがある。例えば: 文字は前向きにも後ろ向きにも書くことができます。この前向きと後ろ向きの共存は、初期の漢字の特徴です。これは甲骨文字や青銅文字にも当てはまります。商代の青銅銘文における「斯」と「侯」の文字も、上述の甲骨文字の例と同じである。 上記の原則を理解していれば、Simuwu Ding の「Si」という文字を見ると、「Si」または「Hou」と発音できることが分かります。 現代の漢字では「司」と「后」という二つの文字を混同することはありませんが、青銅銘や甲骨文では、これらは陽字と陰字の両方で同じ文字です。このように、Simuwu Dingの「Si」という文字は、「Si」という文字、または「Hou」という文字であると言えます。これが、良い面と悪い面が共存する理由です。 (二) 思母屋丁の「母」は母を意味します。商王朝の人の名前は、賈、易、兵、丁でした。『思母武定』の「武」という文字は、母親の名前「武」を意味します。 昔はSimuwu Dingと呼ばれていました。Siは犠牲を意味します。司母武は「武」という名で崇拝される母である。文法構造の観点から見ると、「Si Mu Wu」という3つの単語は、主語と動詞の構造を持つフレーズです。以下のように表示されます。 この句の性質は動詞句です。 現在は Houmuwu に変更されています。"Hou" は女王または母親を意味します。后母語の「后」は地位を意味します。ここでは、前王の王妃、または現王の母を指します。 「后母武」という3つの文字は、女王の母親の名前が武であることを意味します。文法構造の観点から見ると、3 つの単語は同格関係の句を形成します。以下のように表示されます。 いわゆる同格関係とは、2 つの単語が同じ人または物を指し、同じ文の構成要素として機能することを意味します。 上記の句の性質は名詞句です。 個別に議論すれば、Simuwu と Houmuwu の両方を説明することができます。 (三つ) 今度は、大きな三脚に名前を付けましょう。三脚の命名については、昔は周の時代の有名な三脚である毛公丁に人名がつけられているのをよく見かけました。もう一つの例は、1935年に殷墟王墓地区の第1004号墓から発掘され、その模様にちなんで名付けられた牛鼎と鹿鼎です。これらの名前の共通点は、すべて名詞または名詞句にちなんで名付けられていることです。四母武鼎は「母武に犠牲を捧げる」という動詞句にちなんで名付けられましたが、これは明らかに不適切です。これを后母武に変更すると、名詞句、つまり人名にちなんで命名され、つまり、この大きな三脚は母后母を記念して鋳造されたということになり、命名規則に合致します。考古学的な観点から見ると、後墓址は墓主の名前であり、墓主の名前は名詞句でなければなりません。 四木屋丁の改名は、祖国の言語と文字をいかに正しく理解し、使用するかという問題である。また、数十年にわたって誤解されてきたこの貴重な民族文化遺産に正しい名前を回復するという問題でもある。後木屋丁は殷舒で発掘されました。安陽は後木屋丁の故郷です。現在、後木屋丁は正しい名前を持っています。後木屋丁の故郷の住民として、私たちはこれを喜び、応援するべきです。 教科書に士武丁の名称が記載される問題に関しては、この変更は大した問題ではありません。教科書が頻繁に変更されていることに人々は気づいているだろうか。例えば、かつての教科書には「母の記憶」(朱徳の論文)という記事がありましたが、記事のタイトルが曖昧で、「母」は「記憶」の受け手とも「記憶」の主体ともとれるという意見が出ました。後に「母を偲んで」に変更されました。国定教科書の編纂においては、言語と文章の標準化が最も重視されています。 『四木武定』の名称変更は言語と文字の標準化を伴うものであり、名称変更は教科書編集に関する国家の要求に完全に沿ったものである。国連宣言に関しては、それはさらに問題が少ない。国連が四木屋丁の名称変更を理由に、殷墟の世界文化遺産登録を否定することは決してないだろう。それどころか、事実に基づいて真実を追求する中国の精神は、国際的にさらに尊重されるようになるだろう。 (4) 後母武定は商王朝のどの時代の王の鋳造ですか?後母武は誰の母親ですか?昔、文武定は母親を崇拝するためにこの大きな鼎を鋳造したと言う人もいます。現在では、祖庚または祖嘉が母親を偲んでこの大きな三脚を鋳造したと言われています(2011年3月17日の安陽ラジオテレビニュースを参照)。これらの主張の根拠が何なのか分かりません。最近、私は、後木武丁の青銅銘文が甲骨文と同時代のものであることから、甲骨文にも「木武」という名前が登場しているに違いないと考えました。昔は「沐庸」や「沐心」という名前をよく見かけましたが、「沐武」という名前には注目していませんでした。そこで、安養師範大学コンピュータ情報工学部から提供されたソフトウェア「甲骨文字コーパス」で検索してみました。 『甲骨文字絵画集』の資料には、中国国内外の有名な甲骨文字記録が 10 点含まれています。ついに満足のいく答えが得られました。 「Muwu」という名前のアイテムは 20 件あります。引用されているのは以下の4項目です。 (1)卯卯占いでは、母豚の丑を2匹使います。 3月(コレクション19954) (2)…羊(ムウ)。 (コレクション 19955) (3)嘉神の年に慧珠が木武に生まれた。 (コレクション 22076) (4)嘉(徐)、真(鎮)、そして年の母は呉。 ウーお母様。 (コレクション 22206) 上記4点はいずれも郭沫若編『甲骨文集』第7巻に収録されている。内容から判断すると、いずれも供儀の碑文であり、「木兎」が供儀の対象となっている。これら4つの甲骨文字はいずれも甲骨文字の第一期、つまり武定時代の甲骨文字である。 「沐武」は武定の母であり、小怡の配偶者であり、武定の王妃ではないことは明らかです。 歴史家は武定の治世を黄金時代と呼ぶことが多い。商王朝は、商王朝の31人の王の中で最も優れた功績を残した武定の治世中に、総合的な国力が最も強かった。後木武鼎は武定皇帝の繁栄した治世中に鋳造された可能性が十分にある。後木武丁の鋳造時期と一致するのは武定時代のみである。 甲骨文字の発見により、我が国の記録文書の歴史はおよそ 1,000 年前に遡りました。後木武鼎の「木武」は甲骨文字の中に発見されており、それを裏付ける文書による証拠があることを示しています。もし祖庚や祖嘉が母を偲んで鋳造したと信じられているなら、甲骨文字第二期に「母武」という名前が見当たらないので、当然祖庚や祖嘉の母ではあり得ない。また、甲骨文字第四期には「木武」という名前は見当たらないので、この大きな三脚が丁文武によって母親への供物として鋳造されたものである可能性はさらに低い。 |
<<: 正官治世の背後にある価値追求:人口増加が最優先事項に
>>: 唐の代宗皇帝李毓には何人の息子がいましたか?唐代宗皇帝の子供、李玉の簡単な紹介
推薦する
『紅楼夢』の林黛玉の飲酒ゲームとは何ですか?何か比喩はありますか?
林黛玉は中国の古典小説『紅楼夢』のヒロインです。下記の興味深い歴史編集者が詳細な解釈をお届けしますの...
『梁書』に記されている陳伯之とはどのような人物でしょうか?陳伯之の伝記の詳細な説明
南北朝時代の梁朝の歴史を記した『梁書』には、6巻の史書と50巻の伝記が含まれているが、表や記録はない...
『紅楼夢』で賈一家が略奪された後、喬潔に何が起こったのですか?
賈邸への襲撃は『紅楼夢』の中で最も悲劇的な場面である。 Interesting Historyの編集...
四聖心の源泉:第6巻:雑病:走る豚の根
『四聖心源』は、1753年に清朝の黄元宇によって書かれた医学書で、『医聖心源』としても知られています...
ナポレオンの身長はどれくらいでしたか?ナポレオンの身長に関する興味深い話をしてください
ナポレオンの身長に関する興味深い話1. このギャップはいつでも埋められるナポレオンの身長はわずか 1...
南朝時代の作家、呉俊は、人を酔わせる20字の詩を書いた。
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日は呉俊の物語をお話ししま...
中国の伝統文化作品の鑑賞:『易経』第14卦「大有」の原文は何ですか?
大有卦は豊穣を象徴します。火は火を、天は空を表し、炎は空高く舞い上がります。つまり、空には太陽が輝き...
秋千池を演じる俳優の紹介 秋千池 羅蘭はかつて母親から批判された
秋千池を演じる俳優秋千池は金庸によって創造された古典的な悪役です。彼女は武侠小説『射雁英雄の帰還』に...
李毅の「竹窓から風を聞いて苗法思空書に手紙を送る」は、友人への思いを表現しています。
李毅は、号を君于といい、唐代の官吏、詩人である。詩風は大胆で明快である。辺境詩で有名で、七字四行詩を...
なぜ劉禅は劉雍の称号を甘陵王に、劉礼の称号を安平王に変更したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
王師父の代表作『西室』はどのような精神を表現しているのでしょうか?
ご存知の通り、『西室物語』は元代の王師父の代表作の一つです。劇全体は学者の張勝(張俊瑞)と宰相の娘の...
黄庭堅の「清明」:この詩は、詩人が情景に触発されて書いた感情の作品である。
黄庭堅(1045年6月12日 - 1105年9月30日)、字は盧直、幼名は聖泉、別名は清風歌、善宇道...
清朝における近衛兵の地位は何でしたか?宮殿の衛兵はなぜ「豚の膀胱」を腕に抱えていることが多いのでしょうか?
今日は、清朝の近衛兵がどのような立場であったかを『おもしろ歴史』編集長がお伝えします。皆さんのお役に...
林黛玉は賈宝玉との愛に支えが必要だと知っていたのに、なぜ賈おばあちゃんに助けを求めなかったのか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
数学の巨匠ガウスが、生涯で10以上の分野に携わったのはなぜでしょうか?
数学者ガウスに関する逸話は数多くある。最も興味深い逸話の一つは、ガウスが小学生の頃、数学の先生が生徒...