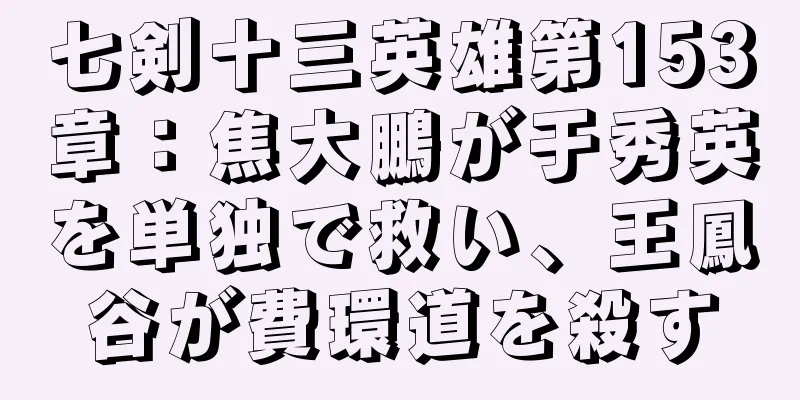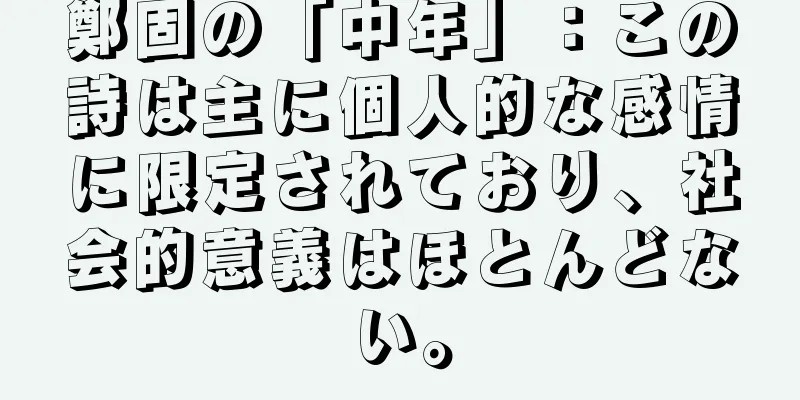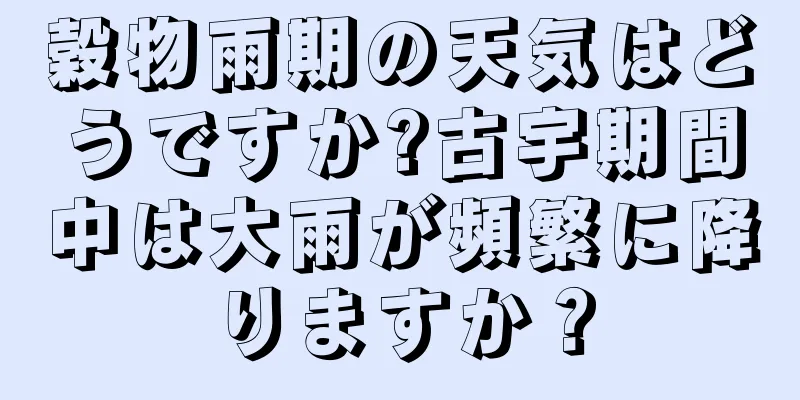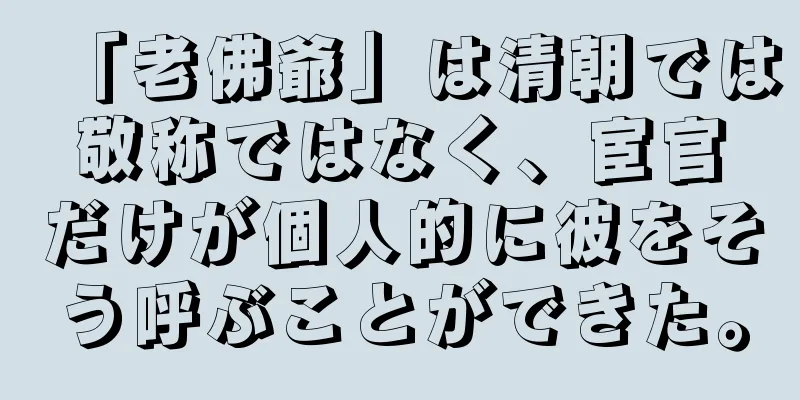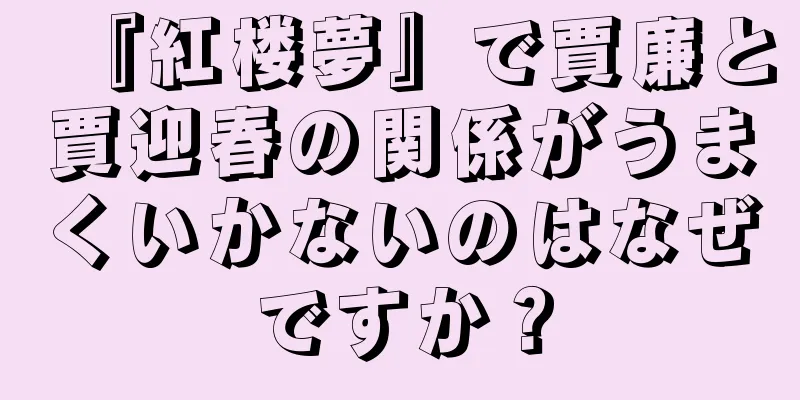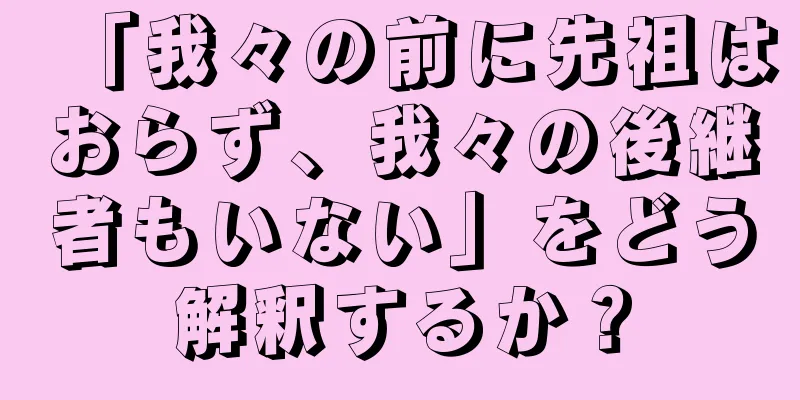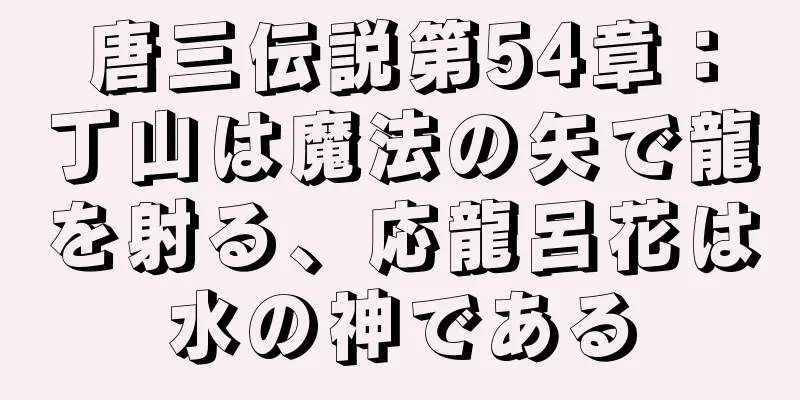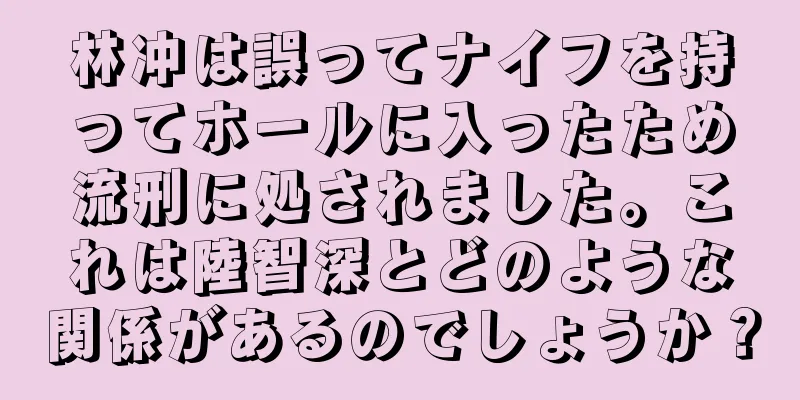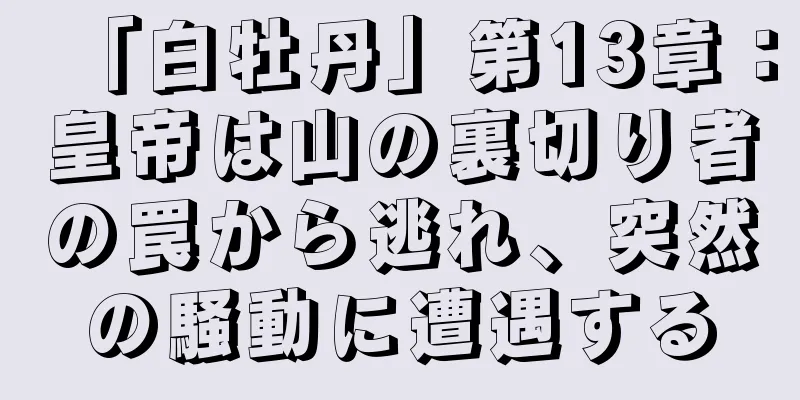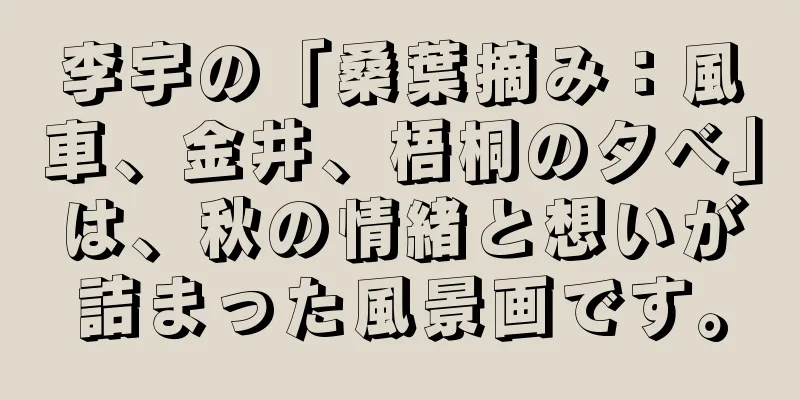明治維新が成功し、百日天下の改革が失敗した本当の理由は何でしょうか?
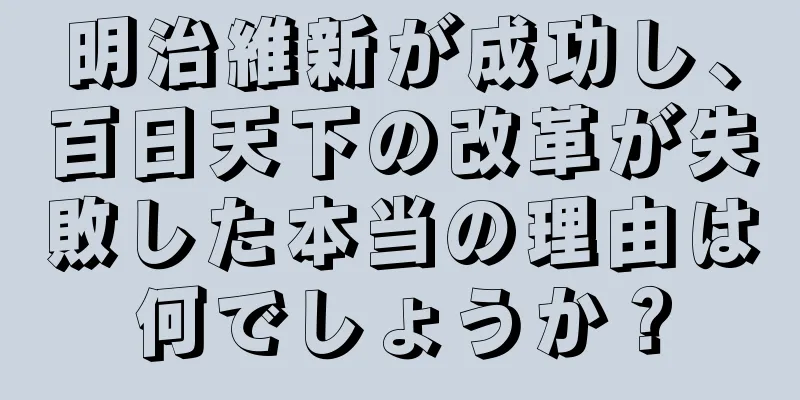
|
百日天下の改革と明治維新は、どちらもアジアの隣国で起こりました。しかし、歴史は日本と中国が非常に異なる結果を達成したことを示しています。日本は改革を成功させたが、中国は完全に失敗した!なぜ日本は成功し、中国は失敗したのか?その理由は、当時の社会制度、人々の考え方、改革の方法と内容などによるもので、それが中国の失敗と日本の成功を決定づけたのです。 改革の社会制度の観点から見ると、改革以前の中国は伝統的な封建制度の社会であり、1840年のアヘン戦争で敗北していました。中国と世界との関係は前例のない変化を遂げた。中国の政治権力発展システムは「中央集権型」の発展モデルです。清朝末期には、システムは王朝全体の中央集権化の頂点に達し、皇帝の権力は人々の生活のあらゆる面に浸透していました。社会システムの管理者が自由に使える権力はほとんどありません。改革とは中央集権体制を変えることです。中央集権体制に挑戦することは、間違いなく王権を危険にさらすことになります。伝統的な中国の王朝は、そのような状況が起こることを許さないだろう。中国では改革の障害がさらに大きくなっています。古来、改革には流血が伴うことがほとんどでしたが、中国は妥協の姿勢を取り、武力に頼らずに問題を解決したいと考えていました。その改革は国民の支持を得られなかった。それは改革者の自覚と頑固さに過ぎません。この改革のやり方は、早い段階で失敗の種をまきました。 日本でも封建制度のもとで社会の変化が起こりましたが、日本の改革はより徹底したものでした。これにより、日本は近代化と西洋化へと進み、徐々に世界の潮流に追いつき、その後、歴史が証明しているように、世界列強の潮流を追い越して、世界をリードする国となりました。日本は突如として世界大国となり、他国を侵略する資本を得た。この小さな島国が世界大戦に参加し、主導権を握り、世界を分割する狂乱を引き起こした。これらすべての成果は反抗的な改革革命によってもたらされた。日本は徹底した改革を実行し、日本社会の進歩に有害な要因を賢明に排除し、古い封建秩序を破壊しました。そして、政治、経済、社会に大きな変化をもたらします。その後、明治政府は富国強兵、殖産興業、文明開化の三大政策を実施しました。富国強兵とは、軍警制度を改革し、軍需産業を興し、徴兵制を実施し、国家の基礎となる新たな軍警制度を構築することであり、工業と商業を発展させ、西洋の先進的な技術、設備、管理方法を導入し、資本主義の発展を強力に支援することであり、文明化と啓蒙を行い、西洋文明を学び、近代教育を発展させ、国民の知識レベルを向上させ、現代人材を育成することである。 イデオロギーの面では、封建制度下での長い孤立が中国人の世界観に影響を与えた。人民はさまざまな封建思想に縛られ、封建制度の下では、封建制が要求する支配思想を長い間学ばなければならず、それが人々の世界観を腐食させました。砲撃が玄関口に当たった時、多くの人々はまだ神に助けを懇願していました。どれだけの人が自分でナイフを取り、戦いに参加できたでしょうか?中国は広大な土地と資源を持つ国です。誰もが自分で団結できる限り、中国は今日より輝かしいかもしれません!資本主義が中国に来た時、中国人はそれが何であるかを知りませんでした!自分たちで作った火薬が奇妙な方法で使われたとき、私たちは自分たちが後進的であることを悟りました!中国人が愚かなわけではありません。私たちには偉大な国家であることを証明する4つの偉大な発明がありますが、中国人の思想と概念は支配者によってますます深く腐食されています。私たちは進歩を常に忘れていました。資本主義が中国に到来したとき、人民は支配者の統治に協力するという資本主義と両立する考えを持っていませんでした。中国では資本主義意識は非常に強いです。 日本では、日本人は「サムライ」精神を唱え、それは常に人々に受け入れられてきました。彼らは死ぬ意志に従います!彼らの考えも時代の産物ですが、日本人はそれを、戦乱の時代に国と国民を導き、強さと繁栄を求めるために必要なイデオロギー的なリーダーシップのツールに変えました。賢明で啓発された指導者がいれば、日本の国家の発展は比較的障害が少なくなり、思想や概念を変えることも難しくなくなるだろう。日本における社会変革の条件は比較的成熟している。 当時の中国には社会変革をもたらすことのできる指導者がいなかったし、当時の社会制度に武力で挑戦する賢明な指導者もいなかった!当時の封建制度を近代化に統合し、強く豊かな国を築ける者は誰もいなかった。康有為は歴史上失敗した試みだった。しかし、それは中国の発展に消えることのない貢献を果たし、その後の継続的な進歩に影響を与えてきました。 1898年の改革運動の内容は、政治面では朝廷の官吏に古いものを捨てて新しいものを求め、新しい政策を実行するよう警告した。官吏、貴族、民衆が手紙を書いて意見を表明することを奨励し、官吏がそれを妨害することを厳しく禁じた。各州の知事に時事に精通した人材を推薦するよう命じた。制度を簡素化し、余分な職員を削減し、旗本制度を廃止した。 国家から支援を受け、生計を立てることが許される特権。この政策は封建王朝の王族の多くの利益に影響を与えた。対話のために拳を使わずに全員を説得するのは難しく、反対の声はますます強くなった。改革派は独断で行動し、権力者の支持を受けなかった。経済面では、首都は鉄道鉱山局と農工商総局を設立して農業、工業、商業の発展を保護し、私営工場を提唱し、鉄道と鉱山局を設立して私営鉄道と鉱山を奨励し、国立銀行を設立し、発明を奨励し、財政を改革して国家予算と決算を編成し、宿場を廃止して郵便局を設置し、軍事面では緑営を廃止し、陸軍を訓練し、海外演習を採用し、徴兵を実施し、海軍を追加しました。文化と教育の面では、北京帝国大学が設立され、各地に中国と西洋の文芸を教える小中学校が設立され、八字文が廃止されて政策文に置き換えられ、経済の専門課程が開設され、翻訳局が設立されて外国の新刊書が翻訳され、新聞や協会の設立が許可され、海外への留学や旅行が奨励された。教育の面では、1898年の改革運動が最も大きな貢献を果たしました。 日本においては、身分制度の改革として、従来の「士農工商」という身分制度を廃止し、公卿や公子など旧貴族を「公家」に、大名以下の武士を「武士」に改め、「版籍奉還」による財政負担を軽減するため、封建的な俸給を段階的に廃止し、さらに武士の「廃刀令」や戸籍制度の基礎となる「戸籍法」を公布した。社会文化の面では、西洋の社会文化や習慣を学び、西洋の作品を翻訳することを推奨しています。暦制では太陰暦を廃止して太陽暦を採用し、西洋近代工業技術を導入し、土地制度を改革して従来の土地政策を廃止して土地取引を許可し、新たな地租政策を実施し、諸藩が設置した関所を廃止し、通貨を統一して1882年に日本銀行を設立し、商工業の発展を図るため、工商組合制度や専売組織を廃止した。教育面では近代的な義務教育が整備され、教育機関は道徳、忠誠心、愛国心などの思想を植え付けるために「試験教育勅語」を公布した。さらに、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツなどの先進国への留学も選抜しています。軍事面では、陸軍はドイツ、海軍はイギリス海軍を参考にして軍の組織が改革され、1872年には20歳以上の成人男子全員に兵役を義務付ける徴兵令が発布された。一般兵役は3年、予備兵役は2年。その後、一般兵役と予備兵役はそれぞれ3年と9年に延長され、合計12年となった。交通面では、各地の交通の整備や新たな鉄道や高速道路の建設を進めていきます。 1872年に最初の鉄道が開通し、1914年までに日本の鉄道の総距離は7,000キロメートルを超えました。司法制度に関しては、西洋の制度を模倣し、1882年に立法刑法典、1898年に立法民法典とドイツ民法典、1899年にアメリカの商法典を制定した。宗教に関しては、政府は政治的な理由から、天皇への忠誠の思想を促進し、それが天皇の国を統治する上で役立つという理由で、神道を強く奨励しました。同時に、他の宗教の存在も認められました。1873年、日本はキリスト教の布教活動の禁止を解除しました。 1871年、明治政府は資本主義国家の体制を調査するために、右大臣岩倉具視を団長とする大規模な外交使節団をヨーロッパとアメリカに派遣した。政府は富国強兵、商工業の発展、文明開化をスローガンに、西洋の科学技術を積極的に導入し、高い地租などによる大規模な原始的蓄積を進め、軍需産業、鉱業、鉄道、船舶などを中心とする国有企業を数多く設立した。同時に、製糸や紡績などの近代的な設備を導入し、モデル工場を設立し、先進技術を推進し、外国人専門家を採用し、留学生を海外に派遣し、高度な科学技術人材を育成しました。 明治政府は天皇の絶対的権威を神格化し、旧大名や公家の特別の地位を維持するために「華族制度」を確立した。また、維新の英雄や財閥を華族に組み入れ、特権階級を育成した。経済的には封建的財閥や寄生的地主を育成した。思想的には神道、皇道、儒教を奨励し、ドイツ観念論哲学を導入した。 1882年、武士道を標榜する「軍人勅諭」が発布された。 1890年、教育勅語が公布され、天皇への忠誠を中心とする軍国主義教育が推進されました。明治維新後、日本は幕府領主によって統治される封建国家から封建的な性格を持つ資本主義国家へと変貌しました。薩摩藩や長州藩など財閥と密接な関係にあった有力藩の武将や官僚貴族が長きにわたって権力を握り、近代天皇制確立の過程で「藩政政治」を遂行した。 1889年に大日本帝国憲法が公布され、1890年に国会が開設され、日本に専制君主制、すなわち近代天皇制が確立されました。外交面では、国の力が強まるにつれて交渉が続けられ、条約の改正が求められるようになった。 明治天皇 日本の百日天下と明治維新の違い。成功の必然性と失敗の必然性は比較すれば明らかです。子孫として、私たちは血を流して得た貴重な歴史的経験から学び、将来の発展のために歴史の教訓を忘れてはなりません。 |
推薦する
なぜ「中国の歴史の半分は河南省にある」と言われるのでしょうか?河南省の歴史はどれくらい長いのでしょうか?
河南省の歴史はどれくらい長いのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょ...
楽平楊麗花公主の実の母親は誰ですか?獨孤家洛の紹介
楊麗華(561年 - 609年)は、北周の宣帝宇文雲の皇后であり、隋の文帝楊堅の長女であり、母は文憲...
薛剛の反唐戦 第38話:楊秀娘が仲人役を務め、陳潔元が密かに英雄たちと友達になる
『薛剛の反唐』は、汝連居士によって書かれた中国の伝統的な物語です。主に、唐代の薛仁貴の息子である薛定...
狄公事件第49話:薛敖草が途中で捕らえられ、狄良公は泥棒を排除することを決意する
『狄公安』は、『武則天四奇』、『狄良公全伝』とも呼ばれ、清代末期の長編探偵小説である。作者名は不明で...
千歳は貴族の称号です。古代に千歳と呼ばれた人は誰でしょうか?
千歳は王爺とも呼ばれ、貴族の称号です。皇帝の叔父、兄弟など、皇帝と同じ家族の男性を指します。「王」の...
関羽は華雄を簡単に殺すことができたのだから、もしそれが河北の四柱だったらどうなるだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
ツバメが運んでくる美しい春の景色、ツバメの春の景色を詠んだ古歌集!
今日は、Interesting Historyの編集者が、ツバメと春の風景を題材にした古代の詩の一覧...
隋唐代志伝 第34章:桃の花と流水を撒いて快楽を求め、玉の手首を切って愛に報いる
『隋唐志演義』は清代の長編歴史ロマンス小説で、清代初期の作家朱仁火によって執筆されました。英雄伝説と...
岑申の詩「庭に植えたばかりのヒノキを李世武啓雲に贈る」の本来の意味を鑑賞する
古代詩:「庭に植えた新しいヒノキを李世武啓雲に贈る」時代: 唐代著者: セン・シェン私はあなたの緑色...
岑神の古詩「永寿王残夫を県に送り返す」の本来の意味を鑑賞
古代詩「永寿王残夫を県に送り返す」時代: 唐代著者: セン・シェン公務員になると、田舎に帰る自由な時...
三国志の歴史において孫権と孫昊の関係はどのようなものですか?孫権にとって孫昊とは誰ですか?
三国志の歴史において孫権と孫昊はどのような関係にあるのでしょうか?孫権にとって孫昊とは誰ですか?孫昊...
牛魔王も鉄扇公主も三昧の火を知らなかったのに、紅坊主はどうやってそれを知ったのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
沈徳謙の「徐州を通り過ぎて」:詩は心から自然に流れ出ており、洗練の痕跡はない
沈徳謙(1673-1769)は、瓢世、桂羽とも呼ばれ、常熟(現在の江蘇省蘇州)出身の清朝の詩人である...
康熙帝が二度の戦いの末に守った鴨緑江の城は、ついに中国に奪われてしまった!
今日は、Interesting Historyの編集者がヤクサ市についての記事をお届けします。ぜひお...
なぜ劉備は劉璋を力ずくで暗殺し、益州を占領しようとしなかったのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...